2003年に埋めた“タイムカプセル”が、22年後の同窓会で地獄のトリガーとなる――。
日本テレビ系ドラマ『良いこと悪いこと』は、「夢」をキーワードに展開する連続殺人ミステリー。掘り起こされた卒業アルバムには、6人の顔が黒く塗りつぶされていた。その夜、最初の犠牲者が現れる。
以降、「将来の夢の絵」と同じ手口で同級生が次々と狙われていく中、主人公・高木将と元クラスメイトの猿橋園子は“被害者”と“容疑者”という立場を超え、真相を追うバディに。
本記事では、全話のあらすじとネタバレを時系列で整理し、謎の構造や犯人像、そして最終回の結末までを論理的に考察していきます。
【全話ネタバレ】良いこと悪いことのあらすじ&ネタバレ
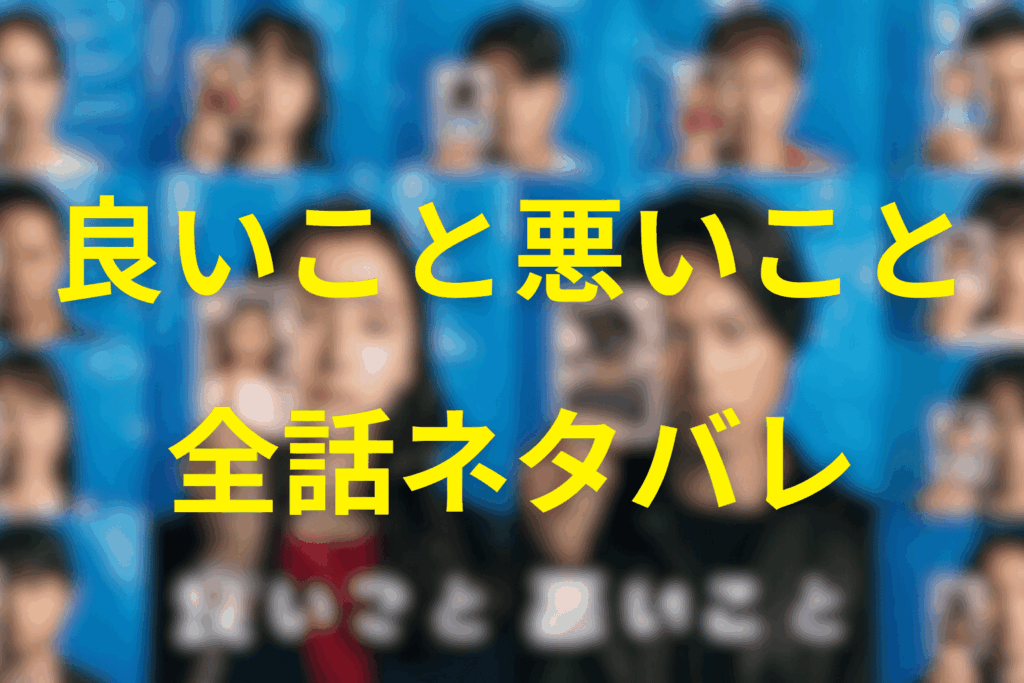
1話:「6人」――“夢”が凶器に変わる夜、バディはこうして生まれる
黒塗りのアルバムが告げた“復讐の開幕”
舞台は学校創立50周年の同窓会。34歳になった高木将(“キング”)が、22年前に埋めたタイムカプセルをクラスメイトと掘り起こす。
中身は当時描いた「みんなの夢」の絵と、誰かが忍ばせた卒業アルバム。6年1組のページを開いた高木は絶句する──高木を含む6人の顔写真が無残に黒塗りされていたのだ。高木には“6人の共通点”に心当たりがあるが、言葉にできないまま夜が更けていく。
ここでドラマは「標的を予告するアルバム」という“仕掛け”を一気に提示し、動機・機会・手口の三点を観客に考えさせるモードへ切り替える。
“夢”が手口に変わる連続事件
その夜、6人のうち最初の犠牲者が出る。以後、「将来の夢の絵」に沿った犯行シグネチャが浮かび上がる。武田敏生は“空を飛ぶ絵”の持ち主で、マンションから転落死。
桜井幹太は“消防士”の夢を描いた人物で、火災に巻き込まれ意識不明に。
この“夢→手口”の対応が二例続けて起きたことで、視聴者の仮説は一気に狭まる。絵にアクセスできる者、6人と園子の過去を知る者──つまり内輪の犯行が濃厚になるわけだ。タイトルの“良いこと/悪いこと”は、“夢(良いこと)”が反転して“悪いこと”に変わる倫理ゲームとして立ち上がる。
バディ誕生――“被害候補”と“容疑候補”の共闘
高木は“殺されたくない”、園子は“疑われたくない”。利害の一致が、二人をバディへと押し出す。公式要約が示すように、高木は真相解明のため、犯人ではないと主張する園子と手を組む。
この構図の妙は、“被害候補”と“容疑候補”を同じ矢印に並べたこと。互いの心に残る“過去の温度差”を抱えたまま共闘するからこそ、会話の一語一句に含みが生まれ、視線の往復に緊張が宿る。バディ化そのものがサスペンスの燃料となり、以後の事件を観測する“視点装置”として機能する点が巧みだ。
“時間割の犯罪”としての構成美
構成面の肝は、“時間割の犯罪”という見せ方にある。1話の終盤までに“夢→手口”が二件確認され、2話の予告では「これまでの被害者は武田と桜井」と整理される。
重要なのは、タイムカプセルの公開タイミングと犯行準備の整合性。あの場で初めて絵を確認した同級生が、その直後に実行できるのか。準備時間の矛盾が“内輪の誰か+事前に絵を知っていた者(=学校関係者や保管者)”という二層の容疑線を生み出す。
推理が“誰が悪いか”にとどまらず、“誰が何を知っていたか”という情報アクセスの物語に拡張していくのが本作の面白さだ。
起動回としての完成度
総じて第1話は、
①黒塗りの6人=標的の提示
②夢→手口の対位法=犯行サインの宣言
③高木×園子のバディ化=視点の固定
という三段構成で物語の“走り方”を決定づけた。以後は、6人の夢の中身と当時の関係性がピースのように少しずつ開示されるだろう。
犯人探しの軸は
(A)夢の絵へ事前にアクセスできた者
(B)6人と園子の因縁を具体的に知る者
(C)短時間で実行可能な者
――この三条件の積。第1話は、その積が誰に向くのかを視聴者に計算させる、極めてロジカルな“起動回”だったと結論づけたい。
【関連】1話については以下記事で解説
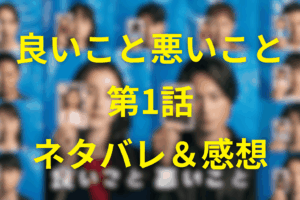
2話:「歌」――“夢の絵”テンプレが露わに、ニコちゃん線が動く
“夢の絵”が犯行のテンプレートに
これまでの2件の襲撃は、“22年前の将来の夢の絵”の再現だった。
貧ちゃん=武田敏生(水川かたまり)は“空を飛ぶ絵”を描いた少年で、成長後にマンションから転落して死亡。カンタロー=桜井幹太(工藤阿須加)は“消防士の絵”のとおり火災に巻き込まれ、意識不明の重体となる。犯行は偶然ではなく、夢の絵というテンプレートに沿って再演されている。
高木と園子は、絵とタイムカプセルに触れられる“クラスの内側”に容疑を絞る。「このクラスの誰かが、あなたを恨んでいるんです。私以外の、誰かが」——園子の一言が、核心を黒く縁取った。
“ニコちゃん”への接触と謝罪のすれ違い
残る標的は4人。そのひとり、“ニコちゃん”こと中島笑美(松井玲奈)に、高木と園子は警告のため接触する。笑美の子ども時代の夢は“スポットライトを浴びるアイドル”。
現在は六本木のクラブでホステスとして働き、華やかな日々を送っている。再会の場で笑美は、かつての仕打ちを園子に謝罪するが、長年の歪みは簡単に埋まらない。ふたりの間に横たわる“時間差の倫理”が、保護計画の行方をも左右していく。
報道サイドの“夜の街”ルート
一方、報道サイドでは園子の同僚・東雲晴香(深川麻衣)と後輩・松井(秋谷郁甫)が、違法薬物の元締めを追って夜の街を取材中。
彼女たちの捜査線は笑美の生活圏と重なり、のちに「夢の絵テンプレ」を実行するための情報×環境の両輪として結びつく。刑事ではなく“メディアの足”が別角度から真相を照らす構成が、第2話の見どころとなる。
「夢」を“犯行手順”に変える構造
第2話の焦点は、“善意の象徴=夢”が犯行の作業手順に転化する瞬間にある。
①夢の絵という共通のインデックスを起点に、
②事故に見せかける舞台装置を仕込む。
この2ステップで、犯人は“善(夢)”を“悪(殺意)”の段取りに変換している。
高木はその冷酷な発想に気づき、標的リストの共有と保護を提案するが、警察は個別事故として扱い、連続性を認めない。守るか、泳がせるか——バディの決断ほどには、行政の歯車は鈍く、重い。
クライマックス――“歌”が鳴り、ニコちゃん転倒
夜、街角に“不気味な替え歌”が流れたのち、物語は最悪の瞬間を迎える。
クラブ帰りの笑美は、園子に“彼氏・城之内のドラッグ流通の証拠”を渡し、一人で歩道を歩く。背後から黒い傘の人物が近づき、ふっと肩を押す。
次の瞬間、夢に描いた“スポットライト”はトラックのヘッドライトに変わり、轟音とともに笑美は倒れ込む。
雨に溶けた血の跡だけが残り、夜のざわめきが一拍遅れて戻る。偶然ではあり得ない“手”の介在——笑美は、連続事件の“3人目の犠牲者”となる。
要点整理
- タイムカプセル/卒アルの“黒塗り”と“夢の絵”が犯行テンプレの設計図。
- 先行2件(転落死・火災重体)は絵どおりの再現。
- 標的は残り4人、その一人が笑美。
- 笑美への接触→謝罪のズレ→保護の是非が焦点に。
- 東雲・松井の夜の街ルートが“犯行舞台”の環境線として機能。
- 終盤、替え歌と転倒ショットで“夢の絵テンプレ”の第二形態を提示。
第2話は、犯人の人物像よりも「犯行の作業手順」を可視化する構成だった。
“夢”という善の記号をテンプレートに変換し、“善悪の入れ替わり”というタイトルの本質を具現化。
そして、“ニコちゃん線”を悲劇で締めくくることで、次回「絶交」への不穏なバトンを渡している。
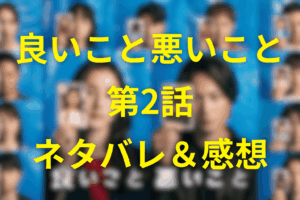
3話:絶交と“宇宙”の罠
替え歌の順番が導く“次の標的”
第3話は、ニコちゃん=中島笑美の死を受け、事件が“替え歌”の順で進んでいると確信した高木が「次の標的はターボー=小山隆弘だ」と推理する場面から始まる。
小山はアメリカでアプリ企業を成功させたIT実業家で、新規事業のPRのために一時帰国していた。だが園子は、「このタイミングでの帰国は偶然とは思えない」と疑念を抱き、過去の“目的のためなら手段を選ばない”という黒い噂を掘り返す。
親友を信じたい高木と、理性的に疑う園子。二人の間に再び緊張が走り、物語は“友情の信頼”と“記者の論理”がぶつかる構図で動き始める。
絶交の痛みと再会のぎこちなさ
高木は、小学6年生の頃に交わした“絶交”の痛みを今も抱えていた。
かつて親友だった小山と喧嘩別れしてから22年、ようやく再会を果たしたものの、互いに素直になれず会話には距離がある。
そして小山は高木に向かって、「復讐しているのは園子だ」と断言する。いじめられていた園子が、加害者だった6人に順番に報復しているのではないか、と。
高木は「園子は変わろうとしてきた」と反論するが、二人の溝は埋まらない。
第3話のタイトル“絶交”は、過去の痛手と現在の疑念が交差する二重の意味を持つモチーフとして機能している。
“森のくまさん”替え歌が犯行の設計図に
事件の設計図として浮上するのが、かつてクラスで作った「森のくまさん」の替え歌。貧ちゃん、カンタロー、ニコちゃん……と順番に死が訪れ、次に狙われるのはターボー。
しかも小山の発表する新規事業は“宇宙を体験する”というテーマで、彼が幼少期に夢見た「宇宙飛行士」と重なる。夢の象徴である“宇宙”が、皮肉にも彼自身を襲うモチーフとして回収されていく構成が見事だ。
東京湾の水死体――新たな“不穏の影”
一方で、物語の裏ではもう一つの不穏が進行している。
高木がテレビニュースを見つめるシーンで、東京湾から身元不明の水死体が発見されたと報道されるのだ。直接的な関係は明かされないが、この出来事が今後の事件とどう絡むのかは不透明。
替え歌の連続殺人とは別軸の“もう一つの死”が示され、物語に“第二の真相”を予感させる。
記者会見の惨劇――ガラスの星屑
クライマックスは、小山の新事業発表会。
“誰でも自宅で宇宙旅行ができる”という壮大なプロジェクトが発表され、会場は大成功の熱気に包まれる。小山は満面の笑みでスピーチを終え、報道陣による囲み取材が始まった。
だがその直後、突如として異変が起こる。取材エリアの天井から、不吉な軋み音が響いたかと思うと、巨大なガラス製の照明パネルが落下。
高木は一瞬の違和感を察知し、咄嗟にステージへ駆け寄って小山を突き飛ばす。次の瞬間、ガラス板が粉々に砕け散り、ステージに無数の破片が降り注いだ。
ライトに照らされたガラス片は、まるで星屑のように輝き、宇宙をテーマにした演出と“死の演出”が皮肉に重なる。
幸いにも小山は軽傷で済み、事件は未遂に終わった。
しかし、替え歌の順番通りに“死を演出”する犯人の目的は依然として不明。これは本当に殺意によるものなのか、それとも次への“警告”なのか――。
成功した発表会の直後に訪れた惨劇が、物語にさらなる不穏な影を落とした。
四重構造で描かれたスリルとテーマ
第3話の構成を整理すると、
- 園子・小山・高木の三角関係による疑心と信頼、
- 替え歌という犯行ロジックの強化、
- “宇宙”モチーフを活かした美しい演出、
- 東京湾の水死体という別線の不穏。
この“四重構造”が重なり、物語にスリルと奥行きを与えている。
犯人探しの枠を超え、“なぜ順番を守るのか”“殺意の根底に何があるのか”という新たな哲学的問いが浮上。単なる復讐劇ではなく、“罪の儀式”として事件が描かれる可能性が見えてきた。
絶交は“終わり”ではなく“再生”の兆し
第3話「絶交」は、友情と復讐が交差する転換点。
ガラスの破片のように散らばった記憶の断片が、星のようにきらめきながら“赦し”と“報い”の境界線をぼかしていく。
友情、信頼、疑念、そして過去の償い。すべてが静かに混ざり合う中で、次なる標的・羽立の運命が迫る。
物語は“絶交”を終わりではなく、“再生の始まり”として描く。
宇宙を夢見た二人のように、壊れた絆が再び光を放つ日は来るのか。次回、替え歌の“最終節”が鳴るとき、真の悪意がついに姿を現す。
3話のネタバレ&考察はこちら↓
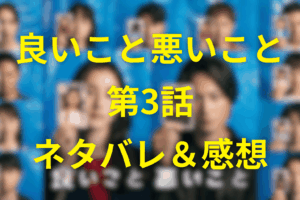
4話:「黒」——“守るつもり”が刺さる夜と、輪の外から差し込む第三の視線
第4話はタイトルどおり“黒”。黒塗りの卒アルと、心の中にある黒い空洞を二重写しにして、物語を一段深く沈めた回だ。
高木(間宮祥太朗)と園子(新木優子)は、連続襲撃が替え歌の順番に沿っていると確信する。
これまでの武田→桜井→笑美に続き、高木の親友・小山(森本慎太郎)も襲われ、次の標的は“ちょんまげ”=羽立太輔(森優作)に絞られていく。
羽立の将来の夢が「刀を構えた侍」だったことから刺殺の可能性まで想定し、二人は学級委員長の小林紗季(藤間爽子)を頼って住所を入手する。
「友達なんかじゃない」——羽立が突きつけた“関係のリセット権”
週末、3人(高木・園子・小山)は羽立のアパートを訪ねる。
輪ゴムで髪を束ね、散らかった部屋で引きこもる羽立は、彼らの顔を見ても驚かない。「僕の番か……」。ニュースで連続事件を知り、自分が次だと理解しているのだ。
彼は台所から包丁を持ち出して園子に渡し、「僕なんて、なんの価値もないんだから」と“ひと思いにやってくれ”とまで言う。
高木は「守りに来た」「友達同士で守りあえば——」と説得を試みるが、返ってきた言葉は冷たい。
「友達なんかじゃない」。
被害者の側にある“関係のリセット権”をきっぱり突きつけられる。ここが第4話の核心である。
善意の限界——“守る”は一方的には成立しない
“守る”は、一方的には成立しない。
過去の加害の記憶は被害者の身体に残り続ける
→加害側の善意は、再演に見えることがある
→届かない言葉が二次加害になる
この三段で見ると、羽立の拒絶はきわめて合理的だ。
井戸の底のような自己否定——父を幼くして亡くし、昨年は母も失い、今は独りで生きているという事実が、彼の「仕方ない」を下支えする。
善意で近づくほど、黒は滲む。
輪の外から差し込む“第三の視線”
一方で、画面には“輪の外”から差し込む視線が初めて強度を持つ。
スナック「イマクニ」に出入りしていた常連客・宇都見(木村昴)の正体が、警視庁捜査一課の刑事だと判明する。
第2話での「しがない公務員です」という台詞が、ここで“逆説的な真実”として回収された。
これにより物語には、当事者(6人)・メディア(園子)に加えて“警察の合理”が正式参戦。素人の考察だけではなく、証拠の線が地形を変え始める。
法則の強度と“守る言葉”の更新
公式ストーリーは「最悪の事態が待ち受ける」とだけ煽って幕を閉じる。
事件のルール(替え歌の順番)は依然として強固で、5人目=羽立の危険は高まる一方。だがヒューマンとしての線は同時に前進している。
法則が強いほど、守るべき相手が先に見える
→守り方を誤ると再被害になる
→“守る言葉”そのものを更新しなければならない
第4話は、ミステリーの燃料(法則)と人間ドラマの酸素(関係の更新)を半々で混ぜ、次回以降の爆発に備えた回と言える。
“黒”が映し出した三つの論点
個人的な“論理の見どころ”を三つに絞る
①謝罪の非対称性——加害と被害は同じ時間を生きていない。加害側の「変わったよ」は、被害側にはしばしば「また来た」に見える。
②第三の視点の投入——宇都見=刑事という視線の増殖により、「6人の内側」だけで完結しない地平が開かれる。クラス全体や教員など、輪の外への疑いが広がる設計だ。
③色の演出——“黒”は不吉の色であると同時に輪郭線である。黒を塗ることで、これまで見落としていた形が浮かび上がる。
“良いことのつもりで近づくと、悪いことに転じる”というタイトルのアイロニーが、一段と鮮明になった。
「守る」とは何かを問い直す
結局のところ、第4話は「守る」とは何かを問い直す1本だった。
羽立に必要なのは、「守ってやる」という上位目線ではなく、まず関係の再定義だ。
次回、替え歌の刃に人間が勝つのか。“言葉の設計”が鍵を握る。
ミステリーの快感とヒューマンの痛覚が、同じ熱量で共存した佳回だった。
4話のネタバレ&考察はこちら↓
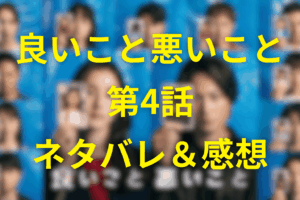
5話:「みんなの夢」――教室の記録と“忘れられた7人目”
第5話は、事件の鍵を22年前の教室へ引き戻す回。
生き残った“キング”高木将(間宮祥太朗)、“ターボー”小山隆弘(森本慎太郎)、“ちょんまげ”羽立太輔(森優作)の3人はガレージで協議し、
「園子(新木優子)以外にも自分たちを恨む人物がクラスにいたのでは」と仮説を立てる。
写真を洗い直す中で羽立がつぶやく。
「僕らのことを一番覚えている“もう1人”がいる」――それは当時の担任で、今は母校の校長となった大谷典代(赤間麻里子)。
生徒思いだった彼女なら、忘れかけた出来事も覚えているかもしれない。4人(高木・小山・羽立・園子)は確かめに行く。
校舎で蘇る記憶と、“父”としてのざわめき
母校の廊下に足を踏み入れた瞬間、園子の脳裏に過去の断片が蘇る。
備品倉庫に閉じ込められた日、昇降口での公開謝罪、階段でランドセルを奪われた屈辱――。
その光景の断片が現在と地続きの痛みとして蘇り、高木の心を揺らす。彼は校長室へ向かう途中、小4の娘・花音(宮崎莉里沙)が男子と口論する場面を目撃。
かつての加害の影が、父親としての責任を突きつけてくる。
校長室の面談――「いじめはなかった」と笑う先生
校長となった大谷は「6年1組に目立ったトラブルはなかった」「園子がひどい仕打ちに遭っていたことも知らない」と微笑みながら応答。
しかし4人は室内に小さな手がかりを見つける。
その年度の卒業アルバムが棚にない――。
語られた“記憶”と残された“記録”の齟齬が、彼女の口元の笑みより雄弁に物語る。
「みんなの夢」という副題が示すように、当時の“夢”を写した掲示や映像、学校が保持する記録物こそが、真相へ繋がる伏線となる。
警察が動く――宇都見の再捜査
警視庁捜査一課の宇都見啓が、事故死として処理された中島笑美・武田敏生の死因を再捜査。
民間=元同級生の追跡と、公的機関=警察の検証が並走することで、事件は“偶然”の皮を剥がし始める。物語のスケールが“教室の罪”から“社会の責任”へと広がる導入線がここで敷かれた。
委員長の再登場――“見て見ぬふり”をした者の証言
そこへ現れるのが、かつてのクラス委員長・小林紗季(藤間爽子)。
クラスの秩序と空気を最も知る人物だ。焼肉のテーブルで紗季は静かに言う。
「気づいてたのに、何もできなかった。あの時、怖かったの」
続けて「高木のことが好きだったから、言えなかった」とも打ち明ける。
彼女の言葉は“人気者の磁場”に巻き込まれた集団心理を映し出し、いじめの風景に社会性――力の偏り――を与えていく。
園子は赦さない。ただ一言、「謝ってすぐ楽にならないで」とだけ返す。その“距離のある対話”こそが、再生への第一歩となる。
校長・大谷の“涙”と“電話”――そして黒い車
物語のラスト、校長室に残った大谷がひとり、「みんなの夢」の映像を再生する。
画面を見つめながら、彼女は小さくつぶやく。
「ごめんなさい……」
そして震える声で電話をかける。
「あなたに言われた通り、タイムカプセルを掘り起こしました。もうやめませんか」
その後、校門前に停まる黒い車にゆっくりと乗り込む。脅されているのか、共犯なのか――その表情は曖昧で、涙だけが真実を語る。
事なかれに徹してきた教師の“良心の崩壊”が静かに描かれ、次回、物語はいよいよ“犯人の正体”と“忘却の構造”へと踏み込んでいく。
掲示板「鷹里小の森」――“博士”=忘れられた7人目
一方、羽立が学校の交流サイト「鷹里小の森」を発見。
「このHPも、俺のことも誰も覚えていない」「誰一人覚えてない」と綴られた書き込みに、
羽立が「覚えてるよ、博士だよね?」と返信すると、即座に「もしかして、ちょんまげ?」と応答が返ってくる。
「さすが、ちょんまげ」「あの7人組を覚えていたのは君だけ」――。
“忘れられた7人目=博士”という線が、現実味を帯びる。
画面は暗転し、教室の記録(夢・卒アル)と匿名の声(掲示板)が交錯。犯行動機=忘却の暴力という主題が、ついに姿を見せる。
結末の布石――三つの視点が交錯する
第5話では、先生=記録の管理者/委員長=秩序の記憶者/博士=忘却の被害者という三つの線が立ち上がる。
彼らの視点がいつ、どの言葉で交わるのか。
“言葉にできる者の責任”が物語の中心に置かれ、「なかったことにはできない」という園子の台詞が、静かに真相篇への扉を開いた。
良いこと悪いこと5話のネタバレはこちら↓
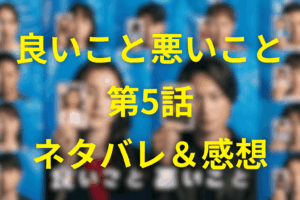
6話:「傘」——“正しさ”が人を救い、そして傷つける
園子が“容疑者”にされる炎上地獄
第6話「傘」(2025年11月15日OA)。
高木と園子が“4件目”を止めるため奔走するなか、ライバル誌が 「美人すぎる記者・猿橋園子 連続殺人犯疑惑!?」 と大見出しを打ち出し、タイムカプセル・黒塗り卒アル・同級生の不審死を列挙。
記事は園子が犯人であるかのように構成され、編集部は問い合わせ殺到で大混乱。園子は言葉を失う。
ワイドショーとSNSは一気に“園子=容疑者”モードに傾き、名前はトレンド入り。自宅直撃と盗撮が相次ぎ、生命の危険すら感じるレベルのバッシングへ発展する。高木や小山は助けたいが、今動けば炎上を加速させるだけで身動きが取れない状況が続く。
紗季の提案と園子の“反論しない”という選択
逃げ場を失った園子が頼ったのは、元委員長の小林紗季。「正しいことを、しよう」と紗季は反論記事での告発を強く勧める。
家族や会社に矛先が向くリスクを前に園子は迷いながらも一度覚悟を固める。
しかし最終的には、「世間と争うより、事件と仲間に向き合いたい」と反論を撤回。高木と小山も「自分たちが園子をいじめていた事実を公開すべき」と腹を括る。
ところが、この一連の騒ぎそのものを仕掛けていたのが紗季本人だったことが判明し、物語は大きく反転する。
紗季の“二つの顔”と弟・春季の悲劇
本話は、紗季の“二つの顔”が全面的に露わになる回だ。冒頭から高木らの会話を録音し週刊誌へ流していたこと、さらに幼少期に園子を体育倉庫へ閉じ込めていた張本人であることが描かれる。
クライマックスでは、紗季が園子を連れ出し、弟・春季の墓前で真相を告白。
かつて園子が手掛けた“大学サッカー部薬物報道”の余波で、無実の弟が誹謗中傷に晒され自死に追い込まれたこと、紗季が長年抱えてきた怒りと悲しみが溢れ出す。紗季は「私は正しいことをする」とナイフを向けるが、皆に掛けられた言葉や“委員長としての自分”を思い出し、その場に崩れ落ちて泣き崩れる。
第四の犠牲者発覚——事件は“いじめの枠”を超える
紗季を警察に引き渡したのち、園子は刑事から“4件目の殺害”を聞かされる。行方不明だった元担任・大谷典代の遺体が凍死状態で発見され、連続殺人は“いじめ加害者”の枠を越えて拡大していた。
犯人像は一気に不明瞭となり、物語は新たな局面へ。
第6話は、ネット炎上という“世論の暴力”を正面から描くと同時に、“傘”というモチーフを通して 「誰かを守るはずの正しさが、別の誰かを傷つける」 という痛烈なテーマを提示して幕を閉じる。
6話のネタバレについてはこちら↓
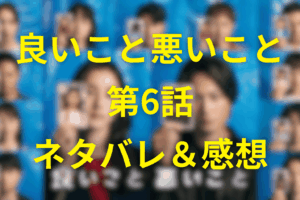
7話:「バトン」——受け継がれた罪と、落とされたバトン
7話はサブタイトルどおり「バトン」がテーマ。小6時代の運動会リレーと、現在の連続殺人事件が“責任の受け渡し”として重ねられていく。
22年前の運動会と、大谷先生の「お別れの会」
冒頭は22年前、6年1組の運動会リレーの回想。紅白リレーのアンカーを任された高木将(キング)は、自信満々にバトンを受け取り、仲間たちの声援を背に全力で走る。その姿は、クラスのヒーローであり「最後は俺に任せろ」と言える存在としてのキングの原点だった。
現在は、元担任・大谷典代の「お別れの会」。キング、園子、小山隆弘(ターボー)らに向けられるのは冷たい視線。「お前らのせいで迷惑してる」「警察に呼ばれた」と非難が集中する。一方、土屋ゆき(ゆっきー)と豊川賢吾(トヨ)だけは「手伝わせてほしい」と名乗り出る。しかしキングは「これは遊びじゃない」「巻き込みたくない」と突き放し、ターボーとも衝突する。
それぞれの“叶わなかった夢”と、羽立の失踪
そのころ、ターボーは羽立太輔(ちょんまげ)と連絡が取れないことに不安を抱いていた。預かっていた合鍵で部屋に入ると、荒れ果てた室内と、姿のない羽立。唯一の手がかりが、古いガラケーだった。
一方ゆっきーは、浮気を繰り返す夫との生活に虚しさを感じながら「将来の夢」の絵を見つめ直す。
トヨも年下オーナーに頭を下げ続け、押しつぶされそうになっていた。そんな二人は「諦めない」と決め、水面下で同級生への聞き込みを始めていた。
ガラケー動画が映す“7人目の影”
イマクニに集まった5人は、ガラケーを再生。小6当時の輪の中に、これまで存在を忘れていた“もう一人の少年”が映っていた。「森のくまさん」の替え歌の歌詞には、その名字“森”が紛れ込んでいる。森くんは6年の途中で転校し、卒アルにも載っていない——その“空白”が、黒塗りアルバムへつながる伏線だった。
さらに、羽立のプロフィール帳から小学校サイト「鷹里小の森」へアクセス。掲示板には、羽立と「博士」を名乗る人物のやりとりが残されていた。「誰も覚えていない」「忘れられた」という怨嗟の書き込み。そして新着メッセージには「今日17時、小6の校外学習で行った場所で」と、まるで招待状のような文が。
森林姓は、高木の娘・花音の担任=森先生とも一致していた。
5人の決意と、校外学習の場所へ
「森くんには聞きたいことがたくさんある」。ターボー、ゆっきー、トヨが意思を固め、視線がキングへ向く。短い沈黙ののち、キングは「ちょんまげを探す。森を見つける。それだけだ」と腹を決める。
一方そのころ、羽立本人は先にビルへ侵入していた。「博士……森くんか」「僕のせいだ、僕が終わらせなきゃ」と呟き、折り畳みナイフを握る。指定された部屋には人形が立っているだけで、約束は果たされていなかった。「約束したのに!」と廊下へ飛び出す。
黒服とのもみ合い、そして——
羽立の声を聞いた5人は、暗いビル内を走る。階段踊り場で、羽立は黒い服の人物ともみ合いに。5人が近づくと黒服は逃げ去り、羽立は床に倒れ「ごめん、逃げられた」と呟く。
「追って!」という園子の声で、4人は四方へ走り出す。しかし黒服は陸上選手のような俊敏さで逃げ続け、通路の影には“複数の黒服”がいるような錯覚さえ生む編集が施されていた。トヨが逆方向から現れるカットもあり、“一人ではない可能性”が示唆される。
衝撃のラスト——ちょんまげ、退場
園子が羽立のもとへ戻ろうとしたそのとき、階段上部からドサッと落ちてくる影。見下ろすと、首に刺し傷を負い、血を流す羽立だった。もう動かない。ちょんまげは、真相に最も近づいた直後に命を落とした。
その絶望的な光景を映し出したところで、7話は幕を閉じる。
7話のネタバレについてはこちら↓
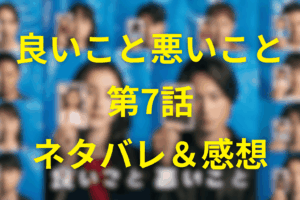
8話:7人目の森と、もう一人の「ドの子」瀬戸しおん
羽立殺害後の混乱と、消えた“夢DVD”の行方
8話は、ちょんまげ=羽立が殺害された直後から始まる。
事情聴取を受けるキング、園子、ターボーらは、犯人と思しき人物を追ったが顔は確認できず、「本当に森智也なのか」と確証が持てない。彼らに残る唯一の“鍵”は、タイムカプセルから抜き取られた「みんなの夢」DVD。そこには、犯人が絶対に見られたくない何かが映っているはずだが、行方は依然として不明のままだ。
思い出される“7人目”博士・森智也の原罪
捜査と記憶をたどる中で、仲良し6人組には“もう1人”――あだ名は「博士」、パソコンが得意な森智也がいたことを思い出す。
森は小学6年当時、「鷹里小の森」というクラスホームページを作成。しかし、そこにはキングたちが“ドの子”への悪口を書き込み、森は「消さなきゃ」と思いながらも仲間でいたい気持ちが勝り、閉鎖できなかった。それが森自身の原罪として重く描かれる。
現在の森は“花音の担任”として目の前に
そんな森の正体は、キングが偶然立ち寄った小学校で明らかに。娘・花音の担任の名札に「森」の文字を見た瞬間、キングは凍りつく。
森はタイムカプセルから抜き取られていたはずのDVDを所持し、キングの家や職場に現れては「自分のことを忘れていたくせに」と怒りをぶつける。キングは「向き合っている」と返しつつも、加害者側として何も言い返せない負い目を抱えている。
困惑する園子と、報道に向き合う覚悟
一方、園子は拘置所の紗季と面会。「自分の記事が誰かの人生を壊すかもしれない」と書けなくなっていたことを明かすと、紗季は「じゃあ記者やめんの?」と突き放し、「あなたは加害者として苦しんで」と告げる。
園子は「記者はやめない。加害者だと自覚して覚悟を持って書く」と決意する。報道の側の“良いこと/悪いこと”に向き合う覚悟の瞬間だ。
キングの告白と、花音のまっすぐな言葉
キングの家では、妻の加奈が「いま必要なのは事件じゃなくて花音の父親」と訴える。しかしキングは事件を優先し、ついに花音へ「パパは昔、いじめっ子だった」と告白する。
「ちゃんと謝れば森先生も許してくれる」と返す花音の純粋な言葉は、“過去の悪いこと”から逃げずに生き直せるのかというテーマの核心を突く。
花音が持ち出したDVDと、追い詰められた森
学校では森がパソコン室でDVDを見返していたが、席を外した隙に花音が侵入。
「これのせいでパパとケンカしてるんでしょ」とDVDを持ち出す。森は追いかけながら「僕はいい先生だ。仲間だとバレたら殺される」と自分に言い聞かせ、いじめ防止ポスターまで破るほど追い詰められている。教室で花音を捕まえた森の暴走を止めたのは、キングだった。
キングと森、22年越しの“罪”の対話
花音を帰らせ、二人きりになったキングと森は、本音をぶつけ合う。森は「悪いのはお前たちだ」と怒りを吐き、キングは「貧ちゃんもカンタローもニコちゃんもちょんまげも死んだ。俺がましなら」と責任を認める。
森が「責任取って死ね」と口走ると、キングは「死ねるわけない。悪い子が良い子になろうとして何が悪い」と返し、「逃げない、お前を受け止める」と宣言。森は崩れ落ち、「本当は助けたかった」と涙を流し、自分も“傍観者の罪”を抱えていたと認める。
DVDの“最後の少女”――もう一人のドの子・瀬戸しおん
森はDVDをキングに託し、一同はバー「イマクニ」で再生する。そこには子ども時代の仲間が夢を語る映像。
そして最後に見覚えのない少女が現れ、「瀬戸紫苑です。夢はピアニストになることです」と語る。
キングが立ち上がり、園子が「誰?」と問うと、森は静かに「ドの子。もう一人のドの子」と告げる。園子の前に、さらに深い“いじめ被害者”がいたことがここで初めて明かされ、8話は衝撃の幕引きとなった。
瀬戸紫苑については以下記事をチェックしてください。
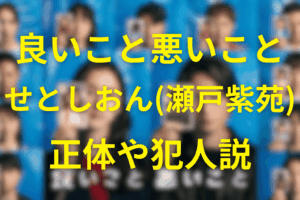
9話:カノン(犯人、だーれだ?)
紫苑の過去が現在と繋がる回
第9話「カノン(犯人、だーれだ?)」は、8話で示された“もう一人のドの子”瀬戸紫苑の線が、ついに現在の連続事件と直結し、実行犯とその動機が一気に表に出る回です。
物語としては大きな答えが提示される一方で、最終回に向けて新たな違和感も残される、明確な転換点となる一話でした。
前回までに“博士”森の証言によって、紫苑は5年生のクラス替え直後にいじめの標的となり、夏休み明けに転校。その後に園子が転校してきて「どの子」と呼ばれるようになった、というクラス内の時系列が整理されていました。その流れを受けて9話では、紫苑の実家である元ピアノ教室が、物語を動かす起点として描かれます。
紫苑の実家と高木の記憶
紫苑の実家の住所を突き止めた高木・園子・ゆっきーは現地へ向かいますが、そこはすでに誰も住んでいない空き家でした。その場で高木は、娘の花音を連れて体験に来たことがあると気づきます。
しかし当時は「新規お断り」で断られていた。その何気ない出来事が、後に取り返しのつかない重さを持つことになります。
そんな中、園子は溜まった郵便物の中から「瀬戸紫苑」と刑事・宇都見啓の名前が並んだハガキを発見します。紫苑が宇都見の婚約者だったという事実が浮かび上がり、3人がスナック「イマクニ」で店主・今國に話を聞くと、紫苑は約1年前に亡くなっていたことが判明します。ここで、22年前の教室と現在の事件が、一本の線で結ばれました。
宇都見の接触と新たな犠牲者
一方その頃、宇都見はターボー小山のもとを訪ね、紫苑の情報提供と引き換えに“事件を解決する”と持ちかけます。
小山に勧められVRゴーグルを手に取った宇都見は「急に暗くなった」と訴え、小山が宇宙映像を確認した瞬間に首を絞めて殺害。ここで“新たな犠牲者”が出てしまいます。
宇都見の告白と復讐の動機
小山の死に打ちのめされる高木の前に宇都見が現れ、これまでの犯行はすべて自分だと告白します。
動機として語られるのは、紫苑が高木と再会したことでいじめのトラウマが蘇り、ピアノが弾けなくなった末に命を絶ったことへの復讐でした。過去と現在が重なり合い、復讐という形で噴き出した感情が、ここで言葉として明かされます。
タクト学園と追悼コンサート
その後、園子は松井健から、紫苑が転校後に「タクト学園」にいたことを聞き、現地へ向かいます。ちょうどその日に追悼コンサートが開かれると知り、高木へ連絡。
会場では宇都見が、紫苑が「自分を救ってくれた曲」と語っていた「カノン」を演奏します。音楽が静かに流れる中、物語はクライマックスへと向かいます。
SIT突入と残された謎
演奏が終わった瞬間、高木はカッターナイフを手に宇都見へ近づきますが、その直前でSITが突入し、宇都見は確保されます。
紫苑の正体、宇都見との関係、そして宇都見が実行犯であることと動機は明らかになりました。
一方で、予告が示す「真犯人」の存在や、宇都見が確保直前に“誰か”へ口パクで何かを伝えたように見える点は未回収のままです。
実行犯は捕まりましたが、物語はなお「もう一段上」があることを示し、最終回へ続きます。最終回では、真犯人の正体と紫苑の死の全貌がどう回収されるのかが最大の焦点となり、見逃せない締めになるはずです。
9話についてはこちら↓
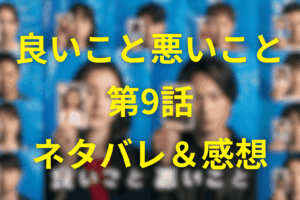
9.5話:犬|DVD「覚えているか?」が過去を引きずり出す
9.5話の位置づけと、この回が担った役割
9.5話「犬」は、本編9話の直後にhuluで配信された特別編です。
連続事件の“真相”に触れたキング(高木将)が、答えだけを手にしながら感情が追いつかない状態に置かれている。そのタイミングで描かれるのは、事件の後日談ではなく、「事件が起きる前に、確かに存在していた時間」でした。
この回は物語を前に進めるのではなく、視聴者の視線を一度、過去へ引き戻す役割を担っています。
この話の起点:DVDと「覚えているか?」という問い
ター坊の葬儀を終えて自宅へ戻ったキングに、妻・加奈が1枚のDVDを手渡します。ケースに添えられた短いメモは「覚えているか?」。
責めるでも、説明するでもない、その一言が、キングの背中を静かに押します。再生ボタンを押した瞬間、キングが封じ込めてきた記憶の扉が開き、この回は現在から過去へと滑り込んでいきます。
明かされる事実:ただの子ども時代があった
DVDが呼び水となり、物語は小学生時代へ。キングを中心にした仲良し6人組は、工事現場の奥で見つけた扉の向こうを「秘密基地」にして遊んでいました。板にペンキを塗り、くだらないルールで盛り上がる。
そこには、後の事件を想像させる影はなく、確かに“ただの子ども時代”が存在していたことが描かれます。
そんな中、ニコちゃんが駆け込んできて「お願い、助けて!」と叫ぶ。川の向こうに取り残された一匹の犬を見つけた6人は、衝動的に川へ飛び込み、力を合わせて犬を救い出します。
その出来事はニュースとして報じられ、カメラの前で笑う子どもたちの姿が、映像として記録されていました。これが9.5話の骨格です。
一番残酷な描写:良い記憶が救いにならない
この回で最もえぐいのは、“良いこと”の記憶が、そのまま救いにならない点です。ニュース映像の中のキングたちは、「良いことをした子ども」として映っています。
けれど現在のキングがそれを見たときに湧き上がるのは、誇らしさではなく罪悪感でした。あの頃、良いこともできた。誰かを助ける選択もできた。ではなぜ、悪いことを止められなかったのか。9.5話は犯人探しのテンポを捨て、キングの中にある「記憶の順番」を静かにひっくり返します。
次話への引き:回想が現在に接続する瞬間
ラストで示されるのは、助けた犬が後に紫苑のいたタクト学園に引き取られていたという事実です。
ここで9.5話は、単なる回想では終わりません。
本編の事件の根にある“タクト学園”へと、一本の補助線が引かれます。最終回を前に、物語の焦点は「誰がやったか」から、「なぜ、ここまで歪んだのか」へと移っていく。そのための、静かで重要な準備回でした。
伏線メモ:回収と余白
・メモ「覚えているか?」は、この物語が証拠だけでなく“記憧”で動くことを示す合図
・犬とタクト学園の接点は、紫苑ルートへ直結する新しい入口
・タクト学園で映る子どもたちの正体は断定されず、想像の余地が残されている
9.5話のネタバレについてはこちら↓
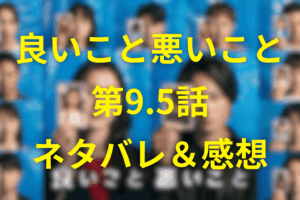
10話:はじまり(最終回)
逮捕の先に残された「理由」と「仕組み」
最終回「はじまり」は、宇都見啓の逮捕で終わる物語ではありませんでした。実行犯が確定しても、事件が起きた理由と、同じことが繰り返される仕組みが残っている。そこまで描き切ったのが10話です。
いじめは本人で終わらず、家族へ反転する
東雲晴香の記事によって、連続事件の背景が“キング”高木将たちのいじめにあったことが世間に広がります。
その矛先は、今度は将の娘・花音へ。落書き、貼り紙、晒し。いじめが「本人への罰」で終わらず、家族にまで反転して襲いかかる構図が、容赦なく突きつけられます。
正義の顔をした暴力を止めた存在
将は暴走しかけ、落書き犯の若者を追い詰めますが、猿橋園子がそれを止めます。
ここは、将が“正義の顔をした暴力”へ転びかけた瞬間であり、園子の存在意義が最もはっきりした場面でした。園子は「悪い子を裁く」側ではなく、「悪い子を増やさない」側に立ち続けます。
点と点が繋がる、タクト学園の記憶
一方、東雲はタクト学園へ向かい、ピアノの前で何かを始めるような姿を見せます。園子が語る瀬戸紫苑の転校先もタクト学園。
ここで将は、スナック「イマクニ」のコースターにあったタクト学園のマークを思い出し、点と点が繋がっていきます。
復讐は一人ではなかったという真実
確定したのは、東雲と今國一成がタクト学園出身で、紫苑の同級生だったこと。
つまり宇都見は単独ではなく、紫苑に“救われた側”の人間とも繋がっていました。復讐の論理は、同級生グループの外側からも補強されていたのです。
夢を折った罪と、ラベルで終わる社会
今國の回想では、紫苑が「夢を語る」ことを教え、彼らの人生を動かした事実が浮かび上がります。
だからこそ、キングが紫苑の夢を折った過去は、単なる子どものいじめでは済まされない。
将自身も「取り返しがつかない」と理解しているのに、社会は簡単に“悪い子”というラベルを貼って終わらせる。その空気が花音に向かう皮肉が、痛々しく響きます。
誰かを殺して完成する救済は、救済ではない
終盤、宇都見が用意した“最後のシナリオ”も見えてきます。
キングに銃を持たせ、加害の歴史を背負わせたまま「ヒーロー」にしてしまう筋書き。しかし将は引き金を引けず、園子もその結末を選ばせません。誰かを殺して完成する救済など、救済ではないからです。
「はじまり」として残された余白
最終的に将は、自分の言葉で過去を認め、責任を取っていく覚悟を固めます。
今國も東雲も紫苑の“光”を守りたかったはずなのに、方法を間違えればまた別の悪い子を生む。最終回は、その分岐点を丁寧に見せました。
ラスト、花音が体育倉庫に閉じ込められ、歴史が繰り返されるかと思った瞬間、誰かが扉を開けて「大丈夫?」と声をかける。顔は映らない。でも、次の世代にヒーローが生まれる余地だけは残した。終わりではなく「はじまり」で締めた、静かな最終回でした。
最終回についてはこちら↓
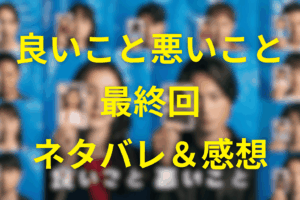
10.5話:エピローグ|宿題「将来の夢」が残した“その後”
10.5話の位置づけと描かれる時間
10.5話は、本編最終回(10話)の“その後”を描くエピローグです。
ここで起きるのは新たな事件ではありません。連続事件が終わった数日後に残された「怒り」「後悔」「生活」を、登場人物たちがどう抱えていくのか。その静かな後日談が描かれます。派手な展開はなく、むしろ事件後の日常に戻る過程こそが、この回の主題になっています。
この話の起点:宿題が突きつける未来の話
真相が明らかになってから数日。
キングと加奈は、真犯人たちの動機や行動を理解したはずなのに、気持ちは整理しきれないままでいます。
そんな中、娘の花音が小学校で宿題『将来の夢』を提出することになり、夫婦は避け続けてきた“未来の話”と向き合わざるを得なくなります。
事件の終結が、決して心の終着点ではないことが、ここではっきり示されます。
明かされる事実:家庭という一番小さな現実
10.5話の中心にあるのは、花音の投げかける素朴な問いです。
「パパとママは、どうして今の仕事をしているの?」。加害と被害、復讐と断罪といった大きな言葉のあとに置かれる、あまりにも日常的な会話。だからこそ、壊れかけていたキング家が“本当に日常へ戻れるのか”が、試される時間になっています。
一番しんどい描写:怒りの行き場を失ったキング
9話までのキングは、怒りを原動力にしてでも真相に近づこうとしていました。
しかし事件が終わった今、その怒りには行き場がありません。花音の「将来の夢」という宿題は、キングにとって“夢”という言葉以上に、「自分は何者で、これから娘に何を渡すのか」という問いになります。
子どもの無邪気な宿題が、大人の人生そのものを問い返してくる。この構図が、10.5話で最も胸に刺さる部分でした。
ここが本編の延長として効いているのは、事件の結末をドラマ的なカタルシスで終わらせず、家庭に持ち帰らせた点です。
花音にとって宿題はただの提出物でも、両親にとっては「明日も学校へ行かせる」という現実の重さの象徴。10.5話は、答え合わせより先に「これからどう生きるのか」を語れと迫ってきます。
エピローグとしての役割と残された問い
エピローグであるため、明確な「次話への引き」はありません。
ただし、この回で夫婦が向き合うのは“犯人”ではなく“未来”です。真相解明で終わった物語に、もう一段だけ「その後も生きる」という現実を重ねることで、最終回の決着を日常へ着地させています。
伏線メモとして残る余白
・宿題『将来の夢』は、本編で物語を動かした言葉が、後日談では“生き直しの問い”へと意味を反転させる
・真相を知った社会の怒りが、どこへ向かうのかは視聴者側に委ねられた宿題として残される
10.5話のネタバレについてはこちら↓
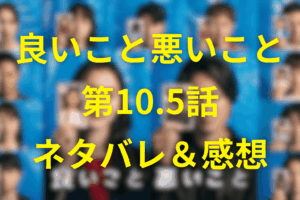
【最終回まで】良いこと悪いことで死んだ人一覧
卒業アルバムに黒塗りにされた6人。
キング、ターボー、貧ちゃん、カンタロー、ニコちゃん、ちょんまげ。
この6人が死ぬことが示唆されていますが、現状亡くなっているのは以下の人物
- 貧ちゃん
- ニコちゃん
- カンタロー
- 大谷先生
- ちょんまげ
- ターボー
と6人。
同級生以外にも先生が亡くなっているという状態で、物語は佳境を迎えています。
最終回を迎える前に、アルバムの人物で残っているのはキングだけになっています。
以下記事では、死んだ人について詳しく考察しているので、ぜひチェックしてください。
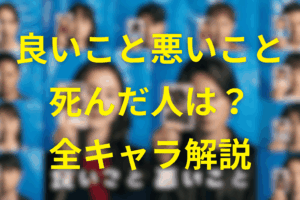
良いこと悪いことのキャスト一覧
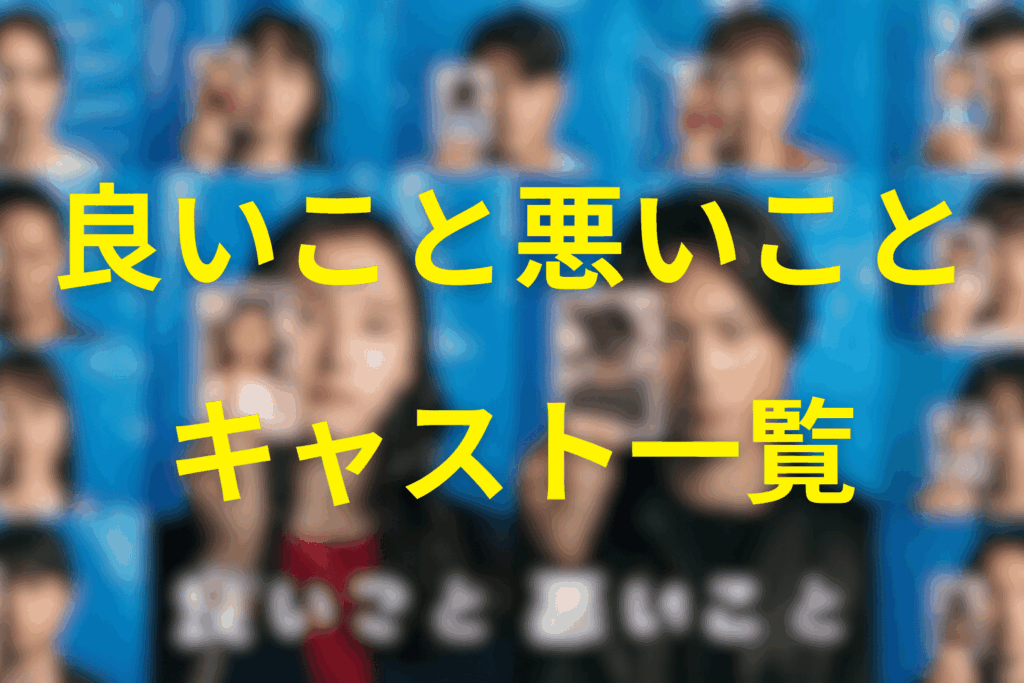
日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、ガクカワサキ脚本によるオリジナル作品で、2025年10月11日から放送予定。
物語は同窓会で再会した小学校の同級生たちが連続殺人事件に巻き込まれる“考察ミステリー”。主演は間宮祥太朗と新木優子によるダブル主演です。以下に主要キャストと役どころを整理します。
主要人物(元6年1組の同級生)
- 高木将(たかき しょう)/キング(間宮祥太朗)
主人公。東京郊外で小さな塗装会社を営む34歳の父親。小学生時代はクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれていた。 - 猿橋園子(さるはし そのこ)/どの子(新木優子)
テレビや雑誌で活躍する記者。久々の同窓会で高木らと再会する。 - 武田敏生(たけだ としき)/貧ちゃん(水川かたまり)
高木と仲の良かったクラスメイト。幼い頃のあだ名がそのまま残っている。 - 土屋ゆき(つちや ゆき)/ゆっきー(剛力彩芽)
現在は専業主婦。22年ぶりに旧友たちと顔を合わせる。 - 豊川賢吾(とよかわ けんご)/トヨ(稲葉友)
美容師として働く。かつての夢と現実に葛藤している。 - 桜井幹太(さくらい かんた)/カンタロー(工藤阿須加)
居酒屋を経営。ハイテンションで園子に声をかける。 - 小林紗季(こばやし さき)/委員長(藤間爽子)
学級委員長だった真面目な女性。 - 高木加奈(徳永えり)
主人公の妻で2歳年上。娘・花音の母。夫の過去が暴かれる中で揺れる姿が描かれる。 - 大谷典代(赤間麻里子)
鷹里小学校校長。元6年1組の担任で、タイムカプセル掘り起こしを呼びかけた人物。22年前の出来事を何か知っている。
周辺人物と新キャスト
同級生以外にも事件を追う刑事や周囲の人物が登場。高木や園子を取り巻くキャラクターとして次が発表されています。
- 金田大樹(木津つばさ)
捜査一課の刑事。視聴者に「ノンストップ考察ミステリー」を呼びかける存在。 - 吉岡愛(玉田志織)
捜査一課の刑事。結末がわからないまま役を演じる楽しさを語る。 - 松井健(秋谷郁甫)
週刊誌「週刊アポロ」の新入社員。ドジだが純粋で、物語にユーモアを添える。 - 丸藤萌歌(田中美久)
スナック「イマクニ」で働くアルバイト。 - 五十嵐駿(矢柴俊博)
週刊アポロの編集長。台本の持つ“エグみ”と“ヒューマニティー”を絶賛し、考察ミステリーを盛り上げる。
さらに、同級生たちの子供時代を演じるキャストとして野林万稔や鈴木礼彩ら、鷹里小学校6年1組の生徒役に多数の若手が出演予定。物語に厚みを加える布陣となっています。
【確定】良いこと悪いことの犯人/真犯人は誰?
ここから先は、最終回まで視聴した前提の確定ネタバレです。
8話までの「犯人予想」から一転し、9話〜最終回で「誰が・何をしたのか」がかなり明確になりました。ここでは、実行犯と真犯人(黒幕・共犯という意味合い)を分けて整理します。
良いこと悪いことの最新考察はこちら↓
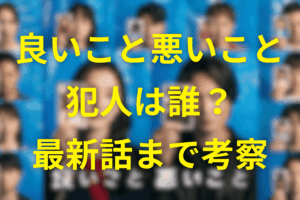
結論:実行犯(連続事件の中心人物)は宇都見啓
まず結論から。
連続事件の実行犯として前面に出てくるのは、刑事の宇都見啓です。最終回でも「宇都見逮捕」のニュースが冒頭で流れ、事件は一度“区切られたはず”の状態になります。
ただしこの作品は、犯人が捕まってスッキリ終わるミステリーではありません。
むしろ、「犯人が捕まったあとに何が残るのか」を描くことに力点を置いたドラマです。だからこそ、まずはこの確定情報を押さえておく必要があります。
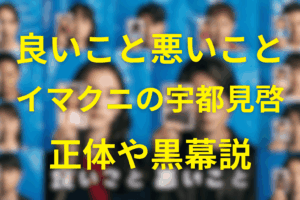
真犯人の整理:このドラマの「犯人」は1人に収束しない
ここで混乱しやすいのが、「犯人」と「真犯人」が同じ意味で使われていない点です。
整理すると、構造はこうなります。
- 実行犯:実際に手を下し、事件を動かした中心人物(宇都見)
- 関与者/共犯的立場:宇都見の計画に乗り、復讐の“脚本”を完成させようとした側
- さらに広げると:世論や空気の中で“石を投げた側”も、加害に参加してしまう構造
最終回は、この多層構造をあえて露出させています。
だから「真犯人は誰?」と聞かれたら、
実行犯は宇都見。
ただし、事件を“成立させた”のは宇都見だけではない。
この答えが、いちばん作品に忠実だと思います。
共犯・関与者として浮かび上がるのが今國一成と東雲
最終回で大きく意味を持つのが、今國一成と東雲の立ち位置です。
2人は単なる“事件の外側の人物”ではなく、事件に関与していた側だと明かされます。
象徴的なのが、終盤の流れです。
- 東雲が週刊誌の記事で「いじめの復讐」という物語を前面に出し、キングが特定されていく空気を作る
- 今國が「宇都見が置いていった」とされる銃を取り出し、キングに握らせる
- 「いじめのリーダーだったキングが今國を撃つ」ことで、復讐の脚本を完成させようとする
つまり、事件の最終局面で「キングに殺人犯になれ」と迫る構図が作られてしまう。
ここに、宇都見単独の事件ではない、不気味さがあります。
ただし最終回は、東雲と今國が「どこまで計画的だったのか」「どこから感情だったのか」を明言し切らず、意図的に余白を残しています。ここが視聴者のモヤモヤや考察欲を生むポイントでもあります。

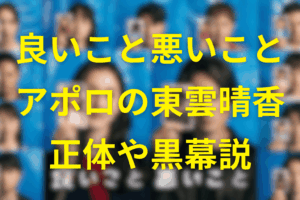
動機の核は「瀬戸紫苑の死」と、“夢を奪われた怒り”の増幅
最終回で効いてくるのは、瀬戸紫苑の存在です。
紫苑の「夢」が、宇都見だけでなく、今國や東雲の人生も押していた。
- 紫苑が夢を語れるようになったこと
- ピアノが「生きた証」になっていたこと
- そこから背中を押され、今國は店を持ち、東雲は記者になったこと
そうした未来が“断ち切られた”怒りが、復讐の論理を完成させてしまう。
ここが本当にえぐいのは、動機が理解できてしまうのに、行為は絶対に許されない点です。
だからこそ園子が止めに入る場面は、単なる正義の勝利ではなく、
正義を他人に強要した瞬間、それはもう善ではない
という結論になります。
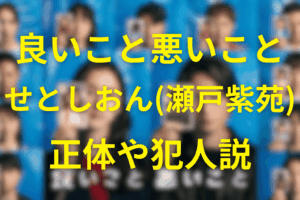
まとめ:真犯人は宇都見で確定。でも、物語が暴いたのは「加害は連鎖する」構造
確定情報として整理すると、次の3点で十分です。
- 実行犯の中心は宇都見啓
- 最終回で今國一成と東雲の関与が明かされる
- 事件は逮捕で終わらず、二次加害や“復讐の脚本”が残る
そしてこのドラマが最終回で突きつけたのは、真犯人を1人に決めて終わる快楽ではなく、
「良いこと/悪いこと」を他人に押しつけた瞬間、
誰でも加害者になり得る
という、かなり冷たい現実だったと思います。
だからこの作品は、犯人が分かったあとこそが本番なんですよね。
ドラマ「良いこと悪いこと」の原作漫画はある?
結論から言えば、「良いこと悪いこと」に原作となる漫画や小説は存在しません。本作は日本テレビによる完全オリジナル脚本のドラマとして制作されています。
ただし、放送開始後に公式コミカライズが制作され、電子書籍として配信がスタートしました。
漫画はドラマをベースにしつつ、心理描写や過去エピソードが丁寧に補完されているため、ドラマ視聴者が“もう一つの良いこと悪いこと”として楽しめる内容になっています。原作があるのではなく、ドラマが本編・漫画が派生作品という位置づけです。
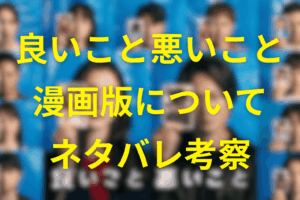
良いこと悪いことの最終回の結末
最終回(第10話「はじまり」)は、「犯人逮捕で事件解決」というエンタメの定番を、前半でいったん提示してから壊してきました。
結末として残るのは“事件の終わり”ではなく、“事件の後に始まる地獄”です。
宇都見逮捕で一区切り…でも、キングの「日常」は戻らない
冒頭、宇都見逮捕のニュースが流れます。
園子への疑いも一度はほどけ、空気だけを見れば「事件は終わった」ように見える。
けれどキング(高木将)は、妻の加奈、娘の花音とフードコートで食事をしていても、もう“前と同じ日常”には戻れない。加奈の「前は当たり前だったのに」という言葉が、最終回の入口として強烈に刺さります。
最終回はここで、「犯人が捕まれば元通りになる」という視聴者の期待を、かなり早い段階で折ってきます。
週刊アポロの記事で「二次加害」がキング家を襲う
決定打になるのが、東雲による記事です。
事件の動機を「いじめの復讐」として拡散し、さらに“いじめのリーダー格”がキングだったと示唆する内容が世に出る。
その結果として起きるのが、二次加害です。
- 家の壁への落書き
- 仕事のキャンセル
- 花音が学校で避けられ、ノートに酷い言葉を書かれる
誰かが直接殴るわけじゃない。
でも、空気が人を追い詰めていく。
最終回は、この「見えない暴力」を真正面から描きました。
東雲がタクト学園へ。「始めるよ」が意味したもの
園子の電話に出ない東雲は、タクト学園へ向かいます。ピアノの前に座り、「始めるよ」と呟く。
この瞬間、物語の重心が「宇都見の逮捕」から「東雲は何者で、何を始めようとしているのか」へと完全に移ります。
最終回の巧さはここです。
犯人が捕まったあとに、ようやく本題が姿を現す。
このドラマの最終回は、そういう構造をしています。
紫苑の「夢」が明かされる。今國と東雲は被害者側でもあった
終盤、今國は自分もいじめを受けていた過去を語り、タクト学園で紫苑と出会ったことが明かされます。
紫苑が語っていた「ピアニストになる夢」、ピアノが“生きた証”だったという言葉が、最終回の情緒の核になります。
ここで視聴者は、今國と東雲を単純な悪役として切り捨てられなくなる。被害者であることと、加害に踏み込むことは、同時に成立してしまう。
その危うさこそが、この作品の一番怖い部分です。
復讐の脚本の最終行は「銃」だった。キングに突きつけられた選択
事件の仕組みは、ここでさらに具体化されます。
- 宇都見が大谷を脅し、DVDを持ち出し、卒業アルバムの顔写真を黒塗りして「この6人だ」と伝えていく
- 今國は「うっちゃんが置いていってくれた」と銃を出し、その銃をキングに握らせる
- 「いじめのリーダーだったキングが今國を撃つ」ことで、キングの復讐を完成させようとする
- その後に雑誌でいじめの報道をし続けることで、いじめの強さを伝え、いじめを無くすような法律をつくらせる
これは復讐として最悪なのに、発想として異様にロジカルです。
だからこそ、背筋が冷える。
キングは撃てない。贖罪は「死」ではなく「生きて向き合う」に置き換わる
キングは銃を構えながらも、撃てずに泣き崩れます。
最終回はここで、贖罪を「死ねば終わる」方向に逃がしません。
- 殺すこともできない
- 殺されることも選べない
- だから、生きて責任を引き受け続けるしかない
この結末はスッキリしない。でも、いじめの問題に対しては、異様なほど現実的です。
顔出しの告白動画と、花音を助けた“ヒーロー”で幕
終盤、園子の取材を受けて、キングは自分の過去を認める告白動画を出します。
「良いこと/悪いこと」を他人に決めてもらわず、自分で考え、選び、その責任を引き受けるという宣言。
ここがタイトル回収であり、最終回が「はじまり」と名付けられた理由でもあります。
そしてラストは、花音が体育倉庫に閉じ込められた場面で、助けに来る“ヒーロー”の存在が示される。
絶望だけで終わらせず、次の世代に何を渡すのかという希望を、一滴だけ落として終わる。
それが、「良いこと悪いこと」最終回の結末でした。
補足として、配信では“その後”を描くオリジナルストーリー(10.5話)も用意されています。最終回の余白まで含めて追うことで、この物語はようやく“日常”へ着地します。
良いこと悪いこと1話〜最終回までの感想
全話見終えて、正直いちばん残ったのは「犯人が誰か」よりも、「いじめの後遺症って、大人になっても人生の根っこを折りにくる」という感覚でした。
タイトルが“良いこと/悪いこと”なのに、視聴後の手触りは白黒じゃなくて、ずっと濁ったグレー。そこがこの作品の怖さであり、強さだったと思います。
ここからは、1話から最終回まで通しての感想を、ドラマの構造ごとに整理して書きます。
序盤は「懐かしさ」がそのまま凶器になる導入が上手い
まず序盤が強烈でした。
同窓会って本来は、少し照れくさい“再会のイベント”のはずなのに、この作品はそこに「卒業アルバム」「歌」「当時の呼び名」みたいな“昔の空気”を混ぜて、いきなり凶器に変えてきます。
しかも怖いのは、視聴者も最初は「同窓会のノリ」を一緒に楽しみそうになること。
その空気が崩れた瞬間に、過去のいじめがただの思い出じゃなく、“現在進行形の罪”として立ち上がる。ここで背筋が冷えました。
「森のくまさん」の替え歌が、ミステリーとしても倫理としても効く
中盤まで作品を牽引したのが、例の替え歌(子どもたちが作った“仲間内の歌”)ですよね。
あれ、単なる暗号じゃなくて、「当時の空気がどれだけ残酷だったか」を証拠として保存してるんです。
歌が流れるたびに、視聴者の頭の中で“順番”が回り始める。
でも同時に、「こんな歌を笑って回してたのか」「それを止めなかったのか」という倫理の問いも刺さる。ここで僕は、犯人当てよりも先に“空気の共犯”を突きつけられている感覚になりました。
中盤の怖さは「夢の絵」が現実をなぞり始めた瞬間
このドラマ、ミステリーの推進力を“トリック”よりも“イメージ”で作ってるのが特徴でした。
中でも「夢の絵」がキーになってから、一気に怖さの質が変わったと思います。
現実の事件が、子どもの落書きみたいな“夢”を後追いしていく。
つまり、犯人は現実を動かしてるのに、動機は過去に縛られ続けている。ここが本当に嫌で、でも見てしまう。この“嫌さ”が作品の芯だと思いました。
9話で「正義側の顔」をした実行犯が出てきて、作品の地獄度が跳ね上がる
終盤の転換点は、やっぱり9話でした。
「犯人候補」じゃなく、「実行犯」として正体が明確になる。その瞬間、作品のジャンルが少し変わるんですよね。
それまで視聴者は、どこかで「犯人は同級生の誰かだろう」と思っていた。
でも、正義の側にいるはずの立場が“手を汚している”と分かった瞬間、視聴者の逃げ道がなくなる。これ、単に意外性があるだけじゃなくて、「正義って何?」「正しい怒りって何?」という問いに直結します。
しかも、ここまで積み上げた感情があるから、「復讐」に共感しかける自分も出てくる。僕はこの辺りで、自分の中の“良いこと/悪いこと”の線引きが一番グラグラしました。
最終回の残酷さは「復讐の後」に社会が次のいじめを始めるところ
最終回で一番きつかったのは、真相そのものよりも、真相が世に出た後の展開でした。
事件が終わってスッキリ、ではなく、そこで“別のいじめ”が始まる。
過去の加害が掘り返され、家族が巻き込まれ、子どもに飛び火する。この地獄が、現実のネット炎上や週刊誌報道と地続きすぎて、笑えない。
「罰」は誰が与えるのか。社会は裁判官になれるのか。そして、正義の名を借りた攻撃は、いじめと何が違うのか。
最終回のタイトルが「はじまり」なのも、そこに繋がっている気がします。
事件が終わっても、“問い”はここから始まる。
この後味の悪さを、あえて視聴者に抱えさせたのが、このドラマの真骨頂だったと思います。
総評|このドラマが突きつけたのは「犯人」じゃなく「共犯」
結局、僕がこの作品で一番怖いと思ったのは、犯人の顔じゃありません。
「空気で人を壊す構造」が、子どもの頃だけじゃなく、大人になっても形を変えて続くこと。
そして、視聴者は安全地帯にいるつもりでも、簡単に“裁く側”に回れてしまうこと。
“良いこと”をしたつもりが、“悪いこと”になっていく。逆に、“悪いこと”の中にも、救いに見える瞬間がある。
その揺れを最後まで描き切ったからこそ、しんどいのに忘れにくいドラマになったんだと思います。
最後にひとつだけ。
見終えて「面白かった」で終われない作品って、ブログで書く側としては正直しんどいです。
けど、こういうドラマほど、言葉にして整理する価値があります。僕はそう感じました。
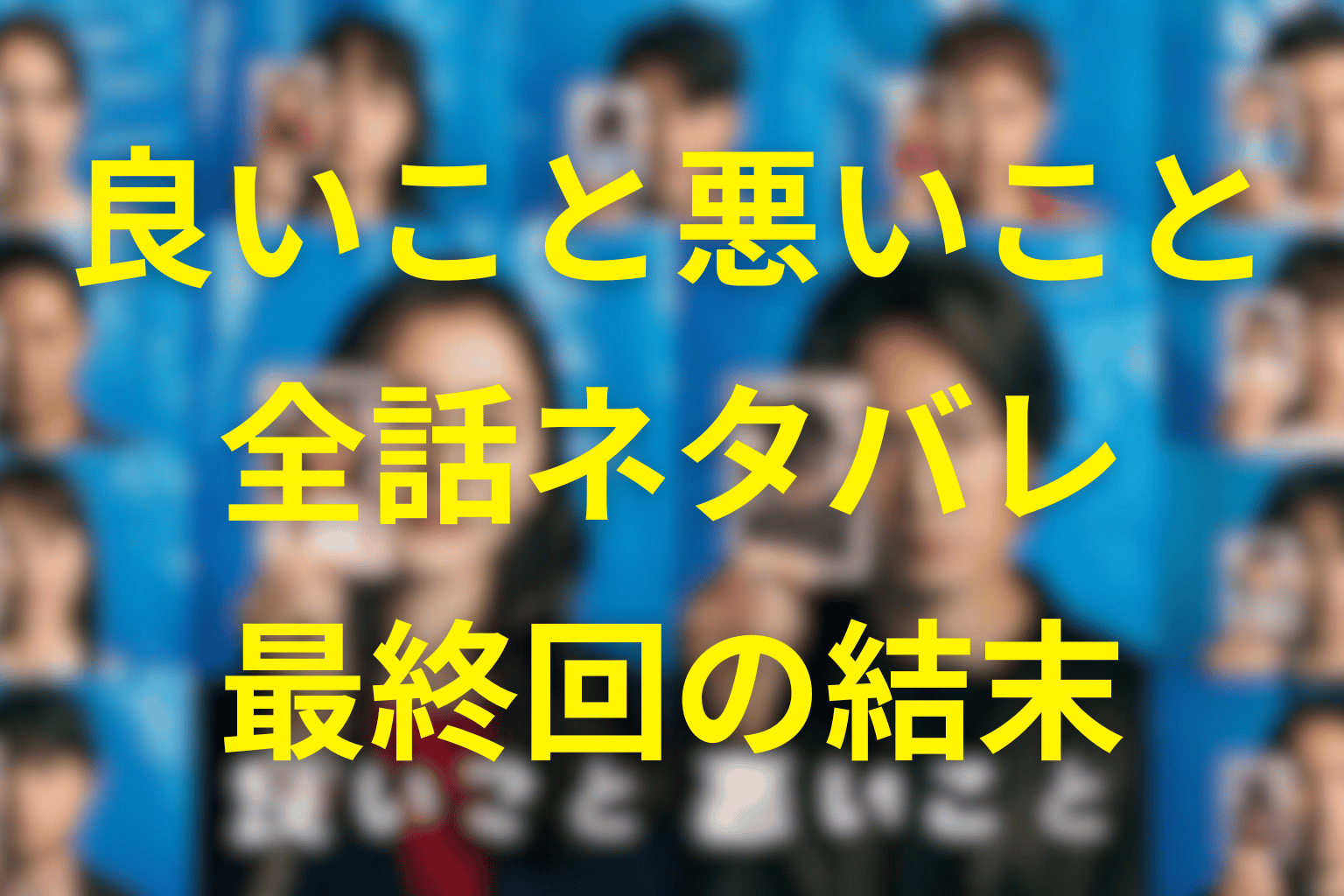
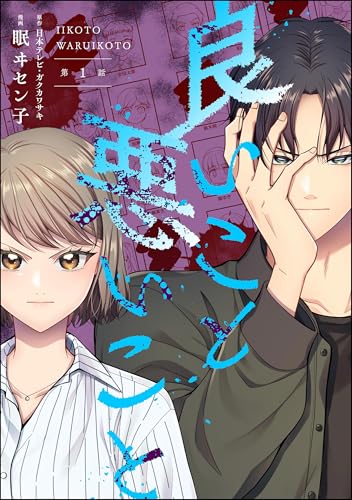
コメント