第4話の最後で浮上してきたのが担任の大谷。
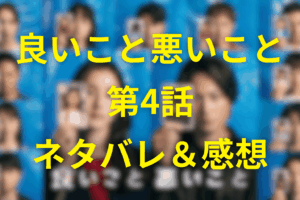
第5話「みんなの夢」は、“言葉にできる者が何を伝えるか”を問う回。
連続殺人の裏で、園子(新木優子)と高木(間宮祥太朗)は母校を訪ね、過去を知る担任・大谷(赤間麻里子)と対峙する。
「いじめはなかった」と笑う先生、見て見ぬふりをした委員長、そして掲示板に残された“博士”という忘れられた声――。
それぞれの“沈黙”が少しずつ崩れ始め、『ごんぎつね』の授業をきっかけに、謝罪と赦しの形が再定義されていく。
ここからドラマ『良いこと悪いこと』第5話のあらすじと感想・考察を紹介します。
良いこと悪いこと5話のあらすじ&ネタバレ
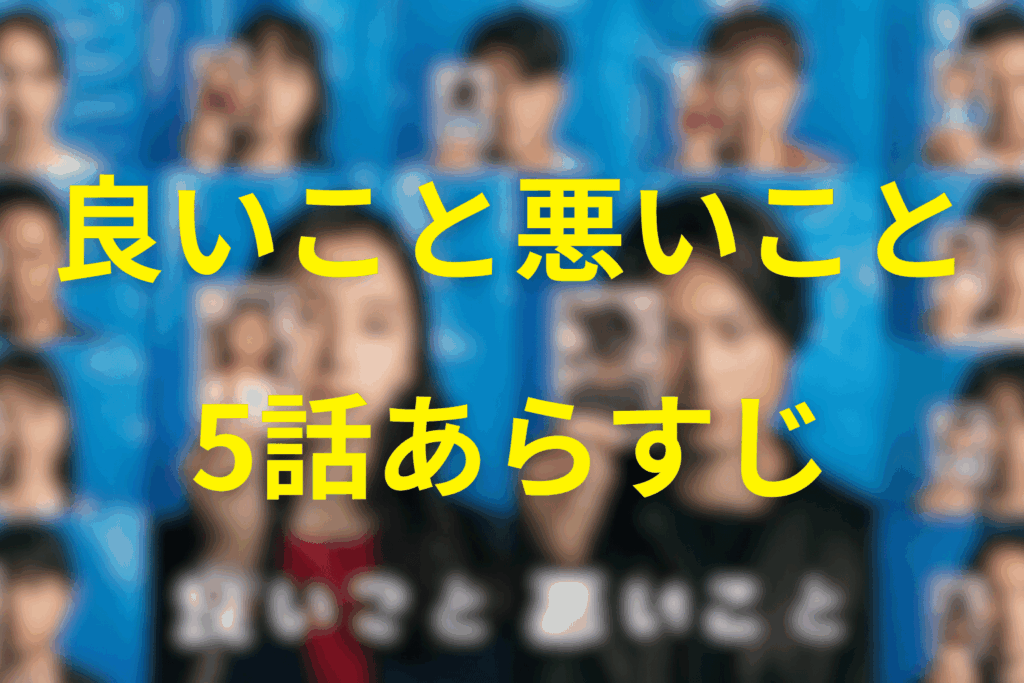
第5話のサブタイトルは「みんなの夢」。
連続殺人の渦中で生き残る“元6年1組”の3人――キングこと高木将(間宮祥太朗)、ターボーこと小山隆弘(森本慎太郎)、ちょんまげこと羽立太輔は、犯人像を「クラス」に引き戻す。
鍵を握るのは、かつての担任・大谷典代と委員長、そしてタイムカプセルに眠る違和感。
さらに掲示板に現れた“博士”という忘れられた声が、事件の地図を描き替えていく。
生き残り3人の作戦会議と「先生しか知らないこと」
連続殺人の標的となっている“キング”こと高木将、“ターボー”小山隆弘、“ちょんまげ”羽立太輔の3人は、高木の自宅ガレージに集まり作戦会議を開く。武田、笑美、桜井と3人の同級生が立て続けに亡くなり、自分たちもいつ狙われるか分からない状況だ。
「園子以外にも、俺たちを恨んでるやつがクラスにいるんじゃないか?」
卒業アルバムのクラス写真を見返しながら、3人は心当たりを探る。しかし、思い当たる顔はなかなか出てこない。
そこで口火を切るのが、ちょんまげだ。
「僕たちのこと知ってる人、もう1人いるよ。大谷先生」
6年1組の担任だった大谷典代は、現在は母校の校長。生徒思いの先生だった記憶もあり、「自分たちが忘れてしまった何か」を覚えているかもしれない——そう考えた3人は、園子に連絡を取り、4人で大谷に会いに行くことを決める。
一方その頃、刑事・宇都見は武田と笑美の「事故死」について違和感を拭えず、上司に再捜査を直訴。
連続不審死として捉え直すべきだと食い下がり、事件は警察レベルでも新たなフェーズに入りつつあった。
母校訪問と園子のフラッシュバック
園子は編集部で、同僚の東雲に「いじめっ子と手を組んでまで取材を続ける意味ある?」と問われる。彼女は静かに答える。
「謝ってほしいわけじゃない。ただ黙って見てるのが苦しいから。それに、死んでほしくはない」
復讐ではなく、「過去をなかったことにさせないため」の取材。
園子自身のスタンスがここではっきり言語化される。
その後、4人は大谷が待つ母校へ向かう。廊下を進むうちに、園子の中で22年前の記憶が立ち上がる。
備品倉庫に閉じ込められたあの日。
昇降口で皆の前に引きずり出されて謝罪させられた屈辱。
ランドセルを階段で奪われて笑いものにされた瞬間——。
懐かしそうに校舎を見回すターボーの横で、園子だけが足を止め、表情を固くしてしまう。そんな園子の様子に、キングの胸には新たな痛みが生まれる。自分が“楽しかった”と信じていた小学校時代と、園子が経験していた現実のギャップが、ここで可視化される。
校長室へ向かう途中、キングは4年生の娘・花音が男の子と口論しているのを目撃する。思わず声を掛けながらも、「自分がかつて何をしてきたのか」が頭をよぎり、簡単には口を挟めない。その一瞬の逡巡が、のちの“親子の会話”に繋がっていく。
大谷校長との面談と「なかったこと」への怒り
校長室では、定年が近い大谷が4人を出迎える。まずは形式的な雑談のあと、キングは黒塗りの卒業アルバムを差し出し、単刀直入に切り込む。
「このクラスの中で、恨まれてもおかしくないようなこと、何か覚えてませんか?」
大谷の答えは「特に目立ったトラブルはなかった」「みんな自慢の教え子だった」というもの。ちょんまげが「いじめはなかったんですか?」と踏み込んでも、「まさか、そんなこと」と笑顔で否定する。
ここで黙っていられなくなるのが園子だ。
「私はこの学校でいい思い出がありません。いじめられていたからです」
ようやく口を開いた園子に対し、大谷は「気づいてあげられなくてごめんなさい。教師失格ね」と謝る。しかし同時に、キングにこう返す。
「あなたが人気者だったでしょ。あなたが覚えてないことを先生が覚えてるわけないじゃない」
この言葉は、“責任の所在”を巧妙にぼかすような一撃でもある。
のちに繋がる“タイムカプセル”の矛盾と照らし合わせると、「先生は何かを知っている」という疑念が一気に強まる。
4人が去ったあと、大谷は机の引き出しからスマホを取り出し、誰かに連絡しようとする。しかし、机の上の娘と孫の写真が目に入り、いったん思いとどまる。その表情には、単純な“見落とした先生”では片付かない、深い後悔と恐れが滲んでいた。
消えた卒業アルバムと委員長の来訪
キングの家に戻ったターボーは、校長室で覚えた違和感を共有する。
「2003年度の卒業アルバムだけ、棚になかった」
タイムカプセルの中に顔を塗りつぶした卒アルが入っていたことを踏まえると、
「誰かが一度タイムカプセルを掘り起こし、アルバムを入れ替えた」
という可能性が浮上する。
つまり「卒アル本体を持っていない人物」、すなわち学校側の人間=大谷が最有力という仮説が立つ。
しかし園子は静かに、しかし強く言う。
「先生が何も知らなかったなんて、あるわけない」
教室でいじめを見て見ぬふりをした大谷の背中。冷たく目をそらしたあの視線。園子の記憶は鮮明だ。
そこへ突然、学級委員長だった小林紗季がシュークリームを持って訪ねてくる。
「みんなが集まってるの、卒アルのことだよね?」
紗季は高木から羽立のことを聞かれた時点で、ただ事ではないと察していたという。しかし、キングは「巻き込みたくない」と事情を話そうとしない。
「でも、あのクラスで起きたことなんだから。きっと私にもできることがあると思う」
そう言う紗季は、まず園子との信頼を築くため、2人きりの食事に誘う。
「あの頃からやり直せないけど、少しでも取り戻したい」という言葉には、加害側の一員としての罪悪感と、償おうとする意志がにじむ。
焼肉での告白と「いじめの傍観者」の罪
焼肉店で向かい合う園子と紗季。園子は料理に箸をつけようとせず、開口一番こうこぼす。
「いじめっ子とご飯食べても、美味しくないですよね」
紗季は真正面からそれを受け止めるように、「何もできなかった。いじめに気づいていたのに、知らないふりをしていた。本当にごめん」と頭を下げる。許してもらえるとは思っていない。それでも伝えなければ前に進めない——そんな誠意が言葉の端々に滲む。
園子は静かに問い返す。
「私が犯人だと思わなかったんですか? 事件のことも、私がいじめられていたことも知ってたんですよね」
その痛みを確かめるかのような言葉に対し、紗季はきっぱり答える。
「園子さんはそんなことしない。いじめっ子だろうと誰だろうと、あの人たちに死んでほしくはないでしょ? 私も同じ」
ここで初めて二人の間で、“怒りの方向が同じ”であることが共有される。
「いじめが許せない」「でも死んでほしくはない」。
この複雑な感情が交差する地点こそ、タイトル「良いこと悪いこと」が照らすグレーゾーンだと強く感じさせる。
さらに紗季は、子どもの頃キングが好きだったと打ち明ける。
「美人すぎる」とからかわれ、教室で浮いてしまった背景には、キングをめぐる小さな構図もあったのかもしれない——そんな“誰も語らなかったもう一つの傷跡”が、ここでそっと明かされる。
園子はすぐに赦さない。「言葉で済むことじゃない」と静かに返す。しかし、彼女がその場に座り、向き合ったこと自体が“関係の再起動”を意味していた。
委員長の来訪と“焼肉のテーブル”――「見て見ぬふり」への謝罪
キング達が作戦会議している時に元クラス委員長・小林紗季(平岩紙)が訪ねてくる。
小林は園子を焼肉に誘い、夜食べに行く。
店のテーブルで、紗季はゆっくりと切り出す。
「ごめんね。いじめに気づいてたのに、何もできなかった」
そして続けて、「高木くんのことが好きだった。だから何も言えなかった」と。
ごんぎつねの授業とキングの「ごめんなさい」
その頃、ちょんまげはターボーの会社で働き始めていた。「働いてもらうっていうか、守るっていうか」とターボーは説明しつつ、羽立に仕事と居場所を与える。
一方キングの家では、娘・花音がクラスメイトの竜馬とケンカして落ち込んでいた。どっちが悪かったのか尋ねると、「花音」と小さく答える娘。キングは「悪いと思ったなら謝ろう。それで仲直りだ」と促すが、花音は「そんな簡単にできない」と背を向けてしまう。
「パパもそうする?」
その問いに「するよ」と答えながら、キングは自分もまだ園子に本心から謝れていないことを痛感する。この“父親として教えたいこと”と“自分ができていないこと”の矛盾が、後の行動の背中を押す。
その後、園子は大谷に頼まれ、4年生向けの特別授業を担当する。題材は新美南吉「ごんぎつね」。
いたずらでうなぎを盗んでしまい、それが病気の家族のためだったと知って後悔するごん——償おうとしても伝わらず、悲劇に終わる物語だ。
園子は子どもたちに問いかける。
「もしごんがちゃんと謝れていたら、どうなっていたと思う?」
ここで手を挙げるのは花音。
「ごんは悪いことをした。かわいそうとは思わない。パパはどう思う?」
教室の後方にいた高木が、静かに答える。
「ごんは“言えなかった”から死んだ。人間は言える。だから伝えるべきなんだ」
「ごんがかわいそうなのは、謝ることもできなかったことだよ。僕たちは人間だから、謝ろうと思えば何度だって謝れる。相手が許してくれるまで、ちゃんと言葉にできる」
その言葉を、自分自身に言い聞かせるように。
「なかったことにはできない」――高木の謝罪と園子の応答
授業を終えたあと、高木は園子のもとへ歩み寄り、深く頭を下げる。
「事件を解決すれば許してもらえると思ってた。違うよな。最初から、謝るべきだった」
園子は涙をこらえながら答える。
「今は、許せない。でも事件を終わらせよう。全部、終わらせよう」
赦しよりも、まず“構造を終わらせる”という共通の覚悟がここに生まれた。
再訪・校長室――「忘れた」は通用しない
園子と高木は再び校長室へ。
「卒業アルバムはどこにあるんですか」「タイムカプセルの中身、誰が変えたんですか」。
矢継ぎ早の質問に、大谷は「いろいろ忘れてしまって」と笑みを保とうとする。
高木は真っ直ぐに見つめ、「俺は加害者です。逃げません」と言葉を絞り出す。だが、大谷は「お帰りください」と面談を打ち切る。
校庭では、花音がクラスメイトに頭を下げる姿があり、園子は「収穫、ありましたね」と静かに呟く。
みんなの夢のビデオと大谷の罪悪感
再び大谷を訪ねたキングと園子は、タイムカプセルと卒業アルバムについて問いただす。
「先生、どうして僕たちの卒アルだけ無いんですか?」
大谷は「覚えていない」「そんなはずはない」と言葉を濁すが、視線は泳ぎ続ける。
キングは自分が園子をいじめていたことも正直に告白し、
「そんなクラスを見ていた先生なら、何か知ってるはずだ」
と訴える。
しかし大谷はそれ以上を拒み、2人を校長室から追い出す。園子はその背中を見ながら、「やっぱり何か隠している」と確信する。
一人になった校長室で、大谷はモニター越しに“みんなの夢”ビデオを再生する。
ヒーローになりたいと言って茶化すキングに、「あなたなら本気でヒーローになれる」と優しく声を掛ける自分。
「強く生きていく」と語る園子の夢。
あの日の子どもたちが笑い合う姿。
大谷の目から涙がこぼれる。
見て見ぬふりをした自分の罪が、
いま連続殺人という形で帰ってきてしまった——。
その罪悪感を噛み締めるように、大谷は電話を取り、
「もうやめませんか。言われた通りタイムカプセルを掘り起こしました。でも、もう耐えられません」
と“誰か”に訴える。
そして地下駐車場。
黒いワゴン車の後部座席に向かって、大谷は深く頭を下げる。
彼女は“ただの教師”ではない。
誰かの指示を受けて動いていた協力者だった——その輪郭がここで決定づけられる。
掲示板「鷹里小の森」と忘れられた7人目・博士
ターボーの会社では、羽立が「鷹里小学校」のワードから“鷹里小の森”という古びた卒業生サイトに辿り着く。掲示板にはこんな書き込みが残されていた。
「このHPも、俺のことも誰も覚えてないんだ」
「誰一人覚えてない」
日付はごく最近。
羽立は画面に向かって投稿する。
「覚えてるよ、博士だよね?」
するとすぐに返事が来る。
「もしかして、ちょんまげ?」
「あの7人組を覚えていたのは君だけ」
画面に次々と流れる恨みの言葉に、羽立は恐怖と動揺でPCを閉じる。
ここで初めて、
- キングたちは“6人組”と思っていた
- しかし博士は“7人組”と言っている
という決定的なズレが浮かび上がる。
卒アルに名前も写真も残っていない“忘れられた7人目”。その影が、いよいよ輪郭を持ち始める——。
制度の回路が動く――宇都見、再捜査に舵
警視庁の宇都見啓(木村昴)が、笑美と武田の“事故死”を再捜査に着手。
「民間の追跡(園子と高木)」に、「公的な記録(警察)」が接続され、事件は“教室の罪”から“社会の責任”へと拡張していく。
良いこと悪いこと5話の伏線まとめ
5話は、一見すると「大谷先生が怪しい回」だが、実際には物語全体の構造を揺さぶる伏線が大量に仕込まれている回でもある。ここでは、その中でも特に大きいポイントを整理しておきたい。
タイムカプセルと消えた卒業アルバム
ターボーが気づいた「校長室に2003年度の卒業アルバムがない」という違和感は、極めて重要な物証だ。タイムカプセルから出てきた“黒塗りアルバム”と照らし合わせると、作業の手順はほぼ一本の線で繋がる。
- 誰かがタイムカプセルを掘り起こす
- 本物の卒業アルバムを抜き取る
- 顔を塗りつぶしたアルバムを新たに入れ替える
- 何もなかったかのように埋め直す
この工程を実行できるのは、学校の敷地に自由に出入りでき、タイムカプセルの場所も把握している教員側の人間。つまり“大谷の関与”が一気に現実味を帯びる。
さらに、ネットでは「大谷は実行役に過ぎず、指示した“外側の誰か”がいる」という分析も多く、この二層構造が5話ではより濃く示唆された。
大谷の電話と黒い車——“外側の手”の存在
大谷が電話で「もうやめませんか」「言われた通りタイムカプセルを掘り起こしました」と話していた場面は決定的だ。これは、
- 大谷が誰かの指示で動いていた
- 自分では止められない“力関係”が背後にある
という二つを明確に示す。
その後、黒いワゴン車に乗り込み、後部座席に向かって頭を下げる描写は、相手が“大谷よりも上の立場”であることの暗示。その存在によって、事件は「6年1組内部の復讐」ではなく「外側の力を含む複合事件」へとスケールアップしていく。
「みんなの夢」ビデオと園子の宣言
校長室で再生された“みんなの夢”ビデオは、ただの回想アイテムではなく、動機と構造に直結する重要映像だ。
- キングが「ヒーローになって悪い奴をやっつける」と語る
- 園子が「二度とこんなことが起きないように強く生きていく」と宣言する
これらは、“あの日の子どもたちの価値観”を固定した証拠であり、大谷が今も大事に保管しつつ隠そうとする姿勢は、「記録」「忘却」「改ざん」という作品テーマに深く結びつく。
委員長の謝罪と「知らないふり」の二重の意味
焼肉の席で紗季が語った「いじめに気づいていたのに、知らないふりをしていた」という告白も重要だ。
ここには二つの意味がある。
- いじめの“加害”は、手を下した人間だけでは成り立たない
- “気づいて黙っていた人間”もまた構造的加害者である
紗季の立場は、過去の真相解明だけでなく、“大人になった今の彼女が何を覚えていて、何を隠しているのか”という謎にもつながる。
主演俳優が「委員長と大谷はキーパーソン」と語った通り、この2人は最終盤の鍵を握っている。
掲示板の“博士”と「7人組」という言い回し
掲示板に現れた“博士”が書き込んだ
「ちょんまげだけだよ。あの7人組で覚えててくれたのは」
という一文は、5話最大級の伏線だ。
ここから分かることは、
- キングたちは「6人組」と思っていた
- しかし博士は「7人組」と認識している
- つまり“博士=忘れられた7人目”である可能性が極めて高い
さらに注目すべきは、“博士”の一人称が「俺」「僕」と揺れている点だ。
これにより、
- 同一IDを複数人が共有している
- 7人目の意思を“誰かが引き継いでいる”
など、複数犯説を支持する考察も急増した。
また、「即レスが来た=ちょんまげの行動をリアルタイムで把握している人物」という推測から、“ターボーの会社のネットワーク経由説”も浮上している。
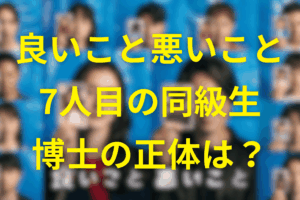
公式ポスターの左上の人物=“7人目”疑惑
日本テレビ本社の巨大ポスターに、キービジュアルにはいない“謎の人物”が写っていた点も5話で大きな話題となった。
SNSでは、
- 「あれが博士?」
- 「7人目のキャストがシレッと写っているのでは?」
という推測が飛び交い、複数のメディアも関連する考察記事を掲載。
制作側が意図的に“謎を増幅させるミスリード”を行っている可能性が高く、最終回に向けて、このポスターがどこまで伏線として機能するのか注目が集まる。
良いこと悪いこと5話の感想&考察
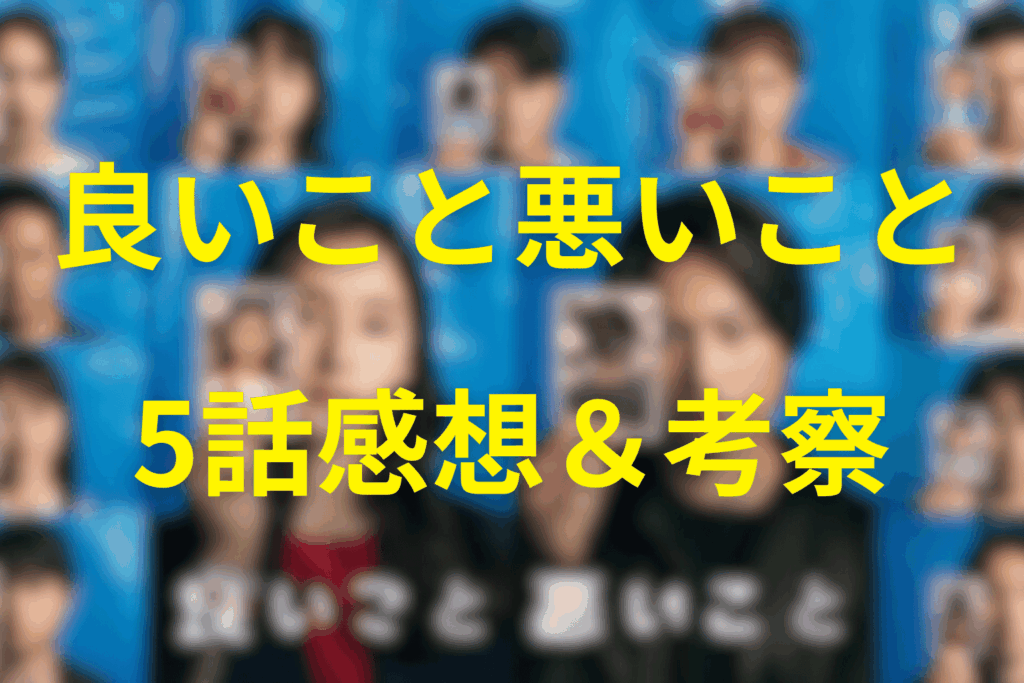
第5話は、「言葉にできる者の責任」を正面から描いた回だ。
『ごんぎつね』という古典を“伝達の寓意”として埋め込み、謝罪を“感情の終止符”ではなく“関係の再起動”として配置した。同時に、先生(大谷)・委員長・博士という“忘却の三角形”を立ち上げ、事件の焦点を加害と被害の二項対立から“記憶と責任の分配”へと拡張した。
それぞれの「言葉」が誰のために、何を動かしたのか。以下、論点別に掘り下げていく。
『ごんぎつね』の置き方――“狐は言えない、人は言える”
園子の授業は、ただの演出ではなく物語を駆動する装置だった。
「狐は言えない、人は言える」――教室の後方からそう答えるのは、高木。
「ごんは“言えなかった”から死んだ。人間は言える。だから伝えるべきだ」
この台詞で、“言葉にできる者は言葉にすべき”という倫理が、物語の中に刻まれる。
そしてそれは、高木自身の“謝罪”の動機となり、園子の「今は許せない」という現実的な返答とぶつかる。
授業→父娘の質疑→謝罪という三段構成が、謝罪の意味を“再起動”のための行為として成立させていた。
先生の「知らなかった」は免罪か――“事なかれ”の個人責任
「いじめはなかった」「覚えていない」と笑う大谷の姿は、学校という制度そのものの“顔”に見える。
だが、終盤の電話で彼女は崩れる。
「あなたに言われた通り、掘り起こした。もうやめませんか」
“知らなかった”という防御線が、“知っていた”あるいは“関与していた”へと軸をずらす。
不作為(見て見ぬふり)と加担(意図的な隠蔽)のあいだに横たわる「個人責任」をどう測るか。
5話はその判断を観客に委ねた。
涙を流す彼女の姿は、事なかれを続けた教師の終焉であり、「沈黙の加害」を描く象徴だった。
委員長の“共犯的謝罪”――赦しを前提にしない誠実さ
焼肉店での会話は、これまでのどの告白よりも静かで痛い。
委員長・紗季(平岩紙)は、箸を握りしめたまま言う。
「許さなくていい。でも、謝りたかった」
そして、「当時、高木が好きだったから、園子をかばえなかった」と続ける。
この“人気者の磁場”がいじめの背景にあったことを、紗季自身が言語化した瞬間だった。
園子はただ一言、「謝ってすぐに楽にならないで」と返す。赦しを急がず、沈黙を共有する。そこにこの作品の誠実さが宿っていた。
「博士」=7人目の輪郭――忘却という二次加害
掲示板の書き込み主“博士”は、「誰も覚えていない」という言葉を何度も繰り返す。
その反復自体が、存在の抹消、すなわち“忘却の暴力”を体現していた。
羽立が「覚えてるよ、博士だよね?」と返した瞬間、「もしかして、ちょんまげ?」という返信が届き、記憶の空白が一気に現実を取り戻す。
博士が“7人目”として浮上したことで、事件は直接的な加害だけでなく、「忘れたことが加害になる」という新しいフェーズに突入した。
“記憶の欠落”こそが、最も静かで深い罪として描かれている。
博士については以下記事で考察しています↓
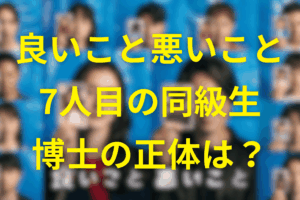
タイムカプセルのロジック――“誰が、何を、いつ、誰に見せたか”
タイムカプセルの中に卒業アルバムが入っていたという一点は、「一度掘り起こした誰か」の存在を示唆している。
卒業アルバムは、そもそも卒業時に配られるもの。なのにカプセルから出てきた。
この異常な順序の逆転が、5話最大のミステリーポイントだ。
誰が掘り、何を入れ替え、いつ埋め直し、誰に見せたのか。
この“情報伝達の履歴”こそが、今後の事件の糸口になる。
大谷=実行者(塗り/掘り/埋め)という仮説のもと、背後で誰が指示したのか――その“黒幕の声”が、電話の相手ではないかと推測される。
制度の回路と“公的記録”――宇都見の再捜査が意味するもの
警視庁の宇都見啓が再び動き出す。
「事故」とされた死を、もう一度テーブルに載せる。
この行為は、私的探求(園子・高木)と公的記録(警察)を橋渡しする象徴だった。
5話で確立した「なかったことにしない」という規範が、ここで社会的手続きへと変換される。
記憶を証拠に変えること。
“教室の真実”を、制度の言葉に翻訳できるかどうか。次の焦点は、そこにある。
5話の伏線・小道具チェック
- 2003年度の卒業アルバムが校長室にない:タイムカプセルとの関連を示唆。
- 「みんなの夢」動画:大谷が保持している理由が“埋め直し仮説”と接続。
- 黒い車:脅迫・共犯の象徴として再登場。
- 掲示板「鷹里小の森」→博士の発見:7人目の実在を補強。
次回への見どころ
キャストコメントどおり、「先生と委員長、そして博士」が物語の核に接近する。
先生=情報の入口、委員長=クラスの秩序の記憶、博士=忘却の被害者。
この三者がどのように“言葉”を取り戻すかが、次回の見どころとなる。
5話はその直前で、登場人物それぞれに“言葉の責任”を割り当てた回。赦しではなく、記憶をつなぐための倫理が整った――物語はいよいよ核心へと向かう。
良いこと悪いことの関連記事
良いこと悪いことの全話ネタバレはこちら↓
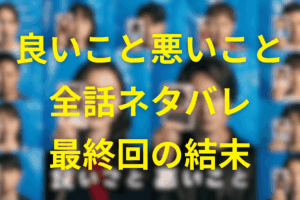
良いこと悪いことの漫画についてはこちら↓
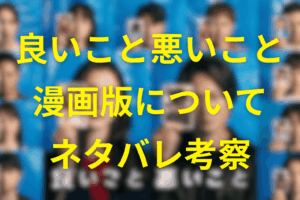
6話についてはこちら↓
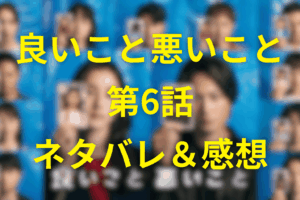
3話についてはこちら↓
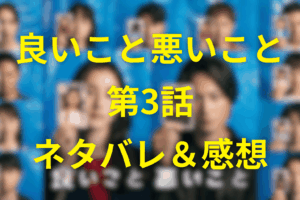
4話についてはこちら↓
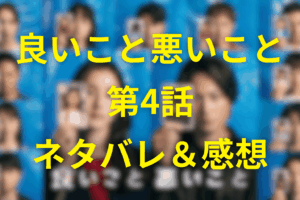
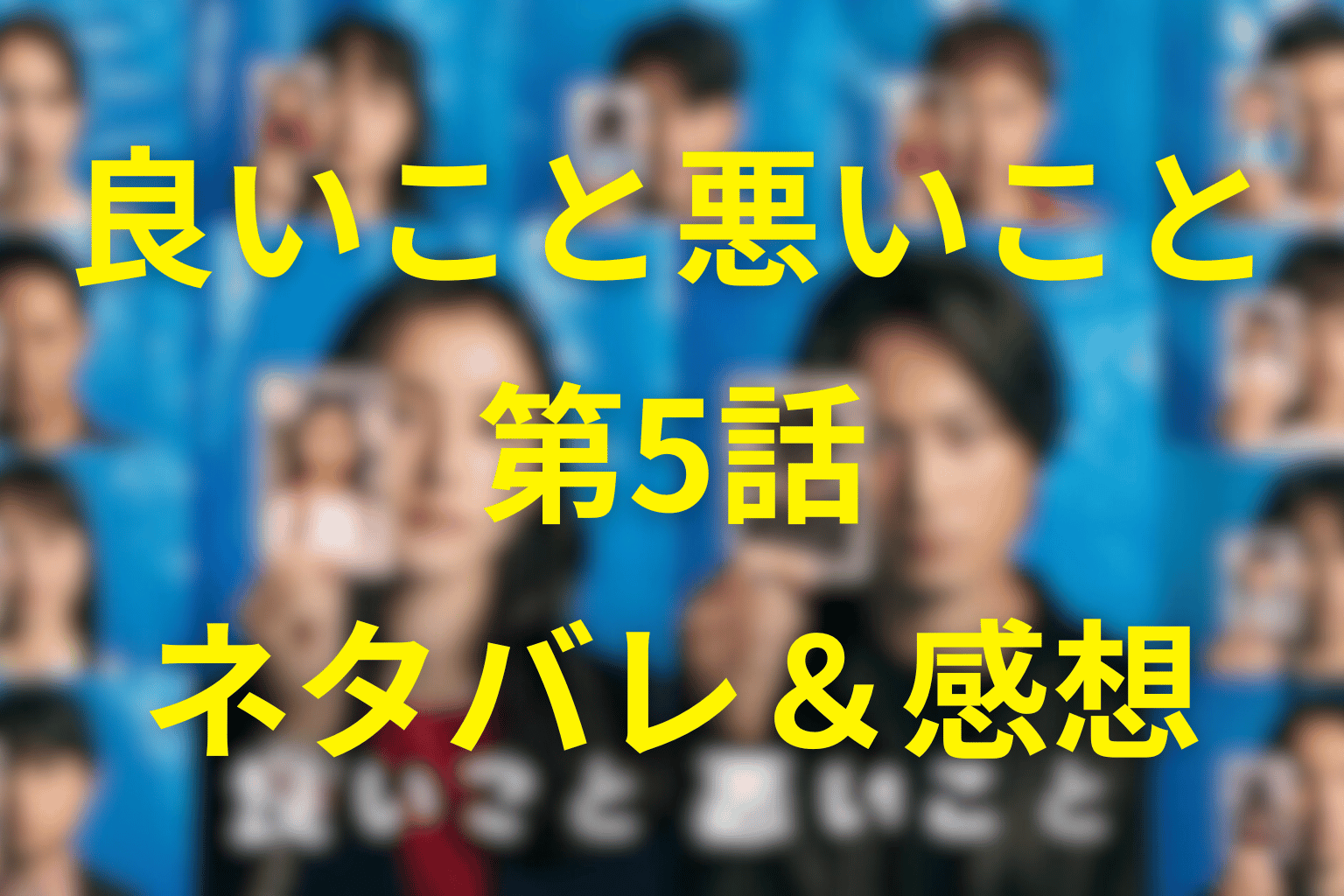
コメント