前話で小山が襲われた衝撃が残る中、第4話では物語がさらに暗く、そして深く潜っていく。
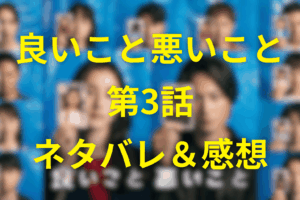
かつてのいじめ加害者・羽立は、高木と園子の訪問を突き放しながらも、わずかに心の扉を開き始める。
“夢と手口”が反転し、替え歌の法則が再び作動する中で、物語の外側には“忘れられた一人”の影が忍び寄る。
ルールに支配された復讐劇が、ついに〈人間の記憶〉という核心へ踏み込んだ回だった。
良いこと悪いこと4話のあらすじ&ネタバレ
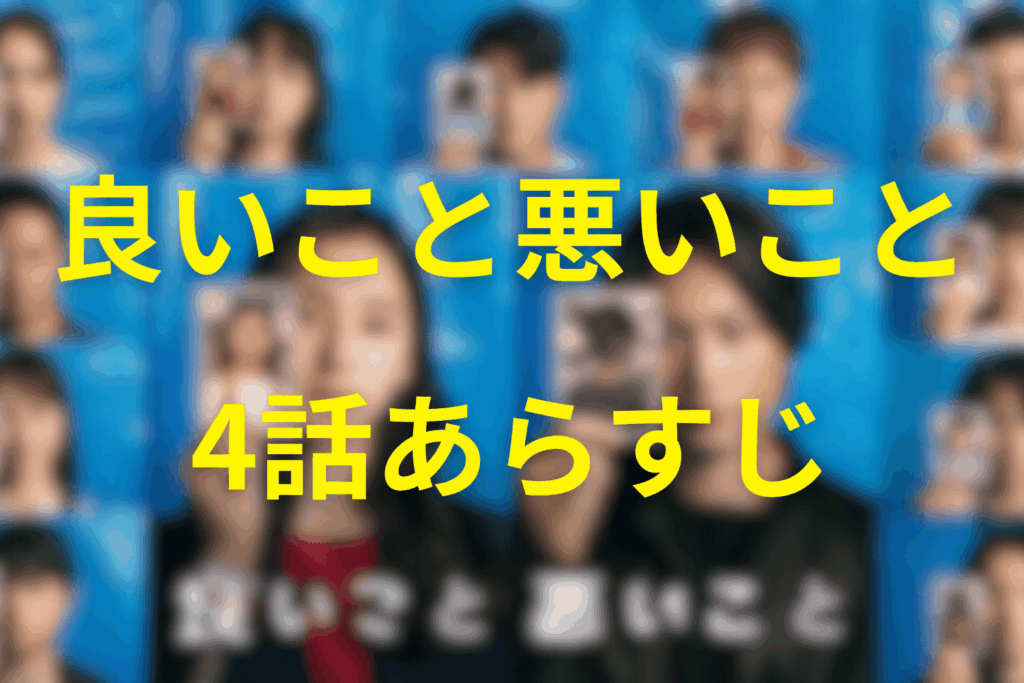
日本テレビ系・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』第4話のサブタイトルは「黒」(11月1日放送)。
タイトル通り、卒業アルバムの“黒塗り”と22年前の“替え歌”という二重のルールが、行動=結果としてついに物語の表層に現れる。
さらに、“忘れられた7人目”の影が初めて可視化され、事件の重心は「6人の内側」から「教室の外側(大人・制度)」へ静かにシフトする。
シリーズ全体の設計図が輪郭を帯び始めた、重要な転位回だった。
冒頭:3件の死と小山の襲撃——“替え歌の順番”が法則化する
冒頭、高木将(間宮祥太朗)と猿橋園子(新木優子)は、連鎖する不審死(武田→桜井→笑美)と襲撃の順番が「替え歌の歌詞順」に一致していると確信する。
そしてついに小山隆弘(森本慎太郎)への直接的な襲撃まで発生し、偶然の域を超える。
残された線上に浮かぶのは“ちょんまげ”こと羽立太輔(森優作)。
「次に狙われるのは羽立だ」——物語は一点へと収束し、緊張が一気に高まる。
学級委員長・小林紗季を頼る——住所が開く過去の扉
羽立を守るため、高木はかつての学級委員長・小林紗季(藤間爽子)に連絡を取る。
彼女の情報で羽立の居場所が判明し、高木・園子・小山の3人は週末に向かうことを決意。
“守りに行く”という行為は、同時に過去と向き合う試練でもある。委員長という“秩序の記憶”を持つ人物が、今の安全策と22年前の記憶を繋ぐ“媒介”として再登場した。
羽立の部屋——「友達なんかじゃない」の拒絶
古びたアパート、散らかった部屋、閉ざされたカーテン。
3人の訪問に、羽立は「僕の番か」と悟ったように呟く。ニュースで自分が次と知っていたのだ。
高木たちが「守りに来た」と伝えても、羽立の反応は真逆。
台所から包丁を持ち出し、園子に押しつけるように差し出し、「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、自分を殺してほしいと言い出します。
羽立は「僕たちは……君をいじめてたんだから」とも口にし、自分が標的にされるのは当然の報いだと受け入れようとする。
高木は「友達同士で守ればいい」と説得しますが、羽立は「友達なんかじゃない」と言い切ります。かつて同じ“輪”にいたはずの彼がここまで拒絶する背景に、この物語の核心が隠れているのはほぼ確実です。
加害と被害の記憶は非対称であり、加害側の“守る”という善意は、被害者にとって“再演”に見える瞬間がある。
「守る/守られる」は当人の合意がなければ成立しない——その倫理を羽立が言葉で突きつけた。
桜井幹太(カンタロー)再び連れ去られ、そして最期へ——犯人の“完遂主義”
一方、2人目の標的だった桜井幹太(カンタロー)は、火災からの回復が進み、車椅子で動けるほどに。ところが突然病室から姿を消します。
間もなく、高木のスマホに動画が届きます。袋をかぶせられ、灯油を浴びたカンタローが“生きたまま炎に包まれていく”という凄惨な映像。送り主は不明ですが、「キングにだけ見せる処刑」という構図が、犯人の恨みの向き先を明確にしています。
カンタローの夢は“消防士”。その夢を嘲笑するかのように「火」で挑む二度目の襲撃は、タイトルにも通じる残酷なアイロニーです。
「守る」の手触り——届かない言葉、ズレの痛み
一度は拒絶されて退いたものの、園子は一人で羽立の部屋を再訪。ここからの会話が4話のハイライトです。
園子は羽立を説得するが、彼の自己評価は地の底に沈んだまま。
「殺されても仕方ない」という諦めが滲み、“守ってやる”という上位目線が逆に彼を追い詰める。ここで作品は、“良いこと”が“悪いこと”に転化する瞬間を静かに描く。
園子は羽立の部屋の掃除を手伝い、黒塗りの夢の絵に込めた思い――「ああはならない」――を静かに語る。
慰めではなく、自分の足で立つための刺激として言葉を残す誠実さが際立った。
「少しだけ」開く——土下座の告白と、関係の再起動
園子は、自分が「どの子」と呼ばれていた当時の痛みを語り始めます。羽立も、
- 高木たちのグループに入りたくて、園子をいじめる側に回った
- 本当は嫌だった
- でも「仲間外れになりたくない」という気持ちに勝てなかった
と、あの頃の臆病さを泣きながら吐き出していきます。
やがて羽立は土下座し、「君をいじめないと友達でいられないと思った」と告白する。
完全な和解ではなくとも、閉じた扉が少しだけ軋んだ。
この“少しだけ”の変化が、次回以降の“同意なき保護を避ける”守り方へと繋がっていく。
園子は全面的に許すわけではなく、「自分を変えられるのは自分だけです」と言い残して部屋を出ていく。この“赦しきらない距離感”がリアルで、関係を一度区切る脚本が巧妙です。
週刊アポロ・松井健が“どの子”の等身大パネルを破壊——メディアの嫉妬と“炎上装置”
別軸では、週刊アポロ編集部の新人記者・松井健(秋谷郁甫)が、園子(=どの子)の等身大パネルを破壊する。
職場での露骨な敵意の発露であり、承認欲求が破壊衝動へ転じる危うさを示す。
事件が“世間の目”を利用して進む構造である以上、メディア内部の歪みは見逃せない撹乱要因。
今後の“情報戦”を左右する布石としても重要なシーンだった。
終盤①:ラストで仕掛けられた“もう一つの視線”——ボンバーマン回想と〈7人目〉
園子の言葉に後押しされ、羽立は部屋を片づけ身なりを整え、園子とともにバー「イマクニ」へ。
高木と小山が待っており、3人はようやく腹を割って語り合います。羽立は「本当は嬉しかった」「2人が友達って思ってくれて」と本音を明かし、都合の悪さから目をそらし続けた自分を振り返ります。
その後、子どもの頃と同じように「ボンバーマン」を始めると、画面は21年前の教室へ切り替わります。6人で遊んでいるはずの場面ですが、
- ゲームは4人プレイ
- 遊戯王カードをする2人
- 漫画を読む1人
人数を合わせると7人がその場にいた計算になります。さらに、羽立の背後には“顔の見えない右手と右ひざ”が映り込んでいる。これが、ネットで「ついに7人目が出た」と話題になったカットです。
また、記憶の食い違いも描かれます。
- 高木は「羽立はずっと宿題をしていた」と認識
- 小山は「宿題のあと一緒にゲームしていた」と証言
このズレが、“忘れられた誰か”の存在を浮かび上がらせていきます。
終盤②:廊下をスコップで引きずる“女の影”——制度の暴力の匂い
続いて、校舎の廊下を土のついたスコップを引きずる女性の影。
タイムカプセルに触れる象徴的なショットであり、アルバムの黒塗りと合わせて“記録の改変”を示唆する強い記号だった。
視聴者の間では、現・校長=当時の担任・大谷典代(赤間麻里子)への疑惑が集中。
“教室の外側(大人・制度)”が事件を動かしている可能性を、画面が初めて照らし出した瞬間だ。
終盤③:スナック「イマクニ」の常連・宇都見の正体——“しがない公務員”は刑事だった
高木が通うスナック「イマクニ」の常連・宇都見啓(木村昴)が、実は警視庁捜査一課の刑事であると判明。
第2話での「しがない公務員」という自己紹介が皮肉にも真実であったというツイストが効く。ここから、素人の推理とプロの捜査が交差する新フェーズに突入。
以降は、私的探求を公的記録へ翻訳できるかが焦点になる。
まとめ:法則(替え歌)の強度と、テーマの更新
第4話の結末で、“替え歌の順番”は依然として強固な法則として生き続け、5人目=羽立の危険は増す一方。
並行して、カンタローの“完遂主義”の死と廊下のスコップが「記録の改変」を立体化した。
作品のテーマは、加害/被害の相関を超え、“忘却”“見て見ぬふり”“記録の書き換え”という構造的な暴力へと拡大。
ミステリーとしての法則の強度と、ヒューマンドラマとしての倫理の厚みが見事に噛み合った、シリーズ屈指の濃密な一話だった。
補足:第4話で増えた“確認すべき事実”チェックリスト
- タイムカプセルの“掘り直し”の有無と時刻(出入記録・備品簿・鍵の管理)。
- 2003年度の卒業アルバムの所在履歴(校長室→カプセルへの移動経路)。
- 「みんなの夢」など学校内記録物の保管・閲覧権限(誰が見たか/誰が編集できたか)。
- ボンバーマン回想に映る“第7の手”の正体(当時の呼称・座席表・クラブ活動記録との照合)。
- 宇都見の再捜査の範囲(“事故死”というラベルを外せるかどうか)。
これらは第5話以降、先生・委員長・博士という三者の線が交わる“真相フェーズ”へ直結する実務的な伏線群となる。
良いこと悪いこと4話の伏線
4話は、表向きには「羽立の再生」と「カンタローの二度目の襲撃」がメインですが、細かい画面情報やラストの連続ショットに、相当量の伏線が仕込まれています。
ここからは、あくまで4話時点で確定・示唆された要素に絞って整理していきます。
回想に映る“右手と右ひざ”――7人目の存在確定
最も大きな伏線はやはり、ボンバーマン回想のカット。
- 6人で遊んでいるはずの場所に、計算上“7人目”が存在する
- 実際、羽立の背後に、顔の映らない右手と右ひざだけが映る
という二段構えで、「本当にもう一人いた」事実を視覚的に刻み込んでいます。
これまでは「本当に7人いたのか?」「勘違いかも」と揺れていた“7人目仮説”が、この回想でほぼ確定に近づく。しかもその人物は、キングたちの記憶から綺麗に抜け落ちている。ここに「忘却」が大きなテーマとして重なってきます。
個人的には、
- 7人目は羽立と同じく“自信がない側”に属していた
- しかし、キングたちにとっては「ゲーム機を持っている」「宿題をやってくれる」など、便利な存在だった
- その利害関係の中で、ある決定的な事件が起きた
という方向のドラマが仕込まれているように感じます。
記憶の食い違い=“都合の悪い真実”の隠蔽?
高木は「羽立はずっと宿題をやってくれていた」と語り、小山は「宿題のあと、一緒にゲームもしていた」と証言。この“細部のズレ”は、単なる言い間違いではなく、脚本が意図的に置いたノイズでしょう。
- 高木の記憶=羽立は“ずっと裏方”のまま
- 小山の記憶=羽立も輪に入っていた
ここから見えてくるのは、それぞれの罪悪感の違いです。
高木は、自分が無意識に誰かを搾取していたことを認めたくないからこそ、羽立を“裏方のまま”の存在として記憶している。一方、小山は後ろめたさゆえに、「いや、ちゃんと一緒に遊んでいた」と“平等だった記憶”に書き換えているようにも読めます。
この“記憶のリライト”は、のちの「忘れられた7人目」がなぜ認識から抜け落ちているのかというテーマにもリンクしていきます。
スコップ女とタイムカプセル――大谷典代の立ち位置
廊下をスコップで引きずる女の後ろ姿は、明らかにタイムカプセル事件との連動を意識したショットです。
- タイムカプセルは一度掘り返され、卒業アルバムが入れ替えられている
- その作業をできるのは、学校内部、とくに権限ある立場の人物
という前提を踏まえると、現在校長の大谷典代は“実行可能なポジション”にいます。
ただし、彼女が“7人目本人”である可能性は低い。
小学生の輪に教師が混じってゲームをするのは不自然ですし、回想の“右手と右ひざ”は明らかに子どもの体格。
現時点の妥当な線は、
- 7人目の事情を最初から知っていた
- または、7人目の親側と強く関係していた
- そのためタイムカプセル(=記憶)を書き換える役割を担った
という、“隠蔽側の大人”としての関与です。
宇都見啓=刑事という二重の顔
イマクニの常連として“フランクな兄ちゃん”にしか見えなかった宇都見啓が、実は事件を追う刑事だった事実は4話の大きな転換点です。
ここで浮かぶ疑問は、
- 宇都見はいつからイマクニに出入りしていたのか
- 過去の“事故死”にも彼が関わっていたのでは?
- イマクニは警察の非公式な張り込み場所だったのか?
など、捜査サイドと同級生サイドをつなぐ“境界人物”としての立ち位置。
4話時点では、
- 警察がようやく事の重大さに気づき始めた段階
- 同時に“警察内部にも黒幕がいる可能性”も示唆
という二重構造の伏線として機能しています。
園子のパネルを壊す松井――“異常な好意”の芽
園子の後輩・松井が、衝動的に彼女の等身大パネルを破壊するラストも見逃せない伏線です。
- 好意・尊敬・執着・嫉妬が混ざり合った危うい感情
- 「所有したい」「支配したい」という暗いベクトルが芽生えている
- 今後、園子への危害/情報リークなど二次的事件への発火点になる可能性
この異常性は、後々確実に物語に影響する布石です。
イマクニという“舞台装置”の強化
4話時点で、イマクニはただのスナックではなく、物語の核心に近い“舞台装置”へ進化しています。
- 同級生の再会場所
- 宇都見刑事の張り込み場所
- 店主の素性が不明で不穏さが漂う
これらが重なり、イマクニは“情報・罪悪感・本音”が交差する現代版「教室」のような空間として機能し始めました。
今後、掲示板の“博士”や7人目の影とも接続される可能性が非常に高く、4話時点の重要伏線のひとつと位置づけられます。
良いこと悪いこと4話の感想&考察
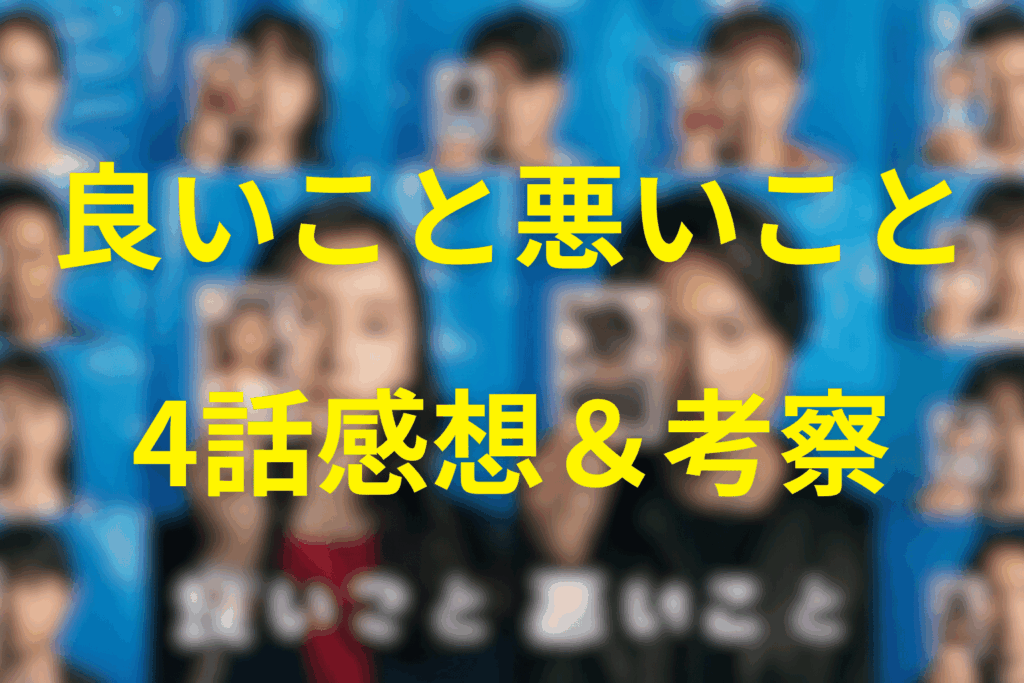
第4話は、“守るつもりが刺さってしまう言葉”の連鎖を、驚くほど冷静な筆致で描いた。
筆者が感じた見どころは三つ——(1)謝罪の非対称性、(2)視線の増殖、(3)法則の倫理だ。
ここからは感想&考察していきます。
謝罪の非対称性——加害と被害は同じ時間を生きていない
高木の「守りに来た」は、善意としては満点だが、羽立にとっては過去の延長線に見える。
加害の記憶は被害者の身体にだけ残り続け、加害者の“成長”や“反省”は、被害者にとって関係の更新ではなく再演になり得る。
羽立の「友達なんかじゃない」という言葉は、関係のリセット権が被害者にあるという宣言だ。ここを丁寧に描いたからこそ、第4話は“悲劇の勢い”に流されず、倫理的な緊張感を保ったまま進行している。
かんたろうが再度連れ去られて、殺された。――“死ぬまで実行される”という犯人の意思表示
桜井幹太(カンタロー)は第2話の火災で一命を取りとめたが、第4話で病院から再度連れ去られ、縛られた画像(動画)とともに“焼かれて殺害”されたことが示される。
園子の「これは死ぬまで終わらない」という言葉が、単なる比喩ではなく犯人の作法=完遂主義として提示された形だ。
放送後は「再び燃やされるとは…」という視聴者の動揺が広がり、犯人が“見せしめ”として徹底している印象を強く残した。
カンタローの“将来の夢=消防士”に対し、火という象徴で再度の襲撃→殺害が演出された点が重要である。
第1~3話を貫く「夢→手口」の対応関係(転落/スポットライト等)が、より残酷な形で補強され、夢が凶器に変わる構造が確定した。
このため、犯人はクラスメートたちの「夢の記録」や「学校保管物」にアクセスできる人物という条件が、いっそう現実味を帯びてくる。
さらに、病院からの再拉致という高難度の犯行が示されたことで、“6人の内側だけでは完結しない”可能性が濃厚となった。
動線や面会ルート、時間帯に詳しい内通者や協力者の存在が前提にある。
つまり、現場の選定・監視・移動を可能にする“外部の手”が働いているという構図だ。
視線の増殖——スコップの女と“忘れられた一人”が作る外側
これまで“6人の輪”で閉じていた物語に、映っていない誰かの気配が入った瞬間、世界は“閉じた系”ではなくなる。回想に挿入された“右手・膝だけの人物”、そしてスコップを引きずる女の影。
どちらも犯人断定の材料ではなく、“忘却の暴力”を象徴する像として配置されている。
視線が増えることで、解釈の責任も増える——視聴者が参加する余地を拡張する構造だ。
この“外側の視線”の導入によって、物語の密度は一段深まった。
法則の倫理——替え歌が持つ“物語の刃”
“替え歌どおり”というワン・ルールは、推理の燃料でありながら、同時に倫理の警鐘でもある。
ルールが強固であるほど、“守るべき相手”が先に可視化されてしまう。
第4話が巧みだったのは、羽立を「守る対象」として固定しなかった点だ。彼は守られたいのではなく、生き直したい。
ラストで芽生えた“微細な変化”は、完全な和解ではないが、人間の物語としての次章を保証する余韻になっている。
週刊アポロの松井健が、猿橋園子の等身大パネルを破壊。――メディア内部の“歪み”が、事件の炎上装置になる
週刊アポロ編集部で、新人記者・松井健が猿橋園子(どの子)の等身大パネルを一発で殴り倒す。
同僚・東雲の「彼氏でもできたんじゃない?」という軽い煽りの直後という職場文脈も含め、個人的な嫉妬と反感が可視化されたシーンだ。
園子が“広告塔”として扱われている構造の中で、松井の破壊行為は単なる感情の爆発ではなく、報道機関という場所で起こる倫理の崩壊を象徴している。
エレベーターホール前での破壊という“公開的”な場面が、その暴力性をさらに際立たせた。
等身大パネルは、“園子という商品=イメージ”の象徴だ。
その破壊は、記者としての倫理よりも承認欲求や嫉妬が勝った瞬間であり、報道の視線が事件の演出と地続きである危険性を示している。
報道は事実を伝えるはずの場でありながら、そこに個人の感情が混じることで“物語の加害者”にもなり得る。松井の一撃は、ニュースを扱う者が“事件そのものを増幅させる存在”になりうることを突きつけた。
松井自身は犯人像の中心からは遠いものの、「情報をどう出すか/出さないか」を握る立場にある。
内部からの悪意ある情報の切り出しや、意図的な報道の歪曲は、園子を“悪い子”として描き出す装置になり得る。
つまり、事件の外圧(世論形成)が園子を追い詰める構造に変化する。
報道の中で生まれる歪みが、物理的な犯行と同じく“攻撃”として機能していく点が本エピソードの要だ。
宇都見=刑事の告白——素人の考察×捜査の合理
宇都見が警視庁捜査一課の刑事であったという種明かしは、作品の構造を一段深めた。
これで現場には、加害/被害の当事者、報道を担う園子、そして警察(宇都見)の三つの視点が揃う。以降、事件は“感情”だけでは動かない。
証拠という合理が物語の地形を変え始め、“6人”という枠組みそのものが疑われる。
本当に6人だけなのか、それとも“6人に見えるように仕組まれている”のか。
この問いが視聴者の思考を占拠し、作品が一気に社会派サスペンスの深みに入った。
「忘れられた一人」仮説——犯人像の更新
“輪の外”にいたもう一人の存在——この仮説が、物語の新たな焦点となる。
もし犯人が園子個人への復讐ではなく、“輪そのもの”、あるいは“排除された記憶”に動機を持つなら、犯行の演出にも合理が通る。
報道と世論を操作し、“園子を巻き込む”ための計画である可能性が高い。
“誰が傷ついたのか”という問いが、ここで根本から再定義される。
7人目の人物については以下記事で考察しています。
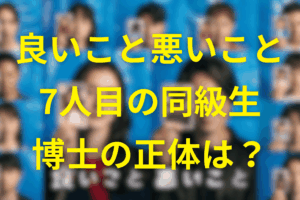
タイトル「黒」の意味——隠蔽と選別の象徴
サブタイトル「黒」は、不吉の色ではなく“境界の色”として機能する。
黒塗りの卒業アルバム、心に残る“黒い空白”、そして刑事の登場による“黒(確定)”。
色彩設計が物語の段階を区切り、闇ではなく“輪郭線”を描き出している。
インクを流し込むことで隠れていた形が見える——まさに今、作品が“真実の輪郭”を取り戻す過程にある。
総括——“こうだからこう、だから面白い”
替え歌という強固な法則/過去の非対称な記憶/輪の外からの視線(スコップの女、刑事・宇都見)。
守る言葉は届かず、被害者の“関係リセット権”が発動。捜査の合理が参入し、6人の外に疑いが広がる。
羽立の“生き直し”に芽が出て、犯人像は輪の構図そのものへ——ミステリーとヒューマンが二重螺旋で進む。
第4話は、“考察のカタルシス”と“人間の痛み”を同じ体温で抱いた佳編だった。
次回、侍=刺殺の示唆がどう回収されるのか。法則を崩すのか、人間が法則を超えるのか。
タイトルの問い「良いこと/悪いこと」に、視聴者それぞれの倫理で応答するタイミングが近づいている。
【4話まで】良いこと悪いことの犯人予想
第4話で“現場のルール”と“外部の視線”が一気に増えました。
替え歌×将来の夢という見立ては依然として強固。一方で、病院からの再連れ去り(=犯行資源の厚み)、スナック常連=刑事・宇都見の正体、“忘れられた一人”の示唆、新人記者・松井の破壊衝動が、容疑のベクトルを“6人の外”に拡散させています。まずは4話で更新・確定した事実から
前提アップデート(4話で確定・強化されたこと)
桜井幹太(カンタロー)は病院から再誘拐され、焼殺が示唆される。
犯人は“未遂で終わらせない=死ぬまで実行する”完遂主義を明確化。手口は“消防士の夢→火”の反転で、夢→手口の法則を強化。病院からの再連れ去りという高難度オペは内通者/協力者の存在を匂わせます。
バーの常連・宇都見の正体が“警視庁・捜査一課の刑事”と判明。
以降は素人考察×捜査の合理が交差する設計に。
回想に“右手と膝”だけ映る“もう一人”の同級生を示唆。
6人の輪に欠けていた誰かがいた可能性が濃く、犯行動機が“園子個人”を超えて輪そのもの/忘却へ拡張。加えて“校舎でスコップを引きずる女”の影も出現。
週刊アポロの新人記者・松井健が、園子の等身大パネルを破壊。
メディア内部の嫉妬と承認欲求が“炎上装置”として機能しうることを可視化。情報流の歪み=印象操作のリスクが上昇。
“5人目=羽立”は継続して高リスク。
公式は“侍の夢→刺殺”の可能性まで明記し、高木・園子・小山は羽立のアパートへ。羽立は「友達なんかじゃない」と拒絶——守りの主語の誤配が露わに。
焦点①:〈同級生〉ライン(園子を除く)
結論先取り:主犯を“6人の内側”だけに限定するのは4話時点で非合理。同級生=情報の源/内情、そこに“外側の手”が噛んでいる二層構造が最も整合的です。
小山隆弘(ターボー)
- 肩書/立場:アプリ会社CEO。6年1組“6人”の一人。
- 疑わしさ:帰国タイミングと事件進行が重なり、自作自演の被襲撃(ミスリード)でアリバイを作る“撹乱役”像が浮く。高木との親友関係は心理的盲点。
- 反証の芽:4話段階で次の標的は羽立と確定線。自分を中盤のターゲットに置く主犯は非効率。“操作役/撹乱役”に寄るのが妥当。
羽立太輔(ちょんまげ)
- 肩書:無職。現行の“次ターゲット”。
- 疑わしさ:物語上“注目が集まり過ぎ”でミスリード臭が強い。自己否定の強度・「友達じゃない」の断絶からも自罰傾向>攻撃傾向。
- 残る可能性:替え歌/夢の記憶に強く接続しうる人物。囮化または手引き/道具化のカードは消えない。
土屋ゆき(ゆっきー)
- 肩書:専業主婦(旧姓・塙)。
- 疑わしさ:家庭都合を理由にアリバイの曖昧化が可能。輪の外に居ながら同窓会線へ接続できる。
- 弱点:替え歌コアからの距離があり、直接動機の弱さは依然課題。
小林紗季(委員長)
高木将(キング)
- 肩書:主人公。
- 疑わしさ:“探偵役=犯人”の古典。替え歌の理解・順序操作が可能。
- 保留:視点固定の物語構造上、単独犯は不自然。共犯前提でのみ成立余地。
桜井幹太(カンタロー)
- 肩書:居酒屋店主。第2話で負傷→第4話で死亡示唆。
- 補足:“被害者のふり”説は消滅。主犯格の線は実質的に脱落。
武田敏生(貧ちゃん)/中島笑美(ニコちゃん)
- 肩書:第1・第3の犠牲者。
- 補足:いずれも実行犯からは脱落。ただし“設計図の原型に関与→口封じ”の可能性は微残。
焦点②:〈レトロスナック「イマクニ」〉店員ライン
同窓会後の流れで自然に人が集まり、情報とアリバイが混ざり合う場所。それがスナック「イマクニ」。店主と店員は“観測者”として、事件の準備や監視に最も適した位置にいる。
焦点③:〈外部の目〉警察・メディア・“忘れられた一人”
宇都見(刑事):当事者線に捜査の合理が重なり、6人の外に容疑の網が広がる構図をつくる当事者。黒幕説はゼロではないが、現時点は物語装置としての“第三の視点”が主。
松井健(週刊アポロ):園子のパネル破壊で承認欲求→破壊衝動を露呈。情報流の歪み(リーク/印象操作)という“言説の凶器”を担いうる外部者。
“忘れられた一人”/スコップの女:ボンバーマン回想の右手・膝、校舎でスコップを引きずる女——いずれも“輪の外からの暴力”の符牒。個人怨恨→構造怨恨へと動機が拡張する可能性。
総括:いま最も整合的な構図(4話時点)
第4話時点で最も整合的な構図は、替え歌×夢の強固な法則を軸に、病院からの再拉致が示した犯行資源、そして警察・メディアという第三の視点、さらに“忘れられた一人”の影が重なる多層構造にある。
同級生たちが情報の源でありながら、外側の“手”(実行・監視・世論操作)が絡む二重構造が成立していると考えるのが自然だ。
主犯を6人の内側に限定せず、小山=操作・撹乱役、今國・丸藤=場の実働、学校や記録にアクセスできる者(教職員・保護者ルート)=鍵穴という図式が最も合理的である。
一方で、羽立が“囮”である可能性は依然として高い。
守る側に求められるのは、「守ってやる」という上位目線ではなく、「どう守られたい?」と相手の主語を取り戻す姿勢だ。
言葉の設計を誤れば、その善意自体が二次加害になる。
第4話は、その危うさを痛烈に浮き彫りにした回だった。
良いこと悪いことの関連記事
良いこと悪いことの全話ネタバレはこちら↓
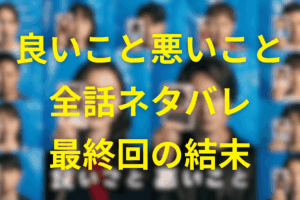
良いこと悪いことの漫画についてはこちら↓
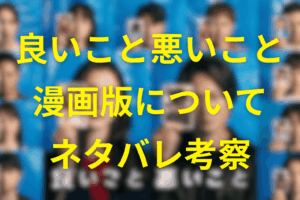
5話についてはこちら↓
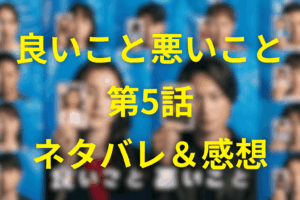
3話についてはこちら↓
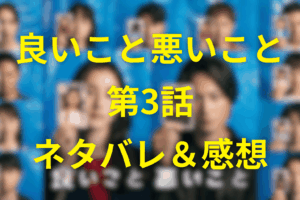
2話についてはこちら↓
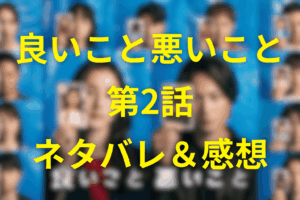
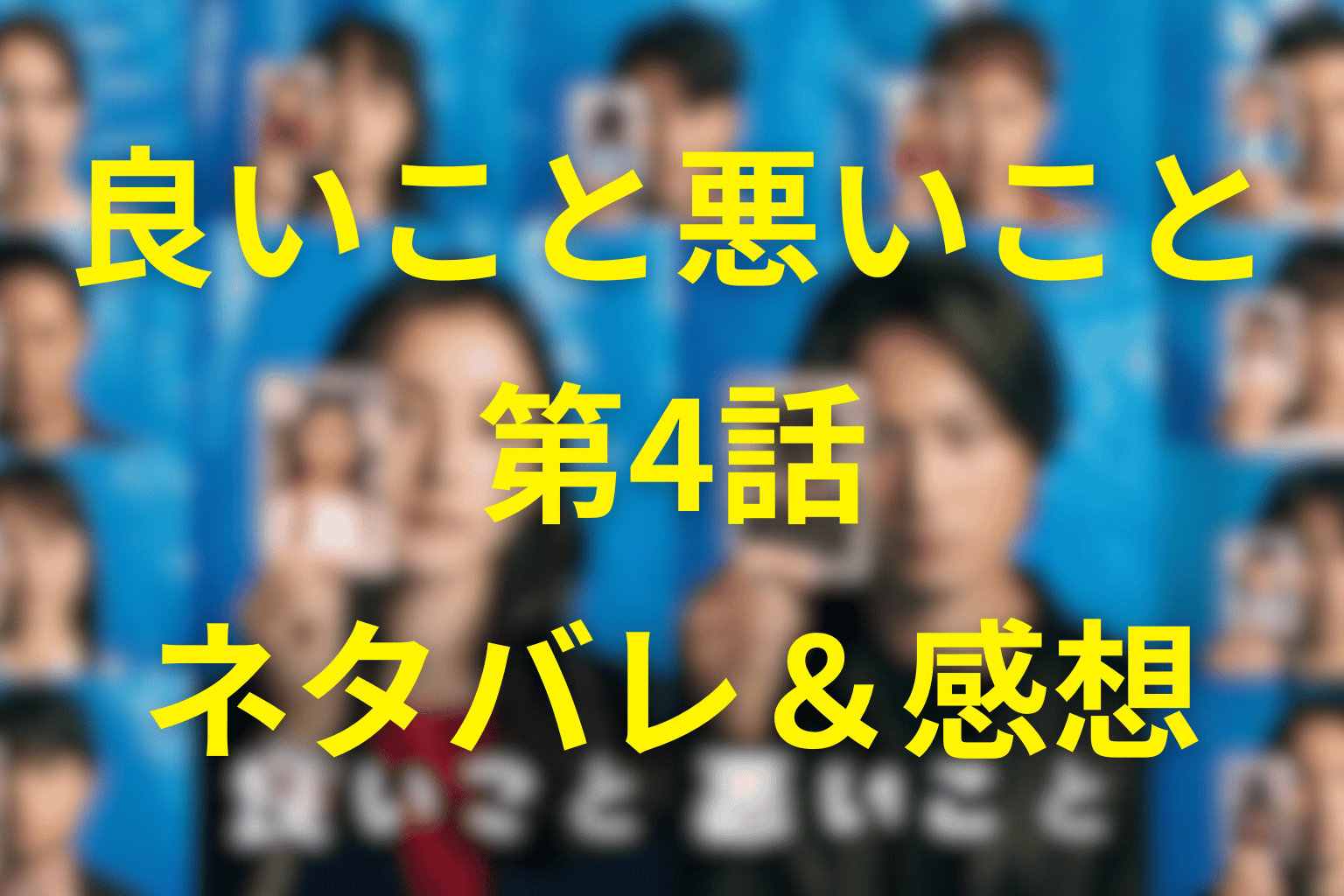
コメント