フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』は、日本の連ドラ史上初となる“水上警察”を舞台にした刑事ドラマ。
陸の捜査がカメラとテクノロジーで進化する一方、海と川は犯罪の抜け道として取り残されていた――。そんな“水上の空白地帯”を埋めるため、新設された東京水上警察署。
ベテラン刑事・碇拓真(佐藤隆太)と、本部から左遷されたエリート・日下部峻(加藤シゲアキ)、そして海のプロ・有馬礼子(山下美月)が、海上アクションとロジカルな捜査を武器に難事件へ挑む。
本記事では、第1話の「漂流箱事件」から、謎の連続殺人、湾岸署との因縁、そして最終回の結末まで――“海でしか描けない正義”の物語を全話まとめて詳しく解説します。
【全話ネタバレ】ドラマ「新東京水上警察」のあらすじ&ネタバレ
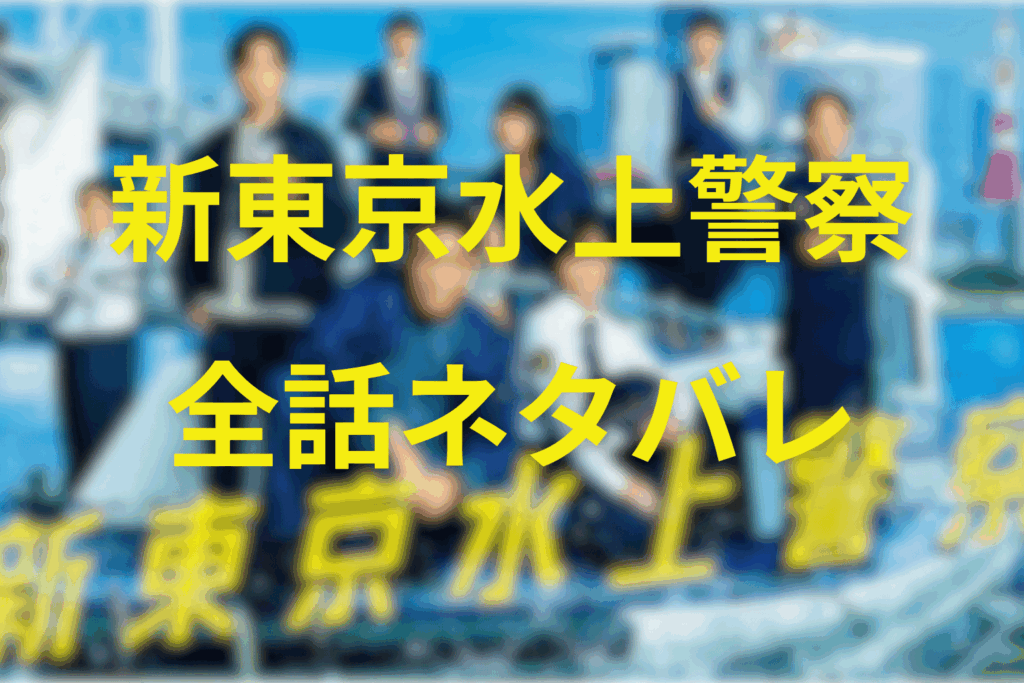
1話:漂う指と「次は」――海から始まる初動捜査はこうして動く
なぜ“今”、水上なのか――物語の出発点
ドラマ『新東京水上警察』の幕開けは、まず「なぜ“今”、水上なのか」という必然性を提示するところから始まる。東京オリンピックから4年、陸の治安は防犯カメラの普及で検挙率が上がる一方、“海と川”は犯罪の抜け道として取り残されていた。
警視庁はその空白を埋めるべく、湾岸部に『東京水上警察署』を新設。発足初日、経歴も性格も異なるが現場力を持つメンバーが集う。海上という“監視の効きにくい領域”を主戦場に据えることで、警察ドラマの地形が一変する。
チームの顔ぶれと“海の作法”
中心となるのは強行犯係の係長・碇拓真(佐藤隆太)。所轄で20年以上の経験を積んだ叩き上げの刑事で、事件のためなら危険も厭わない。一方、日下部峻(加藤シゲアキ)は本部捜査一課から望まぬ異動で水上署に来たキャリア組。
早く本部に戻りたいという功名心が彼の原動力だ。さらに、船舶免許を持つ海技職員・有馬礼子(山下美月)が加わり、“海の安全”という視点を現場に持ち込む。署を束ねるのは、元海技職員の異色署長・玉虫肇(椎名桔平)。
この異種混合の布陣によって、従来の“刑事と相棒”という二項対立では生まれなかったチームの力学が浮かび上がる。
「指」と「次は」――海が運ぶ不穏なメッセージ
やがて「海上に発泡スチロールの箱が漂っている」との通報が入り、警備艇「あかつき」で出動した碇たちは、箱の中から黒く変色した“人間の指らしきもの”を発見する。
そこには、溶けかけた文字で「次は」とだけ書かれたメモが。同時に物語は一気に“連続性”を帯び、犯人の犯行継続を示唆する。海上という匿名性がその予告をさらに不気味にし、水上署は捜査一課と合同で“陸と海”のすり合わせを開始。海では証拠が流れ、漂流物は移動する――つまり時間が情報を奪う。だからこそ初動の“速さ”が唯一の武器になる。
海が描く三段構成――設定・チーム・事件の連動
第1話の構成が見事なのは、設定提示→チーム紹介→事件発火点を“海”で一気に繋いでみせた点だ。
① 水上という監視の薄いフィールドの提示。
② 陸と海のハイブリッドな編成(刑事+海技職員+元海上署長)。
③ 漂流箱の異物感で観客の感覚を“海側”に引き込む仕掛け。
海という環境特性(視界・証拠・移動の速さ)と、人物の初期値(碇=現場勘/日下部=結果主義/有馬=操船と安全)が噛み合い、“水上でしか起こり得ない捜査ドラマ”の輪郭が明確になる。
“正しさが二つある”――人物間の衝突と統合
人物同士の火花も初回から鮮明だ。碇の現場主義は、日下部のキャリア志向としばしば衝突する。
しかし、有馬という“海の作法”の体現者が介在することで、単なる主導権争いではなく“生き延びるための合理性”が成立する。海で生きる正しさと、犯人を挙げるための正しさ。
二つの“正しさ”が同じ艇上でぶつかり、やがて融合していく。この対立と統合の構図こそ、シリーズの駆動力となる。初回の「指」と「次は」は、その統合を強制するタイムリミットとして機能している。
総括――海がルールを変える
総じて第1話は、「海という環境がルールを書き換える」ことを徹底して描き、次回以降への連続性(“次は”の宣告)を見事にセットした。
現場勘で動く碇、結果主義の日下部、操船と安全を担う有馬、そして海を知り尽くした玉虫署長。――この布陣だからこそ、“海の匿名性”と“犯人の予告”に立ち向かえる。捜査はもはや岸では完結しない。次の“箱”が浮かぶ前に、彼らが掴むべきものは何か。その問いを、波の速度で投げかける初回だった。
1話についてはこちら↓
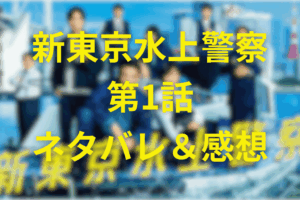
2話:第六台場の白骨遺体と“観閲式”の影――海と陸をつなぐ捜査線
第六台場で発見された遺体――海と介護施設が交錯する序章
2025年10月14日放送。東京湾唯一の人工無人島・第六台場で、銃殺され半ば白骨化した遺体が発見される。
身元は介護施設「キズナオーシャン豊洲」に入居していた資産家・服部義光。水上署の碇拓真(佐藤隆太)と日下部峻(加藤シゲアキ)は、施設の元職員・三上慎吾(松本怜生)を容疑者として追跡。
小型船で逃走を図る三上を追い詰めた瞬間、同乗していた田淵響(山崎裕太)が発砲し、三上は海へ転落する。命は取り留めたものの、事件は再び“水上の現場”に引き戻される。
「湾岸ウォリアーズ」――陸の暴力が海へ転生する構図
田淵は薬物密輸船を狙った強盗グループの主犯格で、かつて台場周辺を荒らした暴走族「湾岸ウォリアーズ」の元メンバー。
総長・黒木謙一(柿澤勇人)を今も崇拝し、陸から海へと活動の場を移している。
陸の暴力が海へ転生し、水上犯罪の生態系が拡張される――本作の世界観を体現する重要な一幕だ。
水上署と湾岸署の主導権争い――「観閲式」の謎が浮上
救命後、三上は沈黙を貫くが、日下部が粘り強く寄り添うことでようやく口を開く。
「服部は自殺だ」と明かし、さらに田淵の行方を問われた際、「観閲式の日……」と言いかけたところで、湾岸署の和田毅(谷田歩)らが病室に押し入り、身柄の引き渡しを強行。
日下部は排除され、水上署と湾岸署の主導権争いが表面化する。
シリーズ設定で明かされていた両署のライバル関係を実地で示し、事件が“捜査の政治”を帯び始める瞬間。
ここで語られた「観閲式」という公的イベントの日時が、攻撃の座標として不穏な意味を帯びてくる。
“水曜の毒殺”――海と陸、二つの現場をつなぐ二重螺旋
捜査の照準は、施設内で毎週水曜に発生する入居者の連続死へと移る。
海(銃撃・転落・救助)と陸(介護施設での毒殺疑惑)という二つの線が二重螺旋を描くように絡み合う。
服部の“銃死”と施設の“毒死”が同一線上にあるのか、それとも別系統なのか。
死の意味の切り分けが、次回への宿題として残される。
シリーズイントロが掲げる「水上の穴場で増える犯罪を、船で追う」というテーマが、海と陸を往還する捜査線として具現化された。
碇の“水恐怖症”――手順で恐怖を制する主人公像
碇は“水恐怖症”という致命的なトラウマを抱えながらも、水上署に所属する刑事。
そのため第2話の緊張は、派手に海へ飛び込むヒーロー譚ではなく、救助を“手順”で成立させる知的サスペンスとして描かれる。
誰がどの順で何を行い、どう人員を動かすか――碇は判断と段取りで現場を制す。
海上アクションの迫力ではなく、“作業の緊張”で物語を支える手法が、水上警察というテーマのリアリティを裏打ちしている。
総括――海と陸、現場と行政をつなぐ“交差点”の回
第六台場の白骨遺体を起点に、田淵=湾岸ウォリアーズの残響、観閲式という“日時”の仕掛け、施設の“水曜”というパターンが一列に並べられた。
海と陸、現場と行政の交差点で物語を加速させ、「まだ終わっていない」という気配を残して幕を閉じる。
観閲式の日に何が起きるのか、服部の死は本当に“自殺”なのか――。
“海で起きたことを陸の制度と言葉で解く”という、このドラマの勝ち筋が鮮明になった回だった。
2話についてのネタバレはこちら↓
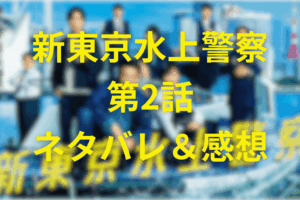
3話:観閲式突入を阻止せよ――『あかつき』強奪事件の全貌
暴走する『あかつき』――“儀礼の海”が一瞬で“実戦の海”に
放送は2025年10月21日。日下部の報告を受けた碇は、『キズナオーシャン豊洲』職員・三上が田淵に撃たれた一件から、田淵が警備艇を奪い観閲式会場へ突っ込む計画を掴む。
田淵が暴発した背景には、薬物密輸船を狙った強盗を水上署に封じられ、稼業が立ち行かなくなった焦りがあったと示唆される。
同時に海技職員・有馬礼子が人質となり、艇『あかつき』が強奪される。舞台は一気に“儀礼の海”から“実戦の海”へと転じる。
群衆の恐怖を封じた“正当な嘘”
観閲式会場には来賓・報道・市民が密集。
その緊迫の中、細野由起子が「これは展示訓練です」と即興アナウンスを放つ。意図は明快で、群衆心理の暴走(パニック)を抑止するための“正当な嘘”だった。
視線とフラッシュが走る中、別艇で追尾する碇と日下部は『あかつき』の針路に並走。二隻が至近距離に寄った刹那、碇は舷側から“飛び”、強行ボーディングに成功する。
“秒で判断・秒で動く”という水上署の職能が、ここで最も鮮明に描かれる。
黒木の存在――“見せ場”と“見せしめ”の交錯
来賓席には暴走族「湾岸ウォリアーズ」総長・黒木謙一の姿。
実行犯・田淵の元所属組織の頂点が、公の式典に座すという皮肉な構図が、事件の“見せしめ性”を際立たせる。
裏社会の力学が表舞台に出現し、「見せ場」と「見せしめ」が同じ舞台で共存する」という強烈な構図が完成した瞬間だ。黒木の出席は、暴力の政治性を象徴し、事件を単なる突発的犯罪ではなく“メッセージ”として印象づける。
ボーディングから制圧まで――“秒”で止める職能のロジック
艇内では碇が襲いかかる田淵を制圧し、操舵室へ急行。
礼子の安全を確認しながら、観閲式会場へ向かう暴走針路をギリギリで逸らす。事件は暴走船の衝突回避と田淵の確保によって収束した。
派手な爆発や演出に頼らず、“やるべきことをやる”現場のロジックで見せ切る構成が秀逸だった。映像的にも、冷静なカット割りと音の抑制が“実働の静けさ”を引き立てている。
碇が“なぜ海にいるのか”命を投げ出す覚悟の真相とは
クライマックスの後には、碇の内面を掘り下げる余韻が残される。
彼の過去(38年前の飛行機事故)にまつわる心の傷が、「なぜ海に居続けるのか」という問いと共にほのめかされ、
次話以降の人物ドラマへと滑らかに橋を架ける。
水を恐れる理由は明かされなかったが、38年前の飛行機事故で“代わりに死んだ子”への罪責感を抱えていると判明。彼の無茶な行動は、その罪と生存への葛藤から来ていた。
結論
第3話は、公共空間の危機管理・現場の判断力・権力の見せ方が同時進行する濃密な一編だった。条件が揃えば惨事は起きる。
だからこそ条件を分解し、現場で潰す――。このドラマが一貫して見せてきた“論理のうねり”が、最も鮮やかに立ち上がった回である。
3話のネタバレについてはこちら↓
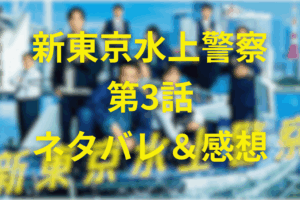
4話:潮風臨海公園の爆発と“あかつき”シージャック――無線がつなぐ父の声
第4話は、二重構造の危機が並走する。
ひとつは潮風臨海公園沖で起きたドローン爆発事件。碇(佐藤隆太)たち水上署が現場へ急行するが、先着の湾岸署に「ここはウチの案件」と押し返される。
それでも碇は引き下がらず、現場近くで“釣り禁止”を訴えていた環境団体「ヴァードアース」に照準を当てる。「まだ湾岸署の事件と確定したわけじゃない」と動きを止めない姿勢が、後半の説得劇で“材料”として効いてくる。
彼の信念は、“組織の境界線”よりも“海で起きた事実”を優先することにある。
職場見学から一転――警備艇「あかつき」シージャック発生
同じ頃、水上署では藤沢(中尾明慶)が妻・麻美(清水葉月)と息子・陸(加藤叶和)を職場見学に招いていた。
警備艇「あかつき」での穏やかなひと時が、突如惨事に転じる。
凶器を手にした上原修也(小須田康人)が現れ、藤沢を刺傷し、妻子を含む隊員を人質に船を占拠。
「早く出航しろ」と脅され、米田航基(宮津侑生)は操舵を強要される。湾岸署との縄張り争いが続く中、水上署は主導権を奪われたまま、艇が沖へ出ていく——最悪の展開が静かに始まった。
礼子の直感――モールスが灯す“声なき通信”
管制室では、有馬礼子(山下美月)が艇内の監視カメラ映像から状況を分析。
カメラの通電ランプに目を止め、点滅をモールス信号代わりにするという奇策を思いつく。
礼子の点滅信号に気づいた藤沢は、命懸けで応答。上原が起爆装置らしきものを持っていることを外へ伝えることに成功する。
だが、異変に気づいた上原がカメラを破壊し、視覚情報は遮断。以降、現場は“言葉だけが頼り”の交渉戦へと切り替わる。
上原の動機――誤解と悔恨の暴走
捜査線上に浮かび上がったのは、上原の息子の死。
彼はSNS炎上を苦に息子が自殺したと信じ込み、警察への不信と怒りを膨らませていた。
しかし、碇と日下部(加藤シゲアキ)の調べで、真相は違うことがわかる。息子は、釣り針にかかった鳥を助けようとして海に落ちた――“誰かのため”の行動だったのだ。
怒りは外側に向いていたが、根底には“息子を理解できなかった父”としての悔恨が渦巻いていた。
クライマックス――海が語る父への赦し
碇は無線を手に、海と風景、潮流、父子の記憶を紡ぐように言葉を選ぶ。
「息子さんは、鳥を助けようとして落ちた。あなたが教えた“優しさ”が、彼の中に生きていたんです」。
その声に、上原の手が震える。
自分を“加害の父”と決めつけていた彼は、初めて赦しの光を見る。
海は命を奪った場所ではなく、優しさを証明する場所だった——その言葉が、彼の暴走を止めた。上原は武器を下ろし、無事確保。藤沢の命もつながる。
この解決は、戦術でも武力でもなく、“人の声”が人を救った瞬間だった。
エピローグ――「海は死ぬ場所じゃない」
事件後、OBの大沢俊夫(小林隆)が署を訪れ、署長・玉虫(椎名桔平)と碇に語る。
「海は死ぬ場所じゃない。生かす場所だ」。
この一言が、シリーズの核となる哲学を再び呼び覚ます。
碇が抱える38年前の飛行機事故の記憶、上原の喪失、藤沢の家族愛――それらすべてが“海”という場所で交わり、
“死を語る海”から“生を語る海”へと物語の重心が移動する。
総括――海と声で人を救う警察ドラマ
第4話は、爆発・シージャック・家族の絆という複合事件を、無線=声の力で解決に導いた回。
水上署と湾岸署の軋轢を超えて、現場の知恵と感情で突破する姿勢が際立つ。
科学でも拳でもなく、“言葉”と“海の記憶”で真実に到達する——それこそが『東京水上警察』の真髄だ。
4話のネタバレについてはこちら↓
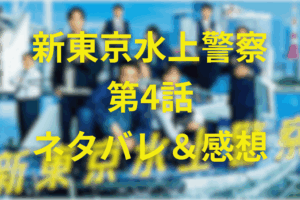
5話:前言撤回します。私に捜査の指示をください
第5話では、水上警察チームが女性アイドルグループ「Re Rise」を巡る事件に挑む。
刑事・細野由起子(山口紗弥加)は、かつて湾岸署勤務時代に不良少女だった北原萌歌(山本奈津美)を補導し、更生を見守ってきた過去を持つ。
そんな矢先、東京湾でブルーシートに包まれ、重りを付けて沈められた女性の水死体が発見される。それは他ならぬ萌歌の遺体だった。
検視の結果、死因は溺死――生きたまま海に沈められた可能性が高い。
由起子は深い衝撃を受け、碇拓真(佐藤隆太)とともに捜査を開始する。現場の重りから倉庫街が特定され、防犯カメラの映像から萌歌が事件当夜、深夜にその倉庫を訪れていたことが判明する。
同時に、日下部峻(加藤シゲアキ)の聞き込みによって、萌歌がかつて最終オーディションで落選した坂上優愛(糸瀬七葉)に逆恨みされていた事実も浮かび上がる。
さらに、萌歌と実業家との不倫疑惑を報じるスキャンダル記事が出回り、SNSでは「権力者による殺人隠蔽」といった陰謀論が過熱。
由起子は「萌歌の死には何か裏がある」と心を乱されていく。
一方、碇は記事掲載のタイミングの不自然さに気づき、「情報を意図的に流した人物がいる」と疑念を抱く。
出版社を訪ねた碇と由起子は、記者・久米島を直撃。だが直後、ヘルメットをかぶった人物に久米島が刺される。咄嗟に由起子が犯人を取り押さえると、正体は記事で“犯人扱い”された実業家・牧原の妻だった。
彼女は「夫が中傷で壊れていくのを見ていられなかった」と供述。夫の名誉を守ろうとした行動が、新たな罪を生んでしまった。
この刺傷事件をきっかけに、萌歌の死の真実が明らかになっていく。
礼子(山下美月)の潮流計算をもとに捜索を行った碇たちは、河川敷で牧原のバッグを発見。中には萌歌に関する手帳が残されていた。そこに記された内容から、碇は事件の全貌を読み解く。
真実――「殺人」ではなく「隠蔽」だった
『Re Rise』のメンバーを集めた碇が告げたのは、驚愕の一言だった。
「萌歌の死は事故死だ。そして、それを隠したのは君たち自身だ」
デビュー前夜、5人のメンバーは誰にも告げず倉庫街に集まり、花火と飲酒を楽しんでいた。
未成年のメンバーがいたため、真面目な萌歌は「未成年に飲ませるわけにいかない」と代わりに酒を飲み干す。結果、泥酔した萌歌は足を滑らせて川に転落。仲間が助ける間もなく溺死してしまう。
恐怖とパニックに陥った少女たちは「未成年飲酒の発覚でデビューが終わる」と怯え、萌歌の死を他殺に偽装するという最悪の選択をした。
遺体をブルーシートで包み、倉庫の重りを括り付けて海に沈め、さらには週刊誌記者に「不倫スキャンダル」を匿名でリーク。世間の注目を実業家に向け、事件を“権力の闇”にすり替える計画だった。
すべては、夢を守るための嘘。だが、その代償はあまりにも大きかった。
碇の論理的な追及により全てが露見し、メンバーたちは泣き崩れる。由起子は静かに、しかし厳しく語りかけた。
「あなたたちは取り返しのつかないことをした。でも、生きていればやり直せる。命がある限り、罪と向き合いなさい。」
その言葉を聞いた少女の一人が泣きながら叫ぶ。
「全部、私のせいです。未成年なのに私が飲まなきゃいけないお酒を、萌歌ちゃんが代わりに飲んでくれたんです!」
萌歌が最後まで仲間思いで、正義感の強い少女だったことが明らかになる。
真相が明らかになった今、由起子は萌歌の魂に報いるように静かに祈りを捧げる。彼女の目に浮かんだ涙は、悔しさと優しさが入り混じるものだった。
ラスト――“更生”を拒む闇の再来
事件の後、日下部(加藤シゲアキ)が更生支援を続けてきた元暴走族・三上慎吾(松本怜生)が出所する。
「もう悪い奴らと関わるなよ」と声をかける日下部に、三上は笑顔でうなずいた。
だが、帰宅した彼を待ち構えていたのは――黒木謙一(柿澤勇人)。
黒木は三上に向かって冷たく笑い、グラスにワインを注ぐ。
「警察にチクったのはお前だな。海の底で詫びるか、俺の下で一生償うか、選べ」
かつての悪の象徴が、更生を目指す若者を再び闇に引きずり込もうとする。
更生を信じた由起子の物語と、再び過去に縛られる三上の現実――二つの“やり直し”の物語が対照的に描かれ、第5話は重い余韻を残して幕を閉じた。
余韻――夢と罪のはざまで
事故死を隠した少女たち、罪を背負いながらも前を向こうとする刑事たち。
「海は人が死ぬ場所じゃない」という信念のもと、碇たちは真実を掘り起こし続ける。
若者の夢と罪が交錯する痛ましい事件を通して、第5話は“更生の難しさ”を二重の形で描いた。由起子が語った「生きていればやり直せる」という言葉は、水上警察というドラマ全体の信念そのものでもあった。
5話についてのあらすじ&ネタバレはこちら↓
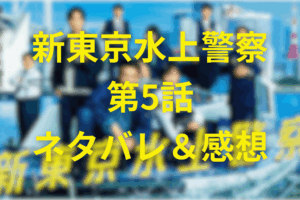
6話:半月(ハーフムーン)が照らす水面の殺意——篠宮班合流、そして“消えるアプリ”が導く真相の輪郭(あらすじ&ネタバレ)
湾岸に浮かぶ“半月殺人”──検視報告と篠宮班の合流
深夜、東京水上警察署・刑事防犯課に検視報告が届く。
海から上がった若い男性の身元は大学生・増田健二。死亡推定は先週月曜の深夜1時ごろ。頭部が“半月”の弧を描くように損壊した猟奇的殺人で、先月の工務店勤務・佐藤守の事件と手口が一致していた。
いずれも発生日が半月。世間では〈ハーフムーン殺人事件〉の通称で騒がれ、同一犯の可能性が濃厚となる。碇拓真(佐藤隆太)は湾岸地図を広げ、被害者の“水の道”をたどる決意を固める。
事件の連続性を受け、警視庁捜査一課が応援に入る。
派遣されたのは、殺人犯捜査第10係=篠宮班の警部・篠宮多江(野波麻帆)。彼女は碇の警察学校時代の同期で、かつて交際していた過去を持つ。
初動会議では、①遺体がどこから流れ着いたかの特定、②被害者同士の共通項の洗い出しを同時進行で指示。
“現場の勘”で動く碇と、“数字で詰める”篠宮の視点が衝突し、緊張感が一気に高まっていく。
その頃、若手刑事・日下部峻(加藤シゲアキ)は、母・涼子の入院を知らされ動揺。
医師から「詳しい結果は明日」とだけ告げられ、焦りが判断を鈍らせる。この“私事の火種”が、後の行動に影を落とす布石となる。
“消えるアプリ”Fog talk──通信の霧が暴く二重鍵
翌日、鑑識班から増田のスマホ復元の報告が入る。
そこに見つかったのは「Fog talk」というメッセージアプリ。
匿名で通信でき、履歴が自動消去される仕組み——犯罪組織“トクリュウ”が常用する“消えるアプリ”だった。
さらに、先の被害者・佐藤のタブレットにも同アプリの痕跡が発見される。物理的な足跡は消えても、通信の癖は消えない。事件は“半月”という時間条件と、“Fog talk”という通信条件の二重鍵で結ばれ始める。
捜査線上には新たな人物が浮上。
不動産会社「ゼネラルハウジング」の社員・泉圭吾(内博貴)。
湾岸の土地勘に明るく、人目の薄い倉庫や空き地に通じる職種であることから、関心の中心に置かれる。母の病を知った日下部は焦る気持ちのまま、泉を任意同行に。
取調室で対峙する二人の間には、「急ぎたい捜査」と「身に覚えのない男」の温度差が生まれる。彼は黒か、グレーか、それとも別の伝声管か——答えはまだ出ない。
海が語る“流れ”──半月の潮と犯人の設計図
水上署と一課の綱引きは続く。
篠宮は“流入点の特定”を重視し、碇は海で拾える微細な手掛かりを積み上げる。半月の夜は潮の動きが読みやすい。犯人は“流れを読む者”なのか、それとも“半月”そのものを儀式として崇拝する者なのか。
トクリュウを媒介にした“設計者”の存在は、依然として霧の中。
だが、被害者二人の行動圏と通信履歴に共通する“時間帯の癖”が見つかり、チームの視線は少しずつ同じ方向を向き始める。
クライマックスでは、事件の全貌はまだ掴めないまま、篠宮班と水上署の“正義”の形だけが鮮明になる。
合理を求める篠宮、現場を信じる碇、焦る日下部——三人の異なる“正しさ”がぶつかり合い、それぞれの覚悟が試される。
第6話は、ハーフムーンの連続性とFog talkの媒介性を際立たせ、“水上の連続殺人”の設計者が確実に存在することを視聴者に確信させる“助走の回”だった。夜の海面に浮かぶ半月が、真相の輪郭を静かに照らし出す。
6話についてのネタバレはこちら↓

7話:問われる本当の気持ち…訪れた決断の時
水上署×篠宮班、緊迫する“ハーフムーン殺人事件”の追跡
水上署の碇拓真らは、捜査一課“篠宮班”と共同で「ハーフムーン殺人事件」を追う。
だが日下部峻は、トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)の実行役2名に“指示役”と目された不動産業者・泉圭吾へ強引な取調べを行い、謹慎に。現場はギクシャクし、捜査ラインも乱れ始める。
篠宮は瓜谷を逮捕するも、アリバイと“強すぎる損傷”が違和感を呼ぶ
篠宮多江は、5か月前に弁護士・蘇我誠宅へ押し入った瓜谷雄志を容疑者として逮捕。
しかし瓜谷にはアリバイがあり、本部の「口封じ」見立ても腑に落ちない。碇は「口封じにしては頭部損傷が激しすぎる」と違和感を覚える。
“ヤメ検”蘇我の裏の顔と、泉圭吾の影
碇たちは被害者・蘇我の素性を掘り下げる。蘇我は“ヤメ検”として反社や闇金と関わる“際どい案件”を担っていたが、関係を断とうとしていた時期があった。
そこに浮かぶのが泉圭吾。蘇我と接点があり、借金や闇金筋のつながりも見え始める。動機のベクトルは“口封じ”から利害へ——事件の重心が静かに入れ替わっていく。
瓜谷が釈放され、捜査線が反転——“犯人はお前だったんだ”
アリバイ崩しができず瓜谷は釈放。水上署が保護に動くも、その場に篠宮が現れ「こちらに引き渡して」と迫る。
そこへ駆け付けた碇が静かに告げる——「お前だったんだな。ハーフムーン事件の犯人は」。物語はここから一気に核心へ雪崩れ込む。
篠宮の“証拠隠匿”と復讐の暴走、そして真犯人の正体
篠宮は被害者・蘇我の恋人だった。
彼女は、蘇我宅からトクリュウ3人が逃走するドライブレコーダー映像を入手していながら隠匿し、捜査を“復讐”へ誘導。
トクリュウの2人を自らの手で殺害していた。さらに瓜谷を撃とうとした刹那、碇が核心を突く——蘇我を殺した真犯人は泉圭吾。
トクリュウの“指示役”として利害のために蘇我を殺し、現場をトクリュウの犯行に擬装したのだと。篠宮は「感情で動くやつは駄目だって、私が言ってたのに……」と崩れ落ち、復讐の幕はここで閉じた。
事件後の余韻——有馬の想い、日下部のプロポーズ
事件後、水上署にはささやかな余韻が残る。仲間は飲み会の段取りで碇を励まし、有馬礼子は「篠宮さんに“私にとって大きな存在です”と伝えてほしい」と頼む。同じころ日下部は有馬に真正面からプロポーズ。
母の病を理由に“ずるい”と自覚しつつも、「結婚すれば全部見せられる」と胸の内を吐露する。感情と職務、恋と正義、その折り合いを視聴者に問いかけたまま7話は静かに幕を閉じた。
7話のネタバレについてはこちら↓

8話:ソラナギ事件と、揺れる礼子の選択
第8話は、礼子の“人生の選択”と、海の神話になぞらえた「ソラナギ事件」が静かに並走し、後半にはシリーズ全体を揺るがす大きな不穏が差し込まれる回でした。
恋・仕事・正義・海――それぞれがぶつかり合い、礼子自身の揺らぎが物語の中心に置かれます。
礼子の“揺れ”と、海に呼び戻される日常
物語は、日下部峻から突然のプロポーズを受けた礼子が、答えを出せずに立ち止まっているところから始まります。気持ちがあるのに即答できない。そんな礼子の変化に気づいた細野由起子は、彼女の胸にある“揺れ”を丁寧に聞き出し、「あなたは昔よりずっと迷いやすくなっている」と、本人すら認められない不安を言語化していきます。
そこへ碇から緊急連絡。東京湾で「刺殺体を載せたボート」が漂流している――礼子は迷いながらも現場に駆けつけ、海技職員としての自分を取り戻すように、潮の流れを読む作業へ没頭していきます。
ソラナギ事件 ―― 海を“証拠隠し”に使った完全犯罪
発見されたボートには、鎖で巻かれ、左胸を銛で貫かれた産廃業者・桂孝一の遺体。
遺体の状況は絵本『ソラナギ物語』そのままで、復讐劇を模した犯行が疑われます。ボート内部は海水で満たされ遺体は冷やされており、死亡推定時刻は大きくズレる。礼子は潮流・風向・ボートの漂流速度から「どこで放たれたのか」を再計算し、犯行地点を特定していきます。
疑惑は漁師・辻村へ。彼の漁場に産廃が流れ込み、出元として桂の会社が疑われていた過去が浮かび上がる。しかし辻村には“飲み会アリバイ”があり、捜査は堂々巡りに。
そこで礼子は、証拠ロープの“サビの跡”から特定の結び方を見抜きます。
時間が経てば自然にほどける「仕掛け結び」。この結びにより、ボートは“犯行の3時間後”に自動的に流れ出した可能性が判明。つまり、アリバイは“礼子の見立てた推定時刻の誤り”を利用した偽装だったのです。
辻村の告白 ―― 海を愛した男の、歪んだ怒り
碇と礼子の追及で、辻村はついに崩れます。海を汚す桂の行為を止めるため、何度も訴え、拒まれ続け、ついに“ソラナギの裁き”に手を染めたと語る。「あいつは海を殺したんだ」と叫ぶ辻村に、礼子は静かに言います。
「波は、遺体を流すためにあるんじゃない」
かつて海に救われた男が、今度は海を“証拠隠しの道具”として使ったという皮肉が胸を刺し、事件は幕を閉じます。
ラスト1分 ―― 信じてきた“大沢俊夫”が闇側に?
しかし、安堵は一瞬で終わります。碇のもとに届く“湾岸ウォリアーズ”黒木のタレコミ。「大きな仕事をする」。礼子と碇が料亭を張り込むと、そこに姿を現したのは――黒木と並んで歩く、大沢俊夫。
礼子の支えであり、碇の恩人であり、“海を守る象徴”だった男。その人物が湾岸の闇とつながっているかもしれない。
第8話は、「事件の真相」よりも、「誰を信じるのか」という揺らぎを礼子に突きつけた回でした。
恋も仕事も仲間も、そして尊敬してきた大沢も――すべてが静かに軋み始めています。
8話のネタバレについてはこちら↓

9話:南極観測船「海雪」の密室殺人と、“見殺し”にされた夫
黒木の“怪しい動き”と料亭での邂逅
東京水上警察署の刑事・碇拓真に、湾岸ウォリアーズ初代総長で今は人材派遣会社社長の黒木謙一が“大きな仕事”をするという情報メールが届くところから9話は始まる。
碇は有馬礼子とともに料亭を張り込み、黒木、礼子の恩師・大沢俊夫、そして黒木に紙扇子を投げつける男の姿を目撃する。のちにこの男が被害者・福本宗介だと判明するが、黒木は「令状を持って来い」と突っぱね、真意が掴めないまま碇たちは退却する。
南極観測船「海雪」で発覚した密室死
その矢先、青海埠頭公園の南極観測船「海雪」内で腐乱遺体が見つかる事件が発生。
現場には湾岸署が先に到着し、防犯映像など主要な証拠をすべて押収。日下部は悔しがりつつも、代わりに野次馬たちを片っ端から撮影して署へ戻る。
検視の結果、遺体は「海雪」をこよなく愛し、展示船のボランティアを務めていた福本宗介。死因は外傷ではなく“密閉された船内での熱中症”で、長時間高温に閉じ込められたことが致命傷だった。
DV被害者だった妻・弓枝の告白
碇と細野は福本の妻・弓枝に事情を聞く。弓枝は長年夫からDVを受けており、事件当日「助けてくれ」という電話を受けたと語る。
しかし恐怖と絶望により船へ向かったものの助けずに立ち去り、「見殺しにした」ことを認める。ただし殺害は否認。一方、湾岸署は弓枝の姿が防犯映像に映っていたこと、扉外側に指紋が残っていたこと、
事件前に夫の「海雪」グッズを大量に捨てていたこと、保険金を示唆する発言などを根拠に彼女を逮捕。和田は「動機も証拠も揃った」と強気の姿勢を崩さない。
浮かび上がる黒木と「海雪」工事の接点
一方、碇は「海雪」の移転工事関係者リストから、黒木のもとで働いていた三上慎吾の名前を発見する。
三上は黒木の会社「湾岸海洋ヒューマンキャリア」から派遣されており、工事に黒木の影が入り込んでいたことが判明。
さらに、日下部が撮影した野次馬映像の中に、料亭で黒木と大沢に同席していた“あの男”――福本宗介本人の姿を確認。黒木に投げつけられた紙扇子が福本の私物だったことから、あの日の席で二人の間に揉め事があったと推測される。
事件の黒幕は弓枝ではなく黒木なのか
これらの点をつなぎ合わせ、碇は「弓枝は犯人ではない。事件の背後に黒木がいる」と断言。DVで苦しみながら夫を救えなかった弓枝の“見殺し”という罪の重さと、黒木=湾岸ウォリアーズの暗躍の両方に向き合う覚悟を固める。
9話は、南極観測船「海雪」を起点に黒木の影が一気に濃くなり、チーム碇と湾岸署の対立も含め、物語が最終章へ加速するターニングポイントとなった。
9話のネタバレについてはこちら↓

10話:台風接近の中で揺れる、捜査と防災の“究極の選択”
二つの危機が同時進行する回
10話は、南極観測船「海雪」で起きた密室殺人と、首都圏直撃目前の大型台風という二つの危機が同時進行する回だった。
碇たちが追う「海雪事件」は、黒木謙一と港湾局、元湾岸ウォーリアーズ、大沢らの利権にまで広がる闇を帯び始める一方、組織としては「まず台風対応を最優先せよ」という現実が立ちはだかる。
三上が語る“海雪の闇”
物語は、海雪で見つかった福本宗介の遺体事件に黒木が関与していると確信した碇が、移転工事の関係者リストに名前があった三上慎吾へ話を聞こうとするところから始まる。
三上は恋人・峰岸華絵と共に出頭し、観閲式の失敗をネタに黒木に脅されていたこと、海雪のスペアキー作成や船内の「貴重な物」の窃盗を強要されたことを告白する。さらに港湾局職員・仲井の不審な動きが映像で浮かび上がり、「仲井が福本に致命傷を与えたのでは」という疑いが強まっていく。
台風優先の判断と、警察内部の葛藤
同じ頃、首都圏には大型台風が接近し、災害対策本部の設置が決定。海雪事件は形式上湾岸署へ引き継がれる流れとなる。碇は署長・玉虫に「今は捜査を優先すべきだ」と詰め寄るが、有馬は「台風で何人の職員が亡くなったと思っているのか」と反論。玉虫も「部下を死地に送りたくない」という信念から出航許可を出さない。
会議後、玉虫は有馬に大沢俊夫の過去を明かす。
水上警察廃止後、大沢は組織を守るために働き詰めとなり、その結果家庭は崩壊、妻は心身を病み自殺。自身も降格と再就職難に追い詰められ、そこに黒木が付け入った可能性が示される。大沢が単純な悪役ではなく、「組織に人生を捧げ壊れてしまった大人」として描かれるのが印象的だ。
三上の拉致で動き出す“水上警察でしか追えない事件”
嵐の前触れの強風の中、峰岸が再び署へ駆け込み「三上がさらわれた」と訴える。
黒木側に車で連れ去られ、「今日で終わり」と脅されたという。華絵の持ち込んだ映像から、三上が海雪で仲井の動きを目撃していたことも判明し、黒木にとって三上は“消すべき駒”になったと碇たちは悟る。
湾岸署との連携により、三上が乗る車は港からフェリーか船へ積み込まれ、海上へ逃走した可能性が浮上。ここでようやく“水上警察にしか追えない事件”となるが、玉虫は台風接近の中での出航を認めず、板挟みの緊張が続く。
日下部の個人的危機と、全員に迫るタイムリミット
その最中、日下部には病院から「母親が危篤」という連絡が入る。捜査か家族か、職務か命か──碇たちが直面している“台風か捜査か”というジレンマが、日下部個人にも重くのしかかる。
10話は、台風・拉致・密室殺人・過去の因縁が同時に爆発し、全てのタイムリミットが重なったところで終了。海雪事件の真相、黒木の狙い、大沢の罪と救済、玉虫や日下部の決断──最終回へ向けて一気にクライマックスへ雪崩れ込む構図が固まった回だった。
10話のネタバレについてはこちら↓
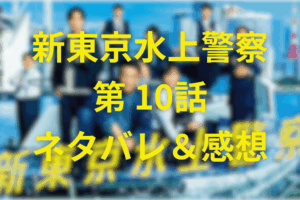
11話(最終回):「生きて帰れ。嵐の海へ、最後の出航」
嵐の東京湾で交錯する、三つの決着
台風が首都圏に迫るなか、黒木謙一は三上慎吾を拉致したまま、貨物船「竜水丸」で海上へ逃走します。
最終回は、「三上の救出」「海雪事件の決着」「黒木と大沢の関係」という三つの軸が、嵐の東京湾という極限状況で一気に収束していく構成でした。
出航を巡る葛藤と、三人の覚悟
碇拓真は追跡を願い出ますが、署長の玉虫は危険を理由に出航を許可しません。そんな中、日下部には母の危篤という私事が重なります。それでも捜査を止めない覚悟を示す日下部。
有馬もまた、恩師・大沢が黒木と行動を共にしている事実に動揺しながら、「今追わなければ、すべてを取り返せなくなる」と訴えます。三人の決意を前に、玉虫は「生きて帰ること」を条件に、最後の出航を認めました。
海雪事件の裏側で動く、もう一つの捜査線
同時進行で、海雪の移転工事をめぐる談合に関わった港湾局職員・仲井が、遺書を残して失踪。細野たちは湾岸署と連携し、仲井の行方と事件の証拠固めを急ぎます。
表の救出劇と並行して、陸では着実に事件の核心が詰められていく流れが描かれました。
竜水丸での対峙と、大沢の選択
碇・日下部・有馬は、ついに竜水丸の停泊場所を特定。無線で呼びかけると応答したのは大沢でした。有馬は沖に停船する全船への緊急検査を通告し、そのまま竜水丸に乗り込みます。船の検査が未実施だと気づいた有馬は、船内調査を宣言。
大沢は有馬を褒めながらも、どこか覚悟を決めたような空気で三人を迎え入れます。
銃撃戦と、嵐の海への転落
船内で三上を捜索する最中、黒木が突然発砲し、緊迫した銃撃戦に発展。追い詰められた黒木は甲板で三上を人質に取り、碇へ銃口を向けます。
ここで大沢が黒木を撃ち、「もう終わりにしよう」と制止する場面が、大きな転換点となりました。それでも黒木は燃料タンクを撃ち抜き、三上を道連れに海へ転落。
大沢は嵐の海に飛び込み、三上だけを救い上げますが、大沢本人はそのまま海に沈んでいきます。
碇の決断と、命を懸けた修理
有馬は動揺を押し殺して操船を続けますが、燃料の減りが異常に早いことに気づきます。
原因は、黒木が撃った燃料タンクの穴からの燃料漏れ。このままでは台風の海で立ち往生し、全員が命を落としかねない。碇は穴を塞ぐため甲板へ出ようとし、止める日下部に従うふりをして手錠をかけ、単独で甲板へ向かいます。その直後、船が大きく揺れ、碇の姿は海へと消えました。
それぞれの喪失と、次の海へ
後日、碇は生還。黒木の遺体は発見されないまま、仲井は睡眠薬を大量に飲んでいたものの命を取り留め、殺害を認めます。
三上もまた、黒木に命じられて行った悪事を供述し、黒木の罪状は固まっていきました。日下部は母の死を経て、有馬へのプロポーズを取り消し、「自分は碇に完敗した」と告白。
有馬は碇に向かって「これから刑事を目指す」と宣言します。喪失と決意を胸に抱えながら、“チーム碇”は次の海へと進んでいく――それが、新東京水上警察の最終回でした。
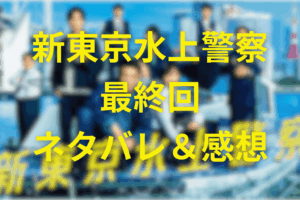
原作「東京水上警察」の結末は?簡単にネタバレ
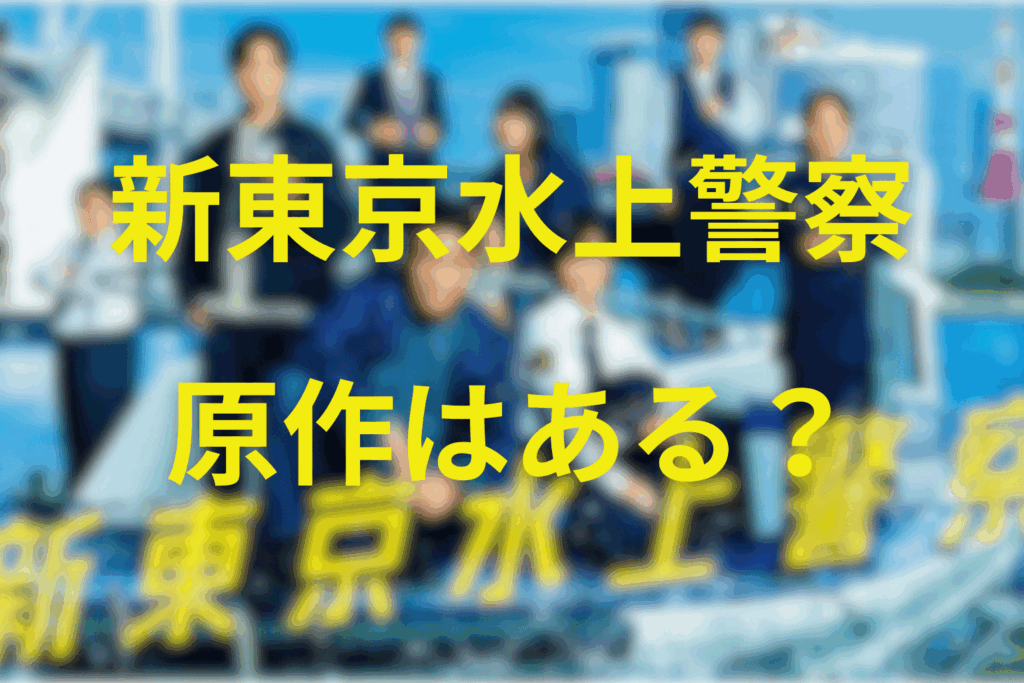
原作の位置づけとシリーズ構成
まず前提を整理しておく。フジテレビ火9ドラマ『東京水上警察』(正式タイトル:『新東京水上警察』)の原作は、吉川英梨による小説シリーズで、講談社文庫から全5巻が刊行(2016〜2020)。
公式でも「現在第5弾まで刊行」と明記されている。したがって“シリーズとしての最終回”はまだ提示されておらず、各巻ごとに独立した事件が完結する構造となっている。また、小説では「五港臨時警察署」が舞台で、ドラマでは「東京水上警察署」へ改称されており、時間軸と組織設定のアレンジが行われている。
各巻クライマックスの簡易ネタバレ(最小限)
1巻『波動』——“観閲式”の海で追跡が頂点へ
白骨遺体と半グレ集団を追う捜査が、都知事臨席の水上観閲式という“予定の塊”に向かって収束。クライマックスは警備艇による追跡劇で、「海×時間×動線」を読み切った水上警察の作戦勝ちで幕を閉じる。シリーズの基軸――速さ=正義、操船=推理――がここで確立される。
2巻『烈渦』——台風下、“都政の闇”を呑み込む決戦
保存船「宗谷」で発見された腐乱死体を発端に、台風接近と湾岸署との主導権争いが同時進行。暴風雨の東京湾という“証拠が溶ける場”を逆手に取り、命懸けの海上戦で真相へ到達する。環境(天候)すら作戦の変数に落とすシリーズの手法が、ここで極まる。
3巻『朽海の城』——豪華客船の“帰港”が審判となる
焼死体を抱えたまま走る豪華客船セレナ・オリンピア号と、湾内で見つかった斧刺さりの水死体――二つの事件が一線上で繋がる。母港への帰還というボトルネックを利用し、包囲を完成。船上と湾内、陸と海の二点同時解決を実現する。タイトルの“城”は、移動する密室=海上構造を象徴している。
4巻『海底の道化師』——“海底の断片”が陸の真相を指す
海底から引き揚げられた免許証、相次ぐ水死体。救難と捜査を並行しながら、連続殺人の影と災害の芽が交錯。最終局面では海底に眠る証拠線を陸の因果と結びつけ、“水の匿名性”を突破して真相に辿り着く。救出の速度と論理の鋭さが両立する巻となっている。
5巻『月下蝋人』——クレーンの“蝋人形”が空中の密室
ガントリークレーンに吊るされた蝋人形の中から刺殺体が発見される。胸元の「996」という数字と異様な製法が手がかりとなり、事件は吊り下げ構造(空間)と数字(記号)の二重トリックで収束。人物の私生活にも揺らぎが生じるが、最終的には“職務としての正しさ”が現場を押し切る形で幕を閉じる。
総括――原作の結末に通底する“海の論理”
シリーズは“各巻完結+世界観継続”。第5弾で完結の告知はなく、“原作としての単一の最終回”は存在しない。したがって「結末」を問うなら、各巻のクライマックスで繰り返される、“海の匿名性を無効化する”=海で論理的に決着をつける手法こそがシリーズ全体の答えとなる。
ドラマ版は、時代設定と組織名を調整し(五臨署→東京水上警察署)、このコンセプトをそのまま継承。シリーズの核である「時間(観閲式などの予定)×水域(潮汐・航路)×動線(船の配置)」を、追跡・包囲・救難という作法で描く。“アクション=解法”という思想は、原作の終わり方に通底する理念として、ドラマ全体を貫いている。
新東京水上警察の原作についてはこちら↓
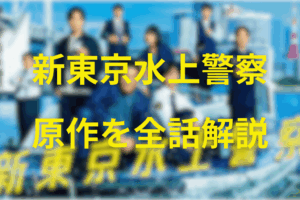
「新東京水上警察」のキャスト一覧
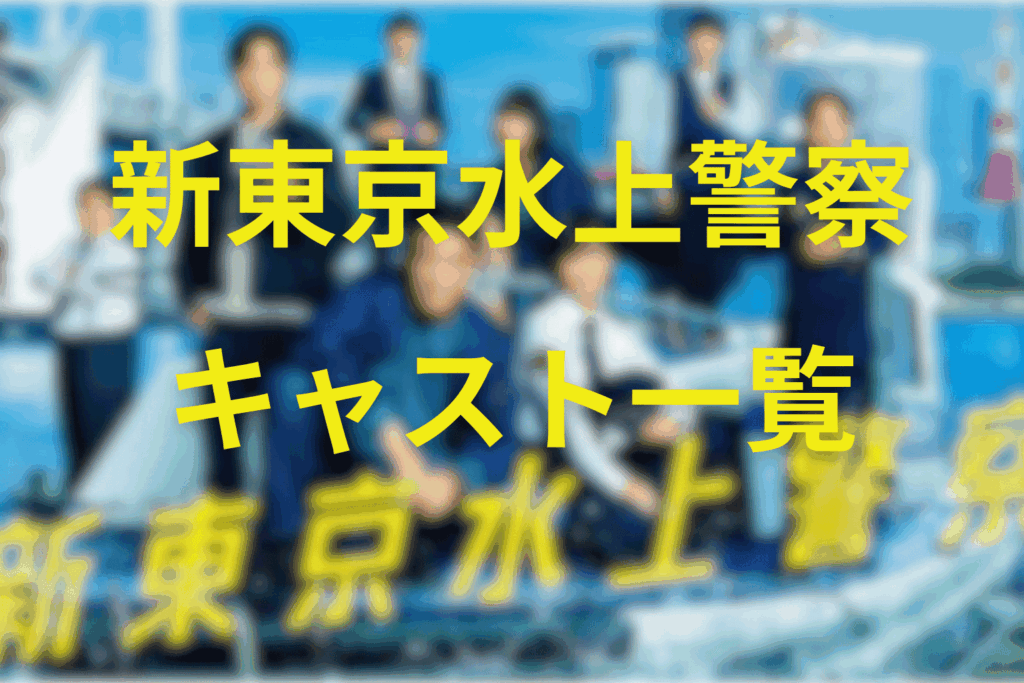
フジテレビの公式発表によれば、『新東京水上警察』は個性豊かなキャラクターが集結する群像劇です。
主演の佐藤隆太さんを中心に、実力派俳優から若手まで幅広い顔ぶれが揃い、水上署を舞台にしたドラマを力強く彩ります。ここでは主要キャストを一覧で紹介します。
主要キャスト
碇拓真(いかり たくま)…佐藤隆太:
水上警察署強行犯係の係長でリーダー。20年以上のキャリアを持つ刑事だが、水にまつわるトラウマを抱えている。
日下部峻(くさかべ しゅん)…加藤シゲアキ:
捜査一課から異動してきたエリート刑事。上昇志向が強く、碇とは水と油の関係ながら、次第に絆を深めていく。
有馬礼子(ありま れいこ)…山下美月:
若手の海技職員で船舶運航のプロ。チーム碇の「航海士」として活躍する。役作りのため一級船舶免許を取得している努力家。
細野由起子(ほその ゆきこ)…山口紗弥加:
水上署のベテラン刑事。物怖じしない性格で現場を仕切る姉御的存在。少年事件にも詳しい。
藤沢充(ふじさわ みつる)…中尾明慶:
元鑑識官の刑事。水上署に鑑識係がいないため貴重な戦力となる。温厚で家族思いだが、優柔不断な一面もある。
遠藤康孝(えんどう やすたか)…齋藤璃佑:
交番勤務から昇格した最年少刑事。真っ直ぐな性格で、碇を憧れの存在としている。
高橋宗司(たかはし そうじ)…皆川猿時:
水上警察署の課長。自由奔放な部下をまとめる中間管理職。碇と日下部に振り回されつつも署内を仕切る存在。
玉虫肇(たまむし はじめ)…椎名桔平:
水上署の署長で元海技職員という異色の経歴を持つ。“海を知るプロ”として警察に転身し、調整役を担う。署内では“たぬきおやじ”と呼ばれる人物。
ライバル・周辺キャスト
和田毅(わだ たけし)…谷田歩:
湾岸署の刑事で碇の天敵。水上署設立に強く反発し、最大のライバルとなる存在。
黒木謙一(くろき けんいち)…柿澤勇人:
人材派遣会社社長。かつて湾岸ウォリアーズの総長だった過去を持ち、水上署に立ちはだかる敵。
三上慎吾(みかみ しんご)…松本怜生:
介護施設スタッフ。事件に関わる重要なキーパーソンとして登場する。
大沢俊夫(おおさわ としお)…小林隆:
海技職員OB。水上署の活動に深く関わる人物であり、過去の経験が物語に影響を与える。
【全話】ドラマ「新東京水上警察」伏線回収まとめ
最終回まで見終えると、序盤では一見バラバラに見えた単発事件が、「港湾利権」と「黒木の逃走」を軸に、きれいに一本の線へ収束していくのが分かります。
ここでは、最終回で回収された伏線、あるいは回収に近づいた要素を整理します。
「海雪」移転工事の談合が“全体の背骨”だった
物語終盤の中心に据えられたのが、南極観測船「海雪」の移転工事をめぐる談合疑惑です。
港湾局の仲井、裏で暗躍する黒木、そして福本宗介殺害事件までが、この一本の利権構造に収束していきました。
最終回で仲井の逮捕が描かれたことで、「港湾の闇」は噂や裏設定ではなく、明確な犯罪として確定します。序盤から散りばめられていた港湾関係の違和感が、ここで一気に回収されました。
礼子の“無線・海上判断”が最終局面の決め手になる
水上警察ドラマらしい伏線回収が、礼子の無線判断です。
最終回、礼子は無線の応答から大沢の存在を察知し、「緊急検査」を口実に貨物船へ入るルートを作りました。
序盤から描かれてきた「現場を知っている側」の強みが、最後は理屈と技術として結実する。感情論ではなく、仕事として突破口を開くこの勝ち方が、チームの戦い方として非常にきれいでした。
大沢の立ち位置が“裏切り”ではなく“償い”として回収される
大沢は、黒木側にいるように見え続けたため、視聴者の中でも「結局どちらの側なのか」が曖昧な人物でした。
しかし最終回で、大沢は黒木を撃ち、三上を救い、その代償として命を落とします。
ここで彼の行動は「裏切り」ではなく、「最後に選んだ正義=償い」として明確に位置づけられました。
揺れ続けた立場が、最も重い形で回収された瞬間です。
【考察】ドラマ「新東京水上警察」未回収の伏線と続編の可能性
ここから先は、最終回で明言されなかった部分をもとにした考察です。確定情報ではなく、物語に残された余白として整理します。
黒木の遺体未発見=生存説の余地が残る
最大の未回収要素は、黒木の生死です。
黒木は海へ消え、遺体が発見された描写はありません。
「捕まった」「死亡した」という結論をあえて出さなかったことで、物語は“続く可能性”を残しました。最終回ラストに置かれた人影の演出も含め、黒木生存説は十分に成立します。
「港湾利権」は仲井で終わりなのか。上の存在がいるのか
仲井の逮捕でひとまず区切りはつきましたが、あれほど大規模な談合が一担当者だけで完結するとは考えにくいのも事実です。
もし続編が描かれるなら、
・仲井の背後にいた上位の存在
・黒木が食い込んでいた別ルートの利権
といった形で、さらに深い闇が掘り起こされる余地があります。
ラストで示された“新しい事件”は続編の火種
事件後に示された船上パーティーでの傷害事件は、「水上警察の仕事は終わらない」という意味だけでも成立します。
しかし、黒木の未決着と並べて提示されたことで、どうしても“次へ進む準備”に見える構成でした。
続編、スペシャル、映画へつなげるための自然な火種と考えられます。
ドラマ「新東京水上警察」の最終回の結末
最終回(第11話)は、黒木謙一が三上慎吾を拉致し、船で海へ逃走するところから始まります。
首都圏に台風が迫るなか、「追うのか、引くのか」という究極の判断を迫られた水上警察。チーム碇は、最後に“水上警察としての正義”を、文字通り命を懸けて証明する回となりました。
台風接近で出航禁止…それでも碇たちが海へ出た理由
署長・玉虫は、台風接近による危険性を理由に、いったん出航を止めます。ここで重要なのは、誰も勢いや根性論で海に出ようとしなかった点です。
日下部は母の危篤という個人的な事情を抱えながらも、「ここで引けば事件は終わらない」と踏みとどまります。礼子もまた、黒木と行動を共にしている大沢の身を案じ、捜索続行を訴えました。
玉虫はその覚悟を受け止め、「必ず生きて帰ること」を条件に出航を許可します。ここで交わされた“約束”が、最終回全体の緊張感を一段引き上げていました。
貨物船「竜水丸」に肉薄、礼子の無線が突破口になる
黒木が乗り込んだ貨物船「竜水丸」の停泊場所を突き止めた碇たちは、荒れる海の中を進み、船へと接近します。
ここで突破口になったのが、礼子の現場感覚でした。無線で竜水丸に呼びかけた礼子は、応答の声から相手が大沢であることを察知します。
そのまま「緊急検査」を名目に船内へ入る道を作り、チームはついに逮捕へ向けた舞台に上がることができました。
机上の理屈ではなく、“海の現場”を知る者の判断が活きた場面です。
甲板での銃撃戦、大沢が撃ったのは黒木だった
船内で黒木を追い詰めた碇たちは、最終的に甲板で黒木と対峙します。黒木は銃を構え、三上を人質に取って抵抗。状況は一気に緊迫します。
この局面で引き金を引いたのは、大沢でした。大沢は黒木を撃ち、黒木は三上を連れたまま海へ飛び込みます。大沢もすぐに海へ入り、三上の救出には成功しますが、その代償として命を落とすという結末を迎えます。
三上は助かった。しかし、大沢は帰ってこない。
最終回は、誰かが必ず犠牲になる“現実の重さ”を突きつける展開でした。
黒木は“死亡確定”ではない。遺体未発見のまま消える
事件としては、三上の救出と港湾局をめぐる不正の摘発まで進みます。しかし、黒木本人については遺体が発見されないまま物語が終わります。
つまり、物語は「決着したようで、決着していない」状態を意図的に残したのです。
視聴後に「黒木は生きているのではないか」と感じさせる余白があり、この曖昧さが最終回の後味をよりビターなものにしています。
港湾局・仲井と「海雪」談合の決着、三上の“告白”
陸側の事件も最終回で整理されます。
海雪の移転工事をめぐる談合に関与していた港湾局の仲井は、いったん失踪しますが、最終的に福本宗介殺害への関与が明らかになり、逮捕されます。
また、拉致されていた三上も、自らが「脅されていた側」であったことを語り、事件の全体像がようやく一本の線としてつながっていきます。
誰が主犯で、誰が利用され、どこから歯車が狂ったのか。最終回は、そこを曖昧にせず言葉にして終わらせました。
ラストは「新しい事件」と“意味深な人影”で終わる
最終回のラストは二段構えです。
ひとつは、事件後も新たな傷害事件が示され、水上警察の仕事が続いていくことを明確にした点。
もうひとつは、ラストに意味深な“人影”を映し、黒木の生存、あるいは新たな黒幕の存在を匂わせた点です。
すべてを説明し切らず、完全な終止符も打たない。
この「終わらせない終わり方」そのものが、続編やスペシャルを強く想像させるラストになっていました。
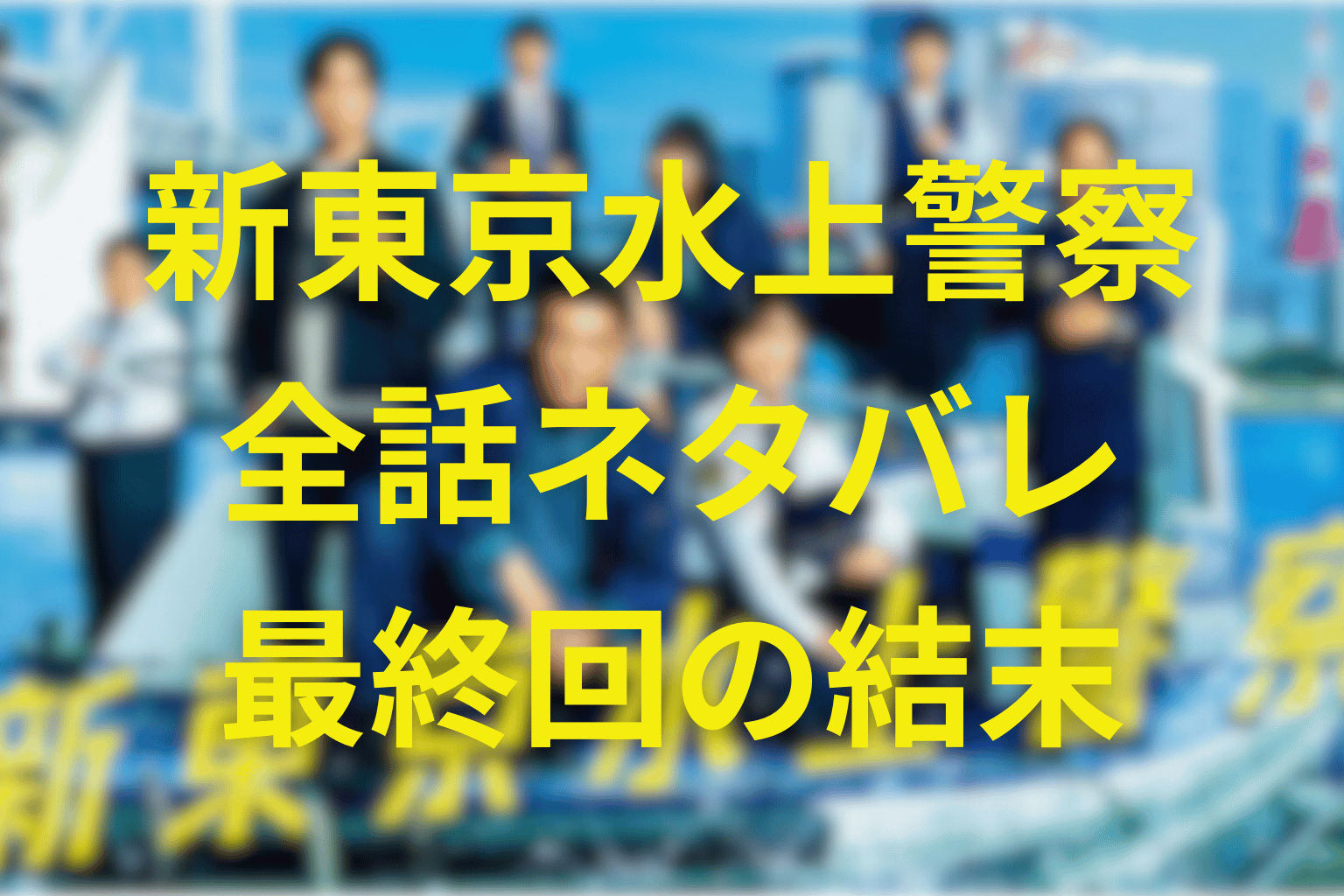
コメント