ドラマ「トリック」シーズン1は、霊能力や怪異を名乗る事件を“トリック”で暴きながら、毎回きれいにスッキリさせない、独特の後味を残してきました。
売れないマジシャン・山田奈緒子と、理屈で超常を否定する物理学者・上田次郎。
二人が挑むのは、超能力そのものよりも、「人はなぜ信じ、なぜ共犯になるのか」という厄介な問題です。
母之泉編で示された“暴けても裁けない現実”、瞬間移動殺人が突きつけた人間の悪意、千里眼回で露わになる正しさの副作用、そして黒門島編で描かれる奈緒子自身の出自と罪悪感。
この記事では、トリック シーズン1全話を通して描かれた事件・トリック・伏線を整理しながら、笑いと不気味さが同時に残る、この作品ならではの魅力を振り返っていきます。
TRICK/トリックの作品概要(基本情報)

シーズン1(通称:TRICK1)は、“超常現象に見える出来事”を、手品と科学でひっくり返していくシリーズの原点です。
まずは土台になる基本情報を整理します。
放送年/話数
- 放送年:2000年
- 放送期間:2000年7月7日〜9月15日
- 話数:全10話
- 放送枠:テレビ朝日系「金曜ナイトドラマ」(当時の放送時間:金曜23:09〜翌0:04)
主なスタッフ(脚本・演出など)
- 脚本:蒔田光治、林誠人
- 演出:堤幸彦、保母浩章、大根仁、木村ひさし
- 音楽:辻陽
- 主題歌(エンディング):鬼束ちひろ「月光」
- オープニング:辻陽「Mystic Antique」
- 制作:オフィスクレッシェンド/製作:テレビ朝日・東宝
主要キャスト
- 山田奈緒子:仲間由紀恵
- 上田次郎:阿部寛
- 矢部謙三:生瀬勝久
- 石原達也:前原一輝
- 山田剛三:岡田眞澄
- 山田里見:野際陽子
(レギュラー周辺として、奈緒子の大家・池田ハル=大島蓉子 なども、シーズン1の“日常側”を支える重要人物です)
世界観の特徴(オカルト×科学、笑い×不穏)
ジャンルとしては、推理(ミステリー)でありながら、コメディとオカルトの匂いが強いのが特徴。
中心にいるのは、自称天才マジシャン・奈緒子と、物理学教授・上田の凸凹コンビで、超常現象や奇怪な事件に隠された“トリック”を解いていく物語です。
ただし「トリックを暴いて終わり」ではなく、パロディや小ネタ、効果音まで含めた“笑わせる演出”が随所に仕込まれ、しかもそれが伏線として機能することがある──という、独特の作りがシリーズの骨格になっています。笑いが多いほど、次の瞬間に刺さる不穏さが増す。その混在が「TRICKの体温」です。
TRICK/トリックのシーズン1のエピソード毎の概要

シーズン1は、奈緒子と上田が“超常現象に見える事件”に巻き込まれ、最後に「それ、トリックでしょ?」と暴いていく基本形を固めたシーズンです。
まず迷子防止のために、シーズン1の“章立て”を先に出します。
- エピソード1:母之泉(第1話〜第3話)
- エピソード2:まるごと消えた村(第4話〜第5話)
- エピソード3:パントマイムで人を殺す女(第6話〜第7話)
- エピソード4:千里眼の男(第8話/単発回)
- エピソード5:黒門島(第9話〜最終話・第10話)
「基本は2話=1章」なのに、『母之泉』だけ3話、『千里眼の男』は1話完結という変則が入っているのが、シーズン1の特徴です
ここでは全話ネタバレに入る前段として、各エピソード(章)が「どんな話で」「何が分かるのか」をざっくり整理します。
エピソード1「母之泉」編(1〜3話)
新興宗教「母之泉」を舞台に、“透視”“壁抜け”“予言”のような現象が連続し、奈緒子と上田が初めて本格的にタッグを組む章です。信者の「信じたい気持ち」と、教団側の「信じさせたい仕掛け」が絡み合い、単なるインチキ退治では済まない後味が残ります。
この章でわかること
- 奈緒子×上田の“凸凹コンビ”が成立する経緯
- 「母之泉」とビッグマザーをめぐる怪異の構図
- 公安(矢部・石原)が事件へ介入する立ち位置
- “暴いても救えない”というTRICKの苦味の方向性
- 奈緒子の父(剛三)に繋がる不穏な匂い
エピソード2「宝女子村」編(4〜5話)
“村人がまるごと消えた”というスケールの大きい怪談風ミステリー。村全体が嘘をついているような閉塞感の中で、奈緒子と上田は「消失」の正体に迫ります。伝説や儀式が前面に出つつ、最後は“人間の都合”が露骨に見えるのが特徴。
この章でわかること
- 「消えたように見せる」ための集団的な演出の怖さ
- 外から来た人間が“空気”に飲まれる感覚
- 因習・伝説が、現実の犯罪や利得と結びつく構造
- 奈緒子の観察眼(現場の勘)が事件解決の軸になること
エピソード3「パントマイム殺人」編(6〜7話)
“見えない凶器で人が死ぬ”という、映像的にもホラー色の強い章。パントマイム=「見せる芸」が、殺人のアリバイ装置へ転用されるのがイヤらしく、目撃があるほど逆に混乱する展開が続きます。
この章でわかること
- 「目の前で見ていたのに防げない」タイプのトリックの怖さ
- 舞台芸・演技が“証拠のすり替え”として機能すること
- 事件の真相が明らかになっても救いが薄い余韻
- 奈緒子の“マジシャンとしての矜持”が強く出る章
エピソード4「千里眼」編(8話・単発)
1話完結で、テンポ良く“千里眼(透視)っぽい能力”の正体に迫る回。コンテストの賑やかさから始まりつつ、後半は霊感商法めいた現実の苦さへ踏み込んでいきます。短い尺でTRICKの笑いと後味を凝縮したタイプ。
この章でわかること
- “当てる”より“当てさせる”情報操作の怖さ
- 見世物の派手さと、被害者の切実さの落差
- トリックを暴くことが、必ずしも救いに直結しない現実
エピソード5「黒門島」編(9〜10話・最終章)
シーズン1の最終章は、事件の舞台が“奈緒子の家族と出自”へ寄っていきます。
父の死をめぐる疑念、母の故郷の島、因習めいた儀式――これまで外側の怪異を暴いてきた物語が、奈緒子自身の内側へ食い込むのが大きな転換点です。
この章でわかること
- 奈緒子の父(剛三)の死と、それに絡む謎
- 母(里見)の過去と「故郷の島」の意味
- 奈緒子が“疑う側”でい続ける理由が深掘りされる
- シーズン1の着地が「事件の解決」より「余韻」に寄ること
章ごとの“事件の顔”が全部違うのが、シーズン1の強さ
章ごとに、扱う“超常現象の看板”が明確に変わるのも、シーズン1のわかりやすさです。たとえば「母之泉」では霊能力者(ビッグマザー)を名乗る存在が登場し、奈緒子と上田がその舞台に乗り込みます。
続く「まるごと消えた村」は、村人消失や“出口が消える”など、スケールが一気に怪談寄りに。
「パントマイムで人を殺す女」は、見えない凶器=見えないナイフという、“見えないもの”の演出でミステリーの手触りを変えます。
単発の「千里眼の男」は、短い尺で「霊感商法っぽさ」と「トリック暴き」の快感を凝縮。
そして最終章「黒門島」で、これまで“外の事件”を解いていた物語が、奈緒子の“内側(家族・出自)”へ向き直る。ここがシーズン1の“季節の変わり目”です。
【全話ネタバレ】トリック(シーズン1)のあらすじ&ネタバレ

1話:透視――賞金に釣られた2人が、“怪異”の入口へ踏み込む
賞金に釣られた奈緒子と、挑発から始まる出会い
売れない自称天才マジシャン・山田奈緒子は、家賃滞納で完全に追い詰められている。
池田荘の大家に急かされ、明日の生活すら見えない中で目に飛び込んできたのが、物理学者・上田次郎による「霊能力者への挑戦状」だった。賞金という言葉に反射的に飛びつき、手品で“超能力者”を装って上田をだます。この導入だけで、奈緒子のしたたかさと「嘘をつく才能」が鮮やかに示される。
貧乏と矛盾が形作る奈緒子の倫理観
奈緒子の貧乏描写は容赦がない。家賃を払えず追い立てられ、賞金に目がくらむ現実が、彼女を常に「嘘をつく側」に立たせる。
一方で、霊能詐欺だけは許せないという一線も持っている。この矛盾こそが、『トリック』という作品の倫理観を決定づけている。奈緒子は守銭奴に見えて、完全な詐欺師にはならない。
上田の本当の目的と宗教団体「母之泉」
しかし上田が求めていたのは、賞金で釣れるインチキ霊能者ではなかった。
彼の狙いは、宗教団体「母之泉」にのめり込んだ日本科技大事務長の娘・大森美和子を連れ戻すための切り札だ。奈緒子は渋々同行し、教祖・霧島澄子、通称ビッグマザーの“透視”と対峙することになる。
ここから物語は、単なる賞金目当ての騙し合いでは済まなくなっていく。
温度差で成立する即席コンビの妙
初回の巧みさは、事件の謎以上にコンビの温度差で笑わせる点にある。
上田は天才を気取るわりに、肝心な場面で腰が引ける。一方の奈緒子は薄情に見えながら、観察眼だけは異様に鋭い。利害一致だけで結ばれた関係が、名コンビへ育っていく予感を、この時点ですでに漂わせている。
笑いの裏に差し込む不穏な影
宗教団体「母之泉」が放つ空気も絶妙だ。
信者たちの独特な言い回しや儀式は笑いを誘うが、そこへ公安の矢部と石原が動いている影が差し込むことで、一気に不穏さが増す。単なるコメディに収まらず、社会の裏側に触れている感覚が残る構成になっている。
父・山田剛三という静かな導線
亡き父・山田剛三が“天才マジシャン”として顔を出すのも重要だ。
奈緒子がただの守銭奴ではなく、マジックに妙な誇りを捨てきれない理由が、ここでさりげなく匂わされる。この要素は、シリーズ全体へつながる静かな導線になっている。
音楽と編集が作る世界観の完成度
音楽と編集も初回から完成形だ。妖しいオープニング曲が「真面目にふざける」世界へ一気に引き込み、ラストは不安と余韻だけを残して唐突に終わる。
このぶつ切り感が癖になり、2000年当時の空気感が画面の隅々に残っているのも再見の楽しさになっている。
科学と怪異の二重底が提示されるラスト
ビッグマザーが上田に突きつける「あと10日で死ぬ」という宣告は、科学と手品のゲームに一瞬だけ本物の怪異を差し込む。トリックを暴く快感と、暴ききれない何かの気配。
その二重底が、第1話の時点ではっきりと提示された。
1話で判明する伏線
- 上田次郎による「霊能力者への挑戦状」と賞金の存在
- 山田奈緒子が超能力者を装って上田をだます出会い
- 宗教団体「母之泉」と教祖・霧島澄子の存在
- 大森美和子の入信という事件の発端
- 公安部の矢部と石原が動いている事実
- ビッグマザーによる上田への死の宣告
- 山田奈緒子の父・山田剛三という過去
- 奈緒子の貧乏生活と池田荘
- 奈緒子の決め台詞「全部お見通しだ!」
シーズン1の1話のネタバレはこちら↓

2話:壁抜け――嘘を暴いた先に残った死
信じたい心が剥き出しになる二度目の儀式
第2話「壁抜け」は、母之泉編の中でも“信じたい心”が一気に露出する回です。
奈緒子と上田は二度目の儀式に参加し、教祖・霧島澄子が封筒に書かれた悩みを言い当てていきます。奈緒子の「貧乳」を暴露する下世話さに会場は沸くものの、奈緒子は封筒をアルコールで透かし、香で匂いを消す仕掛けを冷静に見抜く。
ところが澄子は「疑うと大切な人に不幸が訪れる」と言葉を重ね、上田までもが自分に突きつけられた“死の期限”に動揺し始めます。
トリックを暴いても戻らない美和子
種を明かしても、美和子の心は戻りません。息子を失った痛みが、教団の“水”や言葉にすがる理由になっているからです。
一方、公安の矢部は脱走した元信者が不審死している件で母之泉に踏み込みますが、幹部の津村は悪びれもせず「運命」と言い切る。この社会的な無力感が、笑いの裏に重く沈んでいきます。
奈緒子の矜持と、信者たちの現実
印象的なのは、奈緒子が笑われながらも「お前のやったことは全部お見通しだ!」と啖呵を切る場面です。
自尊心は傷ついても、手品師としての矜持だけは折れない。一方で、信者の女性が「貧乳は恥じゃない」と真顔で励ますやり取りが妙に優しく、彼女たちもまた普通の生活者だと気づかされます。上田の理屈っぽさと臆病さが同居することで奈緒子のツッコミが冴え、軽さが増すほど後半の死が鋭く刺さります。
能力と貧乏の落差が生む痛快さ
奈緒子は封筒のトリックを瞬時に見抜くほど有能なのに、生活は家賃滞納寸前。
この能力と貧乏の落差こそが、彼女の痛快さを加速させています。観る側は笑いながらも、その不安定さを常に突きつけられます。
強行手段と“呪い”が現実味を帯びる瞬間
二人は強行手段で美和子を連れ出し、上田の通信教育仕込みの格闘で追っ手を振り切ります。
笑いの勢いのまま倫理の薄氷を踏むからこそ、怖さが残る。
逃走先で匿ってくれる猟師・青木が、脱会した息子を“呪い”で失ったと語ると、教団の脅しは単なる芝居では済まなくなります。さらに、青木のキジ汁を上田だけが口にしないという小さな違和感が、「どうやって壁を抜けたのか」という謎へと繋がる匂いを残します。
笑いが刃に変わるラスト
終盤、里見が夫の「霊能力者は存在する」という言葉を思い出し、人影を見る挿入が効いてくる。
翌朝、美和子は奈緒子の隣で死体となり、遺書もあって自殺扱いに。矢部の雑な捜査が笑いを運ぶ一方、エンディングの余韻がその落差を強調します。暴いたはずの嘘が、誰かの死によって“本物”に見えてしまう。その嫌な感触こそが、次を見ずにいられなくさせる第2話です。
2話で判明する伏線
- 霧島澄子の「疑うと大切な人に不幸が訪れる」という脅し
- 上田次郎に示される“死の期限”の暗示
- 脱走した元信者が相次いで不審死しているという噂
- 津村俊介が不審死を「運命」と断じる態度
- 青木正吾の息子が脱会後に不可思議な病で死亡した過去
- 青木のキジ汁を上田だけが口にしない違和感
- 里見の悪夢と「霊能力者は存在する」という言葉
- 里見のそばに現れた人影
- 美和子の遺書と毒物による自殺扱い
- 「どうやって侵入したのか(壁抜け)」という未解決の謎
- 上田の嘘の癖(黒目が大きくなる)
シーズン1の2話のネタバレはこちら↓

3話:密室――「しかし証拠はない…」が突きつける冷たさ
トリックは暴ける、だが裁けない
母之泉編の決着となる第3話「密室」は、奈緒子の“トリック暴き”が最も痛い形で突き刺さる回です。
奈緒子は青木の家で霧島澄子(ビッグマザー)の肖像を見つけ、彼が信者側に深く関わっていると疑い始めます。矢部刑事たちが見守る中、帰ろうとする津村たちを引き止め、奈緒子は美和子殺しの仕掛けを言葉にしていく。
前夜のキジ汁に睡眠薬が仕込まれ、奈緒子と美和子が眠り込んだ隙に、津村が青木の手引きで犯行に及んだ――論理は通る。だが、その説明の直後に突きつけられる一文が、この回の冷たさを決定づけます。「しかし証拠はない…」。
密室が意味するものは、部屋だけじゃない
「密室」という題が指すのは、鍵のかかった部屋のトリックだけではありません。
母之泉という共同体そのものが、信者の心を閉じ込める密室でもある。奈緒子の推理は扉をこじ開けるけれど、外の光はあまりに眩しい。インチキを暴けば救える、とは単純に言えない。その現実が、容赦なく突きつけられます。
真実が救いにならない構造
この回の巧みさは、奈緒子が「わかった」と言える地点まで踏み込みながら、社会が求める“確証”には届かない構造を、あえて残している点です。
視聴者は真相解明によるカタルシスを期待するのに、作品は「裁けない現実」を置いていく。信仰対象を失った信者たちが取り残される後味が重く残り、真実とは必ずしも救済ではなく、ただ麻酔を剥がす行為なのだと知らされます。
笑いが落差を生む装置になる
その重さを中和するのが、上田と矢部の情けない騒ぎ方です。
命の危機でも体裁を守ろうとして空回りする上田、事件よりも自分の髪を気にする矢部。
くだらない笑いが挟まるからこそ、次の瞬間に突き落とされる落差がより鋭く効いてくる。『トリック』らしい緩急が、ここでも冴えています。
ビッグマザーは最後まで割り切れない
さらに厄介なのは、ビッグマザーの正体が最後まで完全には割り切れない点です。
トリックで説明がつく場面がある一方で、「どこまでが本当で、どこからが嘘なのか」と迷いが残る。終盤に差し込まれる奈緒子の父にまつわる不穏な影が、このエピソードを単なる完結編ではなく、シリーズ全体の背骨へと繋げていきます。
「本当の霊能力者はいる」という示唆は、次の事件への誘いであると同時に、奈緒子が“暴かずにいられない理由”そのものを照らしています。
正義をひっくり返す捨て台詞
幹部・津村が吐く「本当に救おうとしたのはどっちだ?」という捨て台詞は、正義の快感を反転させる一言です。
暴いた側が正しいはずなのに、取り残されるのは信じた人たち。奈緒子が「今度も本物に会えなかった」と漏らす余韻まで含めて、初回エピソードの着地として、これ以上ないほど意地の悪い完成度になっています。
3話で判明する伏線
- 青木の家にあった霧島澄子(ビッグマザー)の肖像
- キジ汁に睡眠薬が混入されていた事実
- 美和子殺しの構図(津村と青木の手引き)
- 「しかし証拠はない…」に象徴される、暴けても裁けない問題
- 津村の捨て台詞「本当に救おうとしたのはどっちだ?」
- ビッグマザーが触れた奈緒子の父の死
- 「本当の霊能力者はいる」という示唆
- 奈緒子の「今度も本物に会えなかった」という余韻
シーズン1の3話のネタバレはこちら↓

4話:村人が全員消えた――“いなかったこと”にされる恐怖
生活臭の強い導入と、桁違いの依頼
前編の導入からして、『トリック』らしく生活臭が濃い。
沖縄居酒屋のバイトで食いつなぐ奈緒子のもとに舞い込むのは、“村ごと消えた”というスケール感だけが異様に大きい依頼だ。
宝女子村の駐在所に赴任したばかりの前田巡査が「村人が全員消えた」と通報し、捜索に入った隊まで行方不明になる。公安課長・伊藤は霊能力の裏側に詳しい上田に調査を依頼し、上田は渋る奈緒子を半ば強引に連れ出す。矢部も同行するが、任務より自分の都合を優先しがちで、その軽さが事件の不穏さを逆に際立たせる。
ミラクル三井という“冗談が冗談に見えない存在”
村で鍵を握るのが、自称霊能力者・ミラクル三井だ。彼は「物体や痛みを別世界へ送れる」と豪語し、村人を消したのは自分だと言い放つ。
白い帽子に派手な衣装、芝居がかった言動だけを見れば胡散臭い。それでも、無人の村という背景が加わることで、冗談が冗談に見えなくなる怖さが生まれる。
さらに三井には、奈緒子の父・剛三にインチキを暴かれた因縁がある。この過去が、奈緒子の感情を単なる正義から一歩だけ私的な領域へ引き寄せる。
“変な村”が映す共同体の歪み
宝女子村編が名作と呼ばれがちなのは、この村が単なる舞台装置ではなく、排除や噂が増幅する共同体の縮図として描かれるからだ。
三井の言葉の端々からは、村そのものへの怨念が滲む。消えるのは人なのか、記憶なのか、それとも最初から存在しなかったことになるのか。問いの形が進むほど、物語は嫌な方向へ更新されていく。
“消失”を空白として見せる演出
第4話の残酷な巧さは、消失を派手なマジックとして見せない点にある。家も道も残っているのに、人だけがいない。
その違和感は、説明されないほど濃くなる。そこへ現れては消える「謎の少女」が加わり、観る側の理解は意図的に遅らされる。
演出が変わったことで、山の湿気や暗がりの質感が強調され、笑いの隙間から不気味さが滲み出す。理屈が追いつく前に背中が寒くなる、この嫌な引きが後編への中毒性を生む。
悪役で終わらないミラクル三井の厄介さ
ミラクル三井は単なる悪役ではなく、どこか哀れさを抱えた存在だ。
上田の理屈を嘲笑うように、“見せること”そのものへ執着する姿勢が厄介で、彼の言動は最後まで割り切れない。エンディングで流れる音楽が重なると、笑いと恐怖が同じ輪郭に溶け、説明しきれない後味だけが残る。
4話で判明する伏線
- 宝女子村の村人全員消失という前田巡査の通報
- 捜索に入った消防団の失踪
- 公安課長・伊藤が上田に調査を依頼した背景
- ミラクル三井の「消失」能力の存在
- ミラクル三井と山田剛三の因縁
- 村に出没する謎の少女の存在
- 矢部謙三の職務怠慢が生む捜査の混乱
- 「消える」現象が存在そのものに及ぶ可能性
- 解決編へ続く“誰かの消失”という不穏な引き
シーズン1の4話のネタバレはこちら↓
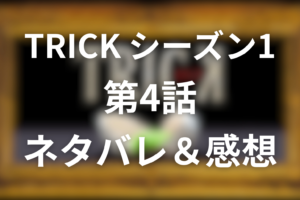
5話:村が消えた…解決篇――密室は人が作る
首なし死体と“出口の消失”で完成する密室
上田らしき首なし死体が現れ、奈緒子と矢部が村の外へ出ようとすると、出口であるはずの橋が消えている。
前回の「村人消失」から恐怖は一気に“密室”へと姿を変える。家に戻って死体を改めるものの、それが本当に上田なのか確信できないまま時間だけが過ぎていく。奈緒子は、ミラクル三井のビデオに映る家で見つけた「怪しげな絵」と、その裏に書かれた不可思議な言葉を手がかりに推理を進める。
三井は“消失”を誇示し、巨石群までも消してみせるが、奈緒子が覚えるのは驚きではなく、「この村そのものが何かを隠している」という嫌な確信だ。さらに、マントを被せられた奈緒子自身が“消される”展開は、コメディの足場を一瞬で外し、視聴者も彼女と同じ不安の中へ放り込まれる。
笑いがあるからこそ際立つ恐怖
極限状況でも軽口と小ネタは健在で、身元確認をめぐるやり取りなどがテンポよく差し込まれる。その“ふざけた空気”があるからこそ、次の瞬間に起きる消失や突然の孤立が、いっそう怖く感じられる。
矢部が意外と人間味を見せる場面もあり、名脇役として物語の温度を微妙に調整する。上田不在の間、奈緒子が矢部と組んで動くことで、これまで見えにくかった彼女の胆力が浮かび上がる。
超常の果てに残る「人間の嘘」
本当に面白いのは、超常現象を派手に積み上げた末に、解決編が「人間の手で作れる嘘」の重さへ着地する点だ。村人は実際に消えたのではなく、外から来た人間を欺くために“消えたふり”をしていた。さらに、同行していた前田巡査すら偽物で、真相に触れた本物は殺されていたという悪趣味さが効いてくる。
手品の種が道具ではなく、“集団の口裏合わせ”にあることが、このエピソードを強烈に後味の悪いものにしている。来た道が木や葉で巧妙に隠され、消えたはずの橋が“復活”する瞬間、こちらも同じ目線誘導に引っかかっていたと気づかされる。
因習としての「生贄」と少女の言葉
奈緒子が出会う「死んでいなければならない」少女の言葉は、村に残る因習――25年ごとの生贄儀式――を示すサインだ。軽快な笑いのテンポの中に打ち込まれる、冷たい釘のような一言である。
ミラクル三井の最期とTRICKの本質
ミラクル三井は、「奇跡を起こす男」というより、村と世間の欲望に利用される“舞台装置”として描かれる。持ち上げられ、化けの皮が剥がれ、帰る場所でも居場所を失った人物が、最後に選ぶのが「自分自身を消す」結末であることが、残酷で忘れがたい。
TRICKの魅力は、種明かしでスッキリさせながら、「人はなぜ騙され、なぜ共犯になるのか」というざらついた後味を必ず残す点にある。第5話はその作法が早くも完成形で、笑っていたはずなのに、見終わると妙に胸が引っかかる。
5話で判明する伏線
- 上田らしき首なし死体の正体
- 村の出口(橋)が消える仕掛け
- 来た道が木や葉で隠されていた事実
- 同行していた前田巡査の“偽物”疑惑
- 村人全員が“消失”を演出していた真相
- ミラクル三井のビデオに映る「怪しげな絵」
- 絵の裏に書かれた不可思議な言葉の意味
- 「死んでいなければならない」少女の正体
- 25年ごとの生贄儀式という因習
- ミラクル三井の過去と最期
シーズン1の5話のネタバレはこちら↓

6話:瞬間移動殺人の秘密――身体が先に信じる嘘
“痛快な種明かし”から外れていく前編の空気
第6話「瞬間移動殺人の秘密」は、エピソード3「パントマイムで人を殺す女」の前編にあたる回です。
ここからのトリックは、霊能詐欺を暴くいつもの快感よりも、「暴けても裁けないかもしれない」という嫌な現実へと重心を移していきます。軽快に始まるのに、どこか最初から後味の悪さが予告されているのが特徴です。
家賃と取引から始まる“血の重さ”
家賃取り立てから逃げる奈緒子が、上田の研究室へ転がり込むところから物語は動きます。そこへ矢部が連れてくるのが、「霊能力で3人の男を殺した」と自首してきた黒坂美幸。しかも彼女の希望は、「監禁して、証人になってほしい」という異様なものです。
上田は半ば強引に監視役を押し付けられ、奈緒子は家賃5か月分を払わせる条件で渋々同行する。この取引の軽さが、後に突きつけられる血の重さを、かえって際立たせます。
静かすぎる“確信犯”としての黒坂美幸
美幸が怖いのは、派手な霊能力者然とした芝居ではなく、妙に地味で静かな確信犯として現れる点です。彼女の宣言は、「イメージしたことを現実にする」という一言だけ。
密室同然の研究室でパントマイムを始めた直後、離れた場所にいる男が実際に死亡する。
ベルトで首を絞める“空の動作”だけで殺人が成立し、続く“見えないナイフ”では、何もない空間から血しぶきまで上がる。理屈で追いつく前に、身体が「信じてしまう」恐怖が先に来る構成です。
笑いと血の落差が生む異質な恐怖
それでも、この回には下世話な笑いがきっちり挟まれます。上田の言葉遊びや矢部と石原の脱力したやり取りが入り、視聴者は一度力を抜かされる。だからこそ、その直後に血の描写で殴られる落差が効く。
笑っていたはずなのに、次の瞬間には背中が冷える。この振り幅が、第6話をシリーズ屈指の“トラウマ回”に押し上げています。
手品とパントマイムの残酷な対比
マジシャンである奈緒子が対峙するのが、同じく“見せる芸”であるパントマイムという点も皮肉です。手品は驚かせても、最後には笑わせられる。一方、美幸のパントマイムは笑いの出口を塞ぎ、観る者を容赦なく“目撃者”に変えてしまう。
舞台芸が犯罪のアリバイ装置になる発想は、シリーズの中でも特にいやらしく、後味の悪さを強めています。
最大の引きは「動機」が見えないこと
第6話が残す最大の引きは、「なぜ彼女は黙って殺さず、わざわざ警察に挑戦するのか」という動機の闇です。トリックの形より先に、人間の底が見えない怖さが立ち上がる。
奈緒子の“疑う才能”が試される一方で、答えは後編へと先送りにされ、視聴者だけが不安を抱えたまま放置されます。
6話で判明する伏線
- 黒坂美幸が「霊能力で3人の男を殺す」と自ら警察に申し出る
- 監視と監禁の舞台が上田の研究室という密室であること
- 奈緒子が報酬として家賃5か月分を要求する取引
- 美幸の能力宣言「イメージしたことを現実にする」
- パントマイムによるベルト絞殺
- パントマイムによる見えないナイフと血しぶき
- 監視中でも成立する瞬間移動/遠隔殺人の謎
- 標的が3人いることの示唆
- 美幸が警察に挑戦する目的が不明なままである点
- 単独犯では説明しきれない協力者の存在を匂わせる違和感
シーズン1の6話のネタバレはこちら↓

7話:遠隔殺人意外な真実――完璧すぎるアリバイ
物証がアリバイになる異常事態
6話で予告された「霊能力で3人殺す女」黒坂美幸の事件は、第7話で一気に底が抜けます。
見えないナイフで刺し殺したはずの被害者の血が美幸の服に付着し、凶器からも指紋が検出される。普通なら決定打になる物証が揃っているのに、上田と奈緒子が目の前で彼女を監視していたため、それらが逆に“完璧なアリバイ”として機能してしまう。
美幸は「最後の一人も証人になって」と言い残し、罪に問われることなく去っていく。この瞬間、追う側は初めて「理屈では勝てないかもしれない」という感覚に直面します。
見えないはずの武器が残す生理的恐怖
この回が厄介なのは、トリックの巧妙さ以上に、「見えないはずの武器」が映像として立ち上がってくる点です。
ベルトで首を絞め、ショットガンを構え、刃物を振り下ろす。ただのパントマイムなのに、殺意の輪郭だけが異様にリアルで、血しぶきの演出も相まって思わず目を逸らしたくなる。
コミカルな空気で油断させた直後にホラーへ落とす、この振り幅はシリーズ屈指です。
追う側に漂う「勝てないかもしれない」空気
ここで追う側の焦りが、単なる混乱から絶望に近いものへ変わります。
鍵になるのが、上田が日頃から好んで観ている昼番組「哲!この部屋」の双子特集。一見するとただの小ネタですが、奈緒子の推理を“双子”という最短距離へ導く重要な導火線になっている。
双子トリックが崩す超能力の幻想
真相は、姉・美幸が監視下でパントマイムを演じている同時刻に、瓜二つの妹・洋子が別の場所で実行犯として殺人を起こしていたというもの。超能力ではなく、視線を一点に集める舞台装置としての“演技”だった。
さらに三人目の被害では、電話越しの銃声と悲鳴を使って死亡時刻を偽装する細工が施されていた。現場にあったナマズ水槽の自動給餌機(Food Timer)の音が、その時刻のズレを暴き、トリックの綻びを露わにする。
日常パートが与える呼吸と冷え
同時に、母・里見が上京し、上田宅に居候するサブプロットが挟み込まれるのも効果的です。殺人の気配で胃が重くなったところに、親子の距離感の気まずさという日常を差し込み、物語に一息つかせる。
ただし、その日常のすぐ隣で人が死ぬ。この並置こそが『トリック』であり、笑っているうちに心が冷えていきます。
救われなさが残る結末
何より胸に残るのは結末です。種明かしのあとにも、爽快なカタルシスは訪れない。妹は姉をかばって罪を背負い、姉はその善意すら利用して口封じに毒を盛る。事件は解決しても、誰一人救われない。
真実は正しさと同義ではない――美幸が残す一言が、その冷たい核心を突いてきます。
7話で判明する伏線
- 黒坂美幸の「霊能力で3人を殺す」宣言の本当の狙い
- 返り血と凶器の指紋が決定打にならない理由
- 黒坂美幸のアリバイを成立させた双子トリック
- 黒坂洋子(双子の妹)の存在
- 3人目・松井一彦の死亡時刻を偽装した仕掛け
- ナマズ水槽の自動給餌機(Food Timer)のタイマー音
- 「哲!この部屋」双子特集が示していたヒント
- 事件後に残る救われなさと、美幸の捨て台詞の意味
シーズン1の7話のネタバレはこちら↓

8話:千里眼を持つ男…――視えていたのは嘘だけ
温泉旅行を賭けた“びっくり人間コンテスト”
家賃を滞納し続ける奈緒子に、大家の池田ハルが持ち込んだのは「びっくり人間コンテスト」のチラシ。
優勝賞品の温泉旅行を家賃代わりに取ってこいという、相変わらずの無茶ぶりで、奈緒子は巣鴨へ向かう。
会場の審査員席には、なぜか上田が鎮座しており、思わぬ再会からいつもの口げんかが始まる。奈緒子の手品は最初こそウケるが、仕掛けの故障で空気は一転。客席のブーイングを切り裂くように現れたのが、片目に眼帯をした自称霊能者・桂木弘章だった。
千里眼が会場を支配する瞬間
桂木は観客や上田が書いた数字を次々と言い当て、場の空気を一気に掌握する。
その能力は“千里眼”と称され、拍手とどよめきが会場を包む。
だがその裏で、桂木は病気の子どもや高齢者に高額な品を売りつける、霊感商法まがいの行為を繰り返していた。被害に遭った老人・菊池は、奈緒子と上田に「インチキを暴してほしい」と依頼し、温泉券まで差し出す。正義と生活が同時に転がり込む、この導入の軽さがTRICKらしい。
対決の鍵は“情報の流れ”
二人が突き止めた核心は、能力ではなく情報だった。数字当ては、会場で見えた数字を第三者が伝えるだけで成立する。
だが桂木はそれだけでなく、奈緒子の部屋や上田の自宅の間取りまで言い当てる。宅配業者を使った下見、向かいの建物からの覗き見、そして秘書が電話やイヤーモニターで指示を送る連携プレー。
超能力の正体が“組織的な情報収集”だと明らかになった瞬間、眼帯も儀式も単なる営業ツールへと転落する。
「橋」と「箸」が暴いた最後の綻び
決定打になるのが、「橋」と「箸」の聞き間違いだ。
上田の部屋にあった“橋のオブジェ”が、関西弁のイントネーションによって「箸」と誤認され、桂木の透視が崩れる。この言葉のズレを突くオチは、理屈と悪意が噛み合った、いかにも意地の悪い笑いになっている。
笑えないラストが残す苦さ
事件としては死人も出ず、矢部が桂木を逮捕して幕を引く。
それでも後味は軽くない。車いすの少年が「僕、治らないの?」と縋ったとき、桂木が笑顔で現実を突きつけるラストは、視聴者の間でも強く記憶に残る場面だ。悪を暴く正義が、弱い希望まで剥がしてしまう。その“正しさの副作用”が、この8話には凝縮されている。
8話で判明する伏線
- コンテストでの数字当ての正体は第三者による情報伝達
- 桂木の千里眼を支える仕掛けは秘書の指示と受信機
- 奈緒子の部屋の間取りが当てられた理由は事前の下見と覗き見
- 「橋」と「箸」の違和感が示した決定的なヒント
- 眼帯の儀式性はミスリードで、本当の鍵は情報操作にあった
シーズン1の8話のネタバレはこちら↓

9話:父を殺した真犯人――疑われた血
“犯人捜し”ではなく、奈緒子の根っこを抉る前編
第9話「父を殺した真犯人」は、黒門島編の前編として、事件の謎よりも先に奈緒子の核心をえぐってくる転換回です。
ある夜、奈緒子の部屋に亡き父・剛三を名乗る不審な電話がかかり、翌朝には差出人不明の手紙が届く。封筒の仕掛けで浮かび上がった住所を辿ると、黒津次男・三男と名乗る兄弟が現れる。彼らは母・里見の故郷である南方の島「黒門島」から来たと語り、奈緒子を島へ連れ戻そうとする。
そして放たれるのが、「父を殺した超能力者は奈緒子だ」という決定的な一言。タイトルの“真犯人”が、犯行の主体ではなく、奈緒子自身を指す言葉として突きつけられる瞬間だ。
父が“現れる”残酷な種明かし
心を強く掴まれるのは、剛三が目の前に“現れる”場面です。
一瞬だけ死者の帰還を信じさせておいて、正体は黒津兄弟による変装だと明かされる。通常なら痛快なはずの種明かしが、この回では喪失の記憶を直接揺さぶる刃になる。
奈緒子はマジシャンで、父も天才マジシャン。その「騙す技術」が、最も騙されたくない相手である家族に向けられる皮肉が、重く胸に残ります。
巫女の血筋と“否定したい疑い”
さらに明かされるのが、里見が黒門島に代々続く巫女の家系であるという事実です。30年前、剛三とともに島を出た過去も語られ、黒津次男は「島を救うために奈緒子が巫女として戻るべきだ」と迫る。
ここで奈緒子は、「自分は本当に霊能力者なのかもしれない」という、最も否定したい疑いを背負わされる。石原から父の死の状況を聞き出すくだりも含め、普段のボロアパートの騒動や軽口が嘘のように静まり、物語は一気に内側へ潜っていく。
重さを際立たせる“上田の暴走ギャグ”
この重苦しさの隙間に、上田が媚薬絡みで情けなく暴走するギャグが差し込まれるのが、TRICKの意地悪さです。
強烈な笑いが入るほど、奈緒子の孤独が際立つ。軽い下ネタが単なる逃げではなく、次に来るシリアスをより深く落とすための助走として機能しているのが悔しいほど巧みです。
黒門島という舞台が持つ因習の気配
ラストで奈緒子は、黒津兄弟とともに黒門島へ向かう決意を固めます。黒門島という名前が連想させる因習島モノの空気が、ここから一気に濃くなっていく。
解くべき謎は、島の怪異だけではありません。奈緒子が父の死と自分の血をどう受け止めるのか、そして上田は“科学”で彼女を救えるのか。笑いと不気味さの配合が意図的に歪められた、シリーズ屈指の嫌な引きです。
9話で判明する伏線
- 父・剛三を名乗る不審な電話の存在
- 差出人不明の手紙
- 封筒から浮かび上がる住所の仕掛け
- 黒津次男・黒津三男という兄弟の登場
- 里見の故郷「黒門島」の存在
- 里見が黒門島の巫女の家系である事実
- 30年前、里見と剛三が島を出た過去
- 剛三が“現れる”出来事の裏にある変装
- 「父を殺した真犯人は奈緒子」という告発
- 石原が語る剛三の死の状況
- 奈緒子が黒門島へ向かう決意
シーズン1の9話のネタバレはこちら↓

10話(最終回):真犯人はお前だ!!――裁けない真実
奈緒子失踪から始まる、家族という名の最終対決
奈緒子の失踪を追う形で、上田はアパートで母・里見と対面する。
里見は静かに、「奈緒子には霊能力があり、その力が父・剛三の死に関わった」と語るが、上田は到底信じない。それでも、すべてを“運命”という言葉で片付けようとする里見の態度には、説明できない不穏さが漂う。
科学VSオカルトというおなじみの構図が、この最終回では家族の秘密へとねじれていく。その歪み方が、いかにもTRICKの終盤らしい導入だ。
黒門島で突きつけられる「力があるかもしれない恐怖」
一方の奈緒子は、黒津兄弟に連れられて母の故郷・黒門島へ到着する。
間髪入れずに進められる婚礼の儀式「アナアキー」、突然のめまい、島の言葉が口をついて出る感覚、枯れた花が戻るような異変。ギャグのテンポを保ったまま、「本当に力があるのでは?」という疑念を突き付けてくる怖さがある。
上田の切り札だった「全部説明できる」という言葉も、この回ではどこか頼りない。奈緒子自身も戸惑いながら、説明できない懐かしさに引き寄せられていく。島そのものが「帰れ」と囁いているように見える演出が、背筋を冷やす。
怪異より前に描かれる「逃げたい」という感情
黒門島編の面白さは、怪異の正体を暴く前に、奈緒子の「逃げたい」が前面に出る点にある。儀式からの脱走劇は笑えるのに、島の因習と「嫁に戻れ」という圧は容赦ない。その瞬間、コメディの輪郭が一気に黒くなる。
分家である黒津兄弟は、島を救う顔をしながら、別の狙いを隠している。奈緒子を追って島に乗り込む上田、偶然バカンスで居合わせる矢部まで巻き込み、元男が託した「割符」が“誰を信じるか”の証明書のように機能する構図が巧だ。
真犯人は「誰か」では終わらない
タイトル通り、この最終回は真犯人を一人指さしてスッキリ終わる話ではない。欲望のために家族を道具にする者、運命を盾に娘を縛ろうとする者、そして何より、奈緒子自身の罪悪感が最大の檻として立ちはだかる。
「宝は要らない」という選択に行き着くラストは、事件解決というより、価値観の決着だ。視聴者の胸に残るのはカタルシスではなく、皮肉と余韻である。
出自で終わる、TRICKらしいシーズンの締め
最終回は、奈緒子が黒門島で“カミヌーリの血”という自分のルーツと向き合う物語として着地する。シーズン1を「事件」ではなく「出自」で終わらせる潔さが印象的だ。
エンドロールで主題歌が生で差し込まれ、現実感がほどけたまま、奈緒子と上田の関係だけが残る。終わりきらない感覚こそが、TRICKという作品の体温であり、最終回にふさわしい余韻になっている。
10話(最終回)で判明する伏線
- 里見が語る「奈緒子の霊能力」と剛三の死の関係
- 黒門島に伝わる婚礼儀式「アナアキー」
- 奈緒子のルーツである黒門島とカミヌーリの血
- 黒津兄弟が剛三を騙ってまで奈緒子を連れ戻した理由
- 黒津兄弟の真の狙いと、島に隠された“宝”
- 黒津元男が託した「割符」の意味
- 「宝は要らない」に繋がる最終的な選択
シーズン1の最終回のネタバレはこちら↓

トリック(シーズン1)の主要キャラクター整理(関係性が分かる最低限)

シーズン1を理解するうえで重要なのは、「誰が事件を解き」「誰が事件を運び」「誰が奈緒子を縛っているか」です。
ここだけ押さえると、各章の見え方が一気に整理されます。
山田奈緒子(仲間由紀恵)
奈緒子は“事件の中心”ではなく、いつも“生活の崖っぷち”にいる側から始まる人物です。
自称天才マジシャンとして事件に首を突っ込み、上田の理屈とぶつかりながらも、最後に「それ、仕掛けでしょ?」へ辿り着く役回り。
奈緒子の芯にあるのが、父・剛三から受け継いだ「超常現象はマジックで説明できる」という感覚で、ここが作品の“反オカルト”を支えます。
山田奈緒子についてはこちら↓

上田次郎(阿部寛)
上田は日本科学技術大学の物理学教授で、超常現象を“科学の側”から斬ろうとする人。
ただし完全無欠の理系ヒーローではなく、プライドと小心が同居しているのがポイントで、奈緒子の観察眼や直感が噛み合ったときに、初めて事件がほどけていく。
理屈の上田/現場の奈緒子という役割分担が、シーズン1の基本形です。
矢部謙三(生瀬勝久)/石原達也(前原一輝)
矢部は公安の刑事で、“事件を持ち込む装置”でもあり、“空気を抜くコメディ装置”でもあります。
石原はその部下で、矢部の雑な指示に振り回されつつ、現場の常識担当として機能することが多い。二人がいることで、奈緒子と上田のコンビが「民間の二人ごと」で終わらず、事件が社会の側に接続されます。
山田里見(野際陽子)
奈緒子の母。序盤は“生活の現実”を背負わせる存在として、終盤は“家族の秘密”へ繋がる存在として、役割が変化します。
シーズン1の最終章に向けて、里見がいることで「事件」ではなく「出自」の匂いが立ち上がってくる。
池田ハル(大島蓉子)
奈緒子が住むアパート「池田荘」の大家で、奈緒子の天敵。家賃の取り立て役として、毎回“現実”を突き付けてくる存在です。
事件がどれだけ怪異でも、奈緒子はここに戻れば家賃の地獄が待っている──この戻り先があるから、非日常が笑いに変換される。
山田剛三(岡田眞澄)
奈緒子の父で、著名な天才マジシャン。幼少期の奈緒子に手品を教え、超常現象はマジックで説明できるという信念を持っていた人物です。
剛三の存在は「現在の事件」ではなく、「奈緒子の価値観」を規定する“見えないレギュラー”。シーズン1終盤で、この父の死が物語の重力になります。
父親の山田剛三についてはこちら↓

TRICK/トリックシーズン1の伏線

「トリック」の伏線って、いわゆる推理小説みたいに“これが犯人の証拠です!”と一直線に回収されるタイプだけじゃないんですよね。
むしろ、ギャグや小道具、会話の脱線が「あとで思い返すと意味がある」形で刺さってくる。作中のコミカルな演出が“伏線”として機能する、という指摘もあります。
霊能力への「挑戦状」が、シリーズ全体の磁場になる
シーズン1の出発点は、金欠の奈緒子が“霊能力者への挑戦状”を掲げる上田を見つけて、賞金目当てに会いに行くところ。ここで「超常現象=暴くべき対象」というルールが決まります。
このルールがあるからこそ、毎回の事件は「信じたい人」と「信じさせたい人」と「信じない人」が衝突する構図になる。つまり、事件を呼び寄せる“磁場”そのものが、最初から伏線になっているわけです。
奈緒子の“父の死”が、物語を最終章へ引っ張る
伏線として一番わかりやすく“縦糸”になっているのが、父・剛三の死。
第9話で、奈最子が父の名を語る男から電話を受け、差出人不明の手紙の“住所”へ向かうところから最終章が起動します。さらに、父の姿をした人物が現れて動揺する奈緒子──ただしそれは父本人ではなく、黒津兄弟が“父の姿を真似た”ものだった、という情報まで提示されます。
この時点で、「霊能力のトリック」ではなく、奈緒子の人生そのものが事件化する。それまでの章とは、明らかに温度が違うんです。
“黒門島”という固有名詞が持つ不穏さ
黒門島編は、「母がかつて住んでいた沖縄県の島」へ奈緒子が向かう、という形で語られます。
ここが上手いのは、島が“舞台”であると同時に、奈緒子にとっては家族史の封印場所として置かれているところ。事件解決のために行くのではなく、自分が何者かを知るために行く。この目的の変化が、そのまま終盤の不気味さに直結します。
最終回直前で投下される「奈緒子の霊能力」発言
最終話(第10話)の導入で、上田は里見から「奈緒子に霊能力があり、その力で剛三が死んだ」と聞かされます。
上田は当然信じられない。しかしその頃、奈緒子は黒津兄弟と黒門島に到着し、婚礼の儀式「アナアキー」が行われる……と、公式系のあらすじでも“異常事態”が並びます。
ここ、シリーズ的には禁じ手に近いんですよ。だって「全部トリックです」と言ってきた物語が、最後に「本当に霊能力かも」を投げてくる。だから視聴者は、ここで初めて“足元”が揺らぐ。
「本物がいるかもしれない」余韻を残す作風そのものが伏線
そもそも「トリック」は、毎回トリックを暴きながらも、作中に“本物の超能力者/霊能力者に見える人物”が存在し、視聴者に苦味の残る余韻を与えることがある、とも説明されています。
つまり、「全部は割り切れない」作り自体が、最終章へ向けた伏線なんですよね。スパッと割り切れる気持ちよさと、割り切れない後味が、最初から同居している。
TRICK/トリックシーズン1の未回収・曖昧なまま残るポイント

TRICKの面白さは「トリックを暴く」だけじゃなく、暴いたのにスッキリしないところにあります。答えを出さない余白があるから、視聴後に“考察”が生まれ続ける。
あえて断言しない“本物かも”の扱い
シーズン1は基本的に“インチキ霊能力”を解体する作りなのに、最終章では母・里見の口から「奈緒子に霊能力があり、その力で剛三が死んだ」と語られる。ここがズルい。
上田は信じきれず、奈緒子本人も“確信の顔”ではないまま島の因習に飲み込まれていく。
つまり物語は、「本物かどうか」より先に、「信じさせる状況」を作ってしまう。その設計が“本物かも”論争の燃料になる。
視聴者の解釈が割れやすい点(2〜4項目)
- ① 奈緒子の霊能力は“本物”なのか?
里見の発言は強いが、作中は断言しきらない。視聴者は「里見の商売・島の空気・上田への牽制」なども含めて解釈が割れる。 - ② 父・剛三の死は“事件”として解けても、感情としては終わらない
黒門島章は“真犯人”の線で進むのに、最終的に残るのは「罪悪感」と「運命っぽさ」。論理で割り切れない余韻が残る作りになっている。 - ③ 「裁けない」「救えない」が、意図的に置かれている
パントマイム章で象徴的なのが「霊能力殺人では逮捕できない」という壁。真相が見えても、社会の側のルールが追いつかない。スッキリしない“現実”が残る。 - ④ “オカルトは嘘”と言い切りたいのに、最後に揺らがされる
上田は理屈で否定する側の象徴なのに、黒門島では理屈の外に連れていかれる。そこでドラマが「勝ち負け」を決めないから、視聴者の解釈も割れる。
「解けないもの」を置く理由
TRICKは、科学vsオカルトの勝負を見せたいわけじゃない。もっと面倒くさい、“人間の弱さ”を見せたい。
信じたい、救われたい、誰かに決めてほしい——その気持ちがある限り、「トリックを暴く」だけでは終わらないし、終われない。だから最終章で奈緒子のルーツに触れて、「疑う側の主人公」すら揺らぐ形にする。視聴後に残るのは答えよりも、“揺れ”そのものなんだと思う。
シーズン1の黒門島(縦軸)だけ追える「縦糸まとめ」

シーズン1の黒門島は、単発の“村事件”というより「奈緒子のルーツ」を物語の前面に押し出す、シリーズの縦軸の起点です。
ここでは“黒門島だけ追いたい人”が最短で理解できるように、匂い→前景化→爆発の順に整理します。
縦糸が匂う回/強まる回/爆発する回(箇条書き時系列)
- 縦糸が匂う(第1〜3話:母之泉)
- 事件自体は「教祖の霊能力(透視・壁抜け)」を暴く章なのに、ラストに向けて奈緒子の父(剛三)に繋がる“不穏な匂い”が差し込まれる。ここが“縦軸の第一声”。
- 縦糸が強まる(第4〜8話:宝女子村〜千里眼)
- 第4〜5話(宝女子村):村の消失トリックの裏で、ミラクル三井と剛三の因縁が語られ、奈緒子の“父”が単なる設定ではなくなる。
- 第8話(千里眼):単発回ながら「当てるより、当てさせる」詐欺の構図が濃い。ここで“霊能力”が、笑い話では済まない現実の顔を見せる。
- 縦糸が爆発する(第9〜10話:黒門島)
- 第9話:奈緒子の元に「父・剛三の名を語る男」から電話→差出人不明の手紙→封筒から浮かぶ住所→黒津兄弟と接触。物語が一気に“奈緒子の側”へ折れ曲がる。
- 最終話(第10話):上田が里見から「奈緒子に霊能力があり、その力で剛三が死んだ」と聞かされる一方、奈緒子は黒門島で婚礼儀式「アナアキー」に巻き込まれていく。縦糸=“出自と罪悪感”が物語の中心に来る。
キーワード索引(父/母/島/儀式/封印…など)
黒門島まわりだけ追うなら、最低限この単語を押さえると早いです。
- 山田剛三(父):奈緒子の父。第9話から“死の真相”が事件として立ち上がる。
- 山田里見(母):上田に“奈緒子の霊能力”を告げる人物。ギャグ枠に見えて縦軸の当事者。
- 黒門島:最終章の舞台。奈緒子のルーツが触れられる“島”。
- 黒津兄弟:奈緒子を島へ導く兄弟。第9話で接触が始まる。
- 霊能力:作中では基本“暴かれる側”だが、黒門島では奈緒子自身に絡んでくる。
- 儀式(アナアキー):最終話で行われる婚礼の儀式。コメディと不穏の混ざり方が象徴的。
- カミヌーリ:黒門島に連なる霊媒師(シャーマン)系のキーワード。黒門島章で奈緒子は“血とルーツ”を知る。
- 封印(=禁忌・秘匿のニュアンス):黒門島は“言ってはいけない/触れてはいけない”が空気として流れる。縦軸の語彙として後のシリーズでも効いてくるタイプ。
超能力者についてはこちら↓

シーズン2以降に“どう効いてくるか”
黒門島が効いてくるのは、「黒門島事件が終わったか」ではなく、“奈緒子は何者なのか?”が、シリーズの根っこに残ったことです。
黒門島の章で語られる“霊能力”や“ルーツ(カミヌーリの血)”は、以降の作品で「本物なのか/作中の誰がどう利用しているのか」という形で、節目ごとに再点火しやすい“火種”になる。
さらに、母・里見の背景自体が「黒門島に代々伝わる霊媒師・カミヌーリの家系」として語られることもあり、縦軸は“島の事件”ではなく“山田家”の物語として広がっていく。
シーズン2についてはこちら↓

TRICK/トリックシーズン1の全体の結末

結末をひと言で言うなら、シーズン1は「事件を解決して終わる」よりも、奈緒子というキャラクターの“底”が見えてしまうところで終わるシーズンです。
章ごとに“超常現象の正体”を暴いてきたのに、最後だけは「暴ききれないもの」が残る。ここが、シーズン1をただの痛快ミステリーで終わらせない決定打になっています。
最終章「黒門島」=シリーズ初の“出自ミステリー”
第9話で奈緒子を動かしたのは、父の名を語る電話と、差出人不明の手紙。
第10話では、上田が里見から“霊能力”の話を聞かされ、奈緒子側では黒門島で婚礼の儀式が進む。
ここまでで、シーズン1の“着地地点”が見えるんです。つまり、最終章は「島のトリック」を暴く話である前に、奈緒子の過去(父の死、母の背景、本人の資質)に触れざるを得ない話になっている。
DVD収録内容の紹介でも、黒門島編は「父親の不審な死」「母親の過去」「奈緒子自身の生い立ち」に迫る章として説明されています。
すべてが“確定”しないラストが、むしろ強烈
公式系のあらすじが提示するのは「奈緒子には霊能力がある」という“言葉”と、黒門島で儀式が行われるという“状況”まで。そこから先、視聴者が感じるのは「結局、本当はどうだったの?」という、答えの出ないざらつきです。
実際、視聴者ブログでは「奈緒子に霊能力があるのかないのか」「父殺しの真相も本当のところはわからない」といった“割り切れなさ”が語られています。
この曖昧さは、逃げじゃなくて、たぶん意地悪なまでの“美学”。「トリックを暴く」ドラマが、最後に「暴けないもの」を置いていくことで、世界観が一段深くなる。エンディングが鬼束ちひろ「月光」なのも、やけに刺さるんですよね。
シーズン1からシーズン2に繋がること

シーズン1は最終章で“奈緒子の奥”に触れつつも、物語自体は大きな連続劇のように次シーズンへ直結していくタイプではありません。とはいえ、確実に「シーズン2で効いてくる地盤」は作っています。
シーズン2は、その地盤の上に“いつものトリック暴き”をもう一段スケールアップして積み上げていく形です。
上田が「権威」になっている=シーズン1の実績の延長線
シーズン2第1話のあらすじでは、上田が「今や超常現象に関して権威的存在」として依頼を受ける、と説明されています。
これって、シーズン1で上田が“挑戦状”を掲げ、奈緒子と組んで次々と事件を解決してきたからこその状態変化。つまり、シーズン1は「コンビ結成のシーズン」であると同時に、上田が“看板”になるための助走でもあるわけです。
奈緒子の「未解決」が、シリーズを縦に貫く
黒門島編で提示された“霊能力”や“父の死”の重さは、シーズンをまたいで残るタイプの余韻です。
作品の特徴としても、「本物に見える存在がいて苦味が残る」傾向が触れられているので、視聴者としては「次のシーズンで、あれはどう扱われるんだろう?」という期待(というか不安)が自然に生まれます。
“同じフォーマット”なのに、空気が少し変わるサイン
音楽面で見ると、シーズン1のエンディングが「月光」なのに対して、シーズン2では「流星群」へ変わるとされています。
もちろん曲が変わったからドラマが別物になるわけじゃない。でも、あの最終章の後味を経たうえでシーズン2に入ると、同じ“トリック暴き”でも、どこかに「割り切れないものを抱えたまま走る感じ」が混ざって見えてくる。ここが「トリック」を長寿シリーズにした理由の一つだと思います。
トリックのシーズン2についてはこちら↓

TRICK/トリックシーズン1の感想

シーズン1の面白さは、毎回トリックを暴いてスッキリする…だけじゃなく、「暴いたあとに、嫌な気分が残る」ところにあると思います。
実際、シリーズ自体も“笑わせる演出が多用される一方で、その中に伏線が含まれることがある”と説明されていて、単なるおふざけでは終わらせない作りが最初から明言されている。
章立てが“味変”として機能している
シーズン1は全10話なのに、事件のタイプがきっちり変わる。宗教団体に潜り込む「母之泉」、村ごと消える「まるごと消えた村」、見えない凶器で殺す「パントマイム」、単発の「千里眼」、そして奈緒子の出自へ踏み込む「黒門島」。
この配列が上手くて、視聴者が慣れてきたタイミングで「今度は質の違う怖さ」をぶつけてくる。慣れさせてから裏切るから、トリックが決まる。
“笑い”は安心ではなく、恐怖の増幅装置
TRICKのギャグって、単に緩めるためのクッションじゃないんですよね。笑いが入ることで、視聴者は一度、事件の怖さから目をそらす。そこで次の瞬間に不穏が刺さると、反動で倍怖い。
しかも小ネタや言葉遊びが、後で思い返すとヒントだったりする。視聴者は「笑ってたのに、そこ見とけってことかよ」と悔しくなる。こういう作りが、シーズン1の中毒性の正体だと思います。
奈緒子×上田は“名コンビ”というより“相互利用の同盟”から始まる
シーズン1の二人は、まだ美しい相棒じゃない。奈緒子は貧乏で、上田は理屈っぽくてプライドが高い。互いに利用し合い、舌打ちし合い、でも現場では背中を預けざるを得ない。
この“仲が良いわけじゃないのに離れられない距離”が、事件以上に面白い。トリックを暴くのは頭脳戦だけど、コンビが育つのは感情戦で、こっちの方が視聴者の記憶に残る。
最終章で「事件」が「家族」へすり替わる瞬間が強烈
終盤の黒門島編で、物語は「外側の怪異」から「奈緒子の内側の傷」へ寄っていく。ここで、シーズン1がただの連続事件簿じゃなくなる。
父の死、母の過去、自分の血──この“逃げ場のないテーマ”を最終章に置いたことで、視聴者はトリックの快感だけでは帰れなくなる。解決しても癒えないものがある、という余韻を抱えたまま次のシーズンへ行きたくなる作りは、シリーズの第一作として本当に強いです。
総じてシーズン1は、「超常現象は嘘だ」と言い切るための物語に見せて、実は“人間が嘘を必要とする瞬間”を描いているシーズンだと思います。暴く側が正しくても、暴かれた側が救われるとは限らない。その苦味まで含めて、TRICKはクセになる。
TRICK/トリックシーズン1のよくある質問(FAQ)
最後に、検索でよく踏まれる疑問を“短く・迷子にならないように”まとめます。
- シーズン1だけで完結する?
-
事件(章)は基本的に各回で解決するので、シーズン1だけでも楽しめます。ただし最終章「黒門島」は“奈緒子の出自”に踏み込むため、ここを「余韻」として受け取るか「続きが気になる導線」として受け取るかで、体感が変わります。
- トリックは怖い?コメディ?
-
どっちもです。下ネタや小ネタで笑わせながら、パントマイム章のように「目撃があるほど怖い」話をぶつけてくる。笑いの温度が高いぶん、不穏が刺さるタイプの作品です。
- シーズン1の黒門島編だけ見ても分かる?
-
黒門島(9〜10話)だけでも“事件”としては追えます。ただ、黒門島が刺さる理由は「奈緒子×上田の積み上げ」と「霊能力を暴いてきたシリーズの文脈」があってこそ。最短でも、母之泉(1〜3話)→黒門島(9〜10話)を押さえるのがおすすめです。
- 結局“本物の霊能力者”はいるの?
-
シーズン1の基本は「超常現象はトリックで説明される」側。でも黒門島では“霊能力の血筋(カミヌーリ)”が語られ、奈緒子自身が揺らぐ。つまり結論は「断言しない作り」で、その曖昧さ自体が作品の狙いです。
トリックの関連記事
シーズン3についてはこちら↓

トリックの考察について↓
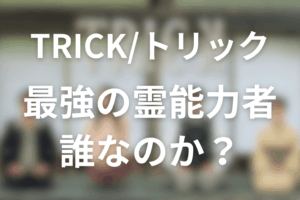


コメント