僕たちがやりました6話は、物語の空気が決定的に変わる回です。
身代わり犯人の出頭によって事件が“終わったかのように”見え、トビオたちは一度は元の生活に戻ります。カラオケに行き、卓球をし、笑うこともできる――それなのに、トビオだけがその幸福を受け入れられない。
担任・立花菜摘の思惑、パイセンの父・輪島宗十郎という巨大な影、そして刑事・飯室の冷たい言葉。6話は、逃げ続けてきた青春が「逃げられない罪」と真正面からぶつかる回でした。
軽いノリで始まった物語が、ここから“生きて苦しむ覚悟”を問うドラマへと反転していきます。
ドラマ「僕たちがやりました(僕やり)」6話のあらすじ&ネタバレ
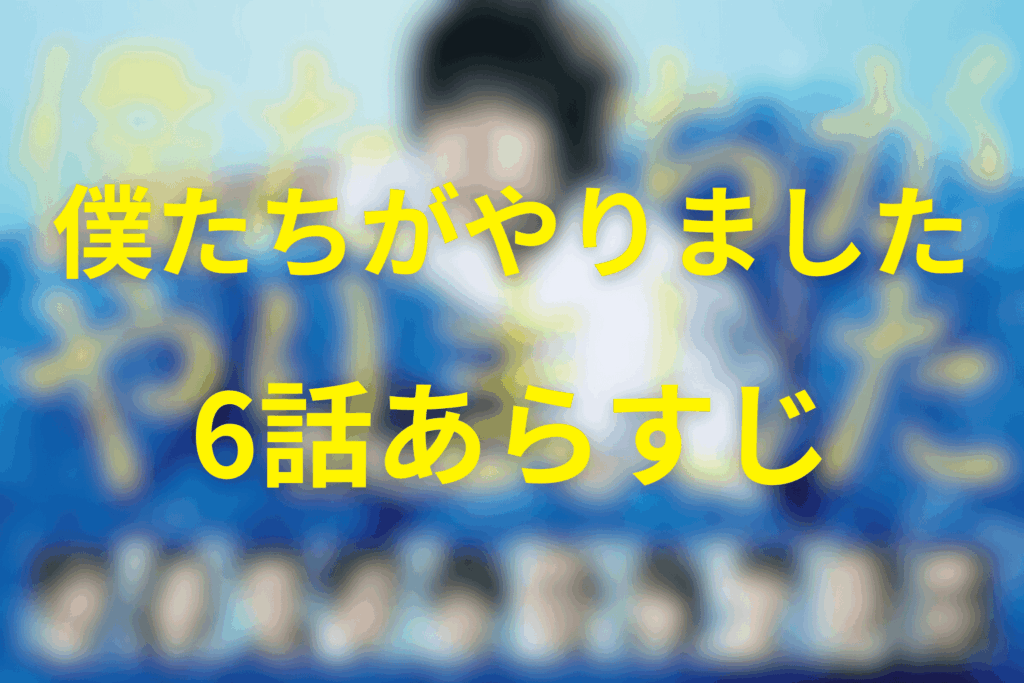
第6話は、身代わり犯人の出頭によって“日常”を取り戻したかに見えたトビオたちが、そこから本当の地獄へと足を踏み入れていく一時間でした。
担任・立花菜摘の“もう一つの顔”と、闇社会のドン・輪島宗十郎につながるパイセンの出自。さらに刑事・飯室の冷酷な一言が、トビオを屋上からの“ジャンプ”へと追い込む——軽やかだった逃避行は、ここで一気に贖罪劇へと反転します。物語のカギを整理しながら、時系列で丁寧に辿っていきます。
「替え玉」で戻った“そこそこな日常”——四人の再会
矢波高爆破事件に「自分が犯人だ」と名乗る男・真中幹男が出頭し、勾留されていたパイセン(小坂秀郎)が保釈されます。肩の荷が下りたトビオ、マル、伊佐美は、カラオケや卓球でハメを外し、逃亡の傷も忘れたかのように“そこそこ幸せ”な日常へ舞い戻ります。
ただし再会の空気は均一ではありません。罪悪感の色が濃いトビオに対し、マルは事件を武勇伝のように語り、伊佐美は「早く忘れたい」と現実への復帰を急ぐ。
第6話の冒頭は、この“軽さ”が後半の落差を最大化するための、意図的な助走になっています。
立花菜摘、協力金と“お誘い”——隠しマイクは即バレ
一方、担任の立花菜摘は、輪島の顧問弁護士・西塚から“協力の礼”として金を受け取り、パイセンをディナーに誘います。ここが、彼女のグレーな立ち位置が見え始める起点です。
パイセンは得意げに隠しカメラと無線マイクを仕込み、別室のトビオたちに生配信する計画を立てますが、菜摘は即座に機材に気づき、逆に主導権を握ります。そして彼女は、パイセンの父が輪島宗十郎であること、自分が輪島への復讐を狙っていることを、あえて本人に明かすのです。
第6話はここで、「教師=味方」という前提を完全に崩し、菜摘を“もう一つの復讐線”の推進役として再配置します。
「父の名」と「復讐の動機」——輪島宗十郎という巨大な影
輪島宗十郎は、政財界にも顔の利く闇社会のドン。
パイセンが「金でどうにかなる」と信じてきた背景には、父の権威と札束があります。一方で、菜摘の過去に輪島が関与している可能性も強く示唆され、彼女の行動は正義と復讐の境界を曖昧にしていきます。
この回で視聴者は、「味方のフリをする敵」「敵のフリをする味方」という構図に翻弄されることになります。さらに刑事・飯室も輪島に接触を図り、替え玉出頭の真偽を独自に追い詰めていく。捜査線と裏社会線が、第6話で一気に交錯しました。
フットサル場の“暴露大会”——身代わりの正体と、四人の分裂
中盤、フットサル場での“暴露大会”によって、身代わり犯人が替え玉であるという現実がトビオたちに突きつけられます。軽口で誤魔化していた空気は一変し、4人は再びそれぞれ別の方向へと散っていく。
マルは相変わらず日常へ戻ろうとし、伊佐美は「忘れるための前進」を選ぶ。
一方でトビオだけが、その輪に同調できない。第6話は「同じ罪でも、引き受け方はまったく違う」というテーマを、4人の分裂という形で視覚化していました。
飯室の“呪い”——「一生苦しめ」と“被害者の顔”
終盤、4人の前に現れた飯室は、淡々と告げます。
「俺のように真実を知ってるやつがいる」
「お前らが殺した人間の顔を伝えに来た」
「生きていく中で幸せを感じるたびに思い出せ。一生苦しめ」
正論でありながら、内面に釘を打ち込むような言葉。この一言が、トビオの心に決定的な“呪い”として残ったことは明白でした。
ラスト——「幸せが気持ち悪い」:トビオ、屋上からのジャンプ
そしてラスト。トビオは「幸せが気持ち悪い」と吐き捨て、学校の屋上から飛び降りる——視聴者の呼吸が止まる瞬間です。
替え玉による偽りの平穏が完全に砕け散り、トビオだけが“別の位相”へ移動してしまう。
このジャンプは、単なる衝撃演出ではなく、物語のフェーズが逃避から贖罪へ切り替わった合図でした。第6話は、シリーズ全体の方向性を決定づける転換点として、強烈な爪痕を残しています。
ドラマ「僕たちがやりました(僕やり)」6話の感想&考察
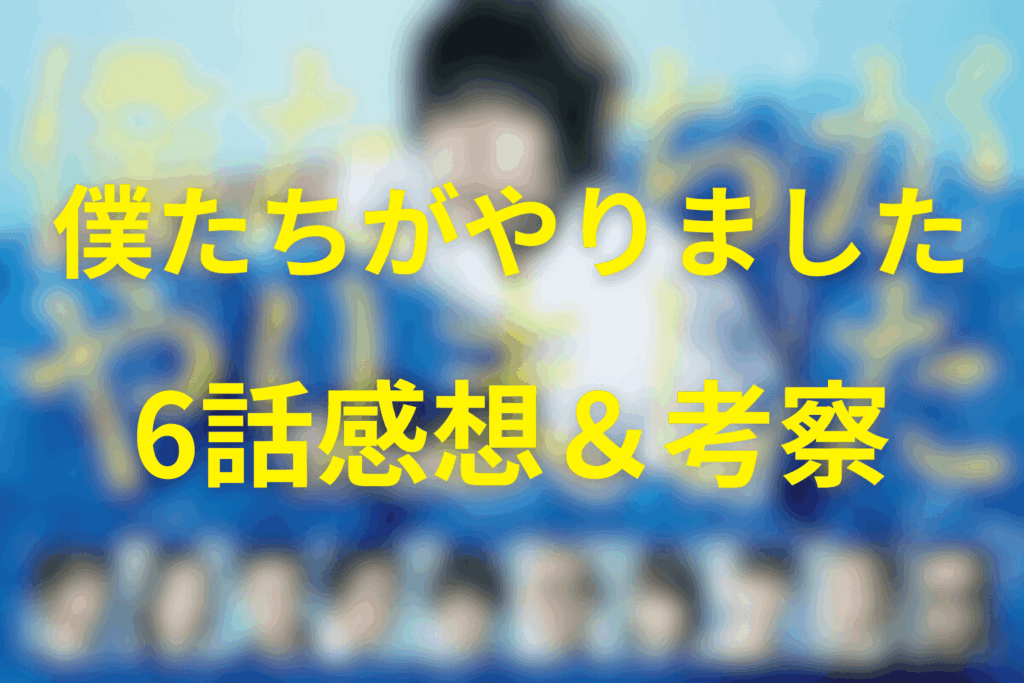
第6話は、シリーズの明確な“反転点”です。ここから物語は、「逃げ足の速い青春劇」から「逃げられない良心のドラマ」へと舵を切ります。以下、論点を三つに分けて整理します。
“幸福アレルギー”としての罪悪感——トビオのジャンプは衝動か、意志か
トビオの「幸せが気持ち悪い」という言葉は、心理的に見れば“認知の不協和”の極点です。
「人を殺したかもしれない」という現実と、目の前の“そこそこ楽しい日常”は、同時に成立しない。そのズレに耐えきれず、彼が選んだのが“身体を使った極端な選択”——屋上からのジャンプでした。
重要なのは、トビオが「死にたい」と明確に言っていない点です。彼が無意識に望んでいたのは、“終わり”ではなく“切り替え”だった。
制作側がこのジャンプを「新しい自分に切り替わるスイッチ」と位置づけたのは妥当で、以降のトビオが「生きて苦しむ覚悟」へ向かうための、倫理的な再起動として機能しています。
この行為は自己破壊ではなく、自己否定を引き受けたうえでの“再スタート”だと読むことができます。
立花菜摘という“二枚舌の正義”——信頼の裏返しが生む推進力
立花菜摘は、「味方だと思っていた大人」が、別の動機を抱えていたという反転装置です。
第6話で彼女が、パイセンの父=輪島の存在と、自身の“復讐”を明かした瞬間、物語は一気にスケールを拡張します。爆破事件という“一つの罪”から、過去の加害と現在の隠蔽を含む“複数の罪”へ。
興味深いのは、菜摘の正義が常に倫理的にグレーな手段を伴っている点です。
協力金の受け取り、盗撮の即看破と主導権奪取、輪島への直接接触——彼女の行動は、「正義もまた暴力になり得る」というテーゼを、理屈ではなく行動で示しています。
菜摘は物語を前に進める“エンジン”であると同時に、最も危うい存在でもある。その二面性が、第6話以降の不穏さを決定づけました。
飯室の台詞の設計——「一生苦しめ」は、視聴者への呪詛でもある
飯室の「一生苦しめ」という言葉は、作中ではトビオへの宣告ですが、メタ的には視聴者への呪詛でもあります。
逃げ切ったと思った瞬間に、「罪は物理的に逃げても、心理的には終わらない」と突きつける。この冷たい正論は、物語のテンポを一気に凍らせ、逃避行にブレーキをかけました。
正しいことを、感情を削いだ温度で言う——その“正論の暴力性”が、これほど機能する台詞も珍しい。
飯室というキャラクターは、善悪の判断者ではなく、「逃げ切り幻想を壊す装置」として、この回で最大限の効果を発揮しています。
余談的考察:四人の“ズレ”は、倫理のポジショニングマップ
第6話で四人が再び分散する構図は、そのまま倫理のポジショニングマップになっています。
- マル:自己正当化と忘却へ最速で向かう快楽主義
- 伊佐美:忘れるために前へ進む自己防衛(のちに贖罪へ傾く芽も見える)
- パイセン:父の権威と金で現実を上書きする特権の罠
- トビオ:幸福アレルギーに耐え切れず、身体で倫理を再起動する存在
このズレが、次話以降の友情・裏切り・和解の振幅を生み、とりわけトビオの物語を“逃避”から“向き合い”へ押し上げていきます。
画作りについて:コメディから贖罪へ——トーンの反転
序盤のカラオケや卓球の軽さ、隠しカメラのバカバカしい笑いは、ラストのジャンプの冷気を最大化するための対比でした。
編集は意図的にテンポを落とし、夜の校舎の無機質な静けさへ移行。音楽も抑制され、トビオの「幸せが気持ち悪い」という独白が、ほぼ真空の中に響きます。
この“トーンの反転”を第6話でやり切ったからこそ、第7話以降のトビオの変化に説得力が生まれました。
立花菜摘の“正義”はどこへ行くのか
菜摘は「復讐のために真実を利用する人」です。
教師という“守る役割”と、復讐者という“壊す役割”を同時に生きる二重性が、物語の不穏を増幅させます。
第6話時点での私の読みはこうです。菜摘の正義は、輪島を倒すためなら手段を選ばない実利主義。
その危うさが、トビオの「生きて償う」倫理と衝突する未来への伏線になっている。第6話の仕掛けは、そこまで含めて非常に巧妙でした。
総括
第6話は、物語の“良心”を視聴者に返してくる回です。
替え玉という、大人のシステムが用意した偽りの平穏を、トビオの身体が拒否する。あのジャンプは、逃避の否定であり、倫理の再起動スイッチでした。
ここから、笑いは痛みに変わり、逃げは向き合いへと反転する。『僕たちがやりました』という作品の価値を決定づけた転回点として、第6話は非常に高く評価したい回です。
ドラマ『僕たちがやりました』の関連記事
次回以降の記事についてはこちら↓

過去の記事についてはこちら↓
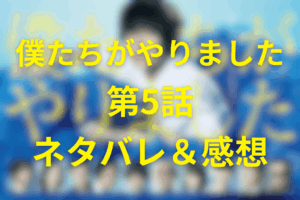
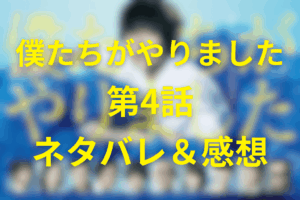
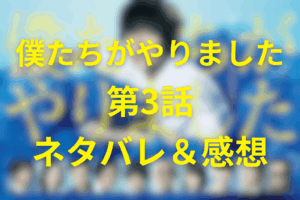
ドラマの豪華キャスト陣については以下記事を参照してくださいね。

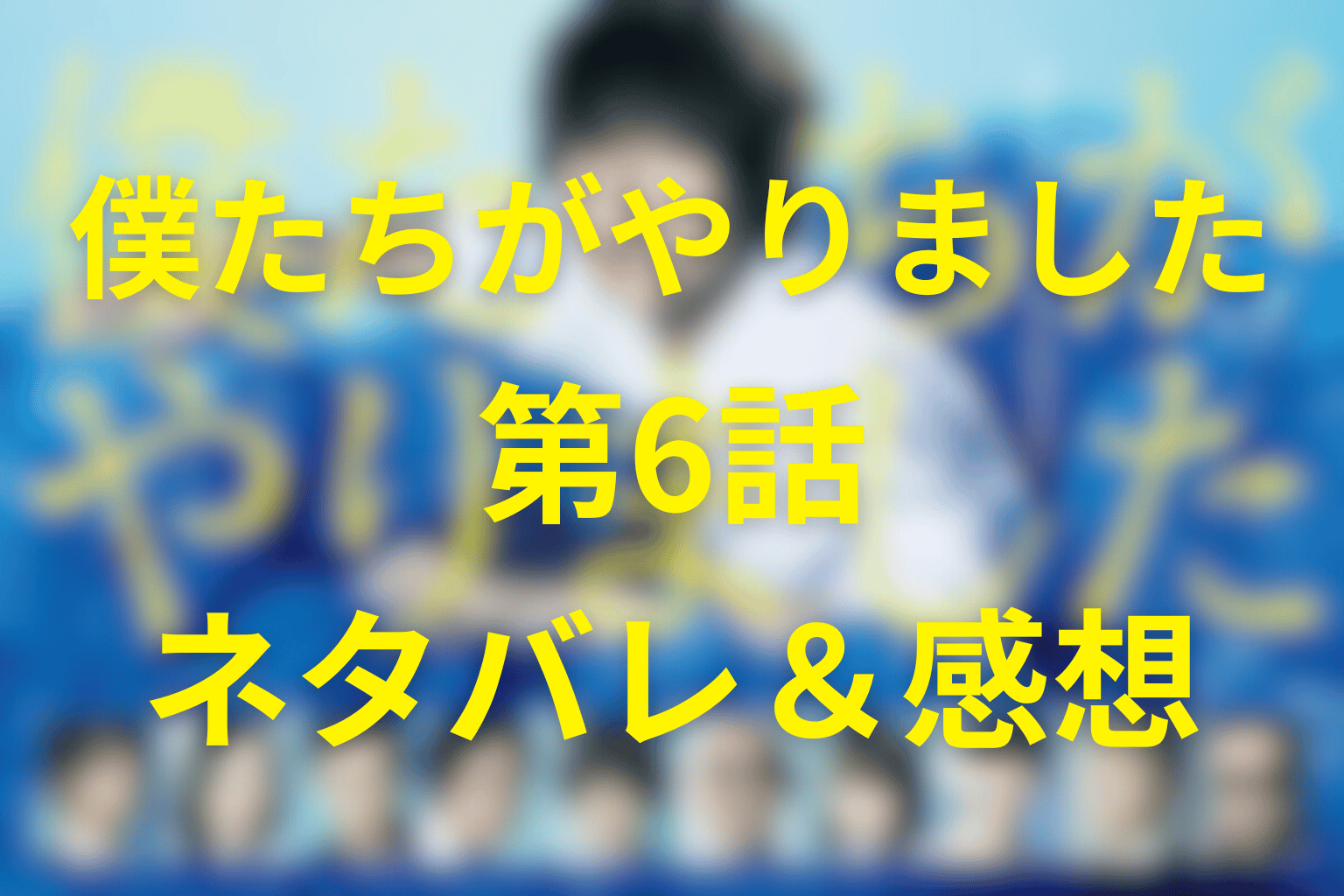
コメント