母の死の真相が明らかになり、父・恵一(長谷川博己)と子どもたちの間に決定的な亀裂が走った第3話。

阿須田家はバラバラに散り、誰もが「家族」という言葉を口にできなくなっていた。
そんな中、第4話で響くのは、三田灯(松嶋菜々子)の冷たい一言――「あなたの愛娘を誘拐しました」。それは恐怖の告白ではなく、ひとりの少女の「家族をもう一度取り戻したい」という願いを代弁する言葉だった。
希衣(本田望結)の小さな依頼を起点に、再び同じ屋根の下に集う阿須田家。“誘拐”という手段を通して描かれるのは、血よりも言葉、正しさよりも“生き直す選択”。
第4話は、家族の再起動をめぐる静かな奇跡の物語だ。
家政婦のミタ4話のあらすじ&ネタバレ
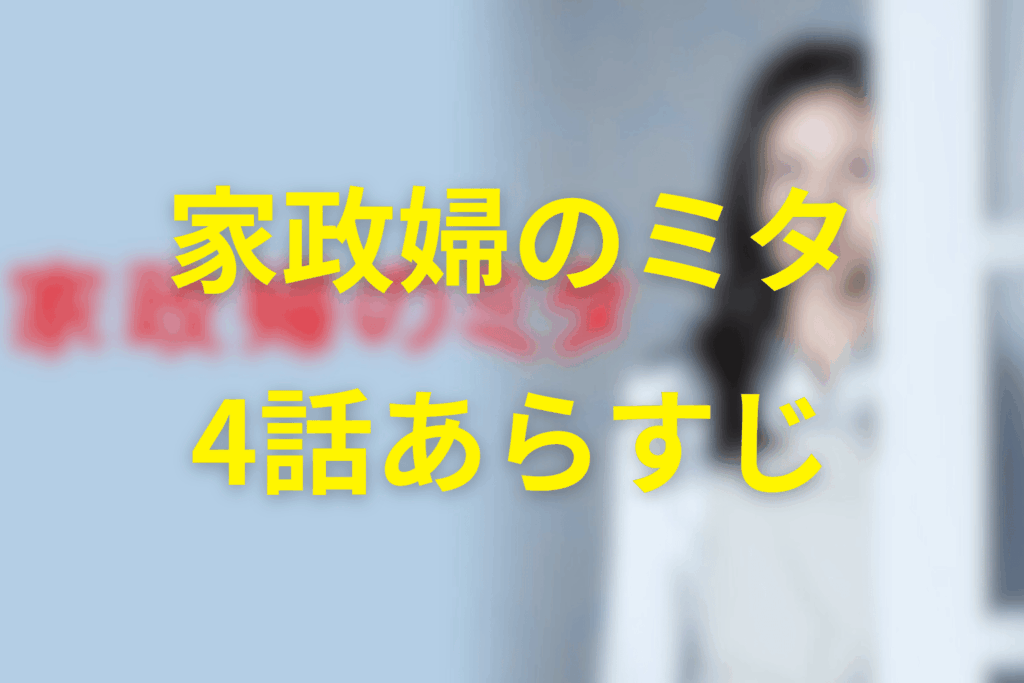
うららへの告白、会社での降格――家の外でも崩れていく父
第3話で“母の死は父の不倫が原因の自殺だった”と知った阿須田家の子どもたちは家を出て、父・恵一はひとり取り残される。朝になっても、三田灯はいつも通り台所に立ち、無言で作業を進める。その背中には、恵一の孤独だけが濃く響く。
恵一は妹・結城うらら(相武紗季)に電話し、ついに真相を告白。「事故じゃない。自殺なんだ」。うららは子どもたちを自宅で保護しつつ、当面は恵一に伏せると約束する。会社ではプロジェクト責任者を外され、モデルルームの受付へ“左遷”される恵一。
かつての不倫相手・風間美枝にすがるも、彼女はきっぱりと拒絶。家庭でも社会でも、彼の居場所は砂のように崩れていく。
近所の皆川(佐藤仁美)は、幼稚園で「あの家政婦はクビになった」と噂を広め、壊れかけた家族に追い打ちをかける。
「仲直りして」――希衣、5時間だけ三田を“雇う”
家を恋しがる次女・希衣(本田望結)は、うららからお金を借りて三田を5時間だけ雇用する。依頼はただひとつ――「家族を仲直りさせるために、みんなで会えるようにして」。この依頼を受け、三田は冷静に、しかし確実に“段取り”を開始する。
ほどなく恵一の携帯が鳴る。「あなたの愛娘を誘拐しました」。発信者は三田。すぐに「希衣さんに雇われました」と付け加えるため“狂言”であることは明白だが、この言葉が離散した家族を再び同じ場所に引き寄せる強いトリガーとなる。
阿須田家に再集合――ベランダの手すりで揺れる“命”
帰宅した恵一と、うららの家から駆け戻った結・翔・海斗。全員が居間にそろった瞬間、希衣はベランダの手すりに腰掛け、「みんなが仲直りしてくれないと、ここから落ちて死ぬ」と宣言する。
駆け寄る兄姉。言葉を失う父。幼い彼女にとって“死”は脅しではなく、「もう一度家族で生きたい」という最小単位の祈りだった。
そのとき、希衣が大切にしていた小さな缶が手から滑り落ちる。中には“家族の小石”。身を乗り出した希衣がバランスを崩して転落――間一髪で三田が抱きとめる。ヒーロー的な高揚を拒むように、三田はただ希衣を居間へ戻し、何事もなかったかのように座らせた。
「出ていってくれないかな」――家族の主語が立つ夜
再会はしたものの、仲直りは遠い。祖父・結城義之(平泉成)は、荷物を取りに来た結のバッグから“遺書”を見つけ激昂し、恵一の胸倉をつかむ。子どもたちは口々に父を非難し、ついに「そっちが出てってくれないかな」と家からの“退去”を宣言。恵一は石のように沈黙したあと、荷をまとめて玄関へ向かう。
このとき三田は、希衣が探していた“お父さんの石”を恵一へ差し出し、静かに告げる。「子どもが悪いことをしたなら、叱るのは当然です。あなたが、父親なら」。それは当意即妙の“正論”ではなく、父であることの最低基準をたった一行で突きつける言葉だった。
恵一は家を出る前、扉の向こうへ問いかける。「お父さんのこと、好きか?」――希衣は小さな声で「大好きだよ」。しかし恵一は「わからない」と答えてしまう。甘い救済を拒むこの返答が、第4話の苦い余韻を決定づけた。
家政婦のミタ4話の感想&考察
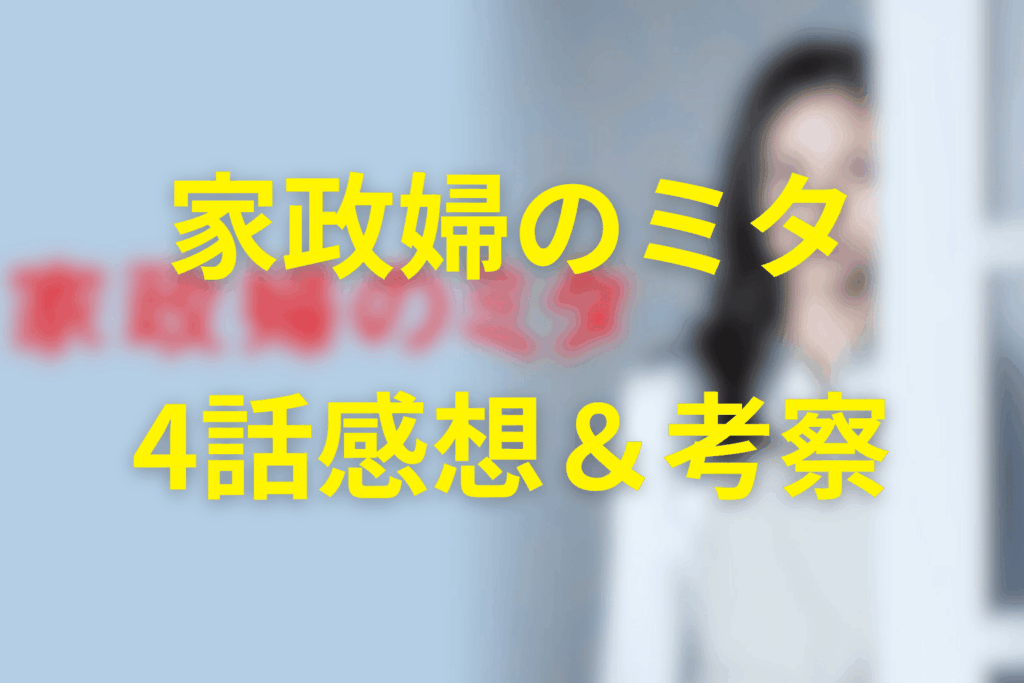
希衣の“誘拐”は、幼い祈りの翻訳
第4話のキーワードは「誘拐=翻訳」だった。希衣の“狂言誘拐”は、壊れてしまった家族に向けて、幼い彼女なりの「助けて」を大人の言語に翻訳する儀式だったように思う。
無邪気なわがままではなく、家の形をもう一度作り直すための最小限の暴力。そこに脚本の胆力と繊細さが共存していた。
希衣の“命の使い方”――「わたしを見て」ではなく「わたしたちで生きたい」
手すりの上で「仲直りしなきゃ死ぬ」と言い切った希衣は、自分の命を“家族の再起動ボタン”として差し出した。
もちろん方法としては危険だ。だがその無茶の奥には“みんなで生きたい”という健やかな欲望があり、視聴者は彼女を責めきれない。缶からこぼれた家族の小石は、阿須田家がまだ“分解可能な部品”として残っていることの比喩にも見える。壊れても、拾い集めればもう一度、別の形で組み直せる。
三田の仕事観――救わないが、命は救う
三田は“誘拐”という過激な手段を選びながらも、あくまで依頼の代行者として動く。
希衣の依頼が「みんなを会わせること」だと分かれば、淡々と装置を回すだけ。ベランダでの一件でも、彼女は“説得”せず、ただ落ちた子どもを抱きとめる。救わないのに、命は救う――この距離感こそが、三田というキャラクターの倫理を最も美しく浮かび上がらせていた。
「出ていって」の主語が変わる瞬間――家族は被害者から当事者へ
「そっちが出てってくれないかな」。結のこの一言で、阿須田家に初めて“主語=わたしたち”が立ち上がった。
誰かの加害を責めているだけの集団から、家の境界を自分たちで引き直す当事者へ。祖父の怒りや近所の噂といった“外圧”が押し寄せる中、子どもたちは家の“内側”のルールを自ら決める。その決断が、たとえ未熟でも確かな光を放っていた。
恵一の「わからない」――正直さは、ときに残酷な救済になる
希衣の「お父さんは希衣のこと好き?」に、恵一は「わからない」と答えた。父親としては最悪の返答かもしれない。
だが私はこの答えを“再生のゼロ地点”として受け止めた。嘘のやさしさを重ねてきた家だからこそ、ここで初めて嘘をやめる。好きかどうかもわからない自分を認めることは、父である前に一人の人間として立ち直るための第一歩だ。
次に「好きだ」と言える日が来るとしたら、それは彼が自分の弱さを引き受けたあとだ。ドラマが“甘くならない”ところに、強い誠実さを感じる。
三田の一言が刺さる――“叱る”は支配ではなく責任の宣言
「子どもが悪いことをしたなら、叱るのは当然です。あなたが、父親なら」。
これは単なる説教ではなく、役割の再定義だ。叱ることは支配ではなく、責任の引き受け。三田は父と子の間に“ルール”を敷き直し、感情で流れがちな議論を最低限の規範に戻してみせた。彼女の無表情は冷酷さではなく、公平さの表現なのだと思う。
“噂”の冷たさと、ドラマの温度差
幼稚園で「家政婦はクビ」と嬉々として話す近所の人。人は他人の不幸を消費してしまう。
だからこそ、このドラマは派手な断罪に向かわず、“家の中で何が起きるか”を見つめる。ベランダの風、キッチンの湯気、玄関の足音――その小さな生活音の連なりの中で、人はまた生き直せるのだと静かに証明している。
そして次回へ――“身体”に踏み込む問い
次回予告のタイトルは「全部脱いで!…承知しました」。刺激的な言葉に見えるが、ここまでの流れを踏まえると、物語はついに“身体”という最後の聖域に踏み込もうとしている。
第4話の“誘拐=翻訳”があったからこそ、次回の問いは“からだの境界”にまで届く。ドラマはなお、家族と責任のかたちを更新し続けていくはずだ。
まとめ
希衣の“狂言誘拐”は、絶望の反対語としての“希望の暴力”だった。
三田は救わない。だが命は救う。そして家族に“選び直すチャンス”だけを残して去る。
甘くないのに、温かい。だから私は、阿須田家の扉が閉まった静かな夜に、そっと深呼吸をした。あの缶の小石は、きっとまた並べ替えられる。別の秩序で、同じ家族として。
家政婦のミタの関連記事
家政婦のミタの全話ネタバレについてはこちら↓



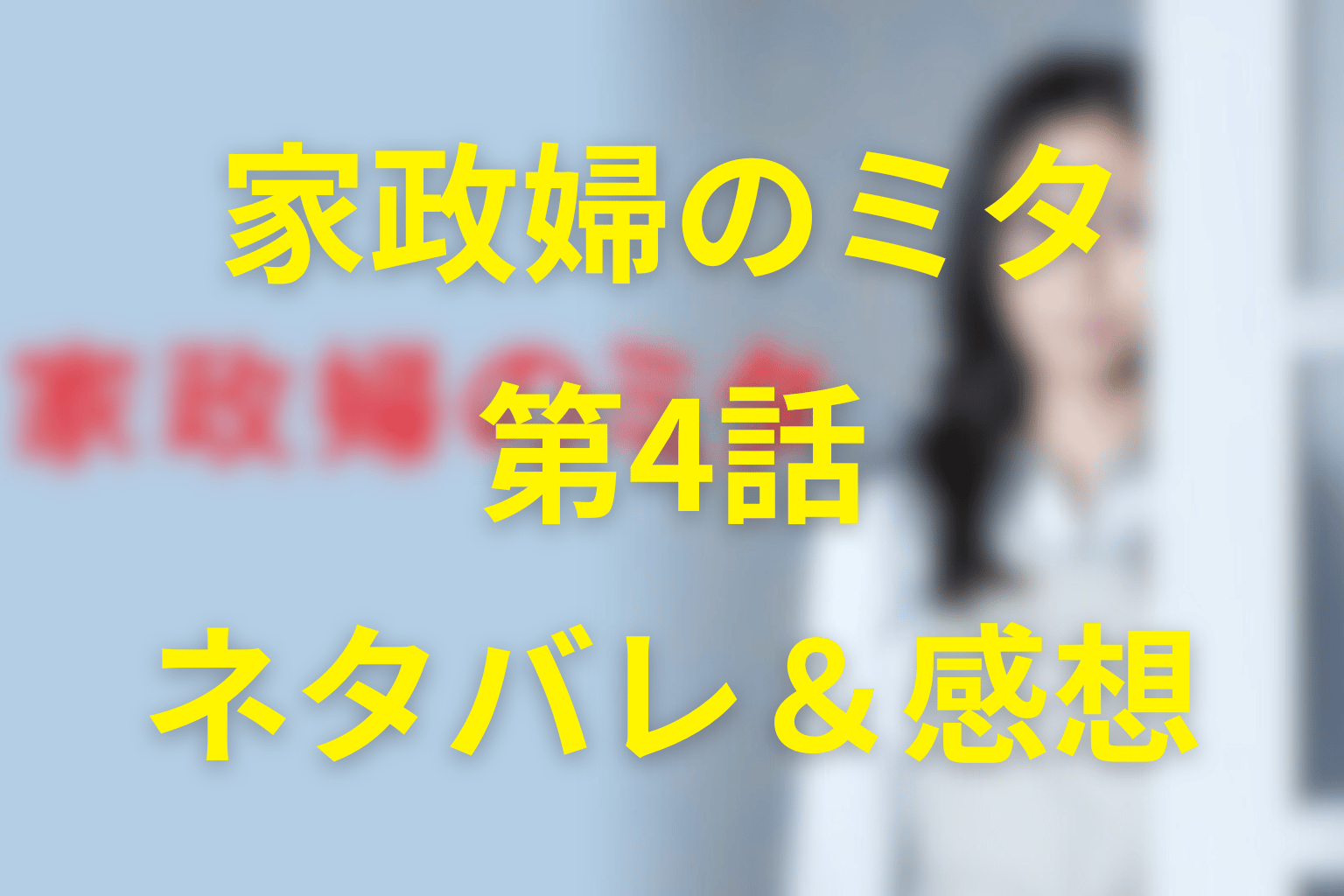
コメント