第5話までで店としての形が整い始めたグランメゾン東京に、第6話で突きつけられるのは、もっと根源的な問いです。
「その料理は、本当にお客様に出せるものなのか」。
グランメゾン東京6話「鰆のロースト 水晶文旦のソース」は、魚料理の完成を描きながら、裏切り・模倣・再起という現実的な痛みを正面から描く回。
仕事の厳しさと、戻る場所の意味が交差する一日を、丁寧に追っていきます。
グランメゾン東京6話のあらすじ&ネタババレ

第6話の核は、魚料理「鰆のロースト 水晶文旦のソース」を完成させる“メニュー開発回”…に見せかけた、芹田の「裏切り」と「帰還」を描く成長回でした。
しかもそれを、トップレストラン50という“外部評価の舞台”と、gakuという“露骨な敵”の圧力と同時に走らせる。物語の推進力が、ここで一段ギアチェンジした印象です。
祥平が「gaku」へ――チームに走る動揺と、尾花の妙な高揚
冒頭で突きつけられるのが、平古祥平が丹後のいる「gaku」に入ったという事実。
京野と相沢は戸惑いを隠せず、チームの空気にも一瞬ノイズが走ります。普通なら「裏切りだ」と感情が先に立つ場面なのに、尾花はどこか楽しそうで、“強力なライバルの出現”を歓迎しているように見える。ここが尾花らしく、同時に怖い。
この時点で視聴者の頭に浮かぶのは一つです。
「この男は、勝負の火種が増えるほど燃えるタイプだ」
そして、燃える人間がいる一方で、燃えきれない人間も生まれる。
第6話は、その“取り残される側”を丁寧に描く回でもあります。
「トップレストラン50」候補入り――魚を変える、という最短で最大の賭け
今年度のトップレストラン50の表彰式が東京で行われることが決まり、グランメゾン東京も候補に入ったと知らされます。
尾花はそれを聞くや否や、日本の食資源の代表格である“魚”を軸に、料理を開発し直すことを決断します。つまり「勝負の一皿」を、もう一度作り直す。
同じ頃、gakuでも丹後と祥平が魚料理の新メニューに取り組んでいる。
トップレストラン50という同じゴールを前に、二つの厨房が“魚”で正面衝突する構図が、ここで完成します。
人手不足と新戦力――久住栞奈がホールに入る
候補入りで客足が戻りつつある一方、店は深刻な人手不足。
そこへフードライターの久住栞奈がホールスタッフとして志願し、チームに加わります。語学力やワインの知識もあり、即戦力としては申し分ない存在に見える。
ただし、ここで京野が彼女の履歴書──特に両親の名前──に引っかかる描写が入る。
さらに栞奈は“3年前の事件”に関係があることを隠したまま入り込んでいる。この不穏さが、後半で漂い始める「内部崩壊の匂い」へと直結していきます。
芹田の鬱屈――「触るな」の一言が刺さる、置いていかれる感覚
新しいメンバーが増え、チームが形になっていくほど、逆に浮き彫りになるのが芹田の孤独です。
店の立ち上げメンバーで、誰よりも真っ直ぐで、誰よりも「料理人になりたい」という気持ちを前に出してきた。それなのに、いつまでも料理を作らせてもらえない。
忙しい厨房で手伝おうと近づいても、尾花から飛んでくるのは「触るな」の一言。
この言葉は、技術不足への警告であると同時に、芹田にとっては“存在否定”に近い響きを持つ。陰で練習し、努力している姿を視聴者は知っているからこそ、この扱いが痛い。
まかないチャーハンの惨敗――努力が“伝わらない”地獄
芹田はまかないを作らせてほしいと申し出て、チャーハンを作ります。
ところが評価は散々で、ほとんど手をつけられずに残されてしまう。
このシーンの残酷さは、「まずい」と言われることよりも、「残される」こと。
料理人にとって残されるという行為は、“会話を拒絶される”に等しい。「お前の料理は、ここではまだ届いていない」と、無言で突きつけられる瞬間です。
京野のフォロー――才能の有無より、努力を続けた先でしか見えないもの
仕事帰り、京野は芹田を飲みに誘い、「才能なんて最初から分かるものじゃない」「努力して腕を上げて初めて見えてくる」と語ります。
京野の言葉が軽くならないのは、彼自身が料理人からギャルソンへ回り、尾花を信じる側に人生を賭けた人間だから。
芹田の“自尊心の折れ方”が、手に取るように分かっている。慰めではなく、構造として支える言葉です。
鰆との出会い――魚料理「鰆のロースト 水晶文旦のソース」誕生までの地獄
尾花と倫子は、最高の魚料理を求めて豊洲へ向かい、食材として鰆を選びます。
そこからは、ひたすら“焼き”を詰める作業。最終的に辿り着くのが、鰆を大きな塊のままローストし、焼いた後に切り分ける火入れです。
香ばしさを前に出しすぎず、断面で素材の香りを楽しませる。
ソースは水晶文旦を主役に、果汁とオリーブオイル、香草、茸、少量のニンニクやセロリ、フヌイユを重ねていく。付け合わせにはラディッキオ・タルディーボやケッパー、赤ワインビネガー、フュメドポワソン。魚の繊細さを壊さないための設計が、言葉の端々からも伝わります。
根性論ではなく、設計思想で「なぜ美味いか」を語れる。
ここは料理ドラマとして、非常に気持ちのいい場面です。
芹田の“努力”が空回りする瞬間――勝手に鰆を捌き、尾花が激怒
芹田もまた、鰆の仕込みに食らいつきます。
魚を捌けるようになろうと、仕入れ先で働かせてほしいと頼み込み、陰で修行までしていた。
しかし仕込み当日、相沢が捌き始めると手伝いを断られ、相沢が席を外した隙に芹田は勝手に鰆を捌いてしまう。
尾花は激怒し、芹田が使った包丁を見て「お前はまだここで料理ができるレベルじゃない」と突き放す。
芹田にとっては、“努力を見せた瞬間”が“否定された瞬間”になる。
そりゃ折れる。こうして芹田はエプロンを投げ、店を飛び出します。
退職、そしてレシピ流出――江藤の甘い罠に自分から入る
飛び出した芹田が向かったのは、gakuのオーナー江藤のもと。
芹田は鰆料理のレシピノートを渡し、「gakuに入れてくれ」と頼みます。
しかし江藤の狙いは人材ではなく、レシピそのもの。
レシピは柿谷へ渡され、「グランメゾンの魚料理を丸パクリする」という、品のない戦術に使われます。
しかも芹田は、過去に江藤から金を受け取って内部情報を流していたことまで明らかになる。ここで“裏切り”は決定的なものとなり、第6話中盤は、視聴者の胸がずっとザワつく時間帯になります。
gaku側――コピー料理は崩壊し、結局“別の一皿”に戻る
江藤はgakuで、グランメゾン東京の鰆料理を再現させようとしますが、出来は散々。
「ただの焼き魚じゃないか」と一蹴され、採用されません。
代わりに押し出されるのが、丹後と祥平が作った“あんこう”の魚料理。
骨付きあんこうをレモンタイムとバターで焼き、鮟肝のポシェ、昆布や味噌のソースで深みを足しつつ、魚の風味を消さない設計です。
皮肉なのは、レシピを盗んでも勝てず、最後は“自分たちの料理”に戻らざるを得なかったこと。江藤の卑劣さが、結果的に「本物と模倣」の差を際立たせてしまいます。
京野の「退職金代わり」ディナー――客として食べて初めて分かる“本番の味”
コンビニ前で酒を飲む芹田の前に、京野が現れます。
退職金は払えないが、代わりにうまいものを食わせてやる。そう言って芹田を“客”としてグランメゾン東京へ招待します。
芹田はコースを食べながら気づく。
いつもの試食より、客として食べる料理のほうが、圧倒的に美味い。
京野は「試作と本番は別物」「一皿には料理人の魂がこもる」「客がいて初めて料理が完成する」と言葉にする。
叱責では届かない相手に、体験で刺す。この教え方こそ、京野の真骨頂です。
鰆が臭い――尾花の“授業”:包丁一本で料理は壊れる
食後、芹田が「鰆のロースト、試作より少し臭い気がした」と漏らすと、尾花は代金を受け取らないと言い出します。
理由は「お客様に出してはいけない料理を出してしまった」から。
実はその鰆は、芹田が捌いたもの。
しかも根菜を切った包丁で魚を捌いたため、アクや匂いが移り、風味が落ちていた。
尾花が怒った理由は精神論ではありません。
「一皿の繊細さが、包丁一本で壊れる世界だ」という現実を叩き込む授業。
芹田はここで初めて、自分の過ちを“舌で理解”します。
土下座と告白――「金もらってスパイしてました」
芹田は土下座して謝罪し、江藤から金をもらってスパイをしていたこと、鰆のレシピを渡したことまで告白します。
芹田は「レシピをパクられたら負ける」と怯えますが、尾花たちは笑う。
「このレベルの料理は、レシピだけじゃ真似できない」
相沢も京野も同じ方向を向いていて、京野は「一流の料理人はレシピ流出を気にしない」と理由まで添える。
実際、gaku側のコピーは失敗している。ここで視聴者も気づかされます。
「自分もどこかで、“レシピさえあれば”と思っていた」と。
「本物は、自分で生み出すしかない」――芹田に突きつけられる選択
尾花は芹田に問いかけます。
うちで簡単に真似できる料理なんて一つもない。三つ星を狙うなら、本物は自分で生み出すしかない。お前は、どんな料理人になりたいんだ――と。
この問答は説教ではなく、“確認”。
追い出すなら、ここで終わらせればいい。
それでも尾花は選択肢を渡し、最後は本人に決めさせる。そこに、尾花の不器用な優しさがあります。
二度目のまかない――味より“気持ち”が通る瞬間
芹田はもう一度、まかないを作らせてほしいと願い出て再挑戦します。今度は鰆も使い、前回よりも“相手を喜ばせる”方向へ寄せた料理。
萌絵は「おいしい」と言い、倫子も「味はまだでも、喜ばせようとして作ったのは伝わる」と受け止めます。
そして最後に、尾花が芹田へ言う。「片付けたら鰆の仕込み、やっとけ。仕込みはお前の仕事だろ」
許可の言葉より先に、仕事を任される。
芹田は、役割を与えられることで居場所を取り戻します。
この回の救いは、ここです。
人は、許されることで立ち上がるんじゃない。
「もう一度、役割を与えられる」ことで、前を向ける。
ラスト――トップレストラン50発表会場へ。栞奈がリンダに告げた本音
物語はトップレストラン50の発表当日へ進みます。
そこでリンダに「グランメゾン東京で働く目的」を問われた栞奈は、「尾花たちが復活するなんて許せない」と告げる。
芹田の問題が一段落した直後に、次は“内部からの火種”を投下して終わる。
第6話は、勝って終わる回ではなく、「整えた直後に、次の爆弾が落ちる回」でした。
グランメゾン東京6話の伏線

第6話は芹田の更生回としてカタルシスが強い一方で、よく見ると“次の争いの種”がかなり露骨に撒かれています。
料理面では鰆の新作が完成し、人間関係は芹田が戻って一度は整う。でも、整ったからこそ壊しやすい。第6話は、まさにそういう回でした。
伏線1:久住栞奈の履歴書、両親の名前に京野が反応した意味
栞奈が提出した履歴書を見て、京野が両親の名前に引っかかる描写が入ります。
ここが重要なのは、京野が“3年前の事件”を知る側の人間だから。つまり彼の反応は、「栞奈は偶然ここに来た人材ではない」という明確なサインです。
栞奈はホールスタッフとして非常に有能で、語学力やワインの知識も申し分ない。だからこそ厄介。
能力が高い人物ほど、内部に入り込んだときの破壊力は大きくなります。店の信用、客の評価、メディアへの露出、そのすべてに触れられる立場にいるという事実が、この先の不安をはっきり示しています。
伏線2:栞奈の「復活させるわけにはいかない」=“敵が内側にいる”確定
第6話ラストで栞奈がリンダに告げた本音は、ほぼ宣戦布告です。
これで、外からの妨害(江藤)だけでなく、内側からも崩され得ることが確定しました。
ここで怖いのは、栞奈の動機が“仕事”ではなく“感情”に近い点。
金で動く人間より、恨みで動く人間のほうが止まらない。状況次第では、江藤以上に危険な存在になり得ます。
伏線3:レシピ流出は「致命傷にならない」けど、「無傷でもない」
尾花たちは「レシピだけでは真似できない」と笑い飛ばします。実際、gaku側のコピーは失敗している。
ただし、ここを“完全勝利”と見るのは危険です。
理由は二つあります。
ひとつは、相手に「方向性」を渡してしまったこと。
食材の選び方、火入れの思想、ソースの組み立て方。完全再現はできなくても、研究の近道にはなってしまう。
もうひとつは、芹田という“穴”が露呈したこと。
江藤は「内部から崩せる」と確信したはず。次は、もっと巧妙な手で来る可能性が高い。
勝てない模倣は諦める。でも、勝てる妨害は続ける。
第6話は、その流れをはっきり示す伏線回でもあります。
伏線4:芹田の復帰と「鰆の仕込み任命」――信頼回復は“これからが本番”
尾花が芹田に鰆の仕込みを任せたのは、単なる優しさではありません。
それは「信頼」と同時に「責任」を渡した行為です。
ただし同時に、これは非常に危うい伏線でもあります。
次に何かトラブルが起きたとき、責任の矢印はまず芹田に向く。本人も「また自分のせいで…」と潰れやすい。
つまり芹田は、チームの弱点にもなり得るし、成長が進めば最大の伸びしろにもなる。第6話は、その両面を同時にセットした回でした。
伏線5:祥平がgakuにいる意味が、勝負の質を変える
祥平がgakuに入ったことで、丹後の店は単なるライバルから“強敵”へと格上げされます。
尾花がそれを楽しんでいるように見えたのも納得で、勝負の質が上がるほど、尾花の料理は研ぎ澄まされていく。
ただし祥平は、単に丹後側の戦力として終わる人物ではありません。
彼の存在は3年前の事件とも直結しているし、尾花との関係もまだ清算されていない。ライバル店にいるからこそ、過去の真相が別角度から炙り出される可能性があります。
伏線6:料理名そのものがテーマ――「素材の味を残す」=“自分の輪郭を残す”宣言
鰆の火入れについて語られる「香ばしさが前に出すぎると、何を食べているか分からなくなる」という考え方。
これは料理だけでなく、人間ドラマの比喩としても機能しています。
評価されたいから、派手な“香ばしさ=演出”に寄る。
でも寄りすぎると、“自分の味=輪郭”が消える。
最終的に残るのは、何者でもない量産型の美味しさ。
芹田の焦りも、まさにこの状態でした。
第6話は、「輪郭を残したまま戦え」というメッセージを、料理そのもので宣言している伏線回だったと言えます。
グランメゾン東京6話の感想&考察

第6話を見終わって一番残ったのは、爽快感よりも「仕事の怖さ」でした。
レシピが盗まれる、裏切りがある――そうしたドラマ的な事件も確かに起きる。でも本質はもっと地味で、もっと残酷で、もっと現実的です。
包丁一本、手順ひとつ、気の緩み一つで「お客様に出してはいけない料理」が生まれる。プロの世界は、そこから逃げられない。その現実を、真正面から突きつけてくる回でした。
芹田が刺さる理由:彼は悪人じゃなく「自分の価値が分からない若手」だから
芹田は、最初から根っこが悪い人間ではありません。
むしろ真っ直ぐで、家族のために働き、料理を天職だと信じてこの世界に飛び込んだ人物です。
でも、若手の地獄は「頑張っても結果が見えない」こと。
先輩は速いし、上手い。
自分は遅いし、足りない。
努力は見えにくい。
周囲は“天才”を基準に語る。
この状態で「触るな」と言われたら、心が折れて当然だと思います。
芹田の裏切りは許されない。でも理解はできる。第6話が上手いのは、ここを“許す物語”にせず、“立て直す物語”にした点です。
「レシピがあれば作れる」を否定する回――職人の本質は“見えない差”にある
尾花たちが言う「レシピだけじゃ真似できない」は、ただの強がりではありません。実際、gaku側のコピーは成立しなかった。
ここで感じたのは、料理に限らない普遍性です。
文章も同じで、構成案や見出しを見ても、同じ熱量や説得力の文章にはならない。
差が出るのは、
何を捨てて、何を残すか
読者の呼吸をどこで変えるか
“伝わらない部分”をどう埋めるか
そういう、見えない決断の積み重ねです。
鰆の火入れもまったく同じ。
香ばしさを出すのは簡単だけど、素材の香りを残すには、思想と実行が必要になる。
第6話は、「職人の価値は見えない差に宿る」ということを、これ以上なく分かりやすく描いていました。
尾花の厳しさは“プライド”じゃなく、“客”に向いている
尾花は口が悪いし、説明も足りないし、若手に優しくありません。それでも第6話で決定的なのは、彼が「金を受け取らない」と言い切った場面です。
普通なら、そこでごまかしたくなる。
「今日は試作だった」「たまたまだ」と言い訳もできる。
でも尾花は「出してはいけない料理を出した」と認める。
厳しさのベクトルが、スタッフの感情ではなく、お客様の体験に向いている。
ここに一流の怖さがあります。
芹田の包丁ミスを責めるのも、怒りの発散ではありません。繊細な鰆の風味が壊れることは、客の幸福が壊れることだから。プロの厳しさは、結局のところ、客への誠実さの裏返しなんだと思います。
京野がいるから、この店は折れない――“優しさの設計”ができる男
芹田を救ったのは、尾花の言葉そのものではなく、京野の段取りです。
飲みに誘う
客として食べさせる
「本番は別物」を言語化する
最後は、店に戻る導線を作る
これは情ではなく、設計。
京野は感情に寄り添いながら、ちゃんと着地を用意する。
第6話は、「厳しい天才」だけではチームが壊れることを示しつつ、「支える大人」がいるから続く、という構造を鮮やかに描いていました。
栞奈の登場で、物語は“料理の勝負”から“人間の勝負”へ広がる
第6話ラスト、栞奈がリンダに告げた本音で、空気が一気に変わります。
外の敵(江藤)だけでなく、内側にも敵がいる。これは店にとって一番怖い構図です。
ここから先の不安は、料理の出来不出来ではなく、
信用
噂
証拠のない疑い
仕込みの些細なミス
そういう“社会の嫌な部分”に移っていくはず。そしてそれを引き起こせる位置にいるのが、ホールに入った栞奈です。
第6話は、料理ドラマの皮をかぶった“信用のサスペンス”が始まる合図でもありました。
「本物」という言葉が殴ってくる回だった
第6話は、「本物」「レシピ」「真似できない」という言葉が、強く残る回です。
芹田の謝罪に対して、大人たちが簡単に揺るがない場面は、気持ちいい反面、背筋が寒くなる。
“本物”という言葉は、誰にでも刺さる。仕事でも人生でも、「じゃあお前は本物なのか?」と問われた瞬間、逃げ場がなくなる。
次回への期待:順位より「守るべきもの」が問われる
トップレストラン50の順位はもちろん気になります。
でも第6話を見た後だと、興味は順位よりも「この店が何を守るのか」に移りました。
芹田は、裏切りを越えて“職人”になれるのか。
尾花は、厳しさを“伝える力”に変えられるのか。
栞奈は、復讐を選ぶのか、それとも料理に負けるのか。
祥平と丹後のgakuは、“自分の料理”で勝てるのか。
第6話は、勝負の舞台装置を整えた回でした。
整えたからこそ、次に壊れる。
だからこそ、次が見たい。そんな終わり方でした。
グランメゾン東京の関連記事
全話のネタバレはこちら↓
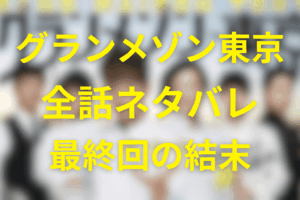
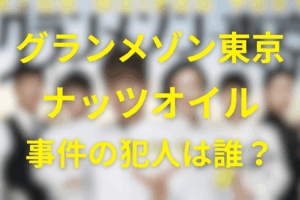
過去の記事についてはこちら↓
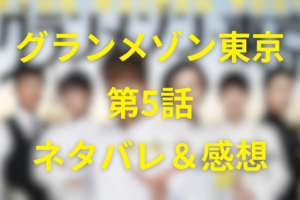
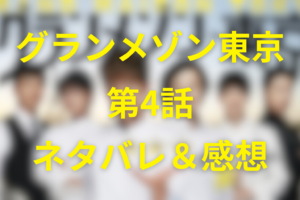
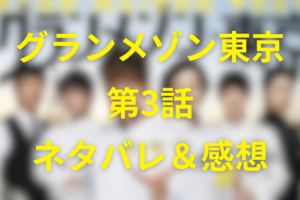
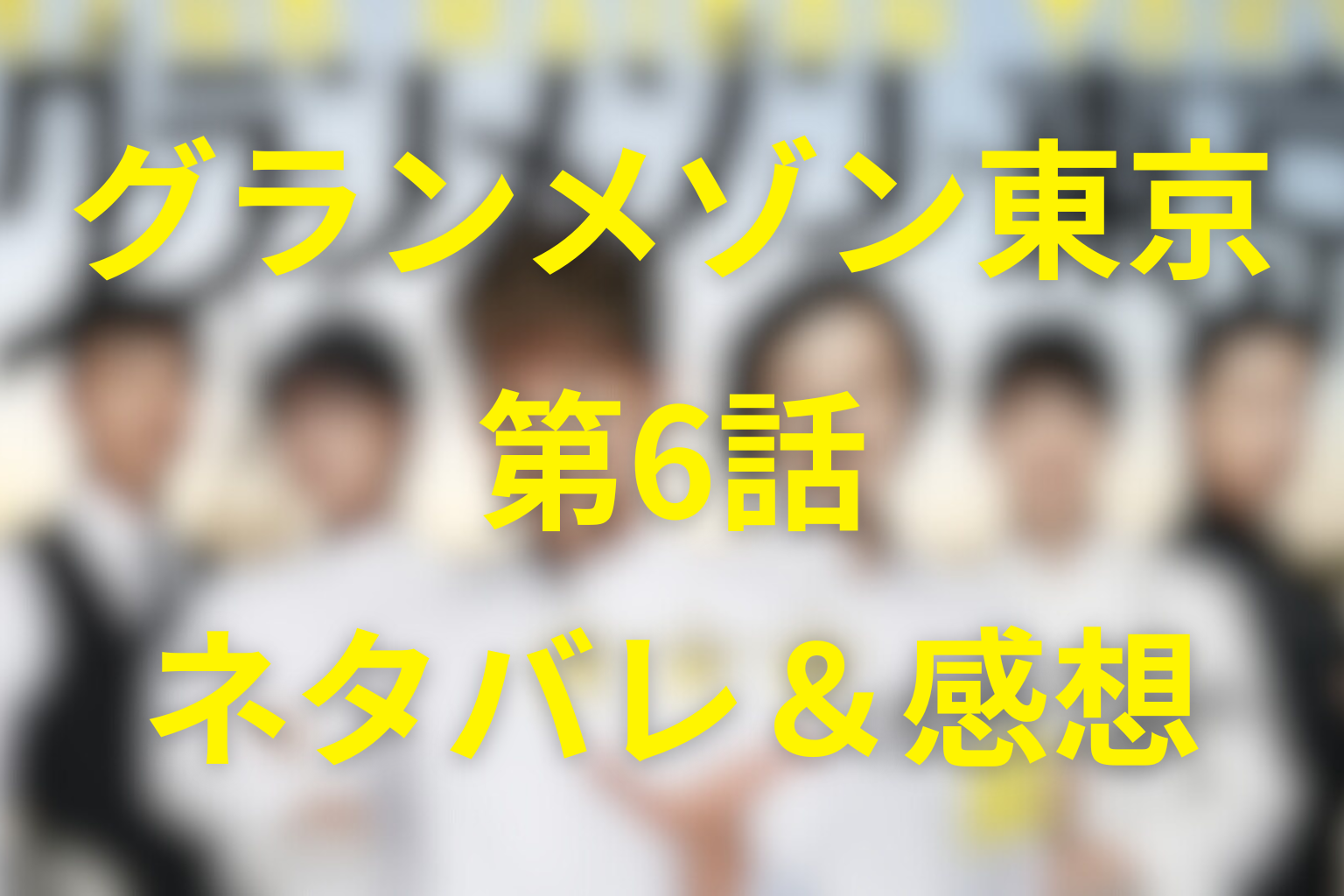
コメント