第2話で開業資金の目処が立ち、第3話で突きつけられるのは「店として、何を柱にするのか」という問いです。
ジビエ料理コンクールという勝負の場に立ちながら、グランメゾン東京は“勝つこと”よりも先に、“どう料理と向き合うか”を試されていきます。
グランメゾン東京3話「鹿肉のロティとコンソメ」は、コンクールでは負けながらも、店の骨格と覚悟がはっきりと形になる回。
この一日が、なぜ「始まり」だったのか。その意味を追っていきます。
グランメゾン東京3話のあらすじ&ネタバレ
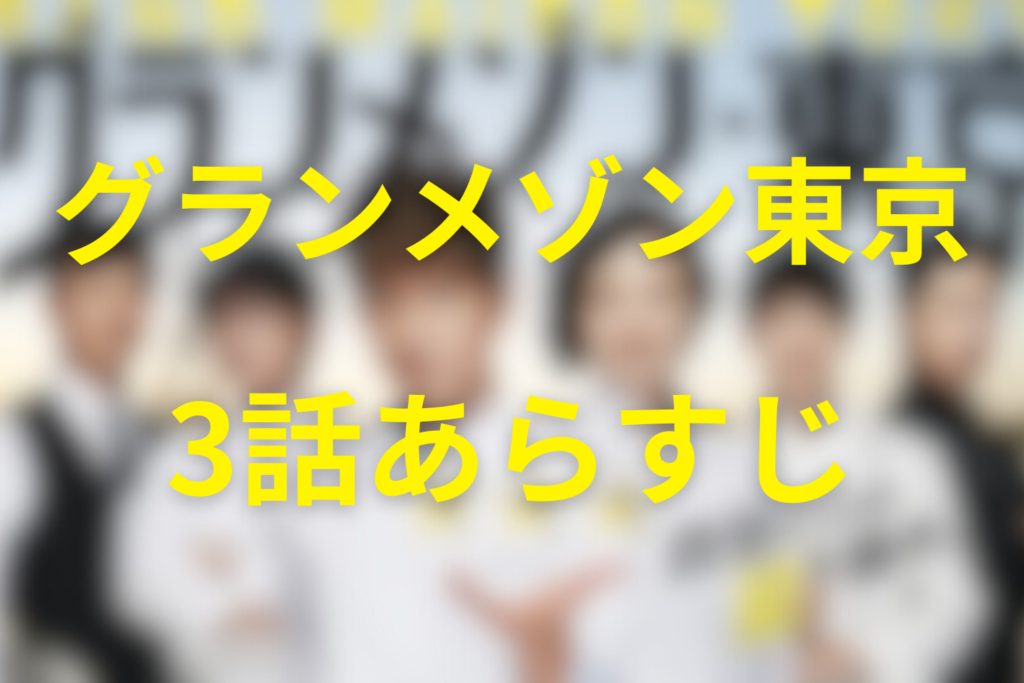
第3話のサブタイトルは「鹿肉のロティとコンソメ」。
物語としては「店の柱になる肉料理」と「プレオープン前の初バトル」が同時進行し、しかも“料理の勝負”が“人の勝負”へとすり替わっていく回です。
肉料理が決まらない――メインディッシュ迷走の沼
「グランメゾン東京」の開店に向けて、尾花(木村拓哉)と倫子(鈴木京香)は、コースの柱になる肉料理を作ろうとしますが、肝心の“納得できる食材”に出会えず、メニューが定まりません。
ここは料理ドラマとして一段ギアを上げているポイントで、才能がある、舌がいい、それだけでは前に進めない。「素材」「火入れ」「ソース」「出す文脈」まで、すべてが揃って初めて一皿になる。その前段階の迷走が、リアルで、焦りが痛いほど伝わってきます。
栞奈の持ち込み案件――“ジビエ料理コンクール”にエントリー
そんな折、京野(沢村一樹)が、フードライターの栞奈(中村アン)から情報を得ます。
それが、農水省と「マリ・クレール ダイニング」が関わる企画として行われる、鹿肉を使ったジビエ料理コンクールへの参加話。店の名前を売るには絶好の舞台で、京野はエントリーを決断します。
この時点での尾花は、最初から乗り気というわけではありません。尾花は「勝てそうな勝負」よりも、「勝つべき理由がある勝負」に燃える人間。条件が整っていない勝負には、本来そこまで食いつかない。
ところが――。
「gaku」参戦で尾花の表情が変わる
コンクール参加店の中に、丹後(尾上菊之助)が率いる「gaku」の名前があると知った瞬間、尾花のスイッチが入ります。
ここで動いているのは単なるプライドではなく、「自分が落ちた場所(過去)」と「今の自分」が直結してしまう感覚。
ライバルがいるから燃えるというより、自分の失墜がまだ終わっていないから燃える。その未完の感情が、尾花を前に押し出します。
江藤、買い占める――“勝負は厨房の外”で始まっていた
直接対決になるかと思われた矢先、gakuオーナーの江藤(手塚とおる)が動きます。
コンクールのメイン食材となる鹿の上質な部位(ロース)を市場から買い占め、グランメゾン東京に回らない状況を作る。さらに仕入れ先が京野の名前を聞いた途端に電話を切るほど、事実上の“ブラックリスト化”まで進んでいます。
江藤は、ただの嫌な人物というより、「勝ち筋を買う人」。
第3話では、彼の関西弁が“演出”として語られる場面もあり、相手との距離を詰めるための道具であることが示されます。言葉すらも商売道具として使う。その姿勢が、尾花たちとの決定的な違いです。
相沢瓶人を口説く――「定時で帰る」を条件にした採用
食材が詰み、メニューも詰む。そこで浮上するのが相沢(及川光博)の存在です。
相沢は料理人としての腕だけでなく、レシピ動画で人気を得ることで“別の勝ち方”を知っている人物。
倫子は「店がオープンするまでの期間限定」「娘アメリーのお迎えに間に合うよう定時で帰る」という条件で協力を依頼します。
「全てを犠牲にしないと三つ星は取れない」と反発する尾花に対し、倫子が言い切るのが重要。
ここで彼女は、理念として“ブラックな情熱”をはっきり拒否します。
相沢は当初、尾花と同じ厨房に入れば生活すべてを持っていかれると感じ、断ります。それでも倫子は「全部は捧げない」と否定し続ける。この押し問答が、のちの“チームの形”を決めていきます。
伝説のジビエ猟師・峰岸――門前払いからの“挑発と試食”
さらに相沢から、伝説のジビエ猟師・峰岸(石丸幹二)の存在が語られます。
上質な肉を求めて尾花と倫子が会いに行きますが、峰岸は頑固で、最初は門前払い。
ただ、尾花の“挑発”が効き、峰岸は二人に料理を食べさせます。尾花と倫子はその美味しさに心を打たれ、改めて卸してほしいと頼みますが、峰岸は拒否します。
理由は重い。「コンクールに勝ちたい」といった動機の人間に、命を渡せない。ここで提示される「食材=命」という価値観は、作品全体の倫理の芯に直結しています。
祥平の“違和感”――相沢がレシピ更新を止めた理由
一方、祥平(玉森裕太)は、尾花に指摘されたキッシュを改良しながら、相沢がしばらくレシピ公開を休んでいることを知り、グランメゾン東京を訪れます。
そこで知るのが、「オーナーシェフは尾花ではなく倫子」「相沢が定時で帰れる条件で働いている」という事実。
祥平にとって、料理人としての世界観が揺さぶられる、かなり大きな衝撃です。
“名前を貸す”という支援――ようやく鹿のもも肉を確保
妨害で新鮮なジビエが手に入らない事情を知った祥平は、自分の名前を貸すことで仕入れを通します。その結果、グランメゾン東京は鹿のもも肉を確保できます。
ここが効いているのは、祥平がまだ完全にグランメゾン側の人間ではないから。正面からぶつかれば潰される。
でも“名前を貸す”という裏方の協力なら、今の立場でもできる。第3話の祥平は、料理の才能より先に「人としての矜持」が動いている印象です。
低温の火入れ→コンソメ――相沢も“沼”に落ちる
もも肉は固い。しかし尾花は使える部位があると見抜き、低温調理での火入れを重ね、ようやくローストとして形にしていきます。
次に始まるのが、ローストに合わせるコンソメの開発。
相沢は一度店を出て娘を迎えに行くものの、家に帰ってもコンソメが頭から離れず、結局は夜に店へ戻り、尾花と議論を重ねます。
「定時で帰る」条件で入った男が、自然と“料理人の顔”に戻ってしまう。その姿を見て、倫子が「自分は才能がないんじゃなく、努力が足りなかったのかもしれない」と気づくのも、この回の大きな転換点です。
倫子の罪悪感と、京野の叱咤――「決めるのがシェフ」
ただし倫子には罪悪感があります。
相沢が帰宅後も店に来てしまう。約束を守れていないのではないか、と。
そこで京野が突きつけるのが、「相沢が帰れないのは、メニューが決まっていないせい。シェフの責任だ」という指摘。倫子に必要なのは、遠慮や謝罪ではなく、決断だと明確に言い切ります。
この言葉を受けて、倫子は“料理長としての背骨”を取り戻す。
「自分を信じられないシェフは絶対に星は取れない」──この台詞が、第3話における倫子の転換点です。
「血」を使う――豚のソース案から、鹿の血コンソメへ
倫子はソース案として、ポワブラード(血を使うソース)を提案します。料理に深みを与えるための発想です。
相沢はすでに試したと語りますが、ここで尾花が閃く。「血なら鹿の血だ」。
鹿肉の野性味や香り、余韻を、同じ“命の成分”で受け止める設計へと切り替える。
コンセプトが一段深まります。
ただし問題は、新鮮な鹿の血が必要なこと。ここで峰岸の存在が、食材供給だけでなく“料理を完成させる鍵”として浮かび上がります。
コンクール当日――尾花がいない。倫子が火を入れる
いよいよコンクール当日。しかし尾花が現れません。
「スーシェフ不在」の厨房で、倫子が中心となって調理を進めます。緊張しながらも、鹿肉のローストに火を入れる。
この場面で描かれているのは、料理技術の勝負ではなく、「責任の火入れ」。
倫子は“料理ができる人”から、“店を背負う人”へ、ここで一歩踏み出します。
結果は「gaku」。でも“負け方”が次の勝ちにつながる
コンクールの結果は、gakuの優勝。食材の差も含めて、今はまだ力負けです。
ただ、この敗北は「才能が足りない」負けではありません。「勝ち筋を買われた」負けであり、同時に「それでも料理で心は動かせる」負け。
そしてこの料理を食べた祥平は涙を流します。
第1話で倫子が尾花の料理に圧倒されて泣いた構図が、ここで祥平にも重なる。料理で人の人生の向きが変わるという、このドラマの核が改めて確認されます。
尾花が連れてきた“答え”――峰岸の心が動く瞬間
コンクール後、尾花は峰岸を連れて店に戻ります。
料理を食べさせ、認めさせる。峰岸はジビエだけでなく、キノコや山菜など“山のもの”も最高の品を届けると約束し、「俺がとってきた命を最高の料理にしてほしい」と語る。
コンクールでは負けた。でも「食材の神様」に認められた。
この承諾は、今後の店の未来を左右する“ルート確保”そのもの。勝敗で言えば、むしろここが一番大きな成果です。
1か月後――相沢の退場(のはずが…)と、キャラ弁の一手
時間が進み、コースの形が見えてきます。相沢は「約束の期間が終わった」と店を去ろうとします。
しかし、娘アメリーの変化を知る。
尾花が毎日作っていたキャラ弁によって、アメリーの笑顔が増えたという話です。
相沢は“キャラ弁の作り方を習う”という名目で店に戻り、結果的に正式メンバーになります。
料理の腕で口説くのが尾花のやり方ですが、第3話の尾花はもう一段上のレイヤーで動く。相沢本人ではなく、相沢が最も大切にしている娘の日常を守る。戻らない理由を、一つずつ潰していくような動きです。
そして来た“最初の客”――リンダ、登場
店が動き出す、そのタイミングで現れるのがリンダ(冨永愛)。
「マリ・クレール ダイニング」の編集長であり、尾花の元恋人。つまり“メディア”であり、“過去”であり、“裁く側”。
プレオープンのドアが開いた瞬間、入ってきたのが最強の審判。
第3話は、次回以降の緊張を一気に高める完璧な引きで終わります。
もう一つの火種――美優の嫉妬と“画鋲”事件
第3話は料理だけでなく、人間関係の不穏さも同時に仕込んできます。
祥平の婚約者・美優(朝倉あき)が、祥平とパティシエの萌絵(吉谷彩子)の距離に疑心暗鬼になり、萌絵のロッカーに画鋲を仕込んで指先を負傷させる出来事が描かれます。
厨房において指の怪我は致命的。
この「恋愛の嫉妬」が「仕事の事故」になる設計が、後々の不安として効いてくる。静かで、かなり怖い伏線です。
グランメゾン東京3話の伏線
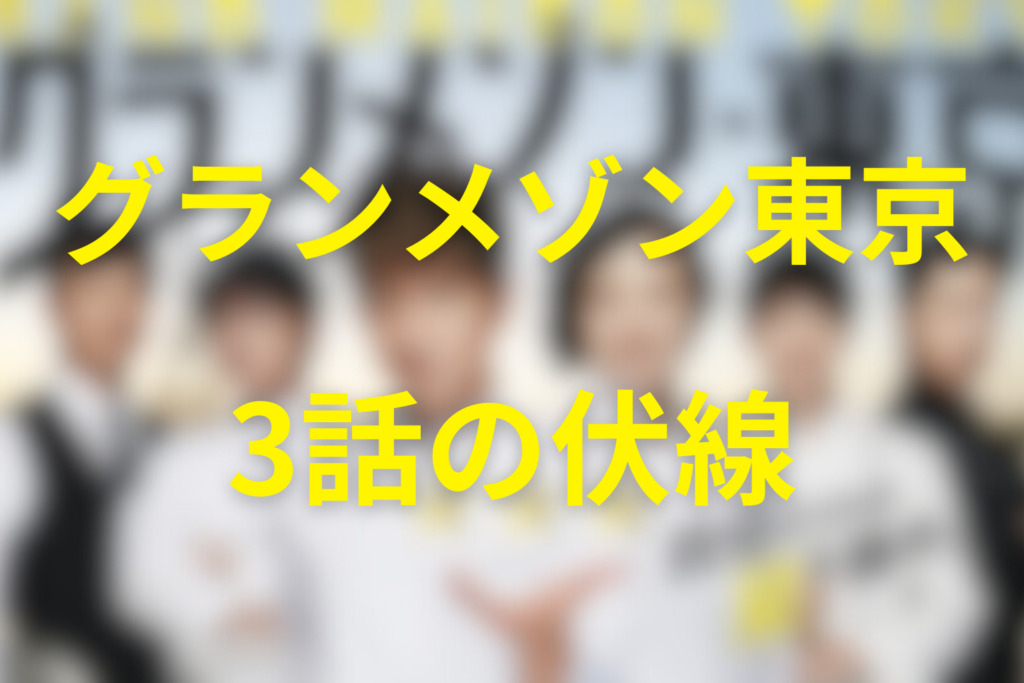
第3話は、表面上だけを見ると「鹿肉のコンクールで負けた回」ですが、伏線の濃度で言えば、シリーズ前半の中でもかなり密度が高い回です。
僕の目線では、この回の伏線は大きく ①敵の正体、②味方の作り方、③倫子の覚醒 の3系統に分かれて仕込まれていました。
伏線1:コンクールは宣伝イベントではなく“リンダの導線”
農水省とマリ・クレールが絡むジビエ料理コンクールは、表向きは国産ジビエ普及の企画です。
ただし、栞奈がリンダの名前を背負って動いている時点で、裏の目的──つまり尾花に接触するための導線──があると読めます。
この構図が怖いのは、料理人にとって一番の爆弾が「悪評」だという点です。
星を狙う店にとって、味以上に恐ろしいのが“物語のコントロール”。リンダは、料理の評価ではなく、語られ方を握っている人物です。
伏線2:江藤の買い占め=「仕入れを断つ」戦い方の提示
江藤がやったのは、単なる嫌がらせではありません。勝負のルールそのものを変える行為です。
「腕があっても、素材が来ない」状況を作る。これは飲食ビジネスとして最も現実的で、最も残酷な攻撃。
この一手が出た以上、今後も戦いは“厨房の外”で続くことが示唆されます。
さらに、江藤がエセ関西弁を使っている=「自分を演じる人物」だと明かされる点も重要。敵が情報操作や印象操作に長けた存在だということを、キャラクター設定で伏線として提示しています。
伏線3:丹後がコンクールを押し切る=gaku内部の温度差
江藤は当初、コンクール参加に消極的でした。それを丹後が「相手が尾花だ」と知って押し切る。
ここには、gaku内部の「経営」と「料理人の意地」の温度差がはっきり表れています。
丹後は料理人として勝ちたい。
江藤は商売として勝ちたい。
このズレは短期的には推進力になりますが、長期的には必ず綻ぶ。つまりgakuも決して盤石ではない、という予告になっています。
伏線4:峰岸の「不純な動機」発言=“星より先に守るもの”の提示
峰岸が「コンクールに勝ちたい」という動機を嫌うのは、ただの頑固さではありません。
それは、この作品が大切にしている倫理観の提示です。
「命を食う」という行為を、勝ち負けの道具にした瞬間に料理は死ぬ。
この価値観を第3話で明確に言語化したことで、以降の星取りが、単なる成功物語ではなくなります。
伏線5:相沢の“定時条件”=チーム運営の実験が始まった
相沢を「定時で帰らせる」条件で口説いたのは、倫子の意思表明でもあります。
三つ星を取りたい。でも家族を壊したくない。
この矛盾を、個人の根性ではなく“チーム設計”で解決できるのか。それがこのドラマの実験であり、相沢加入はその第一歩です。
しかも相沢本人は、結局コンソメにのめり込み、夜に店へ戻ってくる。
「制度」だけでは人は救えない。情熱は勝手に溢れてしまう。この矛盾まで含めて、きれいに伏線として機能しています。
伏線6:祥平の涙と“名前貸し”=引き抜きの導火線
祥平は、まだgaku側、あるいは別の厨房にいます。それでも名前を貸し、料理を食べて涙を流す。
この時点で、心はすでにグランメゾン側に傾いている。
人は理屈で動く前に、味で動く。第3話は、祥平が「戻ってくる準備」を終えたことを示す回でもあります。
伏線7:美優の画鋲=「人間関係が味を壊す」前兆
画鋲事件は、一見すると小さな出来事です。
しかし料理の世界では、指の怪我は即戦力ダウンにつながる致命傷。
しかも動機は嫉妬という、最もコントロールできない感情。
これが膨らめば、厨房が壊れる。グランメゾン側だけでなく、祥平自身の人生も壊れかねない。その不安を、静かに置いています。
伏線8:リンダ来店=「評価者が敵」になる地獄の開始
ラストでリンダが“最初の客”として現れる。
これは単なる新キャラ登場ではありません。
プレオープン=世に出る瞬間を、最悪の審判に踏ませたということ。
ここから先は、味だけでは勝てない。むしろ味が良いほど目をつけられる。物語がそのフェーズに入った、という合図です。
グランメゾン東京3話の感想&考察
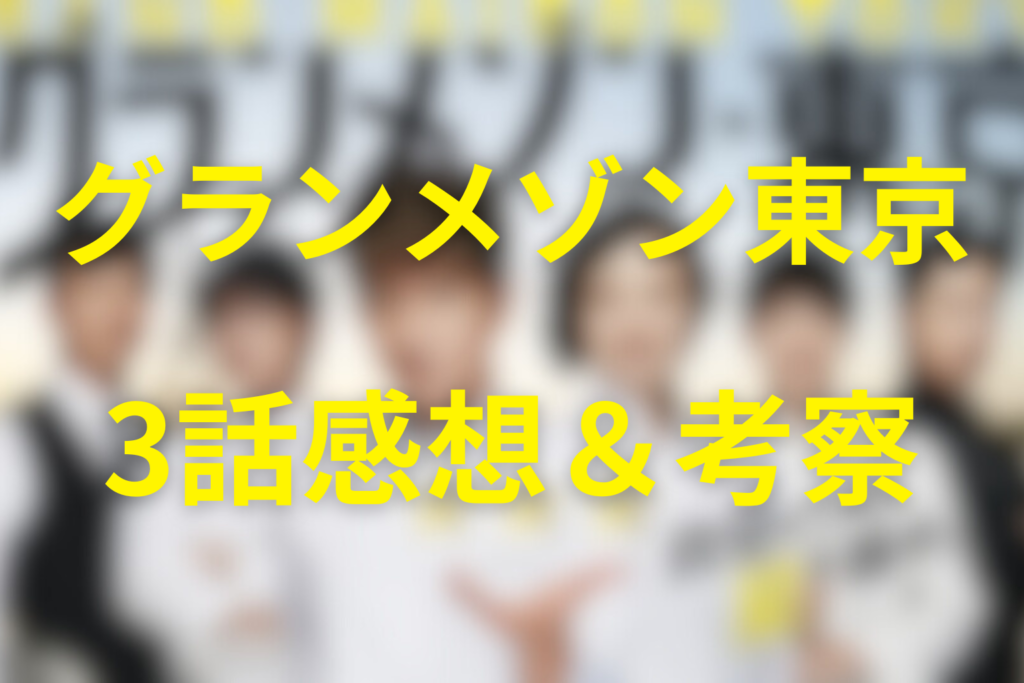
第3話を見終わって一番残ったのは、「勝てなかったのに、店が始まった」という感覚でした。
普通、料理対決回は“勝って次へ”か“負けてリベンジへ”の二択になりがちですが、第3話はもっと現実的で、もっと残酷で、それでも前向きです。負けたのに、“手応え”だけが確かに残る。
第3話は「負け回」じゃない。“店の骨格”が立ち上がる回
コンクールの結果だけを見れば、勝ったのはgaku。
でも視聴者の感情は、明らかにグランメゾン東京側に残ります。
理由はシンプルで、勝敗よりも「店が自立した瞬間」が描かれているからです。
尾花がいない状況で倫子が火入れをする。
相沢がチームに加わる。
峰岸が“命”を預ける。
この3つはすべて、「尾花という天才」から一歩離れて、店そのものが成立し始めた証拠。第3話は勝ち負け以上に、“店の骨格”が立ち上がった回でした。
倫子の成長が良すぎる。「技術」じゃなく「責任」を焼いた
第1話・第2話の倫子は、どうしても尾花の背中を追う立場でした。でも第3話の倫子は、京野の言葉を受けて「決める側」に回ります。
料理は、迷っている時点で負ける。
もちろん試行錯誤は必要だけれど、どこかで“賭ける”瞬間が必要です。その賭けを引き受けるのが料理長であり、オーナーシェフの役割。
倫子がそこに立てたから、相沢は一度は店を出られたし、逆に言えば、倫子が立てなかったら相沢は家族ごと壊れていた。
このドラマは料理の火入れを描きながら、ずっと「人生の火加減」を描いています。
「鹿の血のコンソメ」が象徴するもの――命を“旨味”に変える覚悟
鹿肉に鹿の血を合わせる、という発想は、クラシックなフレンチの文脈にも通じます。同時にそれは、“命を丸ごと受け止める”という宣言でもあります。
ここはまさに、「料理が思想になる瞬間」。
ただ柔らかく焼くだけなら、技術で終わる。
香りを整えるだけなら、センスで終わる。
でも“血”を使うと、皿の上で命が語り出す。
峰岸が「不純な動機」を嫌った理由も、ここで一本につながります。
勝ちたいから命が必要なのではなく、命を最高に扱いたいから料理を作る。この軸がブレなかったからこそ、峰岸が最後に心を許す流れが、すっと腑に落ちました。
相沢が“定時で帰れない”のがリアル。情熱は制度じゃ止まらない
倫子は「定時で帰る」という条件を出しました。これは現代的で、正しい判断です。
でも相沢は結局、家に帰ってもコンソメを作り、夜に店へ戻ってくる。
ここに、このドラマの誠実さがあります。
働き方改革で、すべてが解決するわけじゃない。
情熱のある人は、勝手に燃えるし、勝手に無理をする。
だから必要なのは、ルールよりも先に「帰れる理由」を作ること。
その意味で、尾花のキャラ弁は強烈に効いています。
尾花が「帰れ」と言っても相沢は帰らない。
でも娘が笑顔になるなら、相沢は戻ってくるし、同時に“帰る”ことも肯定できる。料理で人を動かす男が、第3話では料理以外で人を動かしている。このズレが面白い。
江藤の買い占めは卑怯?――でも“現実の戦い方”でもある
江藤は分かりやすく嫌われ役ですが、やっていることは「飲食の勝負の現実」を突いています。
素材を押さえた方が勝つ。これは残酷ですが、現実に起こり得る戦い方です。
印象的なのは、「星はシェフじゃなく店につく」という思想。冷たいようでいて、実は合理的。再現性のあるクオリティを維持するのが店の仕事で、属人化はリスクになる。
だからこそ、グランメゾン東京は“尾花一人の天才劇場”では勝てない。この前提を、江藤という存在が逆説的に補強しています。
美優の画鋲が怖いのは、恋愛ではなく「事故」だから
美優の行動は、単なる嫉妬として片づけるには危険すぎます。厨房において、指の怪我は即致命傷。
怖いのは、彼女が悪女だからではなく、「怪我」という現実的な事故を持ち込める人物だという点です。
料理の世界は、指一本で人生が変わる。その領域に、感情で踏み込める人間がいるという不穏さ。
この違和感は、物語のメインにある事件の真相とも、どこかで接続していく予感があり、背筋が冷えます。
リンダ登場――“最初の客”が最悪で最高
プレオープンの最初の客として現れるリンダ。
これは単なる新キャラ投入ではありません。
彼女は、メディアとして店を殺せる存在。
彼女は、過去の事件とつながる存在。
彼女は、尾花の私情を刺激する存在。
つまり、料理の勝負が「味」から「因縁」へと一気に拡張される瞬間です。
店が産声を上げた瞬間に、最大の捕食者が現れる。この構図が、あまりにも残酷で、だからこそ面白い。
三つ星を取る物語は、優しいだけでは成立しない。
どこかで必ず、「評価される恐怖」と正面衝突しなければならない。
第3話は、その入口を最高に嫌な形で、でも完璧なタイミングで開けた回でした。
グランメゾン東京の関連記事
全話のネタバレはこちら↓
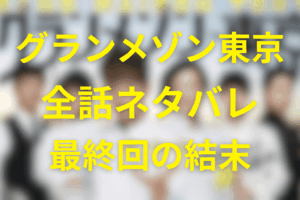
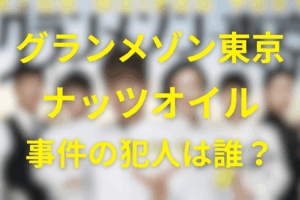
次回以降の記事についてはこちら↓
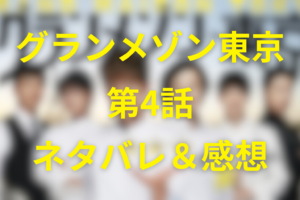
過去の記事についてはこちら↓
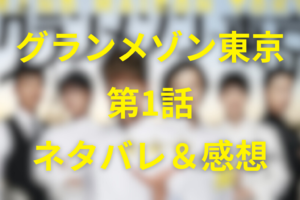
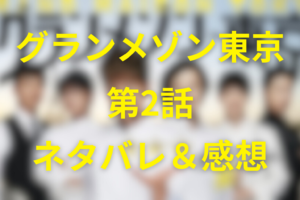
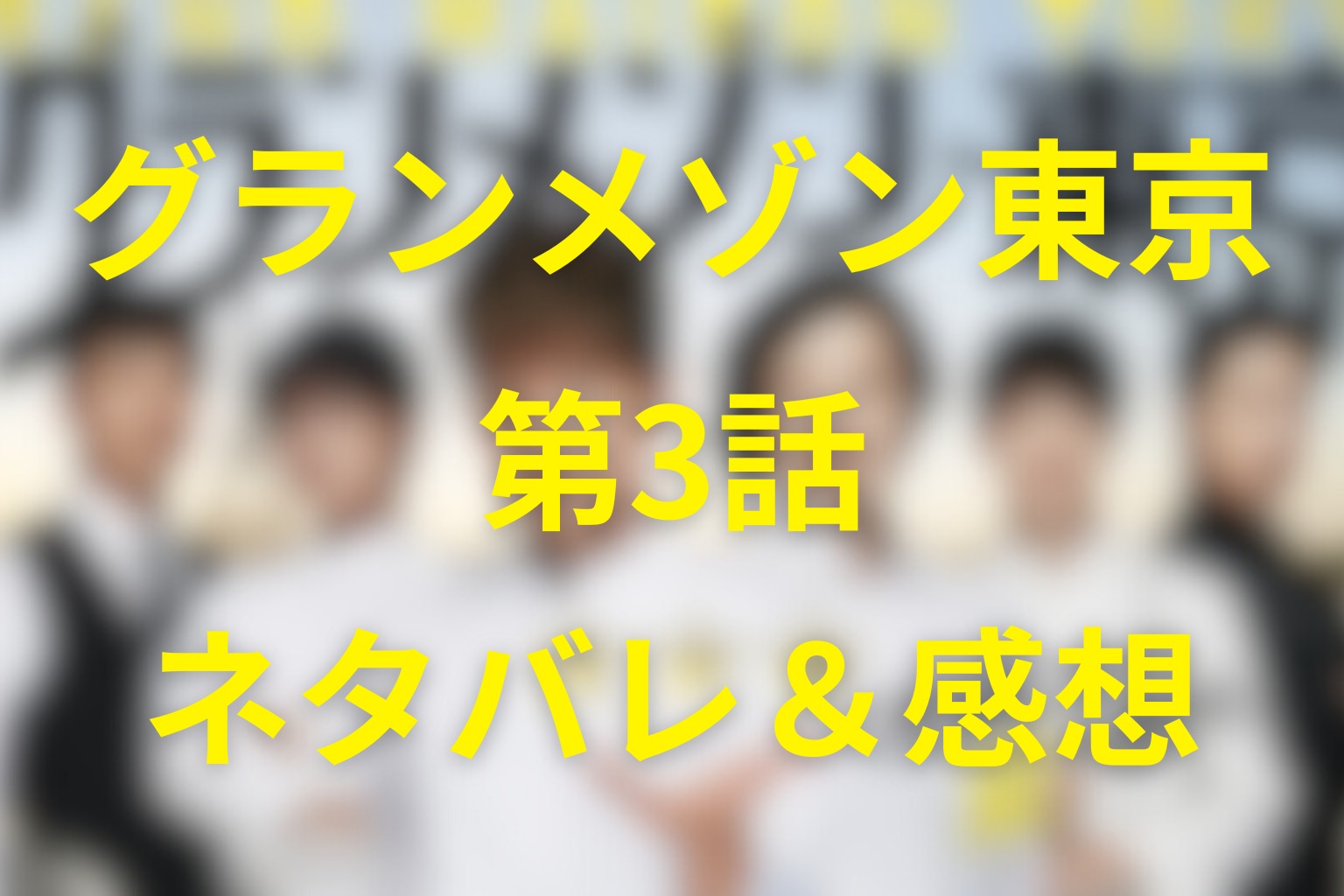
コメント