第2話で“劇場という箱”が整い、登場人物たちがそれぞれの立ち位置を掴み始めた『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(通称:もしがく)。
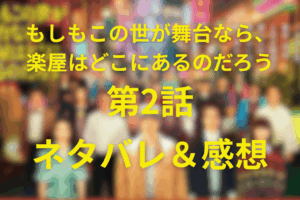
第3話は、“演劇が始まる前の演劇”を描いたエピソードだった。
作家・久部(三成/菅田将暉)が脚本を破り捨て、稽古場の支配構造を壊すところから、物語は一気に熱を帯びていく。
紙の上の「正しさ」が崩れ、声と身体の「正しさ」が稽古場に宿る瞬間。
トニー(市原隼人)は羞恥を越えて声を取り戻し、芸人フォルモン(西村瑞樹)は“負け方の笑い”を掴む。第3話は、作品が“紙の上”から“場の中”へ降りてくる過程そのものだった。
ここでは、そんな「演劇が生まれる瞬間」を中心に、物語の構造と三谷幸喜らしい群像劇の妙を考察していく。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)3話のあらすじ&ネタバレ
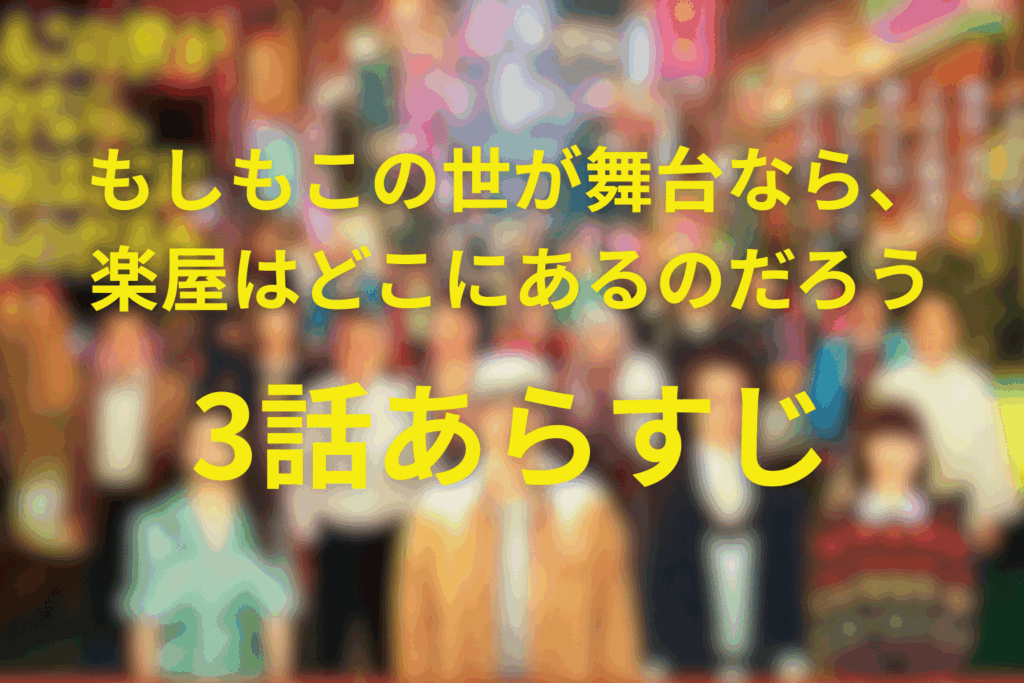
第3話(10月15日放送)は、WS劇場の向かいにある古びたアパート「グローブ荘」から幕を開ける。
演出家・久部三成(菅田将暉)は、WS劇場で上演予定のシェイクスピア『夏の夜の夢』を、自らの“クベ版”として必死に改訂中。
彼を支えるのは放送作家志望の蓬莱省吾(神木隆之介)。
夜食の“具なしラーメン”を差し入れるも、久部は「センスがない」と文句を連発——それでもペンは止まらない。しかし、原稿を巡る意見で衝突が起こる。リカ(二階堂ふみ)と蓬莱が「長すぎる」「セリフは少ない方がいい」と率直に助言すると、久部は激昂し原稿を破り捨てる。
ここで、“作家の独善”と“現場の実務感覚”が初めて激しくぶつかり合う。
稽古スタート:用心棒トニー、俳優デビューの壁
WS劇場では、ついに“クベ版『夏の夜の夢』”の読み合わせがスタート。用心棒のトニー安藤(市原隼人)も半ば強引に出演者に加わる。
しかし初読みの声は予想外に小さく、まるで蚊の鳴くような声量。「ディミトリアスはどこだ……」とつぶやく姿に久部は頭を抱えるが、そのギャップが稽古場の笑いを誘う。
SNSでは「声ちっさ!」「トニー萌えキャラすぎる」とトレンド入り。“強さの象徴”だった用心棒が、“声”という新たな壁にぶつかる導入となる。
ライバル「天上天下」との火花――演出×演出の意地の張り合い
一方で、久部がかつて所属していた劇団「天上天下」が再び登場。
主宰の黒崎(小澤雄太)率いる一派が“クベ版”の動向を探り、ライサンダー役をめぐって稽古バトルが勃発する。
WSチームの芝居はまだぎこちなく、対する天上天下の若手は声量・身体ともに仕上がっている。久部は“演出家としての負けん気”をむき出しにし、稽古は舞台を超えて“意地の勝負”へと発展していく。
覚醒のトニー――挑発が火を点ける
トニーは相手の挑発を受け、“用心棒”のスイッチが入る。身体の芯に眠っていたリズムが呼び覚まされ、声が前に出る。
ライサンダーの台詞が突如として力を帯び、稽古場の空気が一変。市原隼人の圧倒的な演技に、SNSは「トニー覚醒!」「痺れた!」と沸騰。
見せ場は殴り合いではなく、台詞で殴り返す瞬間。フィジカルと声の表現が一本の線でつながるカタルシスが描かれた。
WSチームの成長線――芸人フォルモンの“役割の発見”
お笑いコンビ「コントオブキングス」の彗星フォルモン(西村瑞樹)も稽古に苦戦。
プライドが高く“強い芸”にこだわるが、稽古を重ねるうちに“情けない役”を全力で演じた方が観客の笑いを取れると気づく。芸人としての自己演出から、劇の一部として生きる演者へ変わる瞬間。
この小さな舵切りが、劇団全体のリズムを整え、物語の歯車を進めていく。
ラスト:初日へ向けて走り出す“劇場”
第3話の締めは、いよいよ“初日”の光が見えてくる手応え。
稽古は荒削りながらも、久部の情熱は少しずつ周囲に伝播し、俳優たちはそれぞれの役と向き合い始める。WS劇場という“ストリップ小屋”が、本物の“舞台”へと変貌しつつある臨界点。
次回はついに“クベ版『夏の夜の夢』”の初日。混沌と笑いの稽古場が、どんな“開演”を迎えるのか——期待が高まる。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)3話の見終わった後の感想&考察
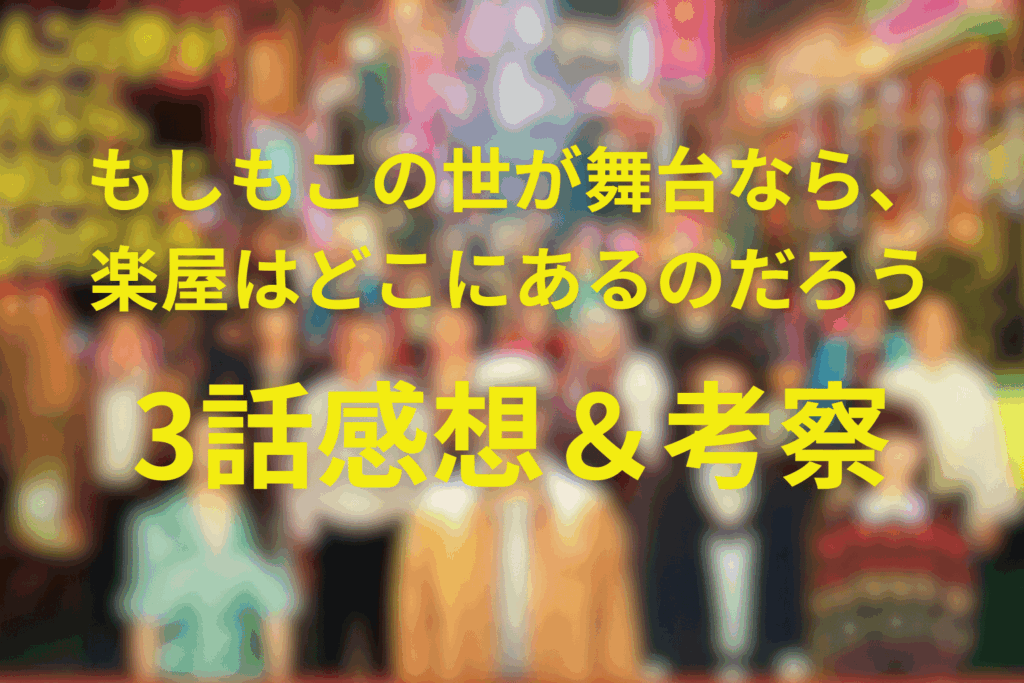
第3話は、“演劇が始まる前の演劇”が描かれた回だった。作家が書き、俳優が読む——それだけの行為が、なぜここまでスリリングになるのか。結論から言えばこうだ。
①久部が持つ“脚本の神性”を一度破壊し、②稽古場という共同体の民主化へ舵を切り、③個々の身体が役を見つける過程を、笑いと衝突で可視化したから。
紙の上の正しさではなく、声と体温の正しさ。第3話はその逆転を“起点”として提示した。
1)「脚本の権威」を相対化する——破ることで場に戻す
久部が原稿を他人に読ませず、批評を拒む場面は、作家の孤独と独善を同時に描く強いワンシーンだ。
しかし彼は最終的に原稿を破り捨てる。これは単なる癇癪ではなく、“脚本の権威を稽古場へ返す”儀式だ。リカと蓬莱の「長いと飽きる」「セリフは少ない方が助かる」という現場の声は、観客の生理そのもの。
久部はそれを受け止め切れず爆発するが、紙を破ったことで“作家の神”から“稽古場の神”へ主権が移る。以降の稽古が回り始めるのは、その主語が変わった瞬間からだ。
第3話は、“作品の主語”を作家個人から“稽古場の集合体”へと移した回である。
「声が出ない」トニー——羞恥からの跳躍
トニー(市原隼人)は身体が強いのに声が出ない。ここが本話の秀逸な仕掛けだ。彼の弱点は技術の不足ではなく、“羞恥”そのもの。
挑発され、恥じる感情が反転した瞬間、呼吸が戦闘モードへ切り替わり、声が自然に前へ押し出される。理屈ではなく、身体が役を掴んだ。
戦うときのリズムと演じるときのリズムが重なり、台詞が“殴る言葉”に変化する。覚醒は奇跡ではなく、身体が導いた必然だった。
「負ける方法」を知るフォルモン——笑いの回路を変える
フォルモン(西村瑞樹)が“情けない役”に振り切る決断は、演劇の王道であり、三谷脚本らしい柔らかい笑いの核心だ。
笑いは勝ち方だけでなく、“負け方”からも生まれる。勝ちに固執する芸は硬く、負けを引き受ける芸は柔らかい。
フォルモンが“負け”を受け入れたことで、WS座組のアンサンブルが一段階よくなった。強さの独占が緩むと、舞台に“余白”が生まれ、他者の呼吸が入り込む。
そのわずかな隙間が、舞台を生かす呼吸になる。
1984年・渋谷という速度——場が人を作る
公式イントロが示すように、物語の舞台は1984年の渋谷。
景気の足音が聞こえ、ネオンの光が人のテンポを速める街だ。この時代設定が効いているのは、“勢い”が正義として許されるから。
稽古が粗くても、勢いと笑いで押し切ることができる。
三谷幸喜は、熱が論理を追い越す瞬間——“勢いが人を変える瞬間”を群像劇のテンポで描き出している。
「三谷の本領」への助走
第3話で明確になったのは、三谷幸喜の本領——人間の衝突を笑いで昇華する構造だ。
勝者を置かず、意地と滑稽を同じ熱量で描く。
その結果、最後に勝つのは個人ではなく、“場”であり“劇”そのもの。
初日を目前に控えた第4話では、いよいよ観客という“第三の身体”が稽古場に介入する。“舞台”が“現実”を侵食する瞬間を、どう描くかに注目したい。
総括
第3話は、“作品が稽古場へ降りる”回だった。
台本の神性を一度壊し、稽古場の民主主義へ移行したことで、演劇が真に始まる。
トニーは羞恥を越えて声を得、フォルモンは負け方で笑いを得た。こうだからこう——人が役を掴んだ瞬間、場が劇へと変わる。初日の幕は、もう耳元まで近づいている。
もしがくの関連記事
全話のネタバレについてはこちら↓
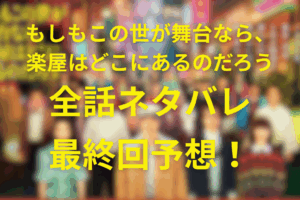
2話についてはこちら↓
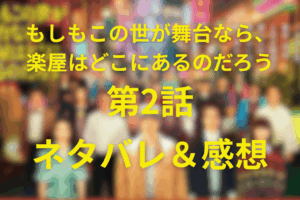
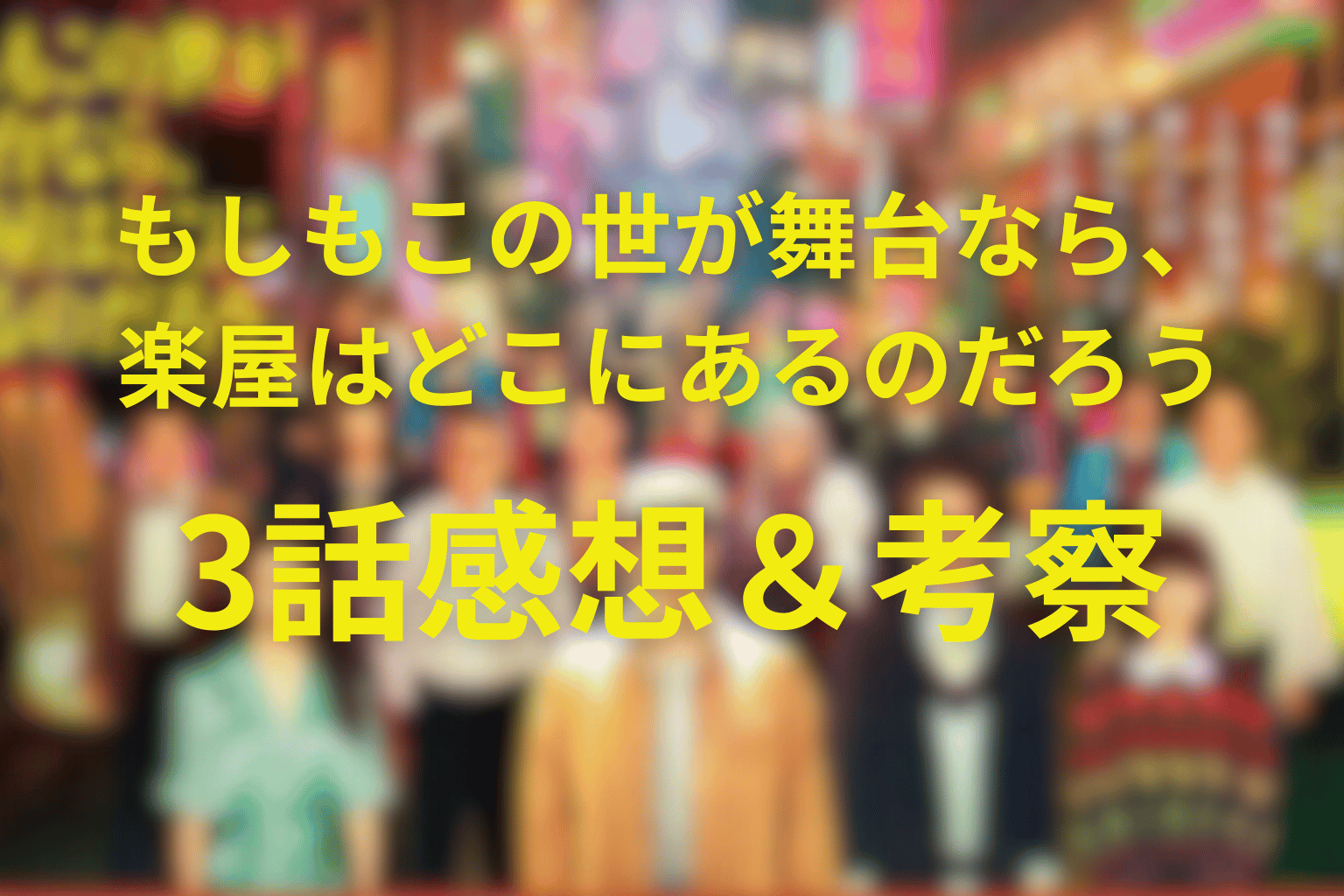
コメント