第1話では、劇団を追放された久部三成が迷い込んだ渋谷・八分坂とWS劇場での出会いが描かれ、彼の再生の物語が幕を開けました。
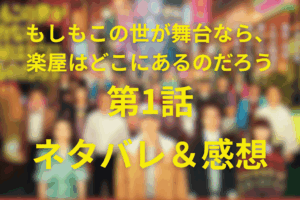
続く第2話では、1984年当時の風営法改正がWS劇場を直撃し、客足が遠のくなかで存続の危機に直面します。
久部はピンスポット担当として舞台裏に立ち、ダンサーや劇場関係者たちと共に逆境に挑む姿が描かれ、彼自身の成長や人間関係の変化が大きな見どころとなります。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)2話のあらすじ
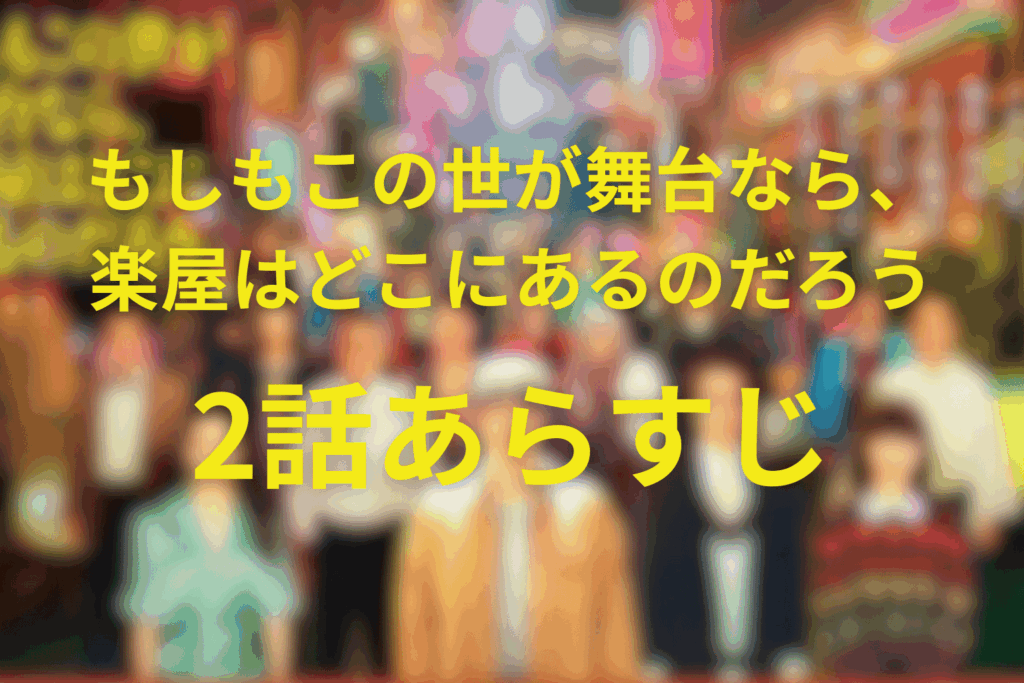
WS劇場に迫る試練
第2話の舞台は、久部三成が迷い込んだ渋谷・八分坂にある「WS劇場」。ここで物語は早くも劇場存続の危機に直面します。1984年当時、風営法の改正によりストリップショーの規制が強化され、それまで熱狂的な客で賑わっていた劇場は見る影もなく閑散としてしまいました。
華やかな舞台に立つダンサーたちも、かつての輝きが薄れ、空席が目立つ客席を前に踊り続けなければならない状況に追い込まれます。
ベテランダンサーのパトラ鈴木は、それでも気丈にステージに立ち続けますが、その姿はWS劇場が抱える厳しい現実を浮き彫りにしていました。支配人の大門は、このままでは劇場が立ち行かないと危機感を募らせ、久部に「ここで働いてみないか」と声を掛けます。
久部は渋々ながら劇場の法被を着込み、パトラのショーでピンスポットライトを担当することになりました。演出家を夢見た彼が照明係として裏方に回るという展開は、彼のプライドを揺さぶるものでありながらも、再生への一歩となる布石でもあります。
劇場存続への模索
WS劇場がどのように規制強化を乗り越えるのか――このエピソードの大きな焦点となるのは、オーナーのジェシー才賀と支配人・大門が打ち出す新しい方向性です。派手なストリップだけでは客を呼べなくなったいま、劇場はどんな興行スタイルに変わろうとするのか。
久部は照明担当として舞台裏からその試みを見つめながら、やがて演出家としての視点で意見を述べる立場に近づいていくでしょう。演劇への情熱を失いかけた久部が、再び「舞台」の力を信じるきっかけを掴む回になると考えられます。
また、ダンサーたちにとってもステージに立つ意味が問われる局面です。観客の歓声がない中で踊り続けることの虚しさ、舞台に自分を捧げてきた矜持。そうした内面の葛藤が描かれることで、彼女たちのキャラクターが一層深掘りされていきます。
人間関係の再構築
第1話で劇団を追放された久部にとって、WS劇場は再生の舞台であり、ここでの再会が彼の物語を動かしていきます。謎めいたダンサー・倖田リカとの関係はさらに進展し、彼女の存在は久部の心を揺さぶり続けるはずです。
観客の減少に苦しみながらも舞台に立つパトラや、子を抱えながら踊り続けるモネの姿は、久部に「舞台に生きる人間の覚悟」を突きつけるでしょう。
さらに周辺人物も絡み合い、劇場という小宇宙に人間ドラマを広げます。モネの息子・朝雄の純粋な視線は、大人たちの矛盾を際立たせる役割を担いそうですし、交番勤務の大瀬六郎は八分坂の治安を守りながら、劇場に関わる人々と距離を縮めていきます。これらの人物たちの物語が交錯することで、WS劇場は単なるショーの場から「夢と現実が交わる舞台裏」へと姿を変えていきます。
結末への布石
第2話は、劇場が法の規制に抗いながら生き残る道を模索する姿を描きつつ、久部が再び舞台に立つための精神的な土台を築く回になるでしょう。
八分坂に集う人々のドラマが重なり合い、やがて久部が演出家として「本当の舞台」を見つけ出すための試練が始まります。彼の再生物語と劇場の存続をめぐる群像劇が、今後どのように絡み合っていくのか――第2話はその大きな転換点となるはずです。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)2話の感想&考察
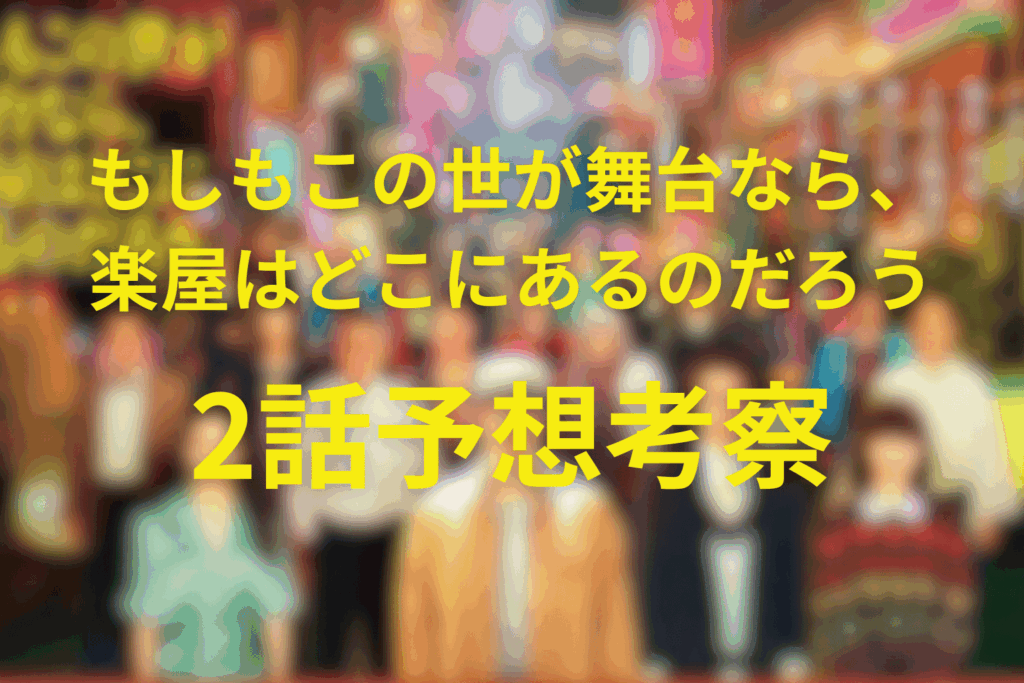
第2話は、初回で描かれた「出会いの瞬間」から一気に舞台装置を転換し、1984年という現実が物語を揺さぶり始めた回だった。風営法の改正によってストリップ劇場が厳しく規制され、華やかな熱狂が嘘のように消えた――WS劇場の客席はガラガラで、踊り子パトラのステージにも歓声が起こらない。ここにまず、現代の視聴者には馴染みの薄い社会背景と、当時の若者たちが抱えていた現実の重さが置かれる。
その状況を受け、主人公・久部三成(菅田将暉)は劇場の法被を着てパトラのショーのピンスポット担当を引き受ける。
劇場支配人・浅野大門から「うちで働いてみないか」と誘われた久部は、劇場スタッフの伴工作に連れられ楽屋へ挨拶に向かう。そこで彼はリカ(二階堂ふみ)と再会するが、久部の「頑張ります!」という気合いに対し、リカは興味なさげに目をそらす。この温度差が、二人の関係の行方と劇場の未来を象徴していた。
風営法の影響で衰退したWS劇場と現実の1984年
第2話の冒頭で強調されたのは、風営法改正による文化の締め付けだ。1984年に全面改定された風俗営業等取締法は、性風俗だけでなくディスコやパチンコといった娯楽施設にも規制を拡大し、警察の裁量を強めた。
公序良俗を盾にストリップ劇場が「規制の対象」とされたことで営業が難しくなり、WS劇場は2年前の熱狂が嘘のように寂れてしまう。この歴史的事実を物語に落とし込み、“伝説のショーが時代の波に呑み込まれていく”という喪失感を視聴者に共有させる脚本が巧みである。
三谷幸喜自身の青春期の体験が反映されているとされる本作は、カルチャーの発信地・渋谷の裏側で生きる若者たちに焦点を当てる。メインストリームから外れた人々の視点で「時代の転換点」を描くことで、80年代の空気感がリアルに伝わってくる。劇場の衰退を“外的圧力”として置いたことで、若者たちが自らの居場所をどう守るのかというテーマが一層明確になった。
久部の“覚醒”――ピンスポから始まる壮大な野望
第2話のクライマックスは、久部がダンサーたちの前で語った「クベシアター構想」だった。自分たちが作った屋根を燃やしておきながらも、パトラの指示でピンスポットを担当することになった久部。楽屋でリカに再会するも相手にされず、何かを変えなければならないと悟った彼は、後半で劇場スタッフやダンサーたちを呼び出し、「このWS劇場を若者たちで復活させよう。いや、日本で一番の劇場にするんです!」と宣言する。
この宣言には論理がある。第1話で理想を振りかざし劇団を追放された久部が、WS劇場では“支える側”に回り、現実の厳しさを知る。ピンスポという裏方を経験することで、彼は「ステージを作る苦労」と「場の喪失」を具体的に理解する。
だからこそ、観客が離れた劇場を“自分たちの劇場”として再生させる大義に突き動かされる。口だけではなく行動で示す久部の姿は、「こうだからこう」という三谷脚本の理詰めの展開であり、視聴者が感情移入できるポイントだった。
リカとの再会と温度差が示すもの
久部が勢いよく「頑張ります!」と声を上げる一方で、リカは興味なさげに視線を逸らす。この温度差は、二人の価値観の違いを示すと同時に、リカの置かれた現実を浮かび上がらせる。彼女はストリップの踊り子としてプロの誇りを持ちながらも、客足が遠のく現実に直面し、劇場の未来に希望を見出せない。だからこそ、久部の情熱はまだ彼女に届かない。
第1話でリカの踊りが大きな反響を呼び、「ふみちゃん色っぽくて昭和の女が似合う」「オーラがすごい」と称賛された。その彼女が第2話では無関心を装う姿は、舞台上の輝きと裏側の虚無感のギャップを際立たせる。久部の計画がリカの心を動かすまでには、まだいくつもの壁があるだろう。
八分坂の人間模様とクベシアター構想への期待
今回のエピソードでは、WS劇場の従業員だけでなく、八分坂で生きる人々の姿も断片的に描かれた。裏方の伴工作は久部をダンサーたちの楽屋に案内し、パトラは空席だらけの客席に苛立ちながらもステージに立ち続ける。巫女の樹里や放送作家志望の蓬莱たちは、劇場の外でそれぞれの役割を模索している。
第2話はこれらの人物を「クベシアター」という一点に収束させるための布石であり、久部の呼びかけが彼らの心にどう響くかが今後の見どころだ。
クベシアター構想は、1980年代の小劇場ブームへのオマージュでもある。1984年の風営法改定によって、ディスコやパチンコなどの娯楽産業が制限され、ストリップ小屋が営業しにくくなった一方、若者たちは小劇場やライブハウスに活躍の場を移した。久部が掲げた「自分たちで劇場を作る」という発想は、その歴史的潮流と重なる。客足が途絶えた劇場を再生させるには、観客の心を掴む“新しい何か”が必要であり、若者たちの自由な発想と情熱こそがそれを生むのだというメッセージが込められている。
視聴者の反響:熱い展開とヒーローへの期待
放送後、ネット上では「演劇版『王様のレストラン』みたいでワクワクする」「クベシアター始動が熱すぎて鳥肌」といったコメントが相次いだ。特に、久部がダンサーたちを説得する場面は「まさか久部、覚醒!」「このまま座長になるのでは」と盛り上がりを見せた。一方、用心棒トニーとリカの関係が明かされるシーンでは驚きと笑いが同時に起こり、「ガチビンタ!」といった感想も上がった。
筆者としては、久部がかつての劇団では独善的な演出家だったのに対し、WS劇場では裏方からスタートし、現実を直視したうえで夢を語る姿に成長を感じた。第1話の「自分だけのミューズとの出会い」が彼の原動力になっていることも見逃せない。リカに振り向いてもらえない悔しさと、劇場を失う危機感が交差し、久部の野心は個人的な恋心から「場所を守る」使命へと拡張している。ここから先、彼がどのように仲間を巻き込み、現実の壁とぶつかりながら劇場を復活させるのか、非常に楽しみだ。
まとめ
第2話は、風営法改正という歴史的背景を織り込みながら、主人公・久部の“覚醒”を描くターニングポイントとなった。WS劇場の衰退という危機から生まれた「クベシアター構想」は、単なる夢物語ではなく、裏方としての経験と現実への危機感が生んだ論理的帰結だった。
リカとの再会で見えた温度差や、八分坂の人々の動きを含め、この物語が目指すのは“劇場の再生”と“青春の再定義”。次回以降、久部の大風呂敷がどのように展開していくのか、そしてリカや仲間たちがその夢にどう関わっていくのかを、論理的かつ感情的に追っていきたい。
もしがくの関連記事
全話のネタバレについてはこちら↓
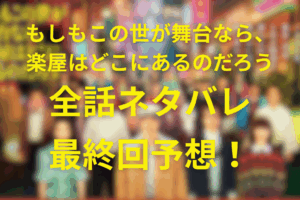
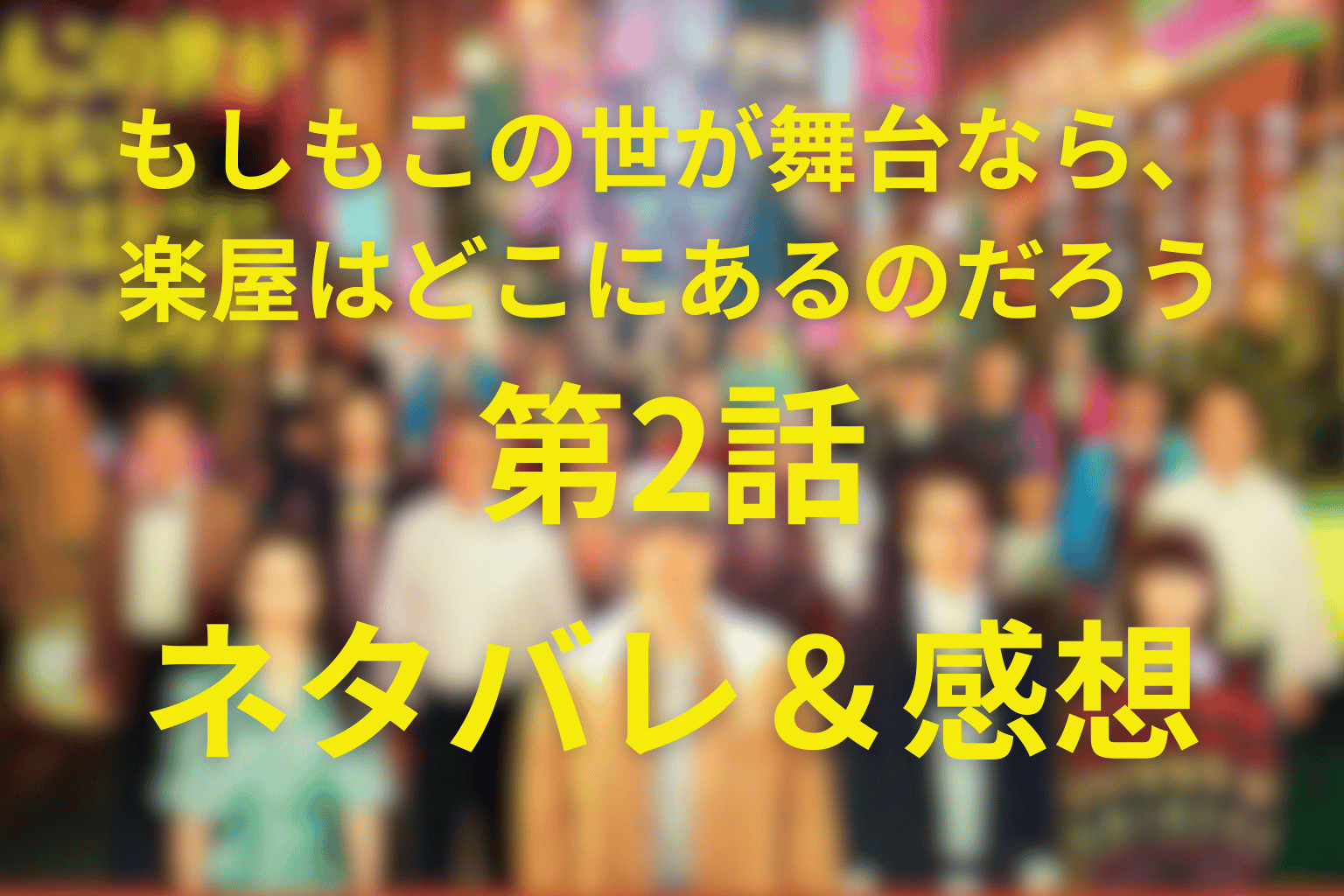
コメント