三谷幸喜氏が25年ぶりにゴールデン帯で脚本を手掛ける注目作『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(通称:もしがく)。
舞台は昭和59年、カルチャーの発信地・渋谷。夢と挫折を抱えた若者たちが、アンダーグラウンドな劇場「WS劇場」に集まり、それぞれの人生を交錯させていきます。
軽妙な会話と群像劇の魅力に彩られた第1話では、主人公・久部三成が新たな挑戦へと踏み出す姿を中心に、個性的なキャラクターたちが次々と登場。三谷作品ならではの笑いと人間ドラマが詰まった物語の始まりを、あらすじと予想考察を交えながら紹介します。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)のキャスト一覧
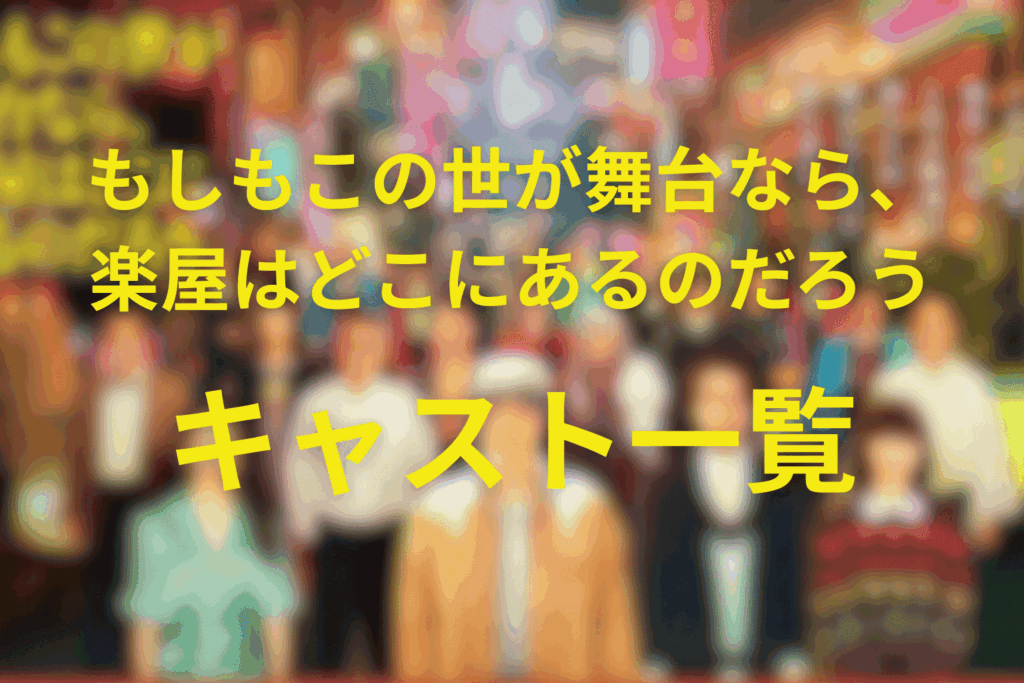
昭和59年の東京・渋谷を舞台にしたオリジナル青春群像劇『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、三谷幸喜氏が25年ぶりにゴールデン帯で脚本を手掛ける注目作です。
三谷作品らしい軽妙な会話と群像劇の魅力が散りばめられ、80年代の空気感をまとった舞台劇的な世界観で描かれます。公式キャラクター紹介によれば、主要な登場人物は以下の通りです。
もしがくの主な登場人物
- 久部三成(くべ みつなり) – 菅田将暉
劇団の演出家の卵。尊敬する艶川幸雄に憧れ、理想のシェイクスピア劇を夢見る青年。劇団をクビになり、八分坂の“WS劇場”へ流れ着く。 - 侘田リカ(わびた りか) – 二階堂ふみ
WS劇場のダンサー。妖艶な雰囲気をまとい、看板スターとして観客を魅了。久部の前に立ちはだかる謎多き女性。 - 蓑菜省吾(みのな しょうご) – 神木隆之介
新人放送作家。ジャケットとネクタイ姿が“若き日の三谷幸喜”を彷彿とさせる。成功を夢見て奮闘中。 - 江頭樹里(えがしら じゅり) – 浜辺美波
八分坂神社の巫女。清楚だが、舞台裏ではWS劇場と不思議な縁を持つ。 - 風呂須太郎(ふろす たろう) – 小林薫
ジャズ喫茶「テンペスト」のマスター。芸達者な若者たちの憩いの場を支える存在。 - トニー安藤(とにー あんどう) – 市原隼人
WS劇場の用心棒。粗暴ながら情に厚く、新参者の久部を敵視する。 - 大瀬六郎(おおせ ろくろう) – 戸塚純貴
渋谷交番勤務の警官。純情で町の風紀を守り、住人と顔なじみ。 - パトラ鈴木(ぱとら すずき) – アンミカ
WS劇場のベテランダンサー。後輩の面倒を見つつ舞台裏を支える姉御。 - 五反田マリ子(ごたんだ まりこ) – 秋元才加
シングルマザーのダンサー。息子・朝庭を育てながら舞台に立つ。 - 朝庭(あさにわ) – 佐藤大空
マリ子の一人息子。母の背中を見て育ち、秘めた才能を持つ。 - お冷や – 菊地凛子
無料案内所の女性。暗号めいた言葉で久部を翻弄。 - 江頭神平(えがしら しんぺい) – 坂東彌十郎
八分坂神社の神主で樹里の父。厳格だが、実はある女性ダンサーの追っかけ。 - うる爺(うるじい) – 井上順
WS劇場の常連。下ネタばかりだが、元落語家の過去を持つ。 - 伴工作(ばん こうさく) – 野間口徹
WS劇場の舞台監督。控えめながら有能で舞台進行を支える。 - ジェシーオ賀(じぇしーおが) – シルビア・グラブ
WS劇場オーナー。アンダーグラウンドな雰囲気を守りつつ、赤字経営に苦心。 - 乱士郎(らんしろう) – 佳久創
ジェシーオ賀の秘書兼ドライバー兼用心棒。無口だが忠誠心が厚い。 - 浅野大門(あさの だいもん) – 野添義弘
WS劇場の支配人。柔和だが劇場運営の手腕は確か。妻・浅野フレには頭が上がらない。 - 浅野フレ(あさの ふれ) – 長野里美
大門の妻。情緒不安定ながら事務を担い、演者への愛情は深い。 - トンちゃん – 富田望生
劇団「天王寺下」の制作スタッフ。久部を気にかけ陰ながら支援。看板俳優・黒崎とは犬猿の仲。 - 彗星フォルモン(西村瑞樹)&王子はるお(大水洋介)
お笑いコンビ「コントオボシングス」。頑固で周囲の助言を聞かない芸人。 - 仮歯 – ひょうろく
ジャズ喫茶「テンペスト」の従業員。気弱で声が小さい。 - 毛利里奈(もうり りな) – 福井夏
WS劇場のモギリ係。派手な服装で観客を迎える。 - ケントちゃん – 松田慎也
スナック「ペログリーンズ」のウェイター。寡黙だが頼れる存在。 - いざなぎダンカン – 小池栄子
WS劇場の看板ダンサー。第1話の物語の鍵を握るとされる人物。
この他にも数多くの役者が出演し、個性的なキャラクターが三谷幸喜作品らしく物語を華やかに彩ります。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)1話のあらすじ&ネタバレ
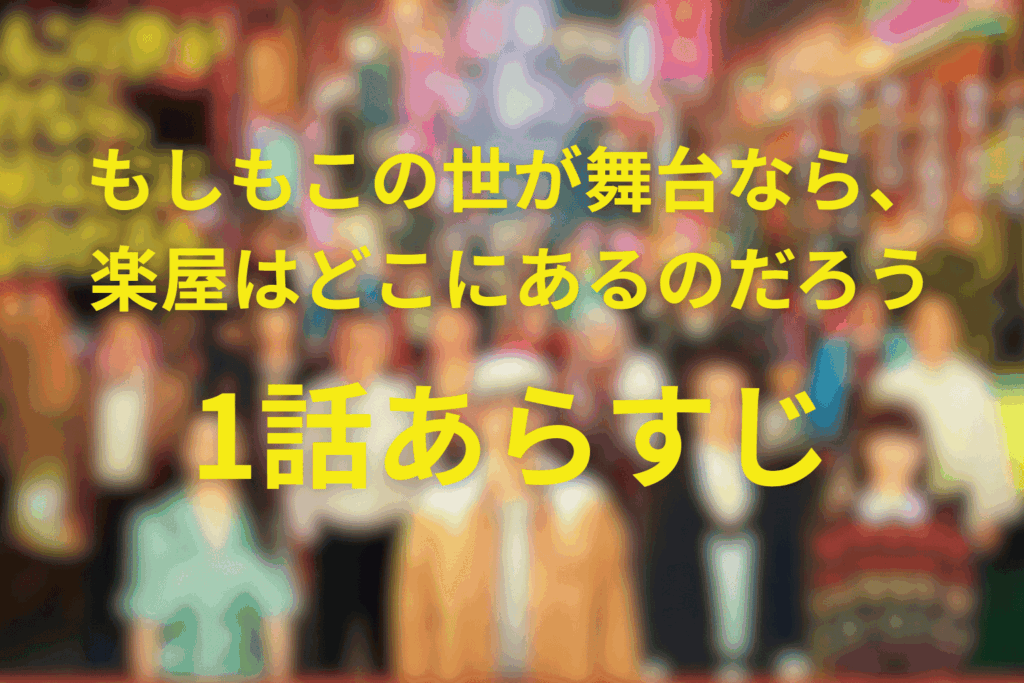
フジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、1984年の渋谷を舞台に描かれる青春群像劇です。
物語の始まりは、劇団「天上天下」に所属する演出家の卵・久部三成の転落から。
蜷川幸雄を心から尊敬し、理想のシェイクスピア劇を作りたいと情熱を燃やす久部でしたが、横暴な性格が災いし劇団を追放されてしまいます。行き場を失った彼が迷い込んだのは、ストリップ小屋のネオンが光り怪しい雰囲気を漂わせるアーケード街「八分坂」でした。
渋谷駅から徒歩八分の距離にあることから名付けられたこの街には、シェイクスピア『お気に召すまま』の一節「Pray speak what has happened(何があったか話してごらん)」の言葉が掲げられており、舞台の裏側に導かれるような不思議な空気が流れています。
久部三成の出会いと再生の予感
八分坂で久部を呼び止めたのは、無料案内所に座るおばば。
彼女に導かれて足を踏み入れたのが、小さな「WS劇場」でした。そこで出会うのは、妖艶なダンサー侘田リカ、若き放送作家の蓬莱省吾、そして八分神社の巫女・江頭樹里といった個性豊かな人々。彼らは久部の挫折した心に少しずつ火を灯し、再び演劇へと向かわせる存在となります。
周囲を取り巻く人々も濃厚です。交番勤務の警官・大瀬六郎、ダンサーのパトラ鈴木や毛脛モネ、ジャズ喫茶のマスター風呂須太郎など、八分坂で生きる人々が次々に登場。彼らは表舞台には立たないものの、それぞれが夢や挫折を抱えており、舞台裏の人間模様が織りなされていきます。
舞台裏に潜む秘密
第1話のサブタイトルは「ここは八分坂」。久部がたどり着いたこの街は華やかさの裏に陰を秘めており、劇場の中ではオーナー・ジェシー才賀や秘書の乱士郎、支配人の浅野大門とその妻・フレが運営に奮闘しています。赤字経営に悩みながらも舞台を守ろうとする彼らの姿に、久部は再び情熱を取り戻す兆しを見せます。
また、「何があったか話してごらん」という言葉が象徴するように、登場人物の過去や秘密が徐々に明かされる構成が仕込まれているのも特徴です。まだ第1話では深い謎までは明示されませんが、久部が再生の道を歩むために避けて通れない人間模様が、舞台裏で静かにうごめき始めています。
シェイクスピアへのオマージュ
本作にはシェイクスピア作品へのオマージュが随所に散りばめられています。
タイトル自体が「全てこの世は舞台、人は皆役者に過ぎぬ」という名台詞をなぞっており、登場人物の名前や店の名称もシェイクスピアの戯曲から取られています。久部の視点だけでなく、視聴者自身も「舞台=人生」として物語を重ね合わせて楽しめる構造になっているのです。
まとめ
第1話は、久部三成が劇団を追われ八分坂に迷い込み、WS劇場の人々と出会うまでが描かれました。まだ彼は自分の居場所を見つけられずにいますが、劇場の裏側での交流を通じて再生の一歩を踏み出しつつあります。青春群像劇として、夢や恋愛、秘密が交錯する物語の序章として十分な濃度を持った回でした。
この作品は「楽屋=舞台裏」をテーマに据え、人生そのものを演劇に重ね合わせる構造を持っています。第1話はその設定を丁寧に提示し、今後久部や周囲の人々がどのように交わり、何を失い、何を得ていくのかを期待させる内容でした。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)第1話の感想&考察
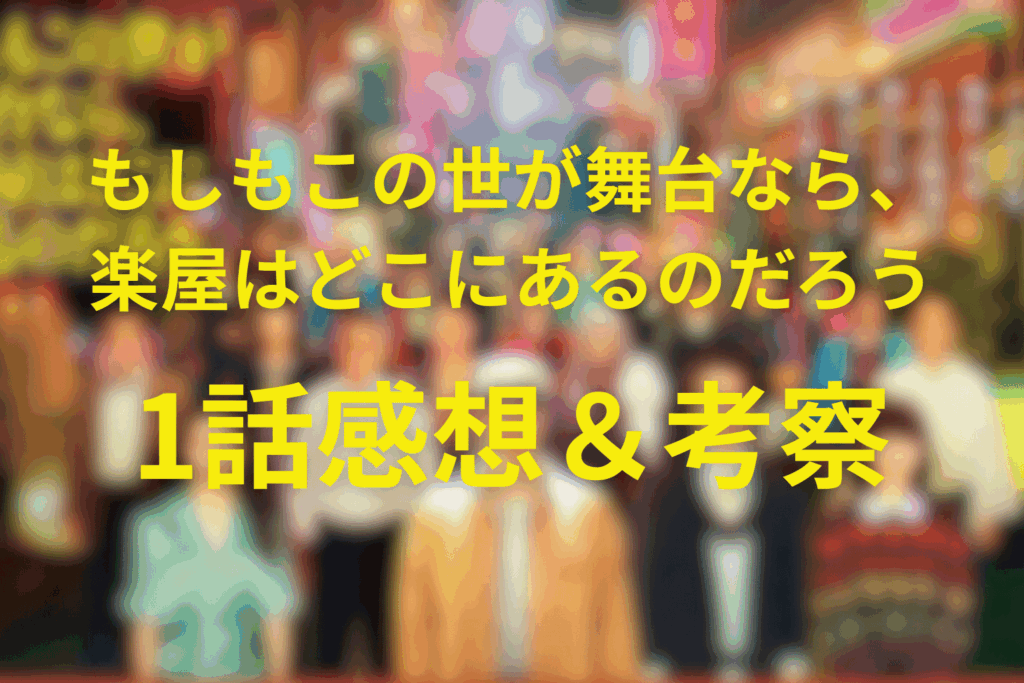
80年代渋谷の息吹
第1話を視聴してまず圧倒されたのは、舞台となる1984年の渋谷を再現した巨大セットの完成度でした。八分坂という架空のアーケード街は、雑多で猥雑な昭和の香りを閉じ込めたかのように息づいています。
ネオンの輝き、ストリップ小屋のけばけばしい看板、劇場内のタバコの煙や古びた椅子の質感。細部に宿るリアリティが、視聴者を一気にタイムスリップさせます。
特に印象的だったのは、アーケードの天井に掲げられた「Pray speak what has happened(何があったか話してごらん)」という英文。シェイクスピアの戯曲から引用されたこの言葉は、物語全体のテーマを示す鍵であり、登場人物たちの過去と秘密を暴き出す呪文のように響きました。
久部三成という主人公の造形
主人公・久部三成は、自信家で横暴、しかし演劇にかける情熱だけは人一倍という青年です。尊敬する蜷川幸雄を追いかけ、「自分こそが演出家として時代を変える」と信じて疑わない。けれどもその強烈なこだわりが裏目に出て、所属劇団を追放され、孤独の中で八分坂へと流れ着きます。
菅田将暉の演技は、久部の激情と脆さを繊細に表現していました。虚勢を張りつつも、挫折に震える目の奥には自分を信じたい必死さが宿っている。自業自得の転落でありながら、なぜか彼を応援したくなる不思議な引力を持っていました。おそらく今後、WS劇場や八分坂の住人たちと関わることで、久部は少しずつ他者を受け入れ、本当の意味での「演出家」へ成長していくのでしょう。
脇役たちの存在感
物語を彩る脇役たちのキャラクター造形も鮮烈です。
- 倖田リカ(二階堂ふみ):妖艶さと影をまとったダンサー。二階堂のしなやかな存在感が、リカという人物の謎めいた魅力を際立たせていました。
- 蓬莱省吾(神木隆之介):若手放送作家。飄々とした軽やかさがありながら、どこか底知れぬ才気を感じさせ、まさに「若き日の三谷幸喜」を投影したような人物。
- 江頭樹里(浜辺美波):八分神社の巫女。清楚で凛とした立ち姿が、荒んだ八分坂に清涼剤を注ぎ込んでいました。
加えて、交番勤務の熱血警官・大瀬六郎、劇場を支える姉御肌のパトラ鈴木、子を抱えて舞台に立ち続ける毛脛モネなど、それぞれの人物が八分坂という「裏の舞台」で生きていることを強烈に印象づけます。彼らの小さな人生の断片が折り重なり、一つの大きな物語へと昇華していく群像劇の醍醐味を感じました。
三谷幸喜らしさとシェイクスピアの融合
本作の脚本を手掛ける三谷幸喜は、25年ぶりにゴールデン帯に戻ってきました。
第1話から感じられたのは、舞台的な構造を活かした独特のリズム。会話劇のテンポの良さ、登場人物たちが「役割」を持って舞台袖から現れるかのような演出は、まるで観客が舞台を覗き見ているかのようでした。
さらにシェイクスピアの要素が絶妙に組み込まれています。登場人物や店舗の名前に散りばめられた引用、物語全体を「人生=舞台」として捉える構造。古典と現代、そして1980年代の若者文化が融合し、視聴者を知的に刺激する仕掛けとなっていました。
第1話の意義と今後の展開
第1話はあくまで導入編。久部が劇団を追われ、八分坂へ流れ着き、WS劇場や住人たちと出会うまでが描かれました。大きな謎はまだ動き出していませんが、「八分坂の裏に潜む秘密」と「登場人物たちの過去」が今後じっくりと明かされていくことを示唆しています。
考察すべきポイントは次の通りです。
- 久部の再生物語:自分本位な彼が、八分坂の人々と交わることで演出家として必要なものを学んでいく過程。
- シェイクスピア的構造:各キャラクターがシェイクスピア作品のテーマや役柄に対応している可能性。
- 八分坂の秘密:アーケードに刻まれた言葉が示す通り、住人たちの過去が物語の核心に迫る。
- 恋愛模様:久部とリカ、久部と樹里など、舞台裏で交錯する人間関係が群像劇をさらに厚みあるものにする。
結論:1980年代青春群像劇の新境地
『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第1話は、昭和の渋谷を背景に、夢と挫折を抱える若者たちの交錯を描いた序章でした。ノスタルジーと知的遊び心が溶け合い、三谷幸喜らしいユーモアと群像劇の手腕が随所に光ります。
久部三成が再び舞台に立つまでに何を得て何を失うのか。八分坂という「舞台裏=楽屋」で明かされる秘密とは何か。観る者の想像力を掻き立てる第1話でした。
今後、WS劇場で実際に上演される舞台や、八分坂の住人が抱える葛藤と秘密が一つずつ明かされていくことで、物語はさらに厚みを増していくでしょう。久部が「舞台」と「楽屋」をどう捉え直すのか。その答えを見届けるために、次話が待ち遠しくてなりません。
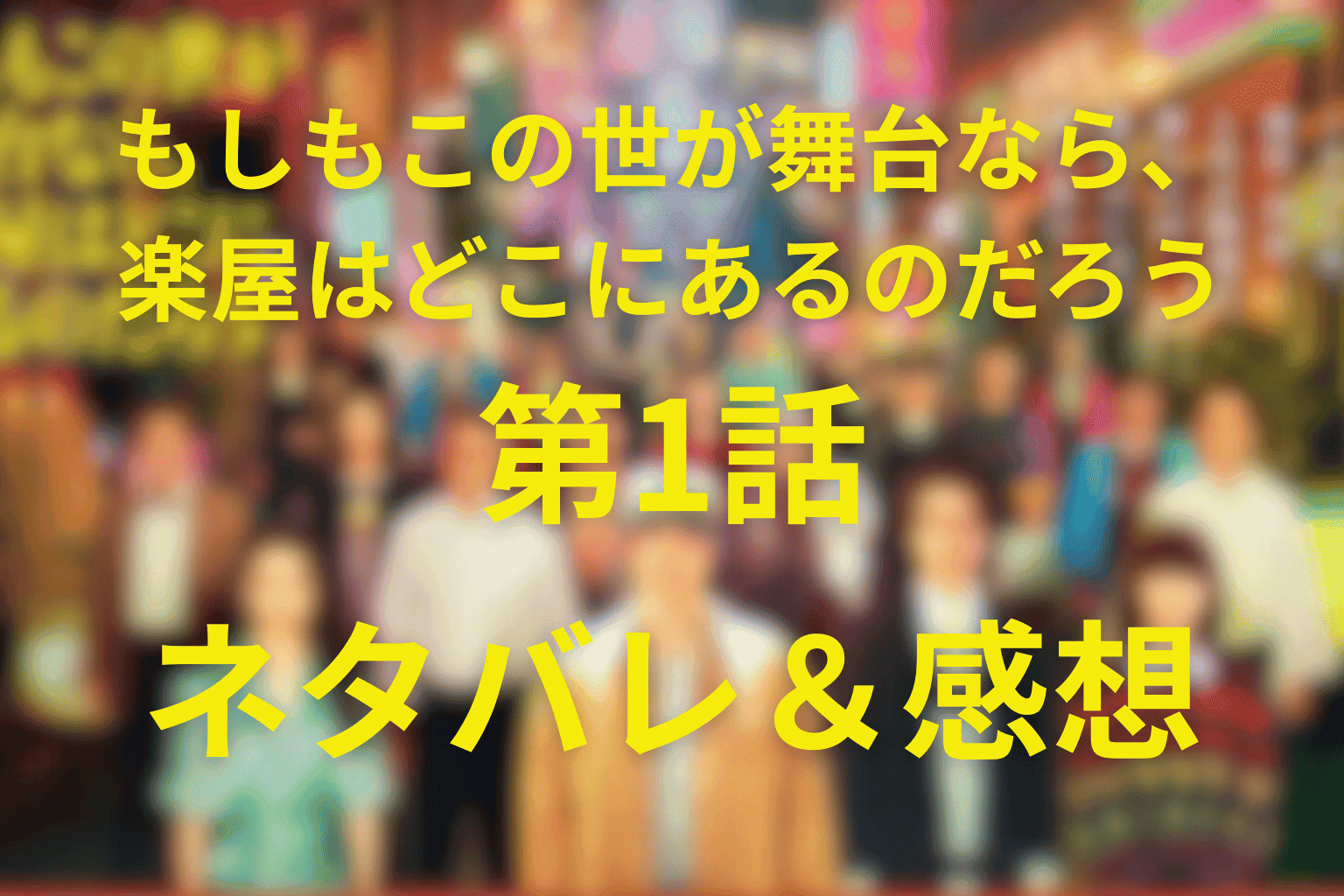
コメント