第1話「橙色の殺人」でキントリが再始動した『緊急取調室』。
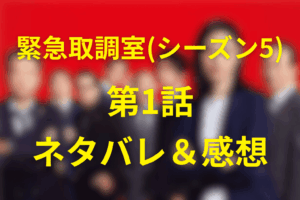
第2話「鈍色の鏡」では、炎上キャスター・倉持真人(山本耕史)と妻・利津子(若村麻由美)を同時に取り調べる“禁じ手”が展開される。
妻の自白で幕を開けた夫婦の物語は、やがて“歩けない男が立つ”という衝撃の転倒劇へ。
そして「眠った子は重い」という一言が、父の最期の覚悟を照らす。
正義を装うメディアと、愛を装う家族――その“鏡合わせ”を、キントリはどんな言葉で映し出すのか。
緊急取調室/キントリ(シーズン5)2話のあらすじ&ネタバレ
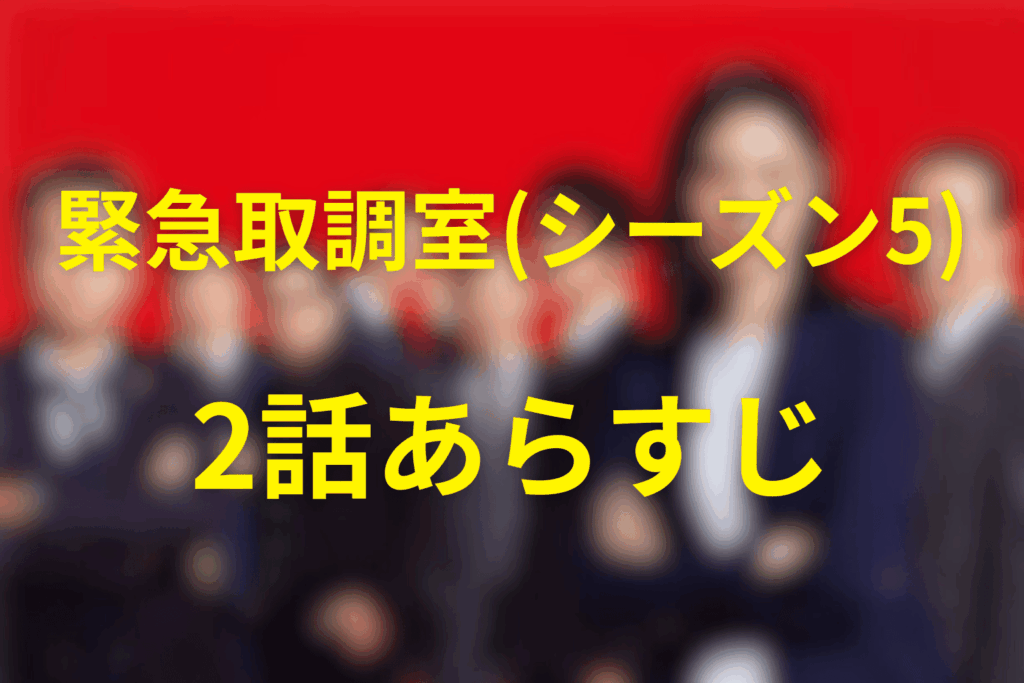
第2話のサブタイトルは「鈍色の鏡」。
第1話で炎上キャスター・倉持真人(山本耕史)の父・磯貝信吾(竜雷太)が“ペンチ”で殺害された事件が続く。
再開発絡みのA線(国家プロジェクト幹部2名の連続殺人)は“真犯人”の自白で実質決着。
しかしその“真犯人”は磯貝殺害(B線)だけを否認する。
ここからキントリは、倉持と別居中の妻・利津子(若村麻由美)を相手に同時聴取という“禁じ手”に踏み込む。物語の中心は、夫婦の言葉が互いを照らし合う“鏡合わせ”だ。
「夫婦同時聴取」という段取り――“ふたりの物語”を同じ時間に並べる
放送日は2025年10月23日(木)。
公式ストーリーが示す通り、キントリは「一刻も早く、かつ確実に」真相に迫るため、前代未聞の夫婦同時聴取を選択する。
「倉持の父親を殺したのは私です。夫もそれを知っています」という利津子の爆弾証言が、取調室の空気を一変させる導火線となる。
キントリは別室で取り調べ中のふたりを“会話させる”段取りを組み、互いの供述をリアルタイムに照射。
言葉のズレをその場で重ね合わせ、真実を炙り出す――まさにキントリ流の知的格闘だ。
夫婦W豹変――利津子が“自白”を引っ込め、倉持が崩れる
中盤、利津子が供述を一転させる。
「私は彼(夫)を警察に呼び出すために自白したの」。
さらに、倉持が証拠品を廃棄していた現場を見ていたことまで明かす。
流れは一気に逆回転し、“夫婦W豹変”が第2話最大の見せ場となる。
同情を装った自白が真犯人を追い詰める“誘導”へと反転し、倉持の鎧が崩れていく。愛情と欺瞞が交錯する取調べの攻防は、シリーズ屈指の緊迫感を生んだ。
「車いすキャスター」の秘密――思い込みを打ち破る立ち上がり
追い詰められた倉持はついに自らの罪を認めるが、同時に「どうやって被害者を運んだのか」という最大の疑問が残る。
ここで小石川春夫(小日向文世)が問いを投げると、倉持は手すりを使って自力で立ち上がる。
「事故で足首を損傷したが、杖があれば立てた。『車いすのキャスター』の方が通りがいいと思った」
視聴者もキントリも信じていた“歩けない”という大前提が崩壊する瞬間だ。思い込みを壊すための“身体の演出”が、取調室の中央で起こる。
「軽かった」理由――眠ると“重い”のに、なぜ父は“軽い”のか
倉持は「睡眠薬で眠らせた父をおぶって運んだが、驚くほど軽かった」と語る。
有希子(天海祐希)は「眠った子どもは重い。しがみつく力が抜けるから」と切り返し、磯貝は眠っておらず、自ら体を支え“軽く”なっていたのではと示唆する。
さらに小石川が「台所の食器が洗って伏せてあった」と指摘。
父は“最後の晩餐(親子丼)”を済ませ、死を覚悟していた。
――被害者が“覚悟”で息子の嘘を軽くしたという、胸を締めつける真相に到達する。
決着――“鈍色の鏡”に映ったのは、父の愛と息子の虚飾
結末として、真犯人は倉持。
だが物語は「誰が殺したか」を越え、「何を映してきたか」へと到達する。
鈍色=曖昧で光を鈍らせる色は、メディアの顔(車いすキャスターの“装い”)と家族の顔(父子の拗れ)が混ざり合う鏡面の比喩だ。
第2話はその鏡を磨くのではなく、曖昧さごと映し切る。
だからこそ痛い。
サブタイトル“鈍色の鏡”の通り、そこに映ったのは父の覚悟と息子の虚飾だった。
付記:数字と文脈
放送翌日の報道によると、世帯視聴率は9.3%、個人視聴率は5.2%(関東地区)。
解決編としての“強い体感”が数字にも表れた。シリーズは12月26日(金)公開の劇場版『THE FINAL』へと連動して進行。
主題歌は緑黄色社会「My Answer」。
選択と後悔のあわいを歌う詞世界が、第2話の“親子の選択”と美しく重なっていた。
緊急取調室/キントリ(シーズン5)2話の感想&考察
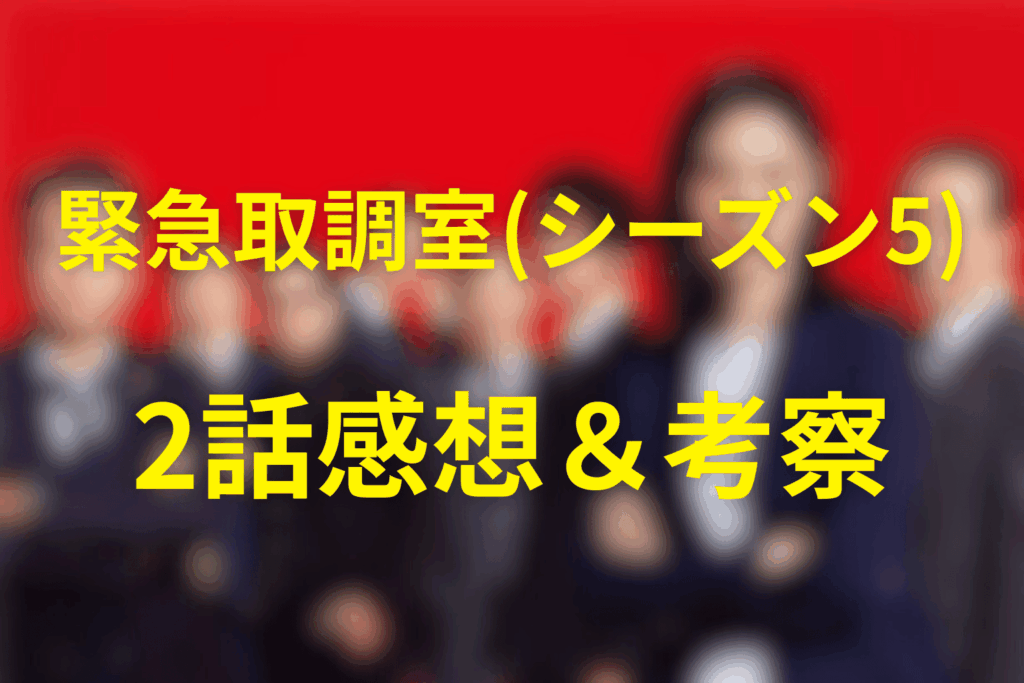
第2話は、手続き(同時聴取)→前提の崩壊(歩ける)→感情の逆流(“軽かった”の謎)という三段ロジックで押し切った。
ここからは、筆者の視点でその仕組みと余韻を掘っていく
同時聴取は“手続きで攻める”心理戦の完成形
同時聴取は派手な演出ではなく、証言の“鏡合わせ”をリアルタイムで発生させる装置だ。
時差のある取り調べでは、相手の物語を“再構成”できてしまうが、同時に並べれば矛盾の温度が下がらない。
実際、利津子が“自白”を引っ込めた瞬間に空気が反転し、倉持は「自分のために犠牲になる妻」という免罪符を失った。
手続きが倫理を可視化する――それがキントリという“プロトコル・ドラマ”の美点であり、心理戦の完成形でもあった。
“思い込み”を破壊する立ち上がり――映像の一手
「車いすのキャスター=歩けない人」という視聴者の思い込みを、倉持が立ち上がるというワンカットで粉砕する。
説明の段落を重ねるより、この“身体の一発”が圧倒的に効く。
自ら“虚飾のブランド”を選び取ったと告白する姿は、職業倫理やメディアへの皮肉にもなっていた。
“正しさを装う虚飾”を、“正しさの装置(取調室)”で剥がす――装い同士の対決が痛快だった。
言葉→物理→感情の順序――“軽い”が連れてくる重さ
「眠った子は重い」という生活の実感から逆算し、「父は眠っていなかった」へ至る論理展開が秀逸だった。
台所の伏せられた食器や“親子丼”の記憶が、“最後の晩餐”という覚悟の時間へ一本につながる。
犯行の責任は消えないまま、父の愛だけが耐えがたい重さで立ち上がる。犯人暴きで終わらず、“覚悟”を描き切ったことが今期第2話の価値だ。
「鈍色の鏡」という題の射程
鈍色(にびいろ)は、光を飲み込み輪郭を鈍らせる色。
ニューススタジオのガラスやモニターの“正しさの光”と、家庭のキッチンに差す鈍い光が対位法的に配置されていた。
メディアの顔と家族の顔、どちらにも嘘が混じる。
鏡は磨かれても、映る“私”が曖昧なら輪郭は鈍い。
キントリは鏡を割らず、曖昧さごと映す。
第2話は、その流儀をもっとも鮮明に見せた回だった。
“夫婦W豹変”の脚本術――利津子は“情”ではなく“戦略”
利津子の“自白”を情ではなく戦略として反転させる脚本は、人物の知性を損なわない丁寧な書き方だ。
「私が罪を被ってくれると思ったの?」という一言は、夫婦の力学を明確に切り取る。
被害者の父と加害者の息子の線に、夫婦の線を直交させ、言葉の連立方程式で解を導く。
井上由美子脚本らしい、“言葉の設計”の快感がここにある。
シリーズ文脈:数字・主題歌・劇場版へ
視聴率は世帯9.3%/個人5.2%を記録し、解決編としての満足度を裏づけた。
主題歌・緑黄色社会「My Answer」は、“選択を自分の答えにする”という詩世界で、倉持が選んだ虚飾と磯貝が選んだ覚悟、その対比をやさしく包み込む。
12月26日(金)公開の劇場版『THE FINAL』へ向け、手続き(同時聴取)と政治(総理の事情聴取)をつなぐ“大きな鏡”がいよいよ見え始めた。
ロジック総括
原因:妻の“戦略的自白”→同時聴取の手続き化/「歩ける」という前提の崩壊/「軽かった」という物理的違和。
作用:思い込みが壊れ、言葉の鏡に本音が滲み出る。父の覚悟という感情の真芯が露出する。
結果:犯人特定の爽快感に留まらず、“正しさの装い”とどう向き合うかという倫理の余韻が残る。
取調室は、嘘を暴く場所ではなく“言葉を配置していく装置”だ。
第2話は、その哲学を最短距離で提示した。次回、キントリがどんな“鏡”を持ち込むのか――その手続きの美学を楽しみにしたい。
緊急取調室/キントリ(シーズン5)の関連記事
キントリ全話のネタバレはこちら↓
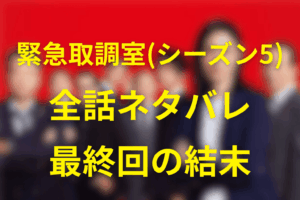
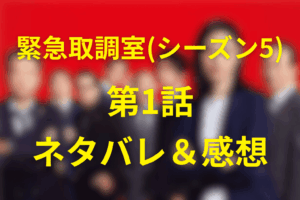
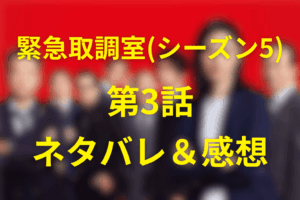
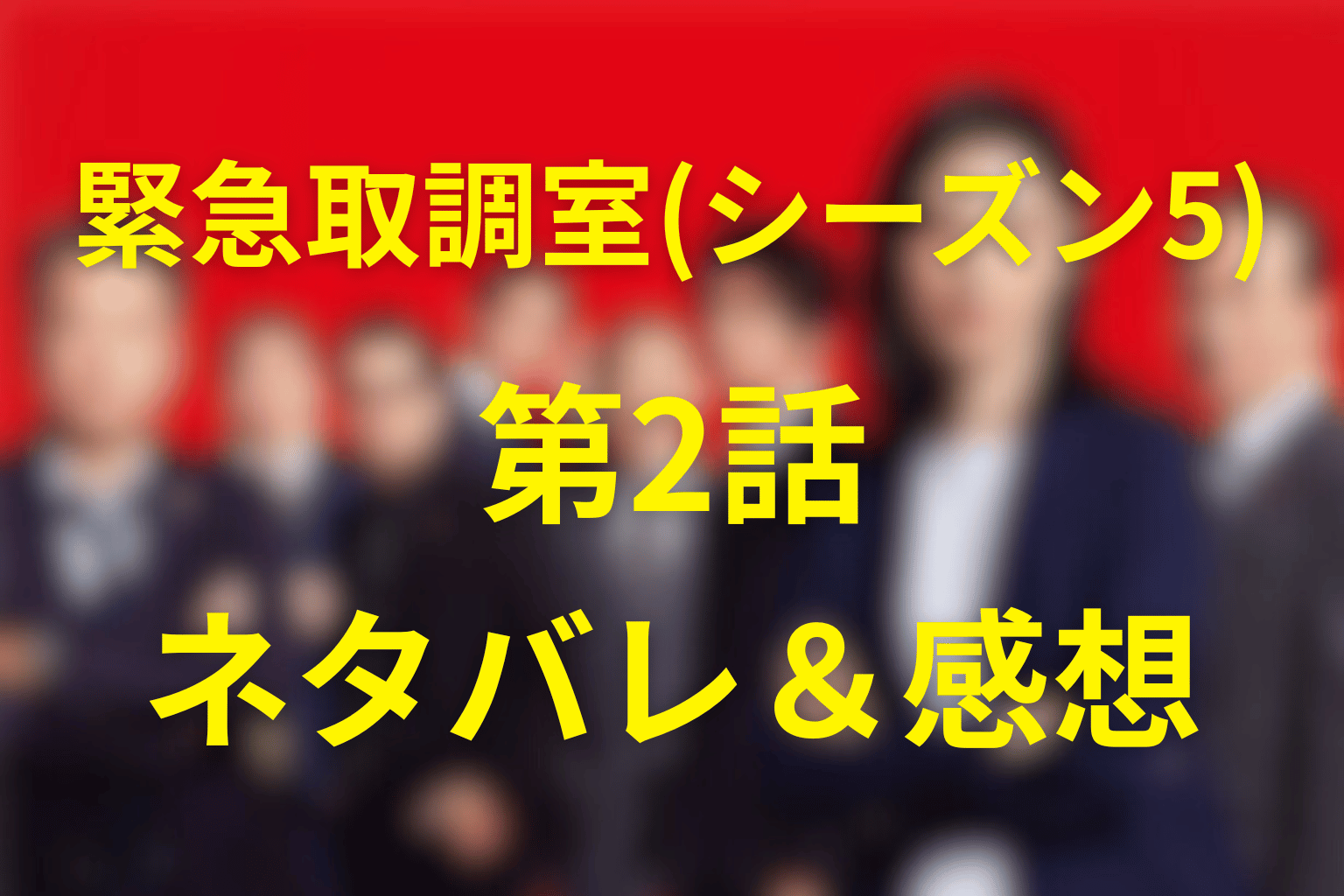
コメント