第4話で“観察する者とされる者”の構図が動き始めた『シナントロープ』。
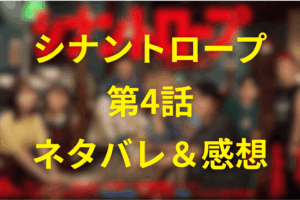
第5話では、そのズレがついに人の心の奥へ踏み込む。
タイトル「空を飛べたらいいのに」は、幼い頃に父親から閉じ込められたという水町(山田杏奈)の告白と響き合い、
“飛ぶ”=外へ出る/自分で生き方を選ぶという意味を帯びていく。
一方、都成(水上恒司)は“観察”を通して彼女に寄り添おうとするが、その行為が信頼を壊す結果に。
“会話”と“観察”の矛盾を軸に、人が他者とどう向き合うかを問う静かな傑作回だ。
シナントロープ5話のあらすじ&ネタバレ
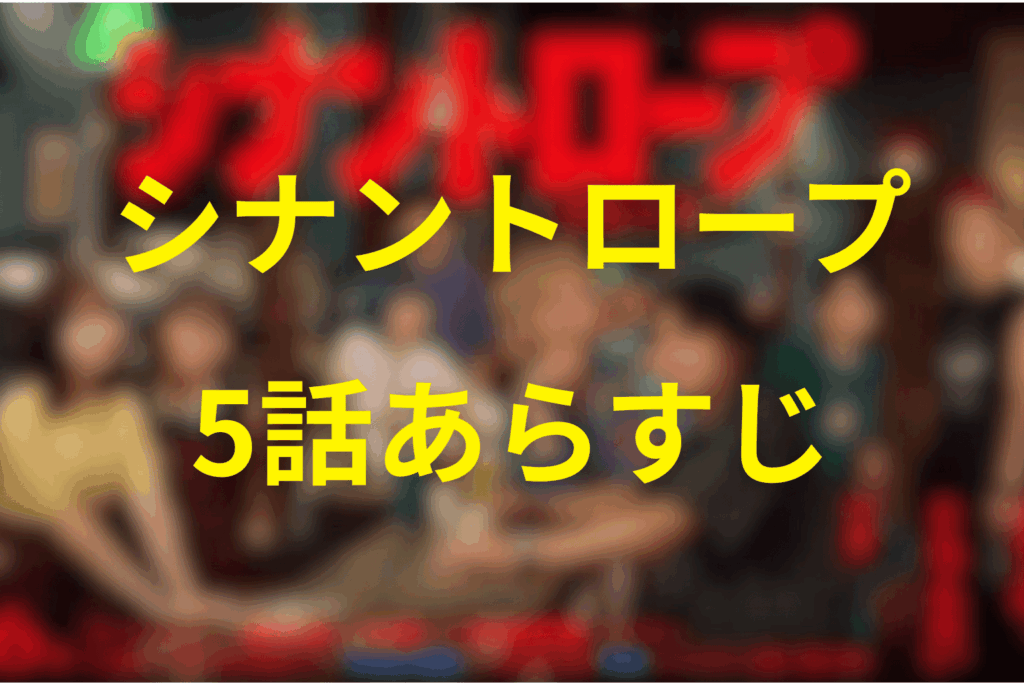
第5話の副題は「空を飛べたらいいのに」。
バーガーショップ〈シナントロープ〉で積み重なってきた“会話”と“観察”のズレが、いよいよ人物の素顔へ切り込む回だ。
物語の入り口は、塚田(高橋侃)のライブ当日。
都成(水上恒司)が店に入ると、帳簿を広げたまま眠っている水町(山田杏奈)の姿がある――ここから、一日が静かにほつれ始める。
ライブ当日の朝──「帰れていない」水町、「声をかけたい」都成
物語の核はシンプルだ。
水町は家に帰れず、大学にも通えていない。都成は声をかけるきっかけを探し、昼へ連れ出そうとする。
しかし、そこに“他人の手”を挟んでしまったことが、失敗の芽となってしまう。
“志沢メモ”作戦は即座に破綻──「訊きたいことがあれば直接訊けばいいじゃん」
都成は志沢(萩原護)が書いた“会話メモ”を頼りに、水町をランチへ誘おうとする。
だが水町はそれを一瞬で見抜き、「志沢を使って嗅ぎ回ってる」と鋭く指摘。そして「訊きたいことがあれば直接訊けばいいじゃん」と言い放つ。
このやりとりによって、都成の“観察の介在”が逆効果だったと示され、ふたりの距離はかえって遠のいていく。
“観察”と“会話”のズレが、物語全体のトーンを決定づける重要な場面である。
「5歳のとき、父親に家へ閉じ込められていました」──水町の封印された記憶
第5話の転機は、水町が幼少期の虐待=監禁を語るシーンだ。
「私は5歳の時、父親によって家に閉じ込められてました」という衝撃の一言が、“飛ぶ”=外へ出る/逃れるというモチーフを一気に濃くする。
“閉じ込められること”と“外へ出たいという願い”が、水町という人物の核として露わになる。タイトルの「空を飛べたらいいのに」は、この告白の延長線上で響き合う。
それぞれの過去が騒ぎ出す──木場・志沢・“バーミン”側の断片
物語後半では、登場人物たちの過去が同時にざわめき出す。
木場(坂東龍汰)が「なんかつれぇ過去でもあったのか?」と問われ、卒業文集を踏みつけるショット。
志沢が都成へ「告白しましょう」「人が人に恋をする条件、今整いました」と詰め寄るシーン。
さらに、龍二(遠藤雄弥)と久太郎(アフロ)が「全部聞き出さねぇと終わんねぇ」と焦りを募らせる場面。
〈バーミン〉側が“核心”ににじり寄る構図が提示され、店側/裏社会側、二つの観察が互いを刺激し始める。
「空を飛べたらいいのに」──タイトルが示す痛みと憧れ
副題の「空を飛べたらいいのに」は、水町の台詞と呼応する。
幼少期に閉じ込められた彼女にとって、“外へ出たい”“上へ逃れたい”という感情は本能に近い。同じ日に置かれた塚田のライブ=音楽で上昇する時間が、その願いを象徴する。
“飛ぶ”ことを願う者と、“飛べない”現実に絡め取られてきた者。店という閉じた空間に、それぞれの垂直方向――落下と上昇――を重ねた設計が印象的だ。
折田と“シマセゲラ”の影──店の外側で進む「観察の極み」
一方、店の外では〈バーミン〉の折田(染谷将太)が“殺し屋シマセゲラ”を追っている。
部下の睦美(森田想)を使って探索を進める中で、「シマセゲラはずっと水町ことみのそばで見守っている」という言葉が登場する。
折田サイドの観察が、水町の物語に急接近していることを示す伏線であり、店の“内側”と“外側”がついに交差し始めたことを暗示している。
1日の終点へ──“会話”と“観察”の矛盾が、ふたりの距離を決める
第5話は、“会話(直接訊く)”と“観察(第三者を介す)”の矛盾を序盤に置き、中盤で“過去の告白”を挟み、終盤でそれぞれの過去が騒ぎ出す予兆を散りばめて終わる。
塚田のライブという“上昇”の時間がありながら、都成と水町の間には“うまく届かない言葉”が残る。
それでも、一度交わった視線が確かに何かを変えた。
この静かな余韻が、第6話「心配すんな、お前はひとりだ」へと橋を架ける。次回は、“孤独”という言葉の定義そのものが問われる展開になるだろう。
シナントロープ5話の感想&考察。
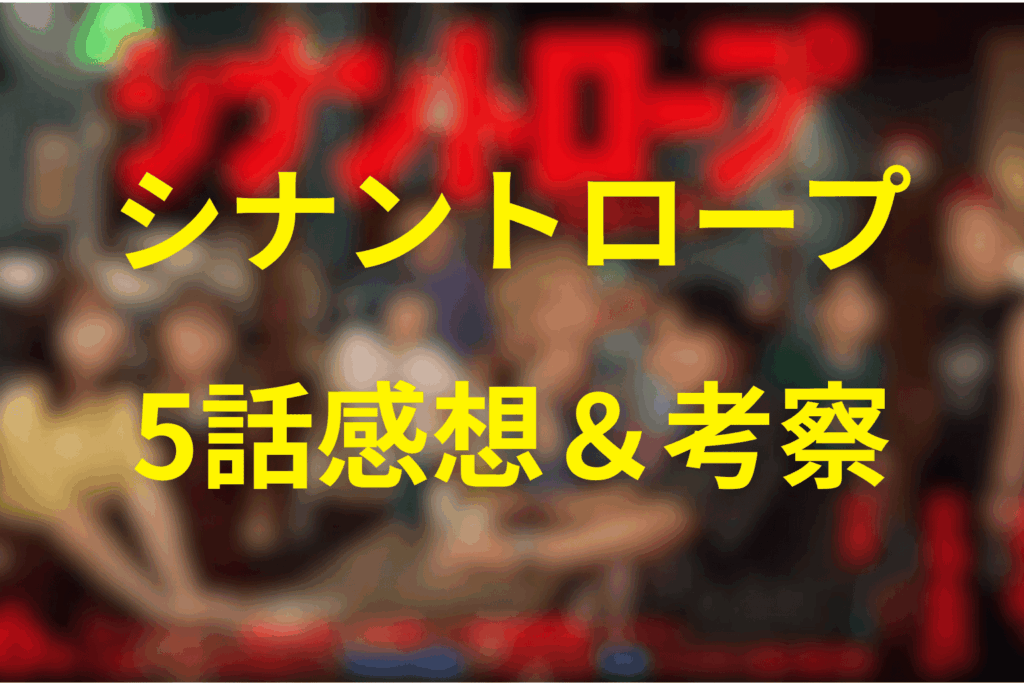
第5話を視聴して強く感じたのは、「会話」と「観察」の矛盾が、そのまま人間関係の難しさとして機能しているということだ。
都成は“よかれと思って”観察を介在させ、結果的に自分の主語を他人へ譲ってしまう。
一方で水町は、言葉で踏み込まれること自体に、幼少期の体験から来る痛みを抱えている。観察に頼る→だから直接の信頼が生まれない→その結果、告白が重く、遅れてやってくる。
この因果のリズムこそ、本話の手触りの核心だった。
タイトルの意味論──「飛ぶ」は“逃げ”ではなく“自由の語彙”
「空を飛べたらいいのに」は、単なる現実逃避の言葉ではない。
閉じ込められた空間から外へ出たい、地面に縛られた視線を解き放ちたい、自分で到達点を決めたい――そうした“自由”の語彙である。
幼少期の監禁告白(「5歳のとき父親に閉じ込められていた」)が示すのは、出口のなかった時間の記憶。
“飛ぶ”とはその出口を自らの意思で獲得することだ。出口のない時間→だから上へ、外へ→そしてライブ(音楽)の上昇感が同日に重ねられる。
副題がその感情の軌跡を的確に言い当てている。
都成の失敗学──“観察の介在”が信頼を毀損する瞬間
都成は志沢メモという第三者の観察を挟んだ。
善意ではあったが、その瞬間、主語は都成から志沢にすり替わる。
水町の「直接訊けばいいじゃん」という言葉は、その移譲に対する正確な拒絶だ。観察で“安全”を確保しようとすれば、自分の言葉は立たなくなる。
信頼は、リスクを伴う直接の会話の中でしか育たない。この失敗が、今後の都成が“自分の言葉”で踏み出すための必然を作った。
ドラマとして、あえて一度つまずかせる設計の丁寧さが際立っている。
“バーミン”の観察術──店の外で進む“もう一つの会話”
折田サイドは、徹底的な観察によって物語を動かす存在として描かれる。
“シマセゲラ”という見えない他者を追い、睦美が情報を集めて束ねる。
第5話では、龍二と久太郎の「全部聞き出さねぇと終わんねぇ」という台詞が象徴的だ。
観察が積み上がる→だから“聞き出す”=暴力の一歩手前に近づく→結果として、店=会話の場と衝突する。観察が尋問へと転化する危うさを、ドラマはギリギリの地点で止めて見せる。
その“引き際”のセンスが、シリーズ全体のバランスを保っている。
“考察祭り”と作り手のスタンス──構造より“呼吸と衝動”
監督・此元和津也はインタビューで「次は感情一本で突き進む、一筆書きのようなものを」「伏線は敷かず、回収もしない」と語っている。
視聴者の“考察祭り”が盛り上がる中でも、作り手は“呼吸と衝動”を優先する姿勢を崩していない。
第5話で水町の告白を“説明”ではなく、呼吸の乱れと“間”で見せた演出は、そのポリシーの実践そのもの。
構造の巧さに頼らない→だから人物の呼吸を撮る→結果、視聴者の身体感覚に届く。感情の生々しさを、理屈ではなく身体で刻む方向にシフトした手触りが鮮やかだった。
鳥の比喩体系──“シマセゲラ”“キバタン”“フクロウ”
シリーズ全体に、鳥のモチーフが連続的に仕込まれている。
木場の“キバタン”、里見の“フクロウ”は、それぞれ人物像を示す暗喩であり、折田が追う“シマセゲラ”は“見えない殺し手”でありながら、“守護者”としての側面も併せ持つ。
第5話で語られた「シマセゲラはずっと水町のそばで見守っている」という断片は、敵と味方の境界を揺るがす仕掛けとして作用している。
鳥=観察者・夜行性・上昇という性質を導入し、人間関係に“距離と高さ”の語彙を持ち込むことで、タイトル「飛ぶ」とも有機的に連動している。
総括
第5話は、謎解きの“面白さ”よりも、人間の“しんどさ”と“希望”を撮る回だった。
都成が“観察”から“会話”へと舵を切るなら、初めて同じ高さの目線が生まれるだろう。
「空を飛べたらいいのに」という願いが、比喩ではなく現実の歩みに変わる――その準備を終えた一本だった。
シナントロープの関連記事
シナントロープの全話ネタバレはこちら↓
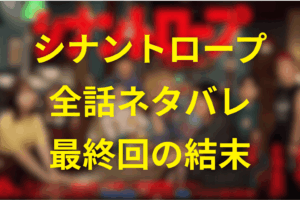
4話についてはこちら↓
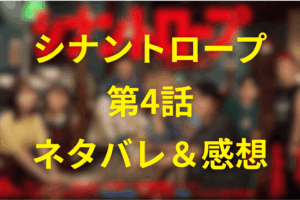
3話についてはこちら↓
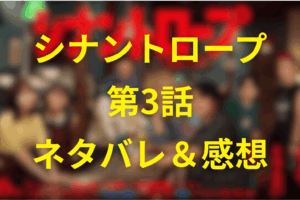
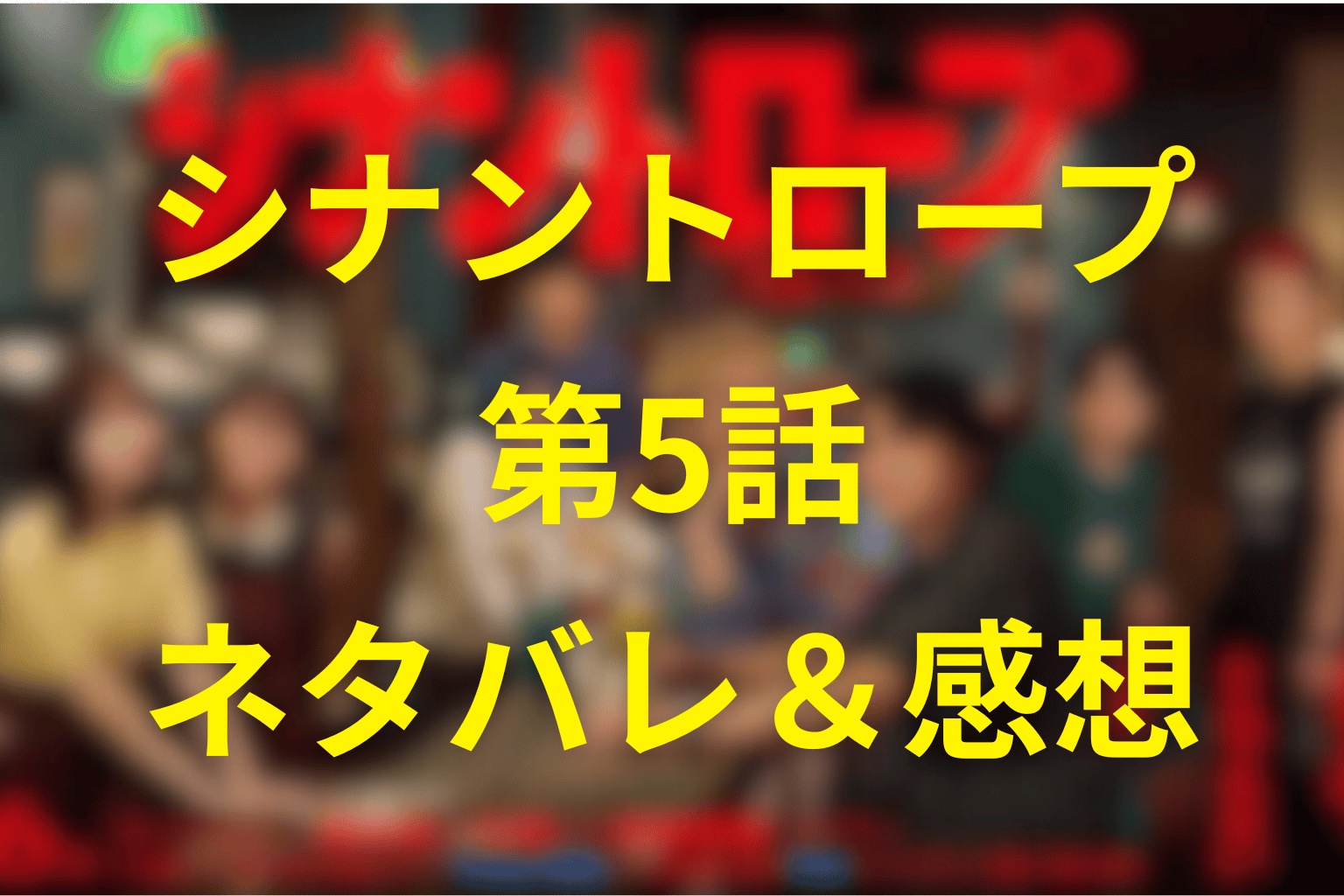
コメント