第9話で「承知しました」が涙に変わった三田。

最終回では、その涙の先にある“笑顔”が描かれる。
亡き夫と息子の幻影に苦しみながらも、阿須田家の生活に戻った彼女は、再び“家族を不幸にしてしまう”という呪いと向き合うことになる。
母への感謝状を破り、書き直させた言葉、希衣の手を握り返す温もり、そして「もう、そっちへ連れて行って」とこぼした夜——
それでも彼女は、生きる側に立ち続ける。
最終回『家政婦のミタ』は、“依頼で動く機械”だった三田が、初めて“自分の意思で笑う人間”へと変わる、静かな奇跡の物語だった。
家政婦のミタ10話のあらすじ&ネタバレ
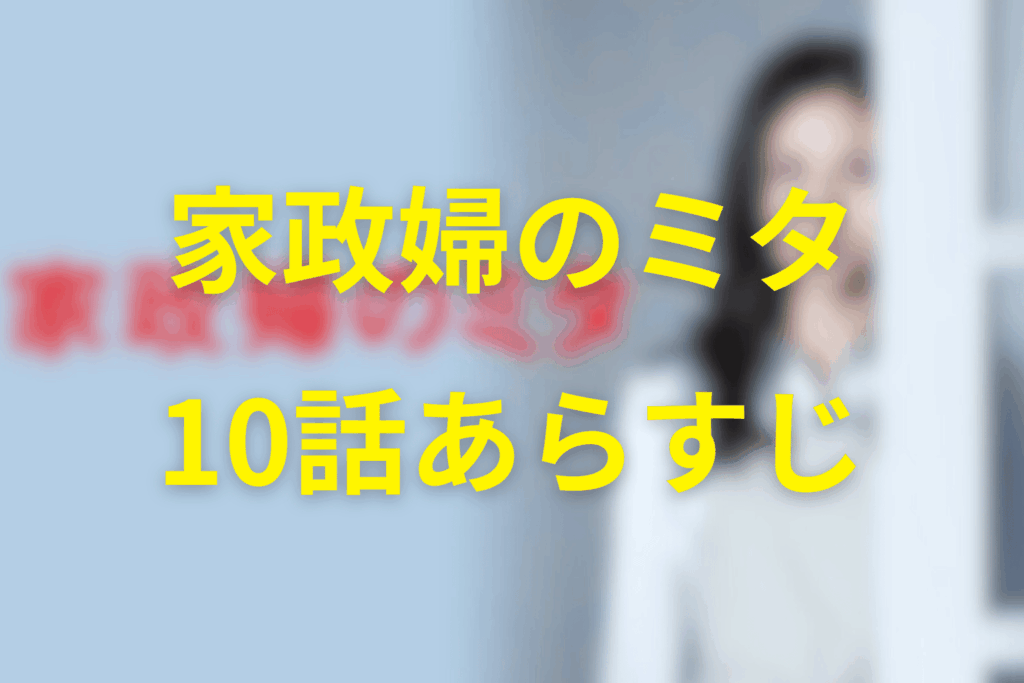
第9話で阿須田家に戻った三田灯(松嶋菜々子)は、家族の団欒にふっと重なる亡き夫と息子の幻影に悩まされ始める。
食卓、買い物、何気ない会話の瞬間に、もういないはずの“二人”の姿が差し込んでくるのだ。
そんな中、次男・海斗(綾部守人)のクラスで「母への感謝状を授業参観で読む」という課題が出される。
母・凪子は亡くなっている。海斗は“父への作文”に逃げようとするが、三田はその原稿を破り、あえて「お母様への感謝状を書いてください」と促す――初めて“自分の意見”を言葉にして。
三田の“揺らぎ”
再び阿須田家に戻って働き始めた家政婦の三田灯(松嶋菜々子)は、いつになく心乱れる日々を過ごしていました。
亡き夫と幼い息子の幻影が頻繁に現れ、その度に彼女の無表情な仮面の裏側で微細な動揺が走ります。普段は決して感情を見せない三田さんですが、家族団らんの食卓でふと手元が狂い包丁で指を切ってしまうなど、その完璧な家政婦ぶりにほころびが見え始めていたのです。
阿須田家の人々は戻ってきてくれた彼女を温かく迎えますが、三田さん自身は「私は家族ではありません」と自らに言い聞かせるように距離を保っていました。
それでも子どもたちと接するうち、彼女の中で何かが少しずつ変わり始めていたのです。
うららの“けじめ”と、三田の揺らぎ
うらら(相武紗季)は恵一(長谷川博己)への想いを断ち切るためお見合いへ。
事情を知る三田は、のど元まで出かかった言葉をのみ込み、何も言わない選択をする。
紹介所の晴海(白川由美)は「言いたいなら言えばいい」と背中を押すが、三田の表情は固い。線を引く訓練を続けてきた人が、その線の内側に足を踏み入れそうになる――第10話の三田は、そんな“揺らぎ”の入口にいる。
「業務命令」で行くランドセル売り場——幻影が差し込む
祖父・義之(平泉成)からの電話を受けて、希衣(本田望結)のランドセル選びに三田も同行することに。
ただし条件はいつも通り――「業務命令なら」。
カラフルな売り場で「どっちが似合う?」と問われ、指を伸ばしかけた瞬間、耳の奥で息子の声が響く。
「ねえママ、どっちがいい?」。目の前に、夫と息子の幻。
三田は息を呑み、硬く握られた希衣の手で現実にたぐり寄せられる。
それでも三田は笑えない——恵一の唐突な質問
帰り際、恵一は三田に外套や腕時計、ドクターバッグのことをふと尋ねる。暑い日も手放さないそれらは、“亡き人の遺品”の気配を帯びている。
触れてはいけない結界に近づいた問いかけに、三田は短く礼をして背を向ける。
心の守りは、まだ解けない。
うららはお見合いをする…
うららはお見合いをするも…自暴自棄になっている様子。
父親はそんなうららをみて、恵一のことをやっぱり好きなのか…というのを確信する。
母の遺書との決別
海斗は最後まで母への作文を父への作文に変えようと悩んでいた。
三田は自分の意志で海斗が父向けの作文を書こうとした時にその作文を破り捨てる。
更に、三田が母親はきっと死のうとしたした時…最後には生きたいと思っていたと助言。
自分がそうだったからだと言います。
家族全員で母親の遺書をライターで燃やし、嫌な記憶との決別をした。
「母へ」の作文——教室の静けさ
海斗は迷いながらも「母への感謝状」を書き上げる。
授業参観当日、自ら手を挙げて読み上げる海斗。ざわめいた教室は、いつしか静かになる。
「ぼくはお母さんの子でよかった」――その一文が空気を変える。
読み終わった後に教室は静かになる。ただ、原稿用紙の2枚目にミタからの花丸と「大変よくできました」と書かれており、海斗はよっしゃーと喜んでしまいました。
海斗の背中の奥に、三田の“破ってでも書かせた”意図がうっすらと見え、彼女は廊下からそっと見守る。
キッチンの小さな事故——“不幸にする”という呪い
夕食の支度を手伝っていた希衣がやけどを負い、すぐさま応急処置と病院へ。大事には至らないが、三田の胸中で“自分は周囲を不幸にする”という呪いの言葉が再燃する。
隣のおばさんは夫に追い出されてしまい、その腹いせに「これ以上悪いこと起きる前に消えて」と言うのでした。
彼女の視線は再び遠く、どこにも焦点を結ばなくなる。
遊園地のベンチ——「私もそっちに連れて行って」
夜、三田はいつもの遊園地へ。ファミリーセットを買い、決まった席に座る。
目の前で笑う夫と息子の幻影に、ついに口が動く。
「もう、そっちへ連れて行って」――胸の奥にしまっていた死への誘惑が言葉になった瞬間、彼女の頬を涙が伝う。
第10話のタイトルが、そのまま画面の質感になるクライマックスだ。
三田が目を開けた瞬間、そこには子供たちの姿が…。
子供達はもうここにくるのはやめて…!と言い、三田さんが何度頼んでも、僕達が全部食べるから!と言い、ファミリーセットを食べる。
三田は涙を流しながら「これ以上、優しくしないでください!」と子供達に言う。
でも、子供達は自分達は不幸にならない、どんなことがあっても幸せになる!と言い、更に三田に一緒に帰ろうと言い、帰宅するのでした。
残された時間の予感
三田は阿須田家での職務を続けるが、笑顔は依然として戻らない。
次の瞬間、物語は最終章へ。
「本当の母親…それはあなたたちが決めることです!」へと続く前夜、
三田は阿須田家への情と亡き家族への悔恨の間で、細いロープを渡っている。
家政婦のミタ10話の感想&考察
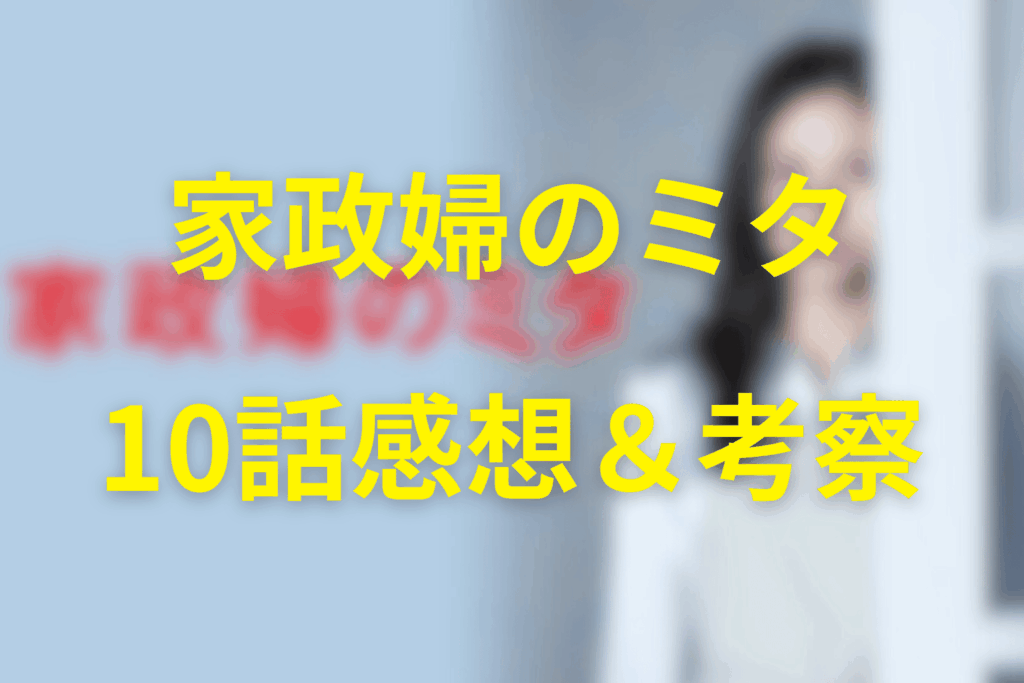
第10話は、“揺らぎ”の物語でした。
三田が“人間の言葉”を取り戻しかけて、でも笑えない身体のまま足を止める。
その微妙な段差を、私は呼吸を浅くしながら見つめていました。
とくに海斗の作文と遊園地のベンチ――「生をつなぎとめる声」と「死へ引かれる声」が、ひと晩の中でせめぎ合う構図が見事です。
「破り捨てる」は、撫でるより優しいときがある
三田が海斗の“父への作文”を破り捨てた行為は、一見乱暴。
でも私はそこに伴走の手つきを感じました。海斗にとって“父へ書く”のは回避であり、“母へ書く”のは直視。
回避の上に置いた言葉は、いずれ剥がれる。だからこそ、三田は上から剝がした。破る音で抉るのではなく、傷が塞がる方向へ連れ戻すために。
結果、海斗は自分の声で「ぼくはお母さんの子でよかった」に辿り着く。
言葉の“主語”が、他人の慰めから自分の肯定へ移った瞬間でした。
「業務命令」の優しさ——ランドセル売り場が開いた心の窓
希衣が発した「業務命令」は、子どもなりの思いやりの翻訳でした。「家族じゃない」と距離を保つ三田に、仕事という言語で好意を渡す。
だから三田は、夫と息子の幻を見ても崩れずにいられた。小さな手に握られて、現実へ帰ることができた。
ここで初めて、阿須田家の“愛”が三田の規範の内側に入るのを見た気がします。
キッチンのやけど——“呪い”はこうして再生産される
希衣のやけどは、物語上の事故でありながら、三田にとっては旧い呪いの再演です。
自分が関わると誰かが傷つく――その思い込みは、過去の放火と喪失から積み上がった自己処罰。やけどが軽傷で済んだ事実よりも、「また私のせいだ」が彼女を支配する。
トラウマの“現在進行形”を、こんなに小さな事故で描けるドラマの慧眼に唸りました。
遊園地のベンチ——“そっちへ”と“こっちで”の張り合い
ベンチでの「そっちへ連れて行って」は、死に憧れる言葉に違いない。
けれど、私はそれを生きるための独白だと受け取りました。言ってしまうことでしか越えられない痛みがある。
これまで三田は、依頼主の言葉だけを鏡返しに実行してきた人。第10話のベンチでは、初めて自分の願いを口に出す。
すると“誰かの依頼”では動かなかった涙が、自分の言葉に反応して溢れてくる。彼女の中の鏡が“人間”に戻る音が、確かに聞こえました。
「笑顔」は最終試験だから、まだ出してはいけない
物語はあえて、ここで笑わせない。笑顔は最終試験で、答え合わせの瞬間に取っておくためです。
第10話は、笑わないまま他者の声に近づく練習を丹念に重ねます。
海斗の作文に“添削”ではなく“破り”を出し、うららの恋に黙って寄り添い、希衣の事故に実務で対処し、そしてベンチで自分の言葉を解禁する。
笑顔に頼らず関係を進める。その慎重さが、次話での“笑顔”に重みを与えることを、脚本は知っている。
小道具の話——“触れる証拠”は生を支える
ランドセル、最中、ファミリーセット、そして石の箱。
このドラマの小道具は、いつも“触れられる証拠”として機能します。
ランドセルは“未来”の証拠、最中は“過去”の鍵、ファミリーセットは“喪失の再演”、石の箱は“家族の枠”。
触れられるものに、私たちは現在の位置を教えてもらう。
だから三田は、触れない笑顔を保留にしながらも、触れられる道具を通して阿須田家とつながり直していく。
解像度の上げどころ
破る勇気/書かせる勇気:回避を一度壊して、直視へ手を引く。行為の倫理がまっすぐ。
業務命令=翻訳装置:好意を“仕事”に翻訳して、線の内側へ招き入れる希衣の賢さ。
ベンチの独白:依頼の鏡から自分語りへ。涙はその転換の物理現象。
第10話は、“承知しました”の向こう側にある三田の心を、とうとう照らした回。
まだ笑えない。けれど、言えるようになった。その一歩こそ、愛よりも強い回復の証だと、私は思う。最終回の扉は、もう、手の届くところまで来ている。
家政婦のミタの関連記事
家政婦のミタの全話ネタバレについてはこちら↓
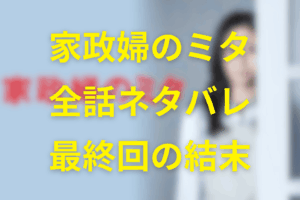

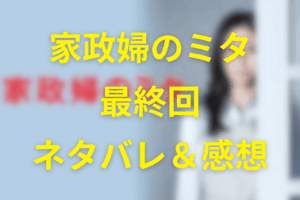
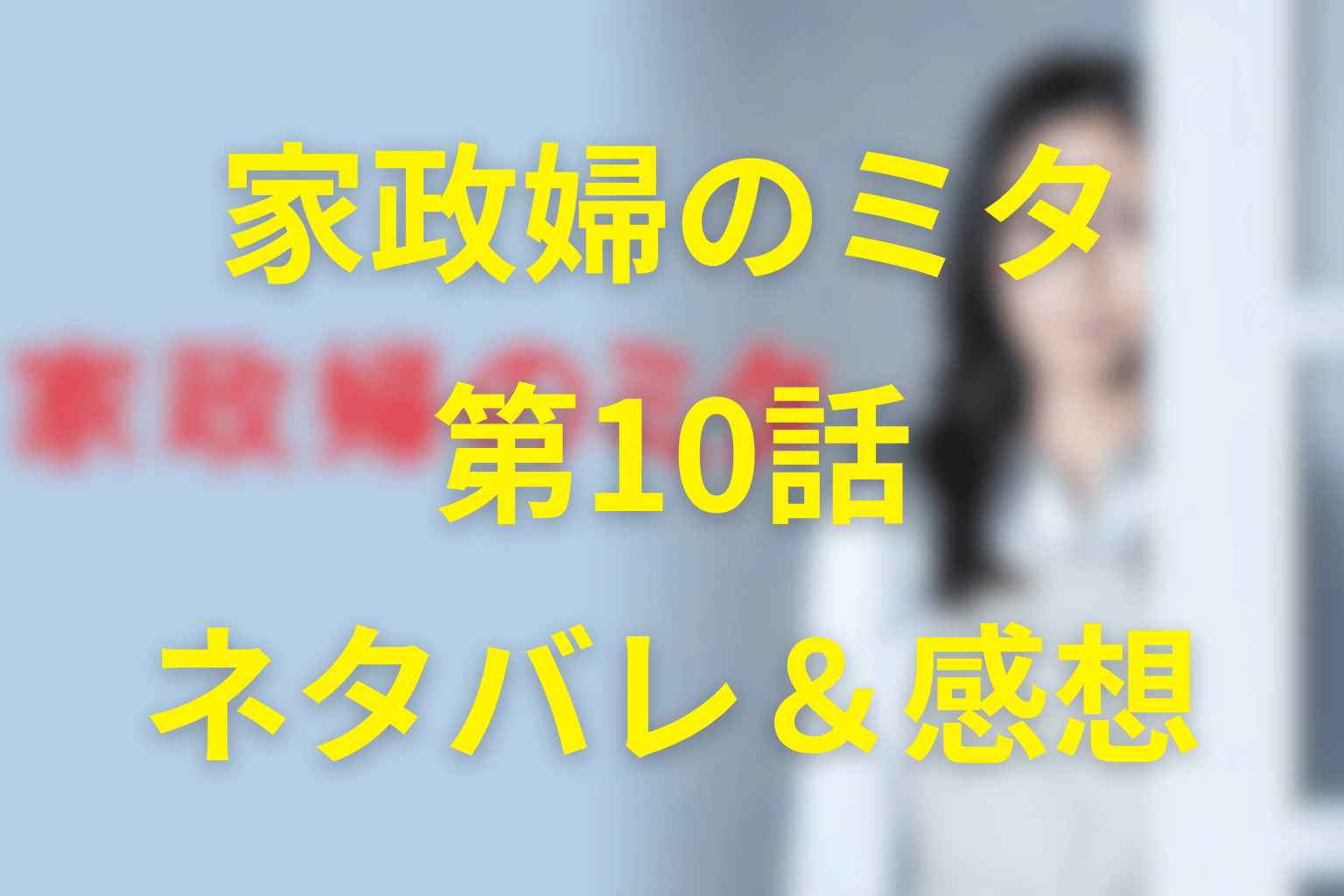
コメント