第8話で過去のすべてを明かし、阿須田家を去った三田。
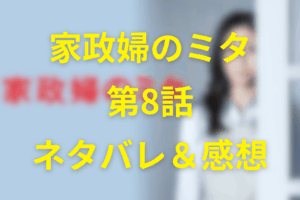
第9話は、彼女が“他人の家”で再び命令を受けるところから始まる。
冷徹に「承知しました」と応じながらも、その行為がどんな結末を招くのか、視聴者は息を詰めて見守る。
一方、三田を失った阿須田家の子どもたちは、空いた席の痛みを埋めるように“取り戻す方法”を模索。
そして迎えるのは、命令が命を危うくする夜。
燃やす家と戻る家、どちらを選ぶのか——。
第9話は、「従う」ことしかできなかった三田が、初めて“応える”人になる物語だった。
家政婦のミタ9話のあらすじ&ネタバレ
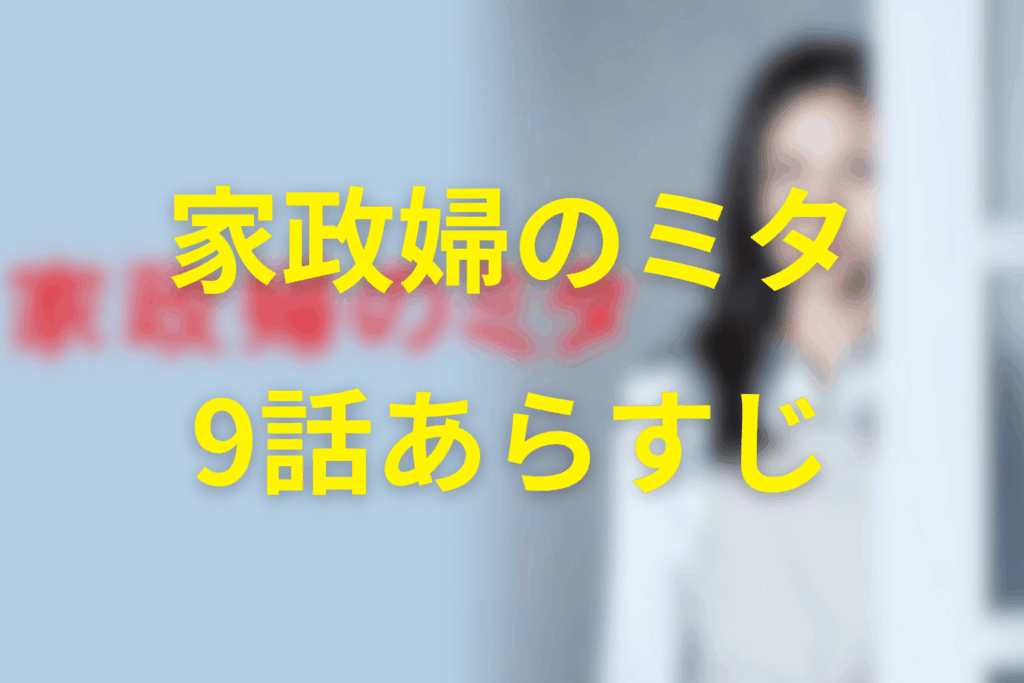
第8話で凄絶な過去を明かした三田灯(松嶋菜々子)は、「約束どおりお暇をいただきます」と阿須田家を去る。
翌朝、いつもの出勤時間になっても玄関のチャイムは鳴らない。恵一(長谷川博己)は家政婦紹介所の晴海(白川由美)に頭を下げ、子どもたちは三田がよく現れる遊園地まで探しに行くが、手がかりはない。
ようやく分かった新しい派遣先は、よりにもよって隣家・皆川家だった。
阿須田家の前で三田の姿を見つけた結(忽那汐里)たちは「戻ってきて」と懇願する。
しかし三田は「皆さんとは何の関係もありません」とだけ告げ、きっぱり背を向ける。
子どもたち(翔・海斗・希衣)は諦め切れず、“隣の家で問題が起きれば三田は解雇されるかも”という短絡から、窃盗の濡れ衣を着せてでも取り戻そうと暴走案を口にする。
物語は、三田の不在が生む空洞と、子どもたちの焦りの危うさを立ち上げていく。
皆川家の“業務命令”…尾行、そして「家を燃やして」
皆川家の主婦・皆川真利子(佐藤仁美)は、さっそく三田に“業務命令”を出す。
内容は夫・功(池田政典)の尾行。接待ゴルフに同行しているらしい――三田は淡々と尾行し、愛人との逢瀬の証拠写真と会話の逐語記録を突きつける。
「妻との結婚自体が間違っていた」という本音まで明かされ、真利子は逆上。
「だったら一家心中よ。明日、家族3人、この家ごと燃やしてくれる?」と命じる。
三田は、いつも通り「承知しました」と答えるのだった。
炎の前夜——“子どもたちの胸騒ぎ”と最悪の依頼
翌日、希衣(本田望結)は皆川家の長男・翼が「バイオリンも受験もやめていい」と話していたことを結に告げる。今日は翼の誕生日。そこへ給油ポリタンクを抱えた三田が無言で横を通り過ぎていく。
胸騒ぎを覚えた阿須田きょうだいはプレゼントを持って皆川家へ。だが真利子は「あなたたちには関係ない」と追い返す。
子どもたちは急いで父にも連絡。最悪の“依頼”が動き出していることを悟る。
火の夜…「一家心中」と「抱きしめる腕」
夜。皆川家のダイニングには灯油が撒かれ、ロウソクの炎がゆらぐ。
三田は自分の頭からも灯油を被り、点火の姿勢に入る。
「一家心中」を命じた真利子は、目の前の現実に蒼白となり、今度は「あなただけ燃えて」と口走ってしまう。
そのとき、結・翔・海斗・希衣が雪崩れ込むように飛び込み、三田を取り囲んで火を止める。彼女は淡々と「依頼どおりに」と言い募るが、子どもたちは命令に従うあなたを、私たちが止めると必死で抱きしめる。
ここで三田の口から、“従順であること”の理由がわずかにこぼれる。
「自分で考え、自由意志で動くたびに人を不幸にした。だからもう、頼まれたことしかやらない」と。
子どもたちは、「それでも生きていてほしい」「もう他人(依頼)になんて殺させない」と言葉を重ねる。
氷の仮面が軋むように、三田の頬に一筋の涙。第9話のサブタイトルが、ここで物語の実景になる。
再会と帰還——“戻ってきて”の意味
騒動のあと、三田は阿須田家へ。
玄関先で、きょうだいは「戻ってきて」と改めて頭を下げ、恵一も深々と礼をする。
三田は一瞬視線を伏せたのち、阿須田家に戻る選択を取る。ただし、その帰還は“ハッピー”という言葉では括れない。次話の予告が示す通り、彼女の脳裏には亡き家族の幻影がちらつき始め、物語は最終章へのカウントダウンへ入る。
家政婦のミタ9話の感想&考察
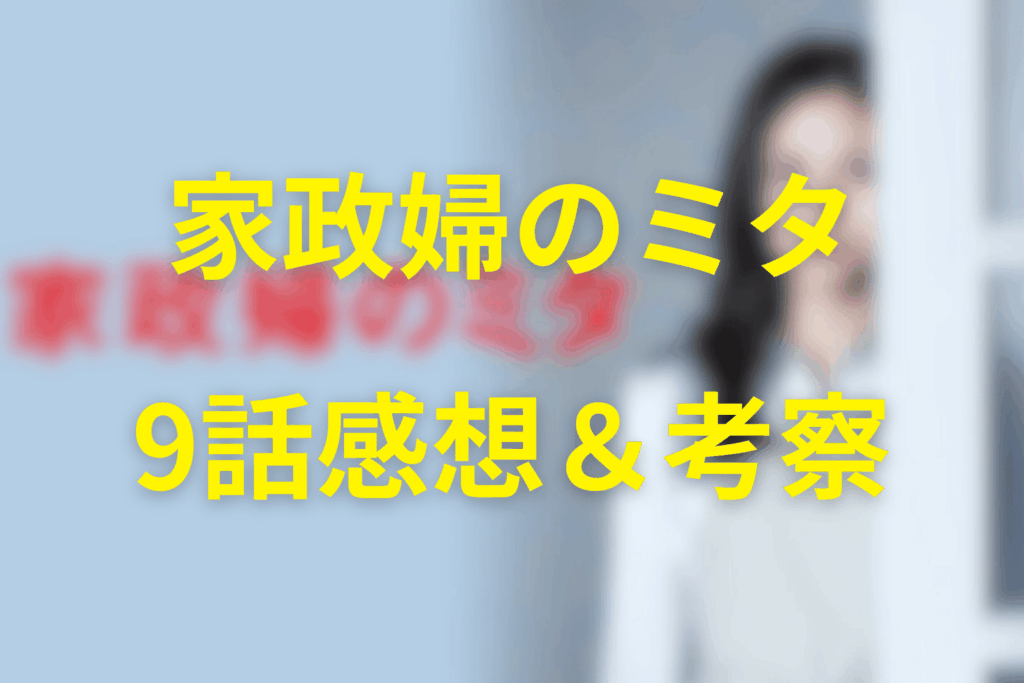
「承知しました」が砕けた夜——“依頼=呪い”を断ち切るのは、抱きしめる腕。
このシリーズを通して最も美しく、そして残酷だったのは、三田の自由意志を封印する論理です。
彼女は“生き延びるために”自分を受注生産の機械にしてきた。
だから「一家心中」でも「焼身」でも承知できる。けれど今夜、それを止める“依頼主”が初めて現れた――阿須田の子どもたちでした。
「やめて」「生きて」と身体で縫い止める。その瞬間、命令体系はひっくり返り、“従う”から“応える”へ三田は一歩進んだのだと思います。
「他人の欲望の代行者」から「他者に触れられる人」へ
三田はこれまで、依頼主の歪んだ欲望を現実に変換する鏡でした。
依頼が狂っていれば、返る現実もまた苛烈になる。
今回は真利子の「家ごと燃やして」が鏡返しに起こり、本人が怖気づくまで“真実”に近づける。
そこへ、阿須田の子どもたちが鏡の前に割り込み、他人の欲望の直進を家族の愛情が横から抱き止めた。三田にとって初めての“抱きしめられる”経験が訪れ、涙という生理的リアクションが初めて漏れたのだと感じる。
“炎”のモチーフ——死の誘惑と誕生日ケーキの火
細部の対置が鮮やか。
灯油とロウソクの炎は“死”の合図であり、同じ夜に翼の誕生日という“生”の合図が重ねられる。
燃やす対象が家(=家族の器)であることも象徴的だ。阿須田家の再生は、家を燃やすことではなく、家に人を戻すことでしか叶わない。
子どもの「プレゼントを持って行こう」という素朴な行為が、家に人を戻す第一歩になっているのが、なんとも詩的で胸に残った。
皆川真利子という“もう一つの家族”——嫉妬と恐怖のエコー
真利子は一見“モンスター主婦”だが、浮気の事実を突きつけられた恐怖と屈辱が、誇張された命令として噴き出しただけとも言える。
彼女の「家ごと燃やして」は、自分の尊厳が消えるくらいなら全部なかったことにしたいという衝動の言語化。
三田はその言葉をそのまま返す鏡となって彼女に見せた。ここで「依頼の言葉を世界に翻訳する」という三田の職能と倫理が際立つ。極端だが、だからこそ依頼主自身が“正気”へ戻るためのショックとなる。
「戻ってきて」は、甘えではなく誓いへ
帰還のとき、阿須田家の「戻ってきて」は依存の甘えに留まらない。
第7話・第8話を経て、恵一と子どもたちは「見る責任」「受け止める準備」を学んだ。だから第9話の「戻ってきて」は、“あなたの命令系を私たちが引き受ける”という誓いに近い。
ここで初めて、阿須田家と三田の関係が対等に近づいたと感じる。次話冒頭で三田が亡き家族の幻影に揺さぶられるのは、その対等化がもたらす“心の復活作用”の副反応でもあるはずだ。
筆者的・核心3点
1.「承知しました」の反転
依頼に従うことで生を消してきた三田が、“止めてほしいという依頼”に従った夜。
命令の構文は同じでも、主語が“家族”になったとき、彼女は初めて自分の側へ戻ってこれた。
2. 炎とケーキの火の二重露光
同じ火でも、ひとつは終わらせ、ひとつは始める。
死と誕生日を一晩に並べることで、物語は“生きるほう”を選び取らせる。
3. “鏡”から“人”へ
依頼を映す鏡であり続けた三田が、抱きしめられる“人”として認識された。
一筋の涙は、その地位の変化のサインだった。
家政婦のミタの関連記事
家政婦のミタの全話ネタバレについてはこちら↓
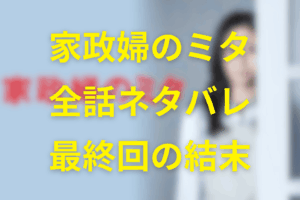
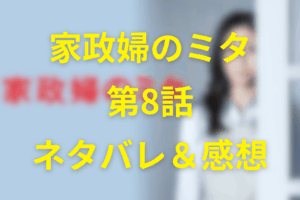
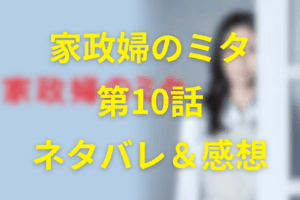
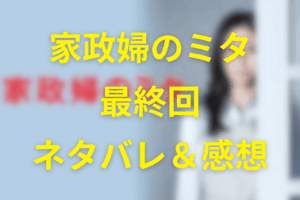
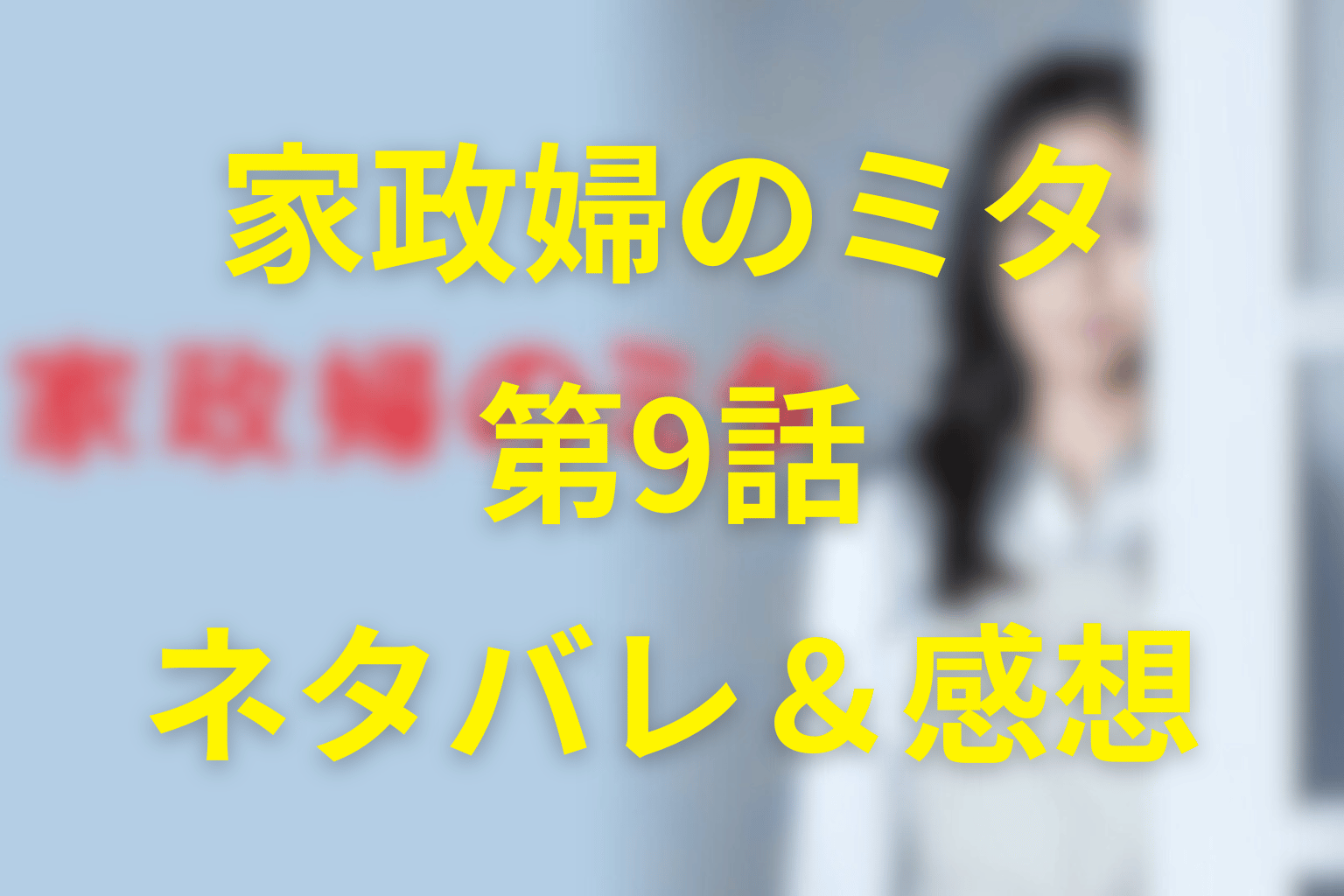
コメント