シーズン1第4話で「♧4 ディスタンス」のゲームを突破した有栖と宇佐木は、新たな生存の拠点「ビーチ」へとたどり着きます。
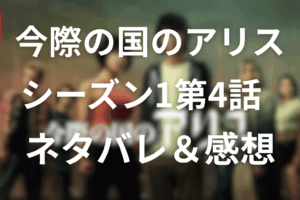
第5話では、この謎の共同体の全貌が明らかになり、狂気と快楽に満ちた秩序の中で有栖が初めて頭脳戦に挑む姿が描かれました。
物語はデスゲームの枠を超え、社会の縮図ともいえる組織の倫理や権力構造を映し出していきます。
今際の国のアリス(シーズン1)5話の見どころ
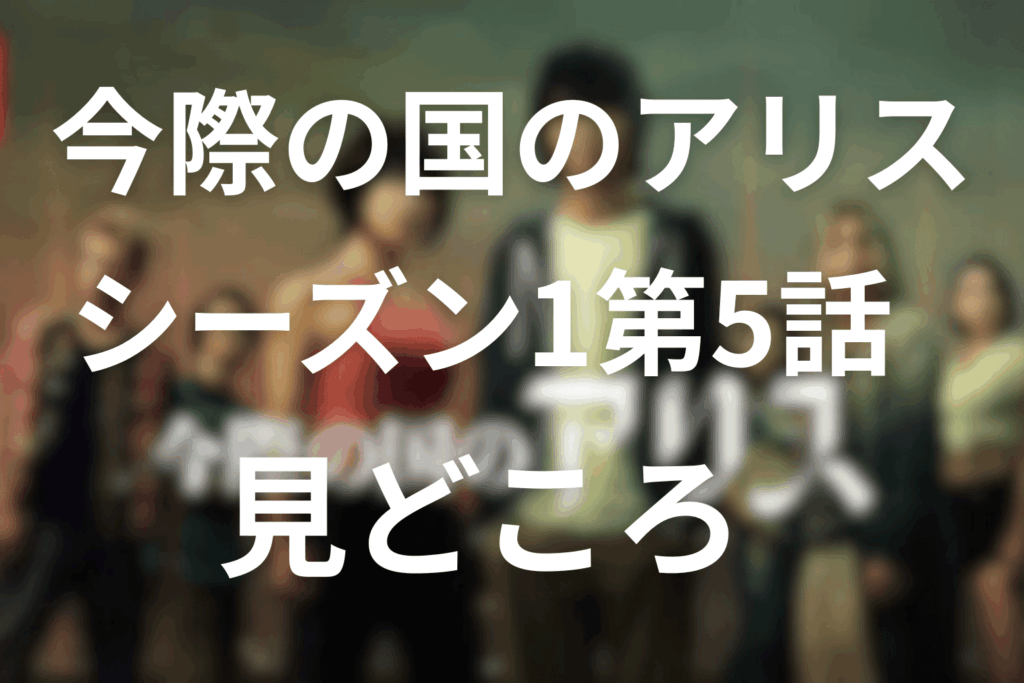
ビーチへの手掛かりと発見
第5話は新章「ビーチ編」の幕開けとなります。有栖と宇佐木はゲーム会場で“ビーチ”に繋がる手掛かりを探し、参加者の中に共通してロッカーキーのような鍵を腕に付けている集団を発見します。
期限が迫る中で二人は彼らを尾行し、たどり着いたのが巨大な建物――謎の共同体「ビーチ」でした。ここが以降の物語を大きく左右する重要な拠点となります。
謎の共同体「ビーチ」の実態
有栖たちの前に現れたのは、幹部のクズリュウやミラ、アンら。そしてカリスマ的存在のボーシヤが「理想の楽園『ビーチ』へようこそ」と宣言します。壁には集められたカードがずらりと並び、全てを揃えればゲームは終わるが「元の世界に帰れるのは一人だけ」という衝撃のルールが告げられます。
さらに「裏切り者は死」という掟も存在し、共同体の厳格さと狂気を浮き彫りにします。一方で内部は水着着用が義務づけられ、発電機で電力をまかないながらパーティや薬物に溺れる者も多く、刹那的な“楽園”のようでもありました。宇佐木が「現実逃避」と冷ややかに語る光景は、楽園と地獄の境界が曖昧であることを示しています。
派閥争いと緊張の構図
ビーチには二つの派閥が存在します。
ボーシヤを頂点とする“カルト派”と、元自衛官アグニが率いる“武闘派”。
ボーシヤはNo.1として絶大な権力を握り、資源や女性を好きに扱える立場にあります。一方、No.2のアグニは武器と実力者を束ね、実務面で大きな力を持つ存在です。二人のにらみ合いは不穏な空気を漂わせ、後の大きな対立の伏線となっていきます。
新たな頭脳戦「♦4 でんきゅう」
有栖が挑むのはダイヤの4「でんきゅう」という頭脳戦。参加者はアンやクイナ、タッタら。
ルールは隣の部屋に吊るされた電球を3つのスイッチから当てるという一見単純なものですが、制限付きの操作と、水位上昇による感電死の危険が加えられています。
焦りが広がる中、有栖は電球が白熱球であることに気づきます。点灯させて熱を帯びさせ、消した後の余熱で正解を導く――シンプルでありながら論理的な解決でした。この推理によって有栖は一目置かれ、アンからも頭脳派として認められる存在となります。
ボーシヤの過去と理想
幹部会ではまだ出現していない♥10の存在が話題となり、ミラは「ハートのゲームでは犠牲が必要」と冷酷に語ります。その後、有栖はボーシヤの過去を聞かされます。
彼はかつて歌舞伎町でホストクラブ「ビーチ」を経営していたが、部下を追い詰めた末に自殺させてしまった過去を持ちます。それでも彼は「成長のために必要な犠牲だった」と言い放ち、この国でNo.1となり英雄になることに固執していました。その狂気と執念は、有栖をも圧倒します。
今際の国のアリス(シーズン1)5話のあらすじ&ネタバレ
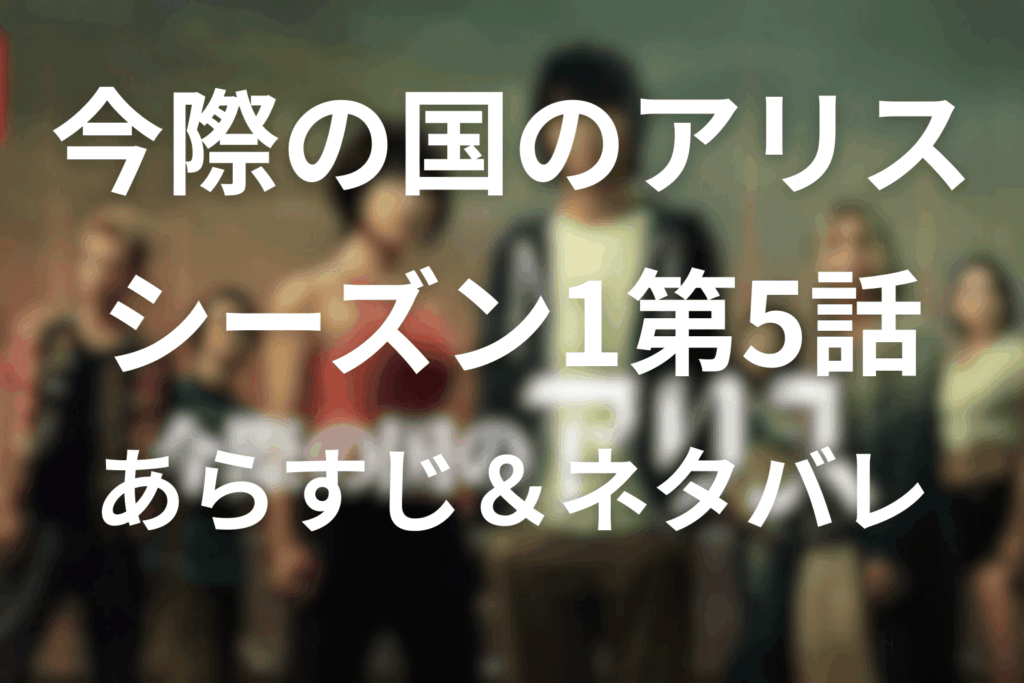
ビーチ発見まで
第5話は、有栖と宇佐木が「ビーチ」という拠点を探し求める場面から始まります。ビザの期限が迫る中、二人はゲーム会場で参加者を観察し、腕にロッカーキーを付けているグループが協力し合っていることに気づきます。
この鍵がビーチと繋がっていると直感した有栖は、宇佐木とともに尾行を開始。車で移動する彼らを追いかけ、やがて光に包まれた巨大なリゾート施設を発見します。そこが噂の「ビーチ」でした。しかし喜ぶ間もなく、有栖と宇佐木は背後から捕らえられ、袋を被せられて建物の中へ連行されてしまいます。
理想郷の真実
椅子に縛りつけられた二人の前に現れたのは、ボーシヤ、クズリュウ、ミラ、アンといった幹部たち。有栖が「この世界は何なのか、消えた人々はどこに行ったのか」と問いかけると、ボーシヤは壁一面に貼られたトランプのリストを示し、「すべてのカードを集めればゲームは終わる」と説明します。
ただし元の世界に戻れるのは一人だけであり、裏切り者は死刑にするという冷酷なルールも明かされます。さらに、ビーチの住人は水着の着用が義務づけられ、集めたカードは組織の財産とされる仕組み。ルールに従うことで食料や電気の供給を受けられますが、その代償として自由はほとんど奪われるも同然でした。
ボーシヤが「理想郷」と語るビーチの実態は、刹那的な快楽に溺れる共同体。燃料で発電し、プールサイドでは毎晩のようにパーティが開かれ、酒とドラッグと性に耽る人々の姿がありました。有栖と宇佐木は、ここが単なる拠点以上に歪んだ共同体であることを悟ります。
ゲームラッシュと「でんきゅう」
ビーチに参加した者たちは、それぞれの適性に応じてゲームに振り分けられます。原作には登場しない「借り物競争」や「人間エレベーター」「マッチ工場でビンゴ」といったユニークな競技が描かれ、宇佐木は「マッチ工場でビンゴ」に参加してクリア。そこで一息つきますが、有栖は幹部候補としてアンに連れられ、タッタやクイナとともに頭脳戦「でんきゅう」に挑むことになります。
このゲームはダイヤ4のカードをかけた知恵比べ。隣室には電球が吊るされ、A・B・Cの3つのスイッチのうちどれかが正解。ドアを開けてスイッチを押せるのは一度きりで、人が中にいるか電気が点灯している間はドアがロックされるという制約があります。
さらに水位がどんどん上がり、電線が触れると全員が感電死する仕掛けも用意されていました。焦る仲間たちに対し、有栖は冷静に「電球が白熱球である」点に注目。点灯させて一度消した後、残る熱を利用して正解を見抜くという発想に辿り着きます。この推理は見事に的中し、全員を救うことに成功しました。
アンは有栖の論理力を高く評価し、後に幹部候補として推薦することを決めます。有栖にとっては、自分がただ流される存在ではなく「役に立つ」ことを示す重要な一歩となりました。
派閥の確執と幹部会
ゲームを終えた有栖は宇佐木と再会しますが、すぐにビーチ内部の派閥争いに直面します。武闘派のニラギが女性を乱暴しようとし、元自衛官アグニはカルベの死を知ると「またどうでもいいやつが生き残ったか」と吐き捨てます。両者の横暴を止めたのはボーシヤでした。「No.1として秩序を守る」と告げる彼の姿にはカリスマ性が漂い、一瞬にして場を収めます。しかしこの一件は、ビーチがカルト的な統制と暴力に支えられた共同体であることを示すものでもありました。
その後の幹部会では、♥10のカードがまだ出ていないことが報告されます。ミラは「ハートのゲームで勝つにはおとりを連れていけばいい」と冷酷に語り、犠牲を前提とした発想を隠そうともしません。ボーシヤは「♥10が現れるまでゲームを続ける」と宣言し、自らも参加する意欲を示します。幹部会の様子からも、この共同体が冷酷な論理と個々の野心で成り立っていることが伺えました。
ボーシヤの過去と有栖への執着
会議の後、ボーシヤは有栖を呼び出し、自分の過去を語ります。
かつて歌舞伎町で「ビーチ」というホストクラブを経営していたボーシヤは、トップに立つために部下を極限まで追い込み、結果的に自殺させてしまった過去を持っていました。
それすら「成長に必要な犠牲だった」と正当化し、己の正義を疑うことはありません。彼はこの国でもNo.1になることに固執し、唯一の英雄として現実世界に戻ることを夢見ています。その執念と狂気に、有栖は恐怖と圧倒を同時に覚えるのでした。
第5話の総括
第5話は「ビーチ」という新たな舞台の全貌を描き、理想と狂気が表裏一体となった共同体の姿を鮮烈に提示しました。快楽に溺れる住人たちの刹那的な日常、冷徹なルール、派閥抗争、そして頭脳戦を通じて浮き彫りになる有栖の成長。物語はここから一気にスケールを広げ、カード争奪戦と人間模様が絡み合う濃密な展開へ突入していきます。
今際の国のアリス(シーズン1)5話の感想&考察
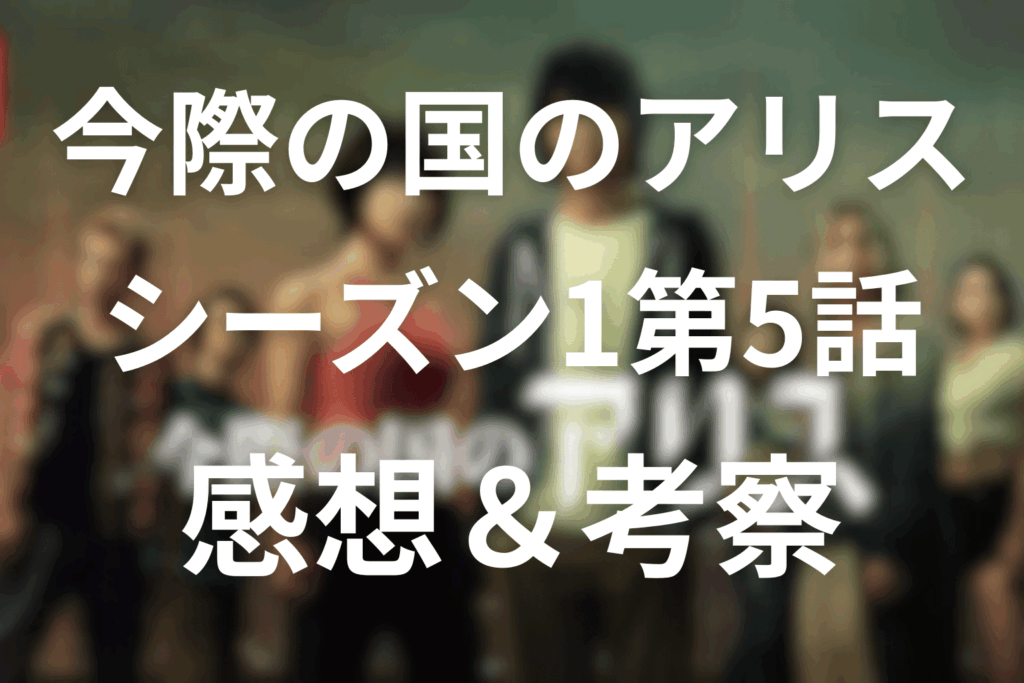
ビーチ編が突きつける生存の倫理
第5話は、デスゲームの枠を超え「組織の中で生き残ること」の倫理が強調された回でした。舞台となるビーチでは、集めたカードはすべて組織の財産とされ、貢献度によってナンバーが割り振られます。権力を握るボーシヤを頂点に、アグニ率いる武闘派が対立する構図は、資本主義社会における階層や権力闘争の縮図のようにも映りました。
また、ビーチの住人たちがパーティや快楽に耽る姿は、明日をも知れぬ命だからこそ現実逃避に走る人間の本性を描き出していました。自由を謳いながらも秩序は強く管理され、裏切ればレーザーによる死が待つ。その矛盾こそが、この共同体の不安定さを象徴していたように思います。
“でんきゅう”の頭脳戦とアリスの成長
ダイヤ4の頭脳戦「でんきゅう」は、第5話の大きな見どころでした。ルールは、三つのスイッチのうち正しいものを選び、隣室の電球を点灯させるというもの。制約として「ドアを開けたまま操作できるのは一度きり」「人が部屋にいる間はロックされる」「時間が経つと水位が上昇し感電死の危険がある」という緊張感に満ちた条件が課されています。
仲間がパニックに陥る中、有栖は冷静に白熱電球に着目します。点灯させて消した後、残る熱で正しいスイッチを見極めるというロジックを導き出し、見事に成功しました。この判断は論理に基づいたものであり、今までの運任せのゲームとは一線を画していました。
有栖は仲間を救うと同時に、幹部候補として認められる存在に成長していきます。罪悪感に囚われていた彼が知恵を武器に生き延びようとする姿は、物語全体の大きな転換点となったと感じました。
ボーシヤの過去とマッドハッターの暗示
物語の後半では、ビーチの支配者ボーシヤの過去が語られます。彼はかつて歌舞伎町で「ビーチ」というホストクラブを経営し、トップを目指すあまり部下を追い込み、自殺に追いやった過去を持ちます。本人はそれを「成長に必要な犠牲」と正当化し、今もNo.1への執着を語る危険な人物でした。
その狂気じみた姿は、「不思議の国のアリス」の帽子屋、マッドハッターを想起させます。水着姿でカリスマを振りまき、住人たちを魅了しながらも容赦なく支配する様は、魅力と狂気の紙一重。彼が「唯一の英雄として帰還する」と豪語する場面は、支配者の傲慢さと同時に、自らの孤独を覆い隠そうとする脆さも透けて見えました。
派閥抗争と今後への布石
ビーチでは、カルト的支配を敷くボーシヤと、圧倒的な武力で睨みを利かせるアグニが二大派閥として存在しています。アグニは仲間の死にも冷淡で、時に暴力によって秩序を保とうとする一方、ボーシヤは秩序を演出しつつも自らゲームに参加しようとする危うさを持っています。
この二人の対立はいつ爆発してもおかしくなく、視聴者の緊張を煽ります。後に起こる「魔女狩り」事件の伏線としても、第5話で描かれる派閥間の緊張は重要な意味を持っていました。
生きる意味を問う物語
第5話を通じて強く感じたのは、「生きるとは何か」というテーマがいっそう色濃くなったことです。有栖はカルベやチョータを失った痛みを背負いながらも、ウサギとともに生き抜く方法を模索し始めます。彼にとってゲームを攻略することは単なる延命ではなく、「生きることを選び続ける意思」の表れになっていました。
一方でボーシヤは、「東京から人が消えたのではなく、自分たちが別の国に入り込んだのだ」と語ります。彼の言葉は世界の本質を暗示すると同時に、この物語が「アリス」の世界観と深くリンクしていることを示していました。デスゲームの仕掛けを超え、人間の欲望と選択が織りなす物語が展開しているのだと改めて実感させられます。
まとめ
第5話は、拠点「ビーチ」の全貌を描くことで、物語を一気にスケールアップさせました。刹那的な快楽に溺れる住人たち、冷徹で狂気的な支配者ボーシヤ、そして頭脳戦「でんきゅう」で成長を見せた有栖。デスゲームの緊張感に社会的寓話を重ねることで、作品は単なるサバイバルを超えた厚みを帯びています。
筆者としては、今後登場するハートの10や絵札のゲームが、どのようにこの歪んだ共同体を崩壊へ導くのかに注目しています。ビーチという「楽園の仮面」をかぶった地獄で、有栖とウサギがどのように生き延びるのか。次回以降、さらに深まる人間模様と極限の選択から目が離せません。
今際の国のアリスの関連記事
シーズン1のネタバレはこちら↓
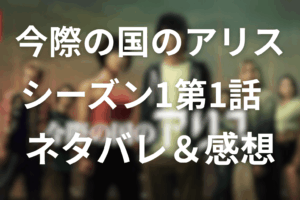
シーズン2のネタバレはこちら↓
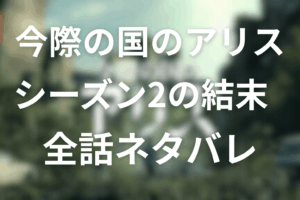
シーズン3のネタバレはこちら↓
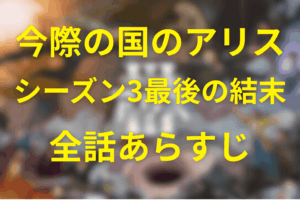
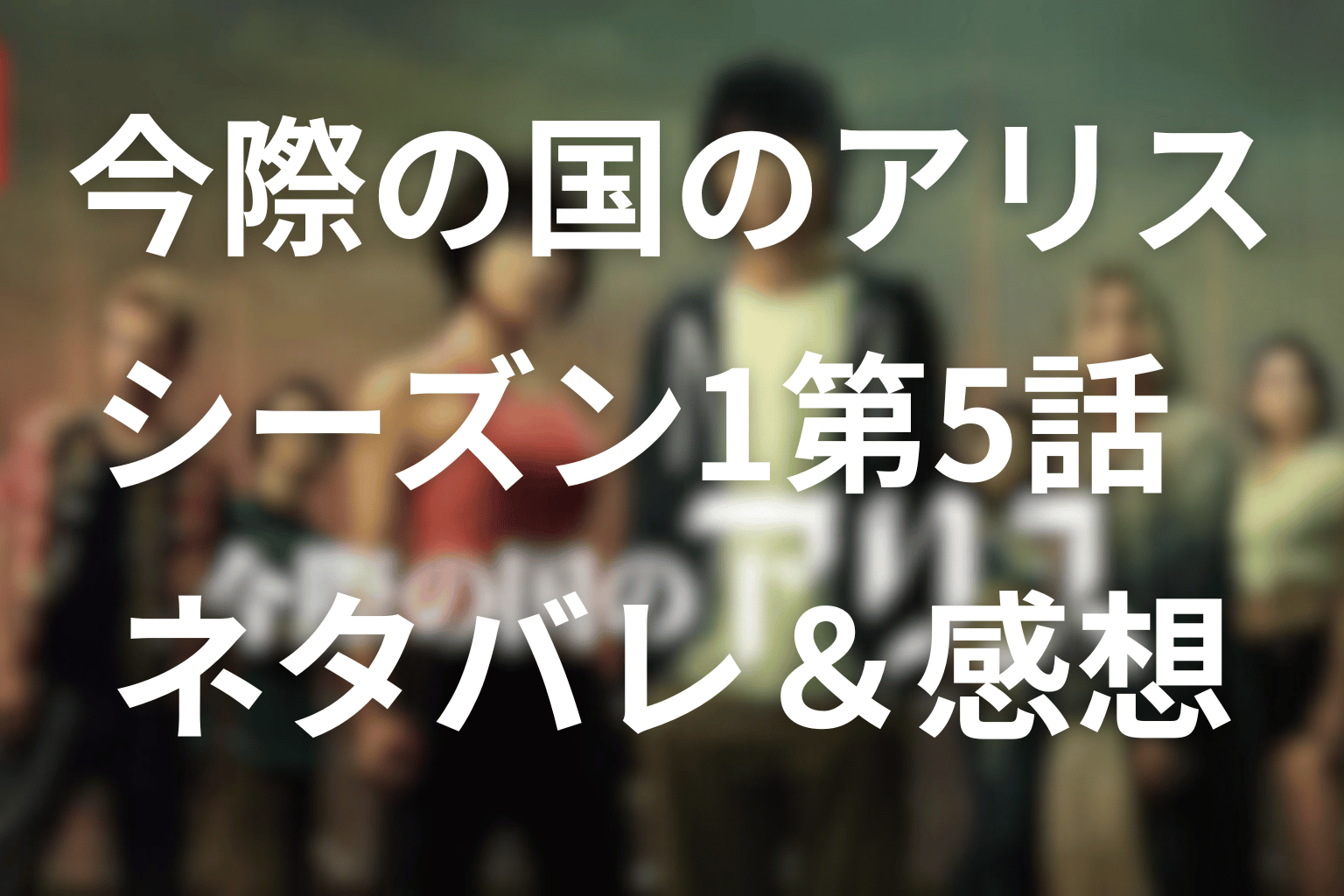
コメント