テレ東ドラマプレミア23枠で放送された『シナントロープ』は、脚本・此元和津也、監督・山岸聖太による青春群像ミステリー。
舞台は街の片隅にあるバーガーショップ「シナントロープ」。そこでは大学生・都成剣之介(水上恒司)をはじめとする8人の若者が、恋や友情、そして目を背けたくなる現実を抱えながら日々を過ごしている。だが、ある夜に起きた“二段構えの強盗事件”を境に、彼らの穏やかな日常はゆっくりと歪み始める。
第1話では「注文する強盗」という異様な侵入劇で登場人物たちの素顔をあぶり出し、第2話では「自首」と「すれ違い」という情報のズレが新たな謎を生む。そして物語は、組織“バーミン”の影、折田の狂気、そして「都市に棲む者たち」が選ぶ“残す関係/断つ関係”の結末へと進んでいく。
本記事では、『シナントロープ』全12話のあらすじとネタバレ、会話に仕込まれた伏線、そして最終回の結末までを論理的に考察していく。
【全話ネタバレ】シナントロープのあらすじ&ネタバレ
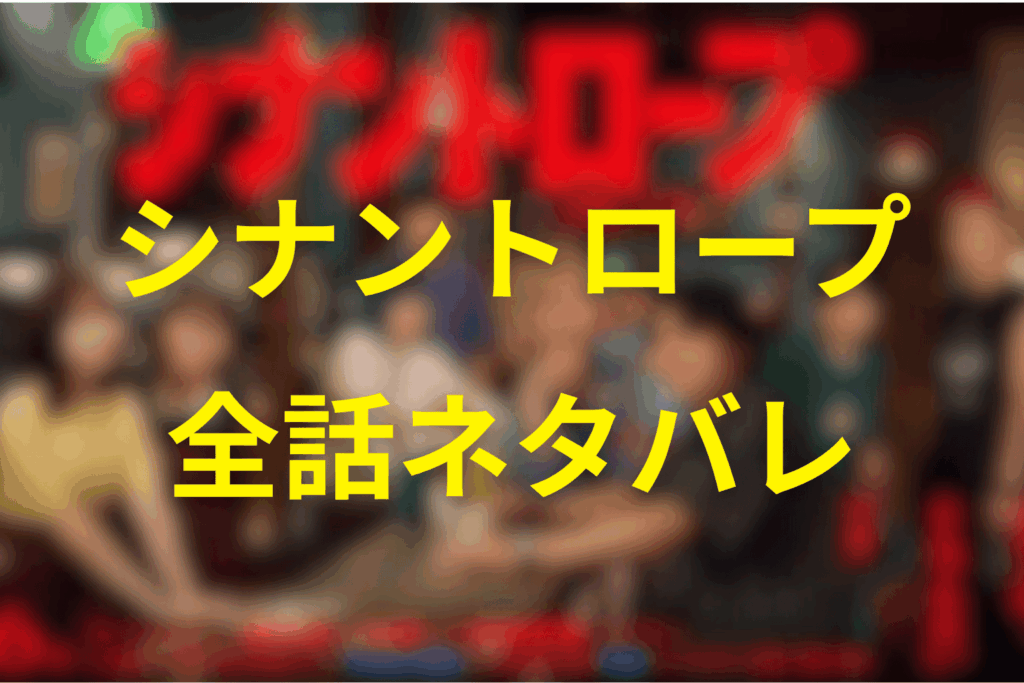
1話:「俺たちは何者かになる」――“二段構えの強盗”が8人の力学を可視化する
二重構造の侵入が見せた“初期値”のドラマ
舞台は、大学生・都成がホール係として働くバーガーショップ「シナントロープ」。同僚の木場とともに忙しいフロアを回している最中、目出し帽の男が入店する。
二人が怖気づいて押し付け合うなか、どんな相手にも動じない水町がすっと前に出て、まるで通常営業のように注文を取ってしまう――ここで一度、緊張は緩む。だが直後、もう一人の目出し帽の男が乱入し、レジ係の志沢に拳銃を突きつけ「金を出せ」と脅す。第1話は、“客”から“強盗”へと反転する二段構えの侵入で、物語を一気に揺らす設計になっている。
この構図が巧みなのは、恐怖の一次波(得体の知れない客)で各人物の“素の反応”を露出させ、暴力の二次波(銃)で人間関係の亀裂を広げていく点にある。
水町の冷静さは「現場の役割を守る」信念の可視化であり、都成と木場の逡巡は「安全と責任の最小化」を本能的に選んだ結果。観客はここで、8人それぞれの“初期値”を直感的に把握できる。この明確な初期設定があるからこそ、以降の選択や変化に説得力が生まれる。
強盗はトリガー――群像劇としての人間模様
物語の土台は群像劇。
イントロで示されるように、8人の若者のあいだで恋愛・友情・絆・裏切りが交錯し、日常の秩序が少しずつ歪んでいく。
強盗事件は単なる事件ではなく、関係性の転換を引き起こすトリガーとして配置されている。犯罪の“解決”よりも、事件が人間関係に何をもたらすかに焦点が置かれているため、終盤で謎が明かされきらなくても観客の関心は途切れない。関係の変質そのものが“次を見たい”という欲望を生むからだ。
“自己定義”の物語――サブタイトルが示す成長の射程
サブタイトル「俺たちは何者かになる」が示すように、テーマは“成り変わり”と“自己定義”。
不可解な強盗事件は、登場人物たちに「自分は何者なのか」を突きつける。都成は逃げ腰の自分と向き合い、水町は冷静さと責任の境界を試され、志沢は“標的にされた者”として沈黙の中で決断する。
出来事→反応→自己定義の流れが、台詞ではなく行動の段取りによって語られるからこそ、余韻が長く残る。
初回の機能整理――“関係ミステリー”の起動回
- 設定の確立:店・時間帯・役割を一気に提示(誰がホール/誰がレジ)。
- 人物の初期値:恐怖刺激に対する反応差でキャラクターを非言語的に描写。
- 謎の核:二段構えの侵入が、単なる金銭目的以上の意図を匂わせる。
- シリーズの駆動因:事件が関係を変質させ、以後の選択を迫る構造。
この4点が噛み合うことで、ミステリーの快楽(検証)と青春ドラマの快楽(変化)が同時進行する。だからこそ第1話は、ロジックと感情の両面で“走り出した”と感じられる起動回になっている。
1話についてはこちら↓
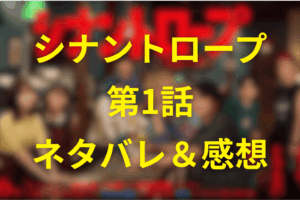
2話:『そのスニーカー可愛いね』――“安心”のラベルが剥がれた夜
“自首”の報せと、ゆるやかに崩れる日常
第2話は、強盗の翌日という“日常の端”から始まる。店は臨時休業となり、後片づけをしていた都成(水上恒司)たちに、オーナー・加藤(黒田大輔)が「犯人は自首した」と告げる。
安堵を裏づける“ことば”が与えられ、8人は新入り・志沢(萩原護)の歓迎会へ。鳥好きの水町(山田杏奈)が、瞬きもせず立つ志沢を「ハシビロコウ」と名づけ、場が和む。二次会のカラオケでは笑い声が響き、ようやく“平常”が戻ったかのように見える――ここまでは“安心”を取り戻す儀式だ。
記憶が鳴らす“警告音”――番号とバイブが繋ぐ不穏
しかし、その“平常”を壊す装置はすでに仕込まれていた。都成は強盗と揉み合った際に見た“左腕の電話番号”を記憶しており、個室に立った合間に“オリタ”の番号へ発信する。次の瞬間、同じフロアのトイレ個室からスマホのバイブ音が響く。覗き込むと、そこには置き忘れられたスマホ。
実は強盗の実行犯・龍二と久太郎も同じビルでカラオケをしており、そのスマホは久太郎のものだった。さらに都成は、ドリンクバーに向かう途中で久太郎とすれ違っていたことも判明する。“安心”のことば(=自首)と“不安”の音(=バイブ)が連続で鳴る構成が、視聴者の弛緩を一気に奪い返す。
人間の記憶×機械の記録――物語を動かす“観察の力”
「番号に電話をかける」という行為はSNSでも話題になった。無謀に見えて、実は都成の記憶が物語を動かすための正攻法になっている。
機器(スマホ)の“記録”と人間(都成)の“記憶”が噛み合い、音→位置→対面未遂というサスペンスの段取りを作る。テクノロジーの強さではなく、人の観察と記憶がドラマの推進力になっている点が巧みだ。
地下で進む“バーミン”の会話――目的は「シマセゲラ」
同時進行で描かれる〈バーミン〉側の動きも重要だ。睦美(森田想)は折田(染谷将太)に報告する。「折田宛てと同じ脅迫状を水町に送ったが、水町は里見を頼った」と。
折田は「水町と“シマセゲラ”は繋がっていない」「シマセゲラさえ見つかればそれでいい」と冷静に答える。つまり脅迫の目的は水町を追い詰めることではなく、“シマセゲラ”の所在を探ること。
敵側の会話が観客の視線を“ヒロインの危機”から“未知の宛先”へと誘導する。
内通者の正体――“観測者”が“監視者”に変わる瞬間
さらに、睦美のスマホにシナントロープのバイトメンバー全員の写真が送られてくる。
撮影者は室田環那(鳴海唯)――内部から外部へ情報を渡す“内通者”がいたことが露見する。視聴者が都成の電話に集中している間に、別のラインではすでに裏切りが進行していたという構図。仲間だと思っていた“観測者”が、視点の置き方ひとつで“監視者”へ変わる。この非対称が生まれた瞬間、店という空間の質が変わった。
柔らかな言葉と冷たい現実――“優しさ”で包む不穏
題名の「そのスニーカー可愛いね」という柔らかいフレーズも、第2話の設計と響き合う。軽い褒め言葉は警戒を解き、ハシビロコウという愛称も宴の輪を緩ませる。
しかし、その下で進行していたのは記憶・監視・脅迫という冷たい構造。“優しい言葉”で観客の防御を外し、音(バイブ)一発で地面を抜く。*の反転こそが、此元脚本の真骨頂だ。
総括――“平常”を装った夜が、最も危険だった
第2話は、「平常に戻れたはずの夜」を音・記憶・視線の三点で崩す回。
- “自首”の報で緩む。
- 番号発信→個室のバイブで緊張が戻る。
- 内通者の露見で、日常が“壁一枚向こうの敵”を抱えた空間へ書き換わる。
次に注目すべきは、室田が“なぜ”“いつから”観測側に立ったのか、そして折田でさえ掴めていない“シマセゲラ”とは誰(何)なのか。店という箱の内と外、“見る/見られる”の境目がどの瞬間に再配置されるのか第2話は、安心というラベルを剥がす手順を手に入れた回だった。
2話のネタバレはこちら↓
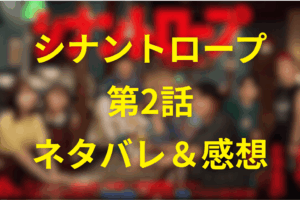
3話:閉店宣告と“写真”の選別――里見と折田が同じマンションという絶望
「事件の余波」から「人間の選別」へ
第3話は、物語の駆動力が「事件の余波」から「人間の選別」へと切り替わる回だ。発端はオーナーの閉店宣告。強盗騒ぎで店の評判が地に落ち、アルバイトたちは解散の危機に直面する。
しかし、水町ことみが「経営を引き継ぎたい」と申し出て、環那だけが離脱。残る6人は継続勤務を誓う。
この因果関係――〈外部要因(強盗)→組織崩壊の兆し→水町の代替案→暫定的連帯〉――が、以後の“共生(シナントロープ)”の脆さを可視化する。
「閉店→継承→一名離脱→再結束」という骨格が、本話の構造的主軸である。
水町の決断と「店を続ける」という現実
「続ける」と決めた瞬間から、店は現実的な課題に直面する。リニューアル当日、昼を過ぎても客はゼロ。
水町は近隣の人気店を分析し、打開策としてデリバリーやグッズ販売を導入する。ここで本作らしい“会話劇×業務オペレーション”の手触りが生まれる。
感情論ではなく、仮説検証で前に進む流儀。店という空間が“生き残るための思考実験”として描かれるのが、この回の魅力だ。
デリバリーで繋がる“偶然”――都成と折田の邂逅
転機となるのは、デリバリー受注の場面。都成が向かった配達先のマンションで、彼は“折田”と遭遇する。
裏社会の代行組織〈バーミン〉を束ねる折田が、よりにもよって里見奈々の暮らすマンションに入居しているという事実。
この“距離の近さ”が、第3話最大の不安要素だ。
空間的近接はそのまま心理的圧力として働き、日常の防壁(里見の部屋)と異常の震源(折田の部屋)が同一ビルに存在する。
“生活圏の隣にある恐怖”という構図が、視聴者の背筋を冷やした。
折田の“写真7枚”――暴力のロジックが静かに立ち上がる
終盤、折田は食事をしながら7枚の写真を眺め、無機質に「こいつにしよ」と呟く。
そこに写っているのは、“シナントロープ”の店員たち。選ばれたのは赤モヒカンのバンドマン・塚田。この演出が際立つのは、犯行計画の“理不尽な合理性”を、セリフの温度と映像の静寂で描き出している点だ。
写真は統計でも証拠でもない。
ただの「顔の並び」から次の犠牲者が選ばれる――被害のロジックが透明であるほど、倫理の不透明さが際立つ。
理屈が通るほどに、恐怖が増幅する構成である。
三つのベクトルで見る第3話の構造
本話は、三つのベクトルが交差して成立している。
- 事業再建ベクトル: 閉店宣告→継承→再開という経営の意思決定。
- 空間ベクトル: 里見と折田が同一マンションという最短距離の配置。
- 選別ベクトル: 写真7枚から“次”を一意に決める捕食者の視線。
この三者が、「続けたい」という能動を「狙われる」という受動へと転倒させる。
店の再出発は、外から見れば“的(まと)”の再設定に過ぎないのだ。
人物関係の微細な変化と群像設計の妙
環那の離脱は単なる不参加ではなく、“内部の穴”を生む。緊急時の穴は、外圧(折田サイド)が侵入するための最短ルートになり得る。
つまり、抜けたピースは“弱点の形”を規定する。誰かの合理が、別の誰かの不条理を呼び込む。
此元和津也の群像設計が最も冴えるのは、この“連鎖の構造”だ。
演出とモチーフ――“無音の暴力”が支配する空間
演出面でも、会話の間合いと静止画(写真)を用いた“無音の暴力”が際立つ。
第1・2話の「事件→余波」というテンポから、3話では「業務→違和感→選別」へと転調。
視覚モチーフは“マスクと写真”、空間モチーフは“店とマンション”で統一されており、場面転換のたびに“近づいてはいけないものが近づく”という横滑りの恐怖が増幅していく。店の光と、マンションの暗がり――希望と不穏が常に同一線上にある構成が見事だ。
総括――“働く”ことが“狩られる順番に並ぶ”瞬間
総じて第3話は、“働く”という能動を“狩られる順番に並ぶ”という受動へと反転させた回である。
論理的に言えば、〈継承の意思→再開→露出増→遭遇→選別〉という一連の流れ。再建の意思は、すなわち危険への露出でもある。
視聴者への問いは明快だ――「再建は、誰を代償にして成立するのか?」次回、写真で選ばれた塚田の周縁から、店と仲間たちの“生存コスト”が試されることになる。
3話のあらすじ&ネタバレについてはこちら↓
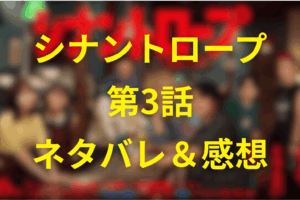
4話:運命は決まってる——大量注文の罠と“20万円”の決断
大量注文の喜びから、空注文の地獄へ
再開した「シナントロープ」は依然として客足が少なく、オーナーの水町ことみ(山田杏奈)は焦りを募らせていた
そんな中、塚田のライブをきっかけに店を知ったという客から“70人分の打ち上げ用ハンバーガー”という大口注文が入る。厨房には久々の活気が戻り、都成(水上恒司)らスタッフは深夜まで仕込みに没頭。
だが、約束の時刻になっても客は現れず——。店内に残ったのは大量の在庫と、誰が責任を取るのかという重苦しい沈黙だけだった。
「20万で俺が払う」——善意が罠に変わる瞬間
場の空気が凍る中、塚田は「20万円で俺が買い取る」と宣言する。
恋人からの借金の申し出も断られ、車の売却も叶わず、追い詰められた彼は車内で見つけた一枚のチラシに目を留める。それは消費者金融「バーミン」の広告。電話をかけた先は、裏社会の代行屋・折田(染谷将太)のオフィスだった。
この瞬間、「注文 → 不履行 → 在庫損失 → 自己負担 → 融資」という巧妙なレールが一本につながる。ターゲットの誠実さと責任感を利用し、本人の意思で“借金”という罠へと歩かせる折田の冷徹な設計が浮かび上がる。
バーミンの構造——“事件を生み出すシステム”
折田の拠点には、事務の睦美(森田想)、実働担当の龍二(遠藤雄弥)と久太郎(アフロ)、さらに監視役の“おじさん”(山本浩司)と若い男(栗原颯人)が控えている。
暴力ではなく、“日常の取引”を入口に人を堕とす。勤勉・責任感・見栄といった人の“善さ”を反転させ、自発的な従属へ導く構造だ。バーミンは単なる闇金融ではなく、“事件を生み出す装置”として描かれている。
店内の論争——SNS拡散か、信頼維持か
一方の店では、余ったハンバーガーの処理を巡って議論が起きる。SNSで“半額販売”を提案する声も出るが、環那(鳴海唯)は衛生面・ブランド価値・炎上リスクを理由に却下。結局、塚田が「自分の責任」として全額を背負うことになる。ここに第4話の核心がある。
折田は、人の心理を読む。努力を注いだ直後ほど、人は撤退できなくなる。「運命は決まってる」とは、超自然的な運命論ではなく、“設計された選択肢”に人間が従ってしまう構造そのものを指している。
ラストの示唆——“救う者”と“陥れる者”
物語の終盤、折田はホテルのスイートでニュース記事を見つめる。
「5歳の少女が自宅監禁から脱出し、シマセゲラに救出された」との報道——それは、ことみの幼少期を示唆するものだった。折田の口元に浮かぶ微笑みは、“バーミン(陥れる者)”と“シマセゲラ(救う者)”という二つの存在が、過去のどこかで交わっていた可能性を匂わせる。
このラストの1カットが、第5話以降で“救済”と“支配”というテーマをどう絡めていくのかを示す布石となる。
総括——“善意”が人を支配する時代の寓話
第4話は、「善意→損失→自責→借金」という因果を、視聴者自身に体験させる構造の妙が光った。
事件は“起きた”のではなく、“設計された”もの。若者の誠実さが、どのようにして搾取の装置に取り込まれるのか——それを冷静に描く筆致が見事だ。次回、塚田がこのレールから抜け出す術を見つけられるのか。
そして、5歳の少女=ことみの過去が、現在の「シナントロープ」にどう影を落とすのかに注目したい。
シナントロープの4話のネタバレについてはこちら↓
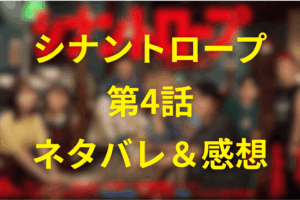
5話:「空を飛べたらいいのに」——“観察”を挟んだ瞬間、信頼は遠のく
塚田(高橋侃)のライブ当日、都成(水上恒司)が店に入ると、帳簿を開いたまま水町(山田杏奈)がうたた寝していた。
どうやら家に帰れず、大学にも行けていない。
ここで都成は、彼女を昼に誘うために志沢(萩原護)の“会話メモ”に頼るが、あっさり失敗する。
水町はそれを即座に見抜き、「訊きたいことがあれば直接訊けばいいじゃん」と切り返す。“観察(第三者)を介した関心”が主語のズレとなって、相手を遠ざける瞬間だ。
善意がもたらす距離──“観察の介在”という誤り
このやり取りが第5話の核心だ。
善意で観察を挟む→だから自分の言葉が立たず、相手の防御を誘発→結果、信頼が生まれない。
つまり、都成のミスは“内容”ではなく“手続き”にある。
彼は安全策として情報を仕入れたが、その“安全”こそが関係の距離を生んだ。ここでタイトルの“飛ぶ”が意味を帯びる。
閉じた場所から外へ出る、上へ抜けるという比喩は、相手に真正面から近づく“直進”の動きと地続きだ。
水町の告白が示す「飛ぶ」ことの意味
予告映像では、水町が「私は5歳の時、父親によって家に閉じ込められてました」と語るシーンが先行していた。
“飛ぶ”とは、出口を手にすること。
その一言で副題の意味がいっそう濃くなる。
また、木場(坂東龍汰)が卒業文集を踏みにじる足元、森田(森田想)の「シマセゲラはずっと水町ことみの、そばで見守っている」という不穏な台詞、志沢の「告白しましょう」「人が人に恋をする条件、今整いました」という言葉が重なり、店の内側=会話の場と外側=観察と監視の場が同時に熱を帯びていく構図が示されている。
監督・此元和津也のスタンス──構造より“呼吸と衝動”
監督の此元和津也はインタビューで「次は感情一本で突き進む、一筆書きのようなものを。伏線は敷かないし、回収もしない。呼吸と衝動だけ」と語っている。
それでも本作が“考察祭り”を呼ぶのは、構造で見せるのではなく、呼吸と間で人物を泳がせるからだ。
観客が“つながり”を勝手に発見してしまうのは、計算ではなく呼吸のリアリズムゆえ。
第5話もまさにその型で、台詞の間合いと目線の揺れだけで、水町の過去と都成の未熟さを立ち上げている。
三段で読む「面白さの根」
原因:都成は“観察の介在”で安全を確保しようとした。
水町は“直接の言葉”以外を拒む事情を抱えていた。
作用:会話は噛み合わず、「直接訊け」という一刀で手続きの誤りが暴かれる。
結果:ふたりの距離は一度離れるが、真正面からの言葉以外に橋はないと分かる。
タイトルの“飛ぶ”は、恐怖を越えて踏み出す動詞になる。
また、次回タイトル「心配すんな、お前はひとりだ」も示唆的だ。
第5話で“会話の主語”を奪い合った先に、孤独の定義が改めて問われる。“ひとり”とは切断か、それとも自立か。
いずれにせよ、鍵は直接の告白であり、観察の代行ではない。シリーズ全体の倫理が、今回の失敗を通してより明確になった。
塚田のライブが象徴する“上昇と停滞”の二重構造
塚田のライブという“上昇”の時間軸に、都成と水町のすれ違う会話を重ねた構成が見事だ。
音楽という上へ引っ張る時間と、未消化の過去という下へ沈む時間が同日に交錯することで、「空を飛べたらいいのに」というタイトルの切実さが増幅される。
第5話は、謎解きではなく“人の設計”を撮る一本だった。
5話のネタバレ&あらすじはこちら↓
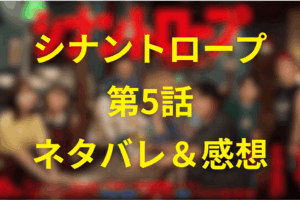
6話:「心配すんな、お前はひとりだ」——合鍵と“不在”があぶり出す境界
開店前の“鍵回収”──水町が線を引き直す
開店前、“シナントロープ”に寝泊まりが増えた水町ことみは、スタッフ全員から合鍵を回収する。
安全管理の名目ではあるが、実際には“みんなの店”から“水町が責任を持つ店”へと舵を切る決断でもあった。
入退室の権限を一本化し、店の境界を再定義することで、彼女は「誰を内に入れ、誰を外に置くか」という線引きを静かに引き直す。
その最中、室田環那が「メニューの字は誰が書いたの?」と問いかけ、筆跡が都成剣之介のものだと判明する。そのやり取りを志沢匠が黙って観察しており、店内の空気に微かな緊張が走る。
この筆跡確認の場面は、コミュニティの中で“役割”と“責任”を可視化する象徴的な場面として描かれていた。
都成の逃避、公園の誤解──「探さないで」の置き手紙
一方の都成は、店に「探さないでください」と書き残し、公園でバイトをサボる。
彼は第5話の“ライブハウスの夜”を誤解し、「ことみはあの男に一目惚れしたのでは」と早合点して悶々とする。幼い自意識と不安が膨らみ、誰かが自分を探してくれるかもしれないという期待に縋りながら時間を潰す。
その頃、店では田丸哲也が応募した漫画賞の結果を開けられず、厨房で身悶えしていた。
そこに大学時代のゼミ仲間が現れ、彼をあざ笑うように嘲る。
“ホーム”である店に外の悪意が土足で入り込み、ことみたちは険しい表情を浮かべる。田丸は「デリバリー行ってきます」と告げて店を出るが、そのまま連絡が途絶える。
彼の不在が、店の秩序を一気に脆くし、ことみたちは捜索に動き始める。
裏社会と監視の影──“時間のズレ”が生む不穏な余白
画面の裏では、折田浩平の周辺がじわりと動き出す。
コードネーム“トンビ”(山本浩司)と“キツツキ”(栗原颯人)という監視役が折田の行動を追い、さらに龍二(遠藤雄弥)、久太郎(アフロ)、睦美(森田想)ら“バーミン”のメンバーがその外郭を囲む。
若者たちの生活空間と、裏社会の監視網が同じ地平で交錯し始め、“外からの視線”が店の内側を侵食していく構図が浮かび上がる。
物語の中盤では、公園で沈む都成に小学生の男の子が声をかける。
「友だちになってあげる」と屈託なく言うその一言が、彼の固まった表情をほぐす。
副題「心配すんな、お前はひとりだ」は、突き放しではなく、“ひとりを前提に、それでも他者と並ぶ”という反歌として響く。
孤独の中に他者のまなざしが差し込む、この短い場面が6話の感情の核を担っていた。
鍵と不在の夜──“線引き”の意味を問うラスト
ラスト、店は鍵(アクセス権)を集中管理することで再び輪郭を取り戻す。
しかし、田丸の不在という“穴”を抱えたまま、閉店時間を迎える。
合鍵、置き手紙、嘲笑、監視——小さな所作と暴力の積み重ねが、「誰を内側に入れ、誰を外側に置くのか」という共同体の根源的な問いを突きつける。
第6話は、派手な事件を起こさずに“線引きの夜”を描いた回。
鍵をめぐる一連の行動が、“孤独の受容”と“責任の所在”を同時に問う構図となり、次回の“交差”(警察線・過去の傷・バーミンの圧力)へ向けた火種を周到に配置して幕を閉じた。
シナントロープ6話についてはこちら↓
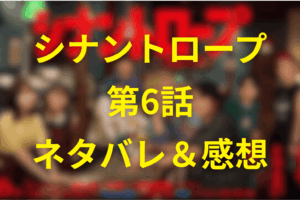
7話:「お待たせ、お嬢ちゃん」――3本の線が同時に深まり、暴力が不可逆点を越える回
第7話は、3本の線が同時に深まる。
①都成(みずかみ恒司)の“外部”=警察・薬物線
②ことみ(山田杏奈)の“内面”=監禁記憶の更新
③バーミン側の“追跡”=「シー=シマセゲラ」仮説の強化
——そしてラストで暴力が不可逆点を越える。
夜道、都成はかつて自分を追った強面の男(松角洋平)と再遭遇。
男の正体は刑事で、「目が血走ってるゾンビみたいなおっさんを見なかったか?」と尋ねる。薬物依存者の影が都成の生活圏にじわりと接続し、店の外側にある“社会の濁り”がこちらへ迫っている導入となる。
ことみが辿る監禁記憶と“オレンジ”の符号
同時刻、ことみは里見(影山優佳)のマンションに泊まり、5歳時の監禁の悪夢を見る。
助けに来た人物はオレンジの目出し帽を被っており、過去の“救済者(オレンジ)”と現在の画面に横切る“オレンジ”が視覚的に接続され、物語の記号が一本化されていく。
山小屋での拷問と「シー=シマセゲラ」仮説の鮮明化
一方、山小屋ではバーミンの折田(染谷将太)と睦美(森田想)が、龍二(遠藤雄弥)に拷問されるカシュー(中山求一郎)から情報を引き出す。
龍二は、かつてのバンド「キノミトキノミ」のドラマー“シー”こそがシマセゲラだと断言。カシューの口からは、シーが酔うと漏らしていたという決定的な一節、「昔、やべぇ奴の息子を殺しかけた。見つかったら表舞台から消えなきゃいけない」が語られる。
さらに折田は「親父は16年前に捕まって獄死した」と明かし、龍二の“親父関与”説を否定。父と息子という語が対位的に響き、復讐の循環を匂わせる。
“オレンジの現在形”が動き出す——クルミの通話
オレンジの目出し帽を被ったクルミがコインランドリーの公衆電話から“シー”に通話し、「もう一度、音楽をやろう」と誘う。しかし“シー”は「ひっそり生きたい」と拒絶。
視聴者の関心は「監視していたオレンジの若者=クルミ?」へ集中し、匿名の象徴“オレンジ”が、過去(救済)と現在(潜伏)を結ぶ“記号の橋”として機能する。
ことみ“偽証”説の浮上——祖母ではなく祖父?
並行して“偽証”説が台頭。志沢(萩原護)の調べで、ことみが「祖母に育てられた」という自己申告に疑義が生じ、実は“祖父”がいる可能性が急浮上する。
視聴者の間では、1話から登場してきたスリの老紳士“インカアジサシ”(綾田俊樹)が祖父なのではという推測が広がる。もし真なら、ことみは“身を守るための虚偽”で来歴を意図的にぼかしてきたことになり、証言者としての信用や動機の読み替えを迫る重要ピースとなる。
折田の残虐がついに露呈——“軽さ”が“殺意”に反転する瞬間
クライマックス。カシューが「こんなことしてタダで済むと思うな」「シーに殺されかけてビビってるガキが!」と折田を挑発し、久太郎(アフロ)が一瞬ためらう。
その刹那、折田は拳銃を抜きカシューを射殺。これまで“軽口と薄笑い”で覆われていた折田の残虐性が、実弾の殺意として露わになり、視聴者も騒然となった場面である。
総じて7話は、3本の線が同時に増幅し、物語の地盤が崩れ始めた回
(A)警察が追う薬物線(都成サイド)、
(B)監禁記憶と“オレンジ”の重ね合わせ(ことみサイド)、
(C)「シー=シマセゲラ」仮説の行動原理(バーミン側)。
終盤には「店に侵入の形跡」が示唆され、次回以降“オレンジの素顔”と“父と息子の連鎖”の解像度が一段上がることを予告して幕を閉じた。
シナントロープ7話についてはこちら↓
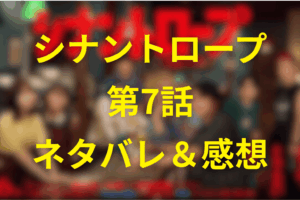
8話:月が綺麗ですねーー恋と陰謀が重なる夜
第8話は、前回シナントロープに“何者かの侵入”があった翌朝から始まります。
里見が空気清浄機カメラで捉えた影を受け、水町は早朝ひとりで店を確認。荒らされた形跡はないものの、都成から合鍵を回収し、昨夜の行動をさりげなく聞き出します。
都成はそれを“焼きもち”と受け取りますが、水町はあくまで冷静。この時点で、彼女が何を把握し、何を疑っているのかは視聴者にもまだ読めません。
志沢の恋が“事件”と接続してしまう
一方の志沢は、ライブ遠征先で出会った女性・忍とやり取りを重ね、東京で会う流れになります。
奥手な志沢は迷いますが、水町は「会いに行きなきゃダメ」と強く背中を押し、服装からタイミングまで指南。志沢は忍が泊まる予定の赤坂のホテルに部屋を取り、会う段取りを整えます。サブタイトル「月が綺麗ですね」のように、少し不器用で甘い“恋の一歩”が踏み出される瞬間でした。
都成と志沢、同じホテルへ誘導される不穏さ
同じ頃、水町は都成にもデリバリーを指示。届け先は、よりによって志沢と同じ赤坂のホテル。
単なる仕事に見えつつ、この“動線の重なり”が意図的にも見える不穏な配置です。そして、こここそ折田側の実働部隊が使っているアジトであると判明します。
赤坂の一室では、睦美が新たな脅迫状を受け取り、撤収を決断。大量の資料と脅迫状を残し、龍二と久太郎に片付けを任せます。このタイミングの脅迫状は、睦美=シマセゲラ自作自演説を強める配置でもあります。
誤接続された内線が“シマセゲラ”を呼び起こす
志沢は勇気を出し、ホテルの内線で忍に電話。ところが、教えられた部屋番号は睦美のアジトと一致しており、受話器を取ったのは龍二。志沢の言葉は龍二には“シマセゲラからの連絡”のように聞こえ、龍二は「シマセゲラがホテルにいる」と確信して捜し回り始めます。
そこへ都成がデリバリーで到着。折田サイドから見れば“匂う存在”の彼は即座に拘束され、「誰の指示だ」「シマセゲラか」と問い詰められます。都成は状況を理解できず、困惑のまま半ば監禁状態に。
インカアジサシ=第三勢力の介入
絶体絶命の都成の前に現れるのが、老紳士インカアジサシ。折田の依頼で来た体で龍二たちと会話しつつ、都成には目配せを送り、「この兄ちゃんは関係ない」と言い切り、巧みに場を収めます。彼の“誰の味方でもない”動きは、街全体を俯瞰する“第三勢力”のようでもあり、都成救出も忠誠というより“バランス調整”に見える絶妙さでした。
第8話は、志沢の恋と都成の配達という“日常の行動”が、折田サイドのアジトで偶然(あるいは必然)に交差し、誰かが張った“見えない糸”に若者たちが絡め取られていく回でした。
恋と陰謀が同じホテルの廊下ですれ違い、水町・睦美・インカアジサシという“裏のキーマン”の影が一気に濃くなる。日常の皮をかぶった危険地帯へ、登場人物たちがじわじわ引き込まれていく転換点といえるエピソードでした。
8話についてのネタバレはこちら↓

9話:反逆の狼煙をあげろ――笑顔の夜に仕掛けられた罠
第9話の舞台は、シナントロープの「全品半額イベント」の一日。いつもは穏やかな店が、朝から行列ができるほどの大盛況となり、さらに“似顔絵イラストプレゼント”企画も同時開催。
都成が客の顔を即座に覚え、水町がその人物像を鳥に置き換え、田丸がそのイメージをイラストとして描くという三人の連携が次々と作品を生み出していく。
キッチンでは木場・里見・志沢・環那・塚田が慌ただしく動き、店全体がシリーズでも屈指の“幸せな空気”に包まれていった。
バーミン側で動き始める“処刑”の準備
しかし街の裏では別の動きが進行している。バーミンの実行部隊である龍二と久太郎は、折田から「シマセゲラを始末できたらお前たちを解放する」という条件付きの依頼を受け、自由への希望と、失敗すれば終わりという恐怖の狭間で“最後の仕事”に向けて準備を進めていた。
遊園地デートに潜む水町の影
イベント後の夜、水町は都成を事務所に呼び出し、突然「デートに行こう」と告げる。そのまま二人は遊園地へ向かい、お化け屋敷やアトラクションで笑い合う姿は、これまでの重苦しい展開の中では異質なほど平和で、まるで普通の大学生のような光景だった。
しかし休憩中、都成が「どうして俺?」と尋ねると、水町は「今のうちに大学生っぽいことをしておきたい」と答え、選んだ理由は“消去法”と軽く笑いながらも、その言葉にはどこか影が差していた。
観覧車で明かされる“脅迫”
夜景を見下ろす観覧車のゴンドラの中で空気は一変。水町は、家の周りを髪の長い男と坊主頭の男に見張られていること、何を信じていいのか分からない恐怖の中で生きていることを涙ながらに告白。
「みんな、私のことを殺そうとしている」と震える声で語った。都成は「助けたい」と真っ直ぐに返し、水町は「気づいた。都成はずっと私の英雄だった」と呟いてそっとキスをする。
このシーンは視聴者の間で大きな話題になったが、多くの人が「幸福の瞬間が逆に怖い」と不穏さを感じ取っていた。
“トンビ&キツツキ”パートがついに本筋と交差
同時に、断片的に描かれてきたトンビとキツツキのパートも動く。折田の部屋を見張っていた中年男・トンビと若い男・キツツキは、宅配業者に扮してマンションへの侵入を決行。
トンビは自分の5歳の子どもを家に閉じ込めていると打ち明け、「木の実と木の実がぶつかるような音のガラガラが好きなんだ」と語る。キツツキが「“キノミとキノミ”、バンド名に良さそう」と返した瞬間、視聴者は過去に語られた“クルミのバンド名”と繋がり、二人の時間軸や背景が本編に深く関わる可能性が一気に濃くなった。
幸せの裏で静かに壊されていくもの
エンディングでは、水町と都成のキスシーンの余韻を断ち切るように、闇の映像が差し込まれる。龍二と久太郎が折田の命令で水町の自宅に忍び込み、営業後の誰もいないシナントロープにはバーミン側の人間が襲来して店内を荒らしていく。
半額イベントと遊園地デートという“シリーズで最も幸福な夜”の裏側で、水町の生活と店が同時に破壊され始めている――その残酷な対比を突きつけたまま、第9話は幕を閉じる。
笑顔の夜に仕掛けられた罠。反逆の狼煙はもう上がっていた。
次の第10話で、この“幸福の裏返り”がどこまで加速していくのか、視聴者は不安と期待の両方を抱えながら物語の続きへと向かうことになる。
9話のネタバレはこちら↓
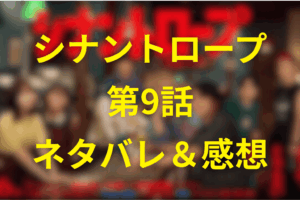
10話:忘れたくなかったんだ
10話は、いつもの朝が一瞬で不穏に転じるところから始まる。都成が「シナントロープ」に出勤すると、店は荒らされ、テーブルも機材も破壊されていた。
壁面には白い文字で「シマセゲラを連れてこい」と大きく残されている。日常そのものだった場所が、誰かの“意図”を突きつける現場へ変貌した瞬間だった。
都成の連絡を受け、木場、田丸、里見、環那、志沢らが続々と駆けつける。しかし、水町ことみとだけは連絡がつかない。この“不在”が、壁に残されたメッセージと結びついた途端、これまでに積み上げられてきた違和感や伏線が一気に輪郭を持ち始める。
裏切りの告白が、事態を一気に変える
荒らされた店内を前に空気を変えたのは、環那だった。耐えきれなくなったように、折田へ情報を流していたことを告白する。里見の部屋に仕掛けられた空気清浄機モニターなど、内部情報が漏れていた理由はほのめかされていたが、それを担っていたのが環那であると明かされるのは、このタイミングだ。
彼女の告白によって、都成たちはようやく折田という男と、その背後にある裏組織バーミン、そしてシマセゲラによる脅迫の一件を“全員で”共有する段階へ進む。
これまでは、誰か一人が断片的に知っているだけの“穴だらけの情報戦”だったが、10話にしてようやく真相のピースが同じテーブルに並べられた。
水町の“不在”が示す予兆と、回収され始める伏線
一方で、水町の行方不明は単なる失踪ではなく、過去の描写と結びつけると大きな問いとして響く。
観覧車で都成に「今のうちにできることはしたい」と語ったこと、幼少期の監禁、ネットでのなりすまし疑惑……彼女が背負ってきた伏線のすべてが、シマセゲラとの関係性を強く示唆する方向へ再配置されていく。
荒らされた店と「シマセゲラを連れてこい」という文字は、脅迫であると同時に“呼び出し”のようにも読める。
考察勢の間では、10話を境にシマセゲラが単なる加害者ではなく“囚われた者たちを解放する媒介”のように描き直されているという読みも出ている。少なくとも視点が「シマセゲラを恐れる側」から「シマセゲラを求める理由」へ転換するのは明確だ。
都成の変化──“守りたい”がようやく行動に変わる
その中で都成のスタンスも変化していく。これまで流されがちで、一歩踏み出せない青年だった彼が、10話では怒りと迷いを抱えながらも「水町が何者でも助けたい」と言い切る。折田が“情報と恐怖”で人を縛るのに対し、都成は“信じる”という感情で立ち向かおうとする。その構図がここでくっきりと立ち上がる。
過去パートでは、トンビとキツツキの物語が、時間軸のトリックを踏まえつつ、現在の事件と重なっていく。
トンビ=水町の父の可能性や、「木の実/キノミ」というモチーフが、音や記憶を通して若者たちの現在の状況と呼応するよう配置され、10話は“すべてがつながっていく”回として機能していた。
反撃の狼煙が上がる
ラストに向けて、荒らされた店・壁のメッセージ・水町の不在・環那の告白という三つの事実が、都成たちの“これからどう動くか”を強く問う形で集約される。彼らはもう、誰かの指示を待つだけの被害者ではいられない。
シマセゲラを“連れていく”のか、“探し出す”のか、それとも“自分たちの側へ引き寄せる”のか――答えはまだ示されない。しかし確かに、11話以降の決着へ向けた反撃の狼煙が上がった回だったと感じさせる締めだった。
10話についてはこちら↓
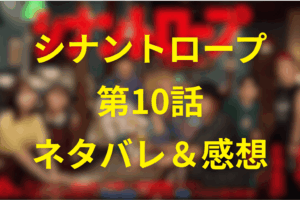
11話:残念なおしらせがある
水町救出へ向けた“準備の回”が本格始動
第11話は、拉致された水町ことみ(山田杏奈)を取り戻すための“救出作戦”が、いよいよ現実の段取りとして動き出す回でした。
都成剣之介(水上恒司)が追い続けてきた「シマセゲラ」――元キノミであり、キノミの“シイ”(栗原颯人)の存在が、ここで「過去」と「現在」をはっきりと接続していきます。断片だった因縁が一本の線になり、物語は最終局面へと向かい始めました。
シイが首を縦に振らない理由と、都成の説得
都成はシイに、水町救出への協力を粘り強く求め続けますが、シイは最後まで簡単には応じません。
この拒否は、恐怖や臆病さだけでは説明できないものです。シイは16年前から折田(染谷将太)と深い因縁で繋がっており、協力することは、自分の過去に再び踏み込む行為でもある。
だからこそ躊躇する。その背景を理解しているからこそ、都成の説得は感情論に流れません。「今は感情よりも段取りだ」と割り切り、焦りの中でも“鍵の順番”だけは崩さない。この冷静さが、都成という人物の一貫した強さだと感じました。
闇の組織〈バーミン〉が見せる“生活者の顔”
一方、闇の組織〈バーミン〉も淡々と行動を続けます。
クルミ確保に失敗した龍二(遠藤雄弥)は、睦美(森田想)に状況を報告したあと、食料調達のためにスーパーへ向かう。この場面が面白いのは、「悪の組織」でありながら行動が一気に生活者レベルへ落ちる点です。
その日常性こそが、逆に追跡の糸口になる。塚田(高橋侃)、里見(影山優佳)、志沢(萩原護)の3人は龍二を目撃し、バイクで待機していた田丸(望月歩)に尾行を依頼。
彼らは感情に任せた突入ではなく、尾行から侵入へと進む地味で合理的な選択をします。この“地味なロジック”こそが、『シナントロープ』らしい気持ちよさです。
明かされる過去と、線を越える瞬間
そしてこの回では、「幼い頃の水町を救った人物」の正体がついに明かされ、物語は決定的な局面へ突入します。
水町奪還に奔走するシナントロープの面々をよそに、ラストでは久太郎(アフロ)が折田と真正面からぶつかり、衝撃的な展開で幕を閉じました。
ここで描かれているのは勝敗ではなく、「誰が、どこで線を越えるのか」という選択の瞬間です。最終話へ向けて、登場人物たちの立ち位置が一段階ずれていく、その不穏な感覚だけが強く残る第11話でした。
11話のネタバレについてはこちら↓
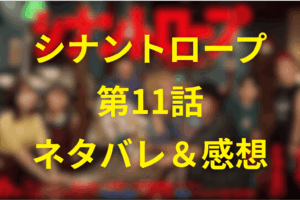
12話(最終回):あの人は…とんでもないです
この話の起点(事件/決断)
クルミと別れて山へ入った都成は、車から降りる龍二を見つけます。
面識があるからこそ「見つかったら終わり」と即座に判断し、顔を隠すため目出し帽をかぶるものの、動きはすでに読まれており、あっさり捕獲されてしまう。右腕を切られ、縛られたまま“折田のもと”へ連行される展開は、ここまで積み上げてきた緊張感の集大成でした。
ただ、都成は抵抗よりも観察を選びます。龍二の怒りや焦りの揺れを見極め、言葉で揺さぶりをかけて隙を作る。
力ではなく判断で主導権を取り返し、拘束を解いて単独で逃走に成功する流れは、都成という人物の本質を端的に示していました。
この話で明かされた事実(確定情報)
追跡する龍二が山中で目にしたのは、折田に殺害された久太郎の遺体でした。相棒を奪われた怒りで龍二は折田を刺し、揉み合いの末、折田は拳銃で龍二を射殺します。偶然その場に戻ってきた都成に対し、折田は「助けを呼びたい」とスマホを要求します。
しかし都成が差し出したのは、発端となった襲撃事件の直後に手に入れていた“折田のスマホ”。
ところが折田はそれを見て「俺のじゃない」と否定し、「突然うちに送られてきた」と語ります。この一言で、“スマホ=折田”という前提が崩れ、山で起きている惨劇が、折田単独の暴走ではなく、もっと前から仕組まれていた可能性が浮かび上がります。
この話の一番ヤバい描写(感情の揺れ)
久太郎の遺体を見た瞬間の龍二の表情、そして復讐が一気に暴発していく流れは、観ている側の呼吸が止まるような重さでした。さらに、重傷を負いながらも折田が逃亡する展開が、「悪が倒れれば終わり」という分かりやすいカタルシスを拒否します。
都成側が結果として“勝った”にもかかわらず、後味は冷たいまま残る。この割り切れなさこそが、『シナントロープ』という作品の核だと感じさせる場面でした。
ラストの引き(疑いが動く)
都成は水町の救出に成功します。しかし本当のクライマックスは、山の決着ではなく、その後に置かれた“1年後”でした。都成は志沢と再会し、「水町の祖父が泥棒のインカアジサシだ」という指摘を受けます。点在していた出来事が、静かに水町へと収束していく。
そして都成は、例のスマホを手に水町へ近づき、「俺と写真撮ってください」と声をかける。彼女の顔の前に画面をかざすと、顔認証でロックが解除される。
この瞬間、スマホは“水町に紐づく物”として機能し、物語の主語が折田から水町へとすり替わります。守られるヒロインなのか、それとも別の顔を持つ当事者なのか。ラスト1分で視点が反転する構成でした。
伏線メモ(回収/未回収)
- 目出し帽:都成が「正体を隠す側」に回る前振りとして回収
- 久太郎の死:龍二の暴走と折田の非情さを確定させる回収
- 折田のスマホ:所有者が揺らぎ、真相のカギとして未回収要素を残す
- インカアジサシ:水町の背景と事件全体を繋ぐ回収
- 顔認証:最後の一手で「誰の物語か」を反転させる合図
最終回のネタバレはこちら↓
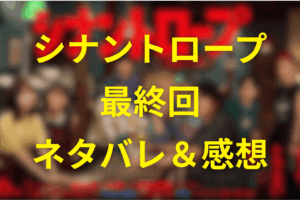
シナントロープのキャスト一覧
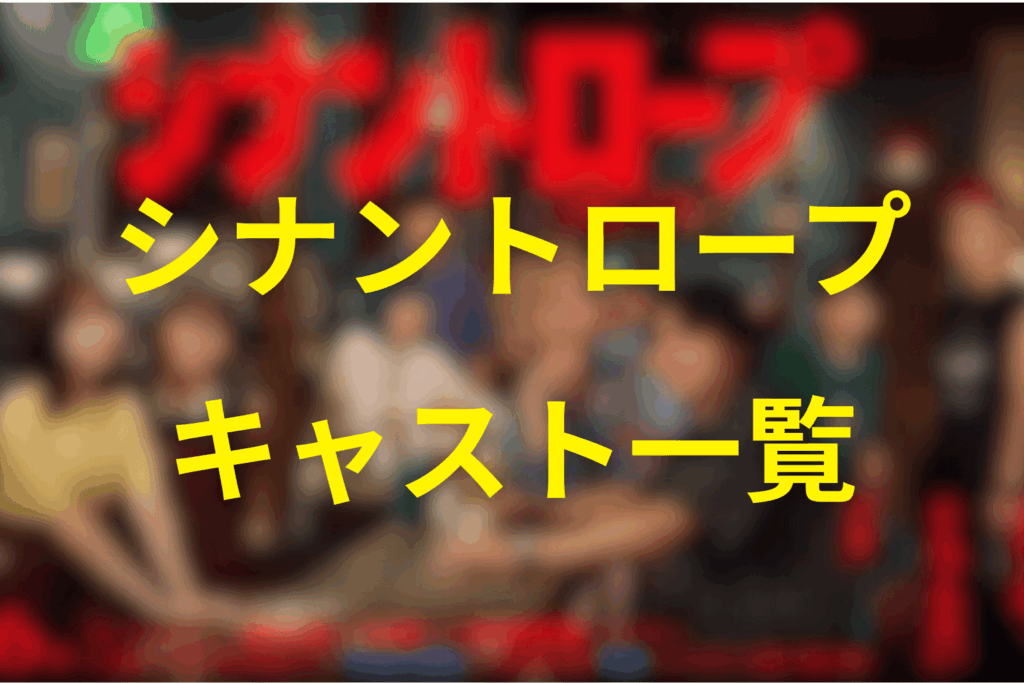
テレ東系ドラマ『シナントロープ』は、『オッドタクシー』の此元和津也が脚本を手掛けるオリジナル作品です。
舞台となるのは街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。主人公・都成剣之介(水上恒司)を中心に、店で働く8人の若者たちと、謎の裏組織〈バーミン〉が交錯する群像劇が描かれます。
バーガーショップ“シナントロープ”のスタッフ
- 都成剣之介(水上恒司)
冴えない大学生。自信はないが温かい心を持つ青年で、店でアルバイトをしている。同僚・水町ことみに密かに想いを寄せる。 - 水町ことみ(山田杏奈)
明るさと影を併せ持つ店員。人懐っこい笑顔の裏に秘密を抱えている。 - 木場寛太〈キバタン〉(坂東龍汰)
店のムードメーカー。お調子者で場を和ませるが、ときおり真剣な表情をのぞかせる。 - 里実奈々(影山優佳)
穏やかで礼儀正しい優等生タイプ。誰にも言えない思いを胸に秘めている。 - 田丸哲也(望月歩)
漫画家志望の優しい青年。仲間の相談に耳を傾ける面倒見の良さが魅力。 - 室田栞奈(鳴海唯)
個性的で“メンヘラ風”と噂される不思議ちゃん。自由奔放な言動で周囲を翻弄する。 - 志沢拓海(萩原護)
新人アルバイトで寡黙な青年。どこかミステリアスな存在感を放つ。 - 塚田竜馬(高橋侃)
バンドマンで店のまとめ役。夢と現実の狭間で揺れながらも仲間思いの頼れる人物。
裏組織〈バーミン〉とその他のキャラクター
バーガーショップの若者たちと対峙するのは、謎めいた裏組織〈バーミン〉。冷酷なトップ・折田浩平(染谷将太)を筆頭に、竜二(遠藤雄弥)、キュウタロウ(アフロ)、ムツミ(森田想)が名を連ねる。彼らが物語にどう絡むかが大きな見どころとなる。
さらに第1話からは、黒田大輔、綾田俊樹、栗原颯人、山本浩司といったベテラン俳優陣のゲスト出演も決定しており、物語に厚みを与えることが期待される。
【全話見て】シナントロープの最終回の結末&伏線回収
ここからは最終回までのネタバレ込みで、「結末」と「伏線回収」をセットで整理します。
シナントロープは途中まで折田がラスボスに見えるんですが、最終回はそこを利用して視聴者の前提をひっくり返してきました。
最終回の結末を時系列で整理(折田・龍二・久太郎/水町)
最終回のクライマックスは、都成が龍二に拘束されながらも揺さぶりで脱出し、折田のもとへ辿り着くところから一気に動きます。そこには、折田に殺害された久太郎の遺体があり、龍二の怒りが折田に向かう。
龍二は折田を刺しますが、揉み合いの末に折田が銃で龍二を射殺。都成は折田にスマホを求められ、都成は“事件の発端となった襲撃直後に手に入れたスマホ”を「折田のスマホ」として差し出します。
ここで折田が言い放つのが、「これは俺のじゃない」。この一言で、折田の“支配者感”が一気にグラつきます。折田は黒幕というより、何者かに踊らされていた可能性が浮上する。
そして1年後。都成は志沢と再会し、志沢が「水町の祖父が泥棒のインカアジサシ」だと指摘します。
都成が水町と再会したラスト、都成は水町に「俺と写真撮ってください」と頼み、彼女の顔でスマホの顔認証を通してロックを解除する。つまり、あのスマホは水町側に繋がっていた。最終回はこの“解錠”で終わります。
伏線回収1 スマホは「折田の持ち物」ではなかった
最終回の伏線回収で一番気持ちいいのがここです。
視聴者は「折田のスマホ=折田の支配の証拠」と思い込んでいたのに、折田本人が否定し、さらに顔認証で水町に紐づく形で回収される。これ、情報の持ち主が“犯人側”から“別のレイヤー”へ移った瞬間なんですよね。
伏線回収2 インカアジサシ(=水町の祖父)で、家系の匂いが変わる
志沢の口から出た「泥棒のインカアジサシ」という情報で、水町は“巻き込まれた被害者”から、“物語の中枢にいる側”へ立ち位置がズレます。
最終回の終盤で、折田より怖いのは水町かもしれない、という視聴者の反応が出たのも納得です。
伏線回収3 折田は「終点」じゃない シマセゲラ線が残る
最終回で折田は確かに大きな役割を果たしたけど、「スマホが俺のじゃない」と否定した時点で“黒幕の椅子”から降りるんですよね。ここがこのドラマの意地悪で面白いところで、視聴者が安心して憎める悪役を用意しつつ、最後に「もっと根が深い」と示して終わる。
シマセゲラの正体や目的まで断言できる描写は残していませんが、少なくとも最終回は「水町に繋がる鍵」が提示された、ここだけは確定です。
未回収の謎(続編があるなら刺さるポイント)
・水町は“何者”として動いていたのか
・インカアジサシの盗みと、今回の事件はどう繋がるのか
・折田は本当にただの駒だったのか(誰に動かされた?)
この3つが残ったおかげで、最終回なのに変に閉じず、後味が不穏で終われた。僕はこの終わり方、かなり好きです。
【全話見て】シナントロープの感想&考察
ここからは感想と考察なので、確定情報と切り分けつつ書きます。
シナントロープは“犯人当て”でスッキリする作品というより、視点が切り替わるたびに、同じ出来事の意味がズレていく怖さが芯にありました。
この作品が刺さるのは「観察される側の恐怖」を徹底したところ
都成はずっと“見てしまう側”の人間なんですが、物語が進むほど「見ているつもりが、見られていた」に変わっていく。
最終回のスマホ解錠は、その象徴でした。都成が追い詰めたと思った折田よりも、もっと静かに深い場所にいる存在がいた、という後味。
折田をラスボスに見せておいて、最後に主役を水町へ渡す脚本
最終回で折田が「俺のじゃない」とスマホを否定した瞬間、物語の主役は“折田を倒す話”から“水町を読み解く話”に切り替わりました。
これ、全話見たあとに振り返ると、序盤から水町だけ「守られているようで、輪郭が薄い」描き方だったのも伏線っぽい。
水町は善悪で裁けない だから怖いし、惹かれる
水町がもし黒幕だとしても、単純に“悪”とは言い切れない描き方がされているのがポイントです。
表情の揺れ、距離感、そして「都成との再会」をあえて甘く見せる演出。最終回で回収されたのは“水町が鍵”という事実で、動機は視聴者に投げられた。だからこそ、続編やスピンオフに繋げられる終わり方にも見えます
もし続編があるなら、僕が見たいのは「都成の選択」
都成は最後、スマホのロックを開けるために水町に写真を頼みました。
あれは“証拠のため”にも見えるし、“君を疑ってる”の意思表示にも見える。続編があるなら、都成がどっち側の人間になるのか。信じるのか、追うのか、同じ側に立つのか。ここが次の物語の一番の勝負どころだと思います。
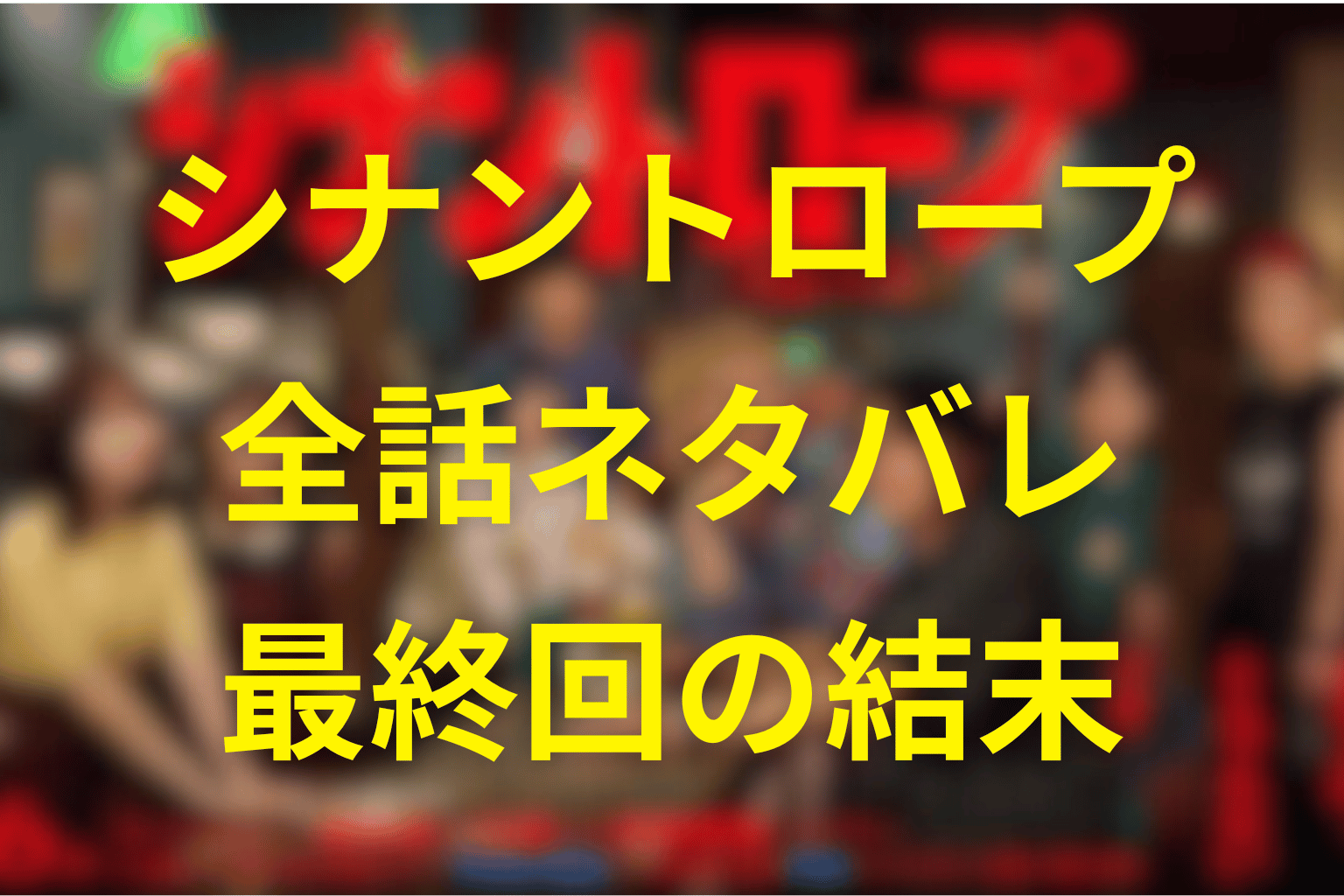
コメント