2019年に刊行された早見和真さんの長編小説『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬を舞台に家族の絆や夢の継承を描いた感動巨編です。
親から子へ、そしてさらに次の世代へと受け継がれていく情熱や信念を、競走馬の血統と重ね合わせて描いた物語は、発売当初から高い評価を受け、第33回山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞しました。
2025年10月12日からTBS日曜劇場でドラマ化され、12月14日に最終回(拡大SP)を迎えます。
この記事では、原作小説のあらすじやネタバレ、そして読後の感想を詳しく紹介し、映像化に向けて作品の魅力を改めて掘り下げます。
原作『ザ・ロイヤルファミリー』の結末だけ先に(ネタバレ)
まず「結局どう終わるの?」を先にまとめます。結末を知ってから、時系列の整理に入りたい人向けです。
物語の大きな到達点は、やはり有馬記念。
ロイヤルの血に夢を託した人々が、最後に“勝負の舞台”へ集まります。
ただし、原作本編の終わり方は、有馬記念で2着という結果に終わり、スカッとした“優勝エンド”ではない。
勝ちきれなかった現実と、それでも確かに届いた夢の手応えが、読後に余韻と痛みとして残るタイプの結末です。
物語の最後の「ロイヤルファミリー競走成績表」でその後の成績が出る
そして決定的なのが、ラストに載る「ロイヤルファミリー競走成績表」。あの“無機質な表”が、言葉より雄弁に「その後」を語る仕掛けになっています。
成績表の内容は(フィクション内の記録として)大阪杯/天皇賞(春)/凱旋門賞/ジャパンカップ/有馬記念…と、読者が思わず二度見するレベルの勝ち鞍が並ぶのがポイントです。
つまり、この作品は「物語本編で勝ち切らない」代わりに、“結果だけが残る”形で夢を時間差で叶える――この二重構造がラストの核です。
ここから先で、「なぜこんな終わり方が効くのか」も含めて整理します。
原作小説『ザ・ロイヤルファミリー』とは?作品情報と受賞歴
先に、作品の土台となる基本情報を押さえておきます。
ここを整理しておくと、以降の考察がブレにくくなります。
『ザ・ロイヤルファミリー』は早見和真さんによる長編小説で、単行本は2019年10月30日に刊行されました。その後、2022年11月28日に文庫版も発売されています。
また本作は、2019年度のJRA賞馬事文化賞、さらに第33回山本周五郎賞を受賞しており、“競馬×大衆文学”という枠を超えて高い評価を受けた一作です。
競馬を題材にしながら、人間の欲望や継承、家族の物語を重層的に描いた点が、多くの読者と選考者の心をつかみました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著者 | 早見和真 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 単行本 | 2019/10/30刊 |
| 文庫 | 2022/11/28刊(新潮文庫) |
| 受賞 | 2019年度JRA賞 馬事文化賞/第33回 山本周五郎賞 |
| 特徴 | 馬主一家の“約20年”を描く長編。競馬の知識がなくても読めるよう設計されている |
JRA賞の選評でも「血の継承」をテーマに、馬主の世界を疑似体験できるリアリティが評価された、と整理されています。
【ネタバレなし】原作『ザ・ロイヤルファミリー』あらすじ|物語の入口
ネタバレに入る前に、まずは物語の入口となるあらすじを簡単にまとめます。
主人公は税理士の栗須栄治。
父を亡くし、どこか空虚さを抱えた彼は、馬主として“ロイヤル”冠の馬で有馬記念制覇を目指すワンマン社長・山王耕造と出会います。栗須はその山王の秘書として働くことになり、次第に競馬という世界の奥深さと、山王が背負う「夢」に触れていきます。
そして、競馬にのめり込む山王と行動を共にするうちに、栗須自身もまた“夢の継承”という大きな渦に巻き込まれていく――。
ここが、『ザ・ロイヤルファミリー』という物語のスタート地点です。
【ネタバレ】原作『ザ・ロイヤルファミリー』あらすじを時系列で整理

ここからはネタバレありで、原作の流れを「大きな構造」で整理します。
この作品は、ざっくり言うと第一部→第二部で“主役(世代)が入れ替わる”構造が効いていて、ここを押さえると理解が一気に楽になります。
第一部「希望」:栗須と山王、ロイヤルホープの物語
第一部の核はシンプルで、「山王耕造の夢に、栗須栄治が付き添う」という構図です。
競馬の世界は、才能よりも運、努力よりも血統、そして何より“継続”が残酷に試される。その現実に、栗須は秘書として足を踏み入れていきます。
転機となるのが、牧場(ノザキファーム)から持ち込まれる一頭の馬。
これが後にロイヤルホープと名付けられます。
ロイヤルホープは気性面に難しさを抱えつつも、山王に懐くような“クセの強い存在”として描かれるのが特徴です。
この第一部は、勝ち切れない現実と、それでも諦めない執念が積み上がっていく章。ここで味わう「勝てない痛み」が、そのまま第二部へと受け継がれていきます。
第二部「家族」:相続で受け継がれる“血”と、ロイヤルファミリー誕生
第二部では、舞台が「山王の夢」から、さらに一段深い「血の継承」へと移ります。
鍵になるのが、相続という制度と、血統という“逃げられない運命”です。
象徴的なのが、「相続馬限定馬主」という設定。これが“親から子へ”という流れを、競馬のルールそのものとして物語に組み込む装置になっています。
そして登場するのが中条耕一。
第一部では中学生だった彼が、第二部では24歳となり、物語は完全に“息子世代”へ引き継がれます。
第二部で中心となるのは、ロイヤルホープの産駒たち。
中でもタイトルそのものを背負う競走馬がロイヤルファミリーで、父ロイヤルホープ、母ロイヤルハピネスという血統が強調されます。
さらにロイヤルリブラン、ロイヤルレインといった馬も登場し、“血が広がっていく”感覚が一気に強まっていくのが、この章の醍醐味です。
クライマックス:有馬記念、勝ち切れない“ロイヤル”の宿命
物語が向かう先は、やはり有馬記念。
この作品は「有馬記念=ゴール」ではなく、「有馬記念=呪い」のように扱ってくるのが、残酷であり巧みです。
クライマックスでロイヤル・ファミリーは有馬記念で惜しくも2着…。
勝つためには、才能だけでも、努力だけでも足りない。血を揃え、チームを作り、時間を積み重ねても、最後の最後で届かない。
この“届かなさ”こそが、ロイヤルの宿命として描かれます。
ラスト:競走成績表が明かす“その後”——勝利を文章で描かない理由
そしてラストの仕掛けが、競走成績表です。
物語本編は余韻を残して閉じる一方で、最後の表だけは冷酷なほど「結果」だけを並べてくる。
そこには(フィクション内の記録として)大阪杯、天皇賞(春)、凱旋門賞、ジャパンカップ、有馬記念といった勝利が記され、「夢は叶った」と分かる。
にもかかわらず、その勝利の瞬間は物語として描かれない。
ここに、作者の強い意志を感じます。
勝利は描けば描くほど消費される。しかし成績表は、読者の想像の中で勝手に膨らむ。だからこそ静かで、でも強烈に刺さる——そんな終わり方になっているのだと思います。
原作「ザ・ロイヤルファミリー」の“キャラクター別”のネタバレ

※ここから先は原作小説の核心に触れるネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。
ロイヤルファイト――白毛の“希望”と、逃げ水のような栄光
ロイヤルファイトは、ロイヤルイザーニャと対をなす存在として描かれます。まずその特徴的な白毛が視覚的な象徴となり、ロイヤル軍団の“看板”として計画された馬です。
作品紹介でも、ロイヤルイザーニャと並ぶ「ロイヤル」軍団の中心として提示され、その白い姿が“希望”のアイコンへと変換されていきます。
ドラマでは第2話の段階で、栗須(クリス)がファイトとイザーニャの調教師探しに奔走する構図が明確に示されます。ここで描かれるのは、オーナーの夢を“走れる形”に変える現場の采配――つまり人間の選択の重要性です。ロイヤルの勝敗は馬の能力だけで決まらない。管理者、騎手、牧場、資金、それぞれのエコシステムが噛み合って初めて“期待馬”が真の期待へと変わる。その現実をファイトが象徴しています。
一方で、第3話ではファイトが負傷し、希望の象徴だった白毛の存在が一転して痛ましい現実を突きつけます。華やかな“ロイヤル”の名とは裏腹に、栄光は逃げ水のように遠のく。
また、作中の枠を超えて“ロイヤルファイト”という名は現実の競馬界でも話題を呼びました。新潟競馬場で開催されたJRAイベントでは、誘導馬オースミムーンが“ロイヤルファイト”名義のゼッケンやブランケットを着用し場内を歩くコラボ演出が行われたのです。白毛の看板馬=ファイトという記号性が、現実の競馬ファンにも共有される仕掛けであり、ドラマと実競馬の境界を越えた“希望の象徴”の拡張が試みられています。
総じて、イザーニャは“血を繋ぐ”存在であり、ファイトは“夢を掲げる”存在です。前者が血統と時間を紡ぐ物語なら、後者は理想を形にするビジョンそのもの。勝敗を超えて、二頭が背負う意味――“ロイヤル”という名にふさわしい象徴性の深さこそが、この物語の余韻を決定づけています。
ロイヤルイザーニャ――“継承”の象徴になった最後の子
物語における「イザーニャ」は、まず母馬の名前として登場します。スペインの地名に由来する名で、9年前に牧場主の息子が名付けたという設定。
老いた繁殖牝馬が「おそらく最後の子」を産む――その“最後”に希望を託すという山王(ロイヤルヒューマン)側のドラマが重なる構成が巧みです。のちにその子馬は「ロイヤルイザーニャ」と名付けられ、ロイヤル軍団の一頭として戦列に加わります。ここに“血をつなぐ”という本作のテーマが象徴的に結びつきます。
もっとも、ロイヤルイザーニャは生まれながらの完成馬ではありません。脚元の弱さを抱え、注目を集めることもなく2歳秋の新馬戦では11着、続く未勝利戦でも12着と惨敗。短期放牧を経て年明けにようやく初勝利を挙げる――そんな地味で現実的な成長曲線を描きます。派手さこそないものの、“負け続けてから勝つ”という物語が、ロイヤル軍団に現実的な希望をもたらす設計となっているのです。
ドラマ版でもこの流れは踏襲され、競馬事業部は未勝利戦を制したイザーニャによって一時的に救われます。ところが、その直後にイザーニャと(後述の)ファイトが揃って負傷する事態が発生し、物語は再び暗転。希望が見えた矢先に不確実性が襲うという展開が、耕造とクリス(栄治)の関係や、組織の意思決定、そして“継承”をめぐる不安と執念を浮かび上がらせていきます。勝利は終着点ではなく、次の試練の始まり――その哲学が明確に打ち出されています。
ロイヤルイザーニャの存在意義を一言で表すなら、「血統の炎を絶やさない証」。
山王が“馬ではなく人を買う”――すなわち信頼できる人間に投資するという理念を掲げる以上、イザーニャの一勝はその信念の正しさをかろうじて支える証左となります。才能の爆発ではなく、弱点と向き合いながら周囲の大人たちが積み重ねた努力の結晶としての小さな勝利。だからこそ、その後の負傷は痛烈に響く。ロイヤルが本当に“継承”を語るに値する陣営であるのか――イザーニャはその試金石となっているのです。
ロイヤルホープについて(引退/原作ネタバレ)
“ロイヤル”計画の第一章を担う存在がロイヤルホープです。
耕造は栗須に導かれて日高のノザキファームを訪れ、そこで見立てた若駒に〈ロイヤルホープ〉と名を授けます。ホープのデビュー勝利によって山王家の“夢”は動き出し、経営難にあえいでいた牧場にも再び光が差す。
原作ではこの馬を、家と人の再生の象徴として描いています。
しかし、彼らの物語は「あと一歩届かない希望」として刻まれます。
2010年、ホープは“引退を懸けた三連戦”として天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念に挑むものの、すべて惜しくも2着。勝利に手が届かなかったこの結果が第一部の象徴となり、次世代が越えるべき“夢のハードル”として作品に残されます。
引退後のホープは、配合戦略の中心的な存在となります。
耕造が生前に決めたロイヤルホープ×ロイヤルハピネスの血統から生まれた仔に、耕一が〈ロイヤルファミリー〉と命名。この瞬間、“ホープ(希望)”から“ファミリー(家族)”へと名が受け継がれ、物語は父から子、馬から馬へとバトンが渡される。ここから第二部が幕を開け、継承の物語が本格的に動き始めます。
山王耕造の秘密と“ロイヤルファミリー”の誕生
山王耕造は強烈な夢を追い続ける一方で、その胸の内に秘めた過去がありました。
実は耕造には若い頃に心を通わせた女性との間に中条耕一(なかじょう こういち)という隠し子がいたのです。長らく存在を公にしていなかった息子・耕一の登場により、物語は大きく動き始めます。
山王は自分が果たせなかった夢の続きを耕一に託そうと決意し、自身の築いた財産や競馬への情熱を次世代へ引き継ぐことを考えます。
ちょうどその頃、山王の愛馬ロイヤルホープにも新たな展開が訪れました。ロイヤルホープは引退し、その仔馬が誕生します。山王は生まれたサラブレッドに「ロイヤルファミリー」と名付けました。こうして物語の後半では、馬主の座が父・耕造から息子・耕一へと受け継がれ、栄治は今度は新オーナーである耕一を支える立場となっていきます。
野崎加奈子の息子“野崎翔平”について
北海道・日高の生産牧場「ノザキファーム」で馬に囲まれて育った、加奈子の一人息子。ドラマでは三浦綺羅さんが演じ、内気ながらも馬の世話を率先してこなす少年として描かれています。母・加奈子の実家が牧場という環境が、彼の“馬を見る目”と身体感覚を自然に磨き上げているのが物語の出発点です。
原作の後半、物語が「父から子へ」という継承の段階に入ると、騎手たちの世代交代が訪れます。
かつてロイヤルホープで主戦を務めた名手・佐木隆二郎の後継者として、彼に憧れてきた若き翔平がロイヤルファミリーの騎手に抜擢される――それが物語の大きな転機となります。作者のインタビューでも「オーナーは耕造から耕一へ、馬はロイヤルホープからロイヤルファミリーへ、そしてジョッキーは佐木から野崎翔平へ」と、“三重の継承”が語られています。
クライマックスの有馬記念では、翔平がロイヤルファミリーの手綱を握り、ライバルの椎名善弘が所有する“ビッグホープ”(鞍上・佐木隆二郎)と壮絶な叩き合いを繰り広げます。結果はハナ差の2着。この“あと一歩届かない”結末が、親世代の未完の夢と子世代への宿題を象徴する印象的な構図になっています。
その直後、耕一が「ここで終わらせない」と引退を撤回し、ロイヤルファミリーのさらなる快進撃を予感させて物語は幕を下ろします。勝利よりも“夢を継ぐ意志”を描く――翔平はその理念を体現するキャラクターなのです。
ドラマ版でも、幼い頃から馬の癖や体調を身体で掴んできた翔平が、緊張に呑まれずに“馬のリズム”へ自分を委ねる姿は大きな見どころになるでしょう。単なる“天才少年”として描くのではなく、ノザキファームでの厳しい日常――堆肥の匂い、冬の馬体管理、早朝の放牧――といった積み重ねが、やがて鞍上での胆力に変わる。そのリアリティこそが、翔平という人物の核心を支える要素になるはずです。
野崎翔平についてはこちら↓
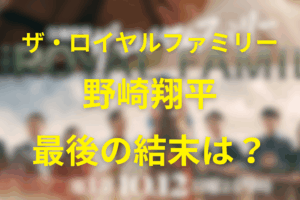
若き馬主・中条耕一の葛藤と挑戦
中条耕一は父とは異なる若い感性と天才的な馬を見る眼を持ちながらも、血筋ゆえの複雑な想いを抱える青年でした。
耕一の魅力は、“若さ”と“才覚”が同時に存在している点にあります。
制度面では「相続馬限定馬主」という制度を利用し、複数の競走馬の馬主に就任(うちの1頭がロイヤルファミリー)。これにより、既存の体制を飛び越えて競馬界の中枢に切り込んでいきます。
さらに、馬の完歩(ストライド)や跳躍の大きさから距離適性を見抜く観察眼を持ち、経験豊富な栄治やベテラン調教師とも臆せず意見を交わす。その若さゆえの未熟さが衝突を生む一方で、常識を覆す突破力にもなっており、そこに彼の人物像の核が見えてきます。
クライマックスとなる有馬記念では、耕一×ロイヤルファミリー×(騎手)野崎翔平という“新生トリオ”が悲願の頂点に挑むも、結果はわずかに届かず2着。それでも耕一はその場で引退撤回を宣言し、父・耕造が追い求めた夢を“終わらせない物語”として継続することを決意します。この「敗北と決断」の組み合わせが、血縁の宿命や功罪を超えて“継承=続けること”というテーマを再定義するフィナーレの核心となります。
総じて耕一は、血のドラマを制度(馬主資格)・経営(馬の選定と体制構築)・技術理解(馬の適性判断)によって現実に落とし込み、耕造のロマンと栄治の忠誠を“勝てる仕組み”へと翻訳する人物です。
耕造に隠された過去=婚外子の存在が、物語後半で“家族”という概念を再構築する原動力となり、その中心に立つのがこの中条耕一。彼はまさに、“ロイヤルファミリー”という名にふさわしい新時代の継承者なのです。
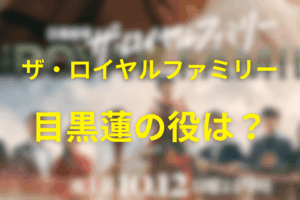
ライバル馬主「椎名義弘」について
原作小説での椎名義弘は、人材派遣会社最大手「株式会社ユアーズ」の創業者兼経営者であり、同時に新興トップ馬主として登場します。日本ダービーを含む複数GIタイトルの制覇歴を持ち、栗須より二歳年上ながら、山王耕造を上回る華々しい実績を積み上げてきた“鉄人”として描かれています。
公の場ではほとんど表情を変えず、勝利時さえ淡々と数字とデータを基準にレースを評価する人物。感情より合理性を優先し、利益と勝率を迷いなく追求する姿が、夢へ命を懸ける山王ラインや栗須ラインと鮮やかな対比を生んでいます。
物語第一部では、山王耕造の前に立ちはだかる“絶対的な壁”であると同時に、栗須にとっては追いつきたい“指標”として存在。山王が「ロイヤルファミリー」立ち上げへ踏み切る背景には、義弘へ抱く劣等感と敬意の入り交じった複雑な感情が強く働いている、という読み方もできます。
義弘自身は、単なる金満馬主ではなく、馬を見る目にも優れた人物。
北陵ファームの出身馬だけでなく、日高の中小牧場出身馬にも積極的に目を配り、“資本力・情報力・審美眼”を兼ね備えたプレイヤー像として立ち上がります。栗須や山王が理想へ挑む側なら、義弘は冷静に成果と結果を積み上げる“現実側の象徴”と言える存在です。
ドラマ版では名前が「椎名善弘」へと変更され、沢村一樹さんが演じています。
人材派遣会社「ソリュー」CEOであり、日本競馬界有数の馬主という設定は原作と同じ軸にあり、無表情かつ精密機械のような強者感もそのまま。原作読者の視点では、“義弘像をほぼそのまま映像化したキャラクター”という印象が強い仕上がりです。
ザ ロイヤル ファミリー原作「椎名展之」について
第二部以降で存在感を増していくのが、椎名義弘の長男・椎名展之です。耕一より一歳年長の若手馬主で、ライバル関係を築きながらも「有名人の父を持つ息子」という共通点から、中条耕一と独特の距離感を保つキャラクターとして描かれます。
父・義弘が無口で硬派な“鉄人”なら、展之はその真逆。社交的で軽口も多く、時に挑発的な発言で場をかき回します。しかし内面は軽いボンボンではなく、父譲りの馬眼力と大胆な勝負勘を兼ね備えた、したたかな戦略家。スポーツ紙での連載コラムを通じて停滞した競馬界へ切り込む姿を見ると、若い世代として既存の権益にメスを入れる役割を担っていると感じられます。
原作終盤では、ロイヤルホープ産駒「ソーパーフェクト」の購入者として物語上の重要ポジションに昇格。
北陵ファームのセリ市でこの馬を落札し、佐木隆二郎へ騎乗依頼する流れは、ロイヤルファミリー陣営にとって“最大のライバル誕生”を告げるシーンとして大きな意味を持ちます。展之は、自身の利益だけでなく「競馬全体を盛り上げたい」という野心も覗かせ、後半のレース描写に躍動感と化学反応を与える存在です。
義弘が山王耕造世代のライバルであるなら、展之は中条耕一世代のライバル。父子二代に渡って山王家・栗須ラインと対峙する構造そのものが、原作のテーマである「血筋」「家同士の因縁」と強く呼応しています。
耕一にとって展之は、敵でありながら“自分が歩むかもしれなかったもう一つの未来像”でもあり、その複雑な感情がクライマックスのレース描写へ厚みを加えています。
ドラマ版では、展之役に中川大志さんを起用。大学卒業後に起業し、若手馬主コミュニティで頭角を現す人物として描かれる設定は原作と共通しています。目黒蓮さん演じる耕一と、中川さん演じる展之がどのように“同世代ライバル”として描かれるのか──原作ファンとしても楽しみなポイントです。
椎名展之についてはこちら↓
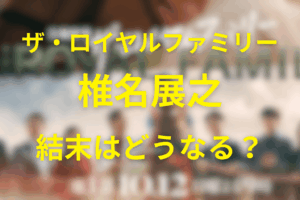
原作小説「ザ・ロイヤルファミリー」の結末。有馬記念の結果は?
長編全体は、山王耕造が掲げた「自分名義のロイヤルで大舞台制覇」という願いが、年月積み重ねつつ息子・中条耕一や秘書・栗須栄治、さらに名馬ロイヤルファミリーへ受け継がれていく物語として締めくくられます。
ラストは派手なハッピーエンドではなく、一度敗北経験挟んでから、静かな仕掛けで“夢が続いていく”姿示す構成になっています。
有馬記念での惜敗と耕一の揺らぎ
クライマックス扱いになる有馬記念では、耕一が馬主という立場でロイヤルファミリーに騎手・野崎翔平乗せ、ライバル勢と顔ぶれそろった大一番へ挑みます。
反対側陣営には、亡きロイヤルホープ血引くビッグホープやソーパーフェクトなど、山王耕造ゆかり血統がずらり。ジョッキーは、かつてホープと共闘した名手・佐木隆二郎です。
ゴール前でロイヤルファミリーが差し脚伸ばし、観客が「勝った」と確信しそうになる瞬間、外からビッグホープが急襲。写真判定結果はごくわずかな差で二着。
レース後、興奮状態続くロイヤルファミリー姿目にした耕一は、「本当に引退させてよいか」「父から託された夢はこの地点で終幕迎えるべきか」と激しく葛藤しつつ、自分自身と向き合う局面へ追い込まれていきます。
成績表だけが語る“その先の物語”
原作の物語本編は、有馬記念後もやもや抱えたまま幕閉じます。
ただし最後ページに、ロイヤルファミリー競走成績表がひっそり掲載されている点が重要です。そこには翌年以降も現役生活続行中である事実が並んでおり、大阪杯、天皇賞(春)、凱旋門賞、ジャパンカップ、さらに次年度有馬記念でついに優勝達成した経歴確認できます。
馬主欄には中条耕一名義が残り、彼が引退表明いったん撤回し、血統と夢へ責任抱えたまま走り続けた事実暗示されています。
つまり原作ラストでは、山王耕造本人は既に他界済みでありながら、彼が掲げた悲願自体は息子とロイヤルファミリーコンビにより時間差実現した、という着地になります。
有馬記念本編で感じる痛み混じり結末と、成績表側で静かに示される“その後の栄光”が二重らせん状に絡み合い、「継承とは、夢断ち切らない意思そのものだ」と読者へ強く印象付けるラストになっていると言えるでしょう。
ザ・ロイヤル ファミリー原作とドラマの違い
ドラマ版『ザ・ロイヤルファミリー』は、原作小説の「骨格」と「ラストの思想」をかなり忠実に押さえつつも、細部の設定や人物配置を大胆に組み替えた“再構成版”という印象です。
とくに、物語のスタート地点(時代)・栗須栄治の立ち位置・山王家の家族関係・競走馬たちの描写は、映像ドラマとしてのメリハリを出すために意図的に改変されています。
ここからは、原作とドラマの主な違いを整理しながら、「なぜその改変が加えられているのか」という観点も含めて分析していきます。
時代設定とスタート地点の違い
原作は1990年代半ば〜後半が物語の起点。栗須栄治がロイヤルヒューマンに関わり始めるのは1996年前後で、当時の景気や雇用状況とリンクして描かれます。
一方ドラマ版は、冒頭で「2011年」という字幕を提示し、そこから現在につながる約20年を描く構成。
インターネット、SNS、人材ビジネス、震災後の価値観など“現代のリアリティ”を物語に落とし込むため、時代軸が大胆にアップデートされています。
その結果、
原作=平成の雇用史と競馬の物語
ドラマ=震災以後〜令和の日本を走り抜けるロイヤル軍団の物語
という構図が鮮明になっています。
栗須栄治の立ち位置と家族設定の改変
原作の栄治は“小さな税理士事務所の青年”で、父と兄と暮らす三人家族。母の死の設定も含め、素朴で静かな生活圏が描かれます。
ドラマ版では、
- 栄治は大手税理士法人勤務のエリート
- しかし大きな挫折を経験
- そのタイミングでロイヤルヒューマン調査を依頼される“外部コンサル的な入口”に変更
と、キャリア設定が大幅に変更。
さらに 原作にいない“姉”が追加され、栄治の孤独を和らげる存在として描かれつつ、
「夢を家族にどう説明するか」
というテーマを丁寧に見せる役割も担っています。
山王耕造との出会い方と、山王優太郎のキャラクター
原作では、耕造と栄治は“ロイヤルダンスの馬券”を通じて出会います。
静かな天ぷら屋での語らいが導入になる一方、
ドラマ版は北海道の競り会場でドラマチックに対面。馬の目利きに関するやり取りから、耕造の存在感とドラマ性を一気に高めています。
また、息子の山王優太郎の描かれ方も大きく異なり、
- 原作 → 対立はあるが“完全な敵ではない”支社長
- ドラマ → リストラと事業整理を進め、競馬事業部を潰そうとする“敵役”
という鮮やかな対立構図が強調されています。
これにより、
「夢を守る父」vs「会社を守るために夢を切る息子」
というドラマ性が明確な軸となっています。
野崎加奈子との再会タイミング
原作では栄治がロイヤルヒューマンに入ってから7年後に加奈子が再登場します。長い時間の積み重ねが物語の重厚さを生みます。
しかしドラマはテンポを優先し、
- 第1話のコンビニで偶然再会
- 早い段階から加奈子と翔平を物語に組み込む
ことで、視聴者が感情移入しやすい家庭ドラマ的ラインを初回から立ち上げています。
ロイヤルヒューマンの経営状況と“競馬事業部”の扱い
原作のロイヤルヒューマンは成長中の会社で、競馬事業部も“社長の夢”として前向きに扱われます。
ドラマ版では設定が逆転し、
- 業績不振
- リストラ・事業整理の危機
- その中で真っ先に切られそうになる“遊び扱い”の競馬事業部
という、より切迫した状況に置かれています。
夢の尊さと危うさ がドラマでは強調されています。
ロイヤルファイト/ロイヤルイザーニャの描き方
原作のロイヤルファイトは比較的“地味な白毛馬”。
イザーニャの引き立て役として描かれます。
ドラマ版ではロイヤルファイトを前面に押し出し、
- 毛色の変更
- 第1話から印象的に登場
- 「ロイヤルの希望」を象徴する馬として扱う
という映像的演出が加えられています。
イザーニャも、
- 原作 → 時間をかけて少しずつ階段を上がる
- ドラマ → 短期間で“勝利→負傷”という大きな起伏
というスピーディーな成長曲線に再構成されています。
佐木隆二郎の「出自」そのものが、原作とドラマで別物
ドラマ版の佐木隆二郎は、キャラクターの“性格”以前に、まず出自=立ち位置が原作と大きく異なるのが興味深いポイントです。
第4話あたりの描写を見ると、ドラマの佐木は「岩手競馬所属の金髪ジョッキー」として登場し、中央の騎手免許取得には高いハードルがある――そんな“越境者”の匂いを背負っています。だから視聴者は、佐木を単なるチャラい天才ではなく、「上に行くためにすべてを賭けている男」として受け取りやすい。
一方、原作の佐木はより露骨です。
良くも悪くも、最初から「強い馬に乗る側の人間」として描かれており、強い馬にしか興味を示さず、馬主に対しても不遜な態度を崩さない問題児。それでも有力馬主から声がかかる――つまり、腕だけは疑いようがない、という設定です。
この違いこそが改変の肝だと思います。ドラマでは佐木を一度「チームロイヤルの一員」として丁寧に描き、“育てる”プロセスを挟むことで、後半の移籍――ソーパーフェクト側に立つ展開を、単なる裏切りに見せないようにしている。
つまりドラマ版の佐木は、悪役として消費される存在ではなく、「勝てる馬に乗る」という競馬の職業倫理を体現するリアリストとして再配置されている。原作とは違う出自を与えたことで、その選択により深い説得力が生まれているように感じます。
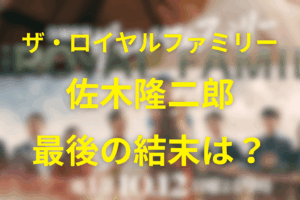
中条耕一(耕造の“もう一人の息子”)の年齢と役割
原作では後半の切り札として高校生くらいの年齢で登場しますが、ドラマ版は大幅に早い段階で投入。
- 大学生〜社会人前後へ年齢を引き上げ
- 物語序盤から登場
- 人気俳優を配し、父子ドラマを強調
という方向性により、物語全体を通じて“家族の再生”を描く構造になっています。
ソーパーフェクトは原作だと「好敵手」、ドラマだと「時代の覇者」で立ち上げてくる
ソーパーフェクト周りは、ドラマ後半の主役級。ここはもう一段、原作における“馬としての立ち位置”を整理すると、原作とドラマの差がよりはっきり見えてきます。
原作のソーパーフェクトは、椎名展之の愛馬であり、ロイヤルファミリーの好敵手として描かれます。設定を細かく見ると、ロイヤルホープ産駒で、セレクタリアセールで1900万円落札という数字が示され、“お買い得感”のある存在でもある。だから原作のソーパーフェクトは、ただの金満馬ではなく、相馬眼と運、そして育成が噛み合って成り上がったライバルとして立ち上がるんですよね。
対してドラマ版は、公式あらすじの段階からソーパーフェクトを「クラシック三冠を制した“時代の覇者”」として提示してきます。さらに有馬記念の最有力候補として、ロイヤルファミリーの前に“条件”のように立ちはだかる。この描き方は、原作のライバル像を、映像向けにより分かりやすく、かつ強度を上げて増幅している印象です。
原作が
「強敵がいるからこそ、勝利が尊い」
という構造だとしたら、ドラマは
「覇者がいるからこそ、勝利が奇跡になる」
という構図を取っている。
だからこそ、ソーパーフェクト陣営の“鞍上(ジョッキー)”の演出が、次の大きな改変──ルメール投入──へと自然につながっていくわけです。
佐木隆二郎の“転身”が、ドラマではよりドラマチックに描かれる
佐木隆二郎は、公式プロフィールでも「強い馬に乗ることにこだわり、GⅠでの勝利を目指す」騎手として紹介されています。
そして第8話では、耕一がロイヤルファミリーの主戦を翔平に託す流れの中で、佐木がチームロイヤルから去り、ソーパーフェクトに騎乗して“ライバル側”に立つ展開が描かれました。
第9話の公式あらすじでも「隆二郎に代わり、ロイヤルファミリーの主戦ジョッキーとなった翔平」と明記されており、主戦交代が物語上でも“確定事項”として扱われているのがポイントです。
ドラマはかなり上手で、佐木は「悪役」ではなく、あくまでプロフェッショナル。だからこそ、チームの物語に“現実”を流し込める存在になっています。
「夢を追うチーム」に対して、「勝てる馬に乗る」という職業的な合理性を真正面からぶつける役割が、ドラマでは佐木に集約されているんですよね。
9話の“乗り替わり”がドラマオリジナルの決定打:佐木→ルメール
ドラマの第9話では、クリストフ・ルメール騎手が本人役で登場し、展之のソーパーフェクトの鞍上として騎乗。佐木からの乗り替わりで、皐月賞(クラシック三冠初戦)を制する流れが描かれています。
またドラマには、武豊騎手、戸崎圭太騎手、坂井瑠星騎手ら現役トップジョッキーが本人役で出演しており、「リアル競馬」の熱量をそのまま物語に接続する演出方針が一貫しています。
佐木がソーパーフェクトに移った時点で、すでに“敵としては十分すぎるほど強い”。それにもかかわらず、さらにルメールを投入する。この一手は、ライバルの強さを「説明」ではなく「名前」で叩き込む演出。
- 佐木=才能と野心を備えた国内トップ級
- ルメール=現実世界でも“最強クラス”の象徴
この並べ方ひとつで、「競馬の世界は非情」「勝つ陣営は最善手を躊躇なく取りに行く」という事実が一瞬で伝わります。そして同時に、佐木というキャラクターの本質──強い馬に執着し、GIを獲りたいという欲──が皮肉な形で突き刺さる。
強い馬を選んでも、さらに“上”が来れば外される。その残酷さが、ドラマ版『ザ・ロイヤルファミリー』のテーマである「継承」と「競争」を、より濃く浮かび上がらせていると感じます。
原作では“ルメール不在”。海外の一流ジョッキー枠は「ガブリエル・トゥーサン」
原作では、フランス人の若手騎手ガブリエル・トゥーサンが登場します。設定上は短期免許で来日する海外ジョッキーで、物語における「世界基準の強さ」を象徴する存在です。
また原作の競走馬設定として、ソーパーフェクトはロイヤルホープ産駒、そしてビッグホープも椎名義弘が所有するロイヤルホープ産駒として整理されています。ロイヤルの血を引く馬同士が、異なる陣営でぶつかる構図が明確です。
原作を読了した読者の整理では、クライマックスとなる有馬記念で
- ソーパーフェクト側にトゥーサン
- ビッグホープ側に佐木隆二郎
という配置が語られることが多く、ここで「海外の一流ジョッキー vs 日本人トップ騎手」という対立構図が完成します。
※この点は原作本文の逐語的描写というより、読後の整理・解釈に基づくものなので、厳密なニュアンスは原作で確認するのが最も確実です。
ドラマ版は、原作における「海外の壁」「世界基準の騎手」という役割を、架空のトゥーサンではなく“ルメール本人”に置き換えた、と考えることができます。
この置き換えが巧いのは、競馬ファンにも、そうでない視聴者にも一瞬で伝わる点です。「ルメール=強い」という共通認識は、もはや説明不要。名前そのものが説得力になる。
原作では“設定”で示していた世界との差を、ドラマでは“実在の象徴”で叩き込む。その判断が、後半の緊張感と勝負のリアリティを一段引き上げているように感じます。
最終回で佐木隆二郎は「ビッグホープ」に乗る?(※ここからは予想)
ここだけは【予想】として切り分けます。
ドラマ最終回(第10話)の公式あらすじを見る限り、中心に置かれているのは「展之のソーパーフェクトが三冠を制し、有馬記念の最有力候補になる」という点で、少なくとも物語上はソーパーフェクトが主役級として描かれています。
ただ、ドラマ第9話で「佐木がソーパーフェクトから降ろされる」という展開を明確に描いた以上、佐木をこのままフェードアウトさせるよりも、
・別の強い馬(原作でいうビッグホープのポジション)で再浮上させる
・あるいは「騎手としての矜持」を回収する決断をさせる
といった“見せ場”が残っている方が、物語としては収まりがいい。
佐木は悪役ではなく、あくまでプロとして合理的な選択をしてきた人物です。だからこそ最終回で、もう一度「何を信じて馬に乗るのか」を問われる瞬間が用意されている可能性は高い。
個人的には、ここが最終回でもっとも熱くなるポイントのひとつになるのではないかと感じています。
結局、どこまでが「同じ」で、どこから「違う」のか?
世界観の細部は大きく変えられているものの、
原作とドラマは “夢の継承”と“家族の物語” という軸を確実に共有しています。
- 夢は血と時間を通じて受け継がれる
- “家族”は血縁だけでなく、馬に人生を賭けた人々すべて
- 敗北を抱えても前へ進み続ける
ドラマは原作のテーマを現代風にアップデートし、
原作はじっくりと世代交代を描く文学として楽しめる。
両方を見ることで、
二つの“ロイヤルファミリー”が補完し合う立体的な魅力が味わえる作品
になっています。
原作『ザ・ロイヤルファミリー』を読んだ感想

熱い人間ドラマとしての魅力
小説『ザ・ロイヤルファミリー』を読み終えてまず感じたのは、これは単なる競馬小説ではなく熱い人間ドラマであるということです。
競馬の知識がなくても物語に引き込まれる工夫が随所にあり、実際に競馬ファンでない私でも全504ページを夢中で読み通すことができました。レースシーンでは手に汗握る迫力があり、特にラストの有馬記念の描写は、まるで自分がその場で観戦しているかのような臨場感でした。専門用語や背景知識も作中で丁寧に説明されるので心配はいらず、むしろ主人公の栄治と共にゼロから学び感動を共有できる楽しさがあります。
「継承」というテーマの深さ
本作のテーマとして強く心に響いたのは「継承」の深さです。
馬の血統が代々受け継がれていくように、人間の情熱や夢、親子の絆もしっかりと次の世代へと受け継がれていく――作品全体を通じて、その尊さが丁寧かつドラマチックに描かれていました。
例えば、オーナー親子だけでなく競馬の騎手の世界でも世代交代が描かれており、ベテラン騎手の引退後にその背中を追っていた若手騎手が大舞台で手綱を託される場面などは胸が熱くなります。こうした“夢のバトンリレー”が随所に散りばめられているからこそ、ラストで長い年月をかけて夢が実る瞬間に大きなカタルシス(爽快感)が生まれるのだと感じました。
忠誠と約束が生む感動
物語の冒頭で山王耕造が栄治に投げかけた「絶対に俺を裏切るな」という言葉は、最後まで強い印象を残すキーワードでした。栄治はその約束を守り抜き、20年間にわたって陰で山王親子を支え続けます。
父を喪った栄治が山王に父親の面影を重ねて尽くす姿と、山王が秘めた想いを息子・耕一に託していく姿は、親子の愛情の形を異なる角度から描いており心を打たれます。
幾度もあと一歩で夢が届かず悔しい思いをしたからこそ、最後に夢が叶った瞬間の感動はひとしおで、栄治や山王一家、そして馬に関わるすべての人々がチーム一丸となって掴んだ勝利に拍手を送りたくなります。
秘書の視点が描く人間模様
さらに本作がユニークだと感じたのは、語り手が馬主でも騎手でもなく「秘書」である点です。
栄治という裏方の視点から競馬の世界が描かれることで物語全体に一本筋が通り、第三者だからこそ見える人間模様が浮き彫りになっていました。栄治自身が20年越しに成長していく姿や心情の変化も丁寧に綴られており、読後には自分も長い旅路を共にしたような充実感が味わえます。
読み終えた時に「この小説は競馬小説ではない、家族小説だ」と感じます。まさに競馬という壮大な舞台を通じて家族の絆や夢を追い続けることの尊さを描き切った名作だと感じました。
読者の反響と映像化への期待
最後に付け加えると、本作は発売当初から「泣ける」「感動した」という声が多く寄せられています。
読者や批評家からも高い評価を受け、何度読み返しても胸を打たれる感動巨編として広く支持されてきました。それほどまでに心を揺さぶる『ザ・ロイヤルファミリー』が映像化される今回のドラマ版では、果たしてどんな感動が我々を待ち受けているのか非常に楽しみです。競馬シーンの迫力や登場人物たちの熱量がどのように描かれるのか、放送終盤の今こそ心待ちにしています。
ザ・ロイヤルファミリーの関連記事
以下記事ではザ・ロイヤルファミリーを1話から最終回まで更新しています↓
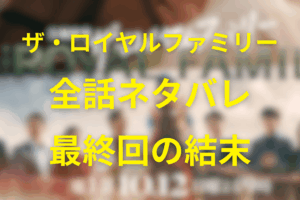
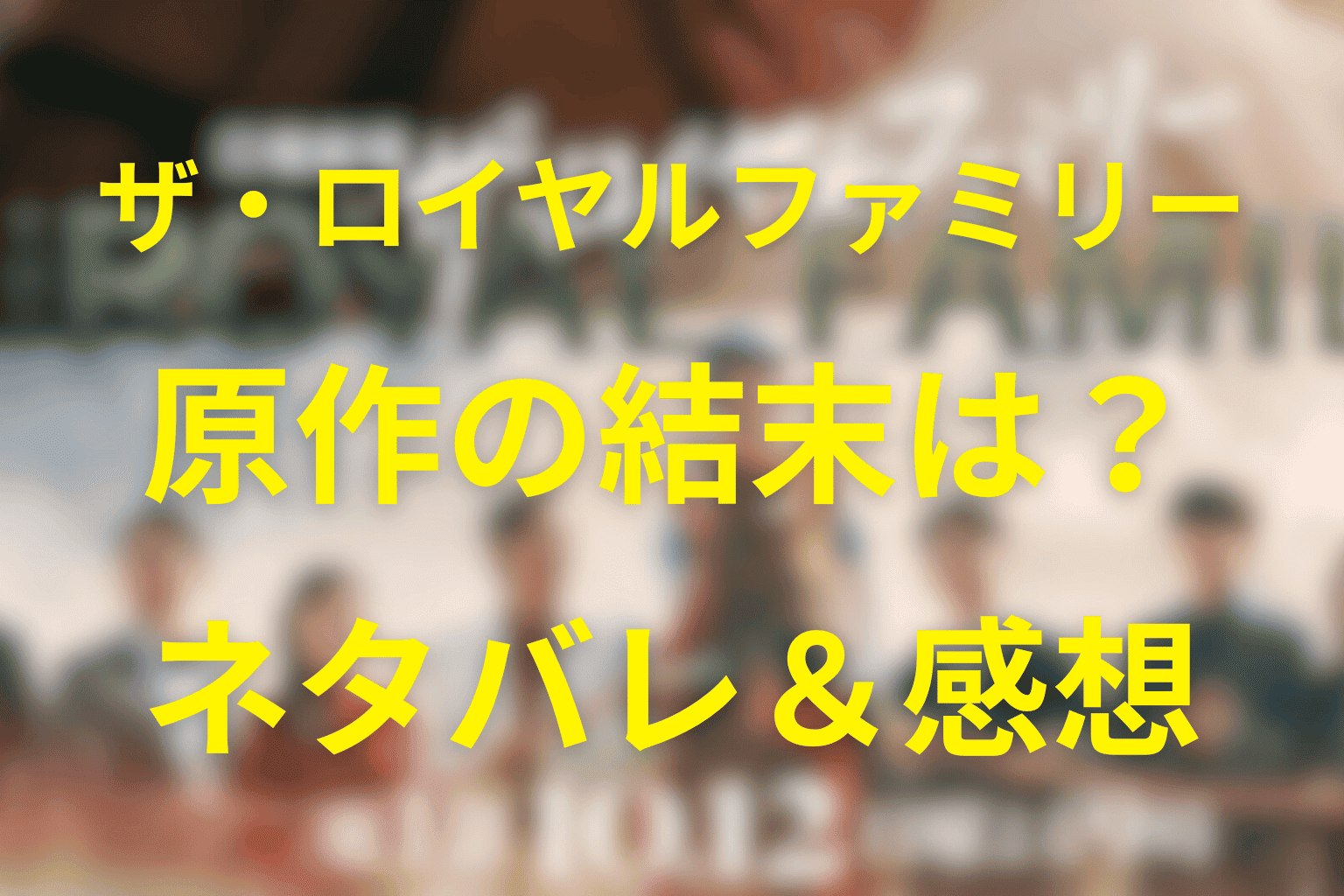

コメント