第10話で描かれるのは、到達点ではなく“準備完了”の瞬間です。
祥平が戻り、全員が同じ厨房に立つことで、グランメゾン東京はついに「最高のチーム」になります。
けれど、この物語は完成したところで終わらない。
完成したからこそ、次に問われるのは「このチームは、本当に勝てるのか」という一点です。
グランメゾン東京10話は、贖罪・才能・チームワークが一本に結ばれ、最終回の勝負条件がすべて揃う回。その一歩手前の緊張感を、丁寧に追っていきます。
グランメゾン東京10話のあらすじ&ネタバレ
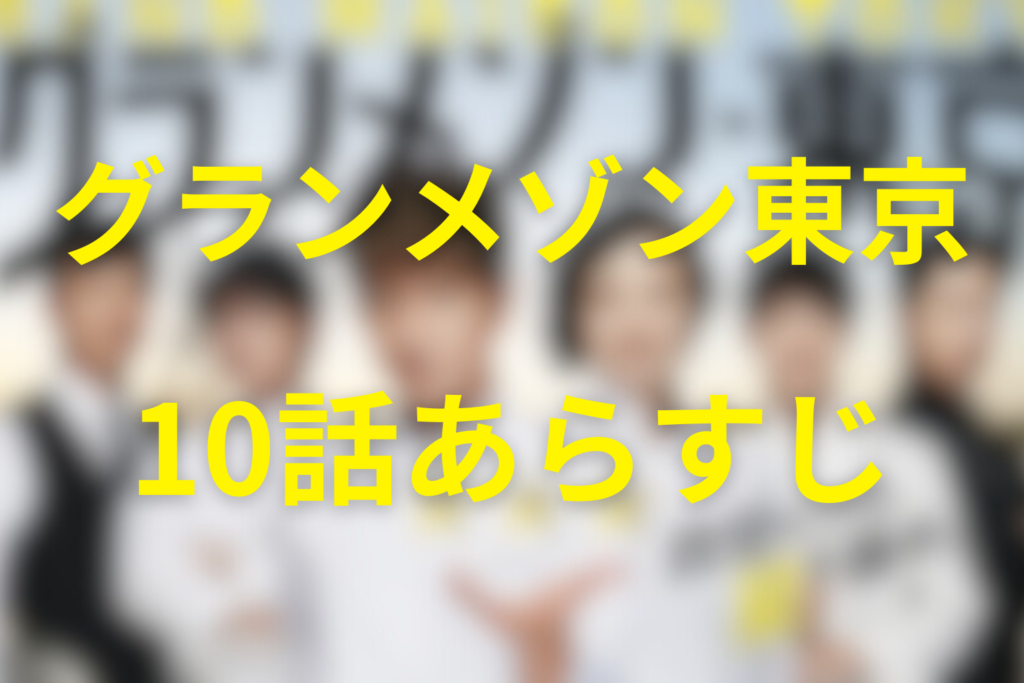
最終回直前の第10話は、物語のピースが「揃う」回です。
祥平が“ようやく”グランメゾン東京に合流し、一方でライバル店gakuは大きく揺れる。しかもミシュランの審査が目前(あるいは始動)という時間制限までついてくるので、ドラマの推進力が一段ギアを上げます。
以下、結末まで踏み込みます。まだ未視聴の方は、観てから読むのがいちばん美味しいです。
リンダの告発で「gaku」を去ることになった祥平――尾花が迎えに来る
発端はリンダの告発。3年前の“アレルギー食材混入事件”に関して、祥平のミスが公になり、祥平は丹後のいる「gaku」を去ることになる。
料理人としては致命傷に近い。尾花はそんな祥平を「グランメゾン東京」に誘うものの、祥平は「店に迷惑がかかる」として拒む。
ここが第10話の肝で、祥平の拒否は“美談”ではなく、自己処罰の延長線上にある。
迷惑をかけたくないというより、「自分がそこに立つ資格がない」と思い込んでいる。だから話は、勧誘というより“再起の資格審査”みたいな張り方をしていく。
祥平、ついに真相を告白する――「悪いのは全部、俺です」
尾花に背中を押され(というか、半ば引きずられ)、祥平はグランメゾン東京の面々の前に立つ。
そして、3年前のミスが自分にあることを認め、頭を下げる。相沢も倫子も、当然ながら簡単には受け入れられない。
特に相沢の怒りは激しい。ここで作品は、祥平を“被害者”として守らない。
視聴者が共感しがちな「若さ」や「怖かった」は、免罪符として機能しない。三つ星を目指す現場で、たった一滴の油が人生を壊す――その残酷さを真正面から置き直す。
逃げようとする祥平を、尾花が止める――「いい加減、逃げるなよ」
告白のあと、祥平は身を引こうとする。
「グランメゾン東京が三つ星を取るのを祈っています」と言い残し、去ろうとする。
そこで尾花が、逃げ癖に釘を刺す。これが尾花らしいのは、慰めではなく“現実に戻せ”という叱咤だから。
ここで印象的なのは、尾花が“正しい言葉”を使わないこと。贖罪を語るとき、綺麗な言葉はだいたい役に立たない。
彼がやるのは、祥平を「料理の現場」に引き戻すことだけ。倫理の答えを言語化する前に、まず手を動かせ――この順番が、このドラマの骨格です。
京野のまかないが、祥平の心を刺す――「諦めた人間に失礼だ!」
祥平を止めるのは尾花だけじゃない。京野が“まかない”を出す。しかも、彼が本気で作った料理だ。
祥平は素直に「うまい」と言う。……が、京野はそこで逆に怒る。「でも、心が動いたか?」「才能があるのに辞めるな」「諦めた人間に失礼だ」と激高する。
京野はギャルソン(ホール)の顔をしてるけど、内側には“料理を諦めた人間”の痛みが沈んでいる。
だからこそ、彼の怒りは説教じゃなく、嫉妬でもなく、「才能がある者が降りることの暴力性」への怒りになる。この回の京野は、静かな人が本気で怒ったときの怖さが出ていて、そこが良い。
「ゴーストシェフ」という苦肉の策――守るために“隠す”
京野たちが思いつく“ある方法”が、祥平を「ゴーストシェフ」として迎えること。
つまり表には出さず、厨房の戦力としてだけ関わらせる。リンダの圧力を避けつつ、ミシュランに向けた新メニュー開発を進めるための苦肉の策だ。
これ、現実的に考えると矛盾も多い。チームって、隠し事があると脆い。
なのにこのドラマは、あえて“隠す”ところから始める。なぜかというと、祥平にとって最初の一歩は「堂々と戻る」じゃなくて、「料理を続ける」ことだから。人格の救済より先に、技術者としての復帰を優先する。ここが、この作品の職業ドラマとしての冷たさ=リアルです。
新メニュー開発:真鱈の白子のポッシェショーフロワ――温度で勝負する一皿
ミシュランに向けて、グランメゾン東京はコースを一新する。ここから料理パートが“最終決戦仕様”になるのが第10話の快感。
象徴的なのが「真鱈の白子のポッシェショーフロワ」。白子を半生で火入れし、一度冷やして臭みを抑えつつ、香箱ガニ由来の要素を合わせ、上にはハーブや野菜を散らす――ここまでは冷たい設計。
そこへ“熱々にローストしたピーカンナッツ”を最後に乗せ、口の中で一瞬だけ温度を上げ、香ばしさを立てる。冷たいのに温度が欲しい、という矛盾を料理で解決する発想が面白い。
しかもこのピーカンナッツの追加は、劇中で栞奈(ソムリエ)からのダメ出しを受けて改善されたポイントとして示される。
味の完成度だけじゃなく、「この店はチームでアップデートする」という物語上の宣言でもある。
メインは「キジバトのドゥミ・アンクルート」――“ロースト”と“パイ包み”のいいとこ取り
メイン開発で扱うのが、希少なキジバトというジビエ。小さく火入れが難しい食材を、一羽丸ごとゆっくりローストしてから捌き、骨を外し、断面にパイ生地を貼ってもう一度焼く。
片面はローストの香ばしさ、片面はパイ包みの旨み――古典の弱点(蒸れて香ばしさが消える)を“半分だけアンクルート”で回避する。
ソースはザクロとオールドカンパリを合わせ、さらに内臓を炒めた要素も添える。ここまでくると料理の説明だけで、チームの執念が見える。素材の希少性・火入れの難しさ・ソースの思想、全部が「三つ星用の一皿」に向かって設計されている。
「リ・ド・ヴォーを入れたクスクスのサラダ」――冷たい見た目、熱い驚き
もう一品、地味に第10話らしいのが「リ・ド・ヴォー(子牛の胸腺肉)を入れたクスクスのサラダ」。
冷製の“タブレ”のように見せつつ、芹や香草で戻したクスクスを型に詰め、その中に“熱々に揚げた”リ・ド・ヴォーを交互に仕込む。食べて初めて温度のギャップで驚かせる設計だ。
これらの料理に共通するのは「温度」。仕上げのタイミングが難しく、全員の息が合わないと完成しない。ここで、ドラマのテーマと料理のテーマが完全に同期する。
一方gakuでは、丹後が行き詰まり――江藤が“計画”を進める
同じ頃、gakuの丹後はミシュラン審査のプレッシャーでメニュー開発に行き詰まる。
そこへ江藤が動く。第10話で江藤は丹後をシェフから解任し、新シェフとして結月を迎える。
これがえげつないのは、丹後が“無能だから切られた”わけじゃないところ。
むしろ、彼が正々堂々やろうとし始めたタイミングで、資本(オーナー)の論理が首根っこを押さえる。料理の世界の美学と、経営の世界の暴力が、最終回に向けて露骨にぶつかり始めるのが第10話です。
リンダが店に来る――祥平は“冷凍庫”に隠れる
祥平を執拗に追うリンダが、グランメゾン東京に現れる。
しかも、厨房まで踏み込む勢いで探す。ここで祥平は冷凍庫(冷蔵庫)に隠れるという、緊張とコメディが紙一重の展開に。
この場面はギャグで終わらない。冷凍庫に隠れるという“卑屈な身の処し方”が、そのまま祥平の心理――まだ自分を表に出せない――を可視化している。
それでも尾花は「料理で殴る」――リンダに新メニューを食わせる
リンダが来店し、尾花は祥平のアイデアも採用した新メニューを試食させる。
ここで勝負のやり方が、交渉じゃなく“皿”なのが良い。言葉で説得できない相手には、味で黙らせる。尾花は一貫している。
ただし、リンダは簡単に折れない。彼女は料理を認めないし、祥平がいる店には星を付けさせないという姿勢を崩さない。ここで「ミシュラン審査が始まる」というカウントダウンが、さらに圧を増す。
追い詰められた祥平が、ついに本音を吐く――「この店に入りたい」
リンダの来店で、祥平は「これ以上迷惑をかけられない」と離れようとする。
尾花は突き放すような言葉を投げる――が、それは“出ていけ”じゃなく“腹を括れ”の合図。祥平は号泣しながら、本音を吐露する。「俺はこの店に入りたい。みんなと一緒に料理を作りたい」。
この瞬間が、第10話の到達点。加入は手続きじゃない。
本人が「ここで料理をする」と決めることが加入だと、作品は言い切る。そして京野が尾花に言う。「出来たな、最高のチームが」。尾花が涙目になるのも、当然だ。
尾花の“大きな決断”が、最終回へ繋がる――禁断の食材「マグロ」
第10話は「祥平合流」で締めるだけじゃない。尾花は新メニュー開発を進める中で、ある大きな決断を下す。
最終回に向けて匂わされるのが、フレンチでは禁断とも言われる食材「マグロ」への挑戦。ここで“祥平が必要”だという論理が、ようやく料理開発の面でも繋がってくる。
第10話は、感情面(贖罪)と職能面(戦力)が一本の線になる回です。
グランメゾン東京10話の伏線

第10話は、単体で泣かせに来る回でありつつ、最終回に向けて「勝ち筋」と「負け筋」を同時に置いていく回でもあります。
ここからの伏線は、言ってしまえば“最終回の設計図”。
今見ると、かなり露骨に置かれているのに、見ている最中は感情で流されて気づきにくい。
以下、僕なりに「第10話の時点で仕込まれているもの」を分解します。
ゴーストシェフ=“贖罪”が終わっていない証拠
祥平を「ゴーストシェフ」にする策は、表向きはリンダ対策。
だけど物語的には、「祥平の贖罪は、まだ社会的に清算されていない」ことのサインです。隠れて働くという形は、罪を背負う者の“暫定的な居場所”でしかない。
だから最終回では、この“暫定”を終わらせる必要がある。祥平が表に出るのか、リンダが矛を収めるのか、あるいは別の形で清算されるのか――第10話の時点で、解決の宿題が残されています。
「温度」への執着は、最終回の“チーム戦”の予告
第10話で提示される新メニューのキーワードが「温度」。
冷たいものに一瞬の熱を足す白子、冷製に見せて熱々を仕込むクスクス、火入れがシビアなキジバト。これらはすべて、個人技より“仕上げの同期”が必要な料理です。
つまり第10話は、「この店は、全員のタイミングが揃って初めて勝てる」という宣言でもある。
京野が言う“最高のチーム”は、精神論ではなくオペレーションの話。ミシュランの審査は一発勝負の連続だから、最後に問われるのは技術より再現性=チームの精度。そのための伏線がここに置かれています。
リンダが“厨房まで踏み込む”=最終局面まで敵で居続ける合図
リンダが店に来るだけならまだしも、厨房に踏み込む勢いで祥平を探し、祥平が冷凍庫に隠れる。ここで敵対関係は「言い合い」から「生活圏の侵食」に変わっています。
要するに、リンダは最終回でも簡単には矛を収めない、という予告です。
むしろ彼女は“審査”というシステムを使って最後まで攻めてくる。だから尾花たちは、味だけでなく、審査の場そのものを設計し直す必要が出てくる――つまり、ONE TEAMで挑むしかなくなる。
gakuのシェフ交代=ライバルが自壊する伏線
江藤が丹後を解任し、結月を迎える。
これは単なる「gakuの内紛」ではなく、最終回のドラマチックな“対比装置”の準備です。グランメゾン東京は“合流”で強くなるのに、gakuは“追放”で弱くなる。
ここで重要なのは、丹後がこの作品における「料理の誇り」の象徴でもあること。彼が店を追われる構図は、最終回で“誇りがどこに帰るか”を見せる布石になっています。丹後が誰を救うのか、gakuがどう立て直されるのか――その入口が第10話です。
尾花の「マグロ」宣言=最後のラスボスは“食材”ではなく“自分”
第10話の時点で、マグロが最終回の核になることは、はっきりと示されています。フレンチで禁断と言われる食材に挑むというのは、外敵と戦う話ではなく、自分の美学と戦う話です。
ここまで尾花は、誰かの弱さに寄り添う形で成長してきた。でも最後は、自分の頑固さ・執念・過去の栄光――つまり“尾花自身”が一番の障害になる。その構図が、第10話ではっきり予告されています。
グランメゾン東京10話の感想&考察
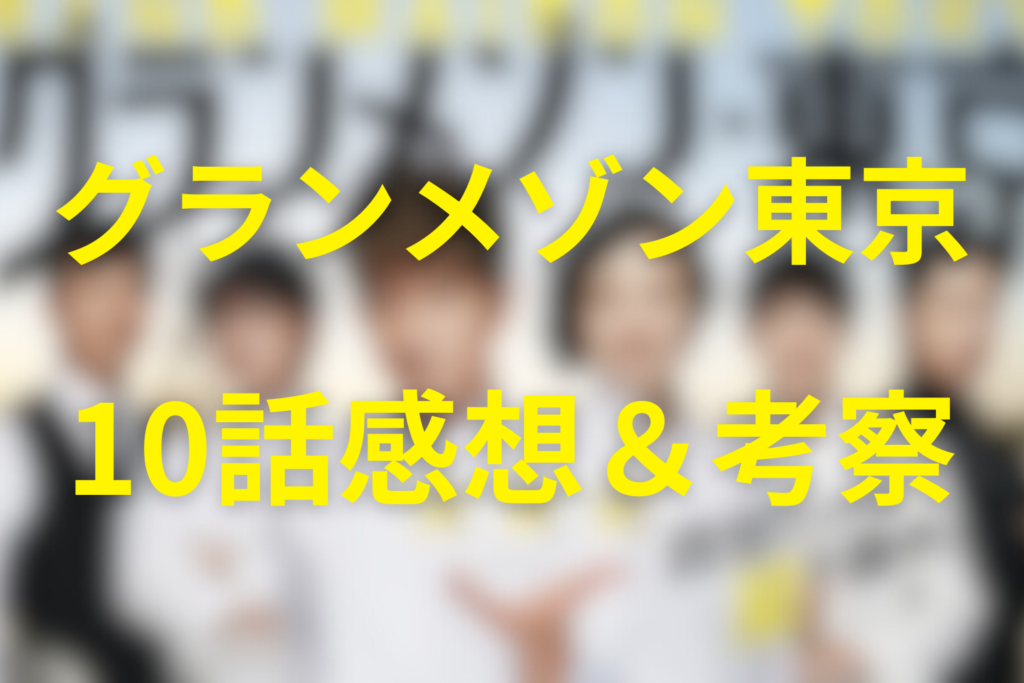
第10話を見終わったあと、胸に残るのは「やっと揃った」という安堵と、「でも、これで終わりじゃない」という嫌な予感の両方です。
祥平が入った瞬間に“最高のチーム”が完成するのに、その完成がむしろ“最後の試練の開始”みたいに見える。ドラマとしてめちゃくちゃ健全な盛り上げ方でした。
ここからは感じたこと・考えたことを遠慮なく書きます。
第10話は「贖罪を、言葉じゃなく皿で返す」回だった
祥平がやったことは取り返せないし、謝って済む話でもない。でも、このドラマは“償いの場”を法廷に置かない。厨房に置く。だから祥平は、土下座より先に、火入れとソースで返すしかない。
現実に近いのはこっちだと思うんですよね。
プロの世界って、反省文より成果物が求められる。もちろんそれは残酷なんだけど、同時に救いでもある。
やり直しを許す唯一の方法が「もう一度、作れるようになること」だから。第10話は、その再起の入口として、すごく誠実でした。
京野の怒りは、作品全体の“倫理”を背負っていた
京野の台詞は、正論としては一瞬乱暴です。でも、京野が言うから成立する。なぜなら彼は、才能の限界を知って諦めた側だから。
諦めた人間が、諦めようとする才能に怒る。これほど説得力のある構図、なかなか作れない。
僕はあそこ、京野が“祥平のため”に怒っているようで、同時に“自分のため”にも怒ってるように見えました。
「諦めた自分」を肯定するために、諦める才能を否定する。だからこそ痛いし、だからこそ刺さる。ホールの人間が厨房の倫理を語れるのは、この男が一度そこに立っていたからだと思います。
リンダは「悪役」じゃなく、“評価”を握る者の病理として描かれている
リンダの振る舞いは、正直かなり強引で、厨房に踏み込むのは「やりすぎ」と感じた視聴者もいたはず。
でも僕は、リンダを単なる悪役として見ると、このドラマの怖さを取りこぼすと思っています。
彼女は「評価」という権力を握っている側で、その権力に縛られてもいる。星を付ける側は、星に取り憑かれる。だから彼女は、尾花の料理に心を動かされた瞬間が一番怖い。
自分のルールが壊れるから。第10話で彼女が折れないのは、強さじゃなく“自己保存”の反射に見えました。
料理のテーマ「温度」が、キャラクターの心情とリンクしていたのが上手い
白子の料理って、冷たいのに温度が欲しい。クスクスも冷製に見えるのに熱が入ってくる。キジバトは火入れがシビアで、焼き過ぎると死ぬ。
これ、まんま人間関係なんですよね。
祥平は冷たい自己処罰の中に、熱い本音を隠してる。
相沢や倫子は怒りで熱いのに、心は冷え切っている。
京野は普段は温度を一定に保つホールの人間なのに、この回だけ熱暴走する。
温度のコントロール=感情のコントロールで、料理の設計思想がドラマの設計思想に重なってる。
こういう“メタ構造”がある回は、脚本家が遊んでるんじゃなく、真面目に戦ってる回です。
gakuの崩れ方が、グランメゾンの強さを際立たせる「鏡」になっている
丹後が追われ、結月が入る。gakuは組織としてのコア(料理人の誇り)を失い、オーナーの都合が前に出る。
一方のグランメゾン東京は、問題児(祥平)を抱え込むことで強くなる。普通、逆なんですよ。リスク要因を切った方が安定する。なのにグランメゾンは“リスク込み”で未来を取りに行く。
僕はここに、このドラマの価値観が出ていると思う。三つ星は“無菌室”から生まれない。泥と火傷と謝罪と、胃が痛くなる夜の連続から生まれる。第10話は、その覚悟を見せた回でした。
「最高のチームが出来た」のに、不安が残るのが最高の終わり方
祥平が泣きながら本音を言い、京野が「最高のチーム」と言う。多くの視聴者がこのシーンに心を動かされたのも納得です。
ただ、ここで終わらせないのがグランメゾン東京。チームが完成した瞬間に、マグロという“禁断”が立ち上がる。
つまり最終回は、敵(リンダ)だけじゃなく、課題(食材)だけでもなく、「完成したチームが、完成したまま勝てるのか?」という問いになる。
完成はゴールじゃなく、スタート地点だと示して終わる。僕はこの終わり方が好きです。
グランメゾン東京の関連記事
全話のネタバレはこちら↓
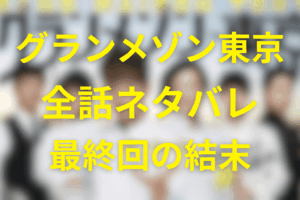
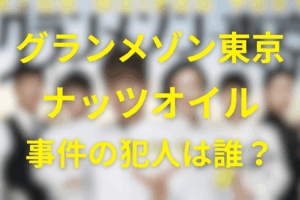
次回の話についてはこちら↓
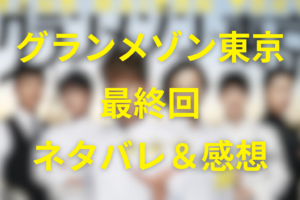
過去の記事についてはこちら↓
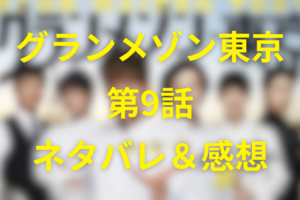
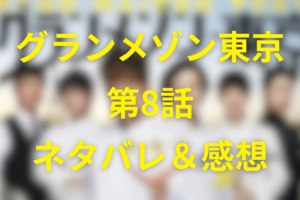
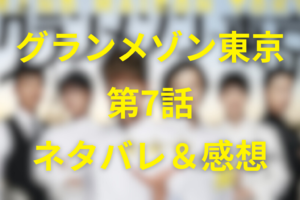
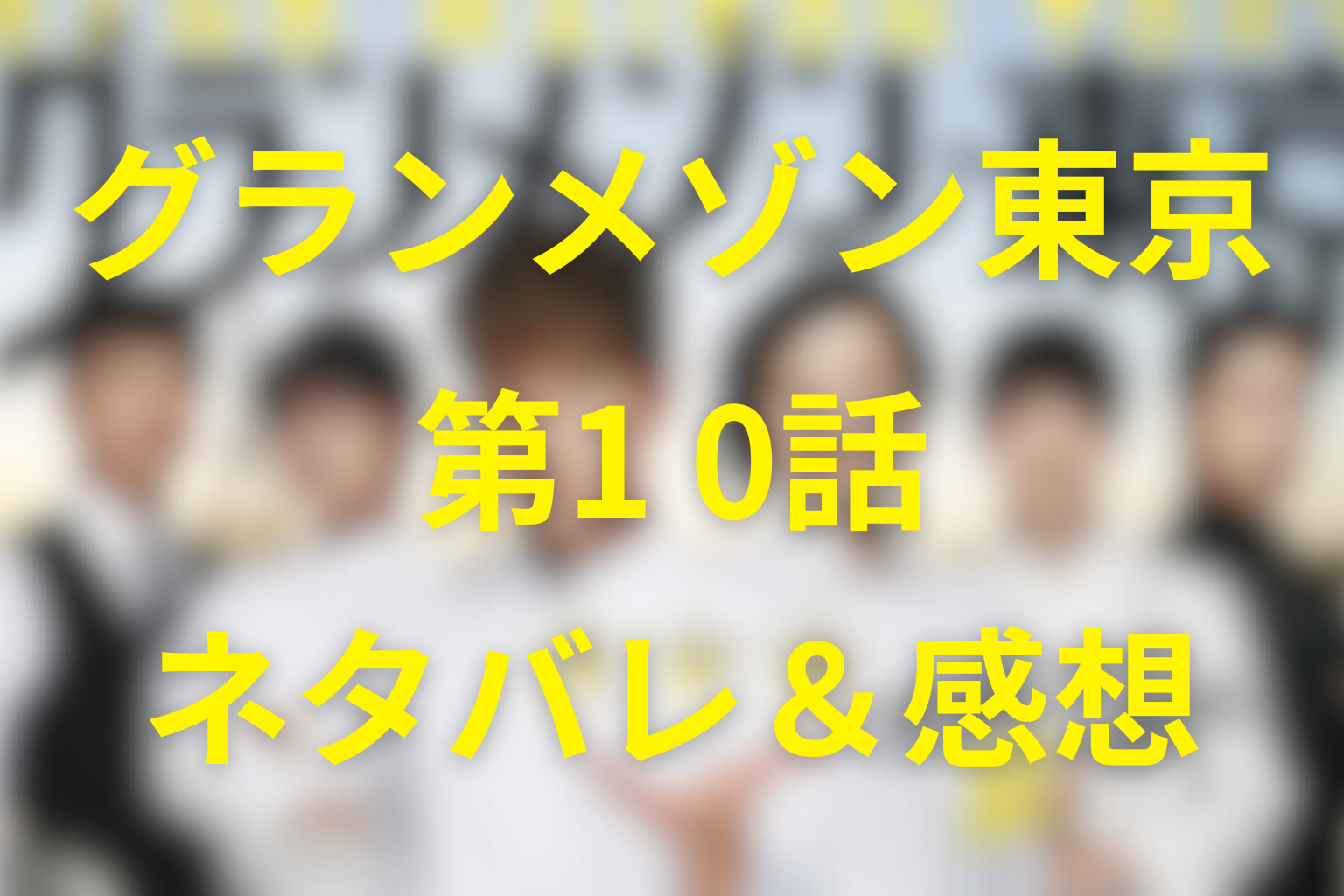
コメント