第4話で祖父と孫の“線”がつながり始めた『不適切にもほどがある!』。
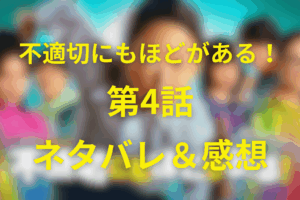
続く第5話では、ついに渚(仲里依紗)が「父に会ってほしい」と市郎(阿部サダヲ)を連れ出し、長らく伏せられてきた“家族の真実”が動き出します。
一方1986年では、キヨシ(坂元愛登)がSNSもスマホもない時代に、不登校の同級生へ“届く言葉”を探して奔走。
やがて、1995年1月17日・午前5時46分――阪神・淡路大震災の時刻が、父娘の記憶とともに刻まれる。
笑いと涙、そして“祈り”が重なり合う第5話のあらすじ・ネタバレ・感想・考察を詳しく紹介します。
不適切にもほどがある!(ふてほど)5話のあらすじ&ネタバレ
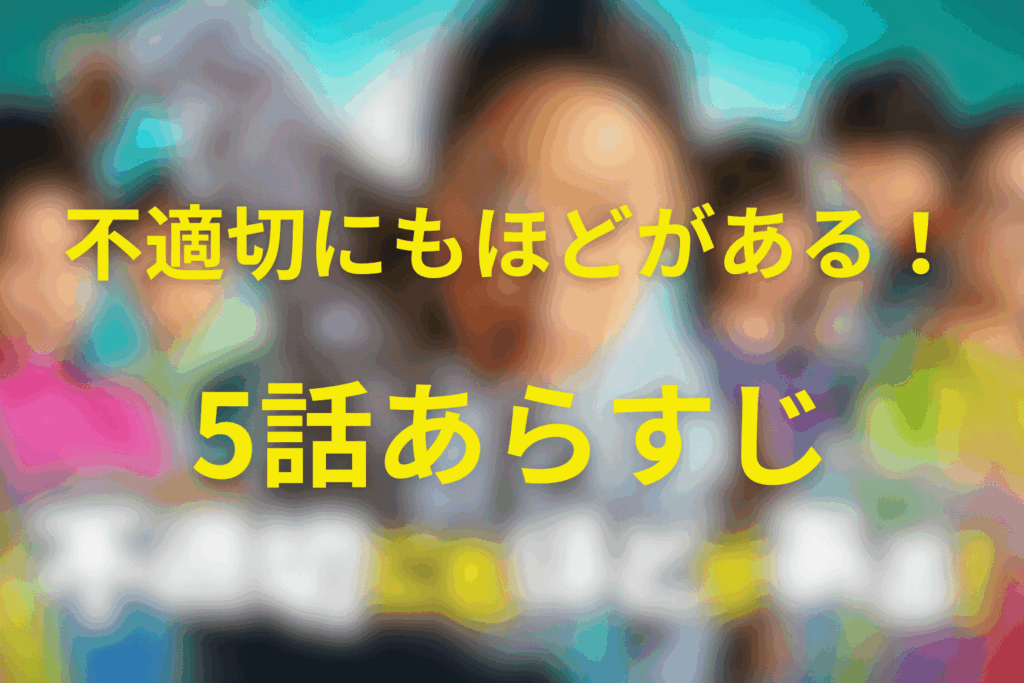
第5話は、コメディの熱量を保ちながら“家族の記憶”という核心に踏み込む回。
渚(仲里依紗)が「父に会ってほしい」と市郎(阿部サダヲ)を誘ったことから、長らく伏せられてきた“親子の謎”がついに動き出す。
一方1986年では、キヨシ(坂元愛登)が不登校のクラスメイトを救うため、SNSもスマホもない時代ならではの連絡方法――“ラジオのハガキ”を使った思いやりを実践。
そしてラスト、1995年1月17日・午前5時46分。阪神・淡路大震災の瞬間が父娘の物語を貫き、昭和・平成・令和をつなぐ“命の線”が描かれる。笑いと歌と涙の振り幅が最も大きい、シリーズ中盤のハイライトだ。
序章:ホテルのラウンジで「おとうさん」と呼ぶ男
渚に連れられ、ホテルのラウンジを訪れた市郎。そこで待っていた渚の父・犬島ゆずる(古田新太)は、初対面の市郎をいきなり「おとうさん」と呼ぶ。
当然、市郎は「お父さんはそっちだろ!」と反発。だが渚が差し出した一枚の写真が、空気を一変させる。
写っていたのは若き日の市郎の娘・純子(河合優実)――つまり渚の母。
渚=市郎の孫、ゆずる=義理の息子。世代と時代を飛び越え、祖父と孫が令和で顔を合わせるという衝撃の事実が明らかになる。
昭和パート:ラジオにハガキを送る“昭和の優しさ”
1986年。サカエ(吉田羊)から「キヨシのクラスに不登校の子がいる」と聞いた純子は、“話し相手になってあげて”と勧める。
SNSもスマホもない時代、キヨシが考えた方法は――ラジオ番組にハガキを送り、相手の耳にメッセージを届けること。
直接会いに行くよりも、匿名性を保ちながら“届く”距離を探る発想が、令和の「SNSの距離問題」と対をなす構成になっている。言葉は声となり、声は電波を渡る。昭和の“伝える力”が、静かに光を放つ名場面だ。
ミュージカルブリッジ:若き“ゆずる”の歌が時を超える
ゆずるの回想パートでは、若き日の彼(錦戸亮)がディスコ全盛期の“ギロッポン”を舞台にミュージカル調で登場。
肩パッド入りのスーツを着こなしながらも、恋も仕事も不器用な青年。
採寸のリズムにのせて、愛と後悔を歌うシークエンスは、クドカン節全開の“笑い泣き”ミュージカル。
軽やかさの裏に、彼が抱える「伝えられなかった想い」が滲み出る。
スーツがつなぐ血縁:仕立ての夜と夜明け前
語られるのは“もう一度の採寸の夜”。
バブルの余韻が残る神戸でテーラーを営むゆずるは、義父・市郎に自作のスーツを着てもらうため手紙を出す。
純子に連れられて神戸を訪れた市郎は、幼い渚を抱きながらぎこちない会話を交わす。
採寸が長引き終電を逃した三人は、居酒屋で夜明けを待ち、笑顔のまま駅へ――。だがその時計の針が、5時46分で止まる。阪神・淡路大震災。
駅へ向かう途中、市郎と純子は帰らぬ人に。ゆずるの語りに、渚は静かに涙を落とす。
“背広”のタイムパラドックス――時を超える記憶の器
ゆずるが1995年に仕立てたスーツを、2024年に“1986年の市郎”が着る。
モノが時間を媒介することで、失われた関係が束の間再生する。
記憶と記録、父と娘、義理の息子と孫――すべてを縫い合わせるのは、一着の背広。その不思議な瞬間に、笑いと喪失が同居する「クドカン時間」が立ち上がる。
令和の軽やかな撹乱:EBS局の“けん玉騒動”
一方、EBS局では栗田(山本耕史)が新MC(八嶋智人)の行動を監視し、「不審な動きがある」と騒ぐ。
GPSまで導入された“番組コンプラ管理”の末、八嶋が密かにやっていたのは――けん玉練習。
大仰な監視社会のパロディとして、父娘ドラマの重さを中和する軽やかな笑いを添える。
この緩急が、“泣けるけど笑える”ふてほど節の真骨頂だ。
ラスト:時を超えて繋がる家族の輪
スーツを纏った市郎が、ゆずると渚に見守られながら一服。
1995年と2024年、昭和と令和、過去と現在。
そのすべてが一瞬で重なり合うエンディングは、視聴者に“時間の尊さ”を静かに刻む。
第5話は、コメディの顔をした“鎮魂”であり、血縁と記憶をめぐる最高のファンタジーだった。
不適切にもほどがある!(ふてほど)5話の感想&考察
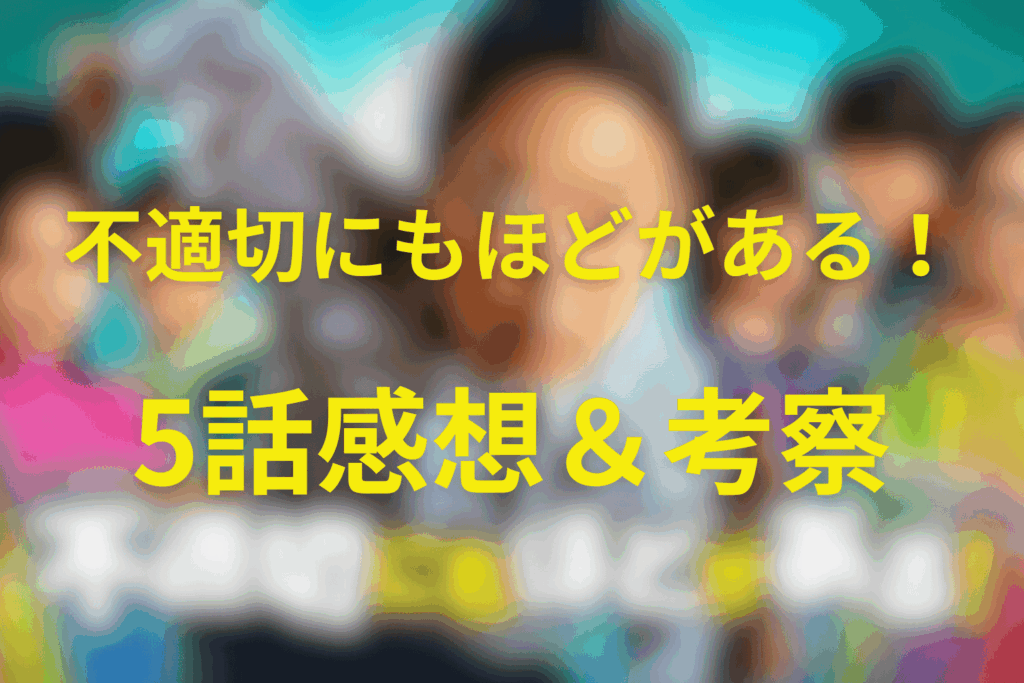
第5話は、タイトルの“ほどがある!”を反転させ、「善意」や「祈り」にも“ほど”があることを静かに突きつける回でした。
祖父と孫が出会い、父と娘の死が語られる。
希望を縫い合わせる“背広”の質感を通して、昭和のハガキも令和のGPSも、誰かに届いてほしいという“祈りの装置”として等価に置かれている――そんな奥行きを持つ一本でした。ここでは主要な論点を整理して掘り下げます。
“背広”というメディウム:身体・時間・家族を縫い合わせる
スーツ(背広)は、この回で最も雄弁な“言葉”でした。
若きゆずるが初めて一人で仕立てるそれは、「義父に認められたい」という切実な願いの形。しかし、その背広は完成と同時に喪失の象徴へと転化する。
年月をまたぎ、2024年に“1986年の市郎”が袖を通すとき、服は時間を媒介する“器”へ。
モノが記憶を運ぶことで、過去と現在が一枚の布のように重なり合う。“時間を着る”という映像の新鮮さと、胸を締めつける余韻が見事でした。
「不登校」と「登校拒否」――名づけの政治学
昭和パートの“不登校エピソード”は、単なる感動話ではなく“言葉の選び方”の話でもありました。
キヨシは、直接会って説得するのではなく、ラジオ番組にハガキを出して相手の耳へメッセージを届ける。
言葉で相手を囲い込まず、“届くかもしれない余白”を残す――その態度は現代の「不登校」や「登校拒否」という名づけの違いへの静かな応答のよう。言葉に正義を押しつけず、距離を含んだ優しさでつながる。
この昭和的アナログのやり方こそ、倫理の原型でした。
震災の描写:言葉の“抑制”が生む現実味
1995年1月17日・午前5時46分――阪神・淡路大震災の時刻。
この固有名詞が語られるだけで、画面の空気が一変する。
ドラマは悲劇を“見せすぎない”。ゆずるの口から淡々と語られるだけで十分に重い。市郎と純子が駅へ向かう途中で命を落とす――説明よりも“間”が語る。
過剰な演出を抑えたからこそ、現実の重みが画面に残った。
祖父と孫の倫理:関係を“現在形”にするために
「おじいちゃん」と呼ばれた瞬間、市郎の時間は二重化します。
1986年では父であり、令和では祖父。
重要なのは、渚が“自分の意思”で市郎に会わせたこと。彼女は“母の代弁者”ではなく、“自分の人生の当事者”として祖父を選んだ。
関係を“過去形”でなく“現在形”に変える力は、いつも名づける側にある。写真一枚という媒介が、その決意を具現化していました。
令和の“監視”、昭和の“便り”――祈りのテクノロジー比較
令和のEBS局では、GPSによる監視が「安全のため」と称して導入される。だが、それは“善意の名を借りた統制”でもある。
一方、昭和のハガキは匿名性と距離感を保ちながら、“自発”を待つメディア。
どちらも「守りたい」「つながりたい」という出発点は同じだが、手段が変わるだけで倫理は真逆になる。“祈り”がテクノロジーを通すとき、形を変えてしまう――それを軽妙に描き出していた。
“若ゆずる=錦戸亮”の配置が生む余韻
若きゆずるを演じる錦戸亮のキャスティングは、過去と現在を音楽でつなぐ“スイッチ”として機能。
愛すべき不器用さとチャーミングな軽さ、そして義父に認められたいという願い。
古田新太の現在のゆずると錦戸の若さが、歌と採寸のリズムで美しく重なる。この世代交代を“同じ音楽”で包んだ構成が、物語を時間劇として完成させていた。
“未来は変えられるのか”問題――予告された死と、希望の余白
第5話は、父娘の“予告された死”をあえて語り切る構成。
その上で物語を「変えられるかもしれない未来」へと開く。
以後の各話は、この“書き換え可能性”を検証する物語となる。
悲劇をあらかじめ提示しながら、視聴者に“まだ終わっていない”という希望を残す構造は見事。笑いと涙が入り交じる中で、運命すら“ほどがある”というメッセージが滲みました。
まとめ:第5話は、“届く”方法をめぐるレッスン
ラジオのハガキ、仕立ての背広、写真一枚、そして沈黙の告白。
時代ごとに「どうやって人に届くのか」を問い直した回。押しつけず、囲い込まず、それでも確かに触れる。
祖父と孫がつながる現在形の幸福と、父と娘の過去形の痛みが同じ画面で重なり合う。
“ほどがある”という言葉が、やさしく倫理を縫い直す――第5話は、クドカン流の“祈りのレッスン”そのものでした。
不適切にもほどがある!の関連記事
不適切にもほどがある!の全話のネタバレはこちら↓
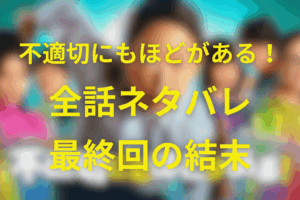
次回以降の話についてはこちら↓
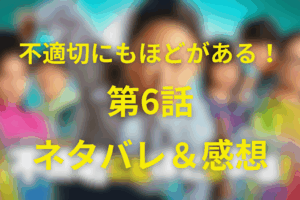
過去の話についてはこちら↓
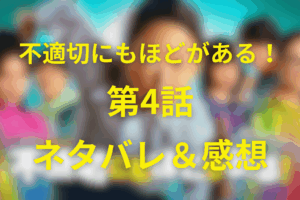
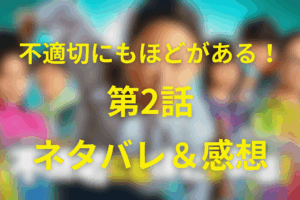
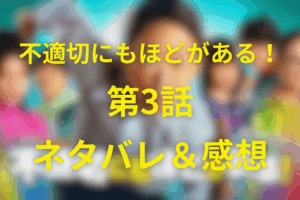
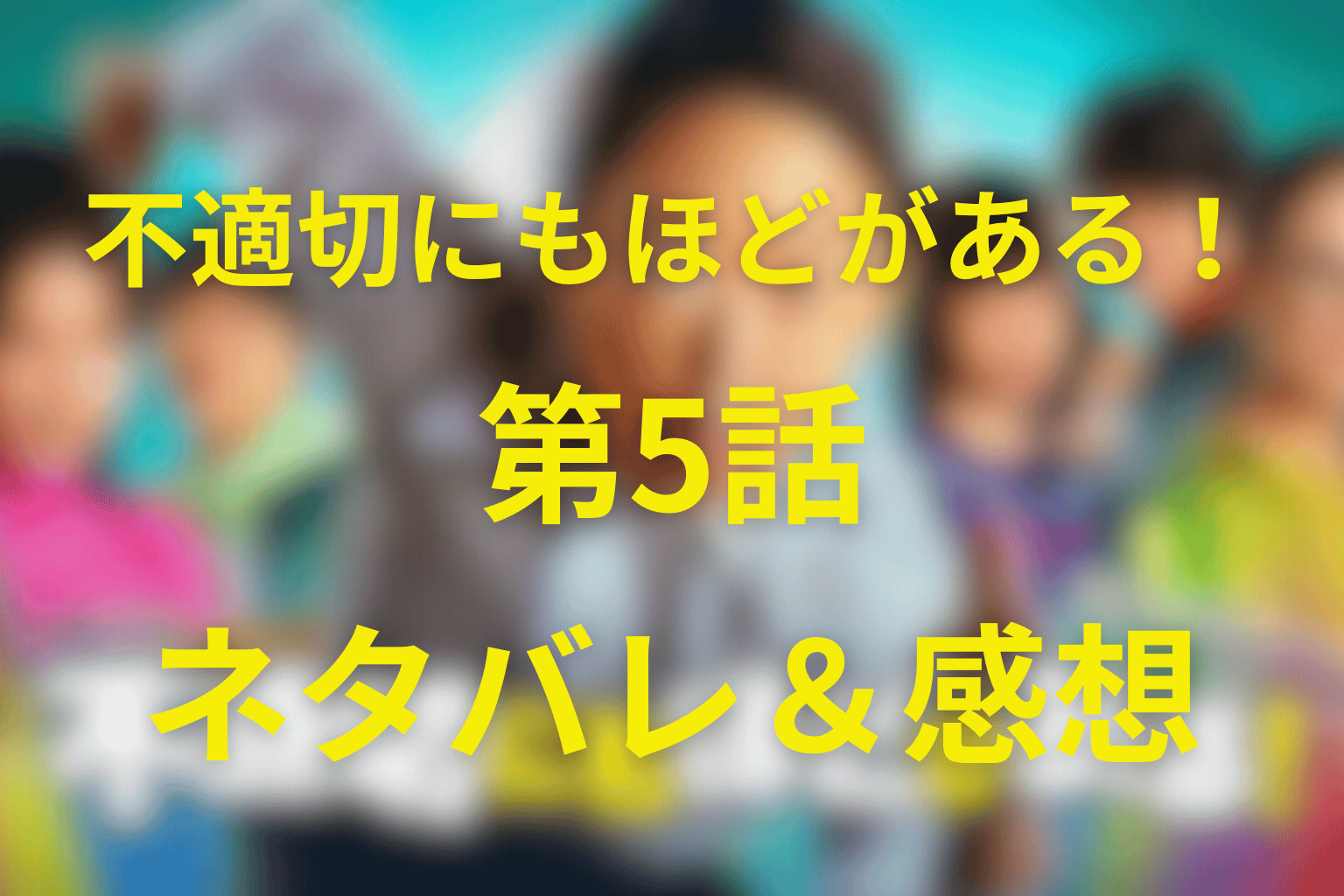
コメント