第5話で、阪神・淡路大震災の記憶と“背広”が親子をつなげた『不適切にもほどがある!』。
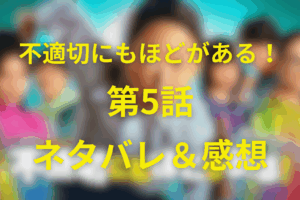
続く第6話「昔話しちゃダメですか?」では、“語ることの意味”が物語の中心に据えられます。
渚(仲里依紗)が同期プロデューサー・羽村(ファーストサマーウイカ)を連れて市郎(阿部サダヲ)のもとを訪れ、
伝説の脚本家・エモケン(池田成志)との“昔話だらけの会議”が波紋を呼ぶ――。
一方で秋津(磯村勇斗)は、市郎に〈小川親子の運命〉を突きつけ、昭和への“帰還”を迫る。「昔話」はただの懐古か、それとも人を動かす知恵か。
昭和と令和が再び交差する第6話のあらすじ・ネタバレ・感想・考察を詳しく紹介します。
不適切にもほどがある!(ふてほど)6話のあらすじ&ネタバレ
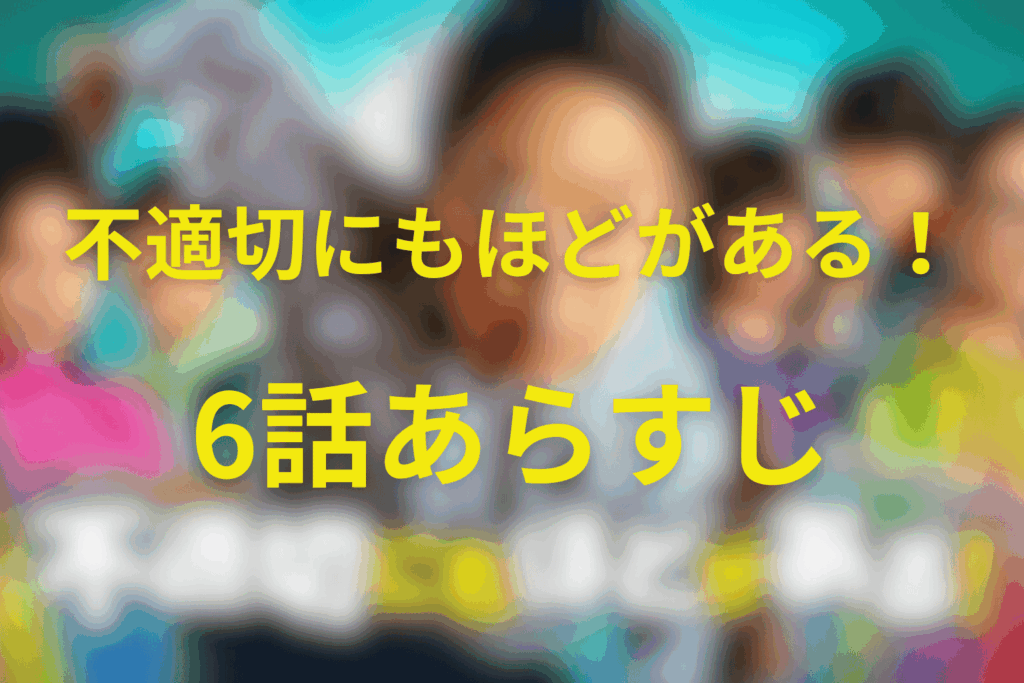
第6話の副題は「昔話しちゃダメですか?」。
渚(仲里依紗)が連れてきた同期プロデューサー・羽村由貴(ファーストサマーウイカ)の“仕事の悩み”と、秋津(磯村勇斗)が握る〈小川親子の運命〉が交錯する回です。
市郎(阿部サダヲ)は羽村の相談を受け、名脚本家“エモケン”こと江面賢太郎(池田成志)との打ち合わせに同行。
一方、秋津は“ある決意”を胸に、市郎を過去(昭和)へと強引に連れ戻す。
「昔話」と「未来」がぶつかる地点で、家族の時間とテレビの言葉が再び交わる――そんな転換点の一話でした。
冒頭:EBSテレビの相談室に持ち込まれた“エモケン問題”
令和のテレビ局EBS。カウンセラーとして働く市郎のもとに、渚が同期プロデューサーの羽村を連れてやって来ます。
羽村の悩みは、憧れの大物脚本家・エモケンとの企画会議。
伝説的存在とのタッグに胸を躍らせる一方、会議では“昔の成功談”ばかりが続き、現場の空気は凍りつく。
「先輩の経験は尊い。でも、それを今どう使うかが問題だ」――市郎はそう語り、羽村とともにエモケンの元へ同行。
会議室が“世代と経験”のぶつかる舞台へと変わっていきます。
羽村×エモケン:昔話は知恵か、マウンティングか
会議では、エモケンが自信満々に“90年代的ヒット方程式”を語り出す。
羽村は尊敬と違和感のはざまで揺れ、渚は空気を読みながらも居心地の悪さを覚える。
そんな中、市郎が静かに割って入る。
「昔話は悪くない。ただ、それを誰のために、今どう使うのかが大事だ」。
懐古と更新、そのどちらも否定しないこの一言が場を緩め、羽村は“現場の責任者”として自らの言葉でエモケンに向き合う。
過去の経験を“威厳”から“資産”へ変える、この会話が第6話の知的な見どころでした。
秋津の介入:小川親子の“運命”を突きつける
一方、秋津は“小川市郎と純子の運命”という秘密を抱えていました。
市郎が令和の快適さに留まろうとする姿に、「逃げるな」と迫る秋津。
「過去は終わっていない。今こそ戻って、父として果たすことがあるだろう」。
その言葉に押され、市郎は再びタイムスリップを決意。
“昔話”をただの回想にせず、“やり直す現在進行形の歴史”として描く展開が胸を打ちます。
市郎、昭和へ――“ただいま”は過去を救う現在形
秋津に導かれ、昭和へ帰還した市郎。
久しぶりに娘・純子(河合優実)と再会し、両手いっぱいに土産を抱えて「ただいま!」と笑う。
抱きしめ合う二人の姿は、父と娘の時間を再び“現在形”に戻す光景でした。過去を修復するのではなく、今この瞬間に更新する――その“再会の手触り”が静かに沁みる。
まさかの展開:純子、令和へ――世代の目線が交差する
第6話の驚きは、父だけでなく純子までもが令和側へ“顔を出す”展開。
渚と父・ゆずる(古田新太)、秋津の息子・真彦(磯村勇斗)と対面し、世代と時代が多層的に重なっていく。
昭和の純子のストレートな感情が、令和の空気の中でもまったく色褪せない。
“過去が現代に来る”ことで、視聴者にも“昔話をどう扱うか”というテーマが身近に迫る。
メタの遊び:松村雄基“本人役”が仕掛けるドラマ史のパロディ
作中では80~90年代ドラマの記憶を背負う松村雄基が“本人役”で登場。
エモケンの懐古トークと鏡合わせのメタ構造で、テレビの歴史そのものが劇中に侵入する。
昭和の熱量と令和のコンプラ意識――その狭間に立つ“テレビ”という存在を、笑いと風刺で描き出していた。
終盤:経験を“資産”に、関係を“現在形”に
羽村は、エモケンの経験を“正解”ではなく“資源”として編集する覚悟を固める。市郎は父として昭和に戻り、純子ともう一度向き合う。
そして純子は令和で、かつての“他者”と交わる。
第6話は、“昔”と“今”を対立ではなく接続で描き、経験を「語り継ぐ知恵」へと昇華。
「昔話しちゃダメですか?」という問いに、ドラマはやさしく答える――“昔話は、今を動かすための言葉である”と。
不適切にもほどがある!(ふてほど)6話の感想&考察
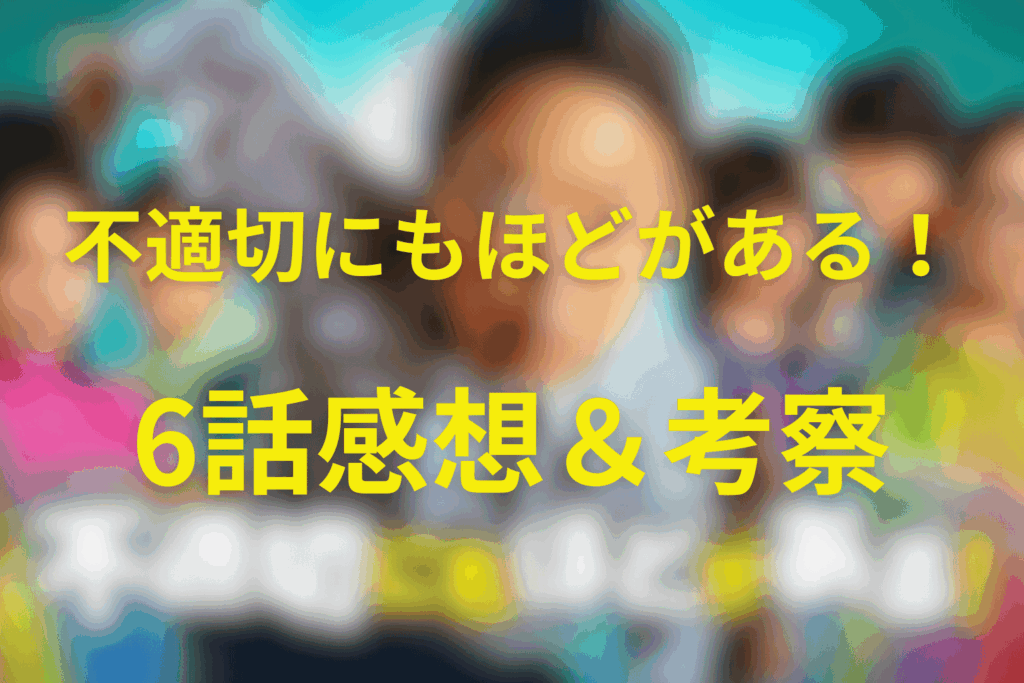
第6話は、“昔話”というテーマを懐古や否定の二択ではなく、「誰が、誰のために、どう語るのか」という実践的な問いとして提示した回でした。
過去を懐かしむだけでも、切り捨てるだけでもなく、“今を動かすための語り”として更新する――その思想が会話にも演出にも貫かれていました。ここでは、YUKIの視点でポイントを整理します。
「昔話」は禁句ではない。“発話の矛先”を変えれば武器になる
エモケン会議のシーンが象徴的でした。
ベテランの経験談が“上から目線”に堕ちるか、“現場の知恵”に転化できるかは、話し手の姿勢と受け手の編集力次第。
市郎が見抜いたのは、昔話の暴力性ではなく“編集の不在”。
過去の経験をそのまま持ち出すのではなく、「今を生きる誰かの選択肢」として再編集することが大切だと説く。
羽村が勇気を出して「言うべきことを言う」責任を取り戻したのは、論破ではなく翻訳の成果でした。この場面は、働く視聴者にとっても「経験をどう使うか」のリアルな問いとして響いたはずです。
“昔”は過去ではなく、親子にとっての“現在形”
昭和に戻った市郎の「ただいま」は、ノスタルジーではなくケアの言葉でした。
純子は“過去の娘”ではなく“今の娘”として存在しており、市郎は“父親として今を生き直す”。
時間SFの体裁をとりながら、実は非常に現実的な親子の再接続の物語です。
過去をやり直すのではなく、「過去の只中で現在を生きる」という哲学を映像で見せた再会シーンは、シリーズ屈指の名場面でした。
純子の令和体験が生む“価値観の翻訳”
純子が令和に来ることで、視点の往復が生まれます。
昭和の“父を責める娘”から、他者の現在を理解する目線へと変化し、同時に令和側の人々も“昭和の直球さ”を再評価する。どちらかの価値観が勝つのではなく、対面による相互翻訳が始まる。
この時間の交錯こそ、「時代が違っても人は分かり合えるのか?」というシリーズ全体の問いへの最初の実践でした。
メタの効用:ドラマ史を“持ち出す”演出の力
松村雄基の“本人役”出演は単なる遊びではありません。
彼の存在が、80~90年代ドラマの“身体性”を呼び込み、説得力を与える。ベテランが語る昔話を、実際の“テレビの歴史”と重ねることで、作品自体が“語り継ぎ”の構造を帯びる。
テレビドラマが自らの過去を俯瞰するというメタ構造は、懐古を再生産ではなく創造に変える仕掛けになっていました。
秋津という“倫理の装置”
秋津は、令和の“適切さ”に救われた側でありながら、そこにある惰性も知っている。
彼が市郎をタイムマシン開発者・井上のもとへ連れ出したのは、「適切さ」は逃げではなく、向き合うための態度だということを体現するため。
第6話における秋津の役割は、“優しい強制”――相手を責めずに動かす力でした。
彼の存在が、コンプラとケアの中間地点を示す“現代の良心”として機能しています。
音楽と演出の説得力:副題の“問い”を身体で落とす
副題「昔話しちゃダメですか?」は、言葉のテーマであると同時に演出のテーマでもあります。
会話のテンポ、間の取り方、音楽の入り方――すべてが“語りのリズム”を可視化する。シリーズ全体で続く“歌”や“ステップ”のモチーフは、言葉を超えて価値観をつなぐ装置。
第6話でもその身体的コミュニケーションが、論理を超えて心に届く瞬間を作り出していました。
まとめ:昔話は“過去の所有”ではなく、“今を動かす資産”
第6話の答えはシンプルです。
- エモケンの“昔話”は、編集すれば資産になる。
- 親子の“昔”は、抱きしめ合うことで現在になる。
- 違う価値観は、対話によって橋がかかる。
この三つがそろうことで、“昔話はもういらない”という短絡的な風潮から抜け出し、“誰かの今を助けるために語り直す”という新しい視座を提示した。
第6話は、「昔話をどう使えば人が前に進めるか」を観客の身体で理解させる、シリーズ屈指の“対話のレッスン”でした。
不適切にもほどがある!の関連記事
不適切にもほどがある!の全話のネタバレはこちら↓
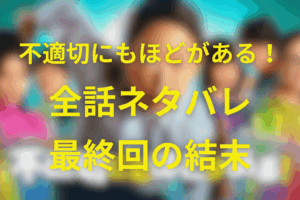
次回以降の話についてはこちら↓
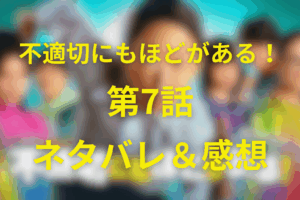
過去の話についてはこちら↓
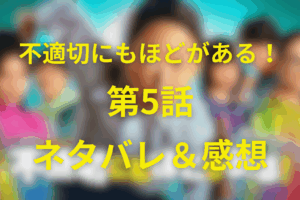
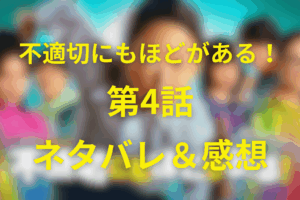
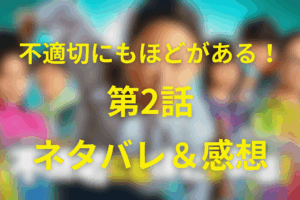
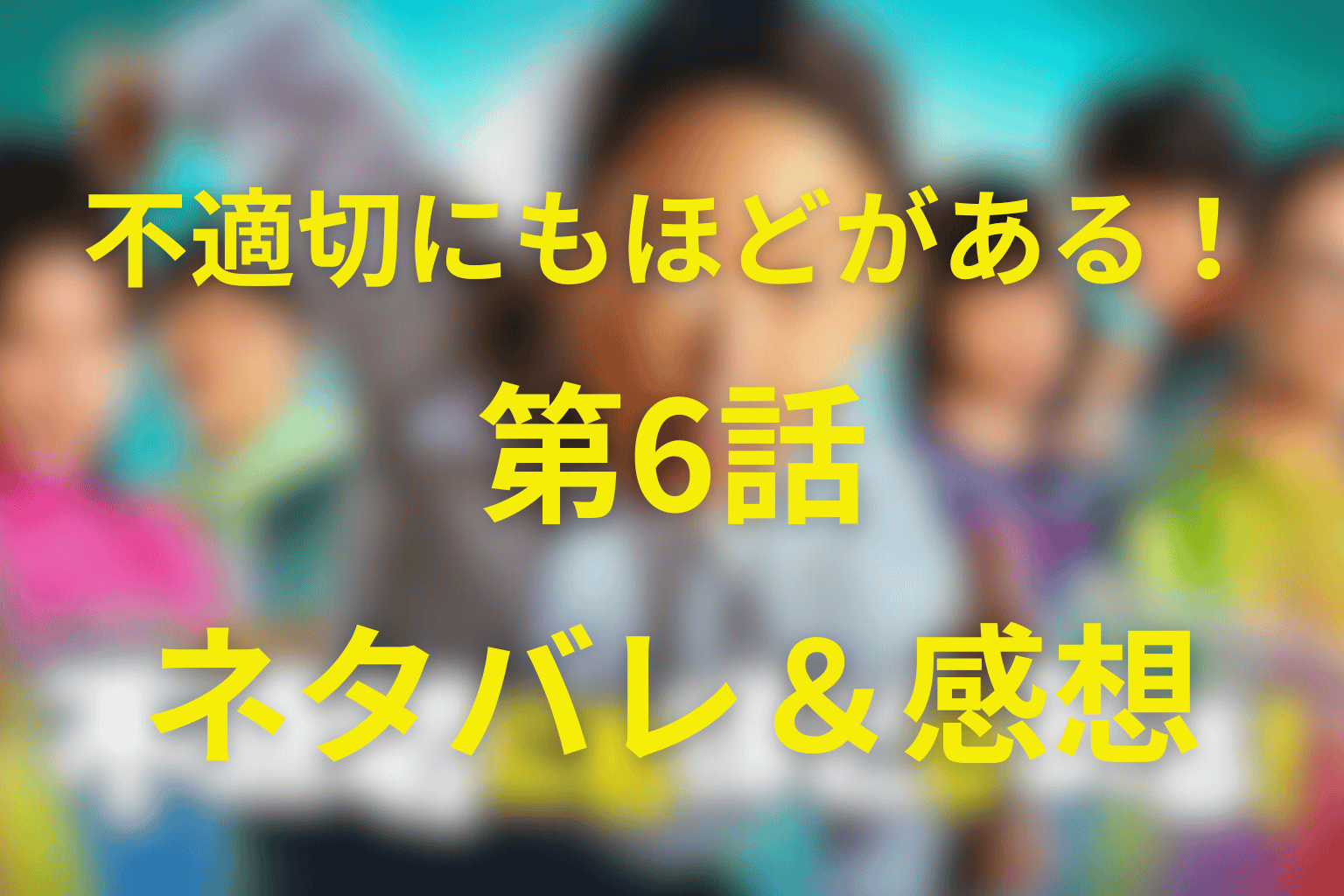
コメント