第8話「証言」は、「誰の言葉を信じるのか」という問いを、極限まで突きつけてくる回だ。マンションの非常階段下で見つかった母親の遺体と、「パパがママを殺した」という少年の証言。その言葉はあまりに強く、捜査は一直線に父親へ向かっていく。
だが倉石義男が優先するのは、証言ではなく遺体が残した沈黙の痕跡だ。踵の傷と靴の不一致、手首に残る圧迫痕、そして逃げた足音の距離。言葉が作る物語と、物理が示す現実が噛み合わないとき、捜査は立ち止まらなければならない。
この回が描くのは、嘘が悪意だけで生まれるわけではないという現実だ。守るための嘘、祈りとしての嘘、そして大人の思い込み。証言の裏にある感情と願いまで拾い上げることができるのかが、最後まで問われ続ける。
※この記事は、ドラマ「臨場 続章」第8話「証言」の結末までのネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
ドラマ「臨場 続章」8話のあらすじ&ネタバレ
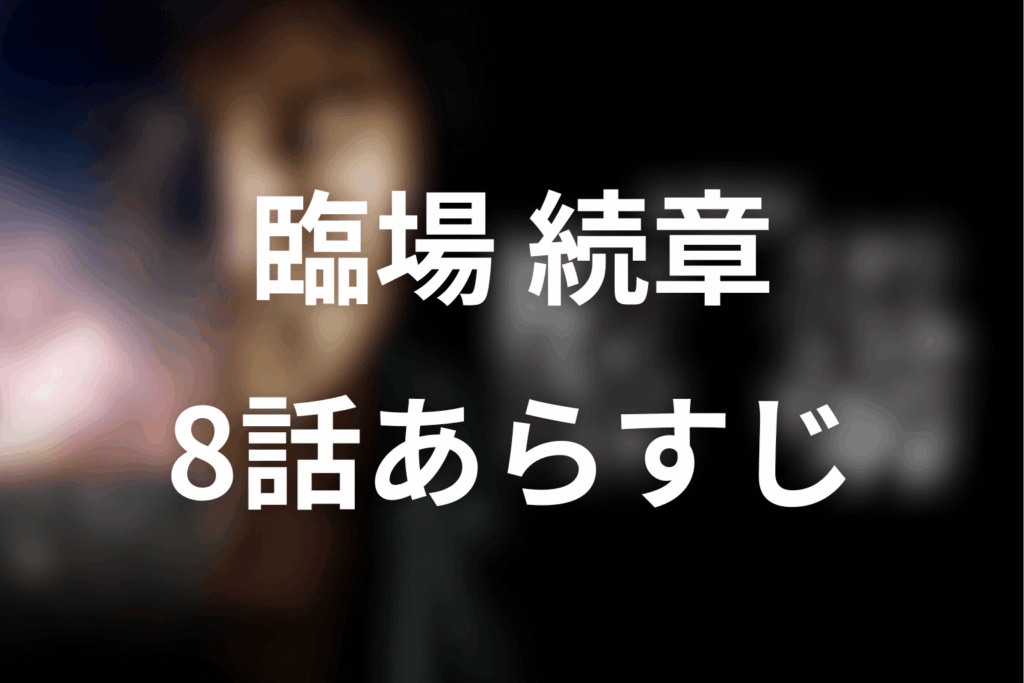
第8話のサブタイトルは「証言」。マンションの非常階段下で見つかった女性の遺体と、「パパがママを殺した」という少年の言葉が、捜査をまっすぐ“父親”へ向けてしまう回です。けれど『臨場』らしさは、証言よりも“死体の痕跡”を優先するところにある。嘘をつくのは生きている人間で、死体は嘘をつかない――その言葉が、いろんな角度から刺さってきます。
※ここから先は、結末(犯人・動機)まで含むネタバレです。
非常階段下の遺体――転落死に見えて「転落だけではない」
臨場要請を受け、検視官の 倉石義男 と検視官心得の 小坂留美、検視補助官の 永嶋武文 が現場へ向かう。現場はマンション外の非常階段下。ちょうど 捜査一課 の 立原真澄 らも到着しており、第一発見者の事情聴取が始まっていた。
遺体は、非常階段から落ちたように見える。だが倉石は、到着してすぐに“事故の匂い”だけでは終わらないと踏む。現場での検視は、まず「遺体を見た目で判断しない」ことから始まる。倉石は淡々と、しかし容赦なく衣服を外させ、皮膚と筋肉の反応を確かめるように全身を観察していく。そうして見つかったのは、単なる転落の外傷とは別系統の痕跡だった。
真っ先に目につくのは、体中に散った古い打撲痕。階段から落ちた衝撃でできる“新しい傷”とは違い、色味も形も古い。これだけで「日常的に暴力を受けていたのでは」という可能性が立つ。さらに倉石は、左手首に残る新しい圧迫痕を発見する。誰かに手首を強く掴まれた、指の力がそのまま沈み込んだような痕だ。
そして、ここで倉石が一気に表情を変えるポイントがある。踵(かかと)の擦過傷。転落の最中に擦ってできたと見える生々しい傷なのに、遺体はなぜか靴をきちんと履いている。普通、踵が剥けるほど擦れるなら、靴が脱げた状態で地面や階段と接触したはず。つまり「靴は途中で脱げた」のに、発見時には「履かされていた」。この矛盾が意味するのは、誰かが死後に靴を履かせ直したということだ。
転落事故なら、そんな手間は発生しない。犯人がいるなら、わざわざ靴に触れるのは指紋や痕跡を残すリスクが増える。にもかかわらず“履かせた”行為がある。倉石は、そこに人間の感情(焦り、あるいは子どもっぽい発想)が介在したと読む。こうして倉石は立原に「これは他殺だ」と告げ、事件として捜査が動き出す。
被害者はマンション住人の 仲田真弓。小学生の息子・ 周平 と二人暮らしのシングルマザーだった。
第一発見者は「ふくろう隊」――夜の職人が聞いた“音”
通報者は、現場近くで水漏れ調査をしていた作業員たち――通称 ふくろう隊。夜間に地中の音を聞き分け、漏水の場所を突き止める職人集団で、 村越英二 と同僚の 植田 がその場にいた。
彼らは調査中、鉄階段を転がり落ちるような音を聞きつけ、すぐに駆け付けた。すると非常階段下に女性の遺体があり、近くに子どもが立ち尽くしていたという。周平は泣き崩れるというより、固まっているように見えた。ふくろう隊にとっても異様な光景だが、彼らはまず通報し、その場を動かさずに大人を呼ぶ。音を聞いて状況を判断する職人だからこそ、現場保存の意識が妙に高い。
ふくろう隊は、現場の“目撃者”というより“音の証言者”だ。視界が悪い夜でも、音なら逃げない。しかも彼らは仕事柄、音の情報を切り分ける精度が異様に高い。倉石もそこに目を付ける。後にこの「音の精度」が、捜査をひっくり返す鍵になる。
「パパがママを殺した」――少年の証言が捜査を固定する
現場にいた周平は幼い。だが口から出た言葉は、あまりに断定的だった。「パパがママを殺した」。事件当夜、父親が母親の部屋に来て揉め、そのあと母が階段下へ落ち、父親が逃げていくのを見た――周平はそう証言する。
この「証言」は強い。しかも、真弓が別れた夫からDVを受けていたらしいこともすぐ判明し、周平自身も父親を怖がっていた節がある。捜査一課が「父親犯人」で固めにかかるのは自然だった。
一方で倉石は、周平の証言をそのまま“事実”として扱わない。子どもが嘘をつくこともあれば、大人が子どもに嘘をつかせることもある。倉石が見ているのは、言葉の内容というより、言葉と遺体の痕跡が噛み合っているかどうかだ。手首の圧迫痕と踵の傷、そして「靴」。証言と物証が違う方向を向いているなら、どちらかが嘘をついている。
一ノ瀬の聴取が崩れる――“感情”が捜査の邪魔をする
周平への事情聴取を担当した 一ノ瀬和之 は、周平の証言を引き出そうとするが、思うようにいかない。子ども相手に、質問の切り口も言葉の強さも難しい。周平は「見た」と言いながら、具体の場面になると輪郭が曖昧で、怖い記憶のはずなのに不自然に平坦な言い方をする。一ノ瀬はだんだん苛立ち、取調室で感情を露わにしてしまう。止めに入ったのは 坂東治久。普段は一ノ瀬が坂東を抑える側なのに、逆転するのが皮肉だ。
その後、立原は一ノ瀬に釘を刺す。「どんな事案でも冷静に聴取に当たれ。感情をむき出しにして、話を聞けると思うな」。そして続けて言う。「検視が向き合うのは死体だ。俺たちの相手は生きてる。死体は嘘をつかないが、生きてる奴は嘘をつく」。ここで立原が口にする“嘘”は、犯人だけのものじゃない。被害者も、目撃者も、そして子どもも、嘘をつく。嘘をつく理由はそれぞれ違う。だからこそ厄介で、だからこそ事件は人間の話になる。
容疑者① 元夫・小菅光晴――DVの過去と、証拠の薄さ
周平の証言どおり、元夫の 小菅光晴 は事件当夜にマンションを訪れていた。防犯カメラにも姿が映っており、訪問自体は本人も認める。しかし小菅は殺害を否認し、取り調べでは開き直る。「周平は嘘をついている」「証拠があるなら見せろ」と強気に言い放ち、DV加害者らしい支配的な空気を隠しもしない。捜査一課は過去の経緯を洗い、真弓が復縁を拒んでいたこと、逃げるように今の部屋へ来たことを積み上げていく。
DVの過去があるなら、復縁を迫って揉め、突き落とした――筋書きは作りやすい。けれど倉石は、小菅を見た瞬間に“手”の違和感を覚える。遺体の手首に残る圧迫痕は、ただ掴んだというより、逃げる相手を一瞬で制止するような一点の力が残っていた。小菅の握力や手の使い方は、その痕を作る人物像と微妙にズレている。現場の再現、そして“力の要素”が加わるほど、小菅は「最も疑わしいのに、最も噛み合わない」存在になっていく。
さらに問題は「靴」だ。転落の最中に脱げた靴を履かせ直す行為は、合理的な犯人像からは外れる。痕跡を隠すなら靴に触れない方がいい。逆に、証言を強めるために靴を履かせたのなら、犯人は“周平の目”を意識していたことになる。小菅は確かに暴力的だが、あの靴の行為と噛み合わない。倉石の視点では、小菅は「犯人に見える材料が多い」だけで、決定打がない。
容疑者② 担任教師・古川達郎――「好意」と「タイムラグ」
次に浮かび上がるのが、周平の担任教師・ 古川達郎 だ。真弓の相談に乗っていた人物であり、周平とも距離が近い。善意の顔をして近づき、母子の弱さにつけ込んでいた可能性もゼロではない。捜査を進めると、古川が事件当日の深夜、マンションを訪ねていたことが判明し、防犯カメラにも映像が残っていた。
古川は、真弓を放っておけなかったのだと言う。父親に怯える周平、追い詰められていく真弓。教師として正しい距離感でいたいのに、感情が先に出る。そんな危うさが古川の態度に滲む。さらに、古川が真弓に手紙を残していたことも明らかになる。踏み出す一歩をためらいながらも、想いを綴った置き手紙。真弓がそれを読んでいた場面があったと聞けば、立原たちは古川を疑わずにいられない。
ただし大きな壁がある。古川の訪問時刻と、ふくろう隊が転落音を聞いた時刻の間に、数時間のギャップがあったのだ。古川がマンションを訪れた“事実”は重いが、犯行時間と噛み合わない。しかも古川は、何らかの鍵を拾ったことがあるなど、状況的に怪しく見える要素も持っている。任意での事情聴取は続くが、物証で詰め切れない。
倉石は古川を見て、別の線を読む。古川は確かに“線を越えそうな男”だが、遺体の手首に残る圧迫痕の強さとは一致しない。ここでも鍵になるのは、言い訳でも態度でもなく、遺体に残る力の痕跡だった。
倉石の確信――「父親は犯人じゃない」と言い切る理由
捜査本部が父親や教師の線で動く一方、倉石は小坂にぽつりと言う。「父親は犯人じゃない」。決めつけではなく、検視官としての“確信”だ。
根拠は複数ある。まず靴。父親が突き落としたなら、犯行後に靴を履かせる合理性が薄い。次に圧迫痕。子どもが証言する“パパ”の暴力は確かに想像できるが、遺体に残る手首の痕は、衝動的な殴打というより、相手を制止するような持続の力に見える。そして周平の様子。母の死を目撃した子どもが、あれほど強く断定しながら、同時に「ママはいつ帰ってくる?」と待つような顔をするのは不自然だ。証言が嘘だと断言するのではなく、「証言がそのまま事実になる状況ではない」と読む。
倉石は“生きている人間の言葉”より、“死体の沈黙”を優先する。その姿勢が、事件の終盤で一気に効いてくる。
サイドシーン:バー「かくれんぼ」の西田先生――DVへの怒りが滲む
捜査の合間、倉石が顔を出すバー「かくれんぼ」では、法医学教授の 西田守 が酒に酔っている。西田は普段どこか飄々としているが、今回は珍しく苛立ちを隠さない。真弓の体に残っていた古傷――あれが日常の暴力だとすれば、医師としても人としても許せないのだろう。ふだん軽口を叩く西田が「DV男はロクなもんじゃない」と吐き捨てる言葉が、事件の陰惨さを逆に浮き彫りにする。
この店のシーンは、単なる息抜きじゃない。倉石が“死”を扱う人間として孤立し過ぎないための呼吸であり、同時に、事件の背景にある社会の歪みを言葉にする場所でもある。
倉石のアプローチ――「絵」で周平の心に近づく
周平の証言が捜査を引っ張る一方で、倉石は周平を“証人”として扱わない。まず子どもとして見る。周平が絵を描くのが好きだと知ると、倉石はスケッチブックに視線を落とし、「うまいな」と素直に褒める。周平が少しだけ表情を緩めると、倉石は自分の不器用さを笑いに変える。「俺はダメだ。猫を描いても牛になる」。周平がクスッと笑う。ここで初めて、周平は“取り調べ”ではなく“会話”に入ってくる。
永嶋もまた、周平のためにスケッチブックや画材を買ってきて寄り添う。彼の空気の読めなさが、逆に子どもには効く瞬間がある。大人の警察官たちが、事件の中心にいる少年をどう扱うか――それ自体が、この回のもう一つのテーマになっている。
倉石は周平に、「怖かったか」「パパはどっちへ行った」と詰めない。絵を見て、部屋の空気を感じ取り、周平が安心できる場所を確保してから、少しずつ“事実”へ近づく。子どもにとって“事実”は、質問に答えることではなく、信じたいことを守ることでもある。倉石はその境界を踏み外さない。
現場を洗い直す――周平が出入りする「管理人室」の存在感
倉石は現場へ戻り、マンションの空気をもう一度嗅ぎ直す。そこで見えてくるのが、周平とマンション管理人・ 岩瀬厚一郎 の距離感だ。周平は真弓の帰りが遅い日、管理人室で絵を描いて待つことが多かったらしい。管理人室には周平のスケッチブックが置かれ、岩瀬は周平に優しく接している。周平も懐いている。
岩瀬は、母子の事情もよく知っていた。真弓が元夫に悩まされていたこと、周平が父親を怖がっていること、母の帰りが遅い日は自分が面倒を見ていたこと。話を聞けば聞くほど“いい人”に見える。立原たちも最初は、岩瀬を「協力者」として扱う。岩瀬自身も、警察に水を出すなど気遣いを見せ、場の空気を和らげようとする。
その岩瀬の口から、一ノ瀬は別の情報を引き出す。事件当夜、担任教師の古川が深夜にマンションを訪ねてきたというのだ。小菅の線で動いていた捜査が、古川へ向き直る。結果的に岩瀬の一言が“疑いの矛先”を動かした形になる。もちろん、その後に時間のギャップが判明し古川は外れていくのだが、犯人が最初から最後まで「自分が疑われにくい位置」に立っていたことが、ここでもはっきりする。
だが倉石は、“いい人”という評価を一旦棚に上げる。重要なのは岩瀬が周平の生活圏に深く入り込み、事件当夜の動線に近いところにいたという事実だ。さらに、管理人室の壁に飾られた一枚の絵が目に入る。周平が描いた岩瀬の姿で、そこには剣道の防具が描かれていた。岩瀬が剣道経験者だという情報が、さりげなく提示される。
倉石は水の入ったグラスを手にしながら、岩瀬の指先の動きや手の使い方を観察する。指紋採取のためではない。人は自分の“手”を無意識に隠せないからだ。遺体に残る圧迫痕の“手”と、目の前の男の“手”が重なるかどうか。倉石の捜査は、いつもそこに戻ってくる。
「靴の謎」を実験で潰す――なぜ踵が傷つくのに靴があるのか
捜査一課は、倉石の指摘した「踵の擦過傷と靴」の矛盾を確認するため、現場で再現実験を行う。転落時に靴がどうなるのか。階段の形状、落下の角度、体の回転。机上の推理ではなく、現場の物理で検証するのが“臨場”の気持ち良さだ。
結果、靴は転落の途中で脱げやすいことが分かる。踵を擦った痕があり得る状況が成立し、なおさら「発見時に靴が履かされていた」ことが不自然になる。つまり、靴は“誰かが後から”触ったという結論が補強される。
ここで捜査は二層構造になる。真弓を突き落とした“犯人”の問題と、靴を履かせた“もう一人”の問題。もし犯人が靴を履かせたのなら、目的は何か。もし別人が履かせたのなら、その人物は現場にいたことになる。倉石は、後者の可能性を強く疑う。なぜなら、靴を履かせる行為は「痕跡を消す」より「誰かのために」やる行為に近いからだ。
「ふくろう隊」の耳――逃げた足音は“6、7歩”だった
捜査が煮詰まる中、倉石はふくろう隊に会いに行く。彼らは地中の音を聴き分ける職人で、夜の現場に慣れている。倉石は興味本位ではなく、捜査のピースとして彼らの話を掘り下げる。さらに倉石は、ふくろう隊に同行して夜回りを体験する。暗闇で音を拾い、微妙な違いを笑いながら言語化する彼らに、倉石は一瞬たじろぎ、思わず表情が崩れる。ふくろう隊はそれを見て「うふふ」と笑う。事件の真ん中に、職人の矜持とユーモアが挟まってくる。
そして彼らが思い出すのが、転落音とほぼ同時に聞いた「逃げる足音」だ。村越英二は言う。逃げた足音は長く続かなかった。具体的には“6、7歩”。彼らの感覚では、それ以上でもそれ以下でもない。
この数字が意味するのは、逃走距離の短さだ。非常階段下で殺人が起き、犯人が走って逃げたのに、足音が6、7歩で終わる。つまり犯人は廊下を走り抜けたのではなく、すぐ近くのどこかへ“逃げ込んだ”。現場の構造を思い出すと、その“逃げ先”は限られる。
手首の圧迫痕が示すもの――剣道経験者の握り方
倉石が重視するのは、遺体の手首に残る圧迫痕だ。掴まれた場所、深さ、指の並び方。単なる乱暴な掴み方ではなく、力が一点に集中しているような痕。小坂留美は、剣道経験者の握力には特徴があることを口にする。左手の小指側に力が集まりやすい――竹刀を握る癖が、日常の握り方にも滲むという。
捜査一課は小菅や古川の握力や手の特徴を見ていくが、圧迫痕を作れるほどの力がない。小坂は痕の深さや指の当たり方から、握りの癖まで読み取ろうとする。たとえば、親指と人差し指だけで乱暴に掴めば痕は散るが、握力のある人間が小指側に力を集めて掴めば、痕は一点に沈む。実際に小坂が自分の手で「この持ち方だとこういう痕になる」と示すと、痕跡の意味が生々しくなる。
そうして見えてくるのは、“力があるだけ”ではなく“力のかけ方に癖がある”犯人像だ。最初に疑われた二人が、物証で外れていく。証言で人を縛っても、遺体がそれを否定するなら、捜査はやり直しだ。
そして残るのが岩瀬。管理人室の絵が示す剣道経験、周平との距離の近さ、現場への近さ。優しい管理人、母子を気遣う近所の大人。その顔の裏側に、遺体が示す“手”が重なってしまう。
真相へ――「6、7歩」で届く場所は管理人室だけ
捜査一課は現場検証を行い、ふくろう隊の証言する足音の距離感を現場に落とし込む。非常階段下から走り出して6、7歩。実際に現場で歩幅を合わせ、走り出して数えると、犯人が向かえる場所が驚くほど限られていることが分かる。数歩で到達できるのは、ちょうど管理人室の扉付近。逆に、外へ抜けたり別の棟へ向かったりするには、足音が6、7歩で収まるはずがない。
ここがこの回の気持ちいいところで、曖昧な「逃げたらしい」を“歩数”に変換してしまう。目撃証言がぶれても、足音は嘘をつかない。遠くへ逃げるなら足音はもっと続く。近くへ隠れるなら、ここしかない。
立原たちは、証言と物証が“管理人室”へ収束するのを見て、方向転換せざるを得なくなる。ここで倉石は、立原たちに釘を刺すように言う。「俺のとは違うな」。つまり、捜査一課が固めかけていた“元夫犯人”という見立ては、検視の視点からは成立しない。犯人の行動、力、逃走距離――すべてが岩瀬の位置に集まっていく。
管理人・岩瀬厚一郎の動機――「父親役」への勘違いと嫉妬
追い詰められた岩瀬は、最初は取り繕う。自分は母子を気遣っていただけだ、と。しかし遺体に残った圧迫痕と剣道経験、そして足音の距離が重なると、逃げ場はない。岩瀬が真弓に好意を抱いていたことも、捜査の中で浮かび上がる。
周平と親しくなり、母子の生活に深く入り込むうちに、岩瀬は自分が“父親役”になれるのではないかと期待してしまった。そこに真弓の何気ない言葉が刺さる。周平が「岩瀬さんがお父さんだったらいいのに」と言っている――そんな趣旨のことを真弓が伝えたことで、岩瀬は「自分は受け入れられている」と誤解する。母子が安心して頼れる大人への感謝の言葉が、岩瀬の中で勝手に“恋の証拠”に変換されてしまう。
そして決定打となったのが、真弓が担任教師からの手紙を嬉しそうに読んでいる姿だった。岩瀬はその瞬間、嫉妬に飲まれる。真弓を問い詰め、非常階段付近で言い争いになる。逃げようとする真弓の手首を強く掴み、振りほどかれそうになった瞬間、岩瀬は衝動的に突き飛ばしてしまう。真弓は非常階段から転落し、致命傷を負う。
転落の音を聞いたふくろう隊が駆け付ける。岩瀬はパニックのまま、6、7歩の距離で管理人室へ逃げ込んだ。自分の生活圏の中に“逃げた”という行動が、後に自分を縛る縄になる。いい人の仮面で近づいた距離の近さが、犯行後の隠れ場所にもなってしまうという、皮肉な構図だった。
追及された岩瀬は、最後は崩れる。真弓を守りたかった、周平の父親になりたかった、そういう言葉が混ざりながらも、結局は「自分の思いどおりにしたかった」だけだと露呈してしまう。恋や家族の幻想にしがみついた末に、人の命を奪った。その現実だけが残る。
真弓が周平に言い聞かせていた「生き返る」という言葉――優しさが嘘になる瞬間
事件をややこしくしたのは、周平の嘘だけじゃない。そもそも周平が“嘘をつく土台”には、真弓が周平に繰り返し語ってきた言葉がある。
DVに怯える夜、真弓は周平を安心させるために「ママは死んでもすぐ生き返る」と言い聞かせていた。そしてさらに「周平がいてくれさえすれば、ママは生き返れる」とまで言う。大人から見れば、苦しさの中で自分に言い聞かせたような言葉でも、子どもにとっては“現実のルール”になる。
この回が切ないのは、その優しさが結果的に“嘘”として機能してしまうことだ。真弓は周平を守るために嘘をつき、周平は真弓を守るために嘘をつく。嘘が嘘を呼び、捜査は最初、父親へ固定される。けれど倉石が見ているのは、嘘そのものではなく、嘘が生まれる理由だ。
周平にとって「死」は終わりではなく、「戻ってくるための準備が必要な出来事」になってしまった。靴を履かせれば歩いて帰れる、悪いのはパパだと言えばママは安心して生き返る――幼い理屈は不器用だけれど一貫している。だからこそ、ラストで周平が「いつ生き返るの?」と問う瞬間が、ただの悲しみではなく“母の言葉の延長”として胸に刺さる。
「赤い靴」を履かせたのは誰か――周平がついた嘘の理由
事件は岩瀬の逮捕で終わらない。最初から最後まで捜査を惑わせた“靴”の謎が残る。踵に擦過傷があるのに靴を履いていた。誰が、何のために履かせたのか。
答えは周平だった。 周平は母が落ちた瞬間を目撃していなかった。にもかかわらず「パパがママを殺した」と言い張ったのは、父親を憎んでいたからだけではない。周平の中には、母が繰り返し口にしていた言葉が残っていた。DVで傷ついた夜、真弓は周平に「ママは死んでもすぐに生き返る」と言い聞かせていた。周平はその言葉を“本気”で信じてしまっていた。
母が倒れているのを見つけた時、周平は「ママはまた戻ってくる」と思った。なら、ママが戻ってくるために必要なものは何か。子どもなりの結論が「靴」だった。近くに転がっていた赤い靴を拾い、母の足に履かせた。そうすればママは歩いて帰ってこられる。周平は本気でそう信じていた。
倉石が周平にそのことを確かめる時も、取調べの口調にはならない。「どうして靴を履かせた?」ではなく、「ママ、歩けるようにしてあげたかったのか」。周平は小さくうなずき、「ママは帰ってくる」と言う。その時点で、周平の“嘘”は隠蔽ではなく祈りだと分かる。
そしてもう一つ、周平の嘘が向いた矛先が「パパ」だった理由がある。真弓は夫の暴力に苦しめられ、父親の存在そのものが母子の恐怖になっていた。父親が悪者になれば、ママは救われる。全部を父親のせいにしてしまえば、ママは安心して生き返るかもしれない。周平の嘘は、幼い祈りの形だった。
ラスト――倉石が周平に渡した「約束」
事件の後、周平は倉石に尋ねる。「ねえ、ママ、いつ生き返るの?」。大人が聞けば言葉を失う問いだ。倉石は嘘で慰めない。だが子どもの世界を壊し過ぎない言葉を選ぶ。「ママはすぐには戻らない。でも、ママはお前を試してる」と。
倉石は周平に“生き方”の宿題を渡す。毎日ちゃんとご飯を食べて、元気いっぱい遊んで、勉強もやって、一人でだって生きていけるところを見せろ。そうしたらママは喜ぶ。寂しくて我慢できない時は、思い切り泣け。周平はうなずき、倉石と指切りをする。
第8話「証言」は、犯人当てのスリルよりも「嘘をついた子ども」をどう受け止めるかに着地する。死体は嘘をつかない。けれど生きている者は嘘をつく。大人の嘘、弱さからの嘘、そして幼い願いからの嘘――その全部が一つの遺体に集まり、最後に倉石の言葉でほどけていく回だった。
事件としては岩瀬が逮捕され、周平は姉のもとへ預けられることになる。けれどこの回の後味は、犯人が捕まったからといって軽くはならない。母は子を守るために「生き返る」という嘘をつき、子は母を戻すために父を犯人にした。嘘は悪意だけで生まれるわけじゃない。倉石が最後に周平へ渡したのは、真実の断罪よりも「生きる」ための小さな約束だった。
大人たちは証言を取るために言葉を削り、検視官は沈黙から真実を拾う。周平の証言も、ふくろう隊の「足音」の証言も、同じ“証言”でありながら性質がまったく違う。だからこそ最後に残るのは、周平の言葉をただの嘘として切り捨てず、嘘の奥にある願いまで抱えたまま前へ進ませる倉石の姿だ。
タイトルが「証言」なのに、結局いちばん信用できたのは“死体”と“音”だったという皮肉も効いている。証言の裏切りを描きながら、人が人を救うのもまた言葉だと示す、シリーズの中でも余韻の濃い一編だ。
周平の指切りが終わった瞬間、事件は終わっても物語は続くと静かに伝わってくる。見届けたくなる。
ドラマ「臨場 続章」8話の伏線
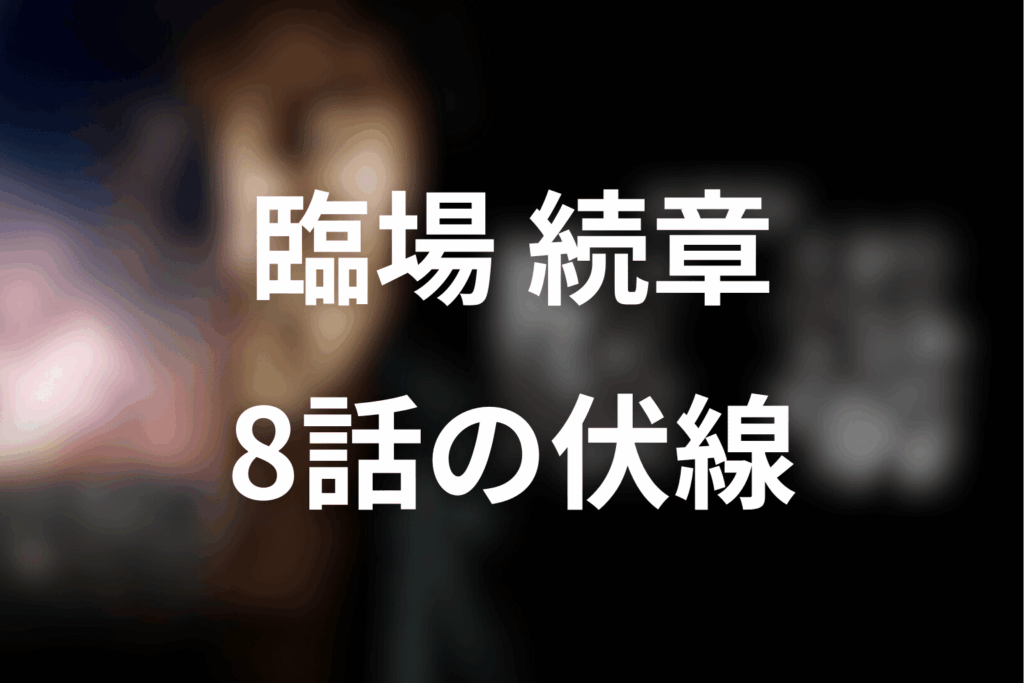
第8話「証言」は、タイトルどおり「人の言葉」を軸にした回だ。目撃者はいる。しかも子どもが、はっきりと「パパがママを殺した」と言い切る。にもかかわらず、倉石義男が追いかけるのは“証言の正しさ”じゃなく、“遺体が語る事実”のほう。
この回のうまいところは、事件の核心が「大人の嘘」だけでなく「子どもの嘘」にも触れている点だ。だから伏線も、犯人当てのためのヒントだけじゃない。仲田周平が何を見て、何を信じて、何を守ろうとしたか――そこに向かって、細部が全部つながっていく。
「靴がきちんと履かされている」という最大の違和感
現場はマンション非常階段下。転落死に見えるのに、遺体には古い殴打痕があり、他殺の匂いが濃い。さらに決定的なのが、踵の擦過傷と“靴”の組み合わせだ。普通なら突き落とされ、体が階段に当たれば靴は脱げたりズレたりする。なのに靴はきちんと履かされていた。
この一点が、「誰かが死後に履かせた」という線を浮上させ、犯人像を“現場で遺体を触れる人物”に絞り込んでいく。ところが終盤、その行為者がまさかの周平だとわかる。 伏線として機能しているのは靴そのものより、「履かせる行為=犯人の工作」と思い込ませる脚本の誘導だ。視聴者は“悪意のある一手”を想像する。でも実際は、幼い子の願いから出た行動だった。この反転が、回全体の読後感を決めている。
手首の圧迫痕は「転落」では説明できない
第8話は、検視で拾った“転落とは別の痕”が、じわじわ効いてくる構成。手首の新しい圧迫痕はその代表だ。転落なら、手首が均一に強く締め付けられる必然性がない。つまり誰かに強く掴まれ、押さえつけられた。
この圧迫痕が「DVを疑われていた元夫」や「好意を寄せていた担任教師」から外れていくのが面白い。疑われる人物が複数いても、痕が語る“腕力の質”だけは変わらない。物証が人間関係の濃さに引っ張られない、臨場らしい伏線だ。
管理人室の“絵”が、剣道の伏線になっている
周平が懐いているマンション管理人の岩瀬厚一郎。優しく面倒見がよく、いかにも「近所に一人はいる頼れる大人」に見える。 その岩瀬を疑う決め手のひとつが、管理人室に飾られた周平の絵だ。そこには、岩瀬が剣道をしている姿が描かれている。
剣道経験者は握り方に癖が出る――その豆知識が、手首の圧迫痕と結びつく。視聴者にとっては「絵」という微笑ましい小道具が、いつの間にか犯人の素性を語るサインに変わっているわけで、かなり上品な伏線の置き方だと思う。しかも絵は、周平と岩瀬の距離の近さも同時に語る。つまり“動機”と“手口”の両方に通じる小道具になっている。
“ふくろう隊”の足音カウントが、逃走距離を暴く
通報したのは水漏れ調査員(通称“ふくろう隊”)。鉄階段を転がり落ちる音を聞いて駆け付け、遺体と周平を発見したという導入がまず効いている。 彼らは転落の音を聞きつけた直後、逃げる足音も耳にしている。ところが、その歩数が「6、7歩」程度だったという証言が、終盤で決定打になる。
もし犯人が外へ逃げたなら、そんな短い足音で終わるはずがない。つまり、犯人は近くの“どこか”に吸い込まれていった。現場の構造を知っている人物、鍵を持っている人物――そうやって候補が狭まり、「見えていたはずの場所」に真犯人が立っていたことが明確になる。
周平の言葉のブレが、「見ていない」伏線になる
周平は「父が逃げた」と言い張る一方で、どこか現実と噛み合わない反応を見せる。象徴的なのが、“ママは死んでもすぐに生き返る”という信念だ。周平にとって事件は“殺人”なのに、“帰ってくるはずの出来事”になっている。
このズレが、単なるトラウマ描写に留まらず、「周平は現場の核心を見ていない」「事実を組み立て直している」という伏線になる。だからこそラストで、靴を履かせたのが周平だったと明かされたとき、物証と心理が一気に一本の線でつながる。嘘の正体は“悪意”じゃなく“否認”で、子どもが崩れないためのギリギリの選択だった――そう思わせるための、丁寧な下ごしらえだ。
置き手紙と「父親だったら…」の一言が、嫉妬の火種を作る
第8話の犯行動機は、恋愛感情というより「孤独と勘違い」が引き金になっている。岩瀬は周平と親しく、仲田真弓から「この子、岩瀬さんがお父さんだったら良かったって」といった趣旨の言葉を受け取ってしまう。
さらに、担任の古川達郎が残した置き手紙を真弓が嬉しそうに読む場面が決定的だ。 “自分の居場所”だと思っていたところに、別の男の気配が差し込む。そこから岩瀬の感情が傾くのは早い。視聴中は「親切な管理人」の顔が先に入ってくるから、この火種が見落とされがちだ。だが振り返ると、動機の伏線はかなりストレートに置かれている。
目立つ容疑者(DV元夫)を立てることで、本筋の動機が際立つ
元夫の小菅光晴はDVの影と、事件当夜のマンション出入りという要素で“わかりやすい犯人役”を背負わされる。周平の証言もそれを後押しする。 ここはミステリーとして王道の配置だ。
ただし第8話は、それを単なる当て馬で終わらせない。DVの影があるからこそ、周平は「パパがやった」という物語を作りやすいし、捜査もその方向に流れやすい。けれど遺体の痕がそれを否定する。結果として、真犯人の動機――“善人の顔をした孤独と嫉妬”――が、より不気味に浮かび上がってくる。
「死体は嘘をつかない」という対比が、回全体の読み解き方を指定する
捜査側も、最初は周平の証言に引っ張られる。けれど立原真澄が一ノ瀬和正に語る“死体は嘘をつかないが、生きている人間は嘘をつく”という趣旨の言葉が、視聴者の視点をスッと切り替える。
この一言があるから、僕らは「周平が嘘をつく可能性」を感情的に拒否せずに済む。子どもの証言を疑うのは残酷だ。でも、嘘には理由がある。その先にしか救いはない――という方向に舵を切るための“テーマ伏線”になっている。結果として、ラストの指切りまで含めて「真相解明=誰かを追い詰めること」ではなく、「残された人が生き直す道を作ること」へ着地できた。
伏線を振り返ると、どれも“犯人当て”のために置かれているというより、周平という子どもの心の動きと、倉石の見立ての精度を同時に支える部品だったと気づく。物証と感情が同じ方向を向く瞬間を作る――それが第8話の強さだ。
ドラマ「臨場 続章」8話の感想&考察
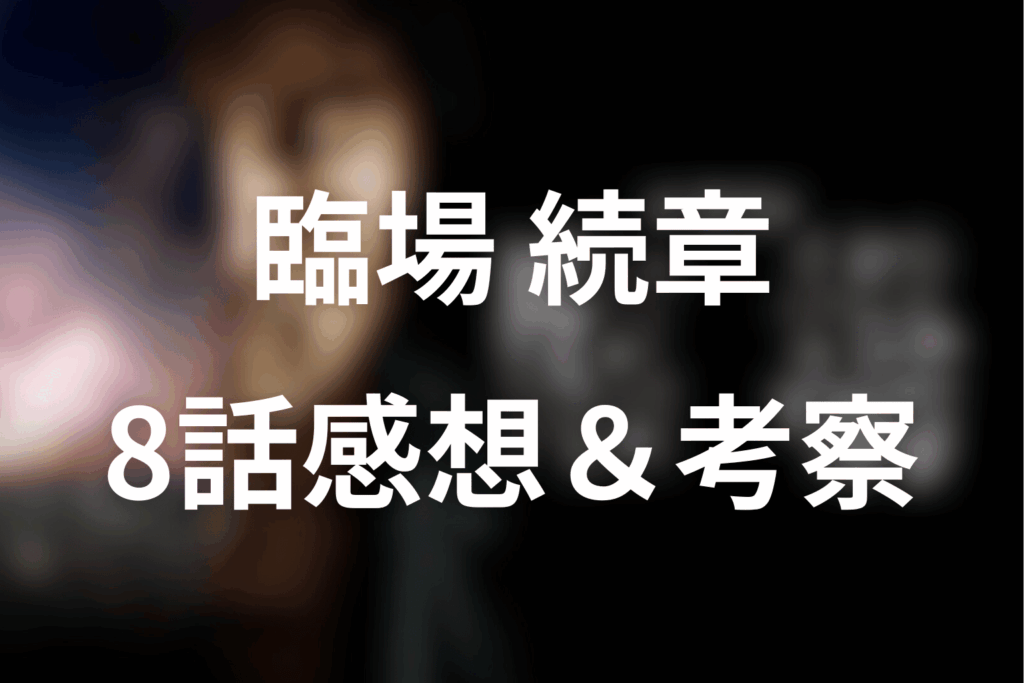
第8話「証言」を見終わって最初に残るのは、事件の残酷さよりも“子どもが抱える物語”の重さだった。母が死んだという現実を、そのまま受け止められる子どもなんていない。だから周平は、真実を語る代わりに、真実から自分を守る物語を語る。
この回はミステリーとしても成立しているけれど、核心は「嘘を暴く快感」じゃない。嘘が必要になってしまった背景と、その嘘をほどく大人の責任を描いている。検視官のドラマでありながら、心のケアのドラマでもあった。
「証言」は武器にも凶器にもなる――嘘を責めない描き方
事件の入口は周平の断言だ。「パパがママを殺した」。この一言が、捜査の方向を一気に決める。
ただ、第8話が優しいのは、周平の嘘を“捜査妨害”として裁かないところだ。子どもが嘘をつく時、それはたいてい「悪いことをしたい」からじゃなく、「悪い現実を直視できない」からだ。大人の世界で言えば自己保身。子どもの世界で言えば生存本能に近い。
しかも嘘をついているのは周平だけじゃない。元夫の小菅は「証拠があるなら見せろ」と開き直り、自分が疑われること自体に反発する。 担任教師も、夜中にマンションを訪ねた事実が浮上し、周りに言いにくい“感情”を抱えている気配がある。
つまり第8話は、嘘を「悪」として切り捨てない。嘘はそれぞれの弱さから生まれ、弱さは誰にでもある――という視点を最初から持っている。だから終盤、嘘がほどけた時に残るのは糾弾ではなく、やりきれなさだ。
“靴”が象徴するのは、子どもの現実感だ
個人的に一番刺さったのは、靴の真相。視聴中は「犯人が履かせた」という推理が自然に浮かぶ。遺体の踵には新しい擦過傷があるのに、靴はきちんと履かされている。 これだけで“死後の工作”が透けて見えるからだ。
ところが、靴を履かせたのは周平だったと分かる。 ここで事件の意味が反転する。工作は工作でも、悪意の工作ではなく、願いの工作。
「生き返って戻って来るには靴が必要」と思った周平の発想は、大人には突飛に見える。でも子どもにとって死は、理屈よりも感覚に近い。ならば“戻ってくる条件”を自分で作る。靴はその条件の象徴だ。
そして巧いのは、物証としての靴が、心理描写としての靴にもなるところ。検視官ドラマの小道具が、そのまま人間ドラマの核心になる。臨場が得意とする“痕跡=感情の翻訳”が、ここで一番きれいに決まっていたと思う。
“ふくろう隊”が持ち込む軽さと、耳が拾う真実
今回の脇役で忘れがたいのが、水漏れ調査員(通称“ふくろう隊”)。彼らは事件の通報者であり、現場の最初の目撃者でもある。
正直、彼らの存在は少しコミカルで、張り詰めた回に呼吸を入れてくれる。倉石が夜回りに付き合うくだりも、硬派な刑事ドラマではあまり見ないタイプの寄り道だ。
でも、この寄り道が無駄じゃない。ふくろう隊の強みは“耳”だ。転落の音、逃げる足音、その歩数が「6、7歩」だったという事実が、最後に事件を決める。
科学捜査ではなく、職人の感覚。ここが面白い。人間の感覚は不確かだけれど、研ぎ澄まされた感覚は時に、機械より具体的な情報を持ってくる。第8話は、検視官ドラマでありながら「人間の感覚もまた証拠になる」と示している。
管理人・岩瀬の怖さは「悪人」ではなく「勘違い」にある
真犯人が岩瀬だと分かった瞬間、ゾッとするのは「最初から怪しい男」ではなかったからだ。周平の面倒を見て、真弓にも気を遣う。近所付き合いの顔をしている。
それが、一言の受け取り方で歪む。「岩瀬さんがお父さんだったら良かったって」という言葉を、自分への好意の証拠だと信じてしまう。そこに担任教師の置き手紙が重なり、嫉妬が暴走する。
ここで重要なのは、真弓が悪いとか、言い方が悪かったとかではない。岩瀬が“勝手に物語を作った”ことが問題なんだ。自分の孤独を埋めるために都合のいいストーリーを作り、そのストーリーが崩れた瞬間に、他人の人生を壊す。
この構造は、現実の事件でもよく見る。悪意よりも、自己中心的な解釈のほうが人を壊す力を持っている。しかも岩瀬は“子どもに好かれている自分”を根拠に、善人の自分像を補強していたようにも見える。だからこそ、崩れた時の反動が大きい。
剣道の伏線が示すのは「手口」だけじゃない
岩瀬が剣道経験者で、握力の癖が手首の圧迫痕と結びつく――これは推理のパーツとして気持ちいい。
ただ、この伏線は手口の説明だけじゃなく、岩瀬の“体の言語”でもあると思った。剣道は相手を制する競技だ。礼節がありながら、相手を押し込む力学がある。岩瀬の犯行はまさに、礼節の仮面の下にある支配欲が噴き出した形に見える。
管理人室の絵が、可愛い小道具から一気に不穏な証拠へ反転する瞬間も含めて、この回は「優しさに見えるものが、別の顔を持つ」怖さを丁寧に描いていた。
DVの影が「疑われやすさ」と「子どもの嘘」を生む
遺体に残る古傷は、真弓が日常的に暴力を受けていた可能性を示している。 その情報が出た途端、捜査も視聴者も「元夫が犯人だろう」と思いやすくなる。
でも周平の視点で見ると、もっと深刻だ。家庭内に暴力があった場合、子どもは“誰が敵か”を早い段階で学ぶ。だから周平は「パパがやった」と言うことで世界を単純化できる。恐怖の原因を一人に固定できる。しかも、そう言えば大人たちは自分を守ってくれると思える。嘘は、助けを呼ぶ方法にもなり得る。
第8話は、DVをセンセーショナルに消費しない。DVが残すもの――疑われやすさ、信じられなさ、子どもの思考の癖――を静かに残している。ここが、単発事件のドラマを越えて、社会派に寄っていく臨場らしさだと思う。
倉石の“寄り添い方”が、真相よりも後味を決めた
周平に対する倉石の接し方は、この回の救いだ。彼は「証言を取るため」に近づかない。絵を褒め、会話の速度を周平に合わせる。
そしてラスト、周平が「ママはいつ生き返るの?」と尋ねた時、倉石は“正論”で叩き潰さない。すぐには戻らない、と現実を置いたうえで、周平が生きていくための“約束の形”を作る。食べて、遊んで、勉強して、どうしても我慢できない時は泣け――そして指切り。
ここで倉石がやっているのは、慰めじゃなく、生活の設計だ。悲しみを消すことはできない。だから「明日をどう過ごすか」を具体化する。しかも、その内容が“頑張れ”ではなく、“ご飯を食べろ、遊べ、泣け”という生活語彙なのがいい。
倉石は遺体に向き合うプロだが、同時に遺族の現実にも向き合うプロなんだと再確認させられた。
一ノ瀬の未熟さが、逆にリアルだった
一ノ瀬は周平の聴取でうまくいかない。焦るし、踏み込みすぎる。視聴者目線だと歯がゆい。
でも、ここはリアルでもある。子どもの嘘を見抜くのは難しいし、まして“嘘をつく理由”まで含めて扱うのは、経験と器がいる。立原の「死体は嘘をつかないが、生きている人間は嘘をつく」という言葉は、一ノ瀬への叱責というより、捜査官としての視点の切り替え指示だ。
一ノ瀬がこの回で失敗したのは、相手を“証人”として見すぎたこと。周平は証人である前に、被害者遺族で、まだ幼い子どもだ。その前提が抜けた瞬間、言葉は凶器になる。第8話は、一ノ瀬の未熟さを晒すことで、倉石の成熟をより際立たせている。
「遺体は最後の証人」――検視官ドラマの倫理
第8話は“証言”を扱いながら、最終的に一番信用できる証言者が遺体であることを強調する。殴打痕、圧迫痕、擦過傷。そこには「こうされた」という一方通行の事実が残り、感情の都合で書き換えられない。
冷たい言い方に聞こえるけれど、この冷たさがあるからこそ、周平の嘘も、岩瀬の勘違いも、元夫の開き直りも、正しい位置に戻せる。遺体の声を拾い上げることは、被害者の尊厳を取り戻すことでもある。倉石が“拾えるものは根こそぎ拾う”タイプの男である意味が、この回ほど腑に落ちる回はない。
まとめ:真実は暴くものじゃなく、渡すもの
第8話を通して感じたのは、真実の扱い方の話だった。真実は“隠された宝”みたいに暴いて終わりじゃない。誰に、どんな形で渡すのかが本題だ。
周平が背負う真実は重い。岩瀬の罪は重い。真弓が抱えた日常も重い。その重さを「解決しました」で片付けないために、倉石の指切りが置かれている。事件が終わっても生活は続く。だからこそ、最後に残るのは“捜査の勝利”ではなく、“生き直すための約束”だった。
ドラマ「臨場 続章」の関連記事
ドラマ「臨場 続章」の全話記事についてはこちら↓
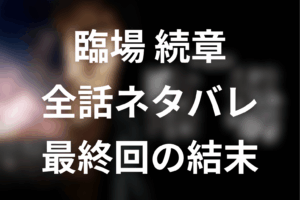
第一章についてはこちら↓
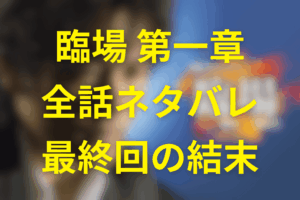
次回以降についてはこちら↓
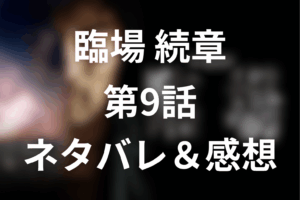
過去の話についてはこちら↓
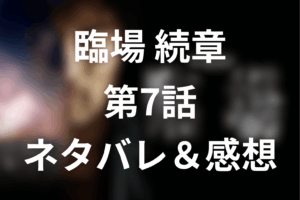
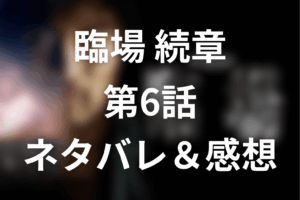
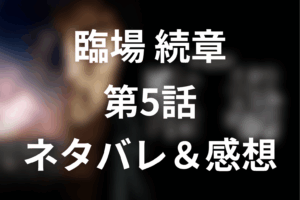
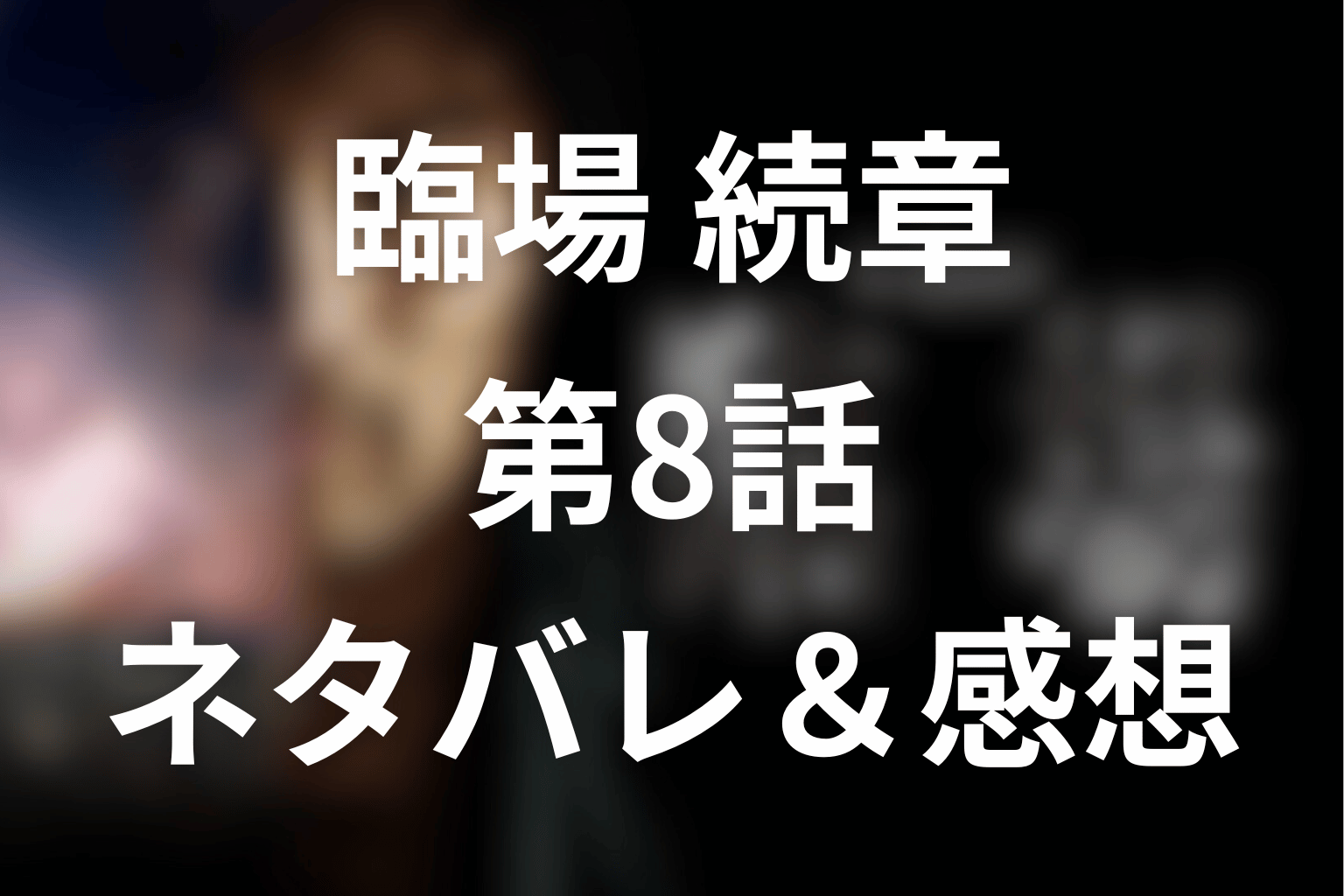
コメント