第7話は、「助かったあと、どう生きるか」を突きつけてくる回でした。
屋上から飛び降り、それでも生き残ったトビオは、「幸せになってトントン」という言葉で自分を納得させようとします。けれど、その“前向きさ”は本当に再生なのか、それとも罪悪感から逃げるための仮面なのか。
一方で、伊佐美は遺族宅を巡り、マルは何事もなかったように日常へ戻り、パイセンは父・輪島という巨大な空洞に近づいていく。そしてトビオと蓮子の関係にも、はっきりとした決着が訪れる。
7話は、誰もが「楽になる選択」をしているようで、実は全員が次の地獄に一歩踏み込んでしまった回だったと感じました。
ドラマ「僕たちがやりました(僕やり)」7話のあらすじ&ネタバレ
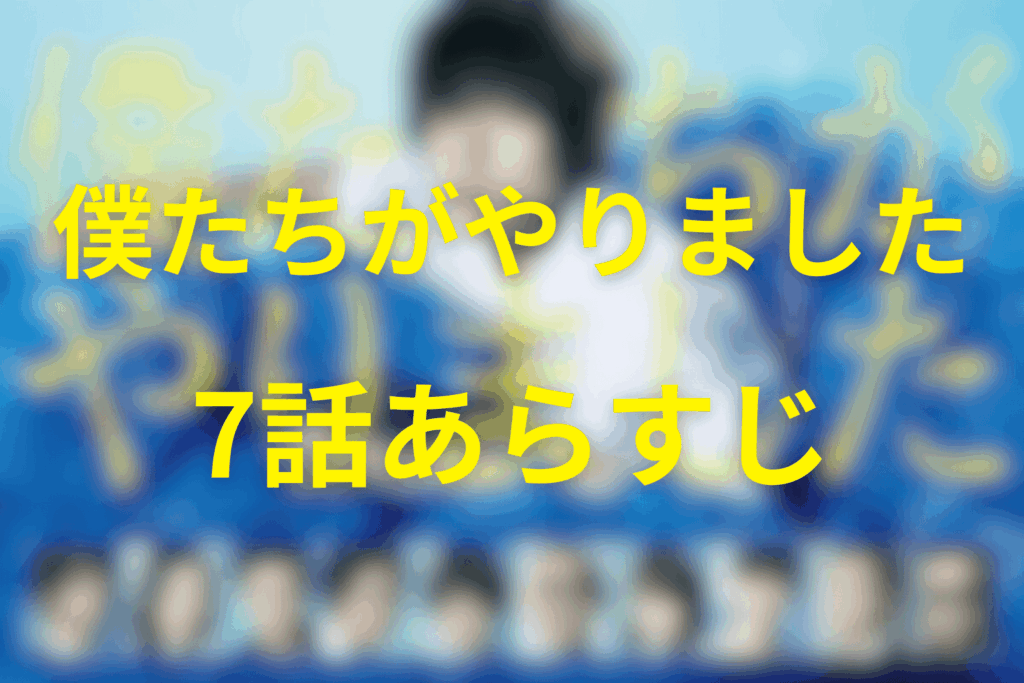
第7話の副題は「罪悪感と偽りの自分…恋にも決着」。
飯室刑事に“真実”を突きつけられたトビオは、校舎の屋上から身を投げる——しかし奇跡的に生還する。なぜ自分は助かったのか、これからどう生きるのか。第7話は、トビオが罪悪感と自己正当化のあいだで“新しい自分”を演じ始める回だった。
一方で、パイセンは父・輪島宗十郎の正体と向き合う決意を固め、伊佐美は遺族宅を一軒ずつ回る“私的な弔い”へ。マルは相変わらず能天気に日常復帰を試みる。
四人がそれぞれ違う距離感で“現実”に触れ始め、友情も価値観も、ゆっくりと崩れていく。
屋上からの転落と“新しい俺”——病院での再会が生むねじれ
飯室に被害者10人の“顔”を突きつけられたトビオは、その場で絶望のスイッチが入る。衝動的に屋上から飛び降りるが、命は助かり、骨折のみで生還する。
搬送先は、皮肉にも市橋が入院している同じ病院だった。
生き延びたトビオは、ここでひとつの結論を出す。
「死ねばそれで償い。生きたなら、新しい俺を始める」。
彼は“幸せになってトントン”という歪んだスローガンを自分に刷り込み、罪悪感を明るさで塗りつぶそうとする。表面上は前向きだが、その笑顔はどこか軽すぎる。
第7話のトビオは、生きる覚悟を決めたというより、「生きている自分を正当化する役」を演じ始めたようにも見える。
市橋の告白とトビオの“背中押し”——友情の顔をした矛盾
リハビリの合間、市橋は蓮子への想いを、はじめて誰かに言葉として打ち明ける。トビオは「応援する」と背中を押すが、内心は穏やかではない。
友情を選んだフリをしながら、トビオは“新しい俺”の仮面を外せない。
市橋の純粋さが際立つほど、トビオの選択は歪んでいく。第7話は、友情が静かに壊れ始める瞬間を丁寧に積み上げていた。
伊佐美の弔い行脚とマルの日常回帰——法の外で揺れる良心
伊佐美は、飯室の「一生苦しめ」という言葉に縛られ、被害者宅を一軒ずつ訪ね、遺影に手を合わせ続ける。
それは警察でも裁判でもない、“私的な贖罪”だった。
一方のマルは、事件がなかったかのようにカラオケで浮かれ、日常へ戻ろうとする。
この対比は、良心を引き受けようとする者と、遮断しようとする者の違いをはっきりと示している。
同じ罪を背負っていても、向き合い方はまったく違う。そのズレが、四人の間に修復できない亀裂を作っていく。
パイセンと父・輪島宗十郎——“愛の空洞”に触れる決意
飯室から「お前は父親に愛されていない」と告げられたことで、パイセンの中に“空白”がはっきりと浮かび上がる。顔も知らない父・輪島宗十郎。その存在は、金と権力で事件をもみ消す闇の象徴だった。
パイセンは菜摘を訪ね、輪島の情報を集め始める。
輪島が息子のためではなく、自分の体面のために動いていた可能性。
そして、菜摘自身が抱える復讐の動機——正義と私怨が絡み合い、物語はさらに不穏な方向へ進んでいく。
恋にも決着——蓮子とトビオ、抑えきれない衝動
連絡が途絶えていたトビオを案じ続けた蓮子と、病院を出たトビオは再会する。
言葉よりも先に、感情が一致した瞬間、二人は関係を持つ。
市橋の想いを知ったうえでの行為。
それは“恋の決着”であると同時に、罪の上塗りでもあった。
第7話のベッドシーンは、直接的な描写を避けながらも、切実さと後ろめたさを同時に映し出している。
裏面で進むもうひとつの決定——今宵の妊娠発覚
この“恋の決着”の裏で、今宵の妊娠が明らかになる。
妊娠検査薬の陽性反応が示され、父親は誰なのかという不穏な問いが投げかけられる。
今宵自身は伊佐美の子だと考えているが、時系列の揺らぎが物語に新たな緊張を生む。ここから先、罪は個人の問題ではなく、次の世代へも影を落とし始める。
終盤の配置——罪悪感は消えないまま、物語は次章へ
“新しい俺”を演じても、罪悪感は静かに反芻を続ける。トビオが手にした幸福は、痛みを和らげる麻酔にすぎない。
伊佐美は弔いへ、マルは逃避へ、パイセンは父探しへ。
四人のベクトルは完全に分散した。
第7話は、次の章で友情・恋・家族のすべてに“ツケ”が回ってくることを、はっきりと示して終わる。
ドラマ「僕たちがやりました(僕やり)」7話の感想&考察

第7話は、「救いのふりをした逃避」を3層で描いた回だと思う。
①トビオの“新しい俺”、②伊佐美の弔い行脚、③蓮子との“恋の決着”。
どれもが即効性の鎮痛剤だが、根の痛み(罪)は消せない。そこがとても丁寧だった。
“幸せになってトントン”という自己正当化の危険
屋上からの生還直後に掲げたトビオのスローガンは、語感の柔らかさとは裏腹に、相手の痛みを自分の都合で割り勘にする発想だ。
しかも彼は、その“幸せ”を友情の背中押し(市橋)と恋の成就(蓮子)の両方で取りに行ってしまう。
応援すると言いながら自分が先に抱く。この自己矛盾が、のちの“より大きい痛み”へ跳ね返ることを、視聴者は予感せずにいられない。
第7話で「恋の決着」が強く印象に残るのは、単なる恋愛イベントではなく、倫理のねじれが最も可視化された瞬間だったからだ。
飯室の言葉がもたらしたもの——罪の“可視化”
被害者10人の写真を前に放たれた飯室の一言、「どれだけ忘れようとしても、幸せの瞬間にこそ思い出す」。
これは説教ではなく、罪悪感の“タイマー”を彼らの内側に埋め込む行為だった。
以降のトビオの“明るさ”は、その不快なカチカチ音をかき消すためのボリューム上げに見える。
忘れたふりをすればするほど、音は大きくなる。この言葉が物語に残した傷は、捜査線が動かなくなったあとも、確実に登場人物たちを追い続けている。
“弔い”と“日常”——伊佐美とマルが示す二極
伊佐美の遺族巡りは、法的な責任とは別に、心の均衡を取り戻したいという衝動だ。罪と向き合うことで、なんとか自分を保とうとしている。
一方のマルは、事件などなかったかのように日常へ戻ろうとする。ただ、その明るさはどこか空洞音を伴っていて、見ていて不安になる。
同じ罪に対する相反する対処が並置されることで、「逃避の多様性」がくっきりと浮かび上がる。第7話の設計は、“社会的罰”が下らない状態で、人はどう折り合うかを、かなり冷酷に描いている。
輪島という“父の不在”が開く深淵
パイセンの“父探し”は、単なる身元確認ではない。「自分は愛された存在だったのか」という確認だ。
ここには、もみ消し=愛という誤読の危険が潜んでいる。
菜摘の復讐動機(両親の借金や保険金をめぐる闇)と重ねると、輪島の行動は「愛」ではなく「体面」によるものとして響きやすい。
血縁が与える救いを信じたいパイセンの眼差しに、視聴者はざらりとした不安を覚えるはずだ。
ラブシーンの“清潔さ”——演出が伝えるもの
話題になった蓮子×トビオのベッドシーンは、露骨な官能ではなく、合意・切実・年齢の脆さを置いていく演出だった。
蓮子が自ら服を脱ぎ、トビオが後ろから抱きしめる。
この構図で、カメラは彼らの幸福の密度と同時に、罪の濃度も確実に増やしていく。
心地よさこそが、罰を思い出させる。その逆説を、ラスト5分で描き切ったのがこの回だった。
“もう一つの決着”——今宵の妊娠が投げかける現実
エンディングの裏面で示される今宵の妊娠発覚は、青春群像に一気に生活の重量を叩き込む。
誰の子なのか。
どう生きるのか。
“犯した罪”と“生まれる命”という、まったく異なるスケールの重さが、次話以降に容赦なくのしかかってくる。
この要素を第7話で提示し、第8話で親(竹内力)との衝突を用意する構図は、連続ドラマとして非常に巧い波の作り方だ。
第7話の位置づけ——“逃げる若さ”から“選ぶ若さ”へ
トビオが掲げた「幸せになってトントン」は、逃げる若さの標語だ。だが、友情・恋・家族の線が一気に絡まり始めた今、彼は“選ばざるを得ない若さ”へと押し出される。
第7話は、手続き的な救い(身代わりの出頭)が用意されても、倫理的な救いは生まれないことを示した回だった。
そして最終盤に待つ「自首」「償い」という地平を、遠景としてはっきり浮かび上がらせた。
ドラマ『僕たちがやりました』の関連記事
次回以降の記事についてはこちら↓
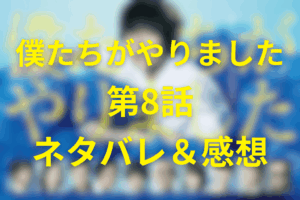
過去の記事についてはこちら↓
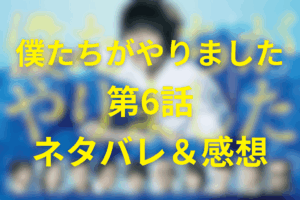
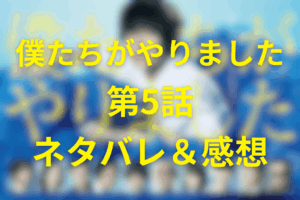
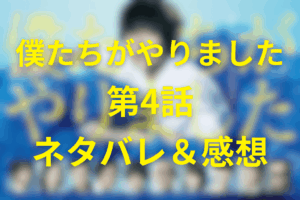
ドラマの豪華キャスト陣については以下記事を参照してくださいね。

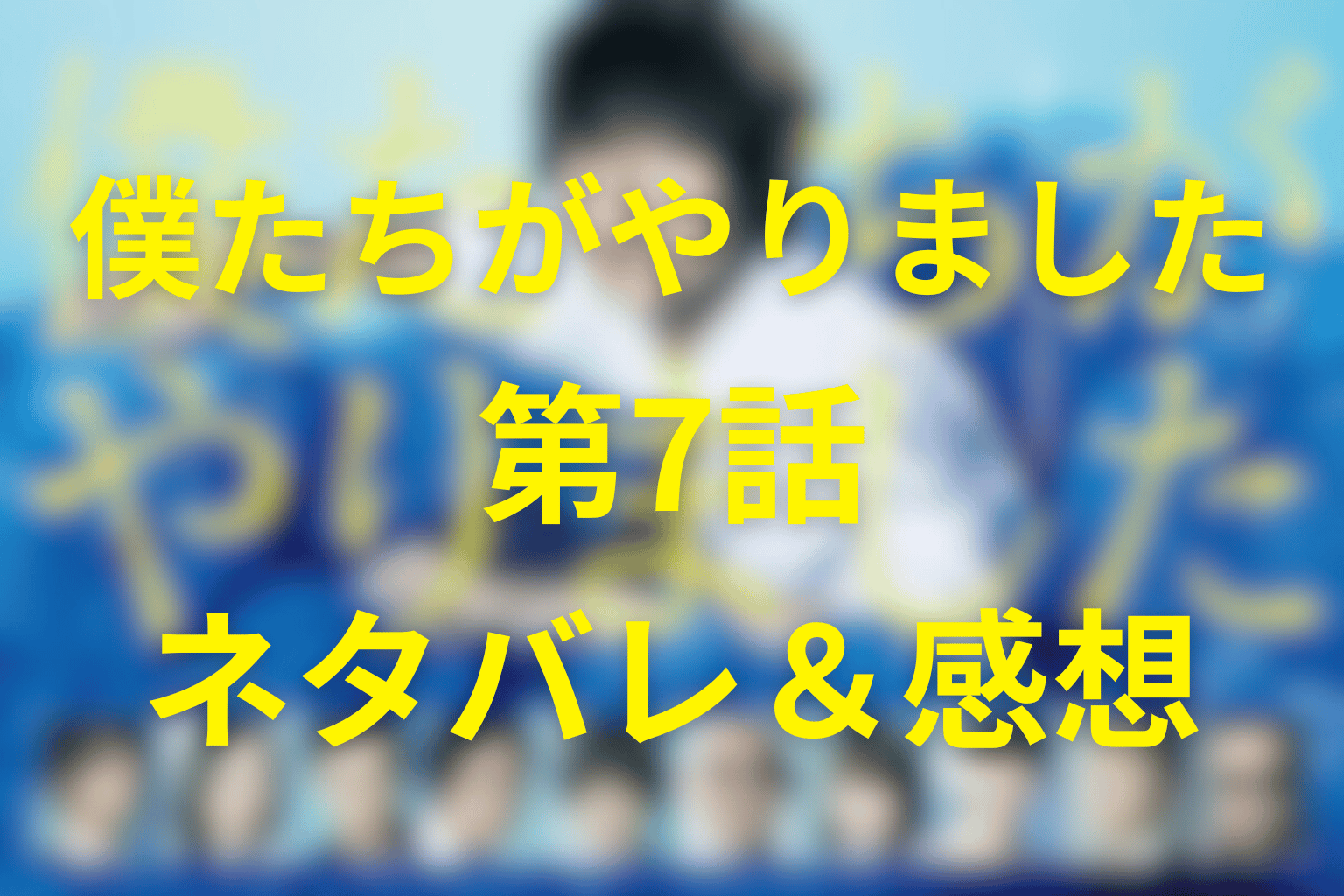
コメント