第3話でようやくチームとしての信頼が芽生えた水上署。
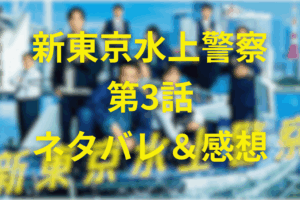
第4話はその絆を試す“命の現場”だ。
湾岸との縄張り争い、家族を巻き込んだシージャック、そして“海に奪われた息子”をめぐる誤解。
過去と現在の痛みが海で交錯し、碇が再び「海と向き合う勇気」を取り戻す——第4話は、アクションよりも“言葉の力”で海を救う、シリーズ屈指の名エピソードとなった。
ドラマ「新東京水上警察」4話のあらすじ&ネタバレ
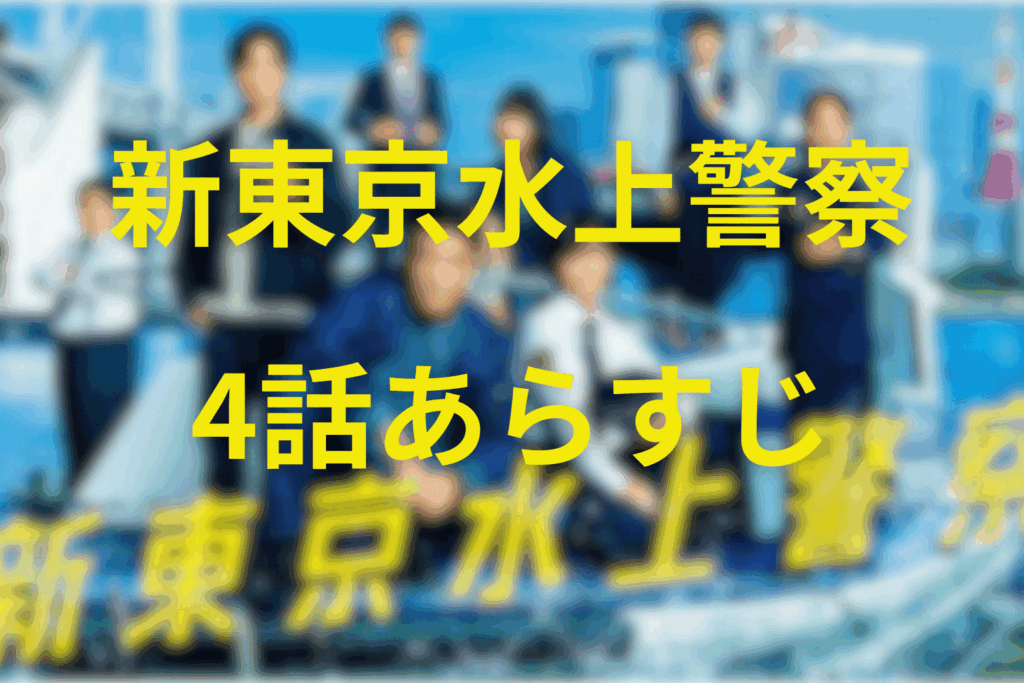
海でつながる二つの線――過去と現在の交錯
第4話のテーマは「海」。
ひとつは碇拓真(佐藤隆太)が抱える38年前の飛行機事故の記憶、もうひとつは潮風臨海公園沖で発生した“爆発ドローン”事件から連鎖するシージャック。
組織の縦割り、父と子の断絶、そして「海は死ぬ場所じゃない」というシリーズの命題が、濃密に絡み合う。過去と現在の痛みが“海”という舞台で結びつく一時間だった。
礼子が踏み込む“碇の傷”――38年前の飛行機事故
有馬礼子(山下美月)は、碇が38年前の飛行機事故で心に深い傷を負ったことを知り、その真相に迫ろうと動く。
事故当時に救助活動にあたった海技職員OB・大沢俊夫(小林隆)を訪ね、記録を確認する礼子。しかし、日下部峻(加藤シゲアキ)は「そこまでする必要はない」と制止する。
同僚としての距離と、チームとしての成果――その狭間で揺れる礼子。碇の過去は語られすぎないが、海を恐れながらも“海で働く”という矛盾を抱えた彼の原点として、後半の説得劇に深くつながっていく。
潮風臨海公園沖の“爆発ドローン”――管轄の壁と現場の誇り
潮風臨海公園沖でドローンが爆発。水上署が急行するも、先着していた湾岸署から「ここはうちの案件だ」と追い返される。
形式的には正しいが、海はつながっており、被害の拡大は時間の問題。
現場の理屈と組織の論理が真っ向から衝突る。
碇は引き下がらず、ドローンの発着が疑われる環境団体〈ヴァードアース〉の事務所を訪問。環境保護を訴える活動の裏で何が起きていたのかを探りながら、海上と空の動線を読み解いていく。
その姿勢に、彼の“現場の信念”がにじむ。
職場見学が一転――警備艇「あかつき」シージャック発生
一方、藤沢充(中尾明慶)は休日を利用し、妻・麻美(清水葉月)と息子・陸(加藤叶和)を署に招いて警備艇「あかつき」を見学させていた。
だがその平穏は一瞬で崩れる。ナイフを持った上原修也(小須田康人)が乗り込み、藤沢を刺傷。妻子と隊員を人質に船を出すシージャックが発生する。
湾岸署と水上署の“縄張り争い”で出遅れるなか、船は沖へ。現場が遠ざかるほど、警察の手足は縛られる。人命が海に晒される焦燥が、緊迫した空気を生んだ。
上原の動機――“息子の死”が生んだ誤解と悔恨
碇・日下部・礼子の捜査で、上原の動機が明らかになる。
彼の息子はSNSの炎上を苦に自殺したと父は信じていた。警察に訴えても動かず、世間への怒りを募らせていたのだ。
しかし真実は、息子が釣り針にかかった鳥を助けようとして海に落ちた事故死だった。息子の優しさを見抜けなかった父の後悔と自責が、社会への憎しみに転化し、暴走へとつながった。
“海が奪った”のではなく、“優しさが生んだ悲劇”——この反転こそ、碇の説得の核心になる。
モールス信号の光と無線の声――「海は死ぬ場所じゃない」
「あかつき」船内の防犯カメラ映像を見た礼子は、インジケーターの点滅にモールス信号を見出す。
藤沢は負傷しながらも応答し、犯人が起爆装置らしきものを所持している情報を送る。映像はすぐに破壊されるが、わずか数秒の“光の会話”が現場をつなぐ命綱となる。
碇は無線で上原と交信し、息子の真実を告げる。「海は息子を奪っていない。息子は誰かを救おうとした」。“海=死”というトラウマに縛られてきた碇が、“海=生”を語る側に立つ瞬間だった。上原は涙をこぼし、投降。事件は終息する。
ラストシーン――“海は死ぬ場所じゃない”という祈り
救出後、大沢と玉虫(椎名桔平)は静かに語り合う。
「海は死ぬ場所じゃない」——その言葉は、碇に向けられた祈りであり、彼自身がこれから海で生き続けるための灯台のように響く。
過去の痛みと現在の事件を“海”という一つの象徴でつなぎ、シリーズの主題を改めて刻み直した回だった。
ドラマ「新東京水上警察」4話の感想&考察
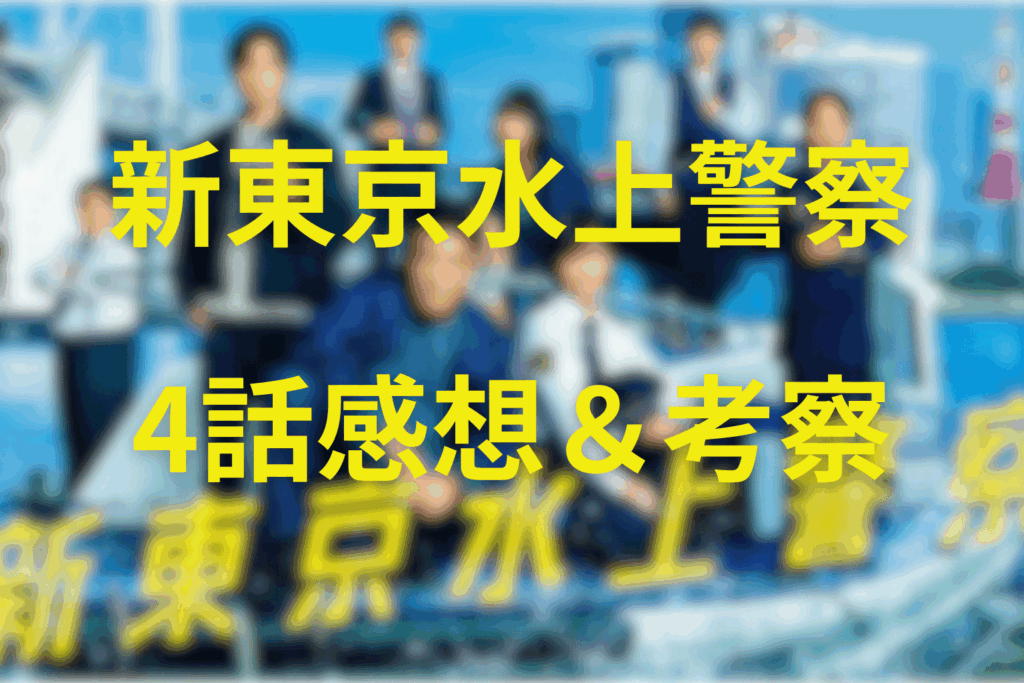
第4話は、海上アクションよりも“言葉”の力が際立つ回だった。
シージャックという緊急事態を描きながら、決着は銃火でも力でもなく、無線越しの説得によってつく。
「水上のプロが、技術と関係性で海を鎮める」——本作の根幹が最も鮮やかに浮かび上がった回だった。
以下、三つの軸で振り返る。
① テーマ:「海は死ぬ場所じゃない」——誰が、誰に言うのか
クライマックスの言葉「海は死ぬ場所じゃない」は、シリーズを貫く命題をもう一段深く掘り下げた。
それを口にするのは、かつて“海=死”の記憶に縛られていた碇(佐藤隆太)だ。
他者(上原)の喪失に触れることで、自分の傷をも癒やすように語る碇の説得は、“論破”ではなく“自己再生の手続き”として描かれる。
法的には重罪人である上原に、父としての悔恨と優しさを重ねて寄り添う——その語りの温度が、シリーズ全体の倫理を決定づけた。第4話は、碇が“海を語る資格を取り戻す”物語でもあった。
② 構成:縦割りの壁→現場の工夫→家族の船——三段構成の妙
ストーリーは、「爆発ドローン事件→湾岸署との管轄争い→環境団体ヴァードアース」という社会派の横軸と、
「職場見学→刺傷→シージャック」というヒューマンな縦軸を同時に走らせ、最後に“無線”で収束させる。
鍵となるのは、監視カメラの点滅をモールス信号として読み取るというアナログな発想だ。
ハイテク犯罪(ドローン)で始まった回を、ローテクの“知恵”で終わらせる構成は見事。礼子(山下美月)が気づき、藤沢(中尾明慶)が応じる。
“それぞれの持ち場で最善を尽くす”ことが、縦割りの壁すら越える力になる——その寓話性が胸に残った。
③ キャラクター:藤沢の「父としての臨界」と、礼子の“踏み込み”
藤沢にとって職場見学は、父としての誇りを息子に見せる時間だった。
それが一転、家族を守る戦場となる。
負傷しながらも、礼子のモールスに応じて外部へ情報を送る判断は、刑事としての矜持と父性の融合だった。中尾明慶の“痛みの呼吸”が緊張のリズムを支え、碇へのバトンを自然に渡す構成も秀逸。
一方で礼子は、日下部(加藤シゲアキ)の制止を振り切り、碇の過去に踏み込んだ。
その越境が、モールスという“他者への想像力”を開く契機になった。礼子の成長は操船技術ではなく、人へのアクセスの成熟として描かれており、チームドラマとしての厚みを生んでいる。
④ 父と子の反転——怒りの誤配が示す社会像
上原の犯行動機は、息子の“自殺”という誤解から始まった。
だが真実は、釣り針にかかった鳥を助けようとして海に落ちた事故死。世間の無関心とSNSの炎上が、父の怒りを外に向けさせたが、実際は“息子の優しさ”を見抜けなかった自責の裏返しだった。
碇はその痛みを受け止め、「海は命を奪ったのではない、優しさが引き起こした不幸だ」と語る。
犯罪を憎むより、人を理解する方向に舵を切る——この柔らかな倫理観こそ、水上署ドラマの核だ。
⑤ “もう一歩”の余白とシリーズの方向性
事件解決がやや早く感じたのは確かだが、無線説得の説得力を補うエピソード(上原の回想や湾岸署との連携描写)がもう少しあれば、クライマックスの厚みはさらに増しただろう。
それでも、海と陸の連動、船上アクションの緊迫感、隊員の役割分担は丁寧に描かれ、水上警察という舞台の独自性がしっかり立っている。
碇のトラウマを“個の痛み”に閉じず、“海で生きる人々の倫理”へと拡張した本話は、シリーズの大きな転換点。
次回は礼子や細野(山口紗弥加)に焦点が移る予兆もあり、チーム劇としての深化に期待が高まる。
新東京水上警察の関連記事
新東京水上警察の最終話までのネタバレはこちら↓
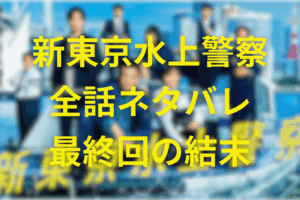
新東京水上警察の原作についてはこちら↓
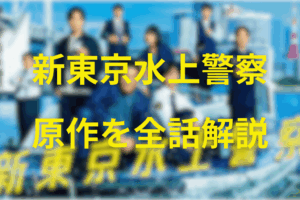
3話についてはこちら↓
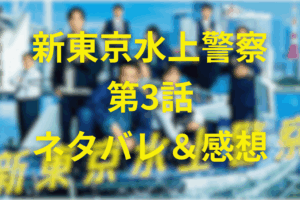
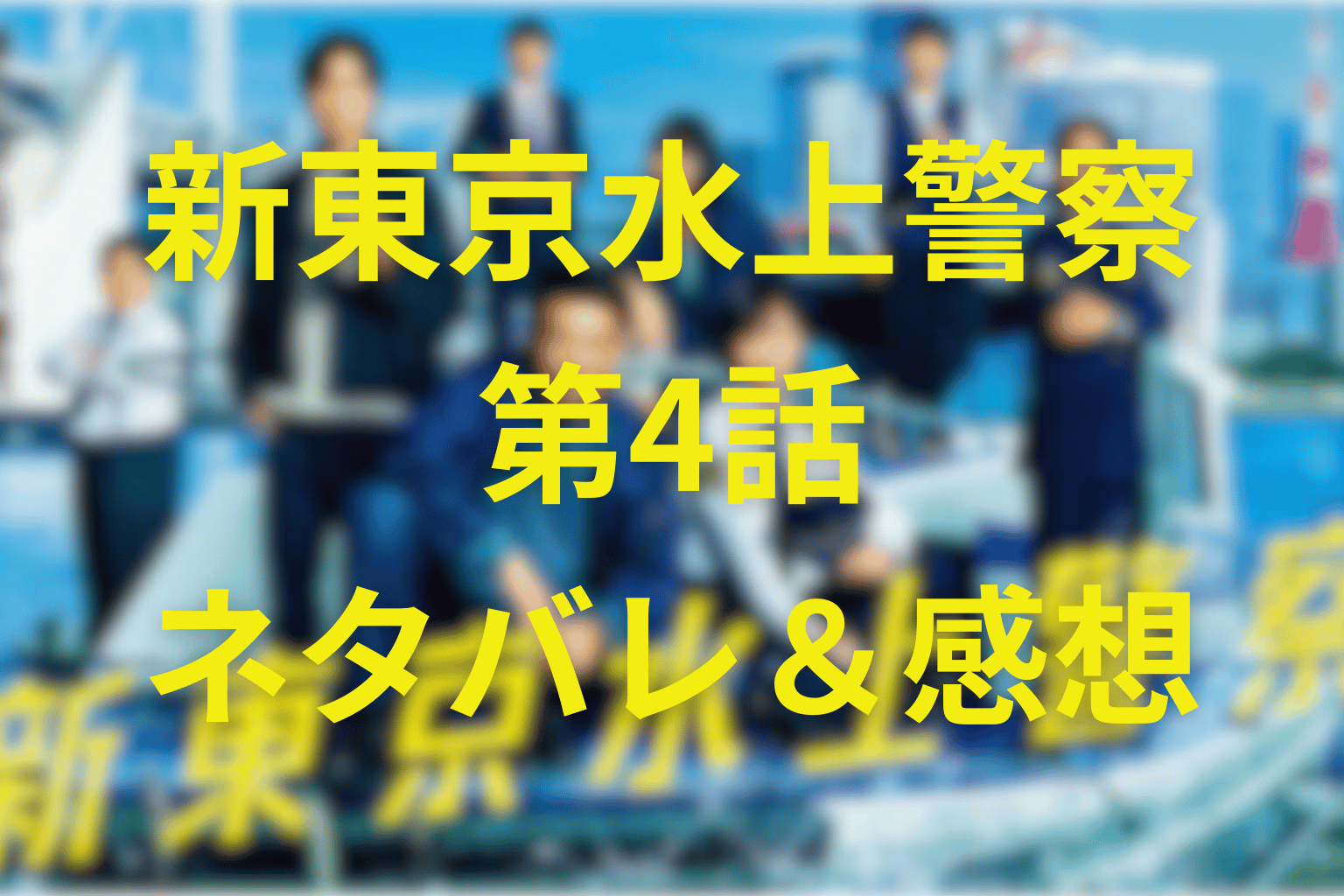
コメント