マチルダ失踪の謎を追う三人にとって、第3話は「過去を掘れば答えに近づける」という希望が、そう簡単ではないと突きつけられる回です。
新たな目撃証言が示す現実と、生活に追われる現在がぶつかり合い、三人の温度は少しずつずれていく。
事件を知りたい気持ちと、今を壊せない現実。その間で揺れる時間が、静かに積み重なっていきます。
※本記事は「ラムネモンキー」第3話のネタバレを含みます。
ドラマ「ラムネモンキー」3話のあらすじ&ネタバレ
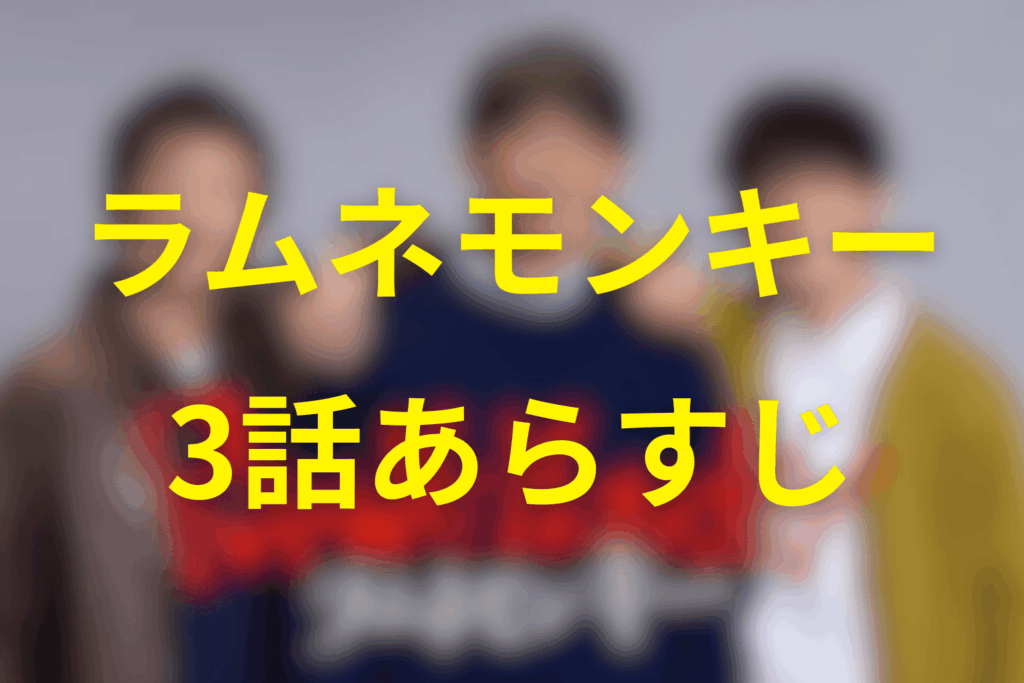
第3話は、マチルダ失踪をめぐる“目撃証言”がひとつ増える一方で、三人の時間が容赦なく現在へ引き戻される回でした。
雄太たちは「過去の答え合わせ」を急ぎたいのに、肇は“今の生活”を守るだけで精一杯。だからこそ、同じ出来事を見ていても、三人の温度が噛み合わない瞬間が何度も訪れます。
そもそも三人が追いかけているのは「事件」だけではありません。
映画部の顧問だったマチルダ(宮下未散)がなぜ消えたのか、その“最後の夜”を知りたい。そして何より、当時言えなかった言葉を、当時のままの気持ちで届けたい。第3話は、そういう個人的な願いが、現実の壁に何度もぶつかる回です。
今回の新情報は、大葉灯里の証言でした。
悲鳴の夜、マチルダの近くに男がいたこと、男が灯里に気づいて立ち去ったこと。この2点が明確になったことで、三人は「誰かがそこにいた」現実から逃げられなくなります。
さらに後半では、肇の脳裏に“チェーンソーの光景”が蘇ります。
体育教師・江藤(通称ジェイソン)がマチルダをチェーンソーで殺したかのような記憶に、肇自身が呑まれていく。第3話は、事件の手がかりと同じくらい、肇の精神が削られていく過程が濃い回です。
ここからは、第3話の流れを場面ごとに整理していきます。
目撃証言:灯里が見た「悲鳴の夜」
三人は、中学時代の同級生・大葉灯里に会い、あの夜の話を聞きます。
灯里が語ったのは、帰宅中に女性の悲鳴が聞こえて、思わず振り向いたこと。そして、その先でマチルダがうずくまっていたことでした。
灯里の証言が刺さるのは、その内容が「派手じゃない」からです。
大事件みたいな派手な出来事ではなく、ほんの数秒の視界の切り取り。でも、その数秒が、人生を丸ごと変えることがある。灯里が語る“数秒”は、まさにそれでした。
その瞬間の灯里にとって、目の前の光景は理解が追いつかなかったはずです。
悲鳴、うずくまるマチルダ、動けない自分。そこに“何が起きたのか”より先に、“怖い”が来る。灯里の証言は、まずその温度を連れてきます。
ここまでなら「転んだ?」「ケガ?」で済む話にも見えます。
でも灯里は、マチルダのすぐ近くに“男がいた”ことをはっきり覚えていました。しかも、その男は灯里に気づいた途端、足早に立ち去っていったという。
灯里が見た男は、マチルダを助けようとしたわけでもなく、救急車を呼ぶ様子もない。
それどころか、目撃者の存在に気づいた瞬間に離れていく。目撃証言としてはシンプルなのに、「やましさ」を想像させる動きが、強烈に残ります。
三人は当然、灯里に“男の手がかり”を求めます。
服装、背格好、歩き方、声――覚えている限りでいいから教えてほしい。けれど灯里が確実に言えるのは、「そこに男がいた」「逃げるように去った」という骨組みだけで、細部は霧の中にある。
その霧が逆にリアルでした。
30年以上前の夜のことを、証拠もなく説明しろと言われても、無理な部分はある。だから三人は、灯里の言葉を“確定情報”として抱えながら、別のピースを探すしかなくなります。
この証言で、三人は初めて「自分たちの記憶」ではなく「第三者の目」を得ます。
雄太の記憶や、噂話や、当時の印象だけではなく、“実際に見た人”の言葉が入った。だからこそ、空気が急に硬くなる。
雄太も紀介も、聞けば聞くほど顔が固くなっていきます。
肇も同じはずなのに、肇だけはどこか“話を聞きながら別の場所を見ている”ような瞬間がある。のちに出てくるチェーンソーの記憶を思うと、この時点から肇の中では別の線が引かれ始めていたのかもしれません。
鶴見巡査に伝えるも…進まない捜査と空気の重さ
三人は、その証言を鶴見巡査へ共有します。
ただ、鶴見はその場で「よし動く」とはならず、困惑したまま言葉を探しているように見えました。
目撃証言が増えたからといって、すぐ事件として動けるわけではない。当時の記憶は曖昧になりやすいし、証拠もない。捜査の重さと、三人の焦り。その温度差が、この場面の空気をしんどくしています。
雄太は、いま目の前に出た言葉を取りこぼしたくない。
灯里が勇気を出して話してくれたのに、それが「困ったな」で終わるのは納得できない。雄太の苛立ちは、事件に対する怒りというより、時間に対する怒りに近い。
紀介は、言葉数が多いタイプではありません。
けれどマチルダの話題になると、沈黙の中に重みが増す。彼が何を抱えているのかは語られきらないのに、“抱えている”ことだけが伝わる。このシリーズらしい描き方です。
そして肇は、うなずきながらも、頭の片隅が別の計算をしている。次の支払い、次の仕事、次の連絡。過去を掘るほど現在が崩れる危険があるのに、過去を掘らないと自分が壊れる危険もある。肇はその二択に挟まれていきます。
三人にとって、この“進まなさ”は痛いです。
警察が動かないなら自分たちで――という単純な話ではなく、動かない現実が「マチルダの不在」を何度も突きつけるから。捜査が進まない時間の中で、マチルダの不在だけが何度も濃くなる。
鶴見がはっきり答えを出せないからこそ、三人は“自分たちで確かめる”方向へ傾いていきます。
第3話は「捜査が進む」気持ちよさより、「当事者が抱えたまま動く」疲労を積み上げる回でした。
肇の現在:仕事ゼロ、借金、そして企画書の迷路
ここから肇パートがぐっと濃くなります。
肇は映画監督でありながら仕事がなく、借金を抱えている。さらに、かつてのツテを頼っても相手にされず、焦りだけが積もっていきます。
肇が“ツテ”に連絡を取る姿は、見ていて苦しい。連絡先があること自体は救いなのに、連絡先があるせいで「頼ってしまう」。頼ってしまうから、「断られる痛み」もちゃんと受け取ってしまう。肇はそのループにいます。
肇は何度も、自分の肩書きを口にします。
映画監督だ、と。けれど肩書きは“名刺の文字”でしかなく、名刺の文字だけでは誰も助けてくれない。肇の会話が空回りするほど、肩書きの軽さが浮き彫りになります。
断られた理由が、才能の有無ではないのもキツい。
単純に「今は余裕がない」「君を助けるメリットがない」「面倒に巻き込まれたくない」。社会はたぶんそういう理由で人を見捨てる。肇の状況は、そういう“現実の鈍い刃”を映します。
肇がしがみつくのは“企画書”でした。
流行要素を盛り込んだ企画書でなんとか仕事につなげようと必死になる。ここは第3話の一番痛いところで、肇は「好きな映画」より「売れる映画」に寄せようとしている自分に気づいている。
「好き」と「売れる」のあいだを行ったり来たりするほど、肇の足元は不安定になる。
それでも肇は止まれない。止まったら終わるから。企画書の文字を積み上げる行為が、今の肇にとっては呼吸みたいなものになっていきます。
ただ、企画書を作っている瞬間だけは、肇の目が死なない。
文字にして、組み立てて、誰かに伝えるために整える。その作業は、少年時代に脚本を書いていた自分と地続きです。だからこそ、肇はやめられない。
そんな肇は自分が出前の配達員を届けている場面で、業界を離れて一般企業に就職した男性(山下)と、その家族の姿を目にします。“幸せそうに暮らしている他人”という、いちばん比較したくないものを見てしまった肇は、言葉にならない落ち込みを抱えます。
この落ち込みがあるからこそ、後半の肇は危うい。
事件の調査どころではないはずなのに、事件の調査にすがってしまう。過去に戻ることで今を忘れられる――そんな危険な逃げ道が、肇の中にできていきます。
白馬のカフェで蘇る記憶:映研が始まった日
肇の現実が苦しくなるほど、回想パートの眩しさが効いてきます。白馬が働くカフェ(ガンダーラ)で、三人は映画を撮った経緯を思い出す。
回想では、ビデオカメラを手に入れた肇が映画部を作り、脚本まで書いたことが語られます。
作品はカンフー映画『ドランクモンキー酔拳』。タイトルからして勢いがあるし、肇の中ではもう完成しているタイプの夢です。
肇は脚本を手に、雄太と紀介へ“夢”を説明します。
ここは肇の少年っぽさが出る場面で、「これ、絶対おもしろいから!」と胸を張れるタイプの熱量。今の肇が失いかけているものが、回想の肇には丸ごとある。
雄太と紀介が気乗りしないのもリアルでした。
中学生って、やりたい気持ちがあっても「本気だと思われるのが恥ずかしい」って壁にぶつかる。肇はその壁を突き抜けられる側で、だからこそ孤独にもなりやすい。
ここで登場するマチルダの存在感が、やっぱり強い。
先生なのに“先生っぽい正しさ”とは別の場所に立っていて、三人の背中を押すやり方が大胆です。回想では、その大胆さが三人の背中を強く押したことが描かれます。
マチルダの指示:映画を作ること、役名で呼び合うこと
顧問のマチルダは、映画を作ることを三人に命じます。
さらに、お互いを役名の「ユン」「チェン」「キンポー」と呼び合うことまで指示する。
この“役名で呼ぶ”ルールが、ただの遊びじゃないのがポイントです。
名前で呼ぶと、どうしても学校の立場や関係性がついてくる。けれど役名で呼べば、いったん同じ土俵に立てる。マチルダは、その一歩を三人に踏ませます。
マチルダは、ただ「やりなさい」と言うだけじゃない。
やる気が揃わない三人に、具体的なルールを与えることで“やらざるを得ない空気”を作る。強引なのに、どこか愛がある。だから三人も、反発しきれない。
だから三人は、役名で呼ぶたびに少しだけ大人になる。
照れながらでも、ふざけながらでも、呼んだ瞬間だけ“映画を作る側”の顔になる。中学生にとっては、そのスイッチがすごく大きい。
このルールは、現在の三人にも残ります。51歳になっても、ユン・チェン・キンポーと呼び合うことで、当時の空気がよみがえる。第3話は、呼び名ひとつで人は過去へ戻れると教えてくれる回でもありました。
その日から三人はカンフー漬けに:青春の練習と、笑いの裏側
マチルダの号令で、三人はカンフー映画に打ち込み始めます。
動きを覚え、型を揃え、何度も同じシーンを繰り返す。映画づくりの入り口が“身体”から始まるのが、いかにも中学生らしい。
練習は単純で、だからこそ積み上がっていく。
最初はバラバラだった動きが、少しずつ揃っていく。息が合った瞬間だけ、三人の顔がぱっと明るくなる。その笑いは、後から思い出すほど眩しいやつです。
その一方で、三人の“はしゃぎ”は、周囲の大人にとっては理解しがたい。
学校という場所は、基本的に「同じであること」を求める。そこからはみ出す表現は、すぐに“問題行動”に見えてしまう。三人はその圧を、少しずつ浴びていきます。
そして第3話は、ついにタイトルの意味が具体的に見える場面へ繋がります。
三人が公園でカンフーの練習をしていると、「中学生が酒を飲んでいる」という通報が入り、江藤にこっぴどく叱られてしまう。
当事者としては笑えないし、第三者目線だと少し笑ってしまう“誤解”です。
肇たちは「ドランクモンキー(酔拳)」を撮ろうとしているだけで、実際に酒を飲んでいるわけではない。けれど、言葉と見た目だけで判断されると、説明は届かない。
この誤解が、映画づくりの進み方まで変えていきます。
「酒」そのものがダメなら、どうする? そこで肇たちがひねり出したのが、“酒に酔って戦う”のではなく、“ラムネでパワーアップする酔拳”という別案。
ラムネで酔拳って、発想はバカみたいで、でも中学生の創作って本来こういうものです。
外からはくだらなく見える。でも本人たちには切実で、真剣で、世界で一番おもしろい。だから「ドランク」ではなく「ラムネ」モンキー――ここでタイトルが回収されます。
“ジェイソン”江藤:規律の人が持ち込んだ恐怖
三人の前に立ちはだかるのが、体育教師・江藤です。
規律を重んじ、体罰も辞さない。生徒たちから「ジェイソン」と呼ばれる存在で、とりわけ口が達者な肇を目の敵にしていた。
江藤の存在は、回想パートの空気を一瞬で変えます。
それまで三人が見ていたのは、映画の世界であり、友情の世界であり、青春の世界。でも江藤が来ると、そこに「教師と生徒」「規則と違反」という現実がドンと割り込む。
江藤は秩序のために生徒を“正す”という理屈を持っている。
その理屈が厄介なのは、正しさを盾にして暴力を正当化できてしまうところです。ジェイソンという呼び名がつくまでに、生徒側の恐怖が積み上がっていたのも納得でした。
さらに回想では、三人が江藤に目をつけられ、台本をゴミ箱に捨てられた過去も描かれます。“作品”そのものを否定される経験が、三人、とくに肇の中に長く残っていたことがわかる場面でした。
江藤は「学校」という仕組みそのものを語るタイプの教師でもあります。
生徒に夢を見させない、勘違いさせない、従わせる。正しいかどうかより、従わせることが目的に見える。この“思想”が、後の肇の人生にも引っかかり続けます。
チェーンソーの記憶:肇の中で「事件」が決定づけられる
現在に戻り、肇はとある家の庭先に置かれたチェーンソーを目にします。
ただの道具のはずなのに、その瞬間だけ、肇の世界は過去に飲み込まれていく。
肇の脳裏に蘇ったのは、江藤がマチルダをチェーンソーで殺した光景でした。
これは「誰かの証言」ではなく「肇の記憶」として出てくるのがポイントです。肇自身が、記憶の確度を測れないまま、恐怖だけが真実みたいに膨らんでいく。
そして肇は、江藤がかつて言い放った言葉を思い出します。
「学校は凡人が自分を天才だと思い込まないための場所だ」という趣旨の一言。その言葉に、人生につまずいた肇は、ふと「正しかったのかもしれない」と呟いてしまう。
この瞬間が苦しいのは、肇の中で“怒り”と“納得”が同居するからです。江藤は許せない。でも、江藤の言葉が今の自分を説明してしまう気もする。だから肇は、過去と現在のどちらにも居場所がなくなっていきます。
肇が江藤を“疑い”として見るのも、ある意味自然です。
過去の暴力の象徴であり、夢を折った相手であり、さらにチェーンソーの記憶まである。肇にとって江藤は、事件の容疑者というより、人生の原因そのものになりかける。
白馬の調査:江藤の「現在地」が判明する
肇の一言を聞いた白馬は、淡々と、しかし決定的な材料を三人に渡します。
江藤の娘の電話番号、そして江藤が体罰で解雇された記事。これらは白馬が、元クラスメートの石井洋子から聞いた情報をもとに掴んだものでした。
白馬は、三人の“回想”をただ聞いているだけの人物ではありません。
三人が言い淀むところを補い、足りないピースを探しに行く。事件が止まりそうになるたびに、白馬の行動が一段ギアを上げる。第3話で白馬の役割は明確に広がりました。
記事の存在は、三人にとってもショックです。
ジェイソンは今も教師として学校にいるのではなく、体罰で解雇された過去がある。つまり“あの頃のやり方”を社会が許さなかったという事実が、今さら突きつけられる。
電話番号を頼りに、三人は江藤が入院している病院へ向かいます。
電話をかけるだけでも心臓が重いのに、病院へ行くとなればなおさら。けれど三人は行く。そこまでしないと、マチルダに辿り着けないと理解してしまったからです。
老いた江藤との対面:震える手に自ら叩かれにいく
病院で対面した江藤は、死の淵をさまよっており、当時のジェイソンのような怖い面影は薄れていました。
それでも三人を見るなり、「言った通り、ろくな大人にならなかった」と叱るように吐き捨てる。弱っていても、言葉の棘だけは残っています。
この言葉は、雄太にも紀介にも刺さるはずです。
“ろくな大人”の定義なんてないのに、江藤は平気で断言する。昔からそうだった、という事実が、たった一言で伝わる。病室の空気が一気に凍るのがわかります。
肇は反発し、言い返します。
けれど江藤は、当時と同じように再び手を上げようとする。ここで三人の心が動きます。江藤の手は震えていて、強くは叩けない。それでも、その動作が“あの頃”を一瞬で呼び戻す。
三人は、江藤の震える手に、自ら頬を寄せていきます。
叩かれるために近づく。普通ならあり得ない行動なのに、三人にとってはそれが“決着”に近い。雄太も紀介も続き、複雑な思いに胸を震わせる。
ビンタの瞬間、三人は同時に中学生に戻ります。
「怖い」「悔しい」「でも終わらせたい」。言語化できない感情が、頬の痛みと一緒にぶつかってくる。三人が泣くのは、弱いからじゃなく、時間が重すぎるからです。
肇は涙を浮かべながら、江藤に向けて乱暴な言葉を投げます。
要するに「簡単にくたばるな」という叱咤です。憎しみだけじゃなく、怒りだけじゃなく、過去を生きた者同士の感情が混ざり合う。第3話の山場は、派手さより、この混ざり方の生々しさで刺してきます。
エピローグ:江藤の死、娘の言葉、そして「酒臭い男」
その数日後、江藤は死亡します。
そして娘からは、「最後に父を先生に戻してくれてありがとうございます」という感謝の言葉が届く。三人があの場で受けたビンタが、“教師としての江藤”を最後に成立させてしまった、という事実が重い。
さらに娘は、重要な情報も伝えます。
実は当時、マチルダにはつきまとっていた男がいたということ。その男は“酒臭い男”だったということ。第3話は、この新しい輪郭を提示して終わります。
灯里の証言で「男がいた」ことが見えた。
肇の記憶で「江藤の影」が濃くなった。そこに「酒臭い男」という情報が足されることで、三人の調査はまた別の方向へ開いていきます。
そして肇は、病院での対面を経て、再び企画書を書き始めます。
人生のスタート地点に戻るように、もう一度“作る”方向へ体を向ける。事件の手がかりと同時に、肇の再起の芽も残して、第3話は幕を閉じました。
第3話のネタバレ整理:ここまでで分かったこと、残ったこと
第3話の終盤まで見終えると、「分かったこと」と「まだ分からないこと」がはっきり二層に分かれます。
分かったのは、悲鳴の夜にマチルダのそばに男がいたこと、そして男が目撃者(灯里)に気づいて立ち去ったこと。ここはもう、三人の“想像”ではなく、証言として土台ができた。
一方で、肇の中で暴れ出したのが「江藤=チェーンソー」という記憶でした。
それが現実なのか、記憶の歪みなのかは、この回では決着しない。けれど、肇がその記憶に支配されることで、三人が江藤に接触し、江藤の“現在地”まで辿り着いたのは大きい。
江藤に関しては、体罰で解雇された過去が明確になります。
つまり、江藤の暴力は学校の中だけで黙認され続けたわけではなく、どこかの時点で社会的に裁かれている。ただ、その裁きがマチルダの不在とどう繋がるのかは、まだ見えません。
そしてラストで投げ込まれた新情報が、「酒臭い男」の存在でした。
マチルダがつきまとわれていた。しかも“酒臭い”という具体的な特徴がある。灯里の証言に出てきた男と同一人物なのか、それとも別なのか――ここが次回以降の最大の焦点になります。
第3話では白馬の動きが物語を大きく前へ進めます。
三人の回想が「語り」だけで終わりそうになるたびに、白馬が調べ、繋げ、具体的な情報に落とす。江藤の娘の電話番号と解雇記事を持ち込んだことで、調査は一段現実に降りてきました。
同時に、タイトルの意味が「ドランクモンキー」から「ラムネモンキー」に変わった過去として描かれたのも大きい。
公園での練習が通報され、江藤に叱られたことで、三人の創作は“社会の目”と初めて正面衝突します。その衝突が、やがてマチルダ失踪の夜へどう繋がっていくのか――不穏さを残しながら、第3話は次へ進みます。
ドラマ「ラムネモンキー」3話の伏線

第3話は、「マチルダ失踪」の謎そのものが一気に解決する回ではありません。
ただ、目撃証言が増え、疑われた人物に“会えてしまい”、さらに新しい人物像(酒臭い男)が浮かび上がって、事件の輪郭が少しだけ固くなりました。
ここでは、3話で提示された伏線を「回収されたもの」「未回収で残ったもの」に分けつつ、今後どこに繋がりそうかを整理します。
1) 事件の核心に近づく伏線
- 灯里の証言:マチルダの近くに“男”がいた
- これまでの手がかりは、3人の記憶と噂が中心でした。3話で初めて「第三者の目撃」が入ったことで、事件が“思い出話”から“現実の出来事”に切り替わります。
- 男が灯里に気づいて立ち去った、という動きが重要です。「助ける/通報する」方向に向かわない=何かを隠している可能性が上がります。
- 新証言:「酒臭い男」に付きまとわれていた
- ラストで追加された一言ですが、情報の質が一段具体的です。“酒臭い”は、職業・生活圏・行動パターンを絞れる特徴になり得ます。
- 灯里が見た男=酒臭い男なのか、別人なのか。ここが一致すれば容疑の線が太くなり、別人なら「現場にいた男」と「ストーカー」2ルートで謎が増えます。
- 鶴見巡査の反応が鈍い
- 目撃証言を持ち込んでも動けないのは、単に証拠が薄いからか、別の事情があるのか。“困惑”が強調されるほど、後半で「実は当時の資料が…」などの展開に繋がりやすい配置です。
- 事件が再び公になることを嫌がっている人物がいるなら、警察側にも波が来ます。
- 西野白馬が“情報のハブ”になりつつある
- カフェという場所柄、街の記憶・噂・人間関係が集まりやすい。白馬がいることで、3人の調査は「同級生ルート」以外にも枝が伸びます。
- 若い世代が事件を“今の問題”として見直す立ち位置にも見えるので、後半で彼女が鍵を拾う可能性は高めです。
2) 「ジェイソン=江藤」ルートの伏線
- チェーンソーのフラッシュバック
- 肇の中では、江藤がマチルダをチェーンソーで殺した光景が“記憶”として浮上します。ここは、真相の提示ではなく「記憶の信頼性」を揺さぶる装置に見えました。
- 重要なのは、“見た”ではなく“思い出した”である点。観客も肇本人も、その記憶が事実かどうか確信できない。だから次の行動(江藤に会いに行く)が生まれます。
- 江藤との対面、そして死
- 3人が病院で江藤と対面できたことで、「疑惑の中心人物」から直接言葉を引き出せるはずでした。しかし、江藤はほどなく亡くなる。ここでルートが物理的に遮断されます。
- 遮断されたからこそ、“江藤は本当に何も知らないのか”が逆に疑問になる。もし江藤が鍵を握っていたなら、真相は娘や周辺人物の証言・当時の記録で補うしかありません。
- 江藤の言葉「勘違いするな」
- 物語上は暴力教師の最悪さを示すセリフですが、3人の人生に深く刺さる形で残ります。ここは事件の伏線というより、3人の“再起動”の伏線です。
- 肇が「流行の企画書」から「書きたいもの」へ戻るきっかけになったなら、今後“作ること”が事件解明の手段にもなるかもしれません。
3) 小道具・物が持つ伏線
- 編集されていない撮影テープの存在
- 3話で示された「当時の映画が編集されていない/テープだけ残っている」という情報は強い。もし、完成作ではカットされたはずの“余白”に、マチルダや不審者、当時の空気が映り込んでいたら…証言より強い証拠になります。
- さらに、過去回で「特定の番号のテープが見当たらない」という要素がある以上、**“欠けた1本”**が事件の核心を握っている可能性もあります。
- ラムネ=タイトル回収であり、暗号でもある
- 「ドランク(酒)」が誤解を生み、結果として“ラムネ”に置き換わる。この流れは、事件の核である「酒臭い男」と不気味に重なります。
- つまり、3人にとっては無害な炭酸(ラムネ)なのに、事件側には“酒”がまとわりつく。同じ“匂い/炭酸”の方向に見えて、全く違う世界が並走している構図です。
- チェーンソー
- 現場にあった道具に反応して記憶が暴走した点は、今後も“物”がスイッチになる伏線。次回以降、写真・テープ・当時の小物などで、3人の記憶がさらに更新される可能性があります。
4) セリフと沈黙の伏線
- 灯里が“細部”を語り切れない
- 「男がいた」ことは強いが、顔や特徴が曖昧。この曖昧さは、のちに別の証言が出たときに“矛盾”として機能します。似た背格好の人物が複数いた場合、記憶は簡単にすり替わるからです。
- 3人が江藤に「マチルダのこと」を真正面から聞けていない
- 病室の場面は、事件追及より“感情の決着”が優先されます。だからこそ、肝心の質問が置き去りになっている。ここが次の回で効いてくるはずです。
- “呼び名”が作る結束
- マチルダが「ユン/チェン/キンポー」と呼び合うことを命じたのは、単なるノリではなく“同じ物語を共有させる儀式”に見えます。
- 今の3人が立ち上がれるかどうかは、この呼び名に戻れるか=自分たちの物語を取り戻せるかにかかっていそうです。
5) ここまでで回収されたポイント
- 「ジェイソン」が誰か
中学時代に恐れられた体育教師・江藤が、3人の中で“ジェイソン”として固定されていたことが明確に回収されました。 - タイトル「ラムネモンキー」への繋がり
“酒”と誤解されたことが、ラムネへ置き換える発想に繋がる流れは、作品タイトルの意味を3話でしっかり立ち上げました。
6) 次回以降の注目点
- 人骨が本当にマチルダなのか、それとも別人なのか。
- 酒臭い男の正体は「学校の外」の人物か?それとも“身内”か?
- 灯里の証言と、娘の証言が同一人物を指すのか。
- 撮影テープは「事件当日」やその直前を映していないか。欠けたテープがあるなら、それは誰が持っているのか。
- 鶴見巡査が抱える“動けない理由”は何か。
- 肇の記憶は、事実の再生なのか、恐怖の創作なのか。
3話は、疑惑を一度「江藤」に集約してから、死で閉じ、最後に「酒臭い男」で再びルートを開き直しました。
この“閉じて開く”構造が綺麗だった分、次回はテープや証言の追加で、いよいよ事件が「個人のトラウマ」から「社会の記録」へ移っていくと見ています。
ドラマ「ラムネモンキー」3話の感想&考察

第3話は、事件の手がかりが増えた回であると同時に、3人の「人生の止まり方」が一番くっきり見えた回でした。
人骨の正体やマチルダの行方はまだ遠い。だけど、目の前に“ジェイソン”が現れたことで、彼らは過去から逃げる言い訳をひとつ失った気がします。
暴力教師を「懐かしい」で片づけない、という怖さ
江藤という人物は、昭和的な体育教師の記号として出しているだけじゃなく、作品のテーマを刺しにくる存在でした。
規律を盾にして手を上げる人間って、当時は「そういうもんだ」と見過ごされやすかった。だから視聴者側も、うっかり“懐かしさ”で受け取ってしまう危険がある。
でも3話はそこを甘やかさない。
江藤は老いて弱っても、過去の自分を反省しているわけではなく、最後まで「叩いて鍛えるのが教育」だと言い切る。ここが苦いし、リアルでした。
そして厄介なのが、3人がその江藤を「憎い」だけで切り捨てられないところ。
怒りと、嫌悪と、どこかで“先生だった人”への情が同居していて、その混ざり方が大人の顔つきになっていました。
病室の「ビンタ」は、赦しじゃなくて“主導権の回収”に見えた
個人的に一番刺さったのは、3人が自分から頬を差し出す場面です。
殴られることを拒むのではなく、殴ることを許すわけでもない。あれは「過去のルール」に従うふりをしながら、主導権だけ奪い返す動きに見えました。
中学生のころの彼らは、江藤の暴力から逃げられなかった。
でも51歳の今は、距離を詰めるのも引くのも自分で決められる。だから“ビンタを受ける”という選択が、屈服ではなく儀式になる。
江藤は最後に「勘違いするな」と吐き捨てるけれど、あの言葉さえ、もう昔ほど彼らを縛れていない。
涙が出るのは、江藤が可哀想だからというより、「自分たちがここまで生き延びた」ことへの確認だった気がします。
「映画を作る」記憶は、3人にとっての救命胴衣
3話の中盤で描かれる、映画研究部の始まりは、事件とは別軸のようでいて実は核心でした。
マチルダが3人に命じたのは、映画を作ることと、役名で呼び合うこと。これって、ただの青春のノリではなく、“現実を生き抜くための別名”を与える行為に見えます。
現実のユン・チェン・キンポーは、それぞれ大人になって挫折している。
ユンは社会的な信用を失い、チェンは仕事が切れて借金に追われ、キンポーは家や体の問題を抱えていそうで、どこか生気が薄い。三者三様なのに、共通しているのは「自分が主役の人生から降ろされた感覚」です。
だからこそ、1988年の“撮る側”の記憶が効く。
誰かに評価されなくても、画角を決め、セリフを書き、動きを作る。世界をこちらの手で編集する。あの感覚だけが、3人に残っている救命胴衣なんだと思いました。
灯里のバレエが示した「失われた未来」の扱い方
灯里の証言は、事件の手がかりとして重要でした。
でもそれ以上に、彼女が“かつての夢”と今も一緒に生きていることが印象的です。
店内で一人こっそり踊るバレエは、技術的には昔ほどではないのかもしれない。
それでも彼女は、踊れる場所を自分で作って、スポットライトも自分で点ける。あの姿は、3人が探している“青春回収”の完成形にも見えました。
「夢に負けた」ではなく、「別の形で抱え直した」。
この作品がミステリーをやりながら、最終的に描きたいのは、たぶんこっちの再生なんだろうなと感じます。
チェーンソーの記憶が示すのは、真相より「記憶の危うさ」
ミステリーとして面白いのは、肇のフラッシュバックが“確定情報”じゃない点です。
チェーンソーという強烈なイメージは、真実の映像というより、恐怖が作り出した編集にも見える。
人は、都合よく忘れるだけじゃなく、都合よく“盛って”思い出すこともある。
特に少年時代の記憶は、映画や噂や後悔と混ざって、いつの間にか別物になる。だからこそ、この作品は「思い出した=真実」にならないのが巧いです。
江藤が亡くなったことで、肇の記憶は検証しにくくなりました。
ここから先は、テープや他者の証言で“編集前の素材”を集めるしかない。過去を掘る、という行為がストーリーの構造と一致していて、気持ちがいい。
「ドランク」と「酒臭い男」──タイトル周りの仕掛けが効いてきた
3話で気持ちよく繋がったのが、タイトルの感触です。
“ドランク”が誤解を招き、“ラムネ”に言い換える。笑える小ネタなのに、ラストの「酒臭い男」というワードが入った瞬間、背中が少し冷えました。
3人にとっての“酒”は濡れ衣で、無害な炭酸に置き換えられる。
でもマチルダの周りには、実際に酒の匂いをまとった男がいたかもしれない。この対比が、事件と青春を一本の線に束ねていきます。
それと同時に、「人は見たいものだけ見て、匂いの強い情報だけ信じる」というテーマも透ける。
マチルダにまつわる噂、3人の改ざんされた記憶、警察の鈍い反応。全部が“イメージ”の暴力です。
白馬という“編集者”の存在が、ドラマ全体のテンポを整えている
西野白馬は、3人にとっての協力者というより、物語の「編集者」みたいな役割を担っているように感じます。
同世代の会話だけだと、どうしても“わかる人にはわかる懐古”に寄りがちですが、白馬がいることで説明が必要になり、3人も過去を言語化せざるを得なくなる。
それに、白馬は感情で飲み込まれない。
事件も青春も、いったんフラットに並べて「最初から思い出すしかない」と背中を押す。あの冷静さがあるから、ドラマがノスタルジーに溺れず、ミステリーの線を保てている気がします。
江藤の娘の電話は、“過去が終わった後に残るもの”を示した
江藤本人から真相を聞けないまま、娘が「酒臭い男」の話を持ってくる。ここ、かなり残酷で、でも現実的でした。
加害側が何も語らず死ぬこともあるし、残された家族が後から断片を拾っていくこともある。
そして娘は、江藤の教育観を肯定しません。
だからこそ、あの電話は“免罪符”じゃない。むしろ「まだ終わっていない」と告げる合図です。江藤が死んだことで、暴力の時代は一区切りついたように見える。でも事件はまだ生きている、という二段構えが効いていました。
ここからの考察:真犯人の輪郭は「学校の外」へ広がる
3話時点で、江藤が犯人だと断定するのは早いと思っています。
疑われた人物が“弱って死ぬ”のは、物語のセオリー的にも「真相を別に隠している」配置になりやすいからです。
むしろ気になるのは、灯里の証言に出てきた男の行動と、酒臭い男の存在がどう繋がるか。
学校の人間関係の外側――町の事情や大人の利害、当時の空気――そっちに真犯人がいるなら、マチルダの失踪は「個人的な恨み」より大きな事件だった可能性が出てきます。
そして、ここで効いてくるのが“撮影テープ”です。
完成作品ではなく、編集されていない素材。そこに真実が映っているなら、事件解決は「思い出す」ではなく「見返す」で進む。記憶改ざんミステリーとして、筋が通ります。
第3話は、暴力教師の話で終わったようで、実は“次に掘るべき場所”をはっきり示した回でした。
笑える青春の形を残しながら、同時に「過去は美談じゃない」と突きつけてくる。だからこそ、この作品の考察は楽しいし、少しだけ怖いです。
ドラマ「ラムネモンキー」の関連記事
全話ネタバレについてはこちら↓
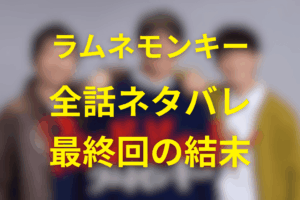
ラムネモンキーの過去の話についてはこちら↓
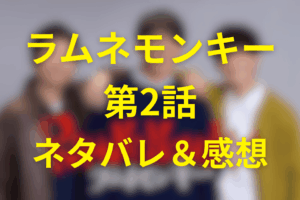
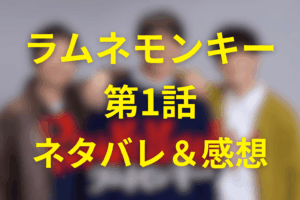
マチルダについてはこちら↓
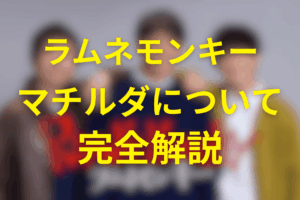
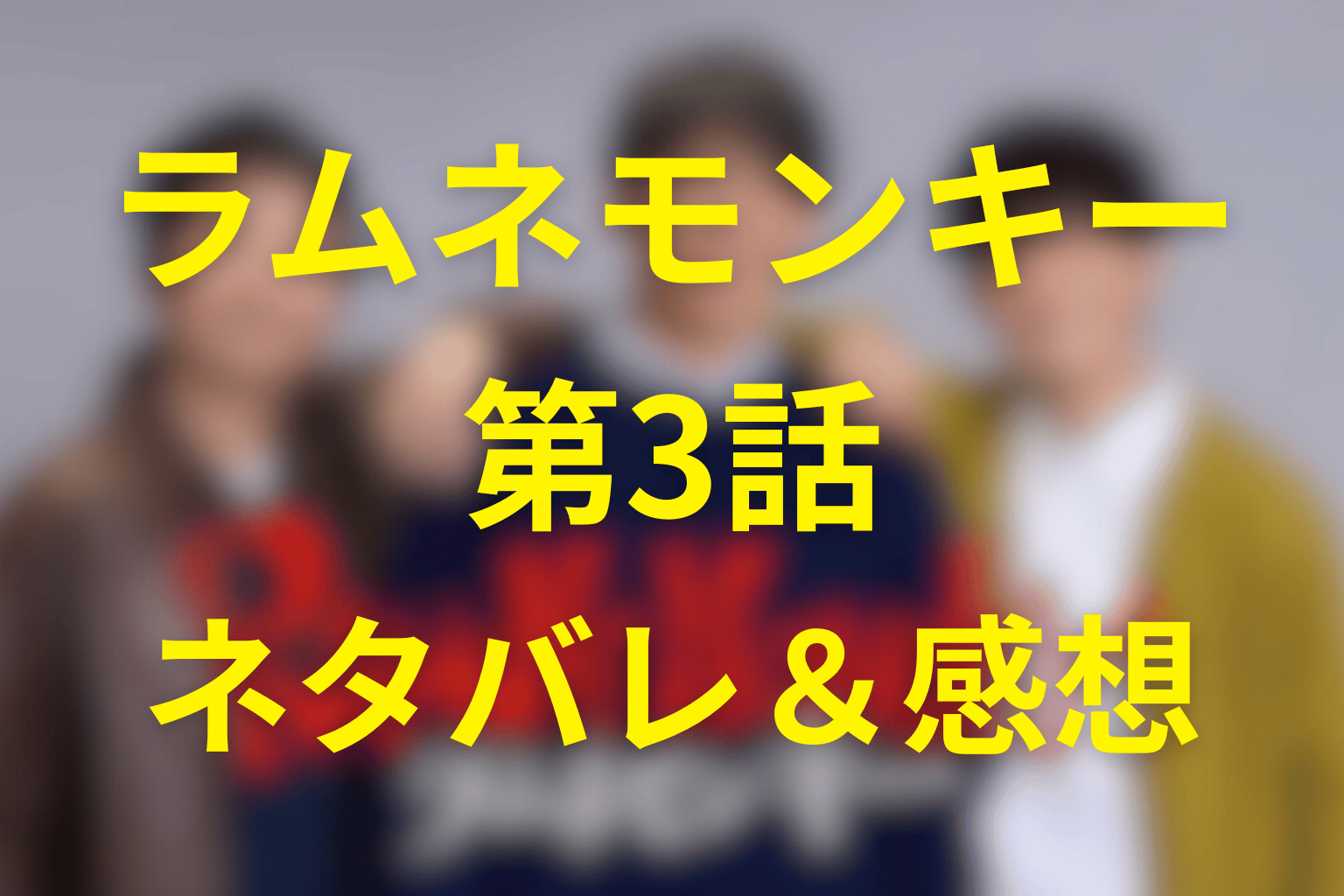
コメント