『アンナチュラル』を見終えたあと、多くの視聴者が口にするのが「犯人より宍戸が一番嫌だった」という感想です。
連続殺人の実行犯ではない。直接ナイフを振るうこともない。なのに、物語の空気をここまで腐らせ、UDIという組織を内側から崩壊寸前まで追い込んだ存在――それが宍戸理一でした。
宍戸は“黒幕”ではありません。しかし同時に、「無害な脇役」でもない。
彼がやっていたのは、事件を解決することではなく、事件を終わらせないこと。真実を暴くのではなく、真実を“売れる形”に加工し、社会に流通させ続けることでした。
この記事では、
・宍戸理一の正体と立ち位置
・なぜUDIにとって最大級に危険な存在だったのか
・高瀬文人との関係性の本質
・最終回で宍戸が迎えた結末と、その意味
を整理しながら、『アンナチュラル』が宍戸というキャラクターを通して描いた「情報の暴力」と「見る側の責任」まで踏み込んで解説していきます。
犯人考察とは違う角度で、後味の悪さの正体を言語化したい人に向けた記事です。
まず結論|宍戸理一は何者で、何をした人物か
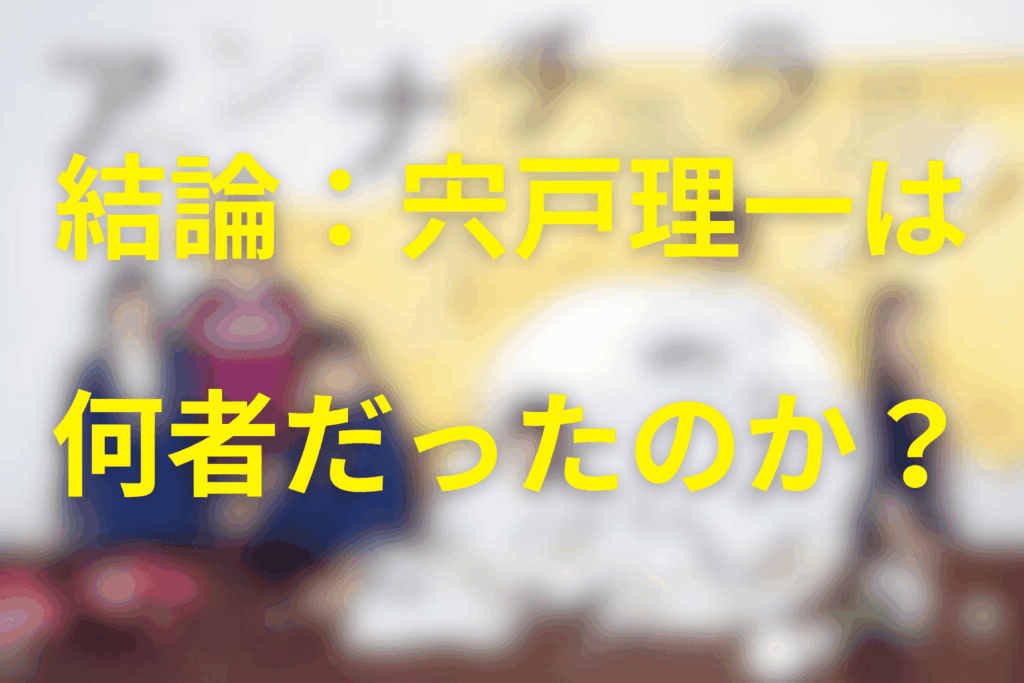
宍戸理一(ししど・りいち)を一言で言うなら、「事件を解決する側」ではなく「事件を“ネタ”として流通させる側」の人間です。
肩書きはフリー記者。
汚い手を使ってでも情報をあぶり出し、週刊誌に売って食っている人物として、作中でもはっきり描かれています。
この記事で分かることは、大きく4つです。
- 宍戸の正体:どんな仕事をして、どんな価値観で動く人物か
- 宍戸の目的:なぜ“真相”ではなく“出し方”に執着するのか
- UDIとの関係:なぜ宍戸はUDIにとって危険な存在なのか
- 最終回での役割:宍戸が物語終盤で何を壊し、何を決定づけたのか
最初に押さえておくべき重要点として、宍戸は黒幕(=連続殺人の実行犯)ではありません。
ただし、だから安全な存在でもない。
むしろ厄介なのは、宍戸が「暴力」ではなく情報を武器にして人を追い詰めるタイプだからです。
事件の当事者ではない顔をしながら、当事者の人生を簡単に壊せる。
そこが宍戸という人物のいちばん怖いところです。
しかも物語終盤では、UDIの情報が週刊誌に売られていた事実が明らかになり、組織そのものが崩壊しかけます。
つまり宍戸は、犯人ではないのに「事件の行方」と「UDIの存続」の両方に影響を与える存在として、終盤の中心に食い込んでくる人物なのです。
宍戸理一とは?職業・立ち位置・登場タイミング
宍戸を理解するには、キャラの善悪で見るより先に、職業と立ち位置を整理した方が早いです。
彼はUDIの人間でも警察でもない。けれど、事件の外側から“解釈の主導権”を奪いに来る。この外部性こそが、宍戸という存在を手強くしています。
宍戸の肩書き(フリー記者)と「週刊誌サイド」の役割
宍戸の肩書きはフリー記者。週刊誌にネタを売って生計を立てている人物です。
しかも「汚い手を使ってでもネタをあぶり出す」ことが前提。つまり、正攻法の取材をするタイプではありません。
フリー記者という立場は、強みと弱さが表裏一体です。
強み
- どこにも属さないため、動きが速い
- 組織の許可や稟議を待たず、最短距離で情報に近づける
弱さ
- どこにも属さないため、倫理の担保が薄い
- 責任の所在が曖昧になりやすく、やり方が逸脱しやすい
週刊誌サイドの役割も同じです。必ずしも嘘を書くわけではない。でも、真実を“救う形”で出すとは限らない。
売れる形に編集し、刺激が強い順に並べ、読者の感情が燃えやすい角度から出す。
宍戸は、そのゲームに完全に慣れた人間です。
宍戸が“怖い”理由(正義でも悪でもない)
宍戸が怖いのは、分かりやすい悪人だからではありません。
むしろ逆で、宍戸には大義がない。
正義のために動かない。
悪のために動くわけでもない。
彼が優先するのは、基本的にこの2つです。
- ネタの強さ(どれだけ人を動かせるか/数字になるか)
- 出し方(いつ、誰に、どの順番で見せれば最大化するか)
ここが重要で、「真実」を目的にすると、真実が出た瞬間に終わります。
でも「出し方」を目的にすると、真実を終わらせないことが利益になる。
だから宍戸は、事件を解決に近づけるより、事件を“燃え続ける形”に整える方向へ傾きやすい。
登場タイミングとしても、宍戸は序盤の事件解決を回す中心人物ではありません。
物語が縦軸(赤い金魚事件)へ寄っていくにつれて、存在感を増していくタイプです。
視聴者が「真相に近づきたい」と思った頃に現れ、真相そのものより世間の見え方を握ろうとする。
だから不快で、だから強い。
宍戸理一は味方か敵か?結論:敵に近い“外部の刃”
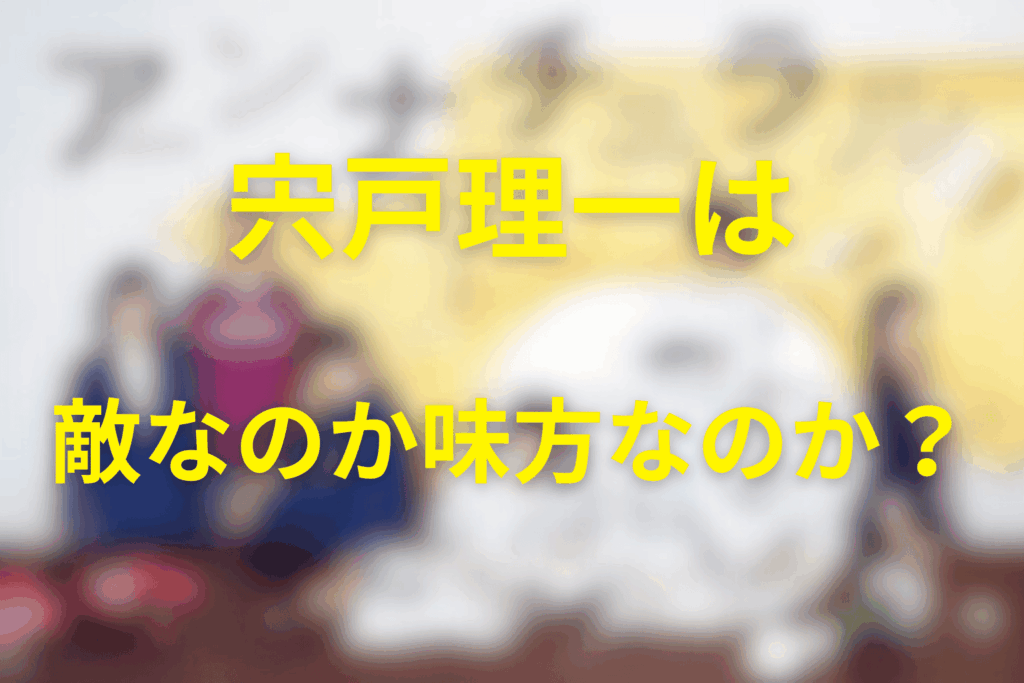
宍戸は、「情報を持っている」という意味では味方に見える瞬間があります。
でも結論としては、味方ではなく、敵に近い外部の刃です。
理由はシンプルで、宍戸の目的が「UDIを助ける」でも「遺族を救う」でもなく、自分が主導権を持つことだから。
宍戸がやることは「暴く」ではなく「商品化」
宍戸は“暴く記者”というより、“売れる形に整える編集者”に近い。
暴くこと自体には公共性があります。
でも宍戸の基準は、公共性より先に収益性が来る。
そしてこのタイプは、真実に近づくほど“次の燃料”が必要になる。
だから時に、真相解明よりも
「まだ確定していない」
「どっちとも言える」
という状態を好む。
宍戸の危険性は、まさにそこにあります。
宍戸が触ると何が壊れるか(遺族・捜査・UDI)
宍戸が触ると壊れるものは、大きく3つです。
① 遺族が壊れる(二次被害)
悲しみの中にいる人にとって、事件が“見出し”になった瞬間から地獄が始まることがある。
真相が出ても救われないのに、真相が出る前に晒されると、傷が増えるだけです。
② 捜査が壊れる(冤罪リスク)
確定していない情報が一人歩きすると、世論が先に“犯人像”を作ってしまう。
その空気に引っ張られれば、捜査は歪む。
③ UDIが壊れる(組織崩壊)
最終回で明らかになるのが、六郎がUDIの情報を週刊誌に流していた事実。
UDIは遺体・遺族・行政案件を扱う以上、情報管理の信用が命です。そこに穴が空けば、機関として終わる。
宍戸は、その穴を広げる存在です。
宍戸理一とUDIの関係は?六郎を通じて侵入した“外部”

UDIラボは、警察でもマスコミでもなく、死因究明のスペシャリストが集まる研究機関として描かれます。
だからこそ、外部の人間である宍戸が“正面から”入り込むのは難しい。
では、どう侵入したのか。答えはシンプルで、内部の人間(六郎)を経由するというやり方でした。
久部六郎との接触(情報ルートとしての利用)
六郎は、真面目で、若くて、まっすぐで、だからこそ危うい。宍戸のような海千山千のフリー記者にとって、六郎は“入り口”として都合が良すぎます。
六郎は善意で動くタイプです。
「役に立ちたい」「期待に応えたい」「評価されたい」――そういう感情が先に立つ。
宍戸はそこを見抜いて、最初から“対等な取引相手”としては扱っていません。
六郎が宍戸と接触し、最初は「うまくやれている」ように見える。
でも実際には、宍戸に泳がされ、情報を引き出され、やがて「UDIに潜り込んだスパイ状態」として縛られていく。
ここで重要なのは、
宍戸が六郎を動かしたのが「正しさ」ではなく、弱みと恐怖だったという点です。
六郎が引き返せなくなった理由も単純で、宍戸は“善悪”で人を縛らない。
「君がやったこと、もう戻れないよね?」という形で、逃げ道を塞ぐ。
最終回で、六郎がUDIの情報を週刊誌に売っていた事実が発覚し、組織が崩壊の危機に陥る。
この流れは、宍戸の侵入経路がどれほど致命的だったかを示しています。
神倉所長が恐れたもの=「情報漏洩」そのもの
神倉所長が恐れているのは、個々のミスや裏切りではありません。
彼が一番恐れているのは、UDIという機関が“信用を失って死ぬ”ことです。
UDIラボは、国や自治体の支援を受ける公益的な研究機関として設定され、死因究明のために、遺体・個人情報・捜査情報を扱います。
この手の機関は、一度でも情報管理を疑われると終わりです。次からは、遺族も、警察も、自治体も、「安心して預けられない場所」になる。
つまり、情報漏洩は単なる不祥事ではなく、存在理由そのものを吹き飛ばす致命傷。
だから最終回で「UDI崩壊の危機」という言葉が使われる。
それほどまでに、漏洩は重い。
【ネタバレ】宍戸理一と高瀬文人の関係は?

宍戸理一と高瀬文人の関係は、単純な「取材する側/される側」ではありません。もっと露骨に言えば、互いの欲が噛み合って成立した“利用し合い”の関係です。
宍戸はフリー記者として、汚い手を使ってでもネタをあぶり出し、週刊誌に売って生計を立てる人間。
つまり彼の仕事は「真実の追求」ではなく、真実(っぽいものも含む)を換金できる形に変換することに寄っています。
そして高瀬は、犯行を隠すだけでなく、“語られる形”に整えることまで含めて事件を完成させようとするタイプ。
二人が接続した時点で、「事件」は捜査の対象である前に、社会に流通する“物語”になってしまう。
ここが、最終盤でいちばんイヤなポイントです。
高瀬が“週刊誌に取材される”構造が生まれた理由
まず宍戸側の理由は明快で、独占できるネタが欲しいからです。
連続殺人の“縦軸”は、当たれば人生が変わる級の大ネタ。
しかも宍戸は組織の人間ではないため、倫理のブレーキより「取れたかどうか」が先に来る。
だから、ネタがあるなら近づくし、危険でも踏み込む。
一方の高瀬側も、単に「捕まりたくない」だけではありません。
むしろ高瀬は、出頭しても殺人を否定し、“妄想としての告白”という逃げ道を用意することで、
- 裁かれない
- でも世間には名前が出る
という、最悪に歪んだポジションを狙っていました。
実際、最終盤では高瀬の殺害告白が「妄想として語られたもの」という建付けで整理され、その内容が“本”として世に出る流れが描かれます。
ここで二人の利害が、完璧に一致します。
- 宍戸:独占ネタで 売れる/儲かる/名前が出る
- 高瀬:真相を曖昧にしながら 名を残す/見せびらかす
普通、犯罪者の告白は「自滅」です。でも宍戸という装置を挟むと、それが商品になる。
アンナチュラルが描いているのは、犯人の狂気だけじゃなく、狂気が流通してしまう社会の構造です。
宍戸が握っていたもの(証拠/情報/“出す順番”)
宍戸の強さは、スクープを掴んだことではありません。掴んだあとに、「いつ、どう出すか」を握っていたことです。
作中でも、宍戸は高瀬事件を「本」という形で社会へ流し、世論の空気を作っていきます。
しかもその中身は、“妄想”という建付け。真実と嘘の境界を、意図的にぼかす。
こうなると世間は、
- 真相を知ろうとする
より先に - 面白がり方を覚えてしまう
ここが、いちばん怖い。
さらに宍戸が恐ろしいのは、情報だけでなく、物証に近いものまで握っていた点です。
被害者の口に押し込まれていた「おさかなボール(赤い金魚の正体)」。
最終回で、宍戸は中堂系にそれを証拠として要求され、いったん差し出します。
しかし次の瞬間、酸で溶かして完全に破壊する。
つまり宍戸は、
- 出す/出さない
- 残す/消す
その両方を操作できる位置にいた。
ここまで来ると、宍戸が握っていたのは“情報”ではなく、事件のハンドルです。
出し方次第で、社会の空気は変わる。空気が変われば、捜査も裁判も、被害者遺族の暮らしも変わる。
宍戸は、その力を
「正義」ではなく
「商売」の道具として扱える人間だった。
だから、厄介なんです。
宍戸は高瀬の共犯か?→「直接の共犯」より「共犯関係」
結論として、宍戸は直接手を下す犯人ではありません。
でも、だから無関係でもない。
アンナチュラルが突きつけるのは、手を下さなくても、犯罪を成立させる側に回れるという現実です。
宍戸はスクープのために高瀬に近づき、殺人の情報を集め、拡散し、曖昧にし、結果として事件を“長生き”させた。
最終的に宍戸は、殺人幇助という形で裁かれます。
ここで重要なのは、“幇助”が軽い罪ではないこと。
高瀬にとって宍戸は、
- 犯行を記録し
- 拡散し
- 曖昧にし
- 物語として延命させる
ための外部装置でした。
宍戸にとって高瀬は、ネタを生み続ける供給源でした。
この相互依存は、ほとんど共犯関係です。
直接の殺人者でなくても、「世間を動かす構造」に入った瞬間、当事者になる。
宍戸理一というキャラクターは、その事実を一番分かりやすく、一番不快な形で体現した存在です。
だから彼は、黒幕ではないのに、物語の中で最も“後味の悪い人物”として残るんですよね。
高瀬についてはこちら↓
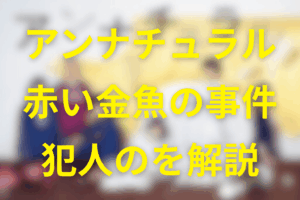
宍戸理一の最後はどうなる?(最終回の結末)

宍戸の結末は、単なる“成敗”ではありません。
情報を武器にしてきた人間が、最終的に情報の前で無力化されるという、強烈に皮肉の効いた終わり方です。事件の決着と同時に、宍戸という人物の「戦い方」そのものが通用しなくなっていきます。
中堂との対決|復讐の一線と、法の決着
最終回、中堂は宍戸がまだ別の証拠を隠していると睨み、宍戸のもとへ向かいます。注射を刺し、「解毒剤が欲しければ証拠を出せ」と迫るこの場面は、中堂が“法医学者”から“復讐者”へ踏み越えかける瞬間でもありました。
宍戸は証拠を差し出しますが、その直後、赤い金魚の痕を残したおさかなボールを酸につけ、証拠を完全に破壊します。
ここで明確になるのは、宍戸という存在が中堂を意図的に追い込み、相手に一線を越えさせようとするタイプの人間だということです。
この場面で決定的なのが、ミコトの制止です。「不条理に負けるな」「戦うなら法医学者として戦え」。彼女は宍戸を止めるのではなく、中堂を“法の側”へ引き戻します。
宍戸はここで、UDIの倫理と人間の弱さを試す装置として機能する。殴るのではなく、殴らせる。宍戸の厄介さは、まさにそこにあります。
宍戸の末路|何を失い、何が残ったのか
最終的に事件はDNAなどの決定的証拠によって収束し、高瀬が罪を語る流れの中で、宍戸も殺人幇助で逮捕されます。宍戸は自由を失い、立場を失い、週刊誌に売ってきた“ネタの力”も失う。
ここで皮肉なのは、宍戸の立ち位置の反転です。
彼はずっと「撮る側」「書く側」「流す側」でした。しかし最後は、「撮られる側」「書かれる側」「流される側」になる。
情報を支配していたつもりが、情報に支配される側へ落ちる。事件が終わった瞬間、宍戸が握っていた“出す順番”という価値は完全に消えていきます。
宍戸は消えても、宍戸的な存在は消えない
ただし、宍戸が排除されても、宍戸を生む構造は残ります。欲と数字が結びつく限り、第二、第三の宍戸は必ず現れる。
アンナチュラルが最後に残す苦さはここです。宍戸は「個人の悪」として処理されたようでいて、実際には社会の癖として残り続ける。だからこそ、彼は救われないまま、後味の悪い存在として記憶に残る。
この終わらせ方自体が、アンナチュラルという作品の倫理観そのものだと思います。
考察|アンナチュラルで宍戸はなぜ必要だったのか

宍戸理一って、視聴者からすると「出てくるだけで空気が濁る」タイプの、かなり嫌な存在です。でも僕は、あの不快感込みで“必要なキャラ”だったと思っています。
理由はシンプルで、宍戸がいることで『アンナチュラル』が描きたかった「社会の痛み」が、事件の外側にまで広がるからです。殺人犯だけを裁いて終わり、にはさせない。むしろ“終わらせない装置”として宍戸が機能しています。
宍戸は「メディアの暴力」を人格化した存在
宍戸は、汚い手を使ってでもネタをあぶり出し、週刊誌に売って生計を立てるフリー記者です。
つまり彼は、善悪以前に「ネタで食う」人間。ここが一番重要なポイントです。
ただ、宍戸を「悪いやつ一人」として片づけてしまうと、このドラマの狙いから外れてしまう。宍戸の不快さって、個人の性格というより、構造そのものの臭さなんですよね。
- 独占ネタに価値がつく(早い者勝ちのゲーム)
- 炎上や恐怖が数字になる(強い感情ほど拡散する)
- 誰かの不幸が“消費”される(需要がある限り供給が止まらない)
宍戸は、この歪んだ構造を人の顔を持った存在として置かれたキャラクターです。顔があるから嫌悪できる。嫌悪できるから、考えざるを得なくなる。
「誰か一人が悪い」のではなく、そういう人間が勝ちやすい仕組みが悪い。宍戸は、その仕組みの象徴です。
宍戸がいたから、UDIの倫理が際立つ
『アンナチュラル』の舞台であるUDIラボは、死因究明のスペシャリストが集まり、死者の事実を社会に返すための場所です。
要するに、UDIの仕事は話を盛ることではない。編集しない事実を積み上げ、死者の声を“証拠”として扱うこと。
一方、宍戸は真実を「売れる真実」に変換する側です。
事実をそのまま出すのではなく、物語性を強め、曖昧さを残し、読者の感情が最も動く形で流通させる。
この対比が、ものすごく残酷です。
- UDI:死者のために、事実をそのまま提示する
- 宍戸:生者の欲(数字・話題)のために、事実を加工して流す
しかも厄介なのは、宍戸のやり方が現実でも普通に起きているという点。
だからこそ、UDIが揺らぐ。鑑定書の改ざん圧力が出たとき、ミコトが迷うとき、中堂が一線を越えそうになるとき——「倫理を守ること」が、きれいごとではなく本気の戦いになる。宍戸がいるから、その戦いがはっきり見えるんです。
視聴者もまた「見出し」に加担し得る
宍戸を見て「最低だな」と思うのは簡単です。でも、このドラマが一段深いのは、見る側を安全圏に置かないところ。
象徴的なのが、第7話の「殺人実況生中継」です。
視聴者数が増えるほど事件が進む。見ているだけで、事件に“参加”してしまう構造。
これって、週刊誌と同じなんですよね。
読まれるから記事が出る。クリックされるから見出しが過激になる。拡散されるから、もっと刺激が必要になる。
宍戸を完全な怪物にしないことで、ドラマは視線をこちらに向けてきます。
「宍戸みたいな奴が悪い」で終わらせない。
宍戸が成立してしまう社会に、視聴者自身も片足突っ込んでいることを突きつけてくる。
だから宍戸は必要だった。
不快で、後味が悪くて、できれば見たくない存在だけど、彼がいないと『アンナチュラル』は「事件を解決するドラマ」で終わってしまう。
宍戸がいることで、この物語は社会の構造そのものを解剖するドラマになったんだと思います。
宍戸理一を演じるキャストは北村有起哉(俳優紹介)
宍戸理一を演じたのは、北村有起哉(きたむら ゆきや)さんです。
フリー記者・宍戸という役柄は、作品全体の空気を一段冷やす存在で、下手をすると“ただ嫌われるだけの悪役”になりかねないポジションでした。
でも北村さんの宍戸は、単なる悪役に収まらない。
嫌悪感があるのに目が離せない、かなり厄介なリアリティを持った人物として成立しています。
“嫌な役”って、薄くすると記号になるし、濃くすると漫画になる。
その中間で、現実にいそうな温度に着地させたのが、北村有起哉という俳優の強さだと思います。
プロフィール(簡潔)
北村有起哉さんの基本プロフィールは以下の通りです。
- 生年月日:1974年4月29日
- 出身地:東京都
- 身長:180cm
舞台・映画・ドラマを横断して活動してきた俳優で、「派手な主演」よりも「物語の空気を決定づける役」に強いタイプ。宍戸のような“場を腐らせる存在”を任せられるのは、キャリアの積み重ねがあってこそです。
演技の見どころ|宍戸の“嫌なリアルさ”を成立させた理由
宍戸の怖さは、暴力性ではありません。
ナイフも銃も持たない。怒鳴らない。理屈も通る。
それなのに、一緒にいると確実に消耗するタイプの人間です。
北村有起哉さんの演技は、この「消耗させる感じ」を徹底的に現実寄りで作ってきます。
- 言葉は丁寧なのに、目がまったく信用できない
- 一瞬だけ善意を装うが、距離の詰め方が異様に早い
- 相手の弱点を嗅ぎ取る速度がやたらと速い
この積み重ねによって、宍戸は「悪役」ではなく、
社会の中に普通に存在していそうな“厄介な大人”になります。
だから視聴者は、怒りより先に「うわ、こういう人いる…」という嫌な既視感を覚える。
怪物じゃない。
むしろ怪物じゃないからこそ怖い。
宍戸というキャラクターが、「連続殺人犯よりも不快な存在」として記憶に残るのは、北村さんが演技で“盛らなかった”からだと思います。
社会の一部として成立するギリギリのリアルさ。そこが、このキャスティングの一番の成功点でした。
よくある疑問Q&A(ネタバレあり)
宍戸理一は情報量が多く、立ち位置も曖昧に見えやすいキャラです。ここでは特に混乱しやすいポイントを、結論から整理します。
Q:宍戸は黒幕?
A:黒幕(=連続殺人の実行犯)は高瀬文人。宍戸は“共犯関係に近い立場”です。
連続殺人を実行したのは高瀬であり、宍戸は直接手を下してはいません。ただし宍戸は、証拠の隠蔽や情報操作に関与し、結果として犯罪を成立・長期化させる側に回っています。
そのため宍戸は「黒幕」ではないものの、最終的には殺人幇助という形で裁かれる存在です。
無関係な第三者ではなく、「犯罪を回す歯車」に組み込まれた人間だと捉えるのが一番近いと思います。
Q:六郎はなぜ宍戸側に取り込まれた?
A:最初は“仕事”、途中からは“脅しと罪悪感”で抜けられなくなった、が実態です。
六郎は最初から悪意を持って裏切ったわけではありません。取材協力という軽い感覚で関わり、気づいたときには個人情報や立場を握られ、引き返せなくなっていた。
宍戸の怖さは、正論や暴力ではなく、「最初の一歩を踏ませた後に逃げ道を塞ぐ」やり方にあります。善人ほど、この構造に弱い。
Q:宍戸が一番ヤバかったのはどの場面?
A:証拠(おさかなカラーボール)を“渡すふり”をしながら、完全に証拠隠滅した場面です。
宍戸は「証拠を持っている」という優位性だけでなく、「証拠を残すか消すか」を選べる位置にいました。
情報を握る人間が一番強いのは、事実を語れるときではなく、語らせないと決めたとき。この場面で、宍戸は完全にその顔を見せています。
Q:宍戸がいなくても事件は解決した?
A:最終的には解決した可能性は高い。ただし“壊れ方”が違ったはずです。
宍戸がいなければ、少なくとも以下は起きなかった可能性が高い。
- 六郎を起点とした情報漏洩とUDI崩壊の危機
- 「妄想としての告白」という形で世論が攪乱される展開
- 証拠隠滅を絡めた最終盤の極端な駆け引き
事件の結末そのものは同じでも、途中で壊れるもの(組織・信頼・倫理)は確実に違っていた。宍戸は“事件を解くため”ではなく、“事件が社会を壊すため”に必要だったキャラクターだと思います。
まとめ|宍戸理一という「外部の刃」が残したもの
宍戸理一を一文で定義するなら、「真相」ではなく「流通」を握ることで、事件を終わらせない外部の刃です。
彼がいたからこそ、UDIが守っているものがはっきりしました。
- 事実:死因をねじ曲げず、死者の声を証拠として扱うこと
- 倫理:勝つために嘘を書かないという“仕事の矜持”
- 仕事:社会に生かすための死因究明
宍戸の後味が悪いのは当然で、あれは欠点ではなく意図です。
あの嫌なリアルさが残る限り、『アンナチュラル』は現実に刺さり続ける。僕はそう思っています。
ドラマ「アンナチュラル」の関連記事
以下で全記事のネタバレについて解説しています。
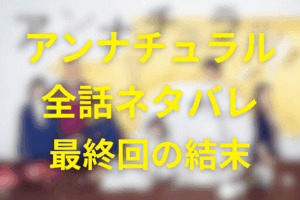
アンナチュラルに登場する人物はこちら↓
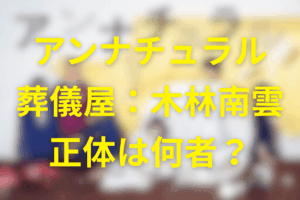
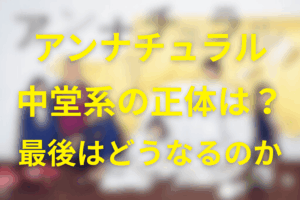
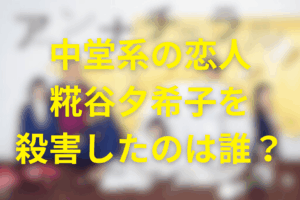
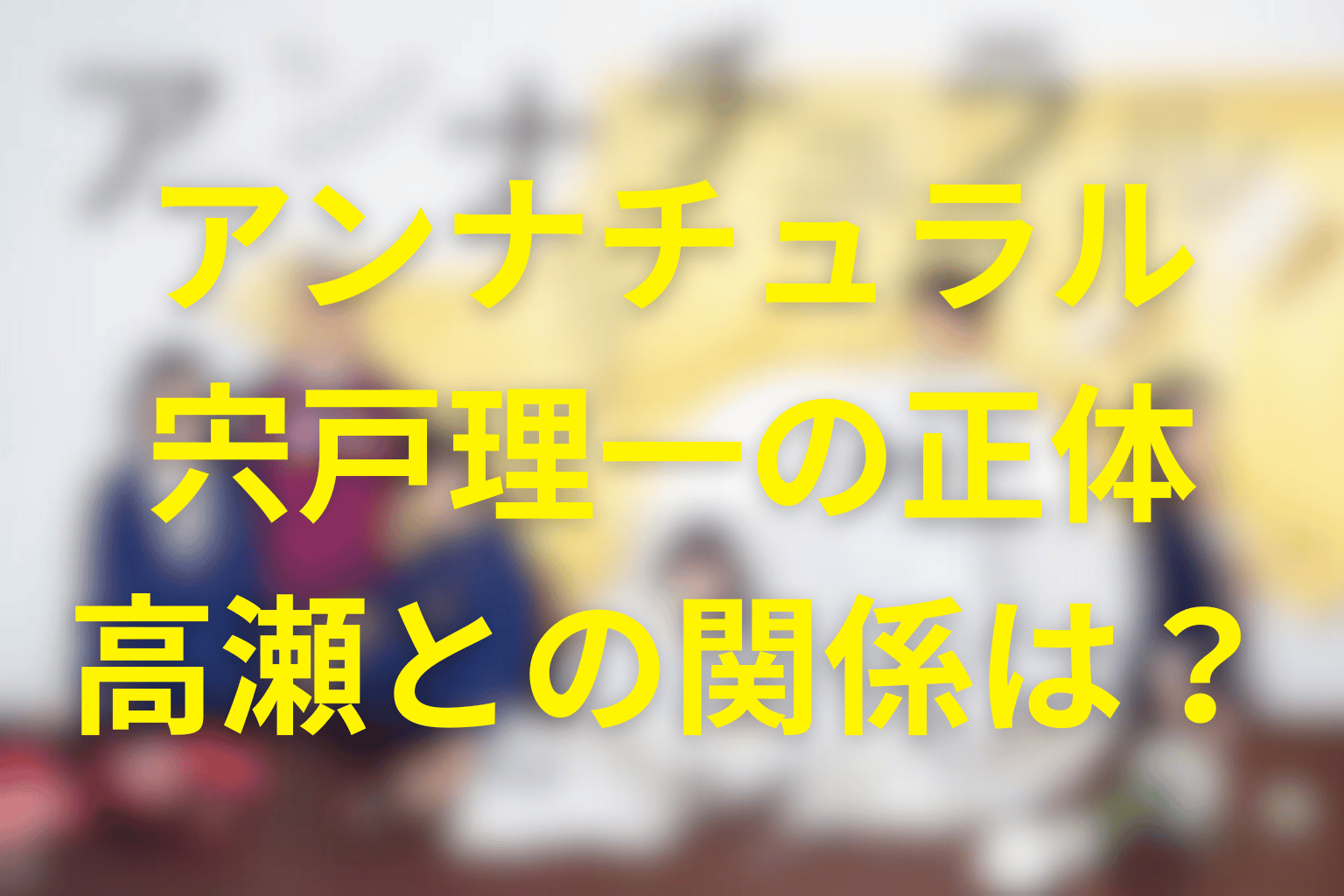
コメント