『アンナチュラル』を通して視聴者の前に立ち上がった“敵”は、単純な悪役ではありません。
赤い金魚の痕を残し、死因を変え続け、理解を拒むように犯行を重ねた高瀬文人は、物語の縦軸そのものを歪ませる存在でした。
なぜ彼は連続性を隠し、なぜ最終回まで裁けなかったのか。本記事では、高瀬の犯人像・手口・心理を整理しながら、アンナチュラルが彼をどう描いたのかを読み解いていきます。
先に結論:「赤い金魚」事件の犯人は高瀬文人
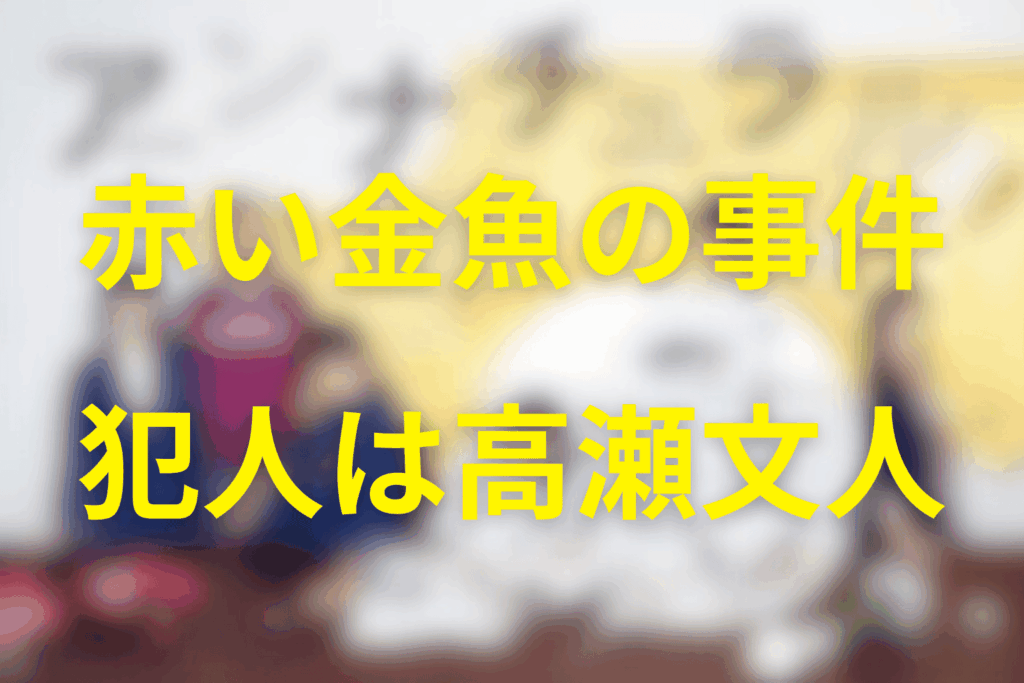
結論から言うと、縦軸として描かれる「赤い金魚」事件――中堂の恋人・糀谷夕希子の死に繋がる連続事件の犯人は、高瀬文人です。
最終回では、高瀬が「夕希子をはじめ複数の女性を殺害した疑い」で警察に出頭する形で物語が動きます。
ただし高瀬は、遺体損壊は認める一方で、肝心の「殺害」そのものは否定します。ここが『アンナチュラル』の最終局面をいちばん苦しくしているポイントで、犯人が分かったから終わりではありません。「分かったのに裁けない」という現実を、正面から突きつけてくる構図になっています。
また高瀬は、物語上では第8話の火災現場から助け出された“生還者”として登場します。
いったんは被害者側に見える立ち位置から、少しずつ「赤い金魚」の線へと接続されていく。この配置によって、連続事件が“特別な悪”ではなく、日常の延長線に潜んでいたことが浮かび上がるのも重要な仕掛けです。
そもそもアンナチュラルの「赤い金魚」事件って何?
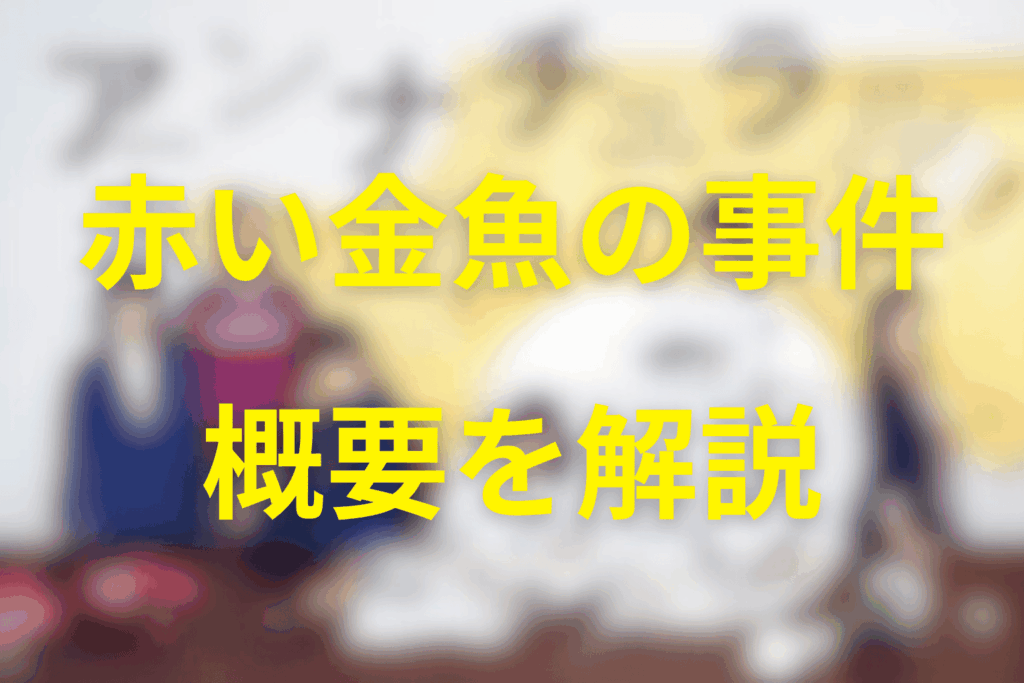
「赤い金魚」事件は、単発の事件名ではなく、複数の遺体に共通して残る“ある痕”を手がかりに繋がっていく連続性そのものを指します。
物語が決定的に動くのが第9話。
空き家に置かれたスーツケースから見つかった若い女性の遺体の口内に、中堂の亡くなった恋人・夕希子と同じ“赤い金魚”の印が発見されます。さらに、その印が残っていた遺体は、夕希子を含めて過去に3体あることが示され、UDIは同一犯による連続事件の可能性を訴えます。
しかし警察(毛利刑事)は、「正式な証拠がない」として連続事件として扱いません。
この“手がかりはあるのに、社会の手続きが動かない”という停滞こそが、赤い金魚事件の本当の怖さであり、物語の縦軸が縦軸として機能する理由です。真実に近づいても、証拠に変換できなければ前に進めない。その現実が、UDIの戦いをより過酷なものにしていきます。
そして最終回では、「赤い金魚殺人事件の全容がついに明かされる」という形で、この縦軸が物語の中心に据えられ、事件の意味と重さが一気に回収されていくことになります。
アンナチュラルの犯人“高瀬文人”の犯行動機
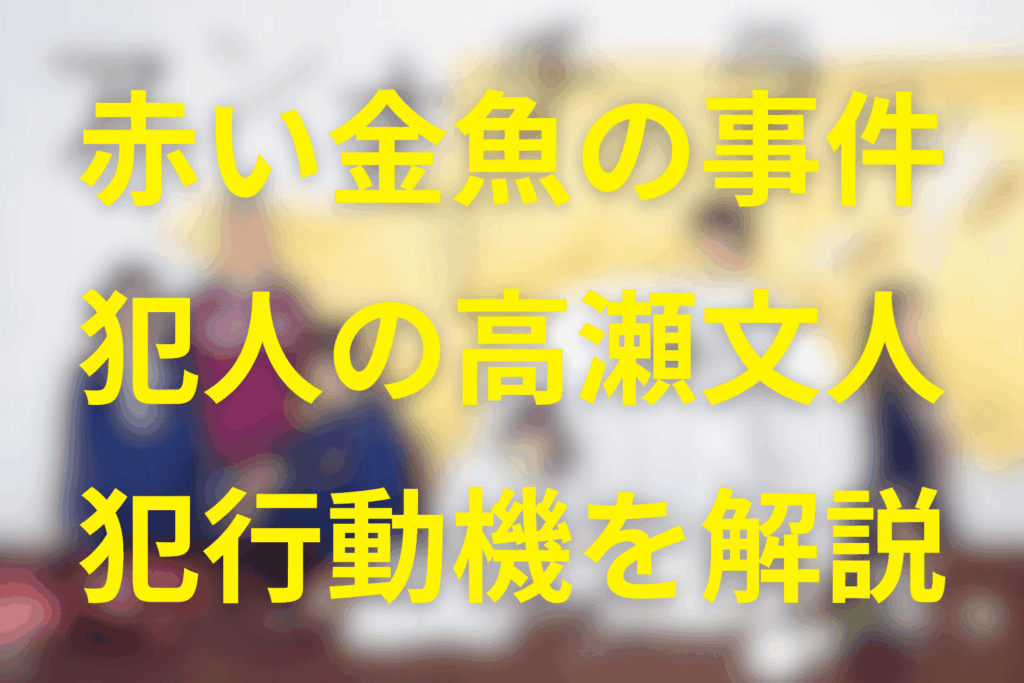
高瀬の動機は、いわゆる“分かりやすい復讐”や“恨み”としては提示されません。
物語の中でも、動機は明確に言語化されず、むしろ本作のテーマである「不条理な死」そのものを体現する存在として高瀬が配置されている、という読みが強いです。
表の動機:A〜Zを埋める「完成」への執着
高瀬の犯行は、アルファベット26音を埋めるように、頭文字に対応する死因・凶器を選んで若い女性を殺していく、という形で語られます。
要するに彼にとって殺人は、突発的な衝動ではなく、ルールに沿って“達成”するための行為でした。死因がバラバラなのは偶然ではなく、最初からそう設計されていた。
ここには怒りや復讐よりも、「やり遂げること」そのものへの執着が見えます。
裏の動機:口を塞ぐ虐待体験が、暴力の型になっている
さらに終盤では、高瀬が幼少期に母親から「しつけ」と称して、口にゴムボールを入れられる虐待を受けていたことが示されます。この体験が、のちに被害者の口の中にボールを押し込むという行為へと接続していく。
ここがいちばん不快なのは、この過去が「同情を誘う背景」にはならない点です。
虐待は、高瀬を救う説明ではなく、彼の犯罪を“型”として固定化する要素になってしまっている。過去の痛みが、他人を黙らせ、支配するための道具に変換されているからこそ、視聴者は犯人を理解した気になれない。
だから『アンナチュラル』は、高瀬に対して“納得できる理由”を与えません。
理解できない悪意が存在する、という現実そのものを、最後まで突きつけてくる構造になっています。
アンナチュラルの犯人“高瀬文人”の犯行の傾向
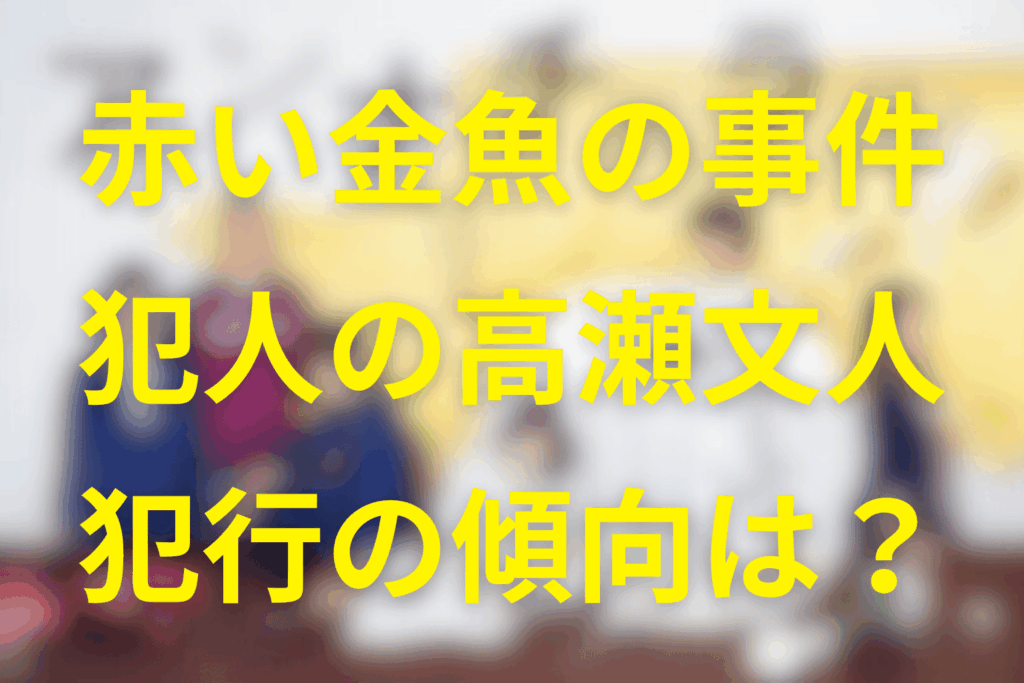
高瀬の犯行は、連続殺人でありながら「連続」に見えにくいよう設計されているのが最大の特徴です。
ここを整理すると、なぜ警察が即座に連続事件として動けず、UDIが証拠の壁に苦しんだのかが見えてきます。
傾向1:標的は「若い女性」に偏っている
被害者はいずれも若い女性で、この偏り自体は連続殺人の典型にも見えます。
ただし、動機が怨恨や人間関係に結びつかないため、個別事件として切り分けられやすく、捜査の初動では共通点として扱われにくい構造になっていました。
傾向2:死因・凶器を毎回変える(A〜Zルール)
高瀬はアルファベットの頭文字に沿って、死因や凶器を意図的に変えています。
この「バラバラ」を最初から作るやり方によって、「同じ犯人なら同じ手口が残るはず」という捜査の前提そのものを破壊している。
連続性を隠すための偶然ではなく、連結されないことを目的とした設計だった点が異様です。
傾向3:「赤い金魚」を口内に残す(=沈黙させる署名)
一方で、高瀬は被害者の口腔内に“赤い金魚”の印を残します。
これは捜査側に向けたヒントというより、犯人自身のための署名に近い。
声を出す場所である「口」を塞ぐ行為は、象徴的に被害者を沈黙させるものであり、同時にUDIだけが辿り着ける連続性の鍵にもなっていました。
傾向4:死因の“物語”を裁判用に組み替える
終盤の高瀬は、「殺していない」「勝手に死んだ」と主張し、死因を事故や食中毒など、立証が難しい領域へ寄せようとします。
鑑定書の表現を削らせようとする圧力が描かれたように、彼の犯行は殺しで終わらず、法の仕組みの中で逃げ切るところまで含めたゲームになっていました。
ここまで徹底しているのは、殺人そのものの快楽だけが目的ではないからです。
高瀬にとって重要だったのは、
「殺す → 繋がれない → 裁けない」
という構造を完成させること。
だからこそ彼の犯行は、最後まで社会と制度の弱点を突く形になっていきます。
「赤い金魚」の意味:殺害におさかなカラーボールを使用
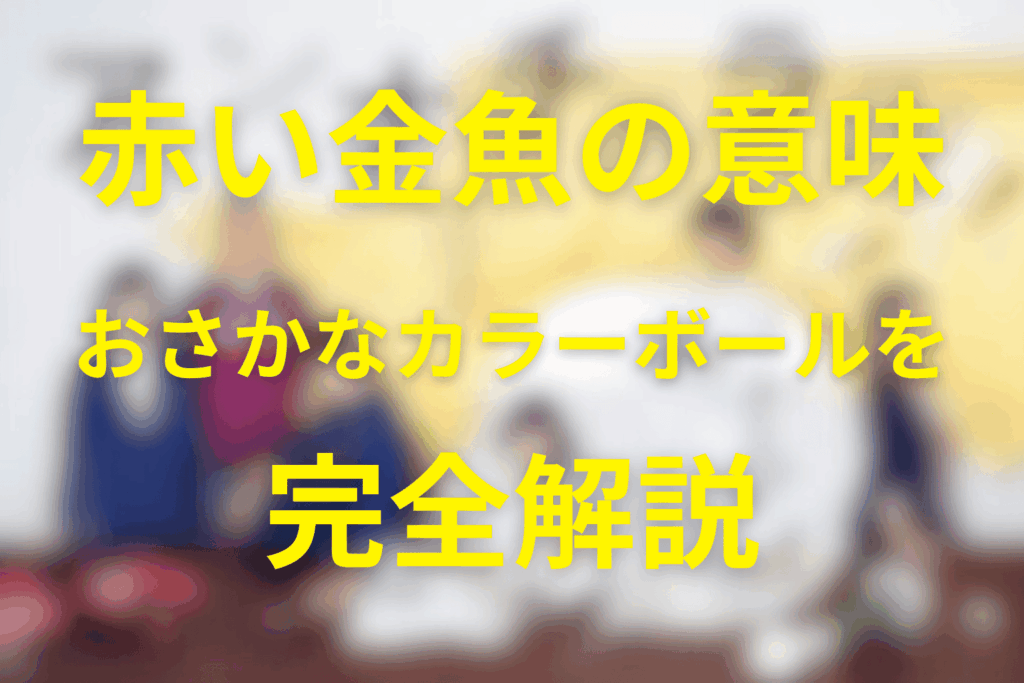
「赤い金魚」の正体は、象徴や暗号ではなく、まず徹底した物証として提示されます。
口の中に残っていた“赤い金魚”は、動物用のおもちゃである「おさかなカラーボール」(魚模様のエンボスが入ったゴム製ボール)を、猿ぐつわ代わりに口腔内へ押し込んだことで残った痕だと判明します。
つまり「赤い金魚」は、犯人が意図的に残したメッセージではなく、暴力行為そのものが身体に刻んだ痕跡でした。
ただし、この作品では物証としての意味にとどまりません。
- 口=言葉の出口
- そこを塞ぐ=被害者の声を奪う
- しかし死体は、声の代わりに痕跡を残す
- その痕跡を拾い上げるのがUDIの仕事
高瀬は被害者を黙らせたつもりでも、身体は嘘をつかず、痕を残す。
その皮肉が、「赤い金魚」という呼び名に収束していきます。
さらに終盤では、高瀬自身が幼少期に母親から口にゴムボールを入れられる虐待を受けていたことが示されます。
この過去が、被害者の口を塞ぐという犯行の“型”に直結している点が、いちばん生々しい。
「赤い金魚」は、
- 被害者の声を奪うための道具であり
- 犯人の過去が歪んだ形で再生された痕であり
- 同時に、死者が残した唯一の証言でもある
象徴として美化されることなく、暴力の具体性と、その痕が真実を語るという法医学の思想を一つに束ねた装置。それが、「赤い金魚」でした。
高瀬の犯行の特徴:A〜Zで埋める“殺人遊戯”
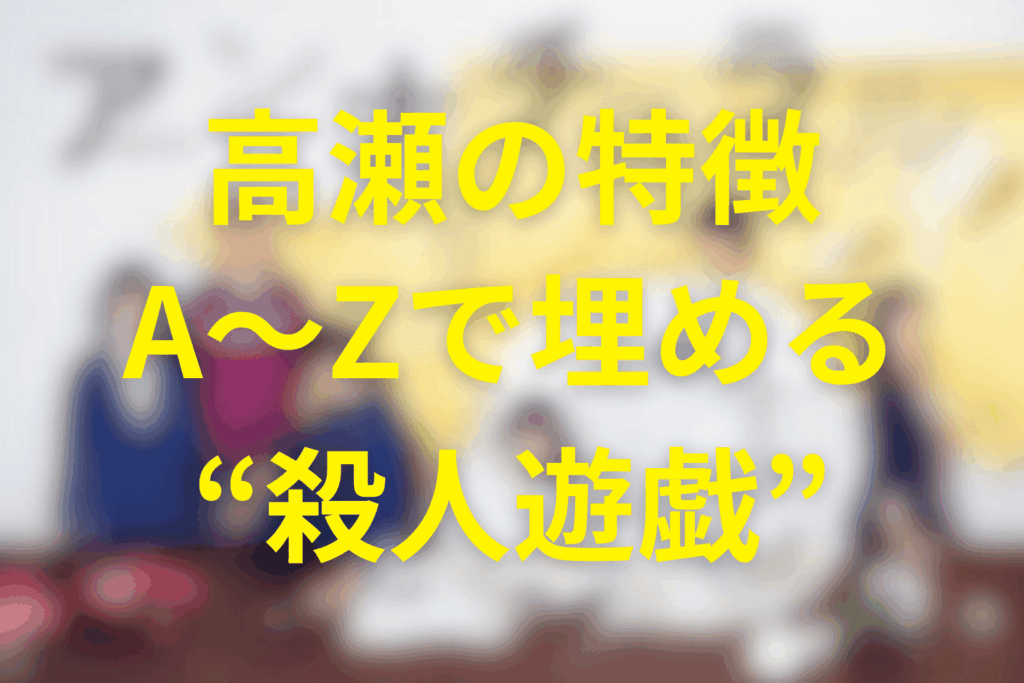
なぜ死因がバラバラだったのか
高瀬の異常性は、被害者の数だけでなく、死因や凶器を意図的に変えていた点にあります。
彼はアルファベット26文字を埋めるように、頭文字に対応する死因・凶器を選び、若い女性を殺害していました。いわゆるA〜Zの“殺人遊戯”です。
つまり捜査側が「同一犯なら似た手口が残るはず」と考える常識を、最初から壊す設計。
連続性を見えにくくすることで、事件同士を繋げにくくしていたわけです。
26人という数が示す“自己証明”
26人という数は偶然ではありません。
アルファベットを埋め切るための数であり、犯人にとっては「達成」のための数です。
この“達成欲”が、動機を復讐や怨恨ではなく、ゲーム性へ寄せてしまう。
ここが最も気持ち悪く、理解に回収できないポイントです。
犯人の高瀬文人が殺害したA〜Zの具体例
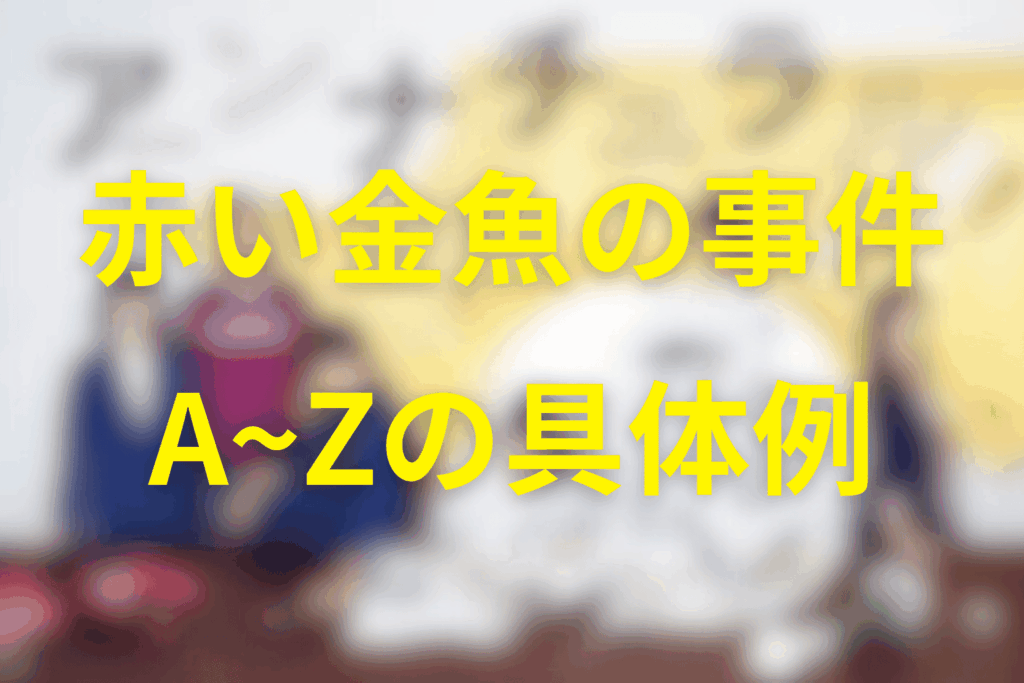
高瀬文人の犯行が異様なのは、単なる“連続殺人”ではなく、「A〜Zを埋める」というルールそのものを目的にしていた点です。
死因や凶器の“頭文字”でアルファベットを順番に埋めるように、毎回手口を変えて若い女性を26人殺害していた――この構造自体が、高瀬の動機の中核にあります。
さらに、被害者の口内に残る“赤い金魚”の印も、実際には猿轡として押し込まれた動物用玩具「おさかなカラーボール」の痕跡でした。
犯行は衝動ではなく、集めて完成させるための行為として設計されていた。そこにあるのは怒りよりも、収集癖に近い冷たさです。
A〜Zは「犯行の暗号」であって、全事件が描写されるわけではない
注意すべきなのは、ドラマ本編で26件すべてが詳細に描かれるわけではない点です。
A〜Zはあくまで高瀬の中にある犯行ルール(暗号)として提示され、視聴者に全体像を理解させる装置になっています。
このルールが見えた瞬間、「この犯人は殺すこと自体より、“埋めること”に興奮している」と理解できてしまう。
だからこそ怖い。感情的な動機ではなく、タスクを完了させる快感に近いからです。
劇中で“明確に結びつく”代表例(A/F/N)
ここでは、作中で比較的はっきり示される代表例だけを整理します。いずれも「頭文字→手口」という発想が、殺しの中心にあることを示しています。
N:Nicotine(ニコチン)
中堂の恋人・糀谷夕希子の事件は、「N(ニコチン)」に該当するものとして位置づけられます。
口腔内の痕跡と化学物質が結びつき、縦軸の起点となる事件です。
F:Formalin(ホルマリン)
橘芹那の事件は「F(ホルマリン)」。
解剖現場に存在するはずの物質が、死因そのものに転化する不気味さが際立ちます。
A:Asunder(バラバラ)
最後の犠牲者・大崎めぐみは、「Asunder(バラバラ)」として扱われ、これでアルファベットが埋まったと示されます。
つまり高瀬にとっては、“完成”のために必要な最後の一手でした。
この3例だけでも、高瀬の殺人が復讐や怒りではなく、タスク完了の快感に寄っていることがはっきり見えます。
アルファベット表に残る“キーワード”例(手口の方向性)
作中では、A〜Zに対応する英単語が並んでいる、という形で整理されます。具体的な例としては、
- E:Electricity(電気)
- K:Knife(ナイフ)
- R:Rope(ロープ)
- S:Suffocation(窒息)
- W:Water(水)
- X:Xenon(キセノン)
といった具合です。
ここで重要なのは、単語だけが並び、詳細な手順が語られないこと。
その結果、「何でも道具化できる」「死因はコレクションにすぎない」という冷たさだけが残ります。
そして、その冷たさを補強するのが“赤い金魚”というサインです。
犯人の側だけが「自分の作品」に印を残していく。殺人が“人を殺す行為”ではなく、世界に自分のルールを刻む行為へと変質していることが、ここではっきりします。
なぜ犯人の高瀬は一度、逃げ切れるところまで行ったのか

最終回の高瀬が厄介なのは、「捕まらない犯人」ではなく、「殺人で裁けない状態」をほぼ完成させていた点です。
逃げ切り寸前に見えた理由は、大きく分けて3つあります。
理由1:連続性が見えないように“死因を散らしていた”
警察が「赤い金魚」の線を、すぐに連続殺人として扱えなかったのは、死因や凶器がバラバラだったからです。
高瀬はここを狙って、A〜Zのアルファベットに対応させる形で手口を変えていました。
通常、連続殺人は「同じやり方」「似た痕跡」から線が引かれる。
その常識を逆手に取り、最初から“繋がらない設計”にしていたことで、捜査は点のまま止まってしまいます。
理由2:本人が「殺してない」と言い切れる状況を作った
高瀬は出頭後、遺体損壊は認めても、肝心の殺害行為は一貫して否定します。
しかも当初は、殺人を直接立証できる決定的証拠が存在しない。
ここが『アンナチュラル』最終回のいちばん胃が痛いポイントで、「真実を知っている」ことと、「法で勝てる」ことは別物だという現実が突きつけられます。
犯人像が見えているのに、裁判では勝てない。
高瀬は、そのズレを完全に理解したうえで、否認という戦略を取っていました。
理由3:裁判の争点を「疑い」にすり替えられた
裁判に持ち込まれた場合、高瀬は死因を「事故」「食中毒」に寄せ、鑑定書の表現ひとつを争点に変える余地を作っていました。
法医学を否定するのではなく、法医学が提出する“言葉の見せ方”を揺らすことで、勝負を泥沼に持ち込む。
さらに、なぜ高瀬が専門的知識を知っていたのか、という点が、UDI内部からの情報漏洩へと繋がり、チームそのものも揺さぶられていきます。
ここまで来ると、「逃げ切れそう」に見えたのも無理はありません。
それでも逃げ切れなかった決定打:夕希子の再解剖とDNA
最終的に状況をひっくり返したのが、夕希子の遺体がアメリカで土葬されており、再解剖が可能だったという事実です。
8年前には拾えなかった微細な証拠が、技術の進歩によって“今”になって立ち上がり、DNAが高瀬と一致する。
ここでようやく、「真実」が「法で裁ける証拠」に変換されました。
高瀬が追い詰められたのは、運でも奇跡でもありません。死体は嘘をつかない、その原則を最後まで実務として貫いた結果です。
だからこそ、この結末は派手な逆転劇ではなく、『アンナチュラル』が最後まで法医学ドラマだったことの証明になっていると思います。
犯人の高瀬文人が週刊誌に取材された理由
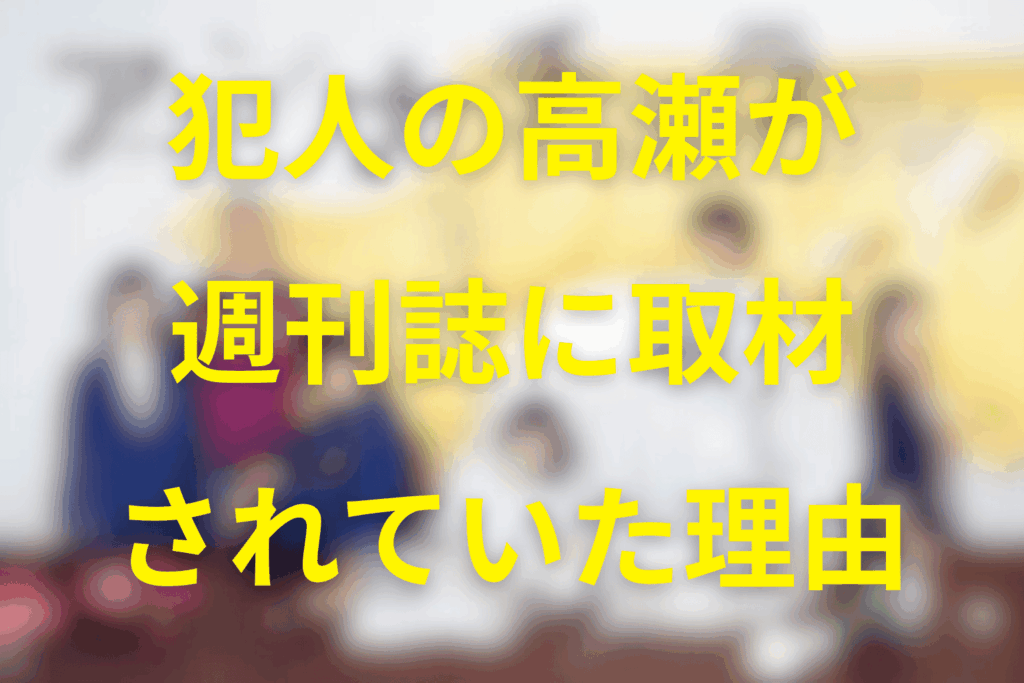
「週刊誌に取材された理由」を、作品内の因果で整理すると、主に2層あります。
1つは取材する側(宍戸)の都合。もう1つは取材される側(高瀬)の都合です。
取材する側:宍戸理一は“事件そのもの”を商品化したかった
宍戸はフリー記者として、高瀬に秘密裏に接触していました。そして高瀬の“告白”をベースに、「26人殺害は妄想か現実か」という趣旨の著書を世に出します。
この時点で、取材対象は「事件」ではなく「事件を起こす人間」へとすり替わっている。宍戸にとって高瀬は、真相解明の相手ではなく、話題を生むネタの鉱脈でした。
ここがいやらしいのは、宍戸の行動原理が正義でも悪でもなく、ほぼ「話題性」に寄っている点です。
社会的に正しいかどうかより、売れるか、注目を集めるか。だから視聴者の怒りも、犯人だけに向かって完結しない。
この構造自体が、アンナチュラル後半の不快さとリアリティを生んでいます。
取材される側:高瀬は“見られること”で、自分の犯罪を完成させたかった
一方の高瀬は、A〜Zを埋めるという殺人ゲームを、一人で完結させても満足できないタイプとして描かれます。
彼にとって重要なのは「やり遂げた」ことそのものではなく、「それが誰かに認識され、記録される」こと。
だから宍戸の取材は、高瀬にとって願ってもない舞台でした。
取材されることで、高瀬は自分の犯罪を“語り”に変換できる。しかも、自首しても殺害を否定し、「証拠がない」状態を作ることで、物語の主導権を自分が握り続けられる。
要するに、高瀬は週刊誌という回路を使って、現実の死を“物語”に昇華させようとした。犯行を社会に刻むために、メディアを共犯者にしたとも言えます。
アンナチュラル終盤が気持ちよく終われないのは、犯人の異常性だけでなく、犯罪とメディアが噛み合った瞬間に生まれる歪みまで、きちんと描いてしまうからです。
そこから目を逸らさないのが、この作品のいちばん残酷で、誠実なところだと思います。
犯人の高瀬文人を演じるキャストは尾上寛之
高瀬文人を演じたキャストは、尾上寛之(おのうえ ひろゆき)さんです。公式情報や最終話の表記でも、高瀬役として名前が明記されています。
終盤に登場する高瀬は、派手なカリスマ性があるわけでも、天才的な頭脳を誇示する怪物でもありません。
第一印象はむしろ“薄い”。感情の起伏が乏しく、どこにでもいそうな男性に見える。その「普通さ」が、この役にとって決定的に重要でした。
高瀬の怖さは、強烈な怒りや復讐心ではなく、「理由になっていない理由」で人を殺している点にあります。
尾上寛之さんの演技は、その空虚さを大げさに説明せず、視線や声の温度だけで成立させていました。感情を爆発させないからこそ、こちらが意味を探してしまう。その過程で、「理解できない」という感覚そのものが恐怖に変わる。
視聴者に「分かりやすい悪」を提示しないためのキャスティングだった、と振り返ると腑に落ちます。高瀬という人物が、最後までどこにも着地しない存在として残るのは、尾上寛之さんの“存在感を削ぎ落とした演技”があってこそでした。
まとめ:高瀬と「赤い金魚」が残したもの
- 縦軸「赤い金魚」事件の犯人は高瀬文人
- 「赤い金魚」の正体は、被害者の口腔内に残る魚模様ボールの痕
- 高瀬は死因・凶器を変え、A〜Zを埋めるように殺害を重ねた
- 背景には口にボールを押し込む虐待があり、犯行と接続している
- 最終的に、夕希子の再解剖とDNA一致で立件の決め手に至る
「赤い金魚」は、犯人のサインであると同時に、もっと残酷な意味で言えば、奪われた声が残した唯一の痕跡です。
その痕跡を拾い上げ、証拠に変換し、法で裁くところまで持っていく。アンナチュラルが最後に描いたのは、そこまで含めた「仕事」だったのだと思います。
ドラマ「アンナチュラル」の関連記事
以下で全記事のネタバレについて解説しています。
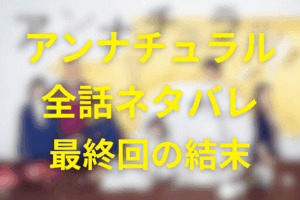
関連する人物についてはこちら↓
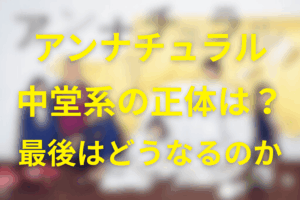
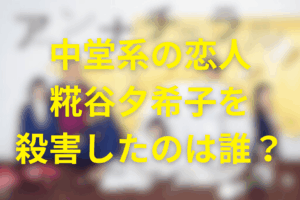
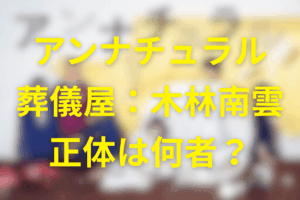
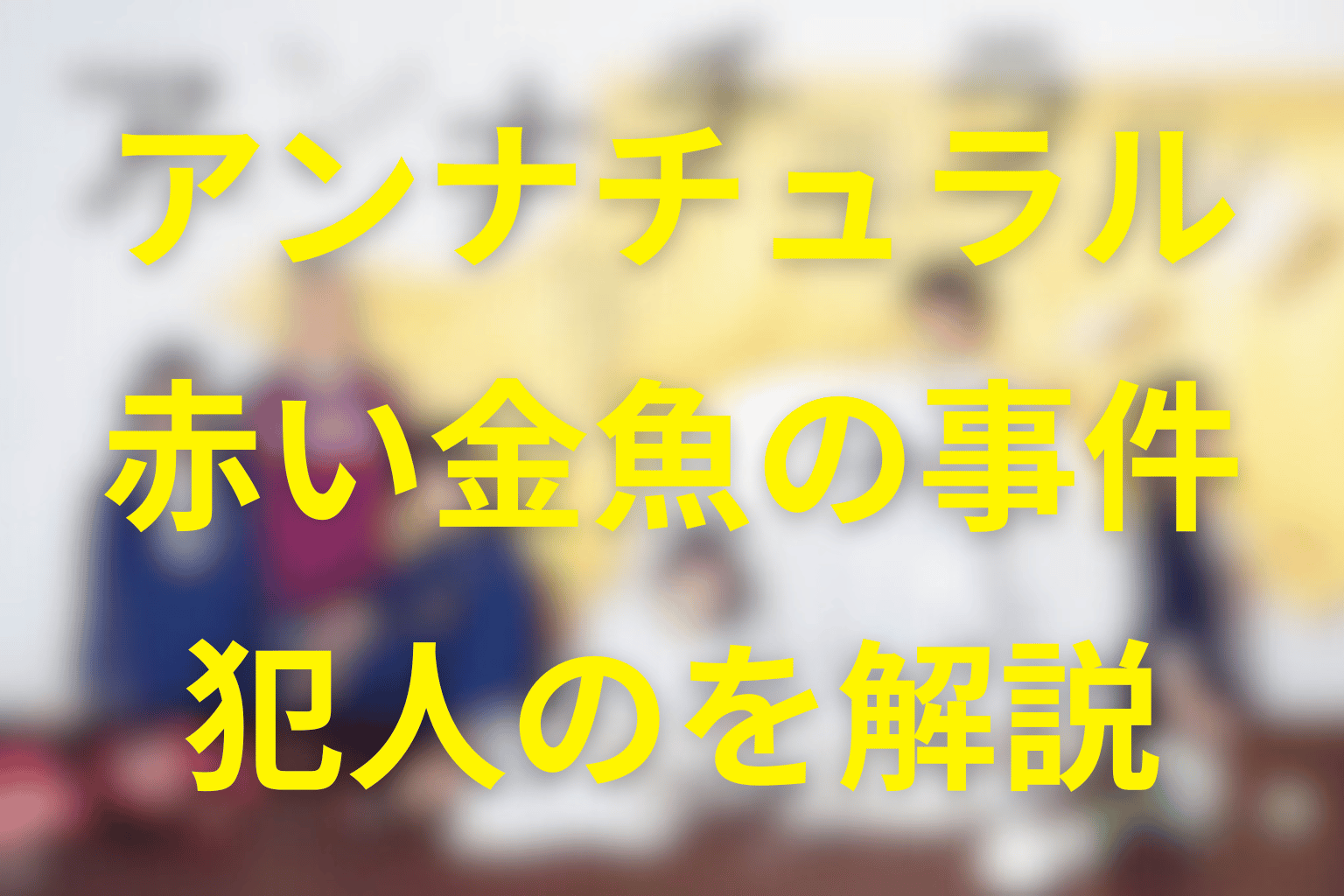
コメント