前話で久部が“舞台を生かす覚悟”を取り戻した『もしがく』。
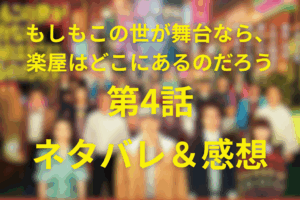
第5話では、クベ版『夏の夜の夢』がついに初日を迎える。
八分坂の劇場に集まったカンパニーは、旗揚げ宣言とともに高揚の渦に包まれるが、その裏では予期せぬトラブルが次々と発生。肉離れ、上がり症、段取りの崩壊——混乱の中で幕は上がり、笑いと緊張が交錯する一夜となった。
“ショウ・マスト・ゴー・オン”の言葉通り、彼らは舞台をやり切れるのか。そして、初日の先に見えた“楽屋”の意味とは——。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)5話のあらすじ&ネタバレ
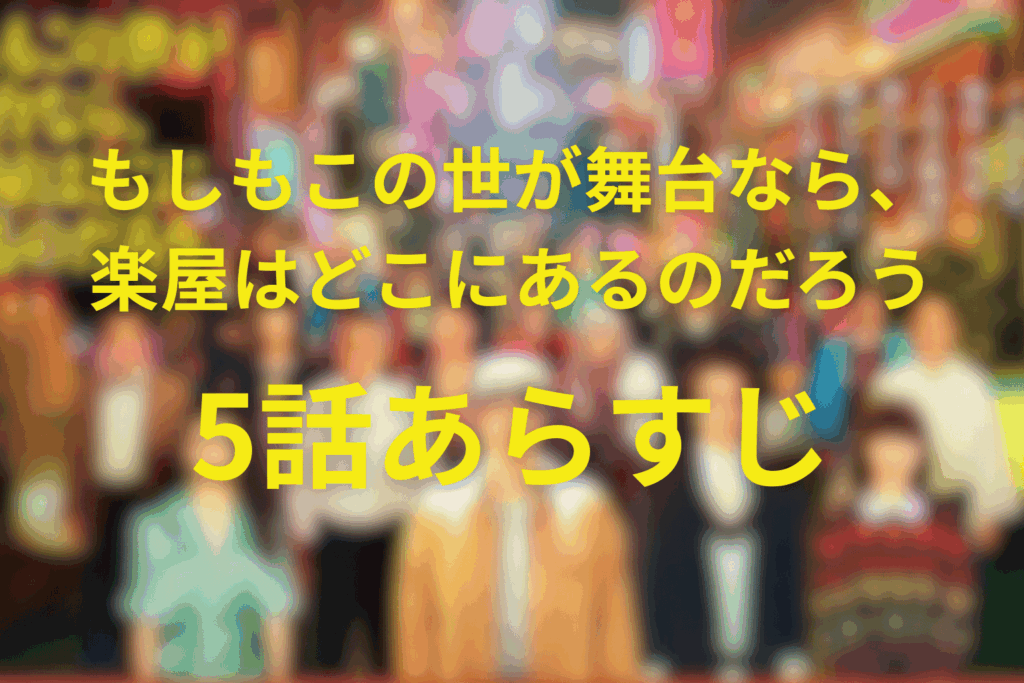
1984年の渋谷・八分坂を舞台に、“三谷幸喜の半自伝的要素”を芯に据えた群像劇『もしがく』。
第5話は、ついにクベ版『夏の夜の夢』が初日を迎える一日を描く。
物語としてはシンプルだが、劇中の「舞台は生き物だ」という哲学が、現場のドタバタとともに具体化していく回だった。「若者たちの夢、くすぶり、恋」を、現場の汗と息づかいで押し切る——そんな熱の立ち上がりが明確になった節目である。
開幕前:旗揚げ宣言とお祓い、そして高鳴る胸の鼓動
朝、WS劇場の関係者ミーティング。
舞台監督・伴工作(野間口徹)が一日の流れを的確に段取りし、緊張と高揚が同時に回り始める。そこで久部三成(菅田将暉)が高らかに「劇団クベシアター、旗揚げです」と宣言。
場内は歓声に包まれ、“初日”らしい空気が満ちる。お祓いのために八分神社の神主・江頭論平(坂東彌十郎)と巫女の樹里(浜辺美波)が来場。論平が倖田リカ(二階堂ふみ)にデレデレし、樹里がそんな父にうんざりする——という、人間くさいコメディの温度も健在だ。
取材の“目”が入る:タブロイド記者と「ダンサーの写真」問題
初日取材にタブロイド紙の記者(宮澤エマ)がやって来る。
80年代風味のルックで鼻息荒く旗揚げを追いかけるこの外部の“目”は、WS劇場の浮き足立ちと、久部の功名心を映し出す装置でもある。
さらに取材の流れで「ダンサーと写真を撮りたい」という要望が発生し、久部がリカを呼ぶはずが、なぜかパトラ鈴木(アンミカ)が現れる小さな食い違いも発火点に。舞台の外(=楽屋的領域)に報道の視線が差し込むことで、内と外の温度差が際立っていく。
開演直前:トラブルのジェットコースター
お祓いが終わっても安寧は訪れない。
パトラ鈴木にまさかの“肉離れ”が発生し、演出・段取りの再構築を余儀なくされる。
さらに、ベテラン“うる爺”(井上順)が本番を前に「無理だ」と急に上がり症を訴え、カンパニー全体が浮足立つ。
久部は荒療治で火消しに回るが、トラブルは雪だるま式に膨張。そのまま、やや不穏さを孕んだまま幕が上がる。次々と巻き起こる思わぬ事態が重なり、ハラハラと笑いが同居する三谷流“舞台あるある”が濃密に畳みかけてくる。
初日公演:笑いは起きる、だが「限度がある」
開いた幕は閉じる。
しかし、その道のりは平坦ではない。終演後、久部は「素人を集めてシェイクスピアなんて、無理な話だった」と肩を落とす。
作品としての緩急はあれど、舞台監督の采配も、役者たちの奮闘も、客席の熱も、すべてが“一回性”の生配信。久部は「自由にやるのはいい、端から王道を目指してはいない。
だけど——“限度”がある。あれでは悪ふざけだ」と、自分の演出プランと実際の舞台の乖離に呆然とする。緊張で真っ白になった“うる爺”が本番中に「郡上おどり」を延々踊ってしまった顛末まで明らかになり、久部の絶望は決定的になる。
「ショウ・マスト・ゴー・オン」の現場的リアリズム
それでも幕は開き、そして閉じた。
ゲネの段階から貫かれてきた「ショウ・マスト・ゴー・オン(幕が上がった以上、やり切る)」という姿勢は、この初日でも変わらない。
第4話の“覚醒”が寄せ集めの面々が役者へと変わる瞬間を描いていたが、初日の現場はさらに苛酷だ。演出家の手を離れ、舞台は“役者のもの”になる。その結果、笑いと事故の境目で走り続けた初日が生まれた——という観点は、第5話の見どころの一つだ。
終演後:客席に残った“老人”——伝説のシェイクスピア俳優
肩を落とす久部の前に、客席に残っていた風采の上がらない老人が現れる。
彼は日本を代表するシェイクスピア俳優・是尾礼三郎(浅野和之)。久部が敬愛する蜷川幸雄作品の常連でもあるという人物で、久部は絶句。つまり“初日”は、ただの敗戦ではなかった。
惨敗の夜にこそ現れた“次の扉”——是尾との邂逅が、WS劇場と久部の運命を揺り動かし始める。
付記:第5話の構図と登場人物の動き
第5話は、①旗揚げ宣言とお祓い(内輪の熱の高まり)→②取材=外部の視線(自意識の揺れ)→③アクシデント連鎖(現場対応力の限界)→④初日の着地(演出と現実のズレ)→⑤伝説の俳優との邂逅(次章への跳躍)という五段構成。群像の動線が一本の“舞台運営”に束ねられる巧さが際立っていた。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)5話の見終わった後の感想&考察
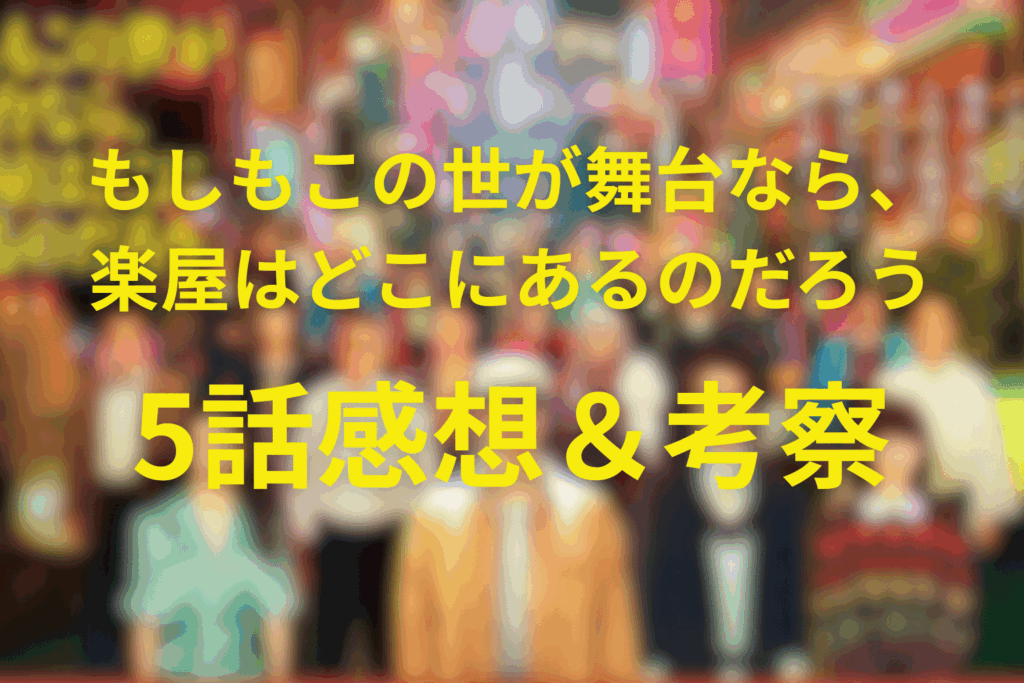
第5話は、物語が“覚醒”した回だと筆者は考える。理由は三つ。「テンポ」「視線」「着地」の最適化が、ようやく三位一体で回り始めたからだ。
テンポ:遅速の“振れ幅”がドラマを生む
序盤の段取りとお祓いは、あえて日常的なリズムで刻む。
そこから肉離れ→上がり症→開幕という“事故の羅列”にギアを入れ、終演後は一転して“敗戦の静けさ”に落とす。この「日常→非常→反省」という三層の振れ幅が、ドラマの体温を一段上げた。
視聴者が「先が気になり続けた1時間」と感じるのは、単に出来事が多いからではない。各トラブルが“舞台づくり”という一本の因果線に束ねられているから、観客の脳内に“次の手”が常に立ち上がる。だから面白い。
視線:内と外、観る者と観られる者
タブロイド記者の導入は、物語の「視線」を増やすうえで効いている。
劇団にとって“内側”=楽屋的空間に、外部の評価軸(取材)が流れ込むことで、久部の功名心、ダンサーのプライド、劇場運営の都合が露出する。
とりわけ「ダンサーとの写真」問題で、リカではなくパトラが前に出る小さなズレは、人物の序列や承認欲求を分かりやすく浮かび上がらせた。舞台の外側に“観客(メディア)”がいることを、物語自体が自覚し始めた瞬間でもある。
着地:「ショウ・マスト・ゴー・オン」の現代性
第4話のゲネで示された“やるしかない”精神が、第5話で完全に現物化した。
正直、初日の舞台は成功とは言いがたい。うる爺が“郡上おどり”でロスした時間と、演出の意図がズレた笑い——演劇的には痛い。
しかし、ここがリアルだ。舞台は生配信、事故は必ず起きる。問題は「どう回収するか」ではなく、「それでも続けるか」である。久部が吐いた「限度がある」という悔恨は、演劇の自由と責任の境界線に向き合った言葉だと思う。
久部と“演出”の孤独——論理で観るとこう面白い
演出家にとって、初日は“実験”であり“敗北”でもある。計画(プラン)と実際(パフォーマンス)の乖離は必ず起きる。
久部が突き当たった壁は、①キャストのコンディション、②観客の反応、③現場の突発事象
という三変数の相互作用だ。論理的に言えば、演出は“確率”に晒される職能であり、100%の再現性を持たない。だから彼は絶望し、だからこそ次の修正が生まれる。第5話は、久部が“演出の孤独”に気づく回として機能している。
カンパニーの“身体”——アンミカ&井上順の使い方
パトラ鈴木の肉離れ、うる爺の上がり症(からの盆踊り)——これらは単なるギャグではない。
三谷脚本は、カンパニーという“身体”の不調としてトラブルを描き、そこで初めて結束が立ち上がる構造を取っている。アンミカという「強いキャラ」をあえて躓かせ、井上順という「場慣れの象徴」に緊張を与える。定石を反転することで、観る者の予測を裏切り、同時に“舞台は生身”であると再確認させた。
樹里という“観客代理”の更新
お祓いに来た樹里は、これまでWS劇場に否定的な位置だった。
だが第5話では、彼女の視線が確実に揺れる。劇場に集う人たちの“人間くささ”と、蓬莱(神木隆之介)の視線の優しさに触れて、樹里が「外の目」から「内の目」へと半歩踏み込む予感が描かれた。
SNSや記事でも、“らんまん夫婦”再会の話題性にとどまらず、二人の化学反応に好意的な反響が見られる。つまり樹里は、物語の“観客代理”として再設計されつつある。
“楽屋”とはどこか——題名への応答
題名の問い「楽屋はどこか?」に、今話は仮説を提示する。
楽屋は単なる裏方部屋ではない。取材の視線が差し込む“外”、事故が連鎖する“舞台”、敗戦の夜に現れた“客席の老人”。この三者が連結した瞬間、楽屋は“場所”ではなく“状態”として立ち上がる。
つまり「守られた内側」ではなく、「守りたい関係」が生まれた場所こそが楽屋だ。久部が絶望してもなお、皆が一緒に居続けるなら、そこにはすでに“楽屋”がある。
是尾礼三郎という“次章の装置”
終盤に現れた是尾は、過去(蜷川演劇の記憶)と現在(WS劇場の試み)を結ぶ橋だ。
伝説の俳優が、粗削りな初日に“何か”を見いだす。これは“正解の提示”ではなく、“次の問い”の付与である。第6話では、是尾と久部の邂逅が物語を大きく動かす気配が示されている。初日の敗戦が、カンパニーを“更新”へと押し出す導火線になるのか——ここが次の見どころだ。
第1話の“溜め”は正しかったのか
第1話の賛否は激しかった。しかし、第5話の到達点を見てしまうと、あの“溜め”は設計として正しかったと筆者は思う。
人物同士の関係線が熟していなければ、今回のジェットコースターは単なる騒音に見えたはずだ。蓬莱の視線、リカの矜持、モネの母としての誇り——それらの下地があるから、事故が物語になる。視聴者が「覚醒」と評した所以は、ここに尽きる。
もしがくの関連記事
全話のネタバレについてはこちら↓
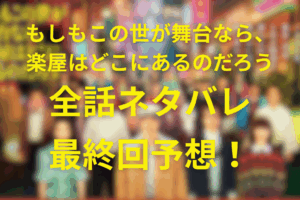
4話についてはこちら↓
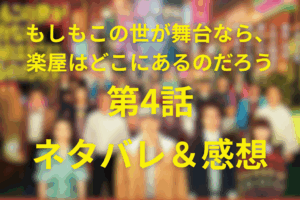
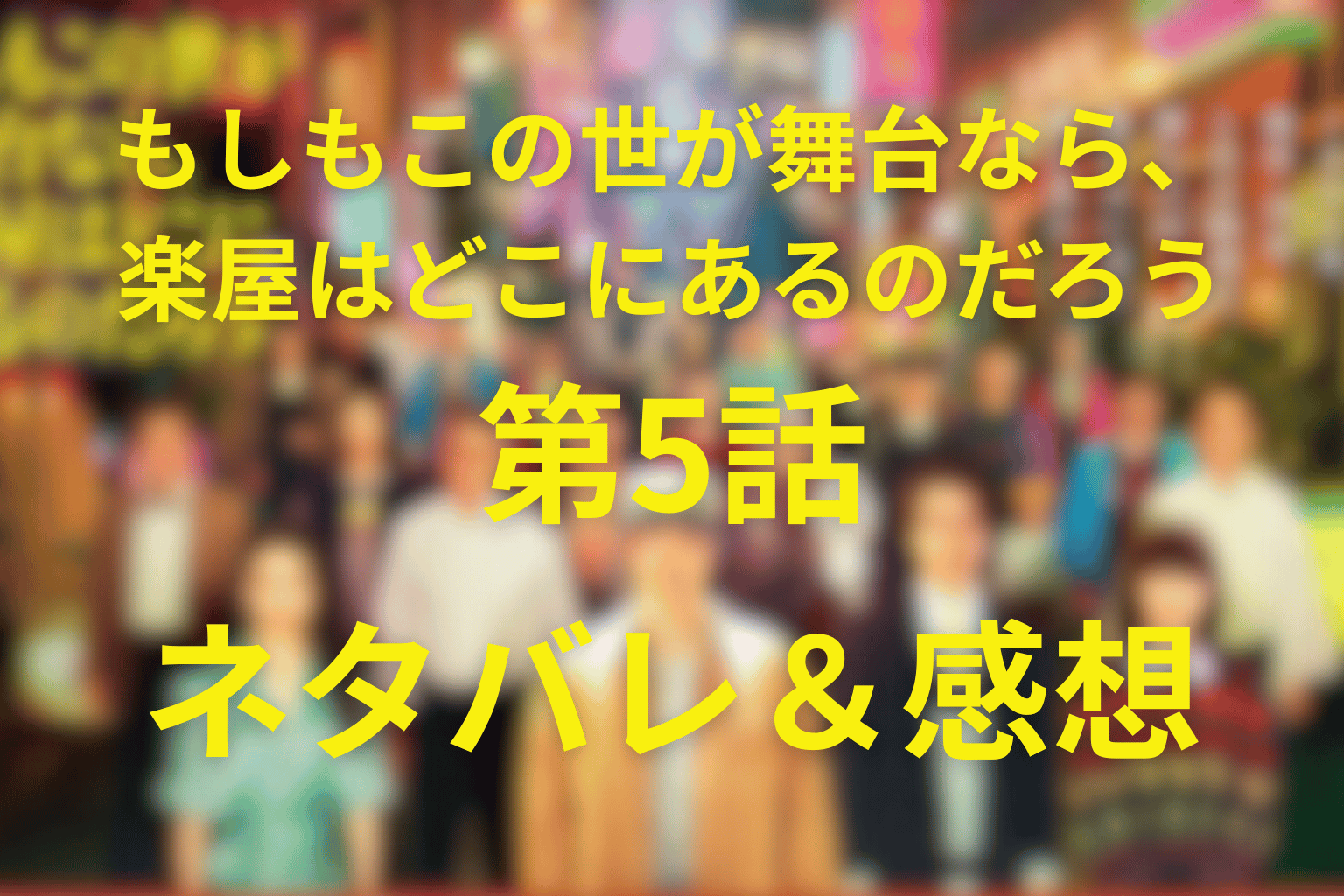
コメント