第4話で「信頼の欠如」が表面化した『仰げば尊し』。
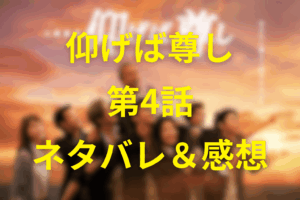
第5話では、その傷をどう修復し、再び音を鳴らすのかが焦点となる。
合宿での“喫煙写真”騒動により吹奏楽部は出場辞退の危機に立たされるが、樋熊(寺尾聰)は「罰を与えるだけが規律ではない」と行動で示す。
海辺での練習、早朝清掃、そして自宅での夕食――“合奏の前提”を作り直す日々の積み重ねが描かれ、部員たちは音ではなく“関係”をチューニングしていく。
一方で、樋熊の体調には忍び寄る影が……。
2016年8月21日(日)の夜9時よりTBS系で放送される注目のドラマ「仰げば尊し」第5話のあらすじと感想を書いていきます。
※以後ネタバレ注意
ドラマ「仰げば尊し」5話のあらすじ&ネタバレ
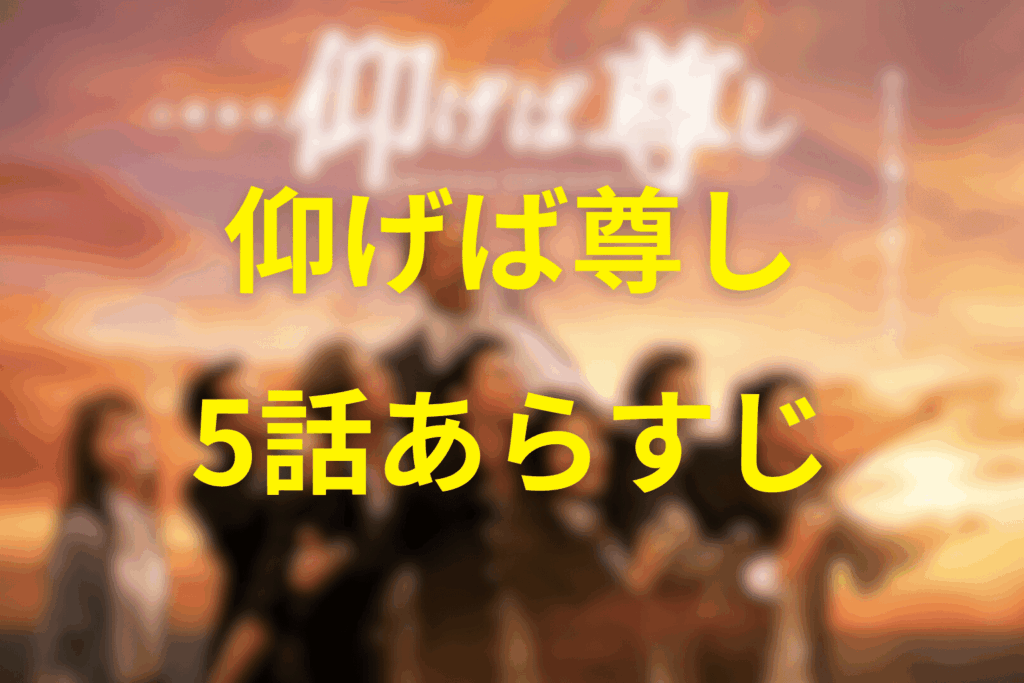
第5話は、「規律をどう運用するか」と「関係をどう編み直すか」を同時に問う回。
合宿で起きた“喫煙写真”騒動の余波が学校全体に波及し、吹奏楽部は出場辞退の危機に立たされる。
結果、10日間の部活動謹慎というペナルティを受けるが、樋熊(寺尾聰)は「場所がないなら作ればいい」と発想を転換。
海辺での臨時練習や早朝清掃、自宅での夕食を通じて、合奏の前提である“信頼”を立て直していく。
それは同時に、部員それぞれの事情(渚の家族問題)や、樋熊自身の“体の異変”とも重なりながら進行していく。
辞退要求と“10日間の謹慎”――制度は敵か、味方か
合宿後、井川(健太郎)の喫煙疑惑が正式に教頭・鮫島(升毅)へ共有される。
鮫島はコンクール出場辞退を強く要求するが、木藤良(真剣佑)や青島(村上虹郎)らが猛反発。
樋熊と奈津紀(多部未華子)の粘り強い説得により、出場は維持されるものの10日間の部活動停止という重いペナルティが課される。
罰としての制度に“対話による修正可能性”が残されており、学校という共同体の可塑性が提示される導入だ。
「場所がないなら作る」――海辺の臨時合奏と“家族の夕食”の意味
部室が使えない10日間、樋熊は学校外での練習を提案。
海の家を借り、潮風のなかで行われる合奏シーンは、制御しづらい環境の中で“呼吸”を合わせる訓練として描かれる。
さらに樋熊は「吹奏楽部は一つの家族だ」と語り、自宅に部員を招き夕食を共にする。
奈津紀は「仕事とプライベートの線引きを」と反対するが、樋熊は“自分の家”という一番やわらかい場所で、責任と信頼を可視化する。
「靴を揃えろ。靴が揃えられなければ音は揃わない」という指導も印象的で、所作と音の関係を重ねる演出が光る。
“誠意”を形に――早朝の校内清掃というレストレイティブな一手
謹慎中、樋熊は「誠意を見せよう」と提案し、部員たちは早朝の校内清掃を始める。
罰=停止の消極的サイクルに対し、関係を修復する能動的サイクルを差し込むレストレイティブな実践。
校内が整うほど音の“間”も整っていくという、環境と合奏の呼応関係が描かれ、この行動が鮫島の心を少しずつ動かす伏線になる。
渚の家庭線――「心の火を消すな」と“母を誘う勇気”
部長・渚(石井杏奈)の家庭線も丁寧に描かれる。両親は離婚し、渚に音楽を勧めたのは別居中の母だった。
樋熊は「心の火は消すな」と声をかけ、コンクールへ母を招く勇気を促す。
渚は一度はためらうが、仲間の支えを受けて、母に来てほしいと自分の言葉で伝える。ここで“家族”という私事が、合奏の質に直結する公的な課題へと反転する。
渚が音大進学を口にする流れも、個人の夢が部全体の目標へと転化していくプロセスだ。
「トップバッター」の抽選と、校内解禁へ――制度は関係で動く
地区大会の抽選で、吹奏楽部はよりによってトップバッターを引き当てる。
経験の浅い部には不利な順番だが、早朝清掃などの“誠意”が実を結び、鮫島は校内練習の解禁に舵を切る。
「退学か猶予か」と二項対立だった第3話から、「辞退か条件付き継続か」へ。
規律の運用が可変であり、関係の更新が制度を動かすことが明確に示される。
忍び寄る影――“診断”の報せと、樋熊の倒れる夜
物語の裏では、樋熊の体調が静かに悪化していく。
前話で示された“要再検査”に続き、第5話では重大な診断が暗示され、ラストで樋熊が自宅で倒れる。
次話で明かされるすい臓がんの診断と治療方針への流れを伏線として敷き、“時間は有限である”という現実を物語の中核に据える。
仰げば尊し5話の感想&考察
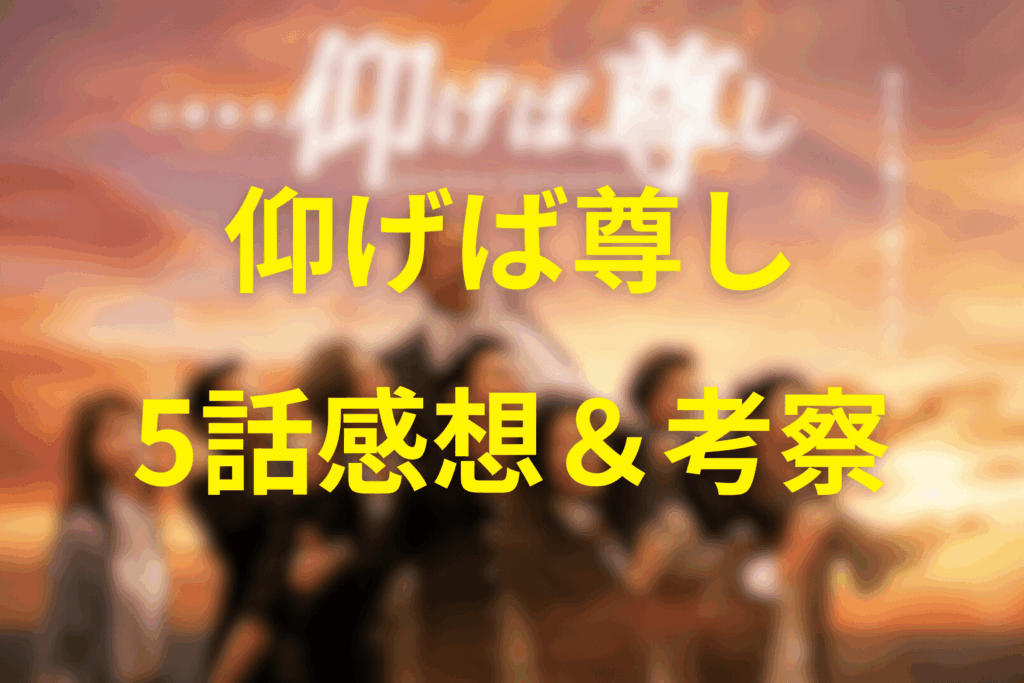
第5話の最大の見どころは、規律(discipline)を“排除の装置”ではなく“成長の手段”として運用している点にある。
辞退要求を10日間の謹慎へ変換し、“外で練習する自由”を残す判断は、単なる温情ではなく秩序の再設計。
罰を止めるだけでなく、行動の方向を変える制度設計として成立している。学校という場が懲罰機関ではなく、“成長の器”として機能しているのが本話の本質だ。
レストレイティブ・プラクティスとしての「清掃」
早朝清掃は修復的司法(Restorative Justice)に近い。
加害/被害という二元論ではなく、共同体に対する“負債”を誠意で返す実践だ。
音が良くなる理由も感情論ではない。場が整えば“聴こえ”が整い、合奏の定位(誰がどこで何を鳴らすか)が定まる。
環境→音→自尊という上昇スパイラルを、視覚(清掃)と聴覚(合奏)で同時に立ち上げた演出が巧みだった。
「家族になる」ための段取り――食卓と靴と呼吸
樋熊宅の夕食は、“場の共有”という教育の設計だ。
食卓で距離を近づけ、靴を揃える→音が揃うという比喩で、身体と耳の関係を示す。
奈津紀が線引きの必要を主張する一方で、樋熊は“近さ”に信頼を見出す。近さのメリットとリスクを両立させることで、熱血の美談に堕さない教育の倫理を保っている。
渚のライン――“私事→公事”への反転
渚が母を誘うまでの逡巡は、個人のドラマでありながら合奏の質に直結している。“誰に聴かせたいか”を自分の言葉で言語化した瞬間、演奏の確信が一段上がる。
第5話は、個の痛みが集団の力に変換される回であり、樋熊の「心の火」は動機の持続可能性を与える種火として機能した。
制度を動かすのは“正しさ”だけではない――可視化された関係資本
トップバッターという不利な状況でも、早朝清掃や誠意の積み重ねが結果的に制度を動かす。
正しい理屈と、信頼という関係資本が制度運用を押し出す。“可変の規律”が“変わらない理念(教育)”を支えるという二層構造が、本作の思想の中心に据えられている。
忍び寄る有限性――指導の時間設計へ
ラストの倒れるシーンは、音楽的にいえばフェルマータ。
時間が引き伸ばされ、指導の“残り時間”が可視化される。
次話で明かされる病名が、樋熊に“時間の配分”という教育的課題を突きつける。“家族になる”という言葉が、有限の時間に照らされてより多義的に響き始める。
演奏未満の“音”がもう鳴っている
海辺の合奏、靴の音、食器の触れ合い、早朝の掃除のざわめき。
これらは演奏に至る前の音であり、地区大会トップバッターという逆境と呼応する。日々の音を積み上げたチームは、本番の沈黙さえ味方にできる。
第5話は、その“準備の音”を丹念に積み上げた回だった。
まとめ(次回への視点)
- 規律の運用:辞退か継続かを分けるのは、正しさ+関係資本。
- 関係設計:夕食・清掃・所作が統合し、“音の倫理”を身体化。
- 有限性の導入:樋熊は時間を配分する局面へ。
- 地区大会:トップバッターを跳ね返すのは、演奏未満の準備の音。
“勝つ技術”の前に“鳴らす関係”を整える。
第5話は、その思想をもっともクリアに可視化した回だった。次話で病名が明かされ、指導の継承と生徒の自立という二重課題が走り始める。
音はここから、いよいよ“言葉抜き”で語り出す。
関連記事
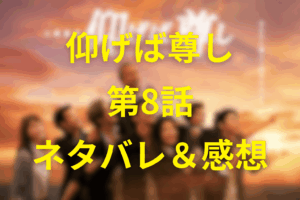
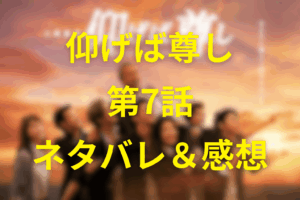



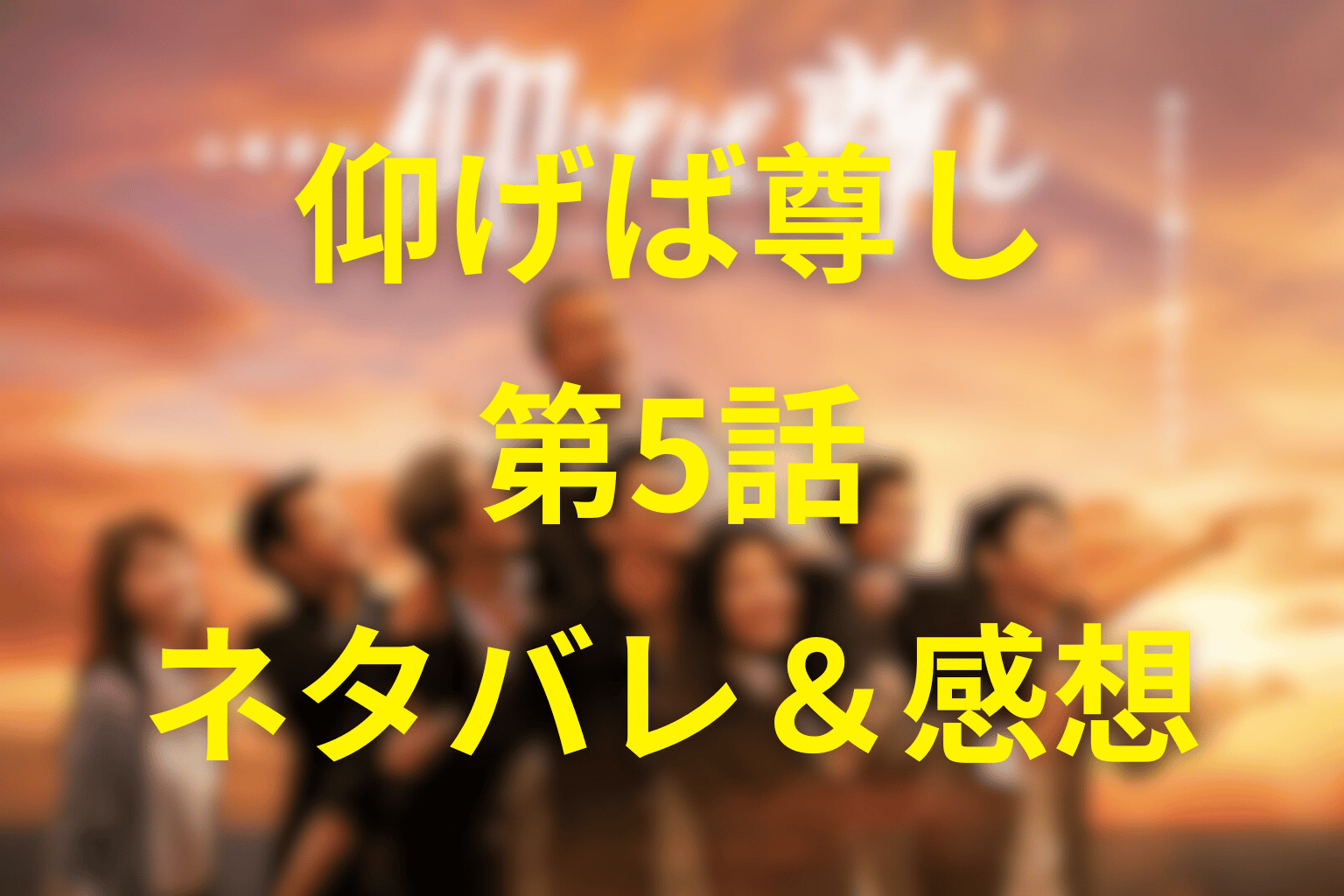
コメント