ロイヤルホープが引退し、“血を残す”第二の人生へ進み始めた前話。
しかし、山王耕造と隠し子・耕一の溝は深いまま。ロイヤル軍団が新たな未来を踏み出すためには、この親子の関係修復が欠かせない――そのテーマが真正面から描かれるのが7話です。
7話では、ホープの後継をどうつなぐか、そして誰が“ロイヤルファミリー”を引き継ぐのかという核心へストレートに踏み込んでいきます。
病床の耕造の焦り、耕一のこじらせた優しさ、栗須の奔走。
すべてが交差した先に、“口取り式”という象徴的な儀式が待っている――そんな継承のドラマが凝縮された回となっています。
ザ・ロイヤルファミリー7話のあらすじ&ネタバレ
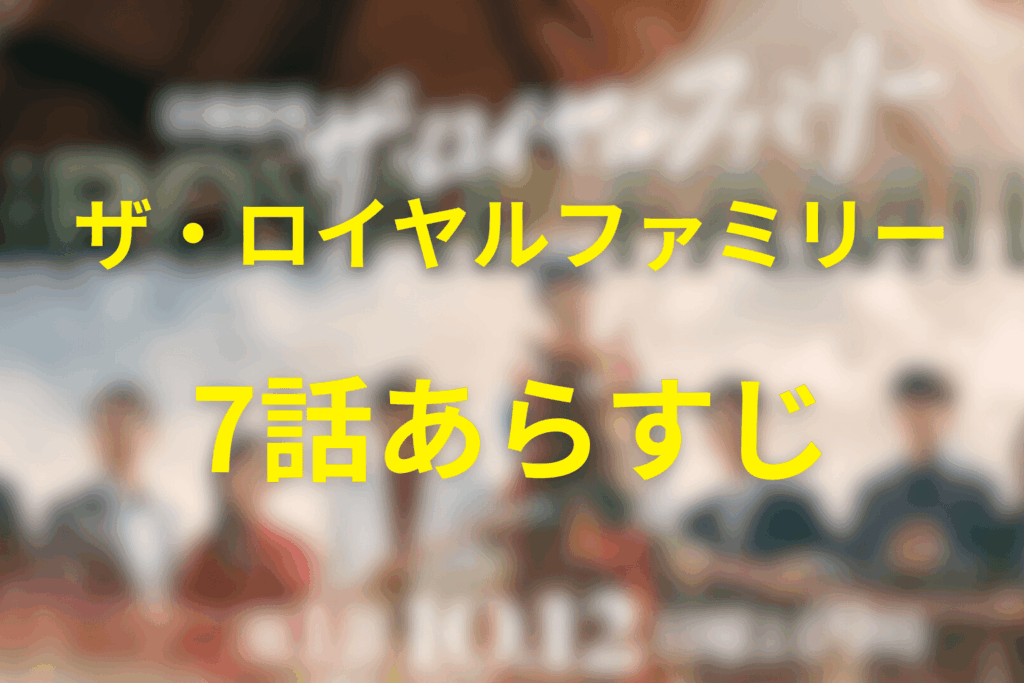
7話「口取り式」は、有馬記念2着という痛みの残る結果から始まり、「山王耕造の最期」と「ロイヤルファミリー誕生」という二つのクライマックスを一気に描き切った回だった。
耕造の余命と向き合う山王家、隠し子の中条耕一、そして栗須とチームロイヤルが、最後のバトンをどう受け取るのかが物語の軸になっていく。
有馬記念2着の余韻と、病床の山王耕造
6話の有馬記念でロイヤルホープは惜しくも2着に敗れた。長年の悲願は果たせず、レース後には耕造の余命が長くないことが発覚。7話はその続きとして静かに幕を開ける。
病室の耕造は、馬主としての闘争心を完全に失ったわけではないが、身体は確実に弱っている。一方、隠し子である耕一は、祖母と母を早くに亡くしたことも重なり、山王家という巨大な存在とどう向き合うべきか、まだ自分の中で答えを出せずにいた。
有馬記念で敗れたことで耕造は「夢の未完」を突きつけられた。同時に、残された時間で“何を残すのか”が一気に現実味を帯びてくる。そこで浮かび上がるのが、「血をつなぐ」というもう一つの夢だった。
ロイヤルホープ引退と「血を残す」決断
ロイヤルホープは有馬記念を最後に現役を退き、繁殖入りのため野崎ファームへ送られる。
ここで象徴的なのは、ホープが「勝てなかった馬」で終わるのではなく、「次世代へ血をつなぐ馬」へ役割を変えていく点だ。
耕造はホープの引退を単なる終わりとしてではなく、「ロイヤルホープとロイヤルハピネスの子を作りたい」という、新たな夢の起点として捉える。
これが後に誕生する競走馬ロイヤルファミリーの出発点になっていく。
父を拒む耕一と、板挟みの栗須
ホープの引退後、栗須のもとに耕一から連絡が入る。「伝えたいことがあるので耕造に会わせてほしい」。父と向き合う覚悟を決めた耕一の言葉に、栗須は安堵を覚えると同時に、慎重に面会を段取りする。
だが対面は最悪の形で崩れた。
耕造は不器用なプライドゆえに歩み寄れず…耕一は「隠し子」という扱いを受け続けてきた怒りを押し込めきれず。
互いの本音は交わらず、耕一は伝えたい気持ちを抱えたまま部屋を出ていく。
栗須は板挟みになる。
「耕造に残された時間は少ない」「耕一も本当は父を嫌いきれていない」。その両方を知る栗須には、ただ黙って見ているという選択肢はなかった。
加奈子の視点が射す光――「反対しているのではなく、心配している」
栗須は行き詰まり、加奈子に相談する。そこで返ってきたのが、状況を一気にひらくひと言だった。
耕一は父を嫌っているのではなく、
“父とつながることで、自分と母・祖母の人生が否定されるのではないか”
と怖れているだけでは?
つまり、“拒否”ではなく“心配”が本質。加奈子の分析を受けて、栗須はアプローチを変える。「父のもとへ連れていく」のではなく、「耕一の本心を聞き、耕造へ翻訳して届ける」方向へ舵を切り直す。
二度目の対面と、耕一の本心
しされ、栗須は耕造と耕一の再会をセッティング。舞台は、ロイヤルホープたちがいる厩舎。
耕造は余計な前置きなく核心を口にする。
「もう謝らない。生活の面倒を見るつもりもない。ただ、俺の馬を継いでくれないか」
つまり“父”としてではなく、“馬主”として託したいという宣言。
栗須が横で支えるから心配はいらないとフォローを入れる。
耕一は一度だけ丁寧に頭を下げる。気持ちは受け取っている。
しかし、口を開いて出た言葉は「お断りします」。
理由は二つ。
- 自分に馬主が務まると思えない
- 引き継ぎたいと思える馬が現状いない
血統オタクとしての冷静さが、父の申し出を跳ね返す形になってしまう。
耕一がロイヤルホープの分析は“本物”
再度の対面はうまくいかず、耕一は栗須に本心を明かすため外へ出る。ここで初めて、耕一の“馬への愛”が言葉になる。
大学では競馬サークルに所属。
ロイヤルホープの走りも細部まで分析している。
父の競馬事業を「大人が本気で挑む夢の場」と理解している。
ただ、何かを言いたそうにするも、耕一は言わない…。ここで耕一外に出た耕一を栗須が追う。
「どうして会おうと思ったんですか。伝えたいことがあったんですよね?」
当初ははぐらかす耕一だが、やがて本音がこぼれ始める。彼が気にしていたのは“ロイヤルホープの配合相手”だった。
耕一はロイヤルホープの血統と、山王ロイヤル所有の繁殖牝馬を徹底分析。
特に名牝「ワルシャワ」との配合では荒い気性の産駒が出る可能性が高い、と冷静に結論を出していた。
「ホープの子どもが、走れない馬になるのが嫌なんです」
耕一の興味は“父子の血縁”ではなく、“ホープの才能を正しく残すこと”。加奈子の読みが正しかったことが、ここで明らかになる。
調教師・広中が驚くほどの知識と情熱を見せる耕一に、栗須ははっきりと感じる。
──この青年こそ、競馬事業を継ぐべき後継者なのではないか。
そして耕一は重大な提案を口にする。
ロイヤルハピネスという“運命の牝馬”
栗須と共に室内へ戻った耕一は、パソコンを使いながらプレゼンを始める。
ホープの血統の長所と短所、気性面、スピード不足の補い方など、冷静に語っていく。
そして「もし引き継ぐなら」と名前を挙げたのが牝馬ロイヤルハピネス。
ホープとの相性が良く、母系の気性や体質を含め不安材料が少ないという判断。
ここでさらに耕造が運命を感じたのが、
ロイヤルハピネスを選んだのが耕造の亡き妻であり、耕一の母親の美紀子であること。
「お母さんが社長のために選んだ牝馬。その子どもなら、自分が引き受ける意味がある」
血統だけでなく、家族の物語まで重なる“正しい配合”。
栗須は涙をこらえながら、その思いを耕造へ伝える。
「あと3年、生きてください」――競走馬登録というタイムリミット
耕一の提案は明快で、覚悟の詰まったものだった。
山王家のビジネスや財産には興味がない。その代わり、競馬事業を継ぎたい。
競馬なら、自分は父と対等な場所で向き合える。
「隠し子」ではなく「正式な後継者」として受け継ぎたい。
優太郎は事業の後継者
耕一は競馬事業の後継者
という“兄弟それぞれの役割”が、ここで初めて現実味を帯びる。
栗須は冷静に現実を突きつける。
競走馬として登録できるのは、種付けの約2年後。
育成期間を含めれば、相続対象となる馬が“競走馬”になるまで最低3年かかる。
つまり、耕造が耕一に馬を譲るには“あと3年生きる”必要がある。
栗須は涙をにじませながら懇願する。
「だから、あと3年は生きてください。ホープとハピネスの子が競走馬として走れるまで」
耕造はその“宣告”を一蹴する。だが、それは弱さではない。
「譲るまでじゃねえ。その馬が先頭でゴールするまでだ」
相続ではなく“勝利”がゴール――耕造の生きる理由が、再び燃え上がる。
山王家の本音と、ロイヤルファミリー誕生
栗須は耕造の妻・京子と嫡男・優太郎にも事情を説明。
二人は馬の相続にこだわりはなく、「馬のことは好きにしていい」とあっさり了承する。
ただ、京子は「治療を続ける耕造がつらいのでは」と複雑な表情を見せる。
それでも、山王家として“ホープの血を耕一へ継がせる”方針が固まる。
時は2020年。
ロイヤルホープとロイヤルハピネスの仔馬が誕生。耕造はその名を 「ロイヤルファミリー」 と名付ける。
物語タイトルが次世代の馬に託される印象的なシーン。
タイトル「ロイヤルファミリー」は、
- 血統としての家族
- チームとしての家族
- 人としての家族
という三層で意味を持ち始める。
同じ頃、翔平は騎手としてデビューし、佐木隆二郎と百合子の間には第一子が誕生。それぞれの家族に、新たな“血”が芽吹き始める。
病室の耕造と、椎名義弘――“父親同士”の短い対話
耕造の容態は依然として厳しい。
そこへライバル馬主・椎名義弘が黄色いバラを携えて現れる。
屋上で短い会話を交わす二人。
椎名もまた、馬主を志す息子を持ち、親としての葛藤を抱えている。
耕造は意外にも柔らかい声で返す。
「子どもにはやらせてみろ」
かつての強欲なワンマンからは想像できない“父としての言葉”。椎名は最後に一通の封筒を差し出す。その中身は明かされないまま、不穏な伏線を残す。
ロイヤルファミリー登録、そして有馬記念への誓い
ロイヤルファミリーは2021年、続いて2022年へと成長。
栗須と耕一は、競走馬登録が完了したことを耕造に報告する。
「まだ譲ったわけじゃない。俺の代理として、デビュー戦を勝たせろ」
その言葉には“父としての誇り”と“馬主としての厳しさ”が宿る。
野崎ファームでは、気性の荒いロイヤルファミリーについて議論が交わされる。広中は短距離路線を提案するが、耕一は譲らない。
「僕たちの目標は、ホープで届かなかった有馬記念をファミリーで獲ることです」
ここで“新たな夢のゴール”が正式に宣言される。
口取り式――「馬主になる」という覚悟の儀式
2022年6月、東京競馬場。
ロイヤルファミリーのデビュー戦。耕造は病室から中継を見守る。
ファミリーは出遅れながらも直線で鋭く伸び、見事に新馬勝ち。耕造の目から静かに涙がこぼれる。
そして口取り式。しかし耕一は馬の隣に立つことをためらい、
「僕の代わりに、栗須さんが……」
と頭を下げる。
栗須は静かに首を振る。栗須はこの時、電話で耕造が亡くなった連絡をうけ、ここから正式にロイヤルファミリーは耕造から耕一の所有馬になった…
「ファミリーのそばに立つのはあなたです。今この瞬間から、あなたがファミリーの馬主なんです」
耕一は涙をこぼしながら、ロイヤルファミリーの隣へ。まだぎこちない笑顔のまま――しかし確かに馬主としての覚悟を受け取る。
この“口取り式”こそ、7話の核心。
山王ロイヤルのバトンが“次の世代”へ正式に渡る瞬間である。
京子の「面白かったわ」という一言が刺さる
耕造がファミリーのゴール後にほぼ喋れない状態で、泣いてる状態…耕造の市とファミリーのゴールをみた京子が、耕造を手を持ち、無きながらつぶやく。
「単勝勝ったわ…面白かったわ…」
前回のロイヤルホープの時は、ホープは勝てない、耕造を信じれないと単勝は買わなかった妻。
浮気も、競馬も、隠し子も。全部含めて、退屈とは無縁の人生だったという、京子なりの最大の賛辞だった。
7話は「バトンパスの回」
ロイヤルファミリーの勝利
口取り式でのバトンパス
耕造の静かな最期
この三つが重なり、物語は“耕一の時代”へ進む。
血統も、夢も、責任も。
バトンは確かに次の世代へと渡された――そんな一話だった。
ザ・ロイヤルファミリー7話の感想&考察
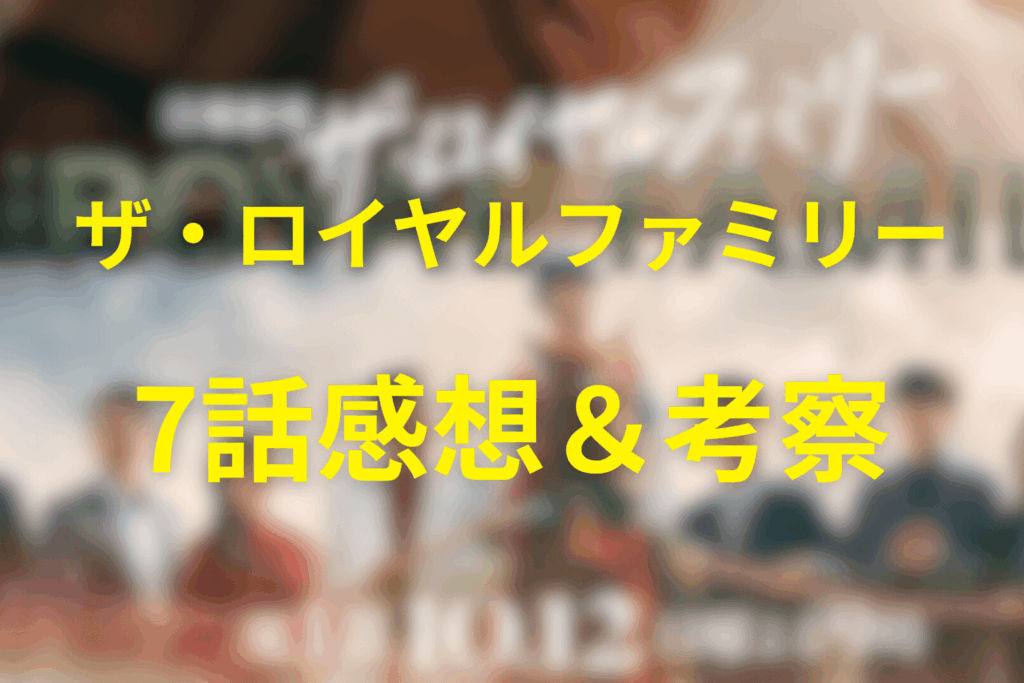
7話は、派手なレースシーン以上に「誰がどの夢を引き受けるのか」という継承の物語が濃密でした。
個人的には、“隠し子は馬オタク”というキャッチーなまとめを超えて、「馬を見る目」「人を見る目」「時間を見る目」が丁寧に描かれた一本だったと感じています。
タイトル「口取り式」が示す三つの意味
競馬ファンなら誰もが知っているように、「口取り式」は勝った馬と関係者がウイナーズサークルで写真を撮るセレモニーのことだ。
7話では、この「口取り式」が明確に三つの意味を持つように設計されていた。
1つ目は文字どおり、ロイヤルファミリーのデビュー戦を勝利で飾った「セレモニー」としての口取り式。
2つ目は、耕造から耕一への「バトンパス」の儀式。
- そこに立っているのは、かつて“いないことにされていた子”だった耕一
- 彼が堂々と馬主として馬のそばに立つ姿は、「隠し子」ではなく「正式な家族」として山王家に迎え入れられたことの視覚的な証拠になっている
3つ目は、視聴者にとっての「ロイヤルファミリーという作品タイトルの口取り式」。
- ロイヤルホープとハピネスの血統
- 山王家とノザキファーム、栗須たちの関係性
- 耕一の出生と葛藤
その全部が一枚の写真に凝縮されることで、「これがこの作品の核です」と提示する一枚になっていた。
タイトル回収が話題になったのも、「口取り式=作品全体の記念写真」になっていたからだろう。
隠し子ではなく“正統な後継者”へ――耕一の提案の意味
耕一は序盤で、耕造の申し出をはっきり断ります。
「ロイヤルの所有馬に引き継ぎたい馬がいない」という辛辣な言葉はヒヤッとするほど。
ただ本当に拒んでいたのは、“今あるものをそのまま引き継ぐこと”。
耕一は血統表を徹底的に調べ、自分なりの「正しい継承」の形を考えていました。
それが、
ロイヤルホープ × ロイヤルハピネス=ロイヤルファミリー。
- ホープのスタミナと勝負根性
- ハピネスの気性と体質
- 亡き母・美紀子の意志
これらを全部ひとつにまとめた馬であれば、初めて“自分が相続する意味がある”。
耕一が望んだのは「血の継承」と「心の継承」の両立でした。
栗須という“通訳者”――馬と人間のあいだのブリッジ
7話で最も光っていた人物は、やはり栗須。
耕造のぶっきらぼうな愛情、耕一のこじらせた優しさ、山王家の本音、加奈子や翔平の揺れる気持ち――これら全てを受け止め、“言葉”にして橋渡しする役割を担っています。
- 耕一の配合分析を耕造に伝える
- 相続や競走馬登録を山王家に説明する
- 加奈子の葛藤を受け止める
栗須は主役ではありませんが、物語の方向を整理する役割の中心にいる人物です。
「今この瞬間から、あなたが馬主です」
という一言は、20年分の夢を耕一へ正式に手渡す“宣言”のようにも聞こえました。
山王耕造の死に方が、あまりにもドラマチックで現実的
耕造の死に方が絶妙だった。
- 病室でロイヤルファミリーのレースを見届け
- ゴールの瞬間に涙を浮かべ
- 直接的な最期のカットは描かず、後から栗須の言葉で知らされる
いわゆる「死に芝居」を強調しないことで、かえって現実味が増していた。
視聴者としては、
「もっと社長の生きざまを見ていたかった」という喪失感と、
「社長らしい去り方だった」という納得感が同時に押し寄せる。
原作でも耕造の死は単なる悲劇ではなく「次の世代へのバトン」として描かれるが、ドラマ版はそこに“レース実況”という映像表現の強度を乗せてきた。
競馬のゴールと、人間の最期。
二つの「フィニッシュ」が重なる瞬間、画面にはドラマが積み上げてきた20年分の時間が圧縮されていた。
京子の「面白かったわ」は、冷たさではなく最高のラブレター
SNSで最も盛り上がったのが、京子の「面白かったわ」という一言の解釈だ。
これは完全に「最高のラブレター」だった。
裏切られ、振り回され。
何度も離婚を考えたであろう相手に対して、
なお最期に出てくる言葉が「楽しかった」ではなく「面白かった」なのが京子らしい。
「楽しい」は穏やかさや安堵を含むが、
「面白い」は波乱や理不尽も含め、感情の揺れ幅そのものを肯定する言葉だ。
京子は、
- あなたと生きるのは安全でも安心でもなかった
- だけど、退屈だけはしなかった
と、清濁あわせ呑んだうえで耕造の人生を承認している。
表面だけ切り取れば辛辣に聞こえるが、20年の夫婦の履歴を知っている視聴者にとっては、これ以上ないエンディング台詞だったはずだ。
ロイヤルホープとロイヤルファミリー――夢は「更新」され続ける
個人的に最も美しかったのは、ロイヤルファミリーが牧場を駆け抜けるシーン。
ホープほどのスター性はまだない。
それでも、耕造が小さく「いい匂いだ」とつぶやく表情には、“未来の才能”を嗅ぎ分ける馬主としての直感がありました。
夢のゴールは変わりません――有馬記念。
しかし、その夢を受け継ぐ者はホープからファミリーへ、そしてさらにその先の世代へと更新されていく。
- 加奈子と翔平の親子
- 椎名父子のライバル構造
- 佐木&百合子に生まれた新しい命
“血筋”というテーマを扱いながら、「血だけでは決まらない関係」も丁寧に描かれています。
耕一が継いだのは「事業」だけでなく「まなざし」
耕一の選択は、「隠し子ドラマ」の定型を超えてきたと感じた。
よくある展開なら、
- 財産争い
- 本妻と愛人サイドの対立
- 会社をめぐる権力闘争
に引っ張られがちだが、このドラマはそこをあえて前面に出していない。
耕一が継いだのは、
- 競馬事業という「箱」
だけでなく、 - 馬と人を信じて夢を見る「まなざし」
だった。
耕造の競馬は、自身の執念の延長だったが、耕一は
- チームとしてのロイヤル
- 新しい馬主仲間
- 馬を取り巻く構造そのもの
を変えていく“システム志向”のキャラクター。
口取り式に立った耕一には、“父と同じ場所に立ちながら、父とは違う未来を見ている男”の影が確かにあった。
耕造の死は悲劇であると同時に、耕一にとって「自分の物語のスタートライン」でもあった。
総評:7話は「未来の口取り式」へ向けた盤面を整えた回
まとめると、7話は
- 隠し子設定を“馬オタク設定”で美しく昇華
- 三者(三父子)の関係性が整理され、継承の構造が見えた
- ロイヤルファミリー誕生からデビュー勝ちまでのテンポ感が秀逸
有馬記念という最終ゴールが見えていても、その道のりでどれだけ感情を揺さぶってくるか――そこがこのドラマの醍醐味。
7話はその“助走”として非常に完成度が高く、「この先の口取り式」を想像させる回でした。
ザ・ロイヤルファミリーの関連記事
ザ・ロイヤルファミリーの全話ネタバレはこちら↓
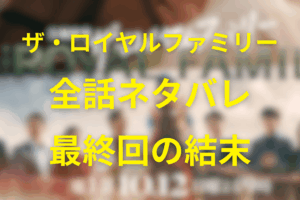
ザ・ロイヤル・ファミリーの原作についてはこちら↓
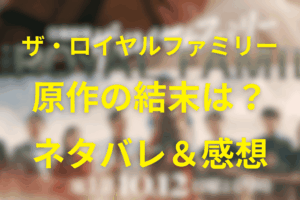
次回以降の話についてはこちら↓
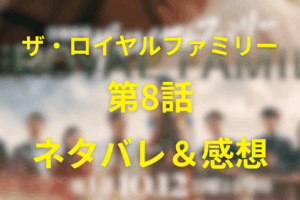
ザ・ロイヤル・ファミリーの過去についてはこちら↓
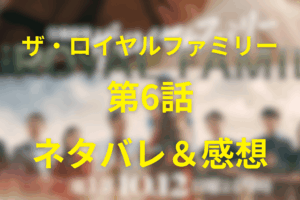
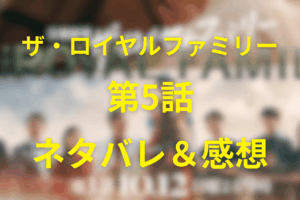
ザ・ロイヤル・ファミリーの目黒蓮についてはこちら↓
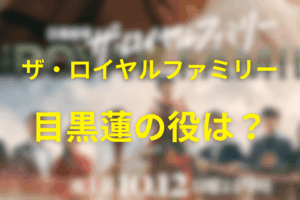
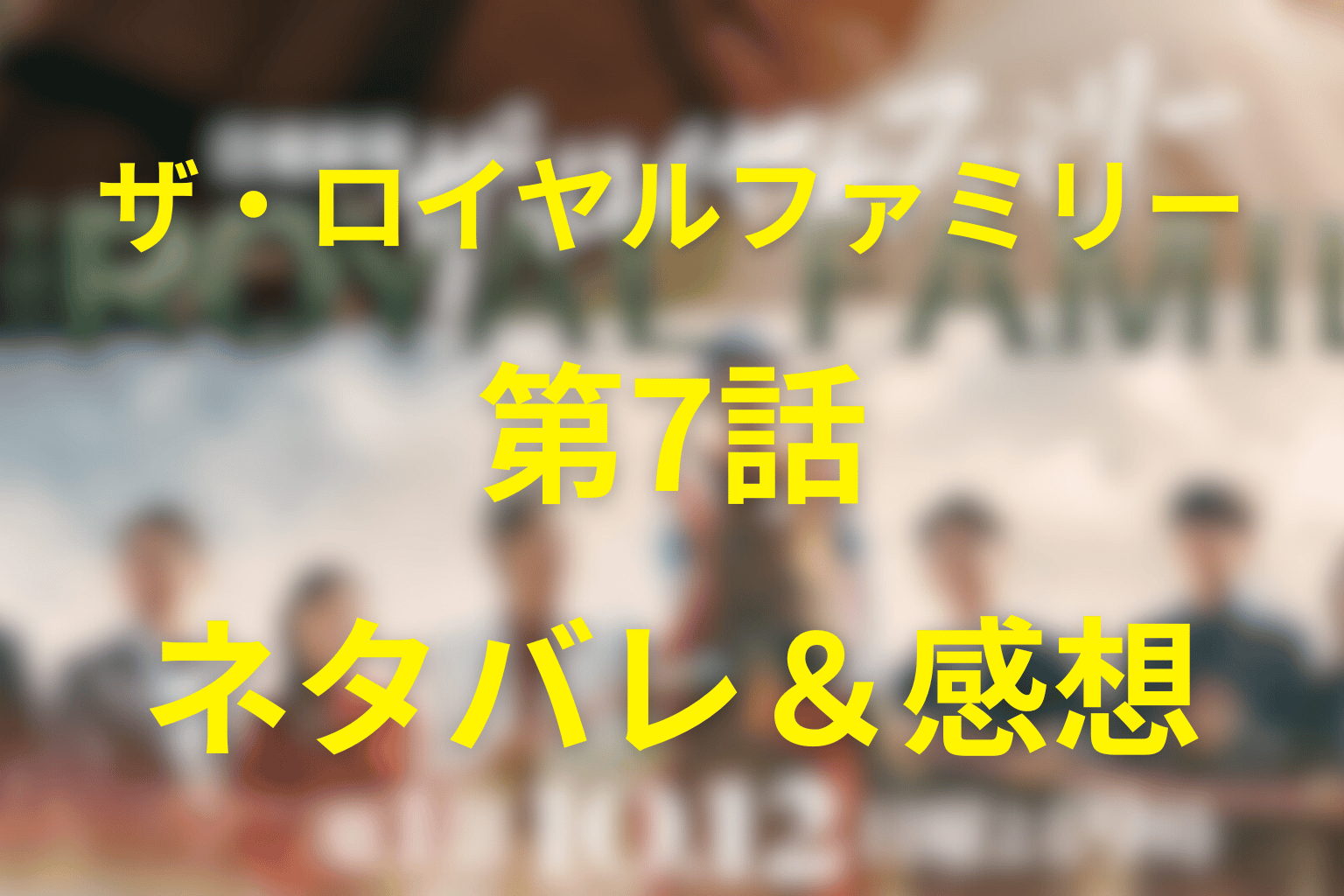
コメント