5話までで積み重ねられたWS劇場の勢いが、6話では“打ち上げ”という一夜を通して思わぬ形で揺れ始めます。
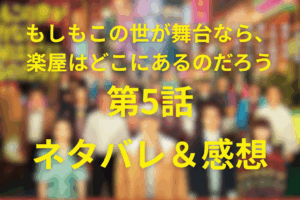
第6話は、久部三成(菅田将暉)が自らの限界と向き合い、演劇という営みの“修正力”を見出していく回だった。
初日の混乱から一夜、彼の前に現れたのは伝説の俳優・是尾礼三郎(浅野和之)。是尾が放った“絶賛でも酷評でもない”ひと言が、久部の心を再び動かしていく。
打ち上げで交錯する視線、静かに立ち上がる関係、そして「楽屋」とは何かという題の問い。
第6話は、敗北を終わりではなく始まりに変える、演劇の“再設計”の夜を描いた。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)6話のあらすじ&ネタバレ
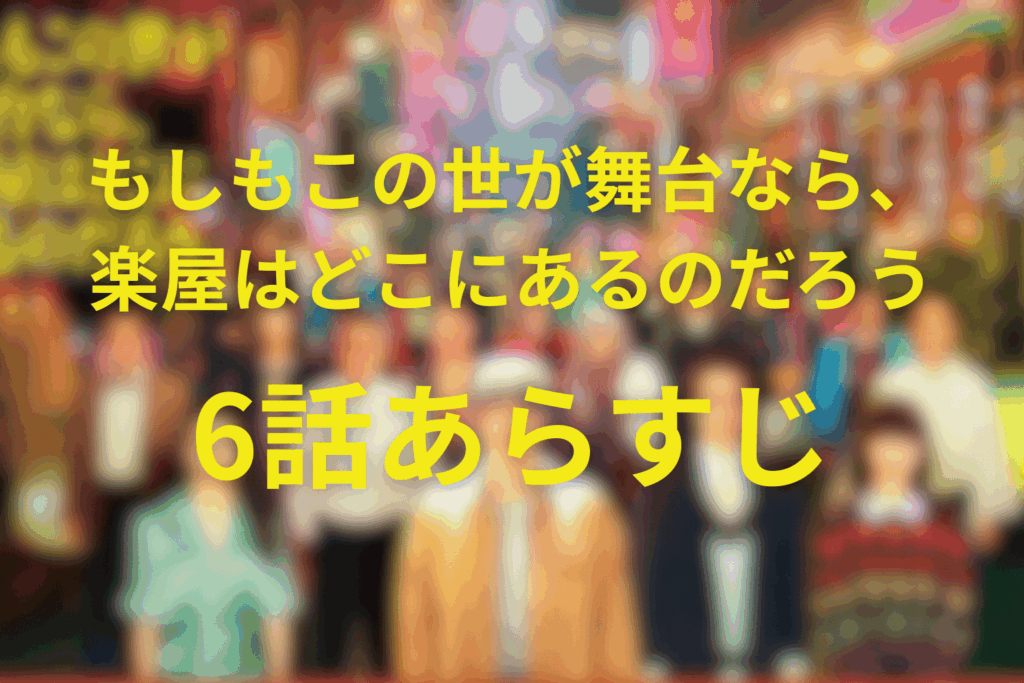
6話「ヘンリー八世」は、クベ版「夏の夜の夢」初日打ち上げの一夜を丸ごと切り取った回。
高揚と嫉妬、誤解と事故、そして“落ちぶれたスター”の現在が、一つの店の中で折り重なっていきます。
クベ版「夏の夜の夢」初日明けと、是尾礼三郎との出会い
クベ版「夏の夜の夢」の初日公演を終えたWS劇場。客席で久部三成は、日本を代表するシェイクスピア俳優・是尾礼三郎から声をかけられます。
是尾は久部が敬愛してやまない大御所俳優で、蜷川演出の舞台にも数多く出演してきた人物。久部は憧れの人に突然認められたような形になり、完全に舞い上がってしまいます。
是尾はクベ版「夏の夜の夢」に対して「ここは面白い」「ここは惜しい」と具体的なポイントを示し、一定の評価を伝えます。
演出家として自信を失いかけていた久部は、その言葉に救われたような表情を見せ、そのまま是尾を初日打ち上げ会場のジャズ喫茶「テンペスト」へと誘います。
テンペストへ向かおうとした久部の前には、メモ帳を手にした巫女・江頭樹里も姿を見せていました。舞台の感動を胸に、印象に残った台詞や演出を熱心にメモしてきた樹里は、久部に直接感想を伝えたい一心で待っていたのです。
樹里と蓬莱の距離が縮まる夜
久部が是尾を連れてテンペストに向かう一方、店の外では放送作家の蓬莱省吾が樹里と会話を始めます。蓬莱は久部の演劇への情熱を素直に褒め、樹里も「今日の芝居を観て、初めて舞台って楽しいと思った」と自分の変化を丁寧に言葉にします。
会話の中で、樹里の母が福岡出身で蓬莱も博多育ちだと分かり、二人は一気に距離を縮めます。これまで八分坂の人たちをどこか見下していた樹里が、少しずつ“同じ目線”で話し始める静かなターニングポイントです。
その頃テンペストでは、リカ、パトラ鈴木、浅野大門と妻のフレ、彗星フォルモンらが打ち上げの賑やかさで久部を迎える準備中。テレビプロデューサーと会ってきた王子はるおも合流しますが、上々の評価をもらった割に表情は晴れません。のちの“独立フラグ”を感じさせる空気がただよいます。
打ち上げ会場テンペストに集う面々
久部と是尾がテンペストに到着すると、店内にはWS劇場の面々に加え、風呂須マスターや仮歯もそろい、まさに「八分坂演劇オールスター」が集結。
久部は「安心と思う心が人の敵」と得意げに乾杯の音頭を取り、是尾を“伝説の俳優”として紹介します。
ほどなく樹里と父・論平も来店。久部と蓬莱が入口まで出迎え、樹里は久部の隣、論平は憧れのリカの隣に座ることに。“神社側”と“劇場側”が初めて同じテーブルにつく象徴的な瞬間です。
さらにテンペストにはジェシー才賀、モギリの毛利里奈、モネ目当ての若い巡査・大瀬六郎まで参加し、大所帯に。ジェシーが「今日の勘定は全部持つ」と宣言し、場はますます盛り上がります。
樹里VSリカの「楽屋トーク」バトル
久部が劇場から戻るまでの間、店内では“女同士の言葉のバトル”が勃発。眠った論平を挟み、カウンター席で向き合う形になった樹里とリカ。リカが「ご感想は?」と聞くと、樹里は素直に「とても素敵でした。役者さんが楽しそうで…」と笑顔で答えます。
しかしリカは、その一言一句に深掘りするような口調で質問を重ねます。
・役者が「楽しそう」と分かる根拠
・どれだけ舞台を観てきたのか
・戯曲と今回の舞台のどちらが面白いと思うのか
樹里が慎重に言葉を選ぶたび、リカは「それは違う」「使い方が間違っている」と論理で押し返す方向へ。最終的には「今日の公演こそ正しい」「もっと勉強しなさい」と突き放すような調子になり、樹里の笑顔は消えてしまいます。
涙をこらえた樹里は、眠る父を起こして外へ出ると、「やっぱりこの街、出て行こう。こんなところ大っ嫌い」と叫び、八分坂を駆け下りていきます。
彼女にとって“楽屋”の世界はまだ残酷で、息苦しい場所でしかないことが刻まれます。
うる爺の必死の稽古と、誤解からの決裂
同じ頃、劇場では“うる爺”がボトム役の台詞を完璧に覚えて久部を待っていました。
初日のアドリブ暴走を反省し、打ち上げにも行かず稽古に励んでいたのです。久部はその姿に感心し、「その芝居でいい」と称賛。うる爺も「台本通りにやるのが一番面白い」とやる気を取り戻します。
しかしテンペストに戻ると、警官の大瀬がうる爺の演技を完コピして店内を沸かせ、久部もそれを笑います。
その様子を入口で目撃したうる爺は、「自分は降板させられた」と完全に誤解。久部が慌てて弁解しても届かず、「そういうことなら早く言ってくださいよ」と笑顔でピースしながら店を去ってしまいます。
うる爺の事故、久部への非難、そして風呂須の一言
その後、大瀬が「老人がバイクにはねられた」という知らせを持って戻り、全員がうる爺だと確信。キャストが病院へ走る中、テンペストには久部、リカ、ジェシーだけが残されます。
ジェシーは久部に、「あなたの勝手なシェイクスピア熱で、WS劇場の人生が狂い始めている」と厳しく非難。久部が芝居をやろうと言わなければ、うる爺が打ち上げを欠席して稽古をし、誤解したまま事故に遭うこともなかった――と言われ、久部は反論できず沈みます。
しかし風呂須は違う視点を示します。「みんな大人で、それぞれ自分の人生を生きているだけだ」と久部に告げ、演出家一人の責任にするのは違うと諭すのです。
是尾の現在の姿と、謎の男トロの登場
一方、ジェシーは久部に、是尾が酒に溺れ業界から外れ、今はほとんど仕事がないという噂を明かします。久部はショックを受けます。
病院からは、うる爺が全治2カ月の骨折で命に別状はないと連絡。久部は「劇団は解散だ」と投げやりに言いますが、おばばは「じゃあ2カ月休演ね」と現実的に返します。
劇場から出た久部の前には、誘導棒を振って交通整理をする是尾の姿があり、久部は一夜で“憧れのスター”の現実を思い知らされます。
その直後、リカが店の外へジェシーを見送り戻ると、WS劇場の前には派手なシャツの男の姿が。「よう」と声をかけるその男は、リカの過去を知るトロ。
リカの顔に走る動揺を残したまま、6話は幕を下ろします。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)6話の感想&考察
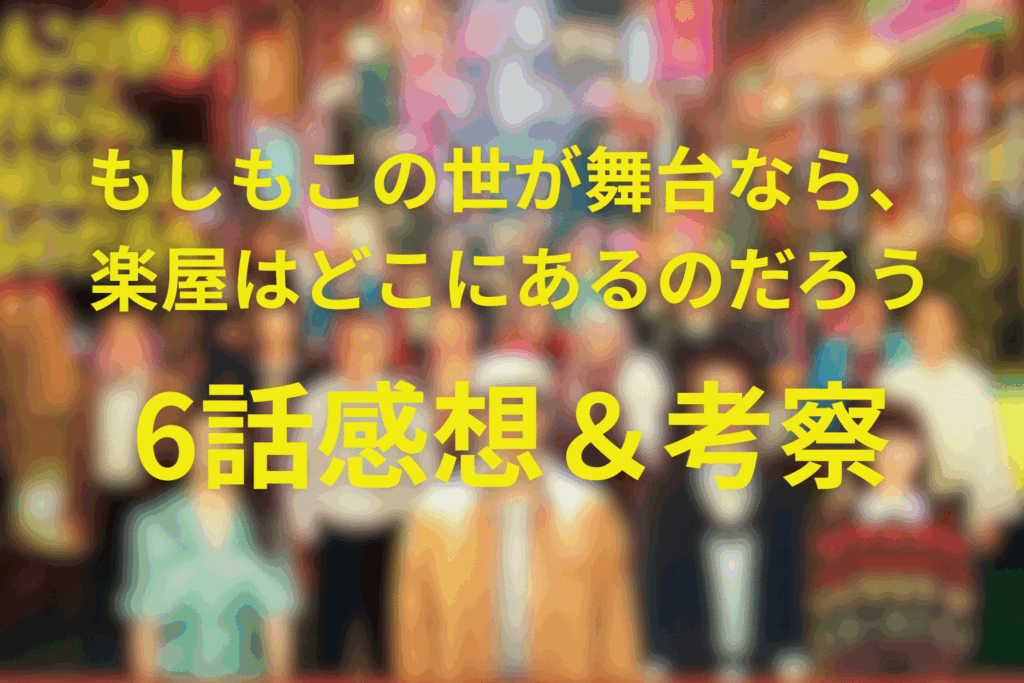
6話は一見「打ち上げ回」ですが、実際はこの先の第二幕に向けた“別れと再配置のフラグ集め”のような構造に感じました。
「落ちていく人」に石を投げるな、というテーマ
6話のモチーフになっているシェイクスピア作品は「ヘンリー八世」。劇中で引用される「落ちていく者をこれ以上責め立てるな」という趣旨の一節が、そのまま今回のテーマに重なっています。
落ちているのは誰か。
・アドリブ暴走からやり直そうとするうる爺
・かつての名優から、現在はバイト暮らしの是尾
・「出て行こう」と繰り返す樹里の心
・自分の理想と現実のはざまで揺れる久部
彼らは皆「下り坂」にいる人たちです。本来なら手を差し伸べるべきなのに、言葉ひとつ、空気ひとつが追い打ちになってしまう。
大瀬のモノマネは悪気ゼロの“場を盛り上げるノリ”で、久部の悪ノリも演劇人ならよくあるテンション。けれど、その軽さがうる爺のプライドに深く刺さる。リカの言葉も同様で、演劇愛ゆえの本気のマウントが樹里の無邪気さを踏みにじる。
「やめてやる今夜」というサブタイトルどおり、今回は“やめる”と言いたくなる人ばかりが出てきます。
でも、それは誰か一人の悪意のせいではなく、小さなすれ違いや空気の読み違えが積もって大事故に至る。ここに、三谷作品らしい人間の怖さと可笑しさがありました。
リカVS樹里のマウント合戦が映す「階層」と「目線」
リカと樹里の会話は、“意地悪”のひと言では片づけられない密度がありました。
リカは八分坂の底辺で生きてきたストリッパー。樹里は神社に守られて育った箱入りの巫女。二人の「当たり前」はまったく違う。それでも同じ舞台を前に向かい合う。
樹里は初めて心から楽しめた舞台の感想を、素直に言おうとしているだけ。でも経験が少ないから語彙も少ない。一方リカは、
・演劇に詳しくないくせに“分かった顔”をするな
・WS劇場を見下してきたくせに、今日だけ褒めるな
という怒りを、言葉のディベートに乗せてぶつける。どちらも“正しい”ことを言っているのがポイントです。
・樹里の「役者さんが楽しそうだった」は観客としての誠実な観察
・リカの「勉強してから語れ」は舞台人としての本音
本来ならゆっくり擦り合わせればいいのに、場末の酒場で丁寧な対話は難しい。だから樹里の「こんな街大っ嫌い!」は、八分坂という“舞台の外”への逃避願望として響いてしまう。
SNSでも賛否が割れ、「リカ怖い」「樹里が気の毒」と反応が分かれ、挑発的なシーンであることがはっきりしていました。
久部の未熟さと、風呂須が示した「責任」のライン
個人的に最も刺さったのは、久部の罪悪感と、それを和らげる風呂須の一言。
ジェシーの言い分は、ある意味で“正論”です。
・久部の「シェイクスピアをやりたい」という理想に周囲が巻き込まれた
・うる爺は失敗し、必死の稽古の末に事故へ
・久部は「自分が運命を動かしている」自覚が薄い
だから「人生が狂い始めている」と責めたくなるのも分かる。しかし風呂須は静かに線を引く。
・みんな大人で、自分の人生のハンドルは自分で持っている
・劇団に関わるのも離れるのもその人の選択
・座長が全員分を背負う必要はない
この二つを同じ回で提示するバランスが見事でした。久部はまだ未熟ですが、風呂須の言葉で「全部自分のせい」にも「全然関係ない」にも逃げない“中間地点”を探し始めるように見えました。
是尾礼三郎という「落ちたスター」が照らす、演劇の残酷さ
是尾の現在は、演劇の残酷さそのままです。
・かつてのシェイクスピア俳優
・今は酒に溺れ、本番遅刻で干され、交通整理のバイト
久部から見れば“自分の未来の可能性”でもある。
・理想を追いすぎて仕事を失う
・芸術性と生活が結びつかない
・それでも舞台への未練を抱えて生きる
誘導棒を振る是尾の姿は、華やかな舞台と生活の現実が同居する残酷な絵でした。
第7話以降で「冬物語」に関わってくる伏線を踏まえれば、彼は“落ちぶれた人”では終わらないはず。その助走となるのが6話でした。
6話が張ったフラグと、7話以降への布石
ここで6話が積み上げたフラグを整理すると――
・樹里の「八分坂なんて大嫌い」
→ それでも劇場に戻るのか、別の形で関わるのか。彼女と八分坂の和解はテーマに直結。
・リカと樹里の関係
→ 生き方の衝突。どこかで反転する可能性は充分。
・はるおの才能とフォルモン
→ 立場逆転の予兆。WS劇場の“笑い”が大きく揺れる可能性。
・うる爺の穴を誰が埋めるのか
→ 是尾の復活ラインは濃厚。救済か、さらなる切なさかの分岐点。
・トロの参戦
→ 恋と劇団のバランスが崩れ、物語の温度が跳ね上がる。
総じて6話は、「楽しい打ち上げの裏で人間関係の地盤が静かに崩れていく回」。視聴後のモヤモヤこそ“第二幕への入口”でした。
この世が舞台なら、まだ一幕のラスト。
本当の“楽屋”に戻る前に、一度つまずいておかないと次へ進めない――
6話はそんな苦い通過儀礼として機能していました。
もしがくの関連記事
全話のネタバレについてはこちら↓
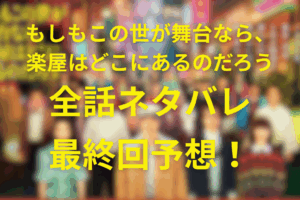
次回以降についてはこちら↓
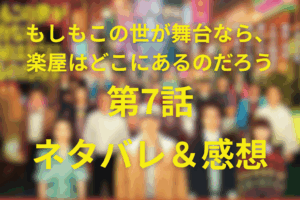
過去についてはこちら↓
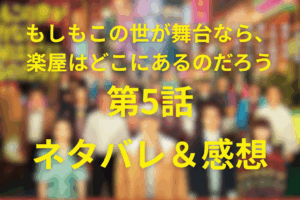
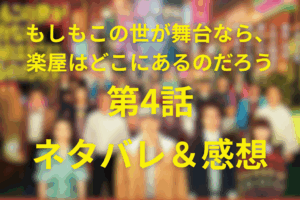
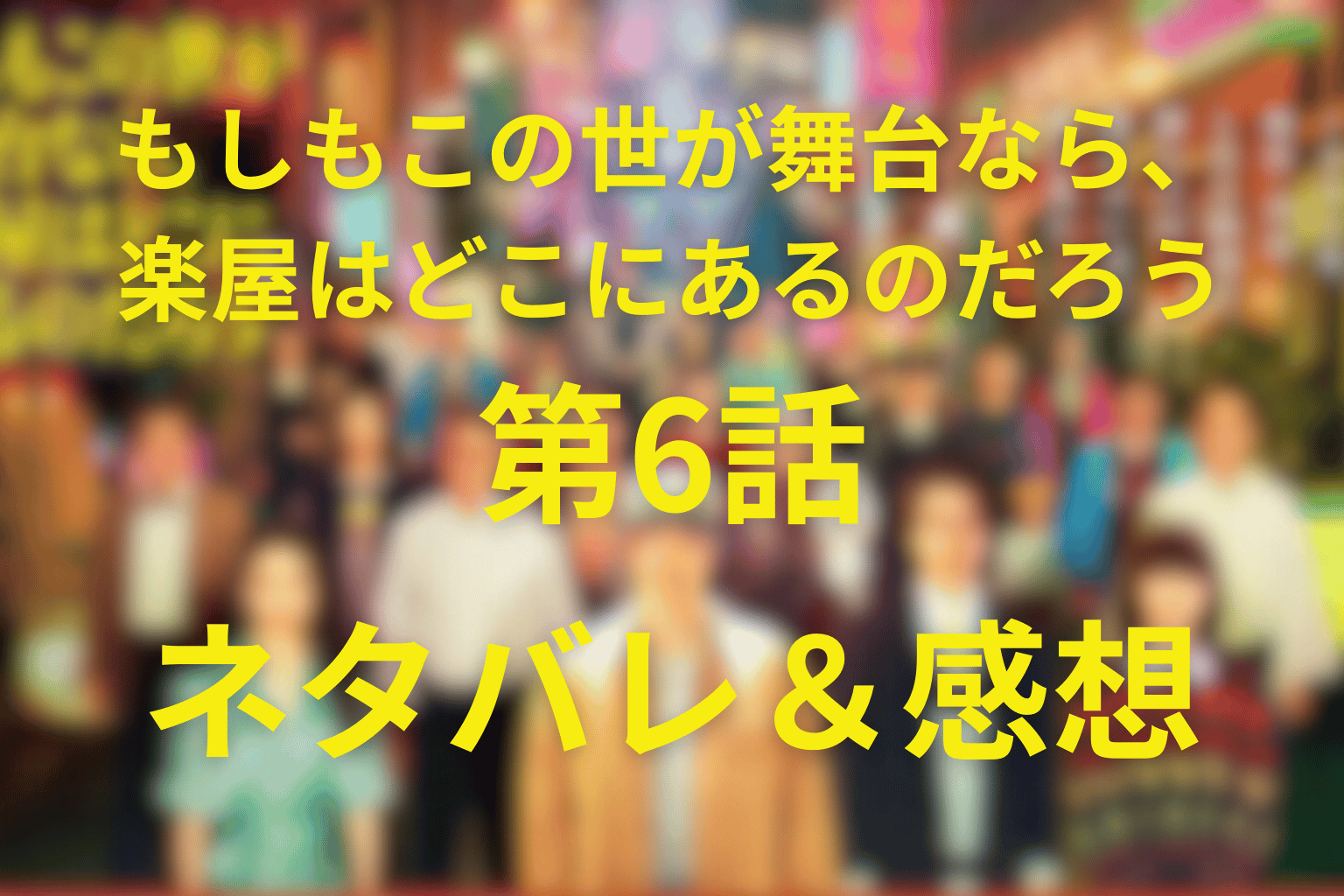
コメント