ドラマ東京P.D. 警視庁広報2係第3話で描かれたのは、犯人を追い詰める快感ではなく、「報道が人を追い詰める速度」の怖さでした。
広報2係は犯人を逮捕する部署ではありません。それでも、実名を出すかどうか、その一行の判断で、遺族の生活も世論も捜査の空気も一気に動いてしまう。
今泉麟太郎が“広報の人間”として本格的に机に根を張り始めた矢先、最も広報向きではない事件が降りかかる。第3話は、広報という仕事の「正解のなさ」を真正面から突きつける回でした。
※この記事は第3話の内容に触れます。未視聴の方はご注意ください。
「東京P.D. 警視庁広報2係」3話のあらすじ&ネタバレ
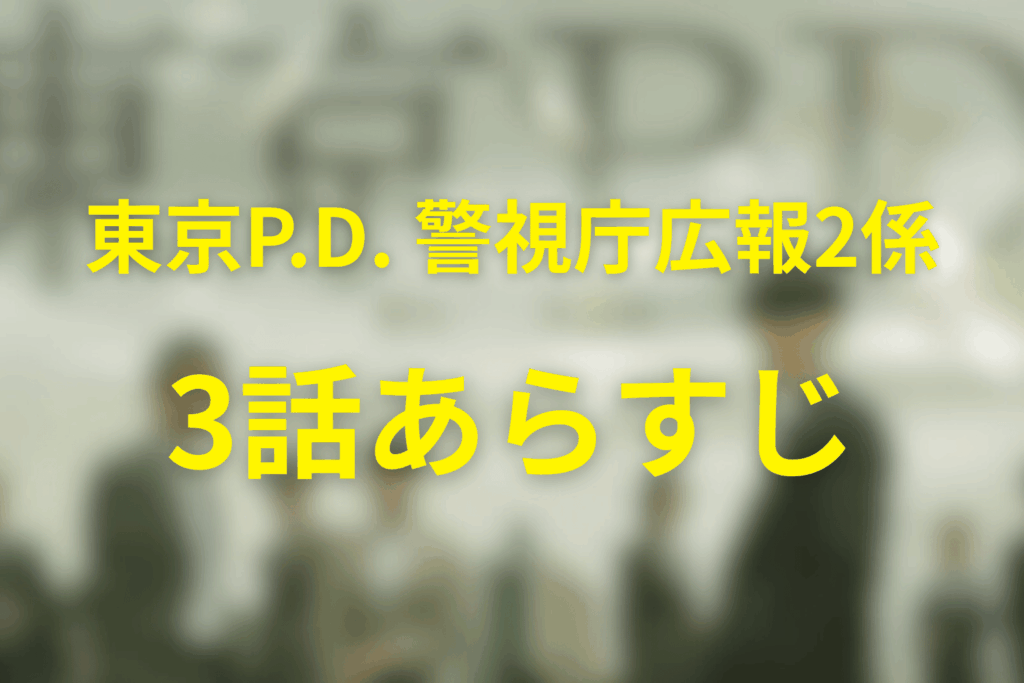
第3話で真正面から描かれるのは、犯人を追い詰めるサスペンスの快感というより、「報道が人を追い詰める速度」の怖さでした。
広報2係は、犯人を逮捕する部署ではありません。それでも、発表の一文・名前の扱い方ひとつで、捜査の流れも、被害者遺族の生活も、世論も、まとめて動いてしまう。
今泉麟太郎が“広報課の人間”として机に根を張り始めたタイミングで、最も広報向きじゃない事件――実名報道が火種になる連続遺体遺棄事件が降ってくる。ここが第3話の地獄の入口です。
序盤:机の上で始まる事件――今泉の「地味な一日」が崩れる
第3話の入りは、派手な現場ではありません。今泉は机に向かい、広報の作業を淡々とこなす。電話が鳴れば対応し、紙をめくり、資料に目を通す。
刑事ドラマでいう“面白いところ”が始まる前の、地味な時間。なのに、この地味さがこのドラマの怖さに直結してきます。
というのも、広報の仕事は基本的に「事件が起きてから」ではなく、「事件が世の中に出る前」に勝負が決まるから。
警察が何を言うか。何を言わないか。誰の名前を出すか。どこまで確定と言うか。
机の上の一行が、そのままテレビのテロップになる。ニュースの画面に出る“短い言葉”を、現場は何十回も迷って選ぶ。今泉は、その世界に足を踏み入れたばかりです。
木崎七恵の失踪:一本の連絡が「千葉山中の5遺体」へ跳ねる
そんな日常を切り裂くのが、20代女性・木崎七恵の失踪。ここから捜査は怒涛です。
七恵の足取りは、防犯カメラの映像で追われ、スマホの位置情報も手がかりになる。失踪直前に七恵と会っていた男がいる――それが川畑礼介。
警察は川畑を被疑者として逮捕し、七恵の行方を追う。でも、物語が一気に重くなるのはここから。
千葉の山中で見つかったのは、七恵の遺体だけじゃありませんでした。周辺からさらに4人の遺体が見つかり、合計5人。
「一人の失踪」から始まった話が、「連続性のある事件」へ姿を変える瞬間。ここで広報側の負荷も跳ね上がります。なぜなら、事件が大きくなるほど“質問の数”が増えるから。しかも、答えられることは増えない。
事件は大きくなるのに、確定は少ない。広報が一番嫌うタイプの展開です。
事件の骨格:SNSでつながった「自殺願望」と未成年被害者という爆弾
川畑と被害者たちは、SNSを通じてつながっていた。
しかも「自殺願望のある女性」と連絡を取っていたことが明らかになる。さらに被害者の中には未成年も含まれている――この組み合わせが、後半の“実名報道”問題を爆発させます。
自殺願望があった、という情報は、捜査の見立てに関わるだけじゃなく、報道によっては「被害者側の落ち度」のように消費されてしまう危険がある。
未成年が含まれる、という情報は、名前を出すこと自体が二次被害になる可能性をはらむ。
つまりこの事件は、捜査の難しさと同時に、情報を出すだけで被害者をもう一度刺してしまう“刺さりやすい構造”を持っているわけです。
広報2係は、ここで「事件の真相」ではなく「事件の伝わり方」を相手に戦うことになります。
今泉の“元記者のクセ”:ニュースの裏側を知る男が、広報になる苦しさ
今泉は元々、事件を「追う側」――記者として現場にいた人間です。だからこそ、今回の騒ぎを“他人事”として見られない。
実名が出れば、記者が遺族の家に行くことも、ネットが被害者のSNSを掘り返すことも、全部想像できてしまう。想像できるのに止められない。それが一番しんどい。
しかも今泉は、広報課に来てから「正しいことを言えば、世の中は正しく反応する」という幻想が崩れていくのを体感している最中。
正確に発表しても、切り取られる。配慮しても、叩かれる。沈黙しても、疑われる。
元記者の“手触り”が残っているほど、その理不尽が刺さってくる。今泉の苛立ちは、単なる感情じゃなく「仕組みへの嫌悪」に見えてきます。
実名を出すか:北川の慎重論と安藤の原則論がぶつかる
捜査一課長の北川一は、被害者の実名公表に慎重です。未成年が含まれている以上、発表が遺族の生活を壊すことは目に見えている。北川の逡巡は、現場の刑事としての“当たり前の情”でもあります。
一方で、広報課の安藤直司は、原則として「名前は出す」方向で動く。
安藤の論理は冷たく見えるけれど、彼が見ているのは“捜査と報道の現実”です。警察が公式に出さなかったとしても、記者は独自に動き、誰かの口から情報が漏れる。ならば、公式発表として最低限の正確性と線引きを担保するのが警察の責任だ――安藤はその立ち位置に立っている。
ここは「北川=優しい」「安藤=冷たい」ではありません。
北川が守りたいのは、被害者と遺族の今この瞬間の生活。
安藤が守りたいのは、捜査の継続性と、警察が嘘をつかないという前提。
守る対象が違うから衝突する。第3話は、その衝突を“善悪”に落とさず、現場の緊張として見せます。視聴者が簡単に気持ちよくなれないのは、たぶんそれが現実に近いから。
捜査一課長レク:実名と住所を読み上げる“手続き”が、火種を完成させる
結局、捜査一課長レクが開かれ、北川は被疑者・川畑礼介の実名と住所、そして被害者5人の実名と住所を読み上げます。
この場面が刺さるのは、読み上げが「正しい手続き」だからです。
レクは記者向けの説明会。警察は説明責任を果たしている。だから表面上は淡々と進む。
でも“読み上げる”という行為の中に、被害者の人が「事件」へ変換されていく瞬間がある。住所まで出るということは、遺族の玄関まで道がつくということでもある。現実の怖さが、手続きの中に潜っている。
さらに記者からは「殺人で逮捕できないのはなぜか」「殺人の可能性は見ているのか」と圧がかかる。北川は現時点で殺人で逮捕できないことを説明しつつも、捜査の方向性を問われると、濁しながら答える。
ここ、広報ドラマとして面白いのは、“捜査の真実”より“発表の表現”が重要になる点です。言い切れば炎上する。言い切らなければ不信が増す。お茶を濁すしかない状況が、逆に疑念を呼ぶ。レクは信頼の綱渡りなんだと痛感します。
レクの裏側:広報2係が抱える「線引き」と「責任」の重さ
レクの場面って、画面上は「北川が座って説明するだけ」に見えます。でも、実際にあの場に“北川の言葉”が出てくるまでに、警察内部では相当な擦り合わせが走っているはずです。
発表する事実は何か。まだ確定していないのはどこか。言い回しをどうするか。被害者が複数の場合、順番や表現で余計な誤解が生まれないか。未成年が含まれるなら、どこまで触れるか。
広報2係は、捜査一課の「言いたい」と、遺族の「言わないでほしい」と、記者の「もっと出せ」の三方向に引っ張られながら、“落としどころ”を作らないといけない。これ、精神的にはほぼ交渉人です。
今泉がきついのは、ここで“正しさの軸”が一本じゃないこと。
捜査のために出す情報と、遺族のために隠す情報は、同居できない瞬間がある。しかも、情報を隠すと「警察が隠蔽してる」と疑われる。情報を出すと「遺族を傷つけた」と責められる。
広報は、どっちを選んでも叩かれる運命にある。その運命を理解した上で、なお選ばなきゃいけない。第3話は、今泉がそこに本格的に放り込まれた回でもあります。
「警察が言った」=「報道が出す」ではない:実名を出すかは各社の戦場
警察が実名を読み上げた――ここで視聴者が勘違いしがちなのが、「じゃあ実名で報じられるのは仕方ないよね」という短絡です。
実際には、警察の発表と報道の判断は別。警察は“公開情報”として提示しただけで、報道は“どう伝えるか”を各社で決める。つまりこの問題、責任が一箇所に集まらない。だからこそ泥沼になります。
第3話は、その“判断の分散”をちゃんと描きます。誰か一人が悪いのではなく、構造として起きる。構造だから止めづらい。
そして広報2係は、構造の真ん中に立たされる。警察の顔として批判も受けるし、記者の圧も受けるし、遺族の怒りも受ける。これ、精神的に一番キツいやつです。
YBXテレビの選択:実名報道を先に出す「勝負」と稲田の葛藤
ここで描かれるのが、YBXテレビの判断。社内では、実名を伏せたい空気もある。世論の反発が怖いし、遺族への二次被害も想像できる。
それでも記者・稲田裕司は「報道する意味」を押し通し、どこよりも早く実名で報道する。
この“先に出す”って、視聴者はつい「スクープ競争」として見がちです。でも現場目線で言えば、「一社が実名に踏み切った瞬間、他社が実名を伏せる理由が弱くなる」んですよね。
伏せれば「隠している」と言われ、出せば「人でなし」と言われる。
つまり報道各社は、正解がないのに“正解っぽい顔”をし続けないといけない。稲田が考え込む描写が入るのは、彼が単なるイケイケ記者じゃなく、重さを理解しているからだと思います。
実名報道が“捜査に効く”理由:広報が恐れつつも否定できない現実
第3話がいやらしい(褒めてます)のは、実名報道を「悪」と断罪しない点です。
実名が出ると、遺族が壊れる。これは事実として描かれる。
でも同時に、実名が出ると“情報が集まりやすい”のも現実として置かれる。
たとえば、被害者が複数いる事件では「この名前、見たことがある」「この人、うちの近所で見たことがある」「あのアカウント、前にやり取りしていたかもしれない」みたいな“断片”が世の中のあちこちに眠っている。
匿名だと、その断片は結びつかない。実名だと、結びつく可能性が上がる。広報が苦しいのは、遺族の痛みを知りながらも、その“結びつき”を捜査にとって無視できない点です。
だから安藤の原則論は、冷たく見えても筋が通ってしまう。
警察が出さない=守った、ではなく、警察が出さない=誰かが勝手に出す、になりがち。
そして勝手に出された情報は、正確性も配慮も保証されない。
この構造を知っているほど、広報は「出す/出さない」を単純に選べない。第3話は、そこを視聴者に一緒に背負わせてくる回です。
実名報道の直撃:木崎家が崩れていく
実名で報道された被害者・木崎七恵。ここから一気に“被害者側の時間”が映ります。
木崎家では、母親が日に日にやつれていく。目が落ち、声が落ち、食べられなくなっていく。
彼女が漏らしかける言葉は、「遺族の自責」を象徴していて、とにかく胃が痛い。妹が母を抱きしめるしかないのも辛い。妹だって被害者なのに、母を支える役に回ってしまう。
こういう場面、犯人が捕まっているとか、捜査が進んでいるとか、そういう“事件ドラマの文法”が一切救いにならないんですよね。ニュースが続く限り、痛みが更新され続けるから。
巻田家の地獄:ポストに行くだけで囲まれ、会社で謝らされる
さらにきついのが、別の被害者・巻田の家の描写。
父親の親戚筋の家にまで記者が押しかけているという連絡が入り、父親は追い詰められる。ポストに行くだけで記者に取り囲まれる。
ここが地獄なのは、「事件の加害者は川畑なのに、遺族が“謝る側”になる」点です。
会社に電話が入れば、父親は頭を下げる。周囲の視線が怖くなれば、外出もできない。
犯人が捕まっても生活は戻らない。むしろ“捕まったからこそ”取材が加速する。実名報道の副作用が、一番弱いところに刺さっているのが見えてしまう。
SNSの暴力:被害者のSNSが晒され「被害者なのに叩かれる」
追い打ちになるのがSNSです。被害者のSNSがさらされ、炎上する。
「被害者なのに叩かれる」――この現象が出てきた瞬間、事件は“現実の社会問題”として視聴者に迫ってきます。
自殺願望があった、という情報が出れば、勝手に「自業自得」方向へ話が曲がる。SNSが特定されれば、真偽不明の投稿や、似た名前の別人まで巻き込まれる。
ネットの“正義”は、被害者の尊厳を守る方向に必ずしも行かない。今泉が怒りを抑えられないのも当然で、広報としての言葉の戦い以前に、人として耐えられない現場です。
ここまでの流れを一度整理:第3話の前半は“情報が暴走するフェーズ”
ここまでの第3話を、時系列で一度だけ整理しておきます。事件の情報量が多い回なので、ここを押さえると後半の感情の動きが追いやすいです。
- 木崎七恵の失踪 → 防犯カメラ&位置情報で川畑礼介が浮上
- 千葉山中で七恵の遺体発見 → 周辺からさらに4遺体が見つかり「5人事件」に
- 川畑がSNSで自殺願望のある女性と接触していた疑い、被害者に未成年が含まれる事実が判明
- 実名公表をめぐって警察内部で揺れ、レクで実名と住所が公表される
- 各社が実名報道に踏み切り、遺族取材とSNS炎上が連鎖する
この段階でドラマが描いているのは、犯人のトリックより「情報が出た瞬間に人が壊れていく」速度です。刑事ドラマの“捜査パート”より、広報ドラマの“社会パート”が前に出るのが第3話の特徴。
夜の合流:広報2係が「現場の匂い」を取り戻す時間
夜、今泉は広報2係の面々と合流します。熊崎、時永、水野、玉田――それぞれが、それぞれのやり方で“報道の渦”を受け止めている。
ここが良いのは、チームがただの仲良し集団じゃないところ。
今泉は元記者で、報道の論理も知っているからこそ怒る。
熊崎は感情が表に出るタイプで、被害者を叩くネットに強い嫌悪を持つ。
時永は比較的冷静だけど、冷静でいられること自体が罪悪感につながりそうな顔をする。
水野と玉田も、言葉数は少なくても「これは簡単な案件じゃない」と目で分かる。
事件の大きさに比べて、広報ができることは少ない。その少なさを、メンバー全員が理解しているから空気が重い。
そして一行は、安藤と下地が待つ店へ向かう。まるで作戦会議。だけど出てくるのは作戦ではなく、「どうすれば誰も壊さないで済むのか」という、答えのない問いばかりです。
巻田家へ:代表取材の提案が“正論なのに刺さる”
安藤のスマホが鳴り、今泉は安藤と共に巻田家へ向かいます。
安藤が提示したのは代表取材という整理案。
複数社が一斉に押しかけるのではなく、限られた枠で取材し、それを共有する。遺族の負担軽減としては理にかなっています。安藤らしい、現実の落としどころ。
でも巻田父は、その提案を受け取る余裕がない。
「そもそもお前らが記者に情報を流すからだろ」「帰ってくれ」「弁護士に頼む」
彼の怒りは、論理への怒りじゃない。生活が壊れたことへの怒りで、誰かを責めないと立っていられない怒りです。
ここで今泉が食らうのは、広報の現場あるあるだと思います。
正しい手順を踏んでも、相手の痛みを減らせない。むしろ“正しい提案”ほど、「それでも何も戻らない」事実を突きつけるから刺さる。
安藤が黙る時間があるなら、あれは“言葉がない”というより、“言葉が無力”だと知っている沈黙なんだろうな、と想像してしまいました。
要望書と通達:取材抑制でいったん静まるが、事件も静まる
その後、被害者側から要望書が届き、広報は「今後、被害者への取材は控えるように」と通達を出します。
ここでテレビは匿名報道へ切り替わる。遺族の家に押しかける画が減り、ひとまずは“鎮火”する。
しかし、鎮火したのは炎上だけじゃなく、事件そのものの熱でもありました。
しばらくして報道は小さくなり、今泉は記者から事件の話を聞かれなくなる。捜査一課に寄せられる情報も少なくなっていく。
安藤が今泉に言う「実名報道がされなければ、こういうことになる」。
この一言が残酷なのは、広報の“勝ち筋”がないことを示しているからです。実名にすれば遺族が潰れる。匿名にすれば事件が薄まる。
どっちに転んでも傷が残る。だから広報は、常に「どの傷を小さくするか」を選ぶしかない。第3話はそれを、綺麗事なしで見せつけてきます。
取材抑制の副作用:広報に「苦情」と「要求」だけが残る
取材を控えるように通達を出し、報道が落ち着く。表面上は“平和”に見えるんですが、広報の現場は別の意味で忙しくなります。
取材が減る=問い合わせがゼロになる、ではない。むしろ「なぜ名前を出した」「なぜ出さない」「なぜ殺人で逮捕しない」「警察はちゃんとやってるのか」という、答えにくい苦情と要求が飛び込みやすくなる。
レクで説明したはずなのに、説明したからこそ文言が切り取られて叩かれる。広報2係が“火消し”ではなく“燃料管理”をしている感じが、じわじわ効いてきます。
ここで今泉が学ぶのは、広報の仕事が「ニュースを作る」でも「ニュースを止める」でもなく、「ニュースになった後の社会の揺れ」を受け止めることだという現実。
そして、その揺れは“正しい説明”では止まらない。止まらないのに、説明し続けないといけない。第3話はそこがきつい。
稲田の炎上:実名を出した側も、守られない
匿名報道に切り替わると、今度は逆方向の炎上が来ます。現場中継で事件を報道していた稲田が「人でなし」と叩かれる。
ここで嫌なのは、叩いている側が「遺族のため」と言えるところです。
遺族のために叩く。正義のために叩く。
でも叩かれるのは、現場で判断を背負った一個人。
そして叩かれる様子がまたニュースになる。燃料が循環する。
この循環構造、今泉が広報になって一番嫌うやつだと思います。広報は“火を消す”仕事なのに、火はいつも別の場所で勝手に燃えるから。
稲田が実名に踏み切ったのは、競争心だけじゃなく「事件を風化させない」「捜査に資する」という理屈もある。
でも世論は、その理屈を理解する前に“誰かを吊るす”。
実名で叩かれ、匿名で叩かれ、どっちでも叩かれる。
報道の現場も、警察の広報も、どこにも安全地帯がない。第3話はこの“逃げ場のなさ”がしんどい回です。
現場検証:川畑礼介は殺人を否認し「自殺幇助」を主張する
事件の核心に戻ると、川畑は現場検証に立ち会わされます。そこで彼は被害者の殺害を否認し、遺体遺棄は認めつつ「自殺幇助だ」と主張する。
この主張が厄介なのは、“被害者側に自殺願望があった”という事実が背景にあること。川畑はそこを盾にして、自分を「救済者」みたいに装うことができてしまう。
さらに川畑と被害者が匿名性の高いアプリでやり取りしていた場合、やり取りのログが残りづらく、直接証拠が薄くなる。
捜査の現場としては「殺した」ことを立証しないと殺人にならない。川畑はその穴を最初から狙っているように見えるのが、また嫌なリアリティです。
「自殺幇助」主張が怖いポイント:法的なラベルが世論のラベルになる
川畑が繰り返す「自殺幇助」という言葉、ここはストーリー上の爆弾です。
なぜなら、法的に“殺人”と“自殺幇助(同意があった/自殺に関与した)”では、見え方がまるで変わるから。
ざっくり言うと、殺人は「本人の意思に関係なく命を奪った」。
一方で自殺幇助のニュアンスは、世間の受け取り方として「本人も望んでいた」「望んだ結果を手伝った」に寄りやすい。もちろん、望んでいたから何をしてもいいわけがないし、弱っている人に付け込む行為は卑劣です。でも“ラベル”が変わるだけで、被害者への視線が一気に冷たくなる危険がある。
だから今泉たちは、「捜査として殺人を立証したい」だけじゃなく、「社会の目線から被害者を守りたい」という意味でも必死になる。
捜査の勝敗が、そのまま世論の勝敗になる。
広報ドラマとして、第3話が一番ゾッとするのはそこです。
取調室の川畑:余裕と軽さが、遺族の痛みをさらにえぐる
取調室での川畑は妙に余裕があります。「新しい情報なんて出てこないんじゃないですか?」と挑発し、「早く裁判して罪を償いたい」と言いながら、出所後の旅行の話まで平然とする。
ここ、視聴者としては腹が立つんだけど、同時に怖い。
この手のタイプは「自分の物語」を作るのがうまい。
自分は殺していない。望みを叶えただけだ。だから長くは入らない。出てきたら好きに生きる。
もしこの理屈が裁判で通ってしまったら、遺族は二度殺される。今泉が「自殺で処理されれば、被害者はもっと叩かれる」と焦るのも、その未来が見えてしまうからです。
被疑者宅の捜索:巨椋が突きつける「殺人の証拠がない」という現実
終盤、今泉は被疑者の家の前に立ち、捜査一課の巨椋雅史と合流します。巨椋は白手袋を渡し、今泉も捜索に加わる。
そこで告げられるのが、「この家の中には、ヤツの殺人を示す物は何一つ出てこなかった」という現実。
これ、ドラマ的には“ここで証拠が出る”方が気持ちいい。でも現実は逆で、証拠が出ない方が多い。証拠がないと殺人が殺人にならない。
今泉の「何で殺人が殺人にならないんですかね?」は、捜査の無力感であり、広報としての恐怖であり、被害者側への申し訳なさでもある。
川畑は秘匿性の高いメッセージアプリを使っていたことを追及される。そこで彼が口にする理屈がまたイヤで、“内面の深い部分は死んだ後に誰でも見られたくない”という、人間の弱さを利用した逃げ道に聞こえる。
匿名性、SNS、消えるやり取り、証拠が残らない構造。
現代の犯罪は、現代のツールで“立証を難しくする”。第3話はその厄介さを、広報ドラマの角度から突いてきました。
ラスト:事件の熱が引くほど、広報は苦しくなる
匿名報道に切り替わり、事件の扱いは小さくなる。今泉も記者に事件を聞かれなくなる。
ここで“静かになる”のが怖いのは、事件が静かになったわけじゃないからです。被害者の人生は終わっている。遺族の生活は壊れている。捜査はまだ詰んでいる。
なのに世間だけが「次のニュース」に移っていく。その移り気のスピードに、広報は置いていかれる。
そしてもう一つ、静まり返った時に浮かび上がるのが「誰が責任を取るのか」という問題です。
実名で傷ついた遺族に対して、誰がどう償うのか。匿名にして風化した事件に対して、誰がどう責任を負うのか。事件の責任は犯人にある。それは大前提。でも“二次被害の責任”は、犯人だけでは完結しない。
広報2係は、その曖昧な責任の受け皿になってしまう。だから今泉の顔から、簡単に晴れが戻らない。
第3話の終盤は、今泉が「広報の仕事」を“嫌いになりかける瞬間”でもあると思いました。
現場に行って犯人を追い詰める方が、まだ分かりやすい。
でも広報は、解決してもしなくても叩かれる。守っても守らなくても誰かが泣く。
その理不尽を受け止めた上で、なお次の発表の言葉を選ばなきゃいけない。この地味な地獄が、次回以降の今泉の成長(あるいは折れ方)につながっていきそうです。
普通の刑事ドラマなら「静かになった=解決に近づいた」みたいな空気が出ることもある。でもこの作品は逆。静かになった分、誰も事件を覚えていない方向へ進んでいく。
守りたいものが多すぎて、誰も完全には守れない。実名を守れば遺族が壊れ、匿名を守れば事件が薄れる。
第3話は、広報の仕事が「正義の実現」ではなく、「社会の破綻を小さくする調整」だと突きつけてきた回だったと思います。
そして、だからこそ次が怖い。
世論の波が引いたとき、川畑の“自殺幇助”の物語が固定されたままになれば、被害者は永遠に叩かれ続ける。捜査が殺人を立証できなければ、広報は何をどう発表するのか。
事件が終わっていないのに、世間だけが終わらせていく――第3話のラストは、その不穏さを残して幕を閉じます。
第3話の要点まとめ:広報2係に突きつけられた「3つの現実」
最後に、第3話で今泉たちが突きつけられた現実を、僕なりに3点だけメモしておきます。物語を追う上でも、ここが頭に入っていると次回以降の“判断”が見やすくなるはず。
- 実名は武器であり、凶器でもある
情報提供や捜査の追い風になる一方で、遺族の生活を壊し、被害者の尊厳を二度殺すリスクがある。 - 匿名は守りであり、風化のスイッチでもある
遺族を守れる可能性が上がる一方で、世の中の関心が急速に離れ、事件が薄まる(=捜査の熱量が落ちやすい)怖さがある。 - 「証拠がない」時代の犯罪は、社会のラベルで人を殺す
川畑の“自殺幇助”の物語が固定されれば、被害者は「被害者」ではなく「叩いていい対象」にされてしまう。捜査の立証が、そのまま世論の立証になる。
第3話は、広報という仕事の“正解のなさ”を、これでもかと見せつけてきました。爽快感の代わりに、後味の重さが残る。でも、その重さがこのドラマの武器だと思います。
「東京P.D. 警視庁広報2係」3話の伏線
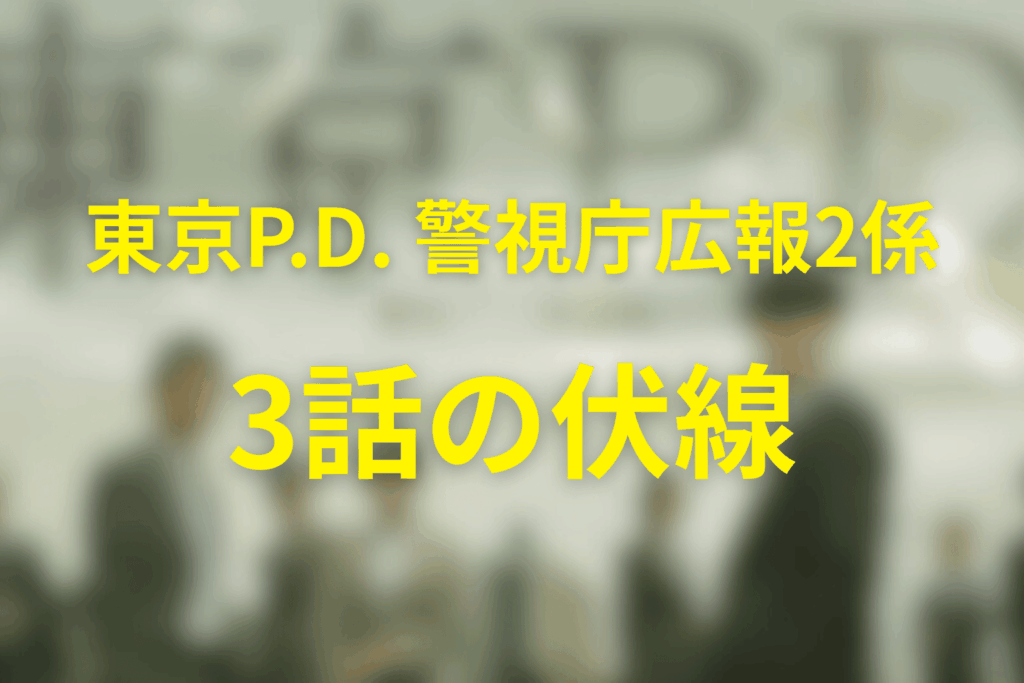
3話は「実名報道の是非」という大テーマで完結したように見せつつ、実は“次に燃える火種”をいくつも仕込んだ回でした。
このドラマの伏線って、犯人当てだけじゃなく「情報が出た後に何が起きるか」「誰が得して、誰が損するか」まで含めて効いてくる。ここでは、3話時点で未回収の“引っかかり”を整理しておきます。
川畑礼介の主張「遺棄だけ/自殺幇助」が成立する“穴”はどこか
川畑は殺害を否認し、「やったのは遺棄だけ」と言い張る。ここが3話の一番イヤなところで、彼の言い分は“論理の穴”に寄りかかっているんですよね。
未回収ポイントは大きく3つ。
- 死亡に至る“具体のプロセス”がまだ見えていない
5人の遺体が見つかった事実は重いのに、川畑がどう関与したのかが曖昧なまま。
ここが曖昧だと、川畑の「自殺を手伝った」物語が世論に固定されやすい。今後、死因や現場状況(同じ手口の反復、遺棄のパターン、準備の痕跡など)がどこまで出るかが勝負になります。 - 匿名性の高いアプリ=“証拠が残らない前提”で動いていた可能性
やり取りの痕跡が薄いほど、立証が難しい。逆に言えば、川畑が最初から「捕まっても殺人にはならない」未来を見ていた可能性がある。
デジタルの証拠(端末解析、クラウド同期、別端末、課金履歴)をどこから崩すかが、4話以降の捜査パートの大きな縦軸になりそうです。 - 単独犯にしては“処理”が重い
5人分の遺体遺棄を一人で回せるのか。車、運搬、山中の場所の選定、時間。
もし協力者がいるなら、ここが一番先に滲むはず。川畑の周辺人物や、SNS上のつながりが今後の伏線になります。
「実名→匿名」の切り替えで、誰が得して誰が損したのか
3話は、被害者実名の公表をめぐって北川と安藤が衝突し、結果として捜査一課長レクで被疑者と被害者の実名・住所が読み上げられる流れでした。
ここで伏線として残るのは、“その後”です。
- 実名報道で遺族が崩れる(損)/一方で世間の関心が上がる(得)
そして抗議・要望書を経て匿名に切り替わると、世間の関心が薄れ、捜査本部に寄せられる情報が減る(損)。
つまり「遺族を守る」と「捜査の熱量を保つ」がトレードオフになっている。
この構図、今後の事件でも必ず繰り返されるはずで、広報2係が“毎回同じ地獄”をどう処理するのかがシリーズの縦軸になりそうです。 - “住所”まで出した意味が重い
名前だけじゃなく住所。ここは演出として強烈でした。
住所は取材の導線にもなるし、ネット特定の導線にもなる。つまり「一度出たら戻らない情報」。
これを出したという事実が、今後「警察はどこまで出す組織なのか」という不信の種にも、逆に「警察は逃げない」という信頼の種にもなり得る。どちらに転ぶかは、次の対応で決まります。
稲田裕司という“報道側の爆弾”が、今後も物語を動かす
YBXテレビがどこよりも早く実名で報道に踏み切った。その決定を押し切ったのが稲田。
ここは単なる“嫌な記者”の配置ではなく、今後の展開装置だと思っています。
- 稲田が実名を押す=警察発表の影響力が可視化される
- 稲田が揺らぐ=報道の正義が崩れる瞬間が描ける
- 稲田が燃える=広報2係が「メディアを守る側」にも回らざるを得ない
3話の時点で稲田が“考え込む”描写が入ったのは、「俺は正しかった」と言い切れない人間だという伏線。ここが今後、今泉と交差していく気がします。
今泉麟太郎の「元記者の視点」は、武器にも凶器にもなる
今泉は、広報の仕事に慣れ始めた矢先に、この事件で“言葉の結果”を見せつけられた。
ここから先の伏線は、事件よりむしろ今泉自身です。
- 今泉は「出す/出さない」ではなく「どう言うか」に執着し始めるはず
元記者だから、切り取られ方・燃え方が分かる。だからこそ、言葉を設計しようとする。
でも設計した言葉ほど、現場の感情と衝突する。今泉が“広報の人間”になっていくのか、逆に“記者の目”を捨てきれず壊れるのか。ここがシリーズの大きな縦軸。 - 「正しさ」で殴られる世界に、今泉がどう耐えるか
実名を出しても叩かれる、匿名にしても叩かれる。
この構造を理解した時、人は冷たくなるか、燃え尽きるか、どちらかに寄りやすい。今泉がどっちに寄るかが、次回以降の伏線です。
“広報は捜査の外側”という建前が、次に崩れる兆し
3話は広報が「報道の渦を受け止める側」になった回でした。けれど、川畑の事件は証拠が薄く、情報提供も減り、捜査は膠着していく。
この状態が続くほど、広報2係は「発表」だけでは済まなくなる。つまり、広報が捜査に踏み込む圧が増える。
このドラマは、広報が“現場の代わりに戦う”物語でもあるので、次に崩れるのは「広報は事件解決に関係ない」という建前だと思います。3話は、その崩壊の助走でした。
「東京P.D. 警視庁広報2係」3話の感想&考察
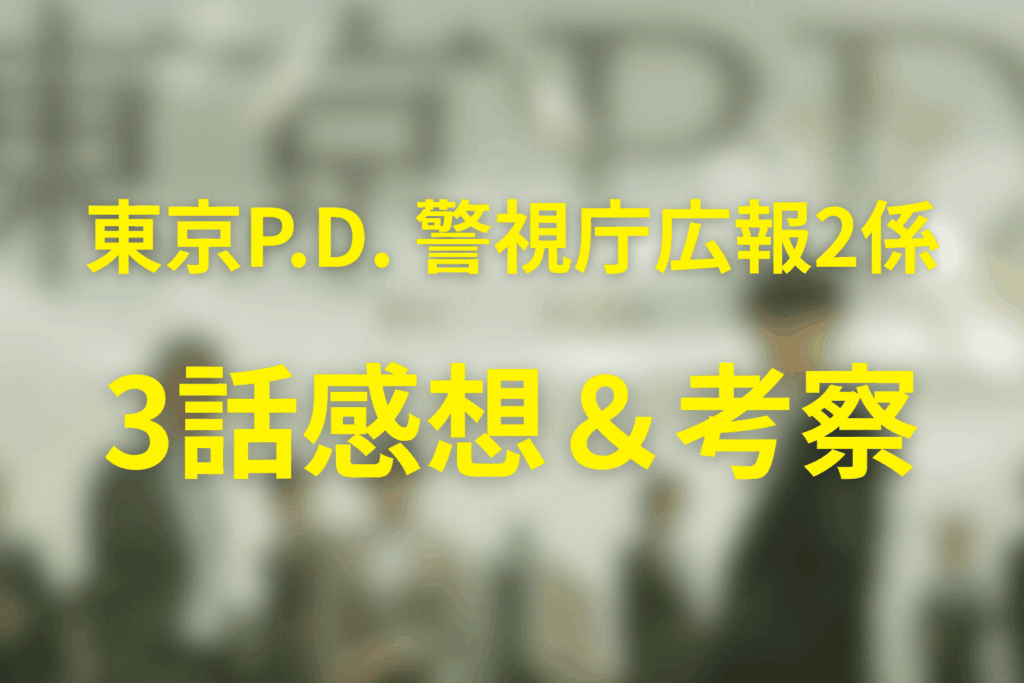
3話を見終わって最初に出た感想は、正直「しんどい」です。
でも、このしんどさって、ドラマが下手だからじゃない。むしろ逆で、“現実の構造”をちゃんと描こうとしてるから、視聴者が気持ちよく逃げられない。
刑事ドラマの気持ちよさ(犯人逮捕!)を、広報ドラマの現実(言葉ひとつで人が壊れる)で上書きしてくる回でした。
「実名報道は悪い/匿名報道は正しい」じゃない。コストの話だった
この回、SNSでも賛否が割れやすいテーマだったと思うんですが、僕は善悪で片付けると絶対ズレると思いました。
実名にも匿名にも、それぞれ“支払うコスト”がある。
- 実名:遺族の生活が壊れる/ネット特定が加速する
- 匿名:世間の関心が薄れる/情報提供が減る/捜査が止まりやすい
3話が上手いのは、実名の地獄と匿名の地獄を、どっちも描いたところ。
要望書で匿名に切り替わったあと、捜査本部への情報が激減する描写がある。ここ、残酷だけどリアルで、視聴者の“正義”を簡単に肯定してくれないんですよね。
結局、広報2係がやっているのは「正解を出す」じゃなくて、「どの損害を小さくするか」を選ぶ仕事なんだと思う。これが広報の地獄。
北川と安藤の対立は、優しさVS冷たさじゃなく“守る対象の違い”
北川が実名公表に難色を示すのは、未成年が含まれているから。感情としては当然です。
一方で安藤は「原則、名前は出す」と押す。これも冷血というより、経験から出る現実論に見えました。
北川が守りたいのは「遺族の生活」。
安藤が守りたいのは「捜査の継続」と「警察発表のコントロール」。
ここが噛み合わないのは、どっちも“正しい”から。だから視聴者が「どっちが悪い」と言い切れない。言い切れないから苦い。3話の後味はそこにあると思います。
稲田の“正義”は、僕ら視聴者の鏡だった
稲田が実名報道を主張した時、彼の中では「公益」「再発防止」「事件を追う」という正義がある。
でも実名を出した瞬間、遺族の地獄が始まる。ここで稲田が考え込むのが肝で、「俺は正しかった」と言い切るタイプだったら、単なる悪役で終わるんですよ。
稲田は“たぶん正しいこと”をしたのに、胸を張れない。
それって、現代の報道だけじゃなく、SNSで拡散する僕らも同じで、「正しいと思って叩いた」「正しいと思って広めた」ことが、誰かの生活を壊すことがある。
この回が怖いのは、被害者遺族への取材やネットの誹謗中傷を、ドラマの外に押し出さず「視聴者の日常の延長」に置いたところです。自分もいつでも“加害の輪”に入れる。
川畑の「自殺幇助」主張がえぐいのは、“物語の勝負”をしているから
川畑の強さ(というか卑劣さ)は、証拠の勝負じゃなく“物語”の勝負をしているところだと思いました。
「殺してない」「遺棄だけ」「幇助」――このラベルを貼れた瞬間、被害者は“叩いていい対象”にされやすい。ここが一番救いがない。
しかも、被害者たちに自殺願望があったという背景がある分、世論は簡単に「本人も望んでたんでしょ?」に傾く。
だから捜査は、川畑を逮捕するだけじゃ足りない。
「被害者の尊厳」を守るためにも、殺人として立証する必要がある。刑事ドラマの“勝ち”が、社会の“勝ち”にもなる構造になっているのが、第3話の怖さでした。
広報2係は、事件を解決する部署じゃない。でも「解決した後の社会」を救う部署だ
このドラマの一番面白いところって、警察ドラマなのに“逮捕”がゴールじゃないところです。
逮捕しても、遺族の生活は戻らない。報道の火種は消えない。ネットは忘れない。むしろ事件の後の方が長い。
だから広報2係の仕事は、「事件の終わり方」を設計することに近い。ただ、その設計はいつも不完全で、どこかで誰かが傷つく。
3話で匿名に切り替えた結果、情報提供が減って捜査が詰む描写が入ったことで、広報の仕事が“慈善”じゃなく“治安”の延長にあることが見えました。
まとめ:3話は“言葉の一行が人を殺す”回だった
3話の伏線も、感想も、結局ここに帰ってきます。
広報の言葉が、テロップになり、記事になり、拡散され、遺族の玄関に人を呼ぶ。
たった一行で、生活が壊れる。
このドラマは、事件の犯人だけじゃなく、「事件を消費する社会」まで含めて“犯人探し”をしている気がします。
そして視聴者も、その捜査対象から逃げられない。
しんどい。でも、目を逸らせない。
第3話は、そのタイプの強さを見せつけてきた回でした。
「東京P.D. 警視庁広報2係」の関連記事
全話のネタバレはこちら↓
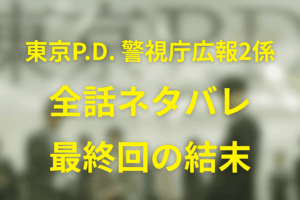
次回以降の話はこちら↓
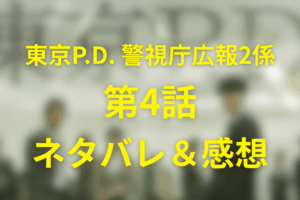
過去の話についてはこちら↓
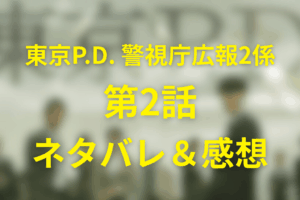
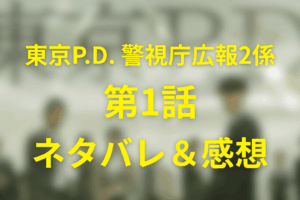
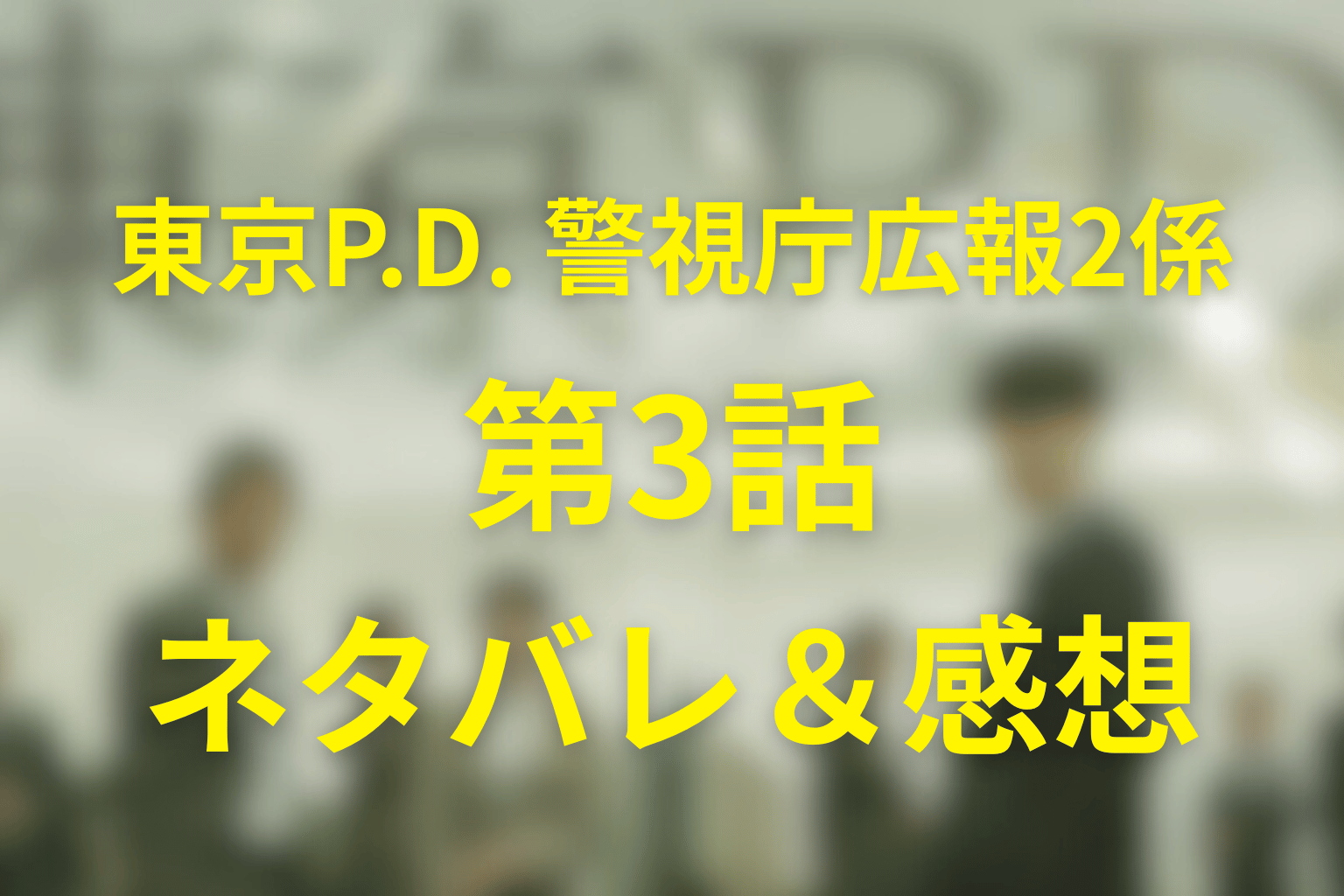
コメント