第4話は、事件そのものよりも「情報がどう扱われたか」が人を追い詰めていく回だ。
連続死体遺棄事件の被疑者・川畑礼介は、殺害を否定し、「自殺を手伝っただけ」と言い切る。その言葉は法の隙間にぴたりとはまり、捜査は決定打を欠いたまま行き詰まっていく。
同時に、実名報道によって事件は過熱し、被害者遺族は悲しむ時間さえ奪われていく。やがて実名が消え、報道量が減ると、今度は「忘れられる恐怖」が残る。この矛盾の中で動くのが、警視庁広報課2係の今泉麟太郎だ。炎上した記者から託された謝罪の手紙を抱え、今泉は“情報を出す側”として、遺族の前に立つことになる。
この回が描くのは、正義や是非ではなく、「伝えたあとに何が残るのか」という問いだ。捜査の突破口と、遺族の時間、そして検索窓に残り続ける傷。そのすべてが、4話の中で静かに結びついていく。
※この記事は、ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」第4話の結末までのネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
「東京P.D. 警視庁広報2係」4話のあらすじ&ネタバレ
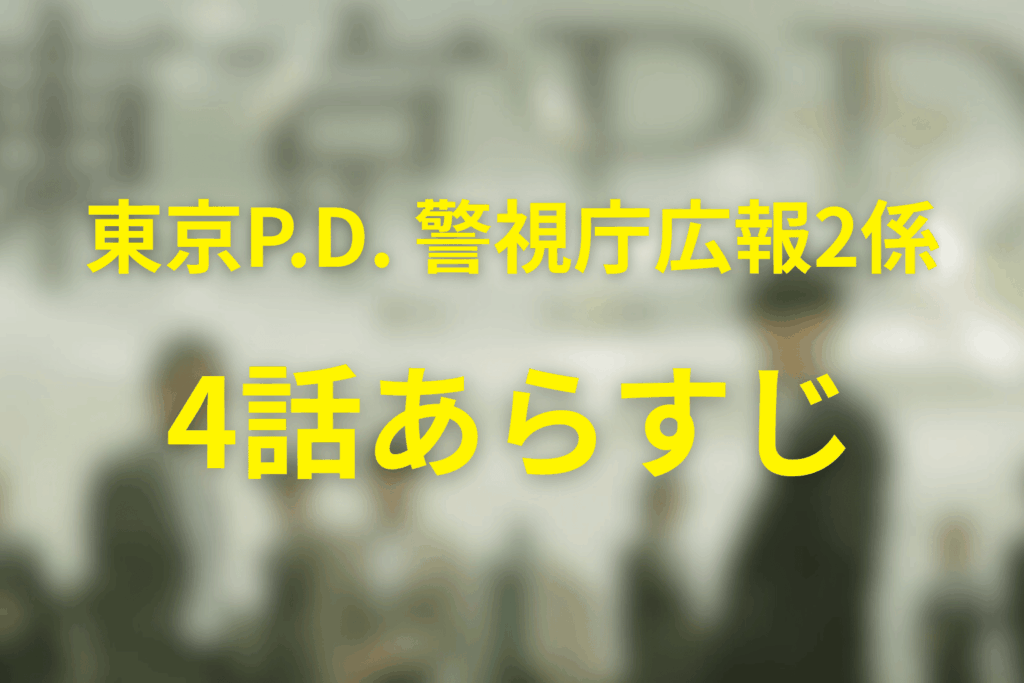
4話は、連続死体遺棄事件の“捜査の行き詰まり”と、実名報道をめぐる“情報の暴走”が、同じ一本の線でつながっていく回でした。
被疑者・川畑礼介は「殺していない」「自殺を手伝っただけ」と言い切り、法の隙間に身を置くように笑う。いっぽうで、被害者遺族は実名報道と過熱取材によって二次被害を受け、怒りと喪失の中で置き去りにされていく。
その真ん中で動くのが、警視庁広報課2係の今泉麟太郎。
「情報を出す側」のはずの警察官が、炎上した記者から“謝罪の手紙”を託され、遺族のもとへ足を運ぶ——。この構図自体が、4話のテーマを象徴しています。
ここからは、4話の流れを時系列で整理しつつ、何が起きて、何が決定打になったのかを丁寧に追っていきます。
前回までの整理:木崎七恵の失踪、川畑逮捕、そして実名報道のスイッチ
そもそもの発端は、20代女性・木崎七恵の失踪でした。防犯カメラやスマホの位置情報を手がかりに、七恵が失踪直前まで会っていた男として川畑礼介が浮上。
捜査が進む中で七恵は山中に遺棄され、周辺からはさらに4人の遺体が見つかります。未成年の被害者も含まれていたことで、警察内部でも情報の扱いは慎重にならざるを得ない状況でした。
ところが、会議の場で被疑者・川畑と被害者5人の実名・住所が共有され、結果的に“実名報道の流れ”が加速します。
報道各社がどう出すか迷う中で、いち早く踏み切ったのがYBXテレビ。記者・稲田裕司が強く主張し、他社に先駆けて実名で報道してしまう——ここが、4話で大きく跳ね返ってくる「起点」になっていました。
そして川畑は、現場検証でも取調べでも、殺害そのものを否認。
「やったのは遺棄だけ」という言い分は、冷静に見るほど危険です。遺棄を認めることで“最低限の罪”は引き受け、殺人の立件だけを難しくする。捜査側はここを崩す物証を探し続けることになります。
実名報道が止まり、ニュースから名前が消える——それでも遺族の時間は止まらない
4話の冒頭では、実名報道によって事件が過熱し、SNSで真偽不明の情報が拡散していく様子が描かれます。
「名前が出た」ことが、情報の連鎖を呼び、被害者の学歴・職歴・交友関係までが勝手に“物語化”されていく。しかも、その物語は往々にして刺激的な方へ寄っていく。遺族は悲しむ前に、守らなければならなくなる。
やがて被害者遺族の働きかけもあり、報道各社は実名を控える方向へシフト。画面や紙面から、被害者の名前が消えていきます。
ただ、その瞬間に起きるのがもう一つの現実で、報道量自体が目に見えて減っていく。事件が「日々のニュース」から外れ、世間の関心が薄れていくのです。
この時点で物語は、二つのラインが同時進行になっていました。
- 世論・報道ライン:実名→炎上→匿名化→報道量が減る→関心が薄れる
- 捜査・立件ライン:遺体遺棄は認める→「自殺ほう助」主張→殺人の物証不足→決定打探し
“名前が消える”ほど事件が静まる一方で、捜査は証拠が足りず、川畑の言い分が強くなる。
遺族にとっては、どちらも地獄です。報道が過熱すれば傷つくし、静まれば置いていかれる。4話はその矛盾を、最初から突きつけてきました。
ここで広報課が難しいのは、「実名を守る」ことと「情報提供を集める」ことが、しばしば逆方向に働く点です。
名前を伏せれば二次被害は減る。でも「誰のことか分からない」ことで、周辺情報が集まりにくくなることもある。逆に実名を出せば捜査協力が得られる可能性は上がるが、遺族の生活は壊れやすい。
4話は、この板挟みが“机上の議論”ではなく、実際の涙や怒号として立ち上がってくるのが辛いところでした。
捜査現場でも状況は厳しく、巨椋雅史は殺人と断定できる証拠が出ないことに苛立ちを募らせます。川畑の主張を崩すには、動機の推測ではなく、決定的な“裏づけ”が必要だったからです。
炎上した稲田裕司——「お前らがお姉ちゃんを二度殺した」の投稿
実名報道を最初に打った稲田裕司は、SNS上で炎上の中心に立たされます。
きっかけは木崎七恵の妹・京子の投稿。報道陣の写真に向けて「お前らがお姉ちゃんを二度殺した」と怒りをぶつける内容が拡散し、稲田の名前が特定されていきました。
世論の矛先は速い。
「実名報道が遺族を傷つけた」という大枠の議論が、“個人攻撃”へと変換される。稲田はその渦に巻き込まれ、上司から「遺族に謝罪してこい」と命じられます。
ただし、謝罪のために遺族宅へ行くこと自体が、遺族にとっては「また来た」「また覗かれる」という二次被害になり得る。
稲田はそのジレンマの中で、警視庁広報課の安藤直司を頼ります。
スナックでの相談——稲田が抱える“正しさ”の限界と、安藤の距離感
夜のスナックで向き合う安藤と稲田。稲田は「遺族にきちんと謝る必要がある」と思いながらも、何をどうすればいいのか分からない。
記者としては“報じた事実”から逃げられない。けれど人としては、遺族の前に立つことが怖い。ここで稲田は、自分の中にある二つの顔に押し潰されそうになっています。
安藤は、記者の論理も知っている人間ですが、この夜の空気は「正しさの議論」よりも、まず“遺族の痛みをどう受け止めるか”が前に出ていました。
安藤が何を言ったのか、稲田が何を受け取ったのか。その答えはすぐに明かされません。けれど後半、今泉が「手紙を書けと背中を押したのは安藤では」と疑う流れにつながっていきます。
ここで大事なのは、安藤が“救世主”として救いの言葉を与えるわけではないこと。
むしろ安藤は、距離の取り方が上手い。慰めるでも、断罪するでもなく、相手が自分で責任を引き受けるしかない場所へ戻していく。4話の安藤は、その怖さを知っている人の顔をしていました。
今泉に託された5通の手紙——広報2係が「届ける側」になる違和感
数日後、今泉が休憩しているところへ稲田が現れます。
稲田が差し出したのは、被害者5人の遺族に宛てた謝罪の手紙。稲田は「自分では渡せない」と言い、今泉に代わりに渡してほしいと頼み込みます。
今泉は戸惑います。
警察と記者は、近すぎても遠すぎても危うい関係。まして遺族対応は、警察の“広報”としても神経を使う領域です。ここで一歩でも間違えれば、「警察が記者の肩を持った」「遺族を丸め込もうとしている」と受け取られかねない。
今泉は安藤に相談しますが、返ってきたのは思いがけない一言——「知るか!」。
突き放すようでいて、これは“簡単に引き受けるな”という釘にも聞こえます。安藤が本気で止めたいのか、それとも今泉に判断させたいのか。今泉は余計に考え込む。
広報2係の中でも異論は出ます。真部正敏は「記者の使いっ走りになる気か」と厳しい。
ただ、下地和哉が真部をその場から連れ出し、今泉が追い詰められないように場を整える。そして熊崎心音が「一緒に行きます」と申し出て、今泉は“単独行動”にはしない形を作ります。
ここで今泉が論理的なのは、動機を「稲田を助けたい」に置かないこと。
手紙を届けるのは“記者のため”ではなく、“遺族のため”になる可能性があるからやる。もし遺族が受け取らないなら、そこで引く。境界線を越えない。今泉はそのルールを自分に課します。
受け取られない手紙、受け取られる手紙——遺族の反応は一枚岩じゃない
今泉と熊崎は、稲田から預かった5通の手紙を持って遺族の元へ向かいます。
しかし現実は厳しく、封筒を見ただけで拒まれる家もある。巻田家では、手紙は読まれないまま突き返されてしまいました。遺族にとっては、内容以前に「記者の文字が届くこと」自体が暴力に近い。
他の遺族の元でも、受け取ってもらえないケースが続きます。
ここで今泉がやるのは、説得ではなく撤退です。受け取り拒否は拒否として受け止める。謝罪を“押し込む”ことが、さらに相手を傷つけると分かっているからです。
そんな中、木崎家は手紙を受け取ります。
京子は封筒を手にしながら、すぐには開けない。怒りはある。けれど、怒りだけでは終われない。封筒を開けることは、姉の死と、そこに群がった視線をもう一度引き受けることでもあるからです。
京子が手紙を読む場面は、言葉以上に“間”が効いていました。
そこに書かれていたのは、度重なる過度な取材への謝罪。言い換えるなら、稲田自身が「あなたたちの悲しみを奪った」と認める文面です。
ただ、謝罪が整っているほど、逆に遺族の中で「じゃあ、なぜ最初からやらなかったのか」という問いが膨らむ。許せるかどうかの前に、遺族の時間は壊されたまま動けなくなる——その感覚が残ります。
カフェでの対面——京子の怒りと、今泉の「それ、建前になってませんか」
手紙を届け終えた今泉は、稲田とカフェで向き合います。
「突き返されたところも多かった」——今泉の報告は、稲田にとって想像以上に重かったはずです。謝罪を“出した”のに、謝罪として受け取られない。これは、誠意の不足というより傷の深さの問題です。
そこへ熊崎が京子を連れてくる。京子は「直接話したい」と稲田本人を指名していました。
京子はまず、手紙を読んだことを告げた上で、「本当に申し訳ないと思っているのか」と問い詰めます。そして、最初からなぜあんなことをしたのか、と。
京子の言葉は、理屈ではなく生活の痛みです。
突然姉が死に、その意味も分からないのに、昼も夜も追い回された。普通に悲しむことすらできなかった。自分たちがどれだけ苦しんでいるか分かるのか。
“取材”という言葉が、ここではほとんど“侵入”に近い響きを持ちます。
稲田は、実名報道には今も意義があると口にします。
実名で伝えることで事件の重大さを社会に提示し、同じ悲劇を繰り返さないために考えてもらう。その発想自体は間違っていない。
ただし稲田も、行き過ぎた報道は謝罪します。遺族の痛みをそのまま伝えたいと思った結果、遺族がさらに痛む形になってしまった——ここで初めて、稲田は自分の矛盾を口に出します。
今泉がここで割って入ります。
メディアの役割が“都合のいい建前”になっていなかったか。視聴率、他社との競争、特ダネを掴む高揚感。気がつけば事件も被害者も遺族も置き去りにしていなかったか。
今泉は、稲田を叩きたいのではなく、「正義が手段を雑にする」瞬間を見抜いてしまったから止めたいのです。
稲田は「被害者にも家族にも感情がある」という当たり前を、ようやく思い出したと認め、もう二度と遺族が傷つくようなことはしないと約束します。
そして京子が、ぽつりと告げます。「姉は、みんなから言われている人じゃない。ほんとの姉は——」
「ほんとの七恵」——宅建合格、笑って出ていった日、そして妹の後悔
京子が語る木崎七恵は、ネットに並んだ断片とは違いました。
七恵は就職後に傷つき、メンタルクリニックに通っていた時期がある。でも少しずつ回復し、宅建試験の勉強を始めて合格した。
何より、最期の日も笑って家を出ていった。つまり七恵は、“死ぬための準備”をしていた人ではなく、“生き直す準備”をしていた人だった。
京子は怒りの矛先を、メディアだけでなく捜査にも向けます。
姉は殺されたはずなのに、どうして殺人で逮捕できないのか。殺したという証拠が見つからないということなのか。もし殺人が認められなければ、刑務所に入るのは何年なのか。死刑にはならないのか。5人も亡くなっているのに——。
ここで浮かび上がるのは、遺族の「感情」と、法律が求める「証明」の落差です。この回で分かりやすく整理すると、争点はほぼここに集約されます。
- 死体遺棄:遺体を捨てた(=川畑はここを早々に認めている)
- 自殺ほう助:本人が“自殺する意思”を持っていて、その実行を手助けした
- 殺人:本人の意思ではなく、相手の命を奪った(=故意と実行が必要)
川畑は「自殺ほう助」を盾にすることで、“被害者の心の内”を論点に持ち込みます。心は見えない。だから証明が難しい。
捜査側が欲しいのは、心の推測ではなく「やった」という確定の手がかり。京子の問いは、巨椋が抱えている苛立ちと同じ地点に刺さっていました。
殺人として立件するには、行為と故意を裏づける物証が要る。逆に言えば、物証が薄いと“言い方の上手い犯人”が有利になる。京子の問いは、その現実を真正面から突いていました。
さらに京子は、怒りの投稿をしたことへの後悔も口にします。耐えられなくなって、姉と同じようなことをしてしまった、と。
今泉はここで核心を確認します。「七恵さんは自分で死のうとはしていなかった、ということですね」。京子はそれを肯定し、だからこそ“自殺ほう助”という言葉が許せない、と涙をこぼす。
稲田は京子に提案します。取材を受けてみないか。それが「ほんとの七恵」を正しく伝えることにならないか。
京子は小さくうなずきます。報道を憎んでいるのに、報道の力を借りなければ真実が届かない。この矛盾を飲み込む決意が、京子の中で生まれた瞬間でした。
特集が呼び込んだ情報提供——「明日、会いに行く」と言っていた七恵
YBXテレビは事件を特集し、木崎家は七恵の近況を語ります。体調が良くなっていたこと、宅建に受かったこと、最期の日も笑って出ていったこと。
そして「犯人を殺人で逮捕してほしい。警察を信じています」と訴えます。
この特集が、捜査の空気を変える情報提供を呼び込みます。
名乗り出たのは、七恵とコスプレイベントで知り合った女性。彼女はその時の動画を持っていました。そこに映る七恵は、事件のラベル(自殺願望、希死念慮)とは真逆の表情をしている。
彼女が伝えたのは、七恵が残した“生きる側の言葉”。
家族に支えられていることに気づき、もう一度生きてみようと思った。イベントも楽しかった。
そして、SNSで相談に乗ってくれた人に「明日会いに行く」と話していた——つまり七恵は未来を見ていた。
この証言は、川畑のロジックを崩します。
「人の心は変わる」と川畑は言える。けれど少なくとも、七恵が“死に引っ張られていた”という前提が揺らぐ。ならば、川畑の「自殺ほう助」は成立しない可能性が高まる。
巨椋は「殺人罪で逮捕するには生ぬるい」と言い切り、決定的な証拠——映像が残っているはずだと踏み込みます。
ここ、4話の構造がうまいのは、出来事が“偶然つながった”のではなく、誰かの行動が次の扉を開けていく因果になっている点です。
- 稲田が炎上し、謝罪の手紙を書く
- 今泉が手紙を届け、京子と稲田が対面する
- 京子が「ほんとの七恵」を語り、取材を受ける決意をする
- 特集によって、七恵を「生きている姿」で知る人物が名乗り出る
- その証言が捜査の方向を決め、川畑宅の“隠し場所”に辿り着く
広報課2係は、犯人を追い詰める部署ではありません。けれど「伝える/伝えない」を巡る判断が、結果的に捜査の突破口へつながっていく。
この回で今泉が担っていたのは、まさに“捜査と世論の接点”でした。
川畑宅の徹底捜索——透明な貯金箱に混じっていた“海外コイン”
巨椋と今泉は川畑の自宅を徹底的に捜索します。
机の引き出し、収納、家電、データ類……どこに“本人しか知らない形”で残すかを想像しながら、見落としを潰していく。ここで今泉が拾った違和感が、透明な貯金箱でした。
大量の硬貨が入った透明の貯金箱。その中に混じっていた海外のコイン。
川畑は海外に行ったことがないはずなのに外国硬貨がある。しかも貯金箱は透明で、本人が中身を眺められる仕様。隠すなら見えない容器でいい。
「隠しているのに、見せたい」——この矛盾が、川畑の“保存癖”をにおわせます。
今泉はその硬貨を回収し、巨椋に共有します。
広報に来ても刑事の眼は鈍っていない。今泉が“違和感を拾える人間”であることが、ここで強く効いてきます。
取調室の心理戦——「弱いでしょ」と笑う川畑、揺さぶり続ける巨椋
取調室(下暁署)で巨椋は川畑を詰めます。
七恵が死ぬ気なんてなかった、という証言が出た。その後、お前は犯行に及んだ。——巨椋の言葉に、川畑はあくまで「死体遺棄ですね」と返す。
巨椋が求める“殺人”の認定を、言葉だけでかわしていきます。
川畑が笑い出すのはここからです。
「弱いでしょ。それだけで俺が殺したって」
人の心なんて簡単に変わるのに、と。七恵がイベントで笑っていたとしても、その後に死にたいと思う可能性はゼロではない。だから「証言だけで殺人は証明できない」。川畑はその一点に賭けている。
さらに川畑は、捜査側をあざけるように言います。
このまま再逮捕して裁判にするのか?裁判官が客観的に見たらどんな判決になる?
「あと一歩?……いや、四歩か五歩かな」
——挑発の言葉は、川畑が“証拠の不足”を確信しているから出てくるものです。
川畑はさらに、「何か証拠でもあるんですか?」と、わざと軽く言います。
捜査側が欲しい言葉を自分が“ぽろっとこぼす”のを待っているだけだろう、とも。取調べを“ゲーム”に見立て、主導権を握った気でいるのが透けて見える。
巨椋が「分かってるんだろ。それでいいのか」と揺さぶっても、川畑は「何がですか」と笑ってかわす。
ここで巨椋が感情で前に出たら、川畑の思うつぼ。だからこそ巨椋は、言葉ではなく物証に切り替えます。
「コイン」——表情が変わった瞬間、隠し場所は割れた
巨椋が口にしたのは、「コイン」。
その一語で、川畑の笑みが消えます。自分が何を隠していたか、本人が一番分かっている。だからこそ反応が早い。
巨椋は、ポリ袋に入った外国の硬貨を提示し、「海外に行ったことがないはずなのに、なぜ貯金箱に入っていた」と突きつけます。
川畑は取り返そうとし、焦りが露骨に出る。
そこで巨椋がコインを手のひらに叩きつけると、コインは割れ、中からマイクロSDカードが転がり出ます。
“隠し方”が生々しいのも印象的でした。
財布や引き出しではなく、硬貨の中。しかも貯金箱の小銭に紛れ込ませる。探す側が「まさか」と思う場所に置くことで、川畑は捜査を舐めていたのかもしれません。
けれど逆に言えば、川畑がそこまでして守りたかったのは「自分の言い分」ではなく、“自分がやったことの記録”そのものだった。
巨椋はすでに中身を確認していました。
パソコンで再生された映像には、川畑が被害者を殺害する様子が残っていた。しかも一人分ではない。他の4人の分もきちんと残されている。
この瞬間、川畑の「自殺ほう助」という主張は完全に崩壊します。言葉で守ってきた外殻が、映像という物証で真っ二つに割れた。
巨椋は川畑を掴むようにして映像を見せ、「全部見た」と告げます。
一人分の“事故”ではなく、5人分の“反復”。しかも川畑自身が残していた記録。偶然や誤解で逃げられる余地は、ここでほぼ消えます。
川畑の顔から余裕が剥がれ落ちるのは、供述が崩れたからだけではありません。「証拠がない限り俺は負けない」という前提が、映像一つで逆転したからです。
そして、映像は“議論を終わらせる”強さを持っています。
「心の中は分からない」「本人は死にたかったのかもしれない」——そうした逃げ道を、記録は一気に塞ぐ。捜査にとっては救いであり、遺族にとってはようやく手が届く正義でもある。
ただ同時に、映像は当事者の時間を凍らせるものでもあります。4話はそこを過剰に煽らず、淡々と“決定打の重さ”として置いていきました。
笑っていた男が壊れる——精神鑑定への逃げ道すら封じられる
映像を突きつけられた川畑は、デスクに頭を打ち付けて取り乱します。
ここで彼が持ち出そうとするのが、「病院に通っていた」「精神的に不安定だった」というライン。つまり精神鑑定で心神喪失を狙い、刑を軽くしようとする道です。
しかし巨椋は冷静に切り返します。
川畑が通っていたのは、不眠を理由に睡眠薬をもらっていただけ。今さら心神喪失を主張しても通らない、と。
“証拠がない余裕”で笑っていた男が、“証拠が出た恐怖”で崩れる。4話の終盤は、この反転が一気に描かれます。
事件は「殺人」として動き出し、SNSの空気も変わります。
これまで世間は、「実名で報じるべきか」「匿名で守るべきか」といった“報道の是非”に熱を使っていました。
でも映像という決定打が出た瞬間、話題は一気に「犯人は何者だ」「なぜやった」に切り替わる。関心の矢印が、遺族ではなく加害者へ向き直る。
その切り替わりの速さ自体が、今泉たち広報の現場には怖いはずです。世論は正義にもなるし、消費にもなる。そのどちらに転ぶかを、現場は選べないから。
川畑は“快楽殺人”として叩かれ、世間は再び熱を帯びる。けれど、その熱が増すほど、被害者の名前の周りにまた別の情報が貼り付いていく危うさも残る。4話は、スッキリとした「勧善懲悪」だけで終わらせません。
最後に残るテーマ——実名の意味と、検索窓に残り続ける傷
事件の決着が見えた一方で、今泉は安藤に問いかけます。
稲田に手紙を書かせたのは、あなたの助言だったのではないか、と。安藤は笑ってはぐらかし、確定の答えを出しません。
否定もしない。だから余計に意味深です。
今泉から見れば、安藤が「記者に寄り添った」のか、「遺族の声を社会につなぐ導線を作った」のか、判断がつかない。けれど結果として、京子の言葉が放送に乗り、情報提供が入り、物証が見つかった。
安藤の“答えない”態度は、善悪のラベルでは片づけられない現場の複雑さを、そのまま背負っているように見えました。
けれど安藤が今泉をどこか“若い頃の自分”に重ねている空気は、はっきり残ります。
安藤が語るのは、実名・顔出しの意味です。
情報提供には確かに意味がある。顔と名前が出ることで、世間が本気で向き合うこともある。
ただしそれは、テレビが情報の出口を握っていた時代の話だ、と安藤は釘を刺します。
いま実名が出れば、学歴も職歴も、卒業アルバムまで掘り返される。被害者ですら炎上する。しかも一度出た情報は、検索すれば何年経っても消えない。
実名を伏せる方向に舵を切っても、すでに出回ったスクリーンショットや切り抜き、まとめの見出しは残る。
しかも“残り方”は、本人が望んだ形では残ってくれません。悲劇の被害者として、あるいは憶測のキャラクターとして、断片だけが回り続ける。
「東京P.D. 警視庁広報2係」4話の伏線
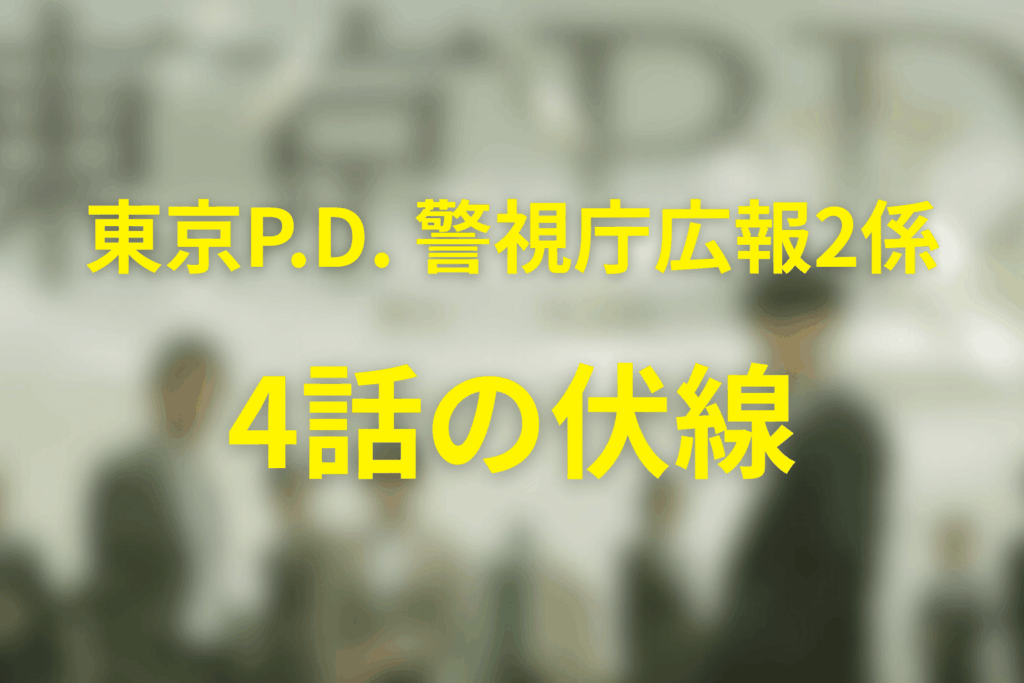
第4話は、事件そのものは大きく前進した一方で、「情報が消える/残る」「誰が声を持つのか」という“後味の重さ”を次の事件へ持ち越した回でした。
※ここから先は、第4話のネタバレを含みます。
匿名報道で“炎上”は収まるが、事件が風化していく(=利益者が増える)
第4話冒頭で描かれたのは、実名報道が減ったことで遺族への二次被害が沈静化する一方、テレビや新聞の露出が減って世間の関心も薄れていく、という「構造」です。
ここ、伏線的に重要なのは「事件が風化すると、誰が得をするのか?」という視点。
- 遺族:静かに弔える。ただし“真相が置き去り”になりやすい
- 加害者(容疑者):目立たずに戦える(殺人で立件されない限り、時間が味方になる)
- 警察:捜査は続くが、世論の後押しが弱くなる
- メディア:燃えにくい題材は扱いづらい
この「匿名=優しさ」だけでは終わらず、匿名=忘却にもつながる、という論点が次回以降の“情報統制(報道協定)”につながっていきます。
稲田の「5通の謝罪の手紙」──“届け方”そのものが伏線
稲田裕司が、被害者5人の遺族に向けて書いた謝罪の手紙を、今泉麟太郎に託す。これ自体はストレートな展開ですが、伏線として効いているのは 「本人が渡せない」 という一点です。
- 手紙の中身より先に、“届ける手段”が問われる
- 「謝る側の都合」では受け取られない
- だから“中継役”が必要になる(=広報2係の仕事の縮図)
つまりこの手紙は、稲田の贖罪というより、情報を相手に届く形へ変換するプロセスを見せる装置でした。今泉がこの経験を積むことで、次の「報道協定」の場面で、単に“嫌な役回り”をやる係ではなくなるはずです。
木崎京子の投稿「お前らが…2度殺した」──二次被害の“再現性”が残った
稲田が炎上した発端が、木崎七恵の妹・京子の投稿だった、という流れは第4話の芯です。
ここで残った伏線は、京子個人の怒りというより、二次被害が“簡単に再現できる” という恐さ。
実名が出る → 周辺情報が掘られる → 解像度の低い“被害者像”が量産される。
この流れは「一度起きたら終わり」じゃなく、別の事件でも同じ形で繰り返される。だからこそ、次回の誘拐事件で「どこまで伏せるか/いつ出すか」が、よりシビアなゲームになっていくはずです。
美沙の証言が残した“名前のない人物”──「SNSで相談に乗っていた人」は誰?
情報提供者として登場した美沙(コスプレイベントで七恵と知り合った人物)が語る「七恵は明日、SNSで相談に乗ってくれた人に会うと言っていた」。ここが第4話の未回収ポイントとして強いです。
第3話の時点で、川畑礼介が“自殺願望のある女性”とSNSで連絡を取っていたことが示されています。
この情報と第4話の証言が噛み合うと、浮かぶ論点は2つ。
- その「相談相手」=川畑だった可能性(ターゲティングの手口)
- 別の人物だった可能性(川畑が単独ではない/紹介者がいる)
どちらに転んでも、「SNSが“入口”になっている」こと自体が、今後の事件の伏線として残ります。
川畑の“外国コイン”とメモリーカード──証拠隠滅じゃなく「保管」していた理由
決定的証拠が、貯金箱の小銭(外国コイン)の中に隠されたメモリーカードだった、というオチは、回収でありながら新しい伏線でもあります。
普通に考えれば「証拠は消す」のが合理的なのに、川畑は“残した”。しかも、全員分の映像。
この“矛盾”が意味するのは、少なくとも次のどれかです。
- 快楽が「行為」ではなく「記録」にあるタイプ
- 誰かに見せる/共有する意図がある(共犯・コミュニティの匂い)
- 捕まる未来すら想定している(自分の物語化)
第4話で事件は決着したように見えて、実は「川畑という人間の動機」はまだ閉じていない。ここは後半の大きな回収に繋がる伏線だと思います。
安藤の一瞬のフラッシュバック──“仕向けた”のは誰で、何を償っているのか
今泉が、稲田の手紙の件で安藤直司に踏み込もうとした瞬間、安藤が一枚上手でかわす。さらに一瞬、過去の記憶がよぎる描写が入る。
この描き方は、明確に「未解決事件を抱えている」という設定と繋がっています。
第4話の安藤は、前面に出て事件を解くというより、人と情報を“配置”して結果を引っ張るタイプとして描かれました。
今泉を“届け役”に置いたこと自体が、次回の「報道協定」でも同じ構図を作る前振りになっているはずです。
「東京P.D. 警視庁広報2係」4話の感想&考察
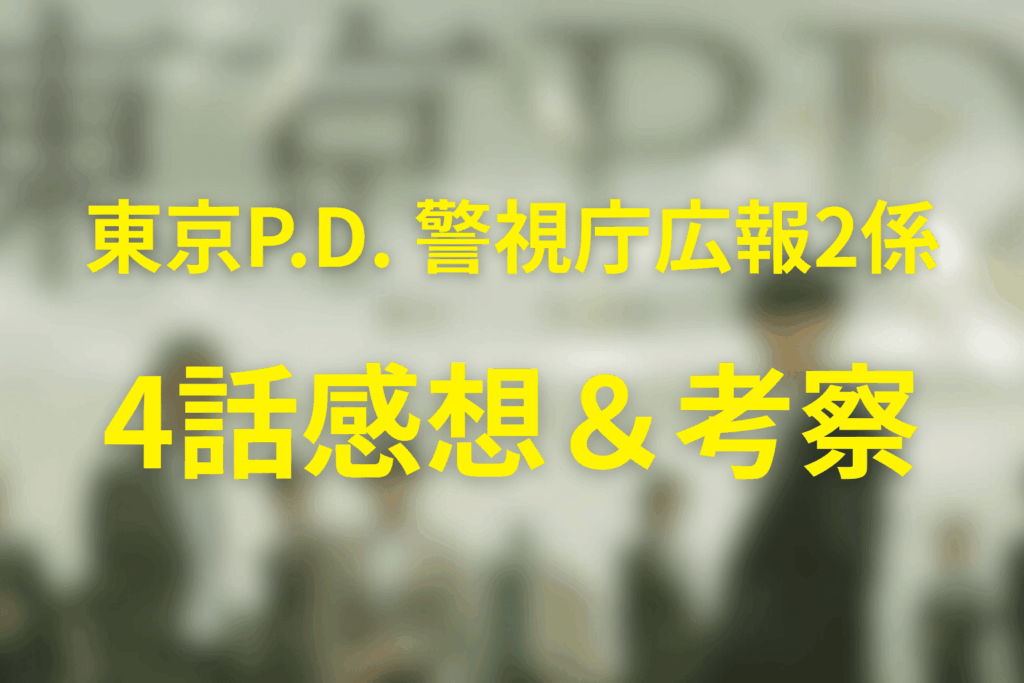
第4話を見終わって残るのは、スッキリというより「正しさって、そんなに単純じゃないよな…」という鈍い重さでした。事件は“殺人”として前に進んだのに、遺族の時間だけは取り戻せない。そこがこの回の肝だと思います。
京子の怒りは「感情」じゃなく、論点の提示だった
京子の言葉は、ただの糾弾じゃない。
「犯人が殺人で逮捕されないのはなぜ?」「このままだと刑はどうなる?」と、感情が論点に変わっていく瞬間があった。
ここで刺さったのは、遺族が求めているのが“慰め”じゃなくて、制度の中での決着だということ。
言い換えると、彼女たちは「同情」よりも「立件」を求めている。だから稲田の謝罪文だけでは、まだ足りない。
そして、この要求はかなり現実的です。
殺人で立件できなければ、川畑は「自殺ほう助」「死体遺棄」の枠の中で戦う。その戦いに勝たれると、遺族の側は“負けた気持ち”だけが残る。第4話は、その不公平感を真正面から描いたと思います。
稲田は“悪役”になり切れない。だからこそリアルで、痛い
稲田は強い言葉で実名報道を語る。でも、その強さが、遺族の目の前では「言い訳」に見える危うさもある。
ここが、このドラマの上手いところで、稲田を単純に“加害者側の人間”として描かない。
稲田は確かに、被害者の名前を“最速で”出した。
でも同時に、遺族と向き合ったとき、逃げずに言葉を返す。これは、ただの保身じゃなくて、彼の中にまだ「報道の仕事に対する信仰」が残っているからだと思う。
ただし、その信仰は便利な免罪符じゃない。第4話の稲田は、正義を語るほどに、自分が見落としてきたもの(遺族の生活、時間、悲しみ方)を突きつけられていく。だから見ていて痛いし、目を逸らせない。
“ログ戦”で見る第4話──取材が「証拠の出どころ」になった回
この回、刑事ドラマとしての面白さは、「証拠がどこから生まれたか」がめちゃくちゃ論理的に繋がっている点です。
- 京子が取材を受ける決断をする
- 放送が流れる
- 情報提供が入る
- 目撃証言+動画で「自殺の意思は薄い」が補強される
- 捜索が“本気モード”に切り替わる
- 物証(メモリーカード)にたどり着く
これってつまり、「報道が被害者を傷つける」だけじゃなく、捜査の背中を押すこともあるという二面性を描いている。
第3話〜第4話で積み上げてきた「実名報道の功罪」が、ただの倫理論争で終わらず、事件解決の“実務”に着地しているのが強かったです。
川畑の笑顔が一番怖い。「殺してない」より「録ってる」が異常
川畑礼介の怖さって、“猟奇性”というより、「責任を回避する頭の良さ」と「人を人として見てない感じ」なんですよね。
自殺ほう助を主張し続けるのも、法律の穴を知っているからというより、「証拠がなければ世界は自分の言い分で動く」と信じているタイプに見える。
だからこそ、メモリーカードの存在が刺さる。
あれは“証拠”である前に、川畑の内面を暴く道具でした。
- 人を殺した“事実”だけじゃなく
- その行為を「記録」して残す感覚
- しかも、隠し方が巧妙で、見つからない前提だったこと
ここまで来ると、快楽殺人というラベルだけで片付けるのは早い気がします。
「なぜ残すのか」「誰に向けた記録なのか」。この問いが残った時点で、川畑の物語は“終わっていない”と思いました。
今泉と安藤の関係は、上司と部下というより「後悔の引き継ぎ」に見える
今泉は、記者を嫌っていたはずなのに、今は“届け役”を引き受けて、人の前に立てるようになっている。
その変化のそばに、いつも安藤がいるのがポイントです。
安藤は、今泉を説教で動かすんじゃなく、役割を与えて動かす。
第4話の手紙の件もそう。表で動くのは今泉で、安藤は裏で配置する側。
そして最後のフラッシュバック。
あれが入ったことで、安藤は「正しいことを言える人」ではなく、正しいことをやれなかった過去を抱えた人として立ち上がってきた。
今泉は、その後悔を知らないまま引き継がされている。だからこの2人の関係、師弟というより“引継ぎ”なんですよね。
次回に向けて:報道協定は「善意のルール」じゃなく、情報戦の契約になる
次回第5話(2026年2月24日放送予定)では誘拐事件が描かれ、“報道協定”が前に出てくる。
第4話で描いた「匿名報道=風化」の延長線上で見ると、ここから先はもっと露骨に、
- 情報を伏せる正義
- 情報を出す正義
- そして「漏れる」現実
がぶつかるはずです。
第4話は、事件解決のカタルシスを見せつつ、同時に「情報を扱う者の罪」を残した回でした。
だから次回は、事件の種類が変わっても、戦い方(=情報の握り合い)は続く。ここがこのドラマの強さだと感じます。
「東京P.D. 警視庁広報2係」の関連記事
全話のネタバレはこちら↓
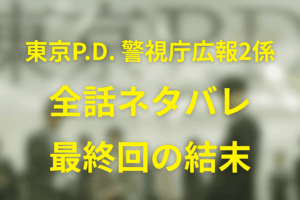
過去の話についてはこちら↓
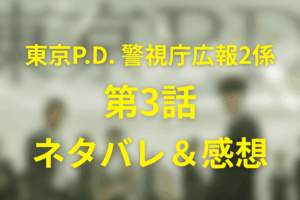
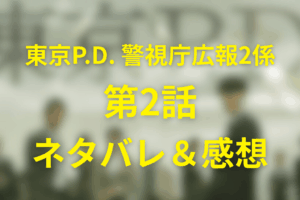
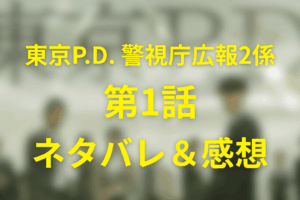
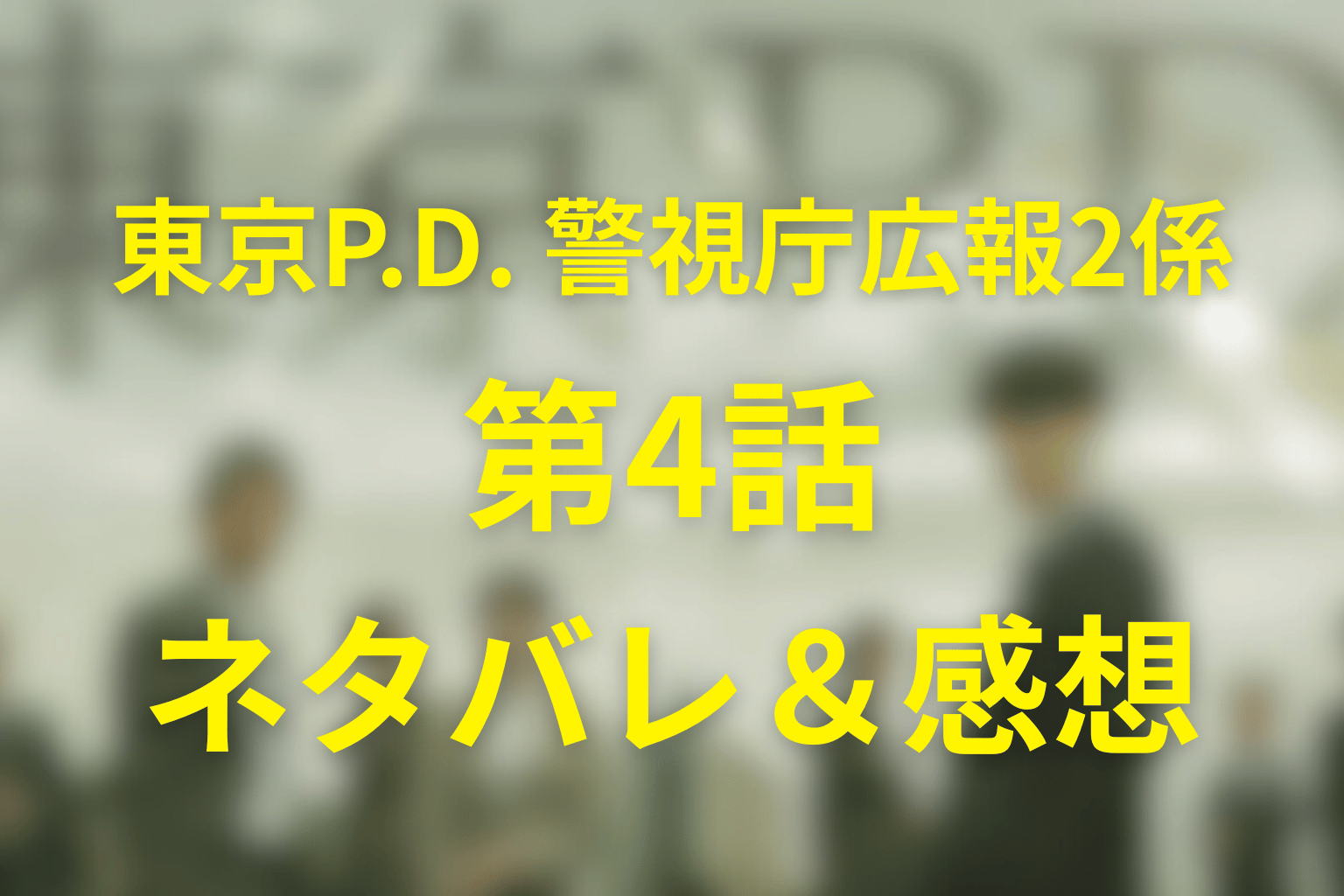
コメント