最終回(第7話)は、これまでの事件とは決定的に質が違います。
アリバイが強固すぎるのです。しかもそれを支えるのは、数人ではなく300人もの証人。普通なら疑う余地すらなく、「確認作業」で終わってしまうはずの状況でした。
ところがこの回では、その“多すぎる証言”こそが真相を覆い隠す装置になります。
証言が多いほど、人は安心して考えるのをやめる。その心理の隙間に、連続殺人と巧妙な入れ替わりが滑り込んでいた――。
父が容疑者になる恐怖、信じたい記憶と疑うべき事実の間で揺れる刑事たち。
そして、美谷時乃が最後に見抜いたのは、時間ではなく「人が見ていた“顔”」でした。
最終回は、シリーズ全体を貫くテーマ――アリバイとは何を守り、何を隠すのか――を、最も残酷な形で突きつけてきます。
ドラマ「アリバイ崩し承ります」7話(最終回)のあらすじ&ネタバレ
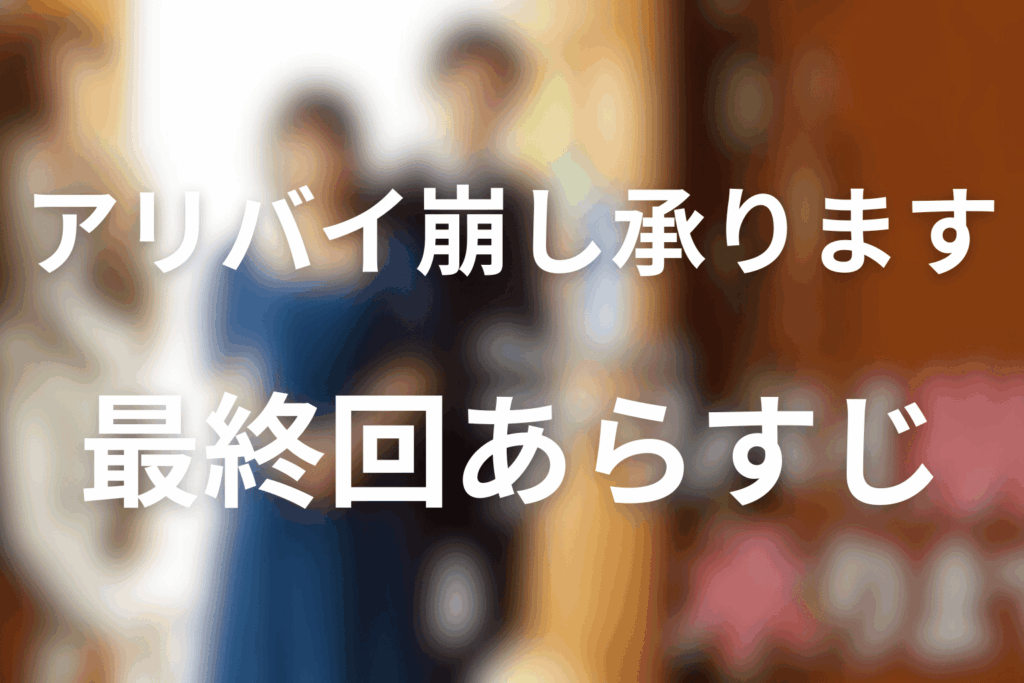
最終回(第7話)はサブタイトルが示す通り、「証人が多すぎる」ことで逆に真相が霞んでいく回でした。
事件の規模も“連続殺人”へ跳ね上がり、いつもの軽妙さの中にちゃんと怖さが差し込まれる。ここでは、時乃の推理の筋道が追えるように、出来事を時系列で噛み砕きつつ整理します。
河川敷の焼死体、落ちていた名刺――「父が容疑者になる」入口
物語は河川敷で見つかった焼死体から始まる。
那野県警捜査一課の察時美幸(安田顕)たちが臨場すると、現場に現れたのは渡海雄馬(成田凌)の父で衆議院議員・渡海一成(徳光和夫)。同伴しているのは秘書の藤枝ミホ(西田尚美)。そして、遺体のそばに落ちていた名刺が“一成の別の秘書”のものだった――この一点で、事件は一気に「身内案件」に変貌する。
焼死体が名越徹(須田邦裕)だと確認される流れは、いかにも最終回らしい重さがある。
雄馬にとっては「警察官」としての正義の前に、「息子」としての感情が割り込んでくる状況だ。
これまで“ボンボン刑事”として周囲に持ち上げられてきた雄馬が、最終回で初めて「父を疑われる」という現実に直面するのが、まず大きな見どころになる。
300人の証人=鉄壁のアリバイ、それでも残る違和感
一成には、遺体の死亡推定時刻に後援会を招いたパーティーへ終始出席していた、という“鉄壁のアリバイ”がある。しかも証人はおよそ300人。普通のミステリーなら、ここで「はい解散」となるレベルの防壁だ。
ところが察時は、一成がふと口にした“あるひと言”が引っかかって仕方ない。さらに追い打ちをかけるのが、藤枝ミホの単独来訪だ。藤枝は捜査一課を訪ね、「秘書を殺したのは一成かもしれない」と告げる。
ここで面白いのは、疑いの材料が「状況証拠」よりも「人が持ち込む物語」になっていく点。名越は最近、一成が本来“息子の雄馬に譲るつもりだった地盤”を自分に譲る話になっていた――つまり、名越が何か弱みを握っていたのでは、という筋書きが立ち上がる。疑惑はロジックからではなく、“それっぽい物語”から膨らんでいく。
最終回のテーマが「多すぎる証人」なのに、視聴者も警察も、最後は「誰の語りを信じるか」に巻き込まれるのが巧い。
察時が時乃に依頼、しかし今回だけは“頼みづらい”
察時が頼るのは、もちろん美谷時計店の店主・美谷時乃(浜辺美波)。
けれど今回は事情が違う。渡海一成は、時乃の祖父・時生(森本レオ)の囲碁仲間だった。時乃にとっては、祖父の記憶と繋がる人物が「容疑者」として目の前に置かれてしまう。
時乃は最初から「一成が犯人だとは思えない」という感情を拭えない。ここが、これまでの“アリバイ崩し”と決定的に違う点だ。
これまでは依頼人(察時)が半ば強引に引っ張っていく構図だったのに、最終回は時乃が「崩すべきアリバイなのか?」という倫理のブレーキを踏む。祖父が言っていた「アリバイ崩しは恨みを買う」という言葉が、ようやく“現実の重み”としてのしかかってくる。
「後援会じゃない一人」――安本孝之という異物
捜査が進むにつれ、パーティー参加者の名簿に“異物”が見つかる。後援会の人間ではないのに、会場に来ていた男がひとりいる。安本孝之――職業はスーパーの店員。政治とも一成とも縁が薄そうな人物だ。
雄馬たちが安本の家に向かうと、そこにあったのは「ベッドに拘束された遺体」。ここで事件は一気に連続殺人へ転じる。しかも二人目の被害者は“後援会じゃない一人”。つまり、証人300人の巨大な輪の外側に、たった一人だけ綻びがあった。その綻びが、実は真相へ繋がる唯一の糸になる。
似すぎる二人、そして時乃の到達――「一人二役」への着地
ここから時乃の推理が加速する。捜査資料の写真を見た時乃は、名越と安本が「どことなく似ている」どころではなく、“かなり似ている”ことに気づく。ここが最終回のコア。
「証人が多すぎる」アリバイを崩すには、証人の数を上回る“別の仕掛け”が要る。そこで出てくるのが、名越=安本に化けるという一人二役の構図だ。
整理すると、表向きに見えていた時系列はこうだ。
- パーティー(18:00〜20:00頃)の最中、18:34に名越の携帯へ着信
- 18:35、名越が会場を出る
- 18:50、安本が会場に現れる
- 翌日、名越の焼死体が発見
- その後、安本の遺体も発見
この段階だと、「名越は18:35以降に会場外で殺され、その犯人は会場にいた(=一成や藤枝)」という読みが成立する。胃の内容物から推定された“死亡のタイミング”もこの読みを補強し、逆に一成と藤枝には強固すぎるアリバイがある――つまり詰む。
しかし時乃は、詰みの理由を「証人の数」ではなく「顔の一致」から崩しにいく。ここが“時計屋探偵”の面白さで、時間ではなく人間の入れ替え(見た目)によって時間が偽装される。
真相:藤枝ミホが仕掛けた連続殺人、名越は“共犯にされた”
真犯人は藤枝ミホ。動機はシンプルで生々しい。「自分のほうが尽くしてきたのに、地盤(後継)を名越に譲ると決めたことが納得できなかった」。この“尽くした側の怒り”は、綺麗に正当化しやすいぶん、犯罪へ滑り落ちるスピードも速い。
藤枝がまずやったのは、名越への刷り込みだ。
「渡海議員は安本という男に脅されている」
「自分が安本を始末する。だからアリバイ工作に協力してほしい」
名越は“議員の地盤を継ぐ話”が潰れるのを恐れ、藤枝の話に乗る。結果、名越は自分が守りたい未来のために、未来を奪う側へ回ってしまう。皮肉だ。
そして当日、名越の携帯にかかった電話は「名越自身が別の携帯からかけたもの」。これで名越は自然に会場を出られる。駐車場の車内で安本に変装し、18:50頃に“安本として”会場へ戻る。これで、
- 名越は会場にいない時間を作りつつ
- その後は“安本として会場にいる”ため
- 目撃証言が「安本がいた」ことの裏取りになる
という、証人300人を逆利用した仕組みが完成する。
パーティー終了後、藤枝は名越と合流して車内で殺害。変装の痕跡を消すため、遺体に灯油をかけて燃やす。序盤で“灯油”が違和感として提示されるのも、ここに繋がっている(あのひと言は、藤枝が情報を植え付けて誘導していた、という解釈が可能になる)。
一方の本物の安本は、パーティー当日に拘束・監禁されていた。藤枝は安本をすぐに殺さず“一日生かしておく”。理由は、死亡時刻や胃の内容物といった検視の観点から、「安本がパーティーで食事をしていない」事実が露呈するのを避けるため。翌日になってから安本を殺害し、部屋にはパーティー券の領収書や議員の著作などを残して、“議員のファンが参加していた”という偽の背景を作る。安本がただの店員だったことを思うと、完全にとばっちりで、胸が悪くなるくらい残酷だ。
決定打として、盗難車の中から凶器と思われるハンマーや、変装に使ったヘアピンが見つかる。アリバイのロジックを崩した上で、物証まで揃えていくラストは、シリーズの締めとして素直に気持ちいい。
終盤:時乃の危機、渡海一成の来訪、そして“秘密”の着地
真相へ迫る時乃のもとに、渡海一成本人が美谷時計店へやって来る。最終回らしく「時乃が危ないのでは」と身構える空気が作られるが、一成は祖父・時生の話をしに来ただけ、という形で緊張が解ける。
ただし、一成は時乃(と祖父)が“アリバイ崩し”をできることを察している。
察時が内々に時乃へ依頼している秘密も、バレかける。しかし結果として、警察署内にその秘密が広まることはなく、雄馬にも「父が犯人ではなかった」という形で救いが残る。最終回なのに不思議と“日常に戻っていく”着地で、シリーズの空気感を最後まで崩さないのが、このドラマらしい。
ドラマ「アリバイ崩し承ります」7話(最終回)の伏線

最終回は、伏線が派手に“ドーン”と回収されるというより、序盤に置いた小さな違和感が、後半で一つの設計図にまとまっていくタイプでした。ここでは「7話の中で提示された情報が、どこに着地するのか」を伏線として整理します。
「灯油」というワードが先に出る違和感
焼死体の現場で“燃料の種類”に触れる発言が出るのは、視聴者の耳にも引っかかる。最終的に「情報を植え付け、疑いを誘導するための仕掛け」へ回収される。
300人の証人=盤石すぎる設定そのもの
「完璧すぎるアリバイ」は、それ自体が“トリックの存在”を示すサイン。多すぎる証言は真実を補強するどころか、逆に“すり替え”を成立させる土壌になる。
名刺が落ちていた=「名越が巻き込まれた」だけではない
名越の名刺は“現場にいた証拠”にも“誰かが置いた誘導”にもなる。焼死で身元が曖昧な状況で、捜査を一成サイドへ引き寄せる導線として機能していた。
「地盤を誰に譲るのか」問題の提示
雄馬に譲るはずが名越へ――この設定が、藤枝の嫉妬と、名越が共犯へ引きずり込まれる動機の両方を作る。最終回の人間ドラマの根っこ。
18:34の着信と、18:35の退出
一見すると“名越が狙われた”普通の導線だが、真相は「名越が自分で自分に電話していた」。ここが崩れると、以降の目撃証言が全部ひっくり返る。
「後援会じゃない一人」安本孝之の存在
最終回のタイトルを、事件構造として具体化している伏線。300人の輪の外の“異物”がいたからこそ、替え玉(なりすまし)の疑いが立つ。
名越と安本が“似ている”という視覚情報
映像作品としての最大の手がかり。写真が出た瞬間に「入れ替わり」を疑える設計で、推理の入口を視聴者にも共有している。
焼死という処理
「証拠隠滅」として自然なだけでなく、“変装の痕跡を消す”という目的に直結していた。なぜ焼いたのかが、動機ではなくトリック回収になるのが巧い。
パーティー券の領収書、著作物などの小道具
安本を「ただの一般人」ではなく「議員のファン」へ偽装するための工作。二件目の殺人を、事件本体から切り離す“擬装”として機能する。
盗難車と、ハンマー/ヘアピン
ロジックの回収だけで終わらず、物証へ着地させる伏線。ヘアピンが“変装の道具”として回収されるのが、タイトル(アリバイ)と同じくらい、事件の手触りを現実に引き寄せる。
ドラマ「アリバイ崩し承ります」7話(最終回)の感想&考察

最終回を見終わってまず残るのは、「アリバイ崩し」という技術が、単なるパズルじゃなく“人間関係の武器”になった感触でした。証人が多いほど真実に近づけそうなのに、実際は逆。
みんなが同じ方向を向いた瞬間、嘘はむしろ守られてしまう――その怖さが、軽いテンポの中にしっかり残る回だったと思います。
「多すぎる証人」は、信頼の総量ではなく“思考停止の総量”
証人300人って、普通は正義の味方なんですよ。裁判でも捜査でも「目撃者が多い=強い」。でもこの回は逆を突く。
“多い”ことが強度になるのは、証言が独立している時だけで、全員が同じ空気を吸って同じものを見た(と思い込む)場では、証言はコピペになる。つまり、証言が増えるほど「検証」が減っていく。最終回のトリックは、そこを突いた。
名越が安本に化けて会場へ戻った瞬間、300人の証言は「安本がいた」という巨大な盾に変わる。これって、現代の情報環境にも似ている。
リポストが増えるほど“真実っぽさ”が上がっていく現象と同じで、数は必ずしも質じゃない。そういう社会的な皮肉が、土曜深夜のライトな枠でスッと入ってくるのが、僕は結構好きでした。
藤枝ミホの怖さは「悪女」より「職場にいそう」なところ
藤枝の動機は、巨大な陰謀でも、政治の闇でもない。「自分のほうが尽くしたのに」という感情。これ、誰でも芽があるんですよね。
もちろん殺人に飛ぶのは異常だけど、“評価されない怒り”や“後から来た人が抜擢される理不尽”は、職場のあるあるでもある。その“あるある”が一線を越えた時、人はどこまで合理的な犯罪を組み立てられるのか――最終回はそこを見せてきた。
しかも藤枝は、ただ衝動的に刺すんじゃない。
- 名越の心理を読む(地盤=未来を餌にする)
- 安本を拉致して“物理的に口を塞ぐ”
- 胃の内容物や死亡推定まで想定して時間差で殺す
- 小道具で背景まで偽装する
ここまで“仕事ができる犯人”だと、怖いのは能力そのものより、その能力が「嫉妬」によって駆動されている点です。努力やスキルが救いにならず、むしろ凶器になっている。
安本孝之が気の毒すぎる=このドラマが最後に見せた「代償」
シリーズ全体、どこかコミカルで、事件も“本格ミステリの型”として楽しめる距離感がありました。ところが最終回は、安本という一般人が「似ていた」というだけで殺される。ここで急に、世界の残酷度が上がる。
僕はこのギャップを、最終回の意図だと受け取りました。つまり、時乃の祖父が言っていた「アリバイ崩しは恨みを買う」「危険がある」という言葉を、事件の残酷さで裏打ちしたかったんじゃないか、と。
アリバイ崩しって、結果的に“嘘をついた人間”だけが損をするなら爽快なんだけど、現実はそうじゃない。嘘の設計図の中で、無関係の人が部品として消費されることがある。安本はその最悪の例で、視聴後に妙な後味が残るのは、むしろ誠実だと思う。
渡海雄馬の最終回は「ボンボン卒業試験」だった
雄馬って、序盤は正直、見ていてムズ痒いキャラでした。ヨイショされ、勢いで空回りし、カッコつけるけど詰めが甘い。
でも最終回で“父が容疑者”になることで、雄馬の中から虚勢が削ぎ落ちる。父を信じたい。警察官として疑わなきゃいけない。どっちにも立てない状況で、ようやく「自分の頭で捜査する」方向に足が向く。
SNSでも「まんまと予告に釣られた」「徳さんが犯人じゃなくて良かった」みたいな声があったけど、僕はそれ以上に、「雄馬が“親の看板”から離れる瞬間」を最終回に置いたのが効いていると思いました。父の存在が巨大であるほど、雄馬が“警察官としての輪郭”を掴む回になる。
察時は結局、変わらない。だからこそ続く
最終回なのに、察時は“本庁に戻る”みたいな大きい変化はしない。むしろ最後まで、時乃に頼る。これ、物語としては「成長がない」とも言えるんだけど、僕はこのドラマの正解はそこだと思ってます。
察時は、正義の人じゃなく、プライドの人でもなく、「自分の能力の限界を知っている人」。だから外部(時乃)に頼る。もちろん職務倫理のグレーはある。でも、彼は自分のグレーを自覚している。そこが憎めない。
そして時乃もまた、祖父の言葉に揺れながら、結局は“時を戻す”側に立つ。最終回でさえ二人の関係は決定的に変わらない。変わらないから、また事件が来れば、同じように始められる。終わり方が“次の一話”の始まりに見えるのは、シリーズものとして強い余韻でした。
最後に:この最終回が突きつけたのは「時間」より「人」
「アリバイ=時間の証明」って思いがちなんだけど、最終回を見て感じたのは、アリバイの正体は“時間”じゃなく“人の信頼”だということ。
- 300人が見た、という事実
- 秘書が告げた、という物語
- 息子が信じたい、という感情
全部が折り重なって、真実を隠してしまう。
時乃の推理は、その信頼の積み木を一段ずつ外していく作業だった。だからこそ、最後の決め台詞「時を戻すことができました」が、単なる決まり文句じゃなく、“人間関係の歪みを正す宣言”に聞こえる。最終回として、しっかり刺さる終わり方でした。
ドラマ「アリバイ崩し承ります」の関連記事
全話の記事のネタバレ

過去の記事についてはこちら↓



コメント