Netflixオリジナルドラマ『今際の国のアリス』シーズン3第5話は、クライマックスへ向けて一気に緊張感が高まる回です。
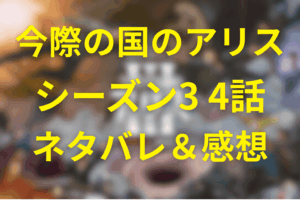
アリスはウサギを救うため、そしてジョーカーの謎を解き明かすためにさらなるデスゲームへ挑戦します。
これまで培ってきた仲間との絆が試され、裏切りや犠牲を覚悟しなければ進めない極限状態に追い込まれる展開は必見。松山龍司とバンダの思惑も一層交錯し、“今際の国”の支配構造やゲームの真意に迫る重要なエピソードです。本記事では、第5話のあらすじ&ネタバレ、見どころ、の感想・考察を詳しくお届けします。
今際の国のアリス(シーズン3)5話の見どころ
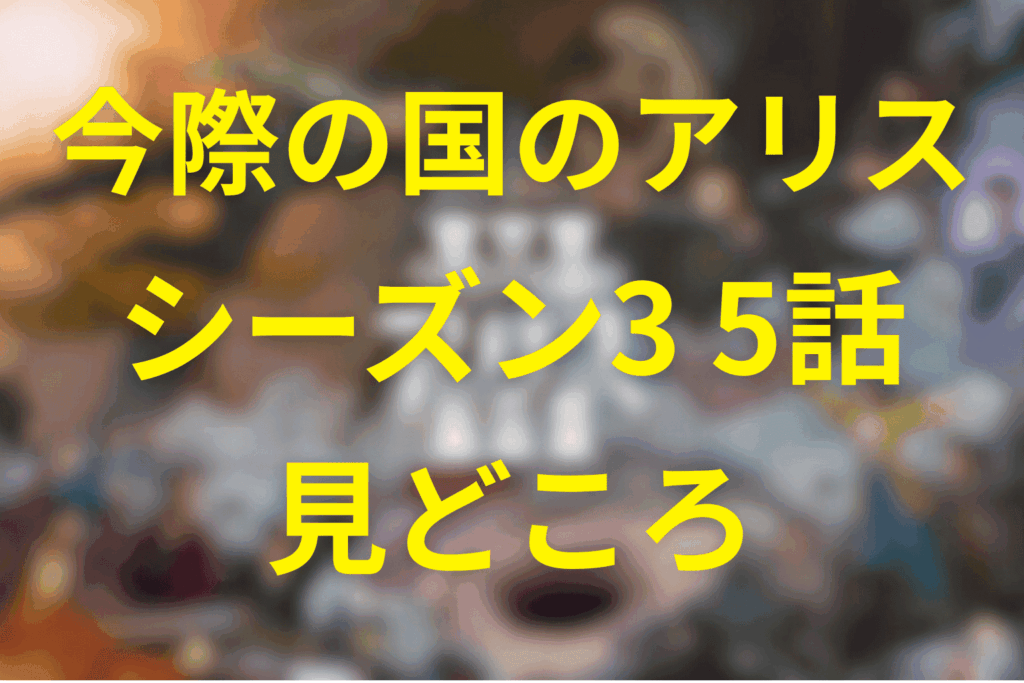
第5話は、5×5の部屋群・ポイント制・ダイスによる通過人数・ロックダウン解除という理詰めの仕組みの上に、壁面スクリーンが映す**“今後起きるな未来”を重ねた設計が最大の見どころ。
ルールは理解できるのに、見せ方が判断を狂わせる──このねじれが、シリーズの核である「正しさではなく設計**が生を分ける」を一段深く体感させる。こうだからこう、だから面白いが論理で積み上がる一話だ。
“未来”で意思決定を揺らすゲームデザイン
幸福な未来の提示が、寄り道・逸走・救出手数の増加を誘発する。
行動経済学的バイアス(楽観/現在/確証/サンクコスト)がポイントと位置の負債へ直結し、計算を壊す装置として機能する構図が秀逸。
最短ではなく“最速”を作るアリス
ダイスが許す大人数の色を優先し、近接で再合流できる分隊進行を敷くアリスの舵取りは、ゾンビ狩りやかんけりからの一貫性。救出は両側タッチの要件ゆえ、**救出余力(位置×ポイント)**をどう残すかが盤面の肝になる。
“二人分”として数えられるウサギの倫理圧
ウサギは“母体+胎児”で人数としては二人に数えられる一方、実務の手数は母体のみというねじれが、隊全体の手数設計に重くのしかかる。数えられる生命/補償されない資源というテーマが、ゲーム理論に割り込む瞬間だ。
レイとリュウジ:観客性と贖罪が盤面を揺らす
レイの秩序を設計しつつ混沌を愉しむ二面性は、合意形成の近道にも破壊因にもなり得る。リュウジは観測者/贖罪者として合理と情のはざまで迷い、30秒という時間圧の下で“間に合う最良”を探す視線が痛い。
次話への視点
出口仮説へ隊で到達するには、誰を残し誰を通すかの優先順位と、ウサギの二人問題をどう処理するかが焦点。意味(未来の見せ方)に押し流されず、人数×資源×時間の三変数を設計で上書きできるか──その成否が、最終局面の温度を決める。
今際の国のアリス(シーズン3)5話のあらすじ&ネタバレ
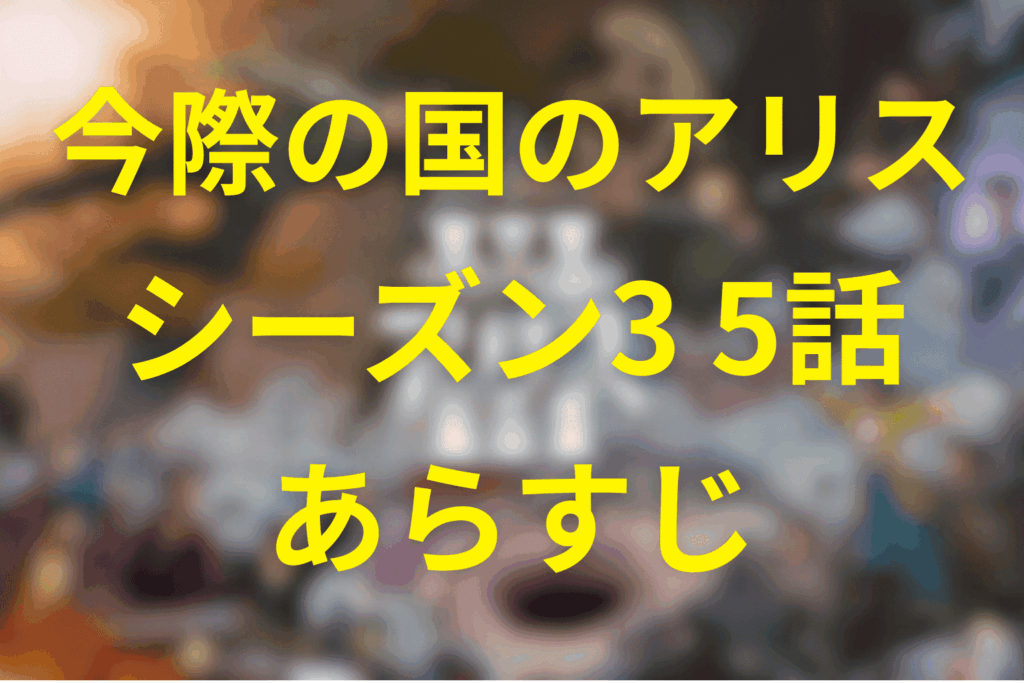
第5話は“最終局面”の開幕回。舞台はディスプレイだらけの渋谷を模した巨大な実験空間で、参加者は各所のスクリーンに映る自分のデジタル分身に導かれながら集合していく。
アリスとウサギはここで再会し、研究者リュウジとも邂逅。だが運営は「参加者は10名」と告げ、部屋の人数を数え上げていた面々は耳を疑う――ウサギの“胎児”も1人としてカウントされるのだ(ウサギ本人とは別のリストバンドを装着)。
ゲーム名は「ミライすごろく」。行った先に見えたビジョンが現実世界で起きるという生々しいゲーム。
以降はこの“未来テスト”の構造と、チームがたどる紆余曲折を整理する。
ルール概要:5×5の迷宮、15ラウンド、ポイント制
- フロアは5×5=25室のマトリクス。各ラウンド、中央台座のダイスを振り、出目の人数だけ次の部屋に進める(色でドアとダイスが対応)。
- 初期ポイントは全員15。移動には1ポイント消費、同室待機はラウンドごとに1ポイント減。ゼロになると失格(死亡)。
- ロックダウン:ダイスの都合で動けず取り残された者の部屋は施錠。隣接2室の両側から、他プレイヤーがリストバンドを同時タッチして解除しなければ救出できない。
- 一部にはマイナス部屋(−1〜−8)があり、入室者から追加でポイントが引かれる。
- 各室の壁面にはその人の“可能な未来”の映像が映り、どの色(進路)を選ぶかで見せられる未来(今後起きる未来)が変化する――出口に至るまで計15ラウンド。
要点は三つ。
①人数制約(ダイス)と②資源制約(ポイント)が③心理誘導(“良さそうな未来”)で揺さぶられる。こうだからこう――理詰めの経路設計と感情の制御を、同時に走らせないと生き残れない。
集合と再編:アリス・ウサギの合流、そして“10人目”の宣告
序盤、分断されていたメンバーは“分身”に先導されながら再集合。
アリスはウサギと抱擁を交わし、リュウジを殴って鬱憤をぶつけるが、ウサギは「この世界に戻ったからこそ、向き合えた」とリュウジを責めない。ここで追加参加者として兄妹のソウタとユナが登場し、合流した9名+胎児の“10人”で最終ゲームが動き出す。
進軍の方針:「人数が多く通れる色を優先」+「再合流の動線」
アリスの基本方針は明快。
ダイスが多人数を許す色=“大きい枠”を優先してポイント散財を抑え、近接室で再合流できるよう色分けで分隊しながら進む――“最短”より“最速”の設計だ。各自の位置は腕時計のマップ機能で共有でき、通話も可能。理屈の上では迷いづらい布陣だ。
罠(1):“良い未来”の誘惑――ソウタ&ユナ、そしてノブの逸脱
部屋によっては“幸福な未来”が提示される。
兄妹のソウタとユナは映像に心を揺すぶられ、アリスの制止を振り切って別ルートへ。
だがその**“ハッピー色”の先にはポイント大幅減が待っていた。
さらにノブも同様に逸走して致命的な減点を食らい、全体の救出リソース(解除タッチに動ける余力)が逼迫する。こうだからこう――良い未来の提示=安全ではない。設計外の寄り道は、ロックダウンの増加と救出コストの膨張を招き、隊の寿命を縮める。
罠(2):マイナス部屋――テツの“−8”即死
薬物依存の過去に苛まれてきたテツは、かつての恋人ユキコの映像に吸い寄せられるように**“−8”部屋**へ。入室時点の残ポイントが7だったため、差し引き即ゼロ――その場で死亡。
マイナス部屋は「心の急所に合わせて置かれている」ことが露骨に示され、以降、メンバーは心理戦への備えを痛感する。
罠(3):“ゼロ目”と分断――ソウタの死亡、ユナ孤立
ソウタとユナの兄妹ルートは、出目ゼロが重なったことで合流不能へ。ユナが0を出して動けず、救出の段取りが崩れる間に、ソウタは大幅減点→死亡。無為もまた死に直結することが、ポイント制の冷酷さとして刻まれる。
救出と再集結:レイのロック解除/出口仮説「A5」
レイがロックダウンに閉じ込められた場面では、アリスが回り道を組んで解除に成功。
グループは二手に分かれつつも同じ角(区画)に再集結し、出口はマップ左下の「A5」にあると仮説を立てる。ただしユナが兄を追って先走り、アリスは彼女から減点を取れずに自分の残ポイントを危険域まで削ることに。
救いたい相手に“代わって支払う”という行為が、終盤の手数を侵食していく。
ウサギの“2人分”という特殊条件
ウサギは胎児ぶんのリストバンドも持つため、移動枠(ダイスの人数)では“2人ぶん”としてカウントされる一方、ポイントは母体と共有ではない(=胎児のポイントが“温存”されているという不思議なねじれ)。
“人としてカウントされるのに、誰も胎児のポイントに手を付けない”という倫理ギミックが盤面をより難しくしたまま、エピソードは次のラウンドへ継続する。
ここまでの“設計”の勝ち筋(アリス視点)
- 「大枠を通る」:ダイスが許容する最大人数の色を優先し、ポイント消費を均す。
- 「近接で再会」:色分けによる分隊進行と時計マップで、救出に必要な“両側タッチ”の位置関係を常に意識。
- 「マイナス部屋は“心の急所”」:個人史を踏み台にした誘導を前提に、救出予備兵力(ポイント・配置)を確保。
- 「最短ではなく“最速”」:**寄り道(ハッピー映像)**に目を奪われず、隊の総当たり手数が最大化する導線だけを選ぶ。
こうだからこう――心理の罠に付き合って分断・救出・減点の負債を積むほど、**最終出口までの“時間と資源”**が失われる。感情を捨てるのではなく、感情のために理屈を先に置くのがアリスのやり方だ。
各人の局面(第5話時点)
- アリス:レイ救出でロック解除、A5出口仮説を提示。ユナからポイントを取れず自己資源を削る矛盾を抱え込む。
- ウサギ(赤ちゃん):“二人”として数えられる特殊条件に晒され、母体/胎児の線引きが倫理圧として隊全体にのしかかる。
- サチコ:ウサギと一緒に行動
- リュウジ:救出より出口優先を主張する場面があり、功利/贖罪の間で摇れる。
- レイ:ロックダウンを経験。解除後は再編の軸へ。
- テツ:“−8”で即死。心理誘導に最も脆かった存在として退場。
- ノブ:逸走→大減点で辛うじて後退・延命。
- ソウタ/ユナ:“良い未来”の誘惑でルート逸脱。ユナは0目で停滞、ソウタは減点死。
物語的な読み:ルールの網目に“理性”と“愛”をどう通すか
「ミライすごろく」は、人数・資源・時間を同時に削るS3集大成の装置だ。
救出の両側タッチは**“誰かがどこかに残らなければならない”ジレンマを生み、マイナス部屋は個人史**をえぐる。胎児の“別カウント”は、生命倫理をゲーム理論へと乱暴に接続する。
第5話は結論を出さない。だが、出口を仮定してそこへ“隊で”たどり着くというアリスの設計原理が、**私情(ユナ)や倫理(胎児)**にどう折り合いを付けるのか――次話(最終)の選択に向けて、問いを最大化して終わる。
補足:盤面の“数字”を俯瞰する(視聴メモ)
- 総室数:25(5×5)。総ラウンド:15。初期ポイント:各15。
- 消費:移動1/待機−1。ロック解除:隣接2室の同時タッチ。
- 罠:マイナス部屋(最大−8)/ゼロ目による停滞。
- 参加者:既存メンバー+ソウタ/ユナ。**ウサギの胎児が“第10の参加者”**として扱われる。
- 確定死:テツ(−8即死)/ソウタ(大幅減点死)。ノブは後退で延命。
- 戦略骨子:大枠優先/近接再合流/救出余力の確保/心理誘導への耐性。
出口仮説「A5」や各人の事件、死亡トリガー、胎児の扱いなどは第5話内で明示・示唆された内容に基づく。最終的な“未来”の帰結は第6話で確定する。主要ルール・出来事の初出は当該話レビューに整備されており、本稿でも要点のみ参照した(ルール/胎児扱い/テツ・ソウタの退場/レイ救出・A5 仮説 など)。
今際の国のアリス(シーズン3)5話の感想&考察
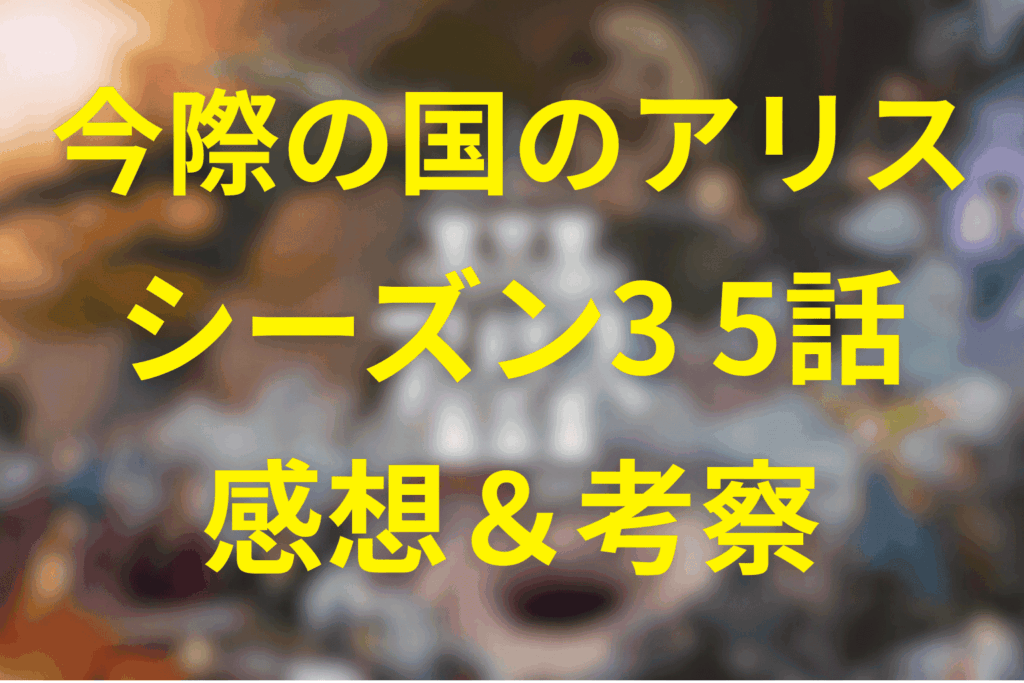
第5話は、シーズン3で積み上げてきた「多数の設計(人数)」「資源の設計(ボンベや手数)」「時間の設計(30秒・ラウンド)」に、いよいよ「意味の設計(未来)」が重ねられる回だ。
マトリクス状の部屋群、ポイント制、ダイスで決まる通過人数、ロックダウンの両側解除――ゲーム機構自体は論理的に説明できるのに、壁面のスクリーンが映す“可能な未来”が判断を濁らせる。
こうだからこう、だから面白い。勝利を決めるのは計算だけではなく、計算を揺らす“見せ方(選択アーキテクチャ)”に抗えるかどうかだ。
総評:ルールはシンプル、心理が複雑――“未来”が罠になる構図
5×5の部屋、移動=ポイント消費、待機=減点、出目が許す人数しか通れない、取り残されればロック――ここにまでなら、アリスの十八番である「最短ではなく最速」の動線設計、「救出余力」を残す隊列設計で突破できるはずだ。
ところが本話では、各室のスクリーンがそれぞれの人物にとって“今後起こる未来”を提示する。
幸福な日常、不幸な未来、埋め合わせたい過去、手を伸ばせば届きそうな救済。それらが正しい導線からの逸脱**を誘う。こうだからこう――ゲームは“計算ができる者”ではなく、“計算を最後まで守れる者”をふるいにかける。第5話は、この“最後まで”の困難さを、具体的な犠牲と救出の段取りの破綻で刻みつける。
ゲームデザイン批評:行動経済学の罠を積層させる巧さ
注目したいのは、スクリーンの「可能な未来」が、単なる“幻”ではなく行動バイアスの寄せ集めとして機能している点だ。
- 楽観バイアス:ハッピーな未来映像は、リスクを過小評価させる。
- 現在バイアス:今もらえる慰め(映像)に引き寄せられ、先のラウンドの負債(ポイント・位置)を軽く見積もる。
- 確証バイアス:見たい未来を補強する情報だけ拾い、危険表示(マイナス部屋)を見落とす。
- サンクコスト効果:逸走したあと“ここまで来たのだから”と戻れなくなる。
結果、寄り道が生む遅滞→出目の重なりで再合流不能→救出のための両側タッチ要員不足→さらに人が減る、という負の連鎖が立ち上がる。計算よりも計算を壊す絵作りに説得力を持たせることで、画面上の悲劇が“起こるべくして起こる”ものに見えるのが本話の強みだ。
アリスの意思決定:最短より“最速”、そして“救出という外部性”
アリスの舵取りは一貫している。ダイスが許す最大人数の色(大枠)を優先し、近接室に再合流できる分隊進行で進む。これは〈ゾンビ狩り〉や〈かんけり〉で見せた「最終多数を取りに行く」「最短ではなく“最速”」の系譜だ。だが本話では、救出が生む外部性がアリスを苦しめる。
ロックダウンは両側からの同時解除が原則で、救出には**“位置”と“ポイント余力”の両方が要る。
だからこそ、逸走者が出るたび隊全体の救出キャパが削れていく。アリスは“隊の最適”を優先しつつも、個別の救い(ユナやレイ)を抱え込む。ここに功利と情のバランスという新たな難問がのしかかる。こうだからこう――設計志向の主人公に、「設計からはみ出す者をどう扱うか」という倫理が課される回である。
ウサギの「二人分」という倫理:数えられる生命、計上されない手当
ウサギが“母体と胎児”の二人として数えられる一方で、ポイントや操作の主体は母体のみというねじれは、“数えられる生命”と“補償されない資源”という倫理問題を露呈させる。
- ダイス上の枠は増えるが、**実務の手数(救出・移動の主体)**は変わらない。
- つまり、集団の制約だけ増え、手当は増えない設計。
この冷酷さは、今際の国が**“生のカウント”と“生の意味”**を乱暴に接続する世界であることを改めて示す。
ウサギは“守る者”であるがゆえに、他者の生と自分(たち)の生の重さを同じ盤面で秤にかけ続けなければならない。選択の重みが増すほど、彼女が切り拓いた“枠外の解”(〈暴走でんしゃ〉の横移動など)が、次にまた必要になる予感が漂う。
リュウジの“観測者”としての苦い有用性
リュウジは、贖罪と答えへの渇きの間で足場が定まらない。彼は“出口優先”の冷徹さを見せる瞬間がある一方で、ウサギの判断に寄り添う柔らかさもある。
科学的合理と人間的情動の二重スリットを抱えたキャラは、シーズン3の「正しさではなく設計」という主題を別角度から補強する。
観測者は結局、他人の生死を材料にする危うさを孕む。その危うさを自覚しているがゆえに、彼の視線は常に痛い。
第5話では、その痛みが判断の速度にわずかな遅延を生み、30秒という圧の下で**“間に合う最良”**が何かを曖昧にする。ここが彼の人間味でもあり、盤面の弱点でもある。
バンダの“意味の運営”――誘因としての愛
画面に映る未来は、ゲームの出題というより**“意味”の運営に見える。
参加者を盤面へ引きずり続ける誘因として、愛・後悔・希望が手際よく配される。ウサギが先に連れ戻され、アリスが追随する構図もその一環だ。第5話の「可能な未来」は、アリスとウサギを盤面に縛り続ける必然として機能している。こうだからこう――ジョーカーステージは難易度でなく意味の密度で圧をかけてくる。バンダはその密度を最大化する“物語の運営者”**として立っているように見える。
キャラクター別・ミクロな気づき
- アリス:隊の総当たり手数を最大化する設計者でありながら、個の救済を抱える。ここでの矛盾が、次話の選択をさらに重くする。
- ウサギ:数えられる二人としての圧を背負い、“枠外の解”を再び発明できるかがカギ。
- レイ:観客性と設計の二刀流。最後の最後でどちらに倒れるかが、物語の引き金になり得る。
- リュウジ:痛みを自覚する観測者。決断の遅延は弱点だが、後悔を避けるための理性もまた彼にはある。
- ノブ/ソウタ/ユナ/テツ:未来の見せ方が人をどれほど簡単に逸走させるか、そして隊列がどれほど脆いかを示す装置として機能。残酷だが、物語上の要。
SNS温度感(印象的な論点)
- 「良い未来が罠」という構図への評価が高い。救いに手を伸ばす行為そのものが隊の寿命を縮める――その皮肉に打ちのめされた声が多い。
- ウサギの二人カウントは賛否を呼ぶ。生命倫理をゲームルールで扱う“荒さ”に反発もあるが、作品の主題(生の意味の設計)に踏み込むためには必要だった、という擁護も。
- アリスの「最速」設計への支持は根強いが、“個の救い”を抱えたことで見せた迷いに“人間らしさ”を見いだす声が散見。
まとめ:正しさではなく、揺らぎまで含めて設計せよ
第5話が突きつけたのは、計算を壊す“見せ方”まで織り込んだ設計の必要性だ。
- 人数(誰と誰が同室か)
- 資源(残ポイント/救出余力)
- 時間(ラウンド/ロックタイミング)
- 意味(スクリーンの未来が生む逸走と合意崩壊)
こうだからこう、だから面白い。勝負は“解き方”ではなく、“解き方が崩れる瞬間の耐性”で決まる。アリスは最速の導線を描き続け、ウサギは枠外の跳躍で檻を破ってきた。第5話は、その二人の生存術を意味の圧でさらに試す。
次話、彼らは「間に合う最良」を選び切れるか。
未来の見せ方に押し流されず、自分たちの未来を“設計”として確定できるのか。結末を前にしてなお、私はこの物語を論理で信じたい――人は、揺らぎごと設計できる、と。
今際の国のアリス(シーズン3)の関連記事
全話まとめた記事はこちら↓
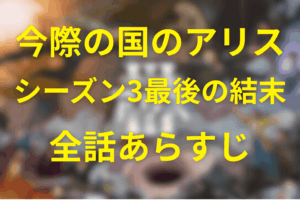
シーズン3の6話(最終回)はこちら↓
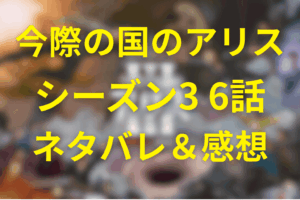
1のネタバレはこちら↓
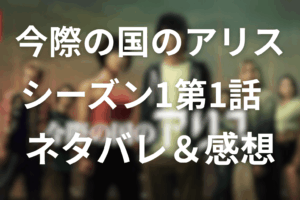
シーズン2のネタバレはこちら↓
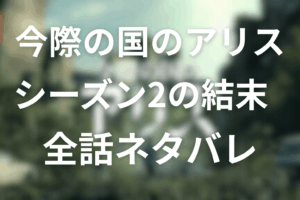
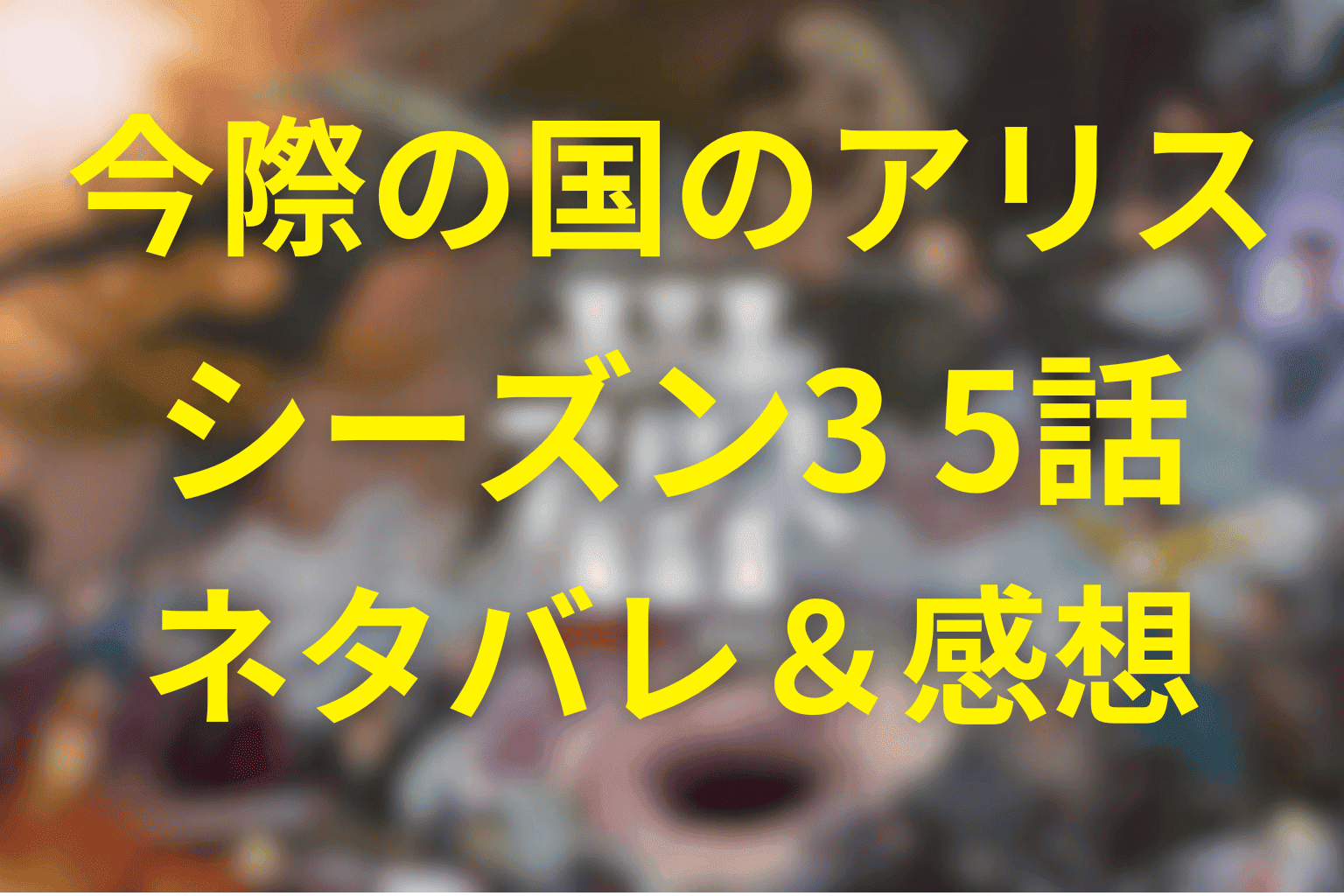
コメント