Netflixオリジナルドラマ『今際の国のアリス』シーズン3第4話は、シリーズのターニングポイントともいえる緊迫のエピソードです。アリスは新たなデスゲームに挑み、仲間を守るために極限の決断を迫られます。
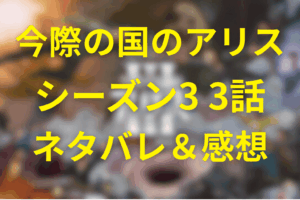
松山龍司とバンダの思惑、そしてジョーカーの真相に近づく手がかりが次々に浮かび上がり、物語はさらに深い混迷へ。第4話は「生と死」「信頼と裏切り」が交錯する重要な回であり、今後の展開を大きく左右する内容となっています。
本記事では、そのあらすじ・ネタバレを詳しく振り返り、見どころや考察をお届けします。
今際の国のアリス(シーズン3)4話の見どころ
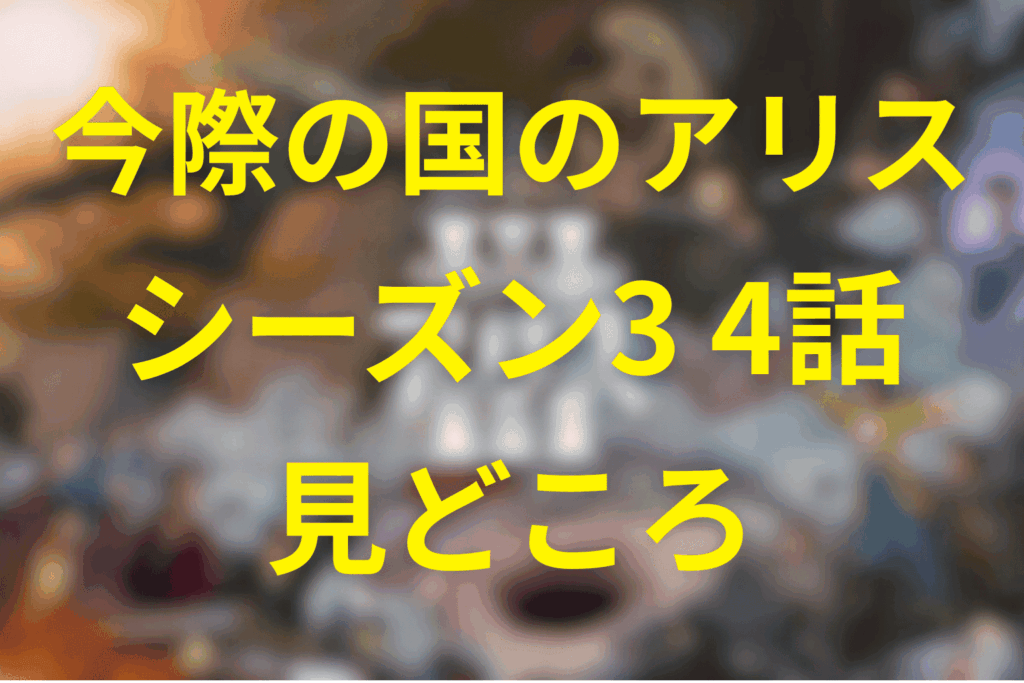
第4話は、前話で提示された「多数」「資源」に“時間の設計”が重なり、意思決定の難度が一段跳ね上がる回。
〈暴走でんしゃ〉→〈東京ビンゴタワー〉の垂直系サバイバルと、アリス陣営の〈かんけり〉という水平系の集団戦を平行編集で畳みかけ、正しさではなく“設計”が生を分けるというS3の主題を体感で刻み込む。
盤面の読み替え、隊列の組み方、時間の使い方──こうだからこう、だから面白いが論理で積み上がる一話だ。
① 30秒が自由を奪う〈暴走でんしゃ〉
各車両に入った瞬間から30秒の判断を強いられ、ボンベ5本の配分が未来の自由を削っていく。安全側を積み上げるほど後半の選択肢が痩せるという逆説が鋭く、ウサギは最後に“枠外”=横移動で出口を発明。二択の外に第三の正解を設計する瞬間が痺れる。
② 揃えるほど落ちる〈東京ビンゴタワー〉
ボタンを押してラインが揃うほど鋼球が激化。
ロープ連結は救いであり重荷でもある。高度・順番・役割を段取りしたチーム運用が肝で、FREEマスへ向かう終盤の“単独性”が、ウサギの輪郭(守る/切り拓く)をさらに濃くする。
③ 最短ではなく“最速”を設計する〈かんけり〉
“缶=タイムボム”ゆえに投げて近道が必ずしも正解ではない。
アリスは受け手→差し手→偽受け手の動線で妨害を無効化し、最短ではなく最速を作る。自分が通るより人を通すための自分を使う姿勢が、〈ゾンビ狩り〉からの一貫性として光る。
④ キャラクターの両義性と演出の圧
秩序を設計しつつ混沌を愉しむレイの“観客性”、リュウジの贖罪を帯びた観測者目線が物語に陰影を与える
。音響は金属音+短いアラームで時間圧を身体化、画面は密度の出し入れで自由度の増減を見せる。人数×資源×時間の三変数を同時に回す難しさが、映像と編集で心拍に刺さる。
今際の国のアリス(シーズン3)4話のあらすじ&ネタバレ
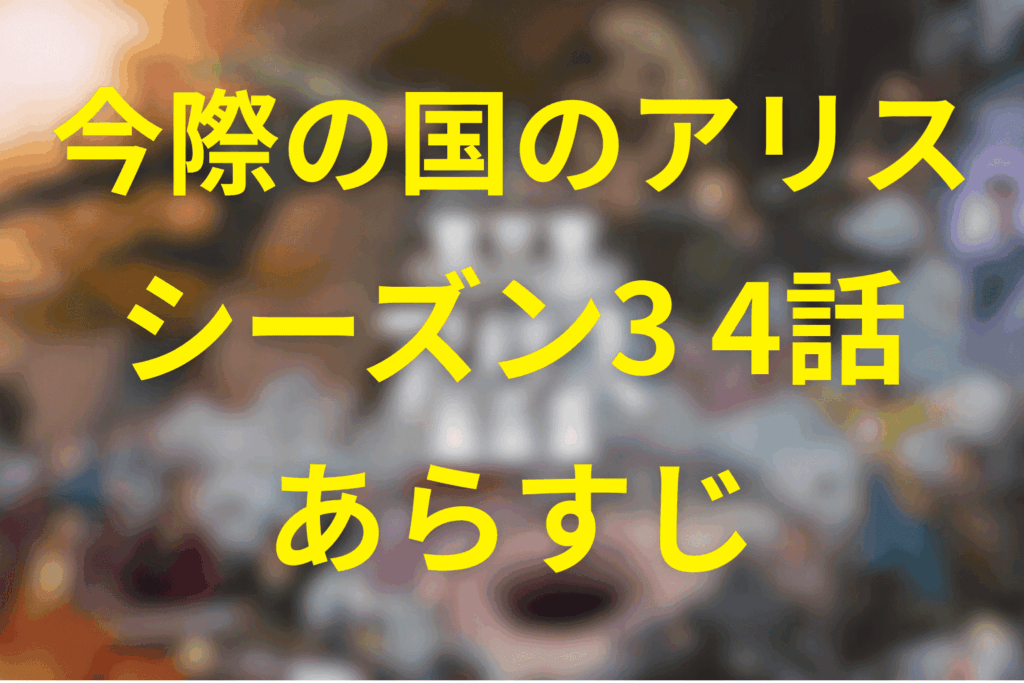
第4話は、ウサギ&リュウジの〈暴走でんしゃ〉がクライマックスへ突入し、その勢いのままセミファイナル〈東京ビンゴタワー〉へ雪崩れ込む“垂直の死闘”パートと、ゾンビ狩りを生き延びたアリス側のセミファイナル〈かんけり〉が爆発的な集団戦へ転じる“水平の総力戦”パートが平行編集で描かれる。
こうだからこう――前話までに積み上げた「人数の設計」「資源の設計」が、今回は“時間の設計”として試される回だ。全体の流れを、主要局面ごとに追っていく。
暴走でんしゃ(前半)――30秒の選択が自由を削る
ウサギとリュウジ、そして同乗する数名は、最後尾から先頭車両(全8両)へ辿り着き非常停止させればクリアというルールのもと、各車両入室後30秒以内にガスマスクを装着する/しないを判断しなければならない。4両には毒ガスが仕掛けられており、各自に配られた中和ボンベは5本。一度入った車両から後戻りは不可、ボンベの譲渡・強奪も不可という、読みの外し=即死の設計だ。
序盤、ウサギは“安全側”に倒す判断を続け、ボンベの減りが早い。これは正しく見えるが、残り距離に対して選択肢が痩せるという“将来の不自由”を招く。リュウジは節約寄りの提案を重ねる一方、30秒の圧は乗員の動揺と微妙な意見のズレを誘発。結果、温存か、保守かの綱引きで、チームの合意形成が遅れがちになる。
ここまでの「正しさの積み重ね」が、次の車両での自由を削っていく――この逆説が、本ゲームの心理負荷のコアだ。
暴走でんしゃ(中盤)――見栄と直感が死を呼ぶ
中盤で一行は“酸素車両”と“毒ガス車両”を交互に引き当て、判断の疲弊が露わになる。判断を誤った者は即座に崩れ落ち、残った者は次の30秒に追われる。ある乗員は勘の連勝に優越感を見せるが、たった一度の外しで喀血し、足を引きずりながら脱落。
別の乗員は周囲の空気に流されるかたちでマスクを外し、数秒後に痙攣し倒れ込む。こうだからこう――“集団で正しくあること”と“個として生きること”は常に緊張関係にある。
チームはボンベ残量と残り車両数を睨みつつ、「ここは使う」「ここは賭ける」をギリギリで擦り合わせるが、賭けに外れた瞬間の犠牲は必ず誰かを連れていく。安全の選択と賭けの失敗が、ほぼ同じ速度で乗員を減らし始める。
暴走でんしゃ(後半)――横移動という第3の選択肢
先頭まであとわずかという局面で、残弾の少なさと読みの迷いが致命的になる。
並走する別列車が現れ、「前へ」以外の選択肢――“横へ”が開く可能性に賭ける決断を下すのだ。
タイミングを合わせ、連結上から横移動。足場の悪い鉄骨、風圧、残弾ゼロの恐怖――条件は最悪だが、縦の一本道というルールに“横の余白”を見つけることこそ、ウサギの生存直感の真骨頂だ。
緊張の末、横移動からの非常停止に成功。
生存者はわずかに絞られるが、彼らはこの“逸脱の正しさ”でクリアを勝ち取る。
結論:〈暴走でんしゃ〉は資源(ボンベ)と時間(30秒)によって「未来の自由」を削る装置であり、ウサギは“枠の外”に出口をつくることでこの装置を裏返した。
セミファイナル①:東京ビンゴタワー――垂直の死闘
暴走でんしゃの勢いのまま、ウサギたちは〈東京ビンゴタワー〉に挑む。
東京タワーの骨組みを縦横に登攀し、各所に設置された数字ボタンを押すたびにビンゴシートの該当マスが点灯。
縦・横・斜めのラインを“揃えたチーム”が勝利するルールだ。FREEマスは最頂部。ところが、数字を点けるたび、上部から巨大な鋼球が落下し、クライマーたちを物理的に振り落としてくる。
- 登るほどに降る――リスクは上へ行くほど増大。
- 繋がるほどに落ちる――ビンゴの達成に近づくほど、落下頻度と球のサイズが上がる。
- 隊列を組め――ロープで身体を結ぶか否か、分散か集中か、チーム設計が問われる。
序盤は低層の盤面形成に専念し、中層でラインの目を作る。中盤、鋼球の直撃で数名がロープごと引き剥がされ、骨組みの隙間へ吸い込まれる。救いに向かった者が共倒れという地獄の連鎖も発生。“人を助けたい”が“隊列の重心を崩す”という無慈悲な算術が支配する。
終盤、最頂部のFREEに届かなければラインが完成しない状況で、ウサギは単独での最終アタックを選ぶ。片手で梁、片手でボタン、タイミングを見て躰をひねる、ウサギはFREEにタッチ。ラインが完成し、チームはクリアする。だがその足元には、戻れなかった者たちの空白が生々しく残る。
結論:〈東京ビンゴタワー〉は“揃える”=“落ちる”*という二律背反の装置。高度を取るほど、絆(ロープ)が重荷にも救いにもなることを刻み付ける。
セミファイナル②:かんけり――水平の総力戦
一方、〈ゾンビ狩り〉を生き延びたアリス側には、もう一つのセミファイナル〈かんけり〉が割り当てられる。ルールは原型の“缶蹴り”を拡張したものだ。
- 会場中央に“缶”(発見=起動でタイムボム)。
- 制限内に缶を“元の台座”へ戻すことができれば、その缶でクリアできる人数は限定(=先着の上限がある)。
- 計10本用意された缶を、チームでリレーのように運搬しなければタイムオーバーで爆発。
- 缶が起動した瞬間に争奪戦が加速し、妨害・強奪・肉弾戦が同時多発する。
ゲームが始まるや、最初の缶は“起動→ルート確保→台座戻し”に失敗し爆発。
二本目は投擲でショートカットしようとした者が空中でキャッチをミスし、起爆の連鎖に巻き込まれる。こうだからこう――時間が敵であると同時に、“早道をしたい”気持ちが最大の敵なのだ。
アリスは一直線の突破ではなく、人の動線と死角を読み、缶を“受ける位置”と“差し出す位置”を数メートル単位で最適化。遮蔽物の角で一度だけ止めて角度をつけ、最短ではなく“最速”のラインを引く。妨害に来る相手には“偽の受け手”を立ててルート認知をズラすなど、戦術的フェイントも駆使。
だが混戦のさなか、利害の衝突は避けられず、乱闘→缶の落下→爆発のスパイクが立つ。直撃を受けた者、衝撃波で壁に叩きつけられた者――立て続けの退場に場の空気は血の匂いに包まれる。
終盤、残った缶の本数と時間の釣り合いが崩れ、“最後の枠”を巡る争奪が激化。アリスは自分がクリア枠に入ることよりも、味方の通過率を上げるラインづくりを選び、自ら囮となって妨害を引き受ける。
台座へ滑り込む仲間の背中を見届けたとき、アリスは反対側の缶の軌道で巻き込まれかけるが、起爆カウントの癖を読んだ最終の横ステップで回避。爆炎の縁を抜け、視界に残るのは生還した人数の数字だ。
アリス陣営で生き残ったのは5人。
有栖良平(アリス)、サチコ、ノブ、レイ、テツ
シオンとナツは爆発に巻き込まれて死亡、カズヤはアリスを通すために死亡。
結論:〈かんけり〉は“速さ”を“短さ”と誤読した者から脱落する集団ゲーム。アリスは「最短」ではなく「最速」を設計し、人を通すために自分を使うことでチーム全体のクリア率を押し上げた。
リュウジの回想――“死後の世界”に取りつかれた理由
〈東京ビンゴタワー〉の前後で、リュウジの過去が断片的に明かされる。
彼は大学の助教として臨死体験の再現に執着し、ある女子学生との“実験”で取り返しのつかない結果を招いた。世間的・法的には不起訴だったものの、自責は彼の心身を食い荒らし、やがて事故で半身不随となって今に至る。
だからこそ彼は、“あの境界”に確かな法則があると信じたい。今際の国は偶然でも悪夢でもない――そんな確証への渇きが、彼をここまで引っ張ってきた。ウサギの危機に躰が勝手に動くのは、贖罪と検証が同じ場所に根を張っているからだ。
バンダの狙い…ウサギやこの世界へ呼んだ理由。アリスを「国民化」させる/壊す
バンダがウサギを選んだのは、アリスの「最も強い動機」を直接揺さぶるためです。
- アリスは「正しさ」より「設計」で生を切り拓く“盤面の書き換え”プレイヤー。彼が盤面から降りてしまえば、〈ジョーカー〉は成立しにくい。
- そこでウサギを先に境界へ引き込む。愛と責任という“揺るがない動機”を突けば、アリスは必ず戻る。
- さらに、極限状況の連続(30秒判断/資源の圧/高度恐怖/集団ゲームの残酷さ)をウサギに浴びせ、アリスに「救えなさ」を突き付け続けることで、
- ① アリスを“国民化”させる(境界に残す) か、
- ② 逆に“世界を畳む答え”へ踏み込ませる(=ジョーカーの核心に触れさせる)か、
どちらに転んでも“実験は進む”。
ウサギ=誘因/状況圧=分岐の押し上げ。バンダにとって、アリスが再起動すること自体が勝ち筋。
生き残りの重力――数字・資源・時間の三面張り
第4話は、
- 数字(最終人数=勝敗)、
- 資源(ボンベ=自由度)、
- 時間(30秒・カウント=判断の圧)
という三要素が互いの制約条件になり、“正しさ”が必ずしも“生存”と一致しないことを、複数ゲームの体感として叩き込んでくる。こうだからこう――多数・節約・猶予の三つ巴で生は決まり、どれか一つだけ正しくても死ぬのだ。
次回への布石――「頂上」と「終端」の先で
- ウサギ側は、垂直の死闘を越え、心身の疲弊と答えへの渇きが臨界に近づく。リュウジの“観測者”としての顔が、決断の瞬間にどう作用するか。
- アリス側は、集団のクリアを優先する姿勢が個の倫理にどう跳ね返ってくるか。仲間の減耗と次のゲーム構造が、彼の“設計志向”をさらに尖らせるはずだ。
- バンダとジョーカーの思惑は、ゲームの難易度ではなく“意味の配置”で圧をかけてくる。答えへ手を伸ばすほど、選ぶ自由は狭まる――このねじれが、いよいよ臨界に達する。
ルール要点の簡易メモ
- 暴走でんしゃ:8両/入室後30秒でマスク判断/毒ガスは4両/ボンベ各自5/後戻り不可/横移動の可能性あり。
- 東京ビンゴタワー:数字ボタンで縦・横・斜めライン/FREEは最頂部/点灯ごとに鋼球落下/ロープ運用の隊列設計が生死を分ける。
- かんけり:缶の起動=タイムボム/台座に戻せばクリア枠が発生(先着・定員あり)/10本の缶/リレー設計(受け手・差し手・偽受け手)と動線の最適化が肝。
今際の国のアリス(シーズン3)4話の感想&考察
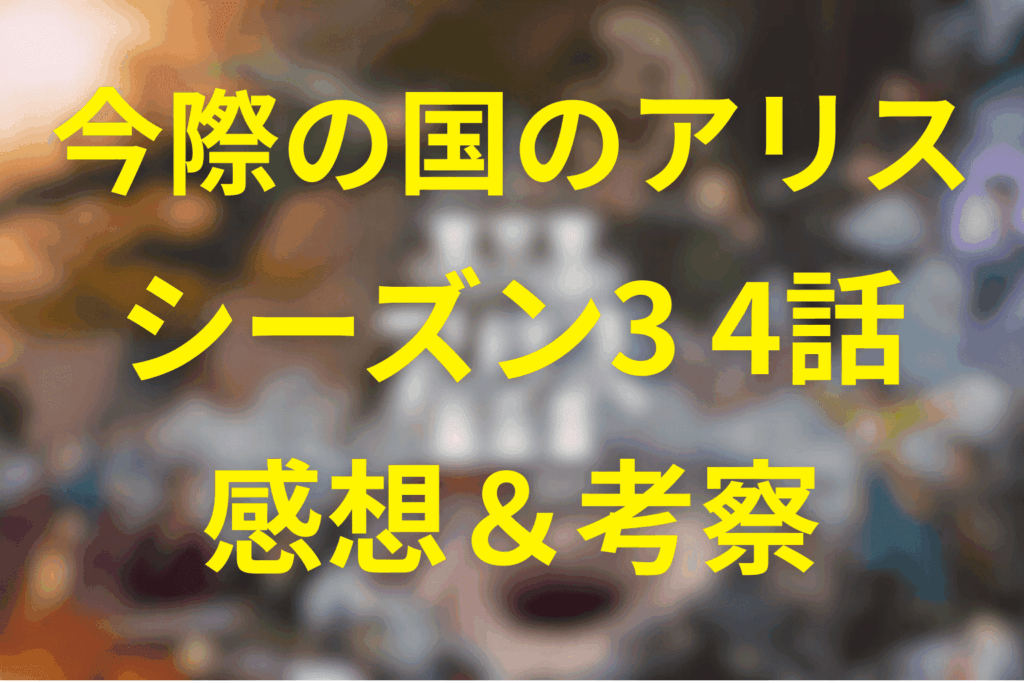
第4話は、前話までで提示された「多数の設計(人数)」「資源の設計(ボンベ)」に加え、ついに「時間の設計(30秒・カウント)」が本格的に牙を剥く回。
ウサギ&リュウジが挑む〈暴走でんしゃ〉と、そこから雪崩れ込む〈東京ビンゴタワー〉、一方でアリス側の〈かんけり〉が始まる“二本柱+平行編集”で、正しさよりも設計こそが生を分ける――というシーズン3の主題が、より立体的に可視化される。
こうだからこう、だから面白い。以下、筆者で深く掘る。
① 総評:第4話は“時間の設計”が物語を支配する回
第4話全体を貫くのは、決められた時間の中で、未来の自由をどう残すかという問いだ。〈暴走でんしゃ〉の30秒判断×後戻り不可や、〈かんけり〉のタイムボム化する缶は、そのまま視聴者の呼吸を詰まらせる装置になっている。
数字(人数)・資源(ボンベ)・時間(30秒)の三面張りで意思決定を迫り、正しさの積み重ねが未来の自由を削るという逆説を、体感として叩き込む。
ここで作品は、「勝利条件の逆算」をできる者だけが前へ進める――という冷酷なルールを確定する。
② 〈暴走でんしゃ〉のゲームデザイン:30秒が自由を刈り取る
入室と同時にカウントが走り、30秒以内にマスク装着を決める。4両が毒ガス、ボンベは各人5本、後戻り不可、ボンベの共有不可。
数式にすればシンプルだが、心理はシンプルではない。なぜなら、安全側を積み上げるほど後半の選択肢が痩せるからだ。短期の安全(今の正しさ)は、長期の自由(後の選択肢)を蝕む。
第2話の〈おみくじ〉で経験した“誤差=制裁”が、ここでは誤差=選択肢の減少という地味な形で襲ってくる。こうだからこう――急ぎすぎる正しさは、のちの“詰み筋”を自ら呼び込む。
③ ウサギの意思決定:保守的な正しさと、未来の自由のトレードオフ
ウサギは“生かす”ために安全側を選ぶ。その選択自体は正しい。
しかし、“正しさの連続”が資源を削るのも事実である。リュウジは節約寄りの提案を重ね、直感と期待値の狭間で小さな軋みが生じる。
ここで見えてくるのは、ウサギというキャラクター“守りの強さ”と“未来を削る危うさ”の同居だ。彼女は人を生かしたい――だからこそ、次の選択肢の余白まで引き受ける設計が追いつかない瞬間がある。第4話は、その矛盾を白日の下にさらす。
④ 枠外への跳躍:横移動という“第三の選択肢”の意味
物語のハイライトは、並走してきた別列車への横移動だ。ルールに明示されていない“横”。
これこそウサギの真骨頂――縦の一本道に、横の余白を見つける。こうだからこう。
- 与えられた二択(装着/非装着)の外に、第三の正しさを発明する。
- それは“賭け”だが、詰み盤面の確率分布を再配列できる賭け。
- “未来の自由”を守るには、既存の選択肢の外側へ一度出る勇気が要る。
この横移動は、時間と資源に縛られたゲームを、空間操作で裏返す鮮やかな手であり、ウサギが“守る”だけでなく“切り拓く”側にも立てることを証明する。
⑤ 〈東京ビンゴタワー〉:揃えるほど落ちる――二律背反の装置
数字ボタンを押すたびに盤面が“揃い”に近づく。だが同時に、上から鋼球が落ちてくる頻度と威力が上がる。揃える=落ちる可能性が増えるという二律背反。
ロープで身体を連結するか否か、“絆”が救いでも重荷でもあることが、冷然と突きつけられる。
⑥ FREEマスを押すという“単独性”:ウサギはなぜ上で一人になるのか
最頂部のFREEマスを押すのは、最後は一人の身体になる。重量配分・ロープ角度・鋼球の落下リズム――複合的な時間地図をウサギは身体で組み上げる。実はこの“単独性”は、彼女のキャラアークと呼応している。
- 〈暴走でんしゃ〉で“横”を発明した彼女は、自分の判断で他者の未来を押し広げることを覚える。
- 〈東京ビンゴタワー〉のFREEでは、“個の決断”がチームの線を完成させる。
守るために、ひとりになる。この逆説がウサギの輪郭をさらに濃くする。
⑦ リュウジの回想:観測と贖罪――“答え”への渇きの正体
リュウジの過去――臨死体験の実験に執着し、取り返しのつかない結果を招いた――は、彼が〈今際〉に固執する理由を説明する。
世間的な責任は問われなかったとしても、自責は彼の内部で燃え続ける。だから彼は、今際の国を“検証の場”として信じたい。ウサギを支え、時に自分の身を投げ出す行動の背後にあるのは、贖罪としての科学だ。
この“観測者”の目線は、〈暴走でんしゃ〉と〈東京ビンゴタワー〉での“発見の瞬間を待つ”視線にもなっていて、説明なくして画面の密度を上げている。彼は物語の推進力というより、意味の照明係として機能する。
⑧ 〈かんけり〉の本質:最短ではなく“最速”を設計する
アリス側の〈かんけり〉は、“缶を台座に戻す”という単純目標をタイムボムが濁らせるゲーム。
最初の数本は“投げれば早い”に見えるが、キャッチミスひとつで爆発の連鎖が起き、会場の幾何学は瞬時に狂う。アリスはここで動線設計に徹し、“受け手→差し手→偽受け手”の三段を数メートル単位で組む。
こうだからこう――
- 最短経路は危険地帯を直通する確率が高い。
- 最速経路は迂回+一拍の“角度付け”で、妨害を無効化する。
- 人を通すための自分になる(囮の引き受け、視線誘導)。
“自分がクリアすること”より“通過率を最大化すること”。多数設計の倫理がここで再演され、〈ゾンビ狩り〉→〈かんけり〉のアリスの一貫性が美しく繋がる。
⑨ 三要素の交差:人数×資源×時間の“設計方程式”
第4話の圧巻は、人数(最終多数)×資源(ボンベ)×時間(30秒/カウント)という三要素が、互いの制約になっている構図だ。
- 人数は〈ゾンビ狩り〉・〈かんけり〉に回帰し、最後の多数が価値を持つ。
- 資源は〈暴走でんしゃ〉で、短期の安全と長期の自由をトレードオフにかける。
- 時間はどのゲームでも判断の圧として、“最適”ではなく“間に合う最良”を選ばせる。
この三変数を同時に回すことが、“ジョーカーステージ”で生き残るための設計方程式。正しさは変数のひとつに過ぎず、設計がその外側を決める。
⑩ レイの“観客性”とバンダの影:秩序は誰のためにあるか
レイは〈信頼バリケード〉で秩序を設計するが、局面が荒れると「面白くなってきた」と呟くタイプだ。
秩序=退屈、混沌=劇的という価値観が、彼女の内部でせめぎ合う。彼女が観客である限り、最後の一歩で“刺激の側”に倒れる危険が常に消えない。だからこそ魅力的でもある。
そしてバンダ。彼は難度で圧をかけるというより、意味の配置で圧をかけてくる。なぜ戻るのか、何を確かめたいのか――問いの角度を操作することで、登場人物たちの“選び”を変える。ゲームのルールよりも物語のルールを運営している存在として、じわじわ重く、嫌な位置に立っている。
⑪ 映像と音響:体感として“設計”をわからせる
- 〈暴走でんしゃ〉:金属音+短いアラームで30秒の圧を身体に入れ、画の圧縮/抜けを交互に当てて、選択肢の痩せを視覚化。
- 〈東京ビンゴタワー〉:上からの落下音の質量感が一段ずつ増し、カメラの“揺れ”がロープのテンションを伝える。揃えるほど危ないを耳と目で納得させる。
- 〈かんけり〉:爆発音の余韻が反響で“角”に溜まり、受け渡しのテンポを音楽的に刻む。“最速”はリズムで作ることが、無言で伝わる。
⑫ SNS温度感(総観):賛否の割れ目
- 〈暴走でんしゃ〉の横移動に「ご都合」と「発明だ」の声が割れる。個人的には“枠外へ跳ぶ”主題の視覚化として必要十分。
- 〈東京ビンゴタワー〉の落下演出は総じて高評価。助けたい vs 隊列の地獄算術を容赦なく切り取った点に賛辞が集まる。
- 〈かんけり〉は「最短と最速の違い」に気づく人が多く、アリスの“人を通す”倫理への支持が厚い。
⑬ 次話への予測:高度の先、終点の先で
- ウサギ:守りの正しさから一歩進んで、未来の自由を守るための切り札(枠外への跳躍)を覚えた。次話では“誰のための自由か”の選択が試されるはず。
- アリス:多数設計の徹底が、個の倫理にどう跳ね返るか。救えなかった人数が視線の端に残り続けるはずで、彼の次の“負け方”の設計が気になる。
- レイ:観客から演者へ踏み込むか。面白さと生存の天秤が、ついに割れる可能性。
- バンダ:ゲーム難度ではなく意味の難度を上げ続けるだろう。答えへ近づくほど、自由は狭まる。
⑭ まとめ:正しさではなく“設計”が生を分ける
第4話は、多数(人数)×資源(ボンベ)×時間(30秒/カウント)の三軸を絡め、“正しさ”がいつも“生存”と一致するわけではないことを、複数ゲームの体感として示した。こうだからこう、だから面白い――
- 勝利条件が“最後の多数”なら、戦略の主語は“私”ではなく“私たち”。
- 資源が有限なら、今の安全は未来の自由を削りうる。
- 時間が圧なら、最適ではなく“間に合う最良”を選び続ける胆力が要る。
そして、枠の外へ跳ぶ(横移動/FREE)ウサギと、自分を使って人を通す(動線設計/囮)アリス。二人の“設計者としての在り方”が照応し始めた点こそが、4話最大の収穫だ。次話、この設計が倫理や愛とどう再接続されるか――そこに視線を据えて、続きに飛び込みたい。
今際の国のアリス(シーズン3)の関連記事
全話まとめた記事はこちら↓
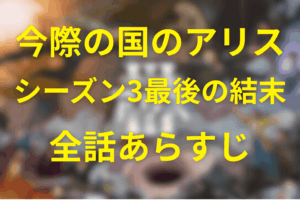
5話についてはこちらの記事をチェック↓
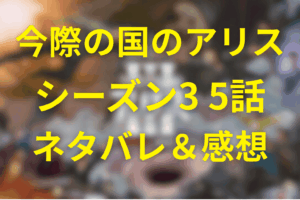
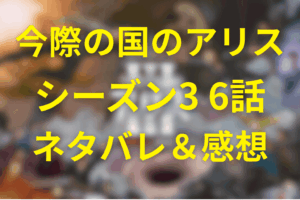
1のネタバレはこちら↓
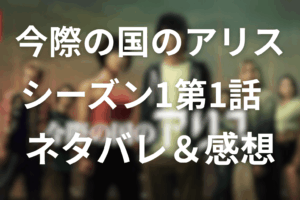
シーズン2のネタバレはこちら↓
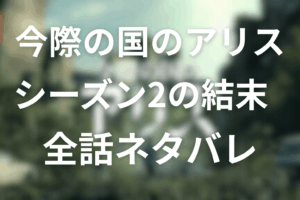
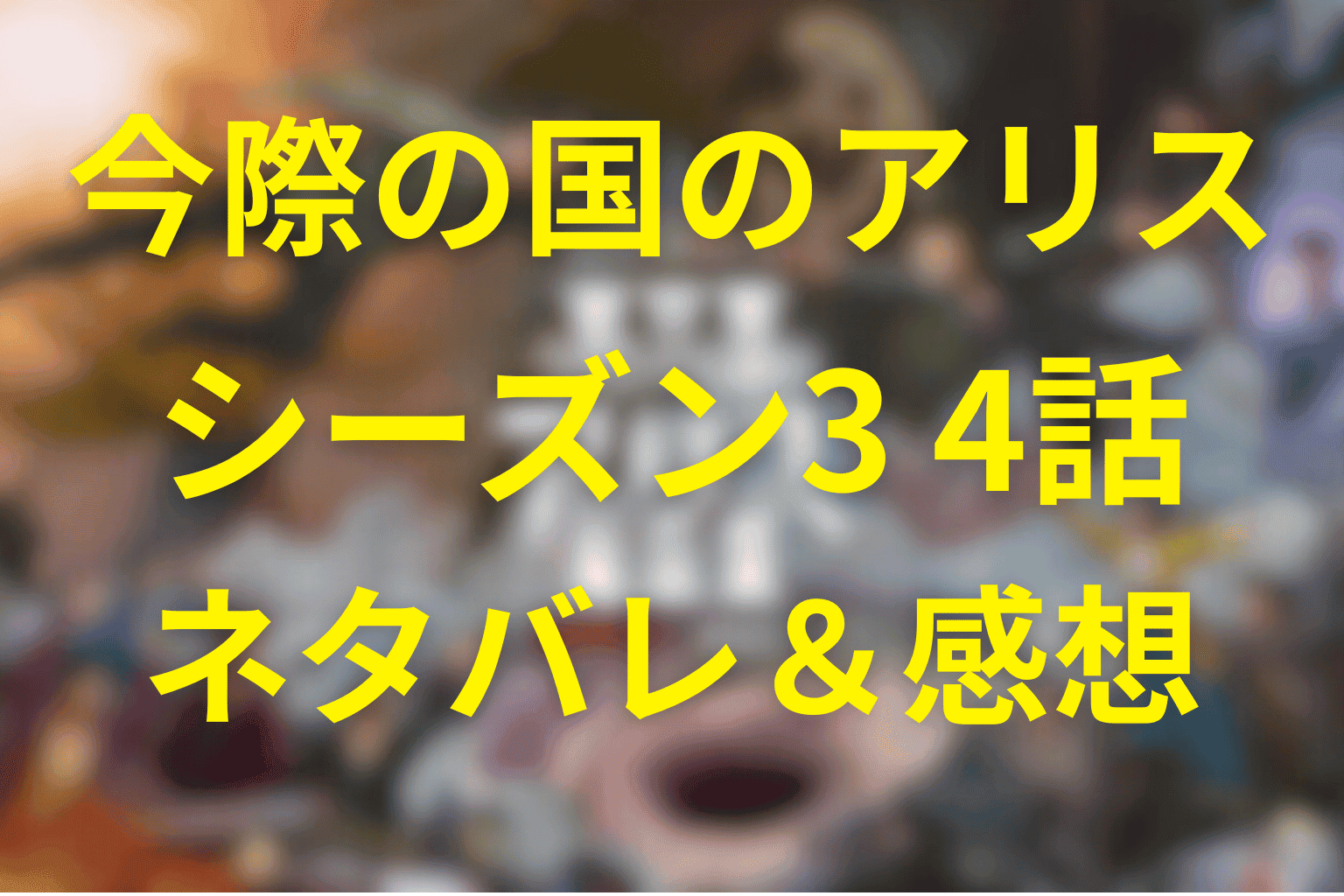
コメント