第4話「似顔絵」は、死体そのものよりも「疑いがどう作られるか」に焦点を当てた回だ。元議員秘書・中西忠雄は、追い詰められた末の自殺に見えた。しかし倉石義男は、首元の痕跡と現場の違和感から、早々に他殺だと断じる。
事件を動かすのは、目撃証言から描かれた一枚の似顔絵だ。似顔絵が完成した瞬間、捜査も視聴者も「この人物が怪しい」という物語に引き込まれていく。だが倉石が見ているのは、その顔ではなく、なぜそこまで“はっきりした顔”が描けたのかという点だった。
似顔絵が暴くのは犯人の顔ではなく、人が人を利用し、疑いを積み上げていく仕組みそのものだ。この回は、証言よりも痕跡を信じる『臨場』らしさが、最も冷たく際立つ一話になっている。
※この記事は、ドラマ「臨場 続章」第4話「似顔絵」の結末までのネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
ドラマ「臨場 続章」4話のあらすじ&ネタバレ
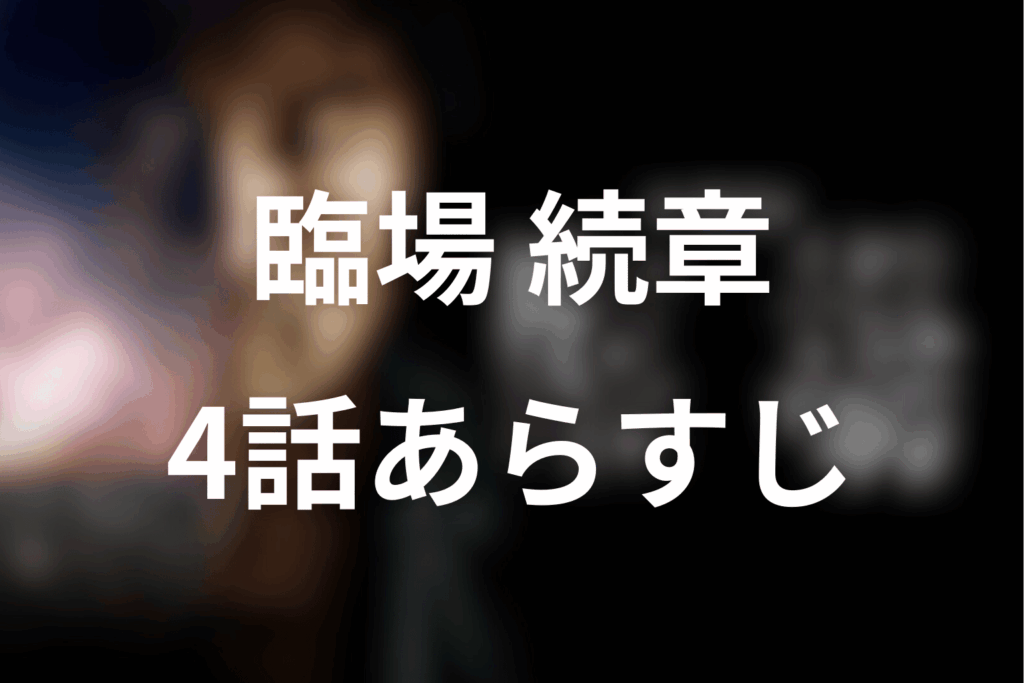
第4話のサブタイトルは「似顔絵」。事件の入口だけ見ると、いかにも「追い詰められた手配犯の自殺」だ。ダム建設の不正入札に関わった疑いで追われていた元議員秘書・中西忠雄が、ホテルの一室で首をつって死亡している。現場にいた刑事も、まずはその線で受け取る。
ところが、このドラマの怖さは“死に方の物語”が簡単に書き換えられるところにある。検視官・倉石義男は、首元に残る痕跡(吉川線など)や現場の状況から、迷いなく「他殺」と断定する。自殺に見せかけた殺人。つまり犯人は、死体をただ捨てたのではなく、社会が納得しやすいラベル――「自殺」を貼り付けようとしている。
そして、その“ラベル貼り”は、事件の核心が「被害者」ではなく「誰かを貶めること」にある可能性を示す。タイトルの「似顔絵」は、まさにその貶めの装置として機能する。ここから先は結末まで含めたネタバレで、時系列に沿って細かく追っていく。
出動要請の朝――倉石は生活を切らず、現場へ持ち込む
倉石の現場入りは、いつも儀式のようで、でも生活の延長でもある。電話が鳴れば出動。けれど彼は、日常をゼロにしない。金魚に餌を入れ、部屋を一瞥してから出ていく。たったそれだけで、「死者の声を聞く男」が同時に「生きている時間を持つ男」だと分かる。
この回は、その“生活の感覚”が重要になる。なぜなら事件の鍵が、ホテルという場所にあるからだ。ホテルは「他人の生活を借りる場所」であり、同時に「生活の痕跡を消す場所」でもある。清掃が入り、部屋は何事もなかったように整う。つまり、死の痕跡も、証拠も、簡単に薄まる。倉石はそこを最初から見越して臨場する。
さらに言えば、ホテルは「匿名」が成立しやすい。誰がいつ来て、いつ去ったか。防犯カメラやカードキーの記録がなければ、廊下ですれ違っても他人同士で終わる。犯人にとっても、隠れ場所というより“すり抜け場所”として使いやすい。今回の犯行は、その条件を最大限に利用している。
ホテルの一室――中西忠雄の首つり遺体と“第一発見者”という役割
中西が見つかったのはホテルの客室。首をつった状態で、すでに死亡していた。第一発見者は、捜査二課の管理官・柳井昌一郎。柳井は中西を追っていた担当者で、事件当日の早朝「中西の居場所」を知らせる密告電話が入ったため、ホテルに直行したという。
ここでまず異様なのが、“密告”のタイミングだ。夜の張り込みでもなく、捜査の積み上げでもなく、朝一番に電話一本で居場所が分かる。柳井は上層の管理官で、現場の泥も吸うタイプだが、だからこそ彼が「密告を受けて踏み込む」という構図が引っかかる。誰かが柳井を動かし、第一発見者という“役”を与えているように見える。
加えて部屋には、柳井と同じ銘柄のタバコが残されていた。偶然なら偶然で済む。しかし倉石が他殺と断定した以上、現場に置かれたものは「犯人の癖」ではなく「犯人の意図」になっていく。タバコは、誰かがわざと置いた小道具かもしれない。
この時点で、現場は二重に“作り物”っぽい。
一つ目は、中西の死に方。手配犯が追い詰められて首をつる――筋がいい。筋がよすぎる。
二つ目は、第一発見者の配置。追っている刑事が密告で現場へ行き、都合よく遺体を発見する――これも筋がよすぎる。
筋が良い出来事ほど、誰かが筋道を整えた可能性が出てくる。だからこそ立原真澄は柳井に事情聴取を行い、一ノ瀬和之は状況を整理しようとする。だが彼らの整理より早く、倉石の検視が結論を押し出す。
「自殺」から「他殺」へ――倉石の断定で捜査が二段階になる
一ノ瀬の見立ては首つり自殺。見た目だけなら妥当だ。だが倉石は、首元の痕跡(吉川線など)や現場のわずかな違いから、他殺だと断定する。
ここで事件の性格が変わる。自殺なら、動機は「なぜ死ぬ気になったか」に寄る。だが他殺なら、動機は「なぜ殺したか」に寄る。さらに自殺に見せかけた他殺なら、「なぜ自殺に見せたいか」まで問われる。
倉石の断定は、犯人の目的が“死”そのものではなく、“死の意味づけ”にある可能性を突く。人は誰でも、死体を見ると勝手に物語を作る。逃げ場がない、後ろめたい、だから自殺――勝手に納得する。その納得を誘導できれば、犯人は捜査を遅らせ、矛先を変えられる。ホテルという舞台は、その誘導に向きすぎている。
倉石が強いのは、ここで「自殺に見せたい=誰かに疑いを向けたい」という“次の一手”まで見通して動き出すところだ。単に「他殺です」で終わらず、「じゃあ誰に疑いが向くように作った?」を捜査の出発点にする。
余談:吉川線が示すもの――「抵抗の痕」が残る首元
ここで出てくる「吉川線」は、法医学・鑑識で使われる言葉で、首を絞められた被害者の頸部に見られることがある表皮剝脱(ひっかき傷)を指す。苦しくて首元の索状物を外そうとして掻きむしった“抵抗の痕”と考えられ、見つかれば他殺判断の材料になる。
もちろん、吉川線が「ある=必ず他殺」「ない=必ず自殺」ではない。抵抗できない状態なら出ない場合もあるし、状況によって残り方も変わる。だからこそ倉石は、単語一つで決め打ちせず、他の痕跡や現場の整合性と合わせて判断する。彼が怖いのは、専門用語を振り回すのではなく、“現象の束”として結論を出すところだ。
柳井昌一郎に向く疑い――二課の管理官は“犯人”か“駒”か
立原が柳井に疑いの目を向けるのは自然だ。第一発見者、密告電話、そして部屋に残されたタバコの銘柄が柳井と同じ。公式のあらすじでも、立原が柳井に対して“ささやかな疑惑”を抱くと触れられている。
ただし立原は、疑いを決め打ちしない。柳井が中西を殺すメリットは薄い。中西は生かして逮捕すれば、捜査二課としての大きな成果になる。殺した瞬間、事件の「口」が塞がる。合理性だけで見れば、柳井はむしろ“利用される側”にも見える。
この回の面白さは、捜査一課と捜査二課の“温度差”もにじむことだ。二課が追ってきた経済事件の手配犯が、突然、殺人事件の被害者になる。二課の手柄が一課の事件に飲み込まれ、逆に二課の人間が疑われる。縄張りの問題というより、組織の自尊心がざわつく。柳井の苛立ちや焦りも、そうした空気を背負っているように見える。
「女が出ていった」――目撃証言と、似顔絵という“決め打ち”の怖さ
捜査を大きく動かすのが、ホテルのハウスキーパー・三原あゆみの証言だ。事件当日、あゆみは中西の部屋から出てくる人物を見ていた。しかもその人物は女。
ここから似顔絵作成が始まる。似顔絵というのは、捜査の中でも特殊な道具だ。指紋やDNAと違って、作るのは“人の記憶”であり、さらに“人の言葉”。完成した瞬間に、像が独り歩きしやすい。「この顔の女が怪しい」という固定観念が、捜査側にも視聴者側にも発生する。
似顔絵は監視カメラ映像とも照合され、女の正体として浮かび上がったのは柳井の妻・柳井香奈恵だった。似顔絵が「他人の記憶」から「具体的な一人の人間」へ変わった瞬間、事件は“夫婦の問題”の匂いを帯び始める。
香奈恵が浮かぶまでの流れも、捜査らしい速度感がある。目撃証言、似顔絵、映像照合。ホテルという場所は人の出入りが多い分、映像が“誰か”を捕まえれば一気に進む。だからこそ逆に、映像に映っていない部分――廊下の死角、清掃の時間、スタッフルームの動線が、犯人の逃げ道になる。
似顔絵が捜査を固定する――「似ている」ほど危ういもの
似顔絵は「証拠」としては脆いが、「物語」としては強い。だから厄介だ。似ていれば似ているほど、“その人が犯人(または関係者)”という筋書きが頭の中で完成してしまう。実際この回でも、似顔絵が香奈恵に結びついた瞬間から、捜査の目線は柳井夫妻へ寄っていく。
ただ、倉石はその流れに飲まれない。似顔絵が似すぎていること自体を、逆に疑いの材料に変える。「似ているから怪しい」ではなく「似すぎているのはなぜか」。ここが倉石らしい視点だ。似顔絵が“目撃の結果”ではなく“既知の顔の再現”なら、証言は目撃ではなく作為になる。
柳井香奈恵の事情――不倫を認め、殺人を否認する
香奈恵は中西との不倫関係を認め、事件当日に中西の部屋を訪ねていたことも認める。だが殺人については否認する。
香奈恵の言い分は「別れ話をしてホテルを出た」。その言葉は、嘘にも真実にも聞こえる。ここがこの回の嫌なところで、“不倫”という汚れた真実があるせいで、「殺人はしていない」という部分だけが逆にリアルに響く瞬間がある。
さらに明かされるのが、柳井夫妻の冷え切った関係だ。家庭内別居のような状態で、柳井もまた過去に事件で追っていた女性と不倫関係にあったという。つまり、夫婦は互いに互いを裏切っている。香奈恵が中西に近づいた背景には、中西が柳井の情報を探るために妻へ接近した、という捜査上の利害も見える。
香奈恵が苦しいのは、彼女が“潔白であっても”疑われることだ。不倫という弱みがある以上、何を言っても信用されにくい。だからこそ、犯人が香奈恵を疑われる位置に置いたとすれば、それは極めて効率のいい罠になる。
柳井夫妻のすれ違い――疑いが家庭を直撃する
香奈恵の浮上は、柳井の捜査官としての顔だけでなく、家庭人としての顔にも直撃する。夫が追う事件の手配犯と、妻が不倫していた。しかもその妻が、事件当日にホテルにいた。捜査のロジックだけで言えば「夫婦で共謀した可能性」すら浮かび得る。立原が疑いの目を向ければ向けるほど、柳井は“管理官としてのプライド”と“夫としての体面”の両方を削られていく。
香奈恵の側も、同じように追い詰められる。不倫は事実。だから言い訳は通らない。でも、殺人はしていない。ここが一番苦しい。「自分が悪いことをした」場面と「自分がしていないことを疑われる」場面が、同じ面に乗ってしまう。犯人が狙ったのは、この“疑われやすさ”そのものだと分かる。
倉石が見抜いた違和感――“似すぎた似顔絵”と証言の迷いのなさ
倉石が引っかかったのは、似顔絵の完成度と、あゆみの証言の断定ぶりだ。似顔絵作成では普通、証言者は迷う。顔の輪郭、目、鼻、髪型――曖昧なパーツを言語化するのは難しい。だがあゆみは迷わない。似顔絵担当者が「普通なら戸惑うはずなのに」と感じるほど、あゆみは即答する。
完成度が高すぎる似顔絵は、二つの可能性を持つ。
・本当に目撃の記憶が鮮明
・そもそも“知っている顔”を描いている
倉石は後者を疑う。似顔絵の出来が良すぎることが、逆に“作為”の臭いになる。
現場が語る“掃除の癖”――消えたバスタオル、拭かれたバスルーム
捜査が進むにつれて、現場の“ちぐはぐ”が増えていく。まず、中西の部屋からバスタオルが一枚なくなっている。
次に、香奈恵のタバコの吸い殻は残っているのに、バスルームだけ指紋が拭かれているという不自然さ。証拠隠滅なら吸い殻も片付ける。なのに吸い殻は残す。つまり、拭いた手は「証拠を消す」手ではなく、「掃除をする」手の可能性が高い。
そして決定的に、タバコの包装が不自然だ。タバコの出し口の銀紙はあるのに、タバコ自体を包んでいるラップ(フィルム)が捨てられていない。ラップだけが消えるというのは、普通の捨て方では起きにくい。
ここで倉石がやるのは、現場を“犯人目線”で想像することではなく、“清掃員目線”で復元することだ。バスルームに入ったなら、タオルを使う。タオルを使えば、タオルは濡れる。濡れたタオルはそのまま捨てず、回収や交換の流れに乗る。だから「タオルが消えた」という現象は、持ち去ってどこかに隠したというより、清掃の動線に紛れ込ませた可能性が高い。
ハウスキーパーは部屋に入れる――“鍵を持つ者”の優位
ホテルの事件で怖いのは、犯人が客とは限らないことだ。清掃スタッフは日常的に部屋へ入る。客の荷物に触れ、タオルを交換し、ゴミを回収する。それは「侵入」ではなく「業務」だ。つまり、証拠を動かしても不自然になりにくい。
あゆみが目撃者として最初に前面に出た時点で、実は彼女は“部屋に入れる側”でもある。倉石がバスタオルや拭き跡に敏感になるのは、この優位を最初から理解しているからだ。
あゆみの“漏れ”――知っているはずのない髪型を口にする
倉石があゆみをマークする中で、あゆみは決定的な“漏れ”を見せる。香奈恵が帽子をかぶっていて髪型が分からなかったはずなのに、あゆみは髪型を具体的に口にしてしまう。これは目撃の記憶ではなく、以前に見て知っていた記憶が混ざっている証拠だ。
似顔絵が似すぎた理由も、ここで一本になる。あゆみは香奈恵を知っていた。だから描けた。だから断言できた。目撃証言は、目撃の結果ではなく、過去の執着が作り出した像になっていた。
三原あゆみの過去――3年前の贈賄事件と、利用された“協力者”
あゆみは3年前、柳井が追っていた贈賄事件で内部情報を提供していた。つまり捜査協力者だった。
彼女は柳井に好意を抱き、柳井はそれを捜査のために利用した。捜査のためだけに利用され、捨てられた――あゆみは傷つき、リストカットを繰り返すほど追い詰められていたという。
ここが最悪なのは、柳井にとってそれが「捜査の一手」でも、あゆみにとっては「人生」だということだ。捜査の論理は人情を切り捨てる。切り捨てられた側は、その恨みだけで呼吸するようになる。この回の犯行動機は、そこから生まれている。
真相――中西の死と似顔絵を利用し、柳井夫妻を貶める計画
あゆみの目的は柳井への復讐。そこへ、柳井が追っていた中西がホテルに現れ、さらにおあつらえ向きに柳井の妻まで現れた。あゆみにとっては絶好の材料が揃った。
あゆみは追い詰められ自殺を考えるほどだった中西を利用し、首つりの形で死を成立させる。そして密告電話で柳井を現場に呼び、第一発見者にする。柳井が疑われる位置に立てば、それだけで警察内部は揺れる。さらに似顔絵を香奈恵に寄せ、妻にも疑いを向ける。夫婦まとめて潰す。復讐としては、そこまでやる。
この回の殺人は、被害者を消すためだけではない。殺人を“利用”して刑事を貶めるための設計図だ。だから視聴後に残るのは、謎解きの爽快感ではなく、冷えた指先みたいな嫌悪感になる。
あゆみの工作の手順――「疑われやすい人」を順番に作る
あゆみの復讐が厄介なのは、トリックが派手だからではなく、疑いの“積み上げ方”が現実的なところだ。彼女がやったのは、犯人らしい証拠を一発で作ることではない。警察が勝手に疑いを深める材料を、順番に置いていくことだった。
流れを整理すると、だいたいこんな手順になる。
- 中西がホテルにいることを把握する
清掃という仕事は、客の顔と部屋番号、滞在の気配を自然に覚えてしまう。あゆみは中西の存在を“仕事の延長”で掴む。 - 柳井を現場に呼ぶ(密告電話)
柳井が来れば、第一発見者という役が完成する。そこに「タバコの一致」などの小道具が重なると、疑いは自然に柳井へ向く。 - 香奈恵を疑われる位置に置く
香奈恵が中西と会っていた事実(不倫)は、それだけで疑いを呼ぶ。あゆみは目撃証言と似顔絵で、その疑いを“確信”に近づける。 - 自分の痕跡を薄め、他人の痕跡を残す
バスルームだけ拭かれている、タオルが消える、ラップが消える――この「掃除の癖」は、あゆみが現場を動かした証拠であると同時に、最初は“妻の証拠隠滅”にも見えるように設計されている。 - 最後に、自分の“過去”で柳井を刺す
殺人の立件だけなら、中西の死で終わる。だがあゆみの狙いは柳井の失脚だ。だから「かつて協力者をどう扱ったか」を証言し、警察官としての信用そのものを壊しにいく。
こうして見ると、似顔絵は“犯人の特定”ではなく、“疑いの誘導”のための道具だったと分かる。タイトルの回収がえげつない。
あゆみの手口は、刑事ドラマの王道である「アリバイ崩し」よりも、現実に起きがちな“印象操作”に近い。だからこそ、倉石が拾うべきものも派手なトリックではなく、証言の温度差や清掃の癖といった地味なズレになる。似顔絵の回なのに、最後は“手”の動きが全部を語るのが皮肉だ。
ラストの対峙――倉石が三原あゆみを追い詰めた「物証」の積み上げ
終盤、倉石たちはあゆみの周辺を洗い直し、決定的な物証にたどり着く。あゆみの仕事道具の中から、香奈恵が落としたタバコのフィルム(ラップ)が見つかるのだ。バスタオルでバスルームを拭いた際にフィルムが巻き込まれ、タオルごと“持ち去られたまま”になっていた。
これで、現場から消えたラップの行き先、バスタオルが消えた理由、バスルームだけが拭かれている不自然さが繋がる。似顔絵の違和感と物証が重なり、あゆみが事件の中心にいることが確定する。倉石がすごいのは、ここまで一貫して「口」より「痕」を優先しているところだ。目撃証言を論破するのではなく、現場の矛盾を物で塞いでいく。
あゆみは過去のこと、柳井に利用されたこと、復讐の意図を語り、柳井が自分をどう使ったかも含めて証言すると告げる。静かな笑顔で「伝えてほしい」と言い残すような場面があり、その静けさが逆にゾッとする。復讐を終えても、彼女の傷は消えない。それでも、彼女は復讐を“生きる理由”として抱えてきた。
事件の余韻――柳井の立場、そして刑事の世界の非情
事件が片付いたあと、柳井の立場は危うくなる。刑事が協力者の心を利用し、捜査のために切り捨てた過去が表に出れば、警察官としての信用は保ちにくい。あゆみが証言すると言った時点で、柳井は捜査とは別の場所で追い詰められていく。
一方で、上層部の論理は冷たい。「利用できるものは利用する」。刑事という仕事の現実ではある。だが、その論理で動いた人間が、結局は利用され返されたのがこの回の皮肉だ。
一ノ瀬の成長と転機――倉石班の“目”が次へ進む
終盤、倉石が何も言わないのに、一ノ瀬と小坂留美が自主的に床を洗って、何か痕跡がないか探す場面が描かれる。倉石班で積み上げた目が、二人の身体に入ってきた証拠だ。
そしてラストで立原は一ノ瀬に捜査一課入りを促す。鑑識の現場で鍛えた観察眼は、捜査の現場でも武器になる。事件の後味は苦いのに、チームの未来は前へ動く。この“苦さと前進”の同居こそ、続章の持ち味だ。
ドラマ「臨場 続章」4話の伏線
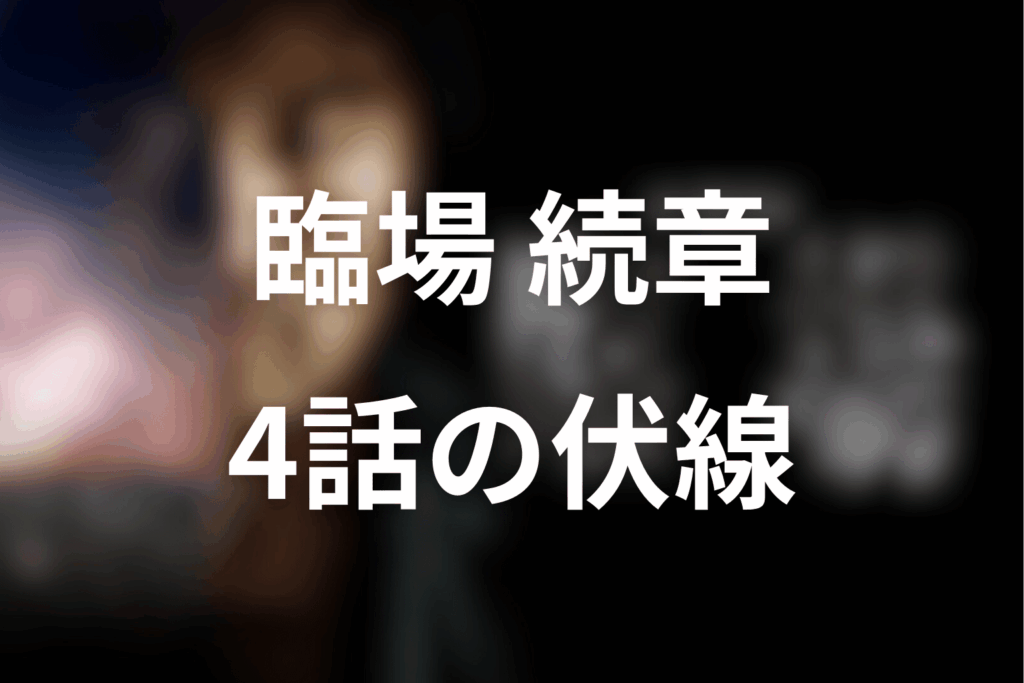
第4話「似顔絵」は、“事件の派手さ”よりも“違和感の積み上げ”で真相にたどり着く回です。元議員秘書の中西忠雄がホテルで首をつった状態で見つかり、若手の一ノ瀬和之は自殺と見立てる。でも倉石義男は「他殺」と言い切る──この“早い断定”が、実はこの回の伏線の起点になっています。
伏線①:わずかな「吉川線」——最初の一手で“絵”が決まっている
まず大前提として、倉石が「これは首つり自殺ではない」と見抜く根拠が“吉川線”です。吉川線は、絞頸などの際に抵抗して自分の首に爪を立てた結果できる表皮剝脱で、他殺判断の材料になり得るとされます。つまりこの時点で、倉石の頭の中では「誰かが“自殺に見せた”」が確定。以降に出てくるタバコや似顔絵は全部、“自殺偽装”という前提に紐づく道具になります。
この回の巧いところは、視聴者にも「自殺に見えても、そうとは限らない」と最初に刷り込んでくる点。だから後で何度ミスリードを振られても、最後は「死体が一番しゃべる」というシリーズの基本に戻ってこられる。倉石の断定は単なる“凄腕演出”じゃなく、後半の伏線回収のための土台になっています。
伏線②:密告電話——“捜査を動かす手”が最初から画面外にいる
次の伏線は、柳井昌一郎のもとに入った密告電話です。朝早く「中西の居場所」を知らせる電話があり、柳井がホテルへ向かい、第一発見者になる。これ、説明だけ聞くと“偶然”にも見えるんですが、物語の構造としては真逆で、「誰かが柳井を現場に立たせた」可能性を示す導線になっています。
さらに言うと、密告電話は“事件”の伏線であると同時に、“柳井という人間の過去”の伏線でもあります。柳井は捜査二課、相手は不正入札絡みの元秘書。最初から「組織犯罪・汚職の臭い」が漂い、個人の怨恨だけで終わらない雰囲気を作っている。後半で「3年前」に繋がった瞬間、密告電話が単なる情報提供ではなく、復讐のスイッチだったとわかります。
伏線③:タバコ銘柄の一致——“疑わせるための証拠”が投げ込まれている
部屋に残ったタバコと同じ銘柄を柳井が吸っている。ここで立原真澄が柳井に小さな疑念を持つ流れは、すごく王道です。視聴者目線でも「第一発見者」「密告電話」「同銘柄タバコ」と疑う材料が揃うから、いったん柳井に視線が集まる。
でもこのタバコは、後半にいくほど“誰かが疑いを作った痕跡”に変わっていきます。いったんは柳井香奈恵の線(不倫相手としての接点)に誘導されつつ、最終的には「証拠の置き方」「消し方」そのものが犯人像を示す。タバコは犯人の癖ではなく、犯人が“人を陥れるために選んだ小道具”だった、という設計です。
伏線④:「似すぎた似顔絵」——証言の“温度”が決定的におかしい
この回の核はここ。目撃者のハウスキーパー(三原あゆみ)の証言から似顔絵が作られるわけですが、出来上がった絵が“似すぎている”。普通、短時間の目撃だけでここまで特定精度が上がるのか?という違和感が、倉石の嗅覚を刺激します。
しかも、証言の仕方が断定的すぎる。迷いがない。現場で見た“その瞬間”だけの記憶というより、もっと前から顔の情報を持っていた人間の喋り方なんですよね。ここが後半の回収ポイントで、あゆみは香奈恵を以前から見知っていたから似顔絵が鮮明だった、という真相に繋がります。
さらに、香奈恵の髪型に関する“うっかり”も、人間臭い伏線です。帽子で現在の髪型が分かりにくかったのに、過去に覚えていた髪型のイメージを口にしてしまう──「見たのは一回だけじゃない」が漏れる瞬間で、証言の信頼性が逆に崩れる。ここは地味だけど強烈な回収でした。
伏線⑤:消えたバスタオル/消えたラップ——“持ち出せる人間”の輪郭
物証で一番好きなのがこの二つです。
- 部屋からバスタオルが一枚なくなっている
- タバコの銀紙はあるのに、外側のラップ(包装フィルム)が捨てられていない
この「あるはずのものがない」系の違和感って、現場の“利用のされ方”を浮かび上がらせるんですよね。犯人は何かを拭いた/何かを持ち出した。しかもそれを自然にできる立場の人間がいる。つまり、ホテルスタッフとして“入っても不自然じゃない人”が犯行の中心に近い。
そして回収が鮮やかで、あゆみの仕事道具からタバコのフィルムが見つかる。バスルームを拭く癖でタオルを使い、そこにフィルムが巻き込まれて持ち出された──「消えたもの」が「出てくるべき場所」に出てくる快感がある。偶然に見えるけど、伏線としてはかなりロジカルです。
伏線⑥:「3年前」の因縁——事件の本体は“殺意”より“恨みの継続”
終盤、あゆみが柳井に内部情報を提供していた過去が明かされます。ここで、第4話の事件が“中西を殺した/殺してない”の話だけではなく、「柳井に復讐する」物語だと確定する。
この「3年前から恨みを燃やして生きてきた」という時間の厚みが、序盤の違和感(密告電話、似すぎた似顔絵、物証の配置)を一気に一本線にします。伏線の本体は、実は“犯行手口”ではなく“感情の持続”だった。だからこそ、最後に倉石が向き合う相手は死者ではなく、生きている犯人になる。そこまで含めて、全部が伏線として回収される構造でした。
ドラマ「臨場 続章」4話の感想&考察
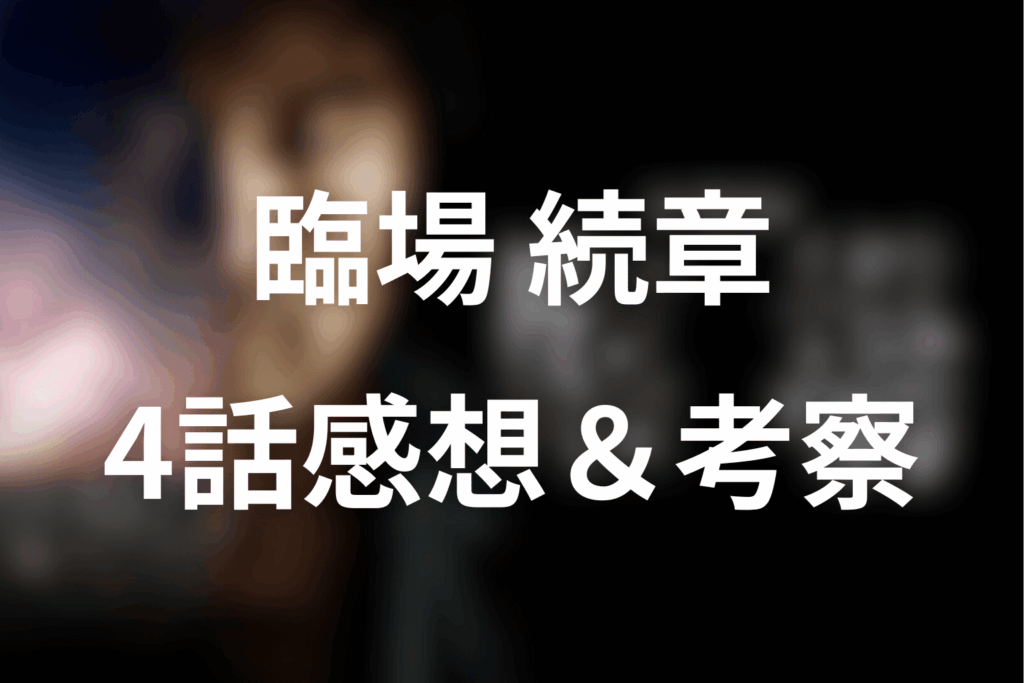
この回を見終わった後に残るのは、「事件を解いたスッキリ」よりも、「人を壊す仕組みって、こんなに静かなんだな」という後味です。中西の死は入口で、本題は“似顔絵”という名の復讐装置。顔を描くはずのタイトルなのに、描かれていたのは人間の業そのものだったと思います。
「似顔絵」は、顔の再現ではなく“人物像の作り替え”だった
似顔絵って本来、捜査のための補助線です。だけど第4話では、あゆみが“似顔絵を武器として使う”。つまり、証拠を作って捜査を誘導し、狙った相手(柳井)を社会的に終わらせるための刃に変えていく。
ここが怖いのは、似顔絵そのものは「真実に近い」こと。香奈恵は確かにホテルにいた。中西と関係があった。だからこそ、“真実の断片”を並べ替えるだけで、人は簡単に犯人にできる。捜査の世界で一番厄介なのは、100%の嘘より、70%の真実で作った罠なんだと突きつけられます。
「殺す」より「貶める」——復讐の矢印が増殖する恐怖
あゆみの目的は「中西を殺す」ではなく、「中西の死(あるいは死に向かう流れ)を利用して柳井を潰す」ことでした。この“目的のズレ”が、普通の犯人像より不気味に映る。命を奪うより、人生を奪う方が長く苦しませられる、という発想だから。
しかも、狙いは柳井だけで終わらない。香奈恵まで巻き込み、場合によっては彼女も“加害者”として社会から排除されかねない筋書きだった。復讐って、最初は一点集中のはずが、いつの間にか「関係するもの全部を焼く」形に変質する。その増殖の仕方がリアルで、見ていて胃が重くなる回でした。
柳井昌一郎の罪は「悪」じゃなく「割り切り」だったと思う
柳井は分かりやすい悪党ではない。でも、あゆみを“捜査のための協力者”として扱い、結果的に心を壊して捨てた。ここで描かれているのは、「正義のためなら手段を選ばない」という刑事の割り切りが、人をどう傷つけるかです。
個人的に刺さったのは、警察組織側の感覚もちゃんと出てくるところ。人情が捜査の邪魔になるかもしれない、利用できるものは利用する──そういう空気があるから、柳井の行動は“個人の資質”だけで片付かない。むしろ、仕組みが生む必然に見えてしまう。だから救いがない。
三原あゆみは「犯人に見える」のに、目が離せない存在だった
正直、この回は序盤で「あ、この人キーマンだな」と感じる作りになっています。だけど、分かりやすい=弱い、ではない。あゆみの怖さは、表情がずっと“静か”なこと。怒鳴らない、暴れない、でも一言一言が鋭い。復讐ってこういう温度で進むんだよな、と。
そしてキャスティングの説得力も大きい。奥貫薫が演じるあゆみは、目立つ派手さがない分、感情の底が見えなくて怖い。柳井役の川野太郎も、薄情さを“過剰に悪く”見せないからこそ現実味が出る。あの二人がぶつかると、ドラマの世界というより、現実の歪みを覗き込む感じになる。
倉石義男の言葉は、死者より“生者”に効く時がある
この回の倉石は、検視官というより“人生の検視官”に近い。あゆみが「恨みがなければ生きていけなかった」と吐き出した時、倉石は断罪だけをしない。かといって同情に寄りすぎもしない。最後に「いい人生を」と言葉を渡すのが、倉石らしさです。
ここ、好き嫌いは分かれると思います。説教に見える瞬間もあるから。だけど僕は、このシリーズの“救いの設計”として必要な場面だと思っています。なぜなら、臨場って毎回「死んだ人の無念」を掬い上げる一方で、「生き残った人の罪と痛み」も残る。その後者を放置しないのが倉石で、だから物語が“事件の後”まで伸びる。第4話はその構造がよく出ていました。
一ノ瀬と立原の関係が、“次の章”へ動き出した回でもある
事件の筋とは別に、チームの変化も効いていました。倉石が何も言わなくても、一ノ瀬と小坂留美が自主的に床を洗って“何か”を探す。あれ、地味だけど胸が熱い。倉石班が「言われたことをやる集団」から「考えて動く集団」に変わってきてる証拠です。
そして最後に立原が一ノ瀬へ、捜査一課入りを促す流れ。物語としては次回以降の配置転換への布石なんだけど、感情としては“卒業”なんですよね。立原はドライに見えて、ちゃんと人を見ている。第4話は事件回でありながら、人間関係の回でもありました。
物証の回収は「偶然」か「必然」か——僕は“臨場らしい必然”だと思う
「タバコのフィルムが仕事道具から見つかる」って、確かに偶然に見える。実際、視聴者のツッコミポイントにもなりやすい部分です。
でも、臨場というシリーズの肝は“偶然を偶然のままにしない目”にあります。偶然落ちたものを、偶然巻き込んだものを、「それでも現場は嘘をつかない」として拾い上げる。倉石がよく言う“根こそぎ拾う”の徹底が、今回の回収の気持ちよさに繋がっている。だから僕は、あの物証は「ご都合」ではなく、この作品の思想に沿った必然だったと思っています。
第4話「似顔絵」は、犯人当ての快感より、「人はどうやって人を壊すのか」という問いが残る回でした。密告電話、似顔絵、タバコ、消えたラップ──全部が“誰かを貶めるための道具”にもなり得る。だからこそ、倉石が最後に投げる言葉が、あの回の唯一の救いになっている。ここまで“事件”と“人生”を重ねてくるのが、臨場の強さだと改めて感じました。
ドラマ「臨場 続章」の関連記事
ドラマ「臨場 続章」の全話記事についてはこちら↓
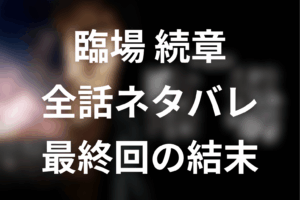
第一章についてはこちら↓
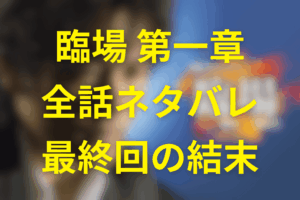
次回以降についてはこちら↓
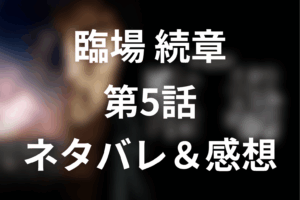
過去の話についてはこちら↓
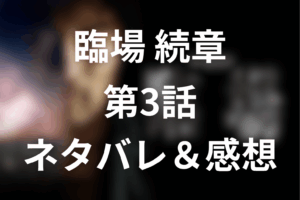
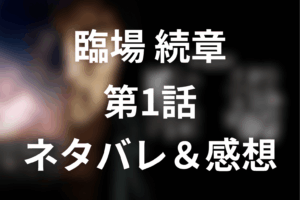
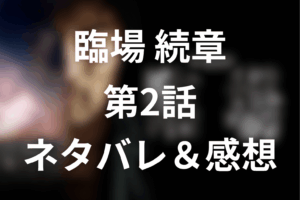
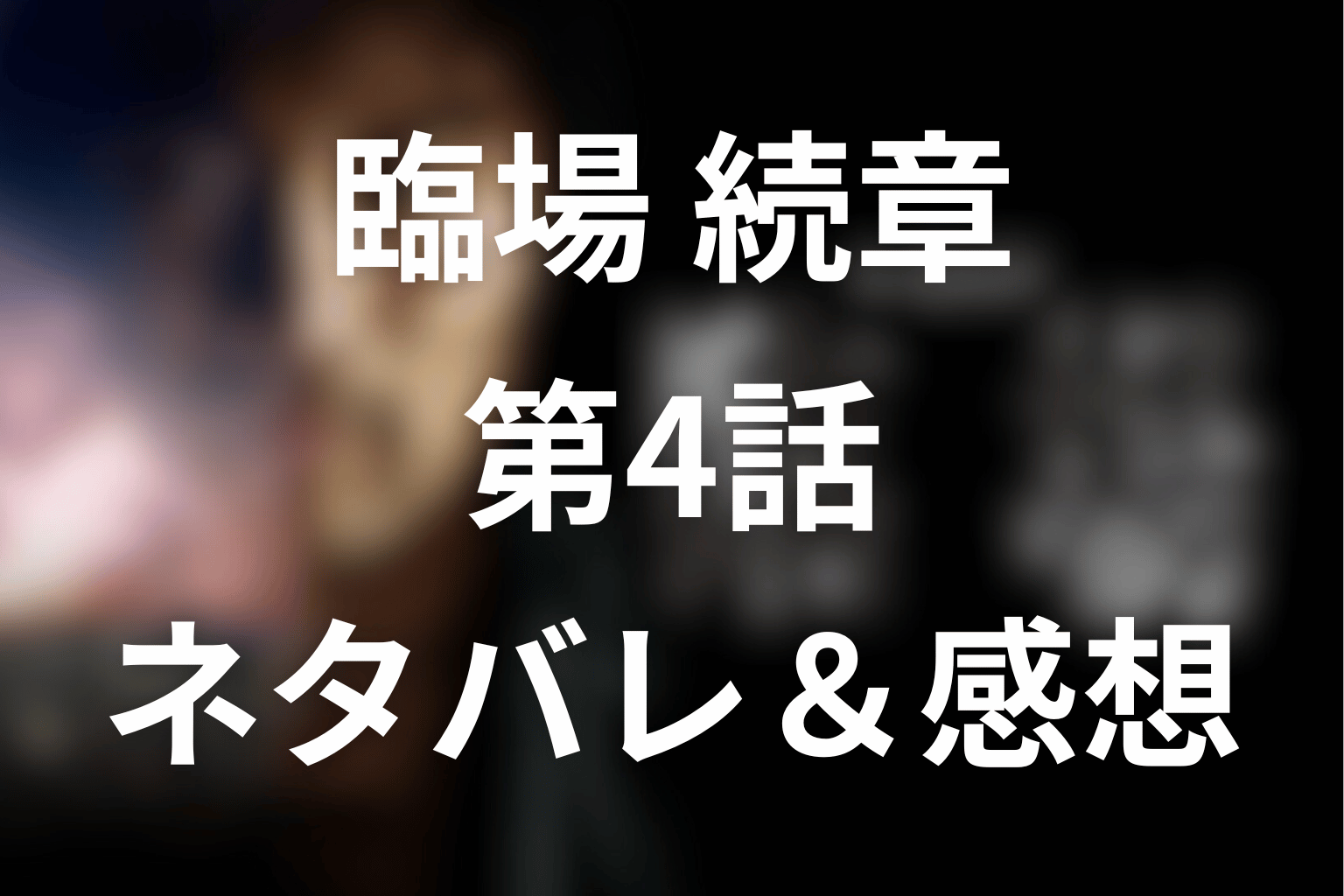
コメント