第2話で“退学の危機”と“音楽への再挑戦”を描いた『仰げば尊し』。
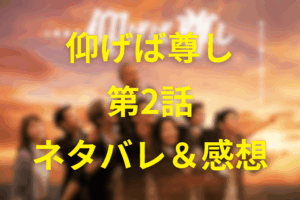
第3話では、その衝突がついに臨界点を迎える。
かつて彼らの夢を壊した卒業生・陣内との抗争が再燃し、青島(村上虹郎)と木藤良(真剣佑)は仲間を守るために再び拳を握る。
しかし、その暴力が引き起こしたのはさらなる退学騒動と校内の分裂だった。一方で、吹奏楽部は全国大会を目指して再始動。
2016年7月31日(日)の夜9時よりTBS系で放送される注目のドラマ「仰げば尊し」第3話のあらすじと感想を書いていきます。
※以後ネタバレ注意
ドラマ「仰げば尊し」3話のあらすじ&ネタバレ
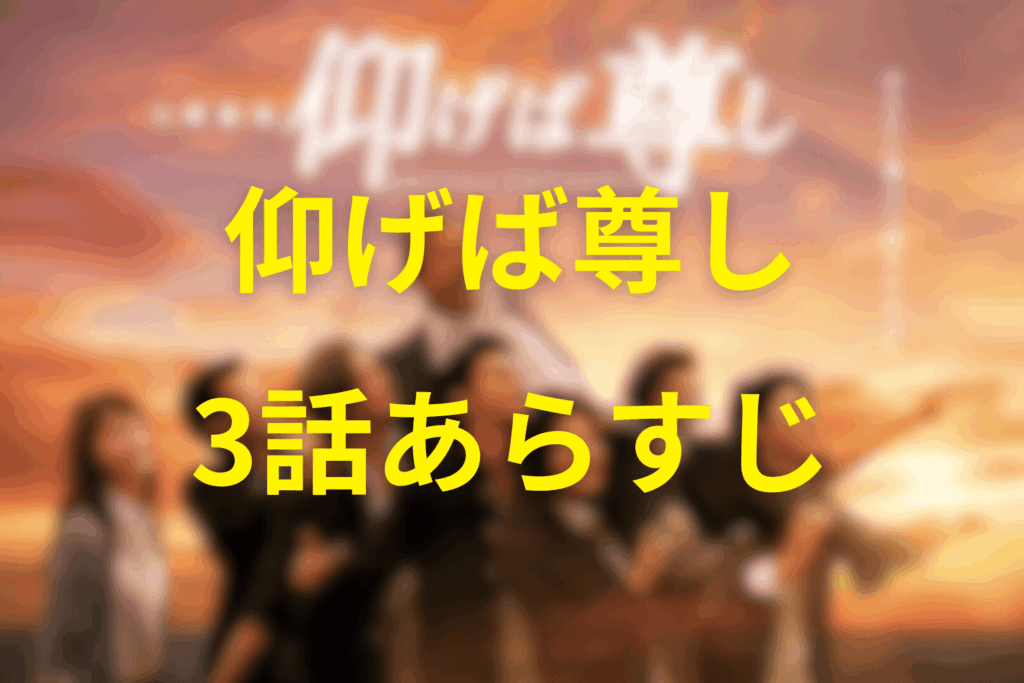
第3話は、「仲間を助ける」という衝動と、「音楽で前へ進む」という理性が激しく軋む回。
卒業生・陣内剛史(高畑裕太)らとの抗争が頂点に達し、警察沙汰・退学問題・パートリーダー選出・旧バンド小屋の破壊を経て、最後に青島(村上虹郎)と木藤良(真剣佑)が吹奏楽部へ入部するという大転換点に到達する。
第3話の骨子は「仲間の救出」「規律と成長」「過去との決別」「共同体への帰還」の4本柱で構成されている。
開幕:拉致・救出・警察沙汰――「守るための暴力」と「守るための制止」
青島、木藤良、安保、高杢、桑田の5人組をかつてのバンド仲間から引き裂いたのは、先輩の陣内たちによる暴力事件だった。
第3話ではその因縁が再燃。高杢(太賀)と桑田(佐野岳)が陣内一派に拉致され、安保(北村匠海)は仲間を助けるために動くが、5人の絆はすでに分裂していた。
呼び出しを受けた青島と木藤良は現場へ駆けつけ、救出に向かう。その後を追った樋熊(寺尾聰)が乱闘の場へ割って入るが、事態は警察沙汰に発展する。
「仲間を助けようとした気持ちに希望を持ってほしい」と樋熊は二人を庇うが、教頭・鮫島(升毅)は退学を進言。
校長・小田桐(石坂浩二)は「教育委員会へ報告するから私が預かる」と処分を保留し、制度の枠内に“教育の猶予”を残した。
吹奏楽部の再設計:課題曲とオーディション、成長の旋律
混乱の中でも、吹奏楽部は“全国大会=音楽の甲子園”を目指す歩みを止めない。
課題曲「エル・カミニート・デル・レイ(王の道)」が決まり、各パートのリーダーをオーディションで選ぶことに。
樋熊の提案で導入された競争制度は、安保・高杢・桑田ら初心者組に火をつける。
副部長・井川(伊藤健太郎)との衝突を経ても、彼らは「認められたい」という思いから練習に励む。練習量と責任の重みがそのまま音に表れ、部全体が変わり始める。
「音が人を変える」――樋熊の信念が制度として具現化された瞬間だった。
青島の停滞と木藤良の“選択”――揺れる心と師の言葉
一方で、木藤良は年内のアメリカ音楽留学を考えていた。
樋熊がそれを知ると、「人のせいにするな。お前、自分が一番やりたいことが分からなくなってるんじゃないか」と諭す。
そして、「だとしたら、お前たちは前から壊れていたんだ」と静かに告げた。
この言葉が、木藤良の“居場所の定義”を根底から揺さぶる。
同じ頃、青島は樋熊と渚、奈津紀(多部未華子)と偶然食事を共にし、自らの過去に触れられたことで心を閉ざす。
奈津紀が「他の楽器をやればよかったじゃん。つまり挫折したってことでしょ」と何気なく言ってしまったことで、青島は席を立ち、再び孤独へ戻ってしまう。
過去の呪縛:旧バンド小屋の破壊と“喪の儀式”
翌日、青島がかつて仲間と練習していた旧バンド小屋に行くと、そこには安保、高杢、桑田の3人が練習していた。
彼らは「もう一度5人で音を合わせたい」と信じていたが、その夜、小屋が陣内によって荒らされ、夢の象徴が踏みにじられる。
怒りに燃える青島を、樋熊と仲間たちが必死に止める。
青島は叫ぶ。「俺たちの大事な場所なんだよ。全部詰まってんだよ!」
木藤良は涙を堪え、「こんなものが残ってるから前を向けないんだ。僕らは、とっくの前に壊れてたんだ」と告げる。
喪失を経て初めて未来が見える――この“破壊と弔い”が、彼らの再出発の火種になる。
クライマックス:樋熊の“盾”と青島の土下座――過去との決別
樋熊は陣内に直接会い、青島たちへの報復を止めてほしいと頭を下げる。
同じ夜、青島も陣内のもとへ向かい、「これ以上関わらないでくれ」と土下座をする。
「気が済むまで殴っていい」と差し出す青島に、陣内は「お前、あの先生にそっくりだな」とつぶやき、手を引いた。樋熊と青島、二人の“謝罪と祈り”が、暴力の連鎖を止めた瞬間だった。
転換点:二人の入部――「反発する衝動」が「奏でる意志」に変わる
数日後、吹奏楽部のパートリーダーオーディションが行われる。
安保、高杢、桑田は惜しくも選ばれなかったが、落胆する彼らの前に、青島と木藤良が現れる。
「勝手に陣内のところ行って怪我すんなよ、樋熊」「俺たちが見せてやるよ。ステージに上がる夢、俺たちが見せてやる!」
その言葉と共に二人は入部を表明。
木藤良はアメリカ留学を辞め、サックスを選び、青島はトランペットを手にする。
二人の“帰還”は、音楽によって仲間と和解し、自分を取り戻す第一歩だった。この瞬間、“排除の論理”と“受け止めの論理”の綱引きは音楽の側へ傾き、物語は確かな前進を見せる。
ラスト:教師と生徒、そして新たな一歩
入部を果たした青島と木藤良を前に、樋熊は静かに微笑む。
青島は樋熊と固く握手を交わし、渚は涙をこらえる。奈津紀はこの光景を見て、教育実習先を美崎高校に決める。
かつて“壊れた5人”と呼ばれた生徒たちが、再び音楽を通してつながる――。
第3話は、暴力の時代を終わらせ、“音の時代”が始まる決定的な回となった。
ドラマ「仰げば尊し」3話の感想&考察
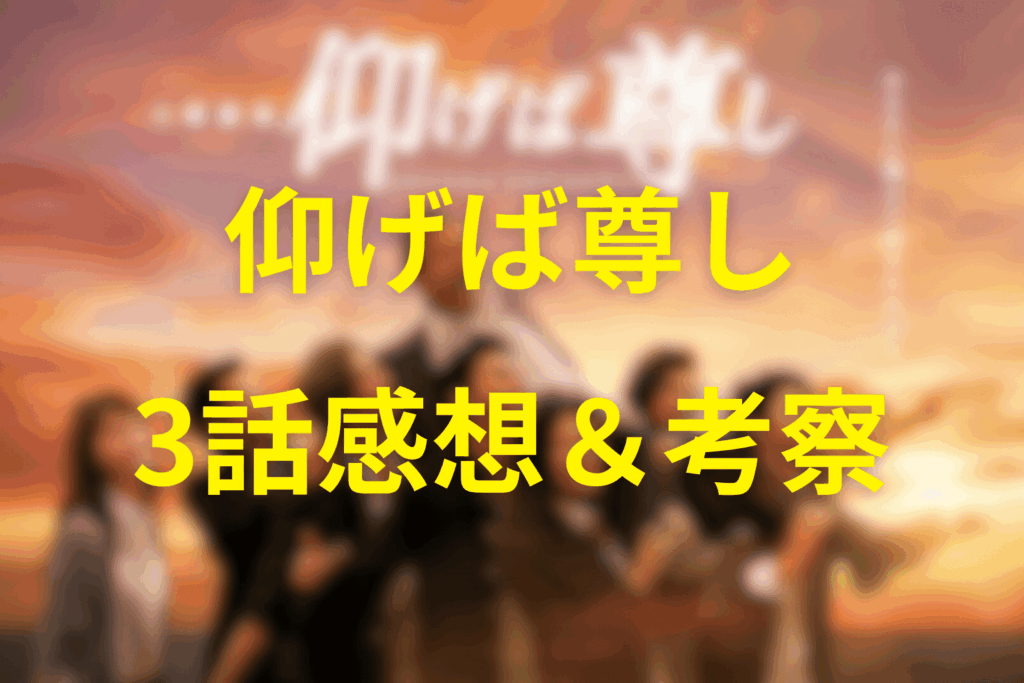
第3話は、規律(discipline)の二つの使い方が最も鮮明に描かれた回。
ひとつは鮫島が振るう“排除の規律”、もう一つは樋熊が用いる“回収の規律”。
同じルールでも、外すためにも戻すためにも使える——その差を、音楽という共同作業が埋めていく構図が秀逸だ。
規律の二面性――「退学」か「猶予」か
鮫島の退学推進は秩序維持のための正論。
だが校長・小田桐の処分保留は、規律を教育の機能として拡張する運用だった。
「教育委員会へ報告するから私が預かる」という一言は、法的な猶予=時間の確保であり、教育の目的(成長の機会)を守る政治的判断でもある。
学校が懲罰の場ではなく“希望の装置”として機能した象徴的な場面だ。
オーディションの設計思想――“責任=音になる”
パートリーダーのオーディションは、競争ではなく責任の可視化だ。
リーダーを目指すことで、安保・高杢・桑田は“認められたい”という欲求を自覚し、練習→成果→承認の循環を体得していく。
初心者であっても責任が先に立てば、音は量で、やがて質で変わる。
この制度設計によって、部は自律的に成長し始めた。
旧バンド小屋の破壊――「喪と弔い」の段取り
陣内によるバンド小屋破壊は、青島にとって“過去の弔い”を意味する。
居場所と記憶の喪失は痛みを伴うが、同時に“現在を選び直す自由”をもたらす。木藤良の「思い出が足かせ」という言葉は残酷だが、前へ進むための真実だ。
暴力ではなく演奏で過去を弔うことで、ラストの入部が倫理的な帰還へと変わる。
入部の一行が描く“共同体への帰還”
第3話のラストで、青島と木藤良は正式に入部。
この“帰還”は、組織に“置かれる”ことではなく、自らルールを引き受けることを意味する。
青島の「ステージに上がる夢、俺たちが見せてやる」は、暴力の循環から抜け出し、責任を持って居場所を築く宣言だ。
青島と木藤良――“衝動”と“言語化”の相補性
青島は衝動で動き、木藤良は言葉で導く。
乱闘に走る青島の速さと、真実を言葉で突きつける木藤良の正確さ。二人の関係は、行為と発話が互いを補い合い、暴力を表現に転換する装置として機能している。
この構造が、シリーズの“音楽で更生する”というテーマを最も象徴的に体現している。
樋熊の“盾”は倫理の輪郭
樋熊は警察沙汰の現場へ飛び込み、退学圧力にも対抗する。
身体的危険と制度的危険の双方に足を踏み入れることで、教師としての倫理が立ち上がる。
彼の言葉が“音”になるのは、言葉だけでなく身体で引き受けているからだ。
SNS的温度差――“ROOKIES的”という比較について
SNSでは「ROOKIESっぽい」との声もあるが、本作の違いは“身体の表現”にある。
殴り合いの代わりに、ブレス(呼吸)やアタック(出だし)で緊張を描く。
“鳴らない音”を葛藤として可視化する第3話は、暴力の外側で調律を始める章だった。
次回に向けた論点整理
・制度運用:処分保留の“時間”をどう教育に転化するか。
・役割設計:オーディション結果が合奏のバランスにどう影響するか。
・心理の段取り:青島の“安全感”をどう積み増し、再発を防ぐか。
・対外リスク:陣内の残滓(仲間・風評)への備え。
これらの布石が、“全国”へ向けた勝ち筋の前提条件となるはずだ。
第3話の視聴率・ロケ地は以下記事にまとめましたのでご覧ください。


関連記事
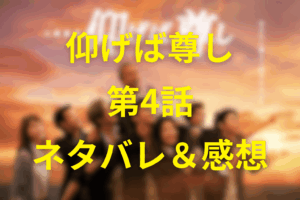
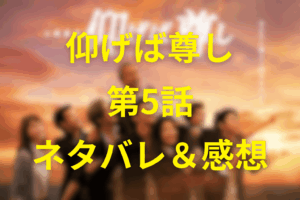



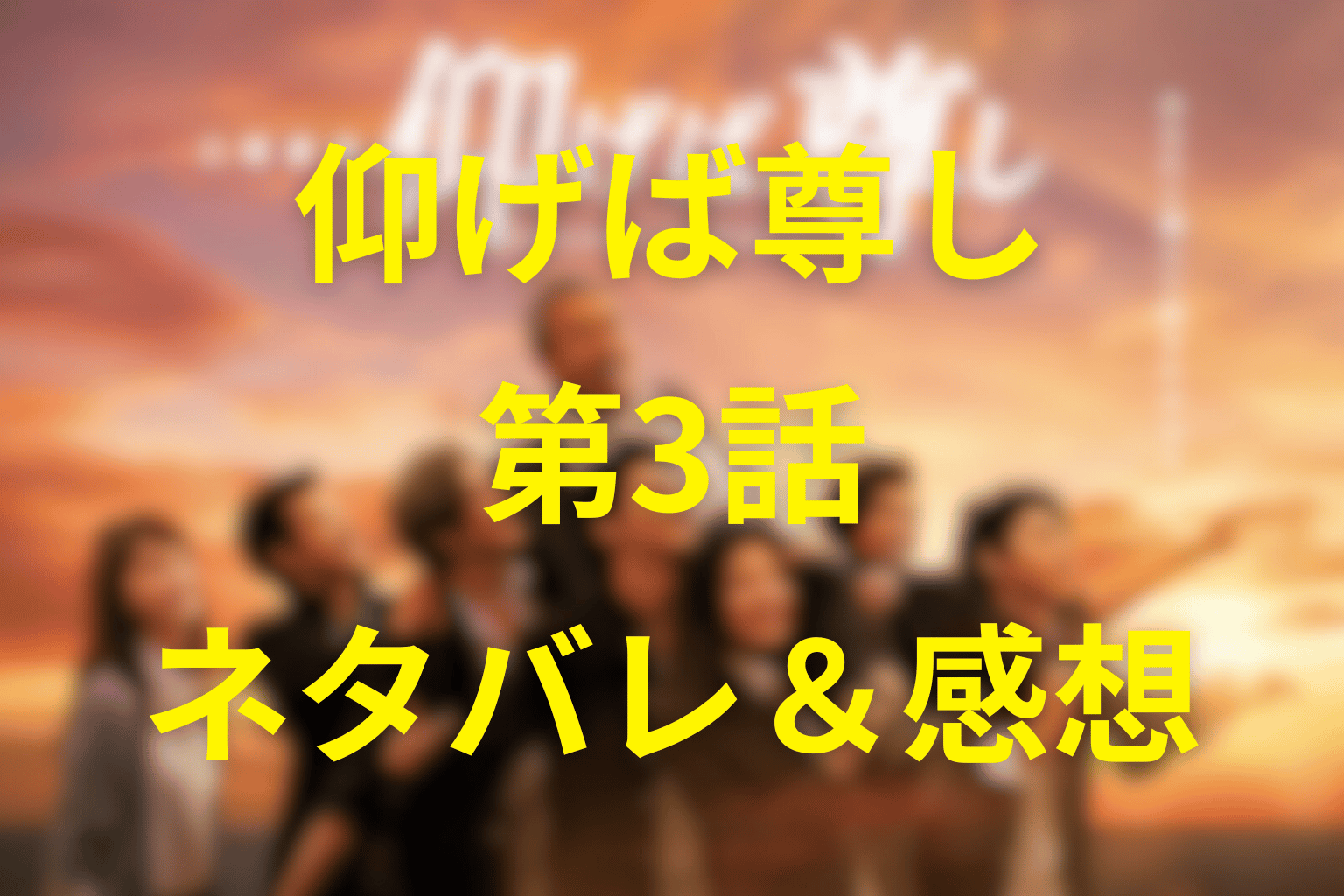
コメント