毎週日曜日夜9時よりフジテレビ系列で放送されるドラマ「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」の第8話が終了しました。
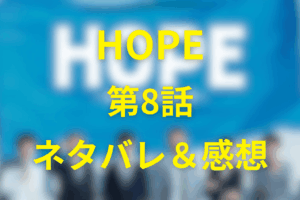
中島裕翔主演『HOPE〜期待ゼロの新入社員〜』最終回は、「働く意味」と「希望の本質」を問い直す集大成。
営業三課が挑む太陽熱発電プロジェクトに突如として暗雲が立ちこめ、組織の理屈と個人の矜持が激しくぶつかり合う。
守るために立ち上がる上司、葛藤の中で選択を迫られる部下、そして、それぞれの場所で“働き続ける理由”を見つめ直す同期たち。
別れの予感の中で、彼らが最後に選び取るのは「終わり」ではなく「続き」。
HOPEというタイトルの意味が、静かに解き明かされる最終章。
毎週日曜日夜9時から放送の9月18日(日)「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」の最終回(第9話)のあらすじと感想を紹介したいと思います。
※以後ネタバレ注意
HOPE(ドラマ)9話(最終回)のあらすじ&ネタバレ

最終回は、太陽熱発電プロジェクトへの監査突入から始まります。
きっかけは、一ノ瀬歩(中島裕翔)が上海駐在への電話で、鷹野専務(風間杜夫)の不正を示唆する言葉をうっかり口にしてしまったこと。
監査は営業三課・織田課長(遠藤憲一)だけでなく、窓口の江部(宮川一朗太)、さらには鷹野専務まで波及。
やがて、仲介会社の実態と“社内の線”が次々と明らかになっていきます。
監査で浮かぶ“九垓社”と“赤城プランニング”
調査の結果、途中から仲介として挟み込まれた九垓社は実態のないペーパーカンパニーで、その社外取締役に江部のいとこの名が。
過去にも赤城プランニングを経由させ、手数料を抜き取っていたことが判明します。
印鑑列は整っていても実質は“中抜き”。三課が抱いていた違和感が、ここで疑念から確信へと変わります。
波及する余震――冷え込む対中取引と「責任の所在」
汀洲社とのトラブルをきっかけに、中国側の取引先が与一物産を次々と敬遠。
資源二課の香月(山本美月)や食品二課の白石(中村ゆり)まで火消しに奔走する事態に。
自分の一言が引き金になったと肩を落とす歩に、織田は「責任を負うのは俺の義務であり権利だ。お前は堂々としていろ」と声をかける。三課の矜持を体現する場面です。
「一個人の責任」で幕引き――織田、辞表提出
やがて会社は、“一個人の責任”として終わらせる形で社内外の処理を図り、織田に辞職を促します。
織田は宇野部長(松澤一之)へ辞表を提出。
それは“現場の正しさ”を貫いてきた男が、最後まで部下の安全を守り抜くための静かな決断でした。
江部の処分、鷹野の行き先
監査の結末として、江部は懲戒解雇。鷹野専務は関連会社への出向処分に。
社内には仲介慣行の文化差や統制の甘さが露呈し、形式上は収束しても“風穴”はそのまま残る。
HOPEというタイトルが皮肉に響く一連の顛末です。
“去る者”と“残る者”――三課の空白と同期の日常
織田の退職後、営業二課の小早川(遠山俊也)が三課長を兼務。
「三課は二課に吸収されるのでは」と噂が流れる中、同期四人はいつも通りの一日を選び、送別会ではなく“今日の仕事”を淡々とこなす。
彼らの静かな選択が、成長の証として描かれます。
桐明のスピーチ――「どこで働くか」より「誰と働くか」
就活イベントで登壇した桐明(瀬戸康史)は、「大切なのは、どこで働くかではなく、誰と関係を築くか」と語る。
かつて新人時代に何度も折れかけた彼が、上司や同期との“横のつながり”で立ち直ってきた実体験を、未来の後輩たちへと手渡すシーンです。
歩の“最終出勤日”と、新しい扉
契約更新は叶わず、歩は与一物産を退職。
再就職活動を進める中、差出人不明の面接案内が届く。
訪れた先「翔道インターナショナル」の扉を開けると、そこには織田。彼は独立しており、「また一緒に働こう」と歩を迎える。安芸(山内圭哉)も加わり、三人は再び“同じ盤”に立つ。
希望の形が、穏やかに結実するラストでした。
HOPE(ドラマ)9話(最終回)の感想&考察
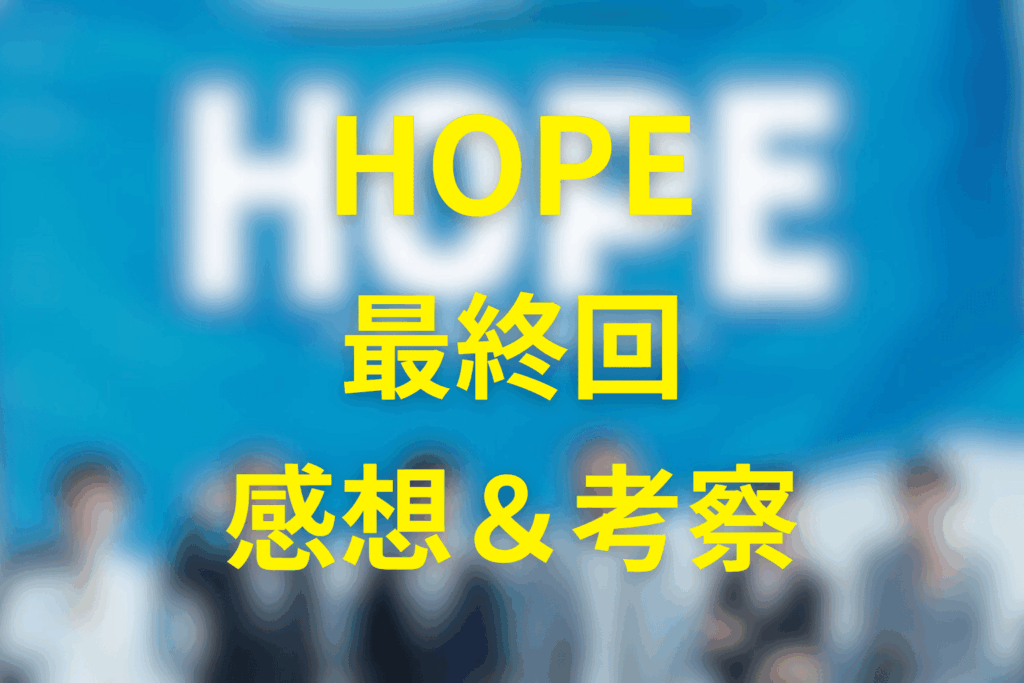
最終回の焦点は二つ。
(1)“責任”という制度の顔、(2)それでも人を救う“関係”の力。
どちらも抽象に見えて、脚本は手続と現場の温度で確かに描いていました。
スケープゴートの論理――「義務であり権利」という逆説
「一個人の責任で幕引き」という常套手段を前に、織田は“現場の誇り”で引き取る。
彼の言葉「責任を負うのは俺の義務であり権利」が象徴するのは、責任を可視化することで残る者を守る逆説。
制度の理不尽を受け入れながらも、関係の中に希望を見いだす決断でした。
監査が照らした“統制の穴”と文化差
仲介会社の後出し介入、身内の取締役、印鑑列の免罪符――
大企業の“形式的統制”がもたらす空洞を、ドラマはリアルに描く。
さらに“海外慣行”という文化の違いを挿み、「日本の規範をどこまで外に貫けるか」という実務的な問いを残しました。
「どこで」より「誰と」――職業観の更新
桐明のスピーチは、シリーズ全体の総括とも言える。
働く場所より、働く関係を選ぶという発想。
情報が分散し、決裁が多層化する時代にこそ、横の関係こそが成果の基盤になる。八話までの積み上げが“理念”として言語化される構成でした。
歩の“非更新”は敗北ではなく再選択
歩が契約を更新されなかった結末は、一見敗北に見えるが、「場を変えても続ける」という選択であり、職業人としての成熟の証。
織田の起業=“規範のプラットフォームを作る”という発想は、HOPEが掲げてきた「過程に宿る希望」を未来へ接続する終着点でした。
江部という鏡――“歪んだ出口”としての不正
江部は、成果への渇望と組織への失望が絡まり、不正へと転げ落ちた中間層の象徴。
懲戒解雇という断罪は、個人の物語を閉じながらも、“歪みを生んだ組織の責任”を観客に問う構造として機能していました。
ラストカットの意味――“同じ盤”に戻るという希望
小さなオフィス、少ない仲間、見えない未来。
それでも“再び同じ盤に立つ”選択をした三人は、囲碁の盤面に代わる新しい舞台で、もう一度「自分の手」を打ち始める。
敗北ではなく“続き”としての再開。この静かなラストに、HOPEの題がようやく真に重なりました。
総括――制度と関係、その両輪でHOPEを回す
制度(監査・人事)と関係(上司・同期)という二つの歯車を最後まで噛み合わせ、白黒ではなく“続けるために何を選ぶか”を問い続けた最終回。
希望とは、与えられるものではなく、現場が選び取る技術。
その信念で幕を閉じたHOPEは、働くすべての人への静かなエールとして深く残りました。
関連記事
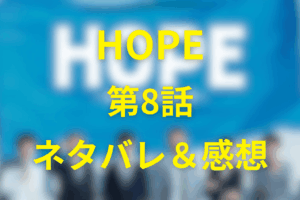
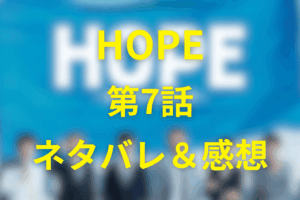
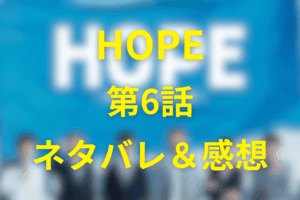

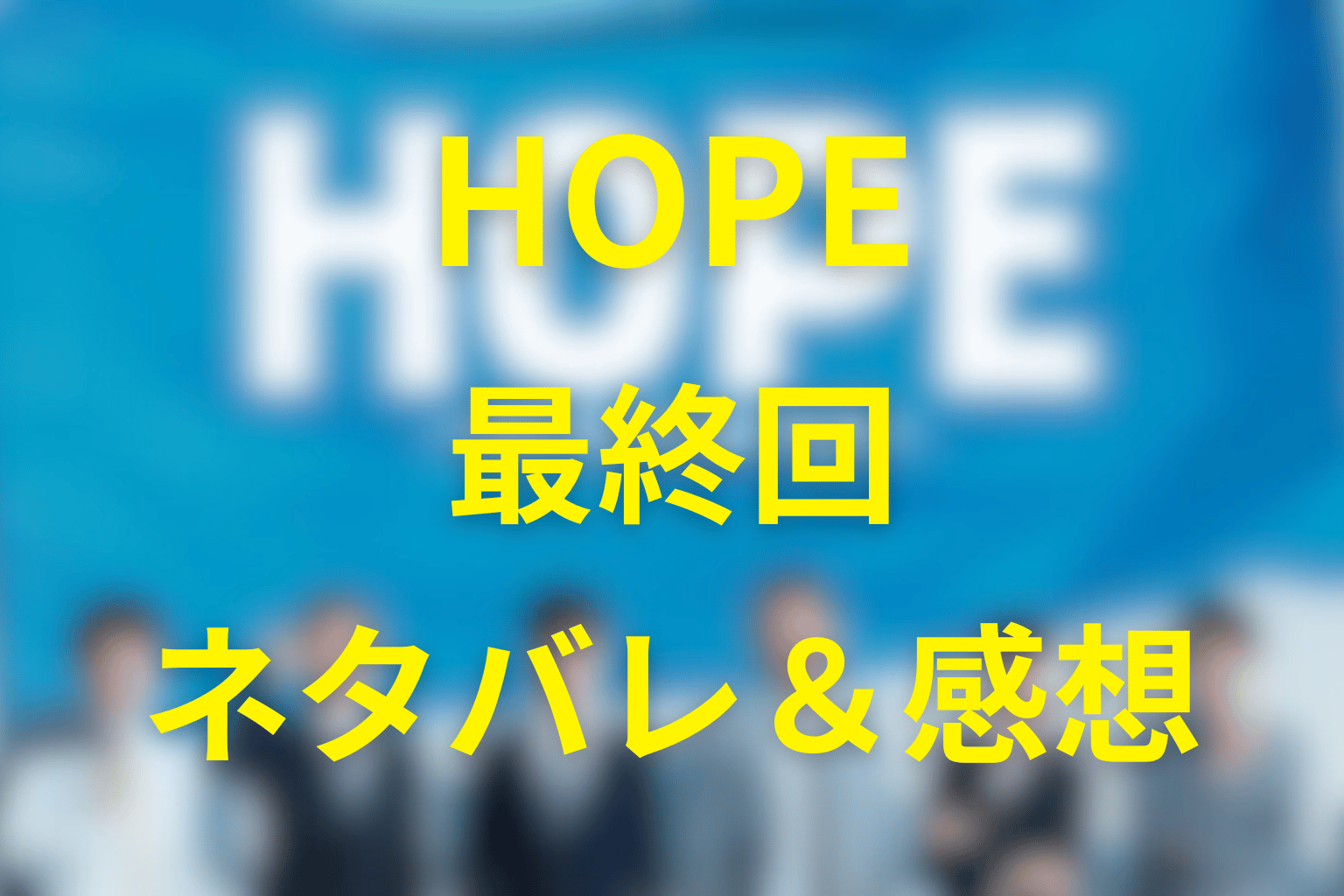
コメント