前回の1話では、昭和の熱血教師・小川市郎(阿部サダヲ)が令和へタイムスリップし、“昔の普通”が“今の不適切”に変わる衝撃が描かれた。
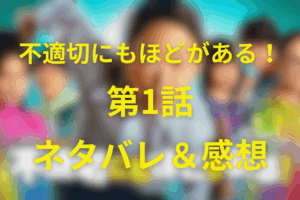
そして第2話では、舞台を家庭から職場へ――。
令和の働く母・犬島渚(仲里依紗)の苦しみに、市郎が“昭和の情熱”で切り込む。
一方、1986年ではサカエ(吉田羊)が純子(河合優実)とキヨシ(坂元愛登)の“青春の暴走”を止めようと奔走する。笑いと涙の中で、制度と心のすれ違いをどう埋めるのか。
ここから、『不適切にもほどがある!』2話のネタバレ&考察を詳しく紹介します。
不適切にもほどがある!(ふてほど)2話のあらすじ&ネタバレ
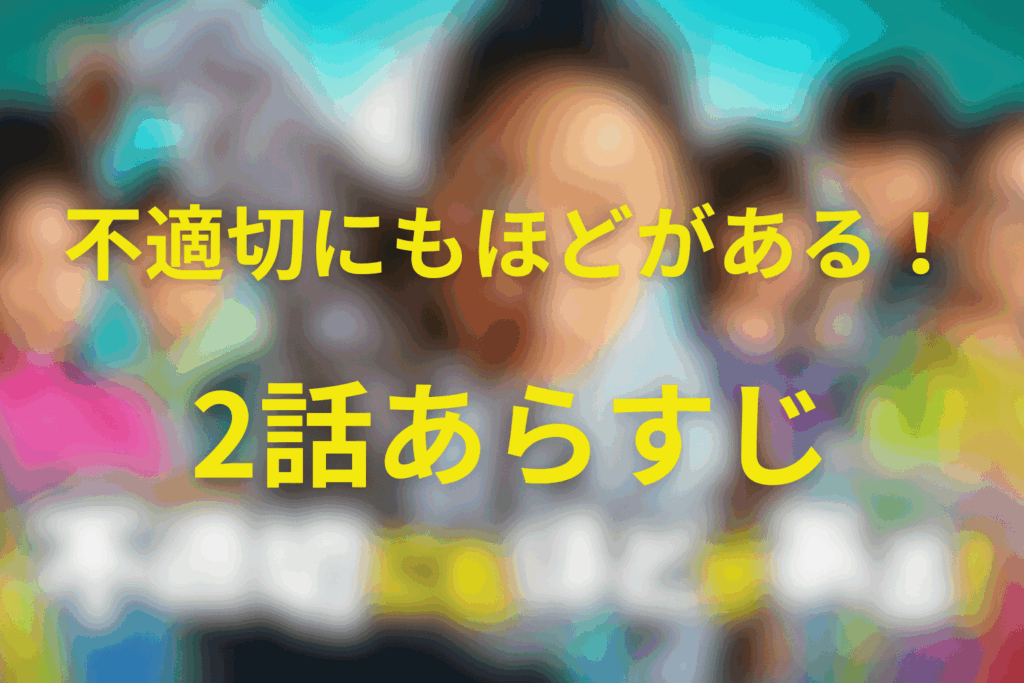
“昭和と令和をつなぐ一本の着信”から始まった第2話。
小川市郎(阿部サダヲ)のスマホに、1986年にいる向坂サカエ(吉田羊)からビデオ通話が入る。
犬島渚(仲里依紗)と秋津睦実(磯村勇斗)は、「タイムスリップは実在する」という衝撃の事実を目の当たりにする。しかし市郎が真っ先に伝えたのは、娘・純子(河合優実)とサカエの息子・キヨシ(坂元愛登)の“チョメチョメ”阻止。
サカエに「今すぐ小川家へ!」と懇願し、親として最低限の“現場対応”を依頼する。
渚の涙の理由——現代の働き方はなぜこんなに苦しいのか
市郎は、初対面で渚が泣いていた理由が気になっていたと打ち明ける。渚は「職場復帰」からの苦闘を語り始める。
テレビ局では“働き方改革”が進む一方で、引き継ぎはスマホのメモ頼み。上司は「紙、無理なんで」と言い放ち、シフト制の新人は定時で帰る。
結果、「自分で全部やったほうが早い」と託児所との往復まで抱え込む日々。
限界地点で缶ビールに手を伸ばした瞬間、現れたのが市郎。
その“一口”を奪われたことで、張り詰めた糸が切れ、渚は辞表と離婚届を出していた。場面には実名ネタや毒の効いた笑いが散りばめられ、SNSでも話題に。
だがその下に流れるのは、「制度はあるのに、誰も私を見てくれない」という切実な孤独だった。
昭和側の“臨場感”——サカエが小川家に乗り込む
一方、1986年側ではサカエが小川家を訪問。
純子に「小川は未来へ行って戻れない」「自分たちは未来から来た」と明かす。
怪談の“宜保愛子”に例えて茶化す純子へ、「宜保愛子じゃない!」と即ツッコミ。テンポの良い掛け合いの中に、親として子の暴走を止めたい緊張が走る。
EBSテレビで“昭和のカウンセラー”爆誕——歌って踊って核心に触れる
渚が荷物を取りに局へ戻ると、上司の引き止めに遭い身動きが取れない。
市郎は「今あんたがしてほしいことが、俺にできることだ」と駆けつける。
職場はミュージカルへ突入。柿澤勇人がキレキレのダンスを披露し、視聴者も沸騰。結果、市郎は渚の職場で“昭和のアドバイザー”として採用される。
彼の役目は、令和の働き方に“人間の温度”を戻す“応急処置”となった。
もうひとつの伏線:トイレは封鎖、看板の“S”で落下=タイムスリップのトリガー?
市郎が最初に使っていた“喫茶トイレ=時空の通路”は改修で封鎖。
帰還ルートを失ったまま渚といい雰囲気になった喫茶「SCANDAL」で、サカエに電話をかけようと看板の“S”に登った市郎は、文字の落下とともに昭和へ“落ちる”。
「市郎と渚の関係が深まるほど時代が反発する」ような描写が、早くも視聴者の注目を集める。関係性がタイムスリップのトリガーになる――そんな法則の萌芽を感じさせる演出だ。
タイムマシンの開発者は誰か——第2話で明かされた“名指し”
物語の根幹に関わる情報も提示される。
タイムマシンの開発者は、サカエの元夫でキヨシの父・井上昌和教授(三宅弘城)。
第2話でこの事実が正式に明かされ、1話の伏線がつながる。彼が語る「タイムパラドックス(過去改変が未来を変える)」は、渚と市郎の距離、純子とキヨシの恋、そして“親と子”の絆すべてに波紋を広げる。
以降、彼の存在が物語の“倫理の軸”として機能していく。
不適切にもほどがある!(ふてほど)2話の感想&考察
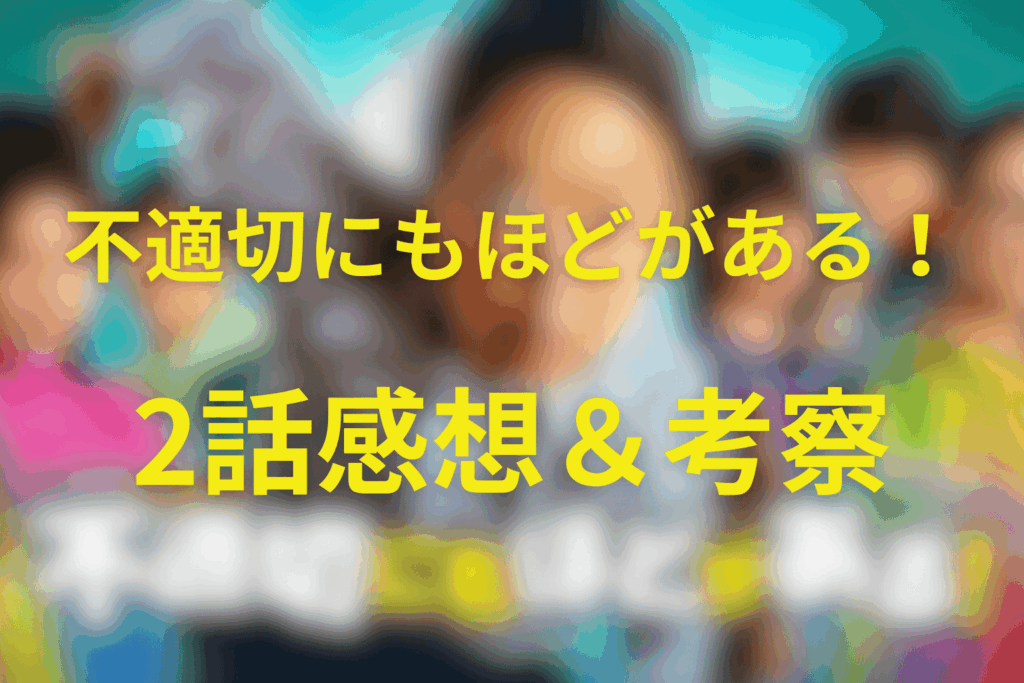
制度は正しいのに、なぜ人が壊れるのか
第2話は、「働き方改革」を敵にせず描いた点が見事だ。渚の職場には託児もシフト制も揃っている。
それでも彼女が行き詰まるのは、責任の置き場が“個人の胸”に積もるから。誰も矢面に立たない正しさが、彼女の一口の余裕を奪っていく。
市郎が奪った“缶ビールの一口”のギャグが刺さるのは、その一口分の息継ぎすら失った現代女性の現実を描いているからだ。
制度 vs. 現場の身体——「心の血流」を誰が流すのか
ミュージカル化する職場の混乱は、渚の“動けない身体”を象徴している。
市郎の台詞「今あんたがしてほしいことが、俺にできることだ」は、上からの助言ではなく、当事者の主語を取り戻す言葉だった。
第2話が描いたのは「働きやすさ」ではなく、「働ける関係性」。
令和の職場に昭和の熱を持ち込むことで、“血の通う現場”を取り戻していく。
タイムスリップの“反発装置”——ロマンスが近づくと時間が跳ね返る
市郎と渚が近づくたび、時代が反発する。
1話の帰路発見、2話の“S”落下――どちらも二人が“恋の気配”を漂わせた直後だ。制作側が意識的に“距離と跳ね返り”を仕掛けているなら、これは恋愛が“歴史改変”に直結することを示す“安全装置”。
次回、開発者・井上の説明が入れば、「恋」と「時間」の関係がより鮮明になるだろう。
科学 vs. 倫理——タイムマシン開発者の罪と正義
井上昌和がタイムマシンを作った背景が明かされ、物語は科学の領域に踏み込む。
だが彼の存在は、同時に“していいこと”を問う倫理の回路でもある。
家族や若者の青春を巻き込みながら進む時間実験は、科学が“感情の領域”をどこまで侵すかという問題に発展していく。
笑いと身体——ミュージカルの意義と名指しギャグの妙
八嶋智人の登場、宜保愛子ツッコミ、柿澤勇人の圧巻のダンス。
第2話は笑いとフィジカルを駆使して“疲弊した現代”を見せた。
名指しギャグは現実への針を立て、ミュージカルは整理できない感情を身体で表現する。笑いを入り口に、渚の「辞表と離婚届」の重みをきっちり喉奥に残す構成が秀逸だ。
昭和パートの“親の責任”——サカエと市郎、二つの不器用さ
昭和側ではサカエが説明責任を背負い、小川家の秩序を立て直す。市郎は渚の“一口”を奪う無神経さと、駆けつける真っ直ぐさを併せ持つ。
どちらも正義であり、どちらも不適切。
この相反する“人間らしさ”こそが、タイトルの意味を最も端的に体現している。
総括
第2話は、「制度が人を救うのではなく、人が人を救う」を笑いと歌で包んで描いた回。
働き方が“正しさの配列”になった令和に、昭和の“顔の見える関与”をぶつけることで、渚の主語は回復する。
同時に、恋の接近が時間の反発を招くという“見えない律”も提示された。
ここからは渚の再起、市郎の帰還、純子とキヨシの距離――三本の線を、井上の“科学と倫理”がどう交差させるのか。
次回、第3話からが本当の綱引きとなる。
不適切にもほどがある!の関連記事
不適切にもほどがある!の全話のネタバレはこちら↓
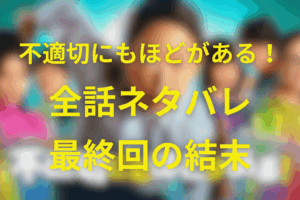
次回以降の話についてはこちら↓
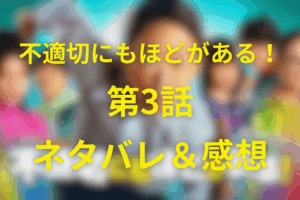
過去の話についてはこちら↓
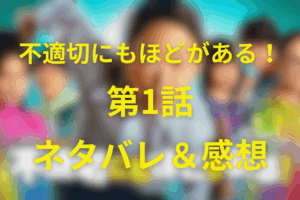
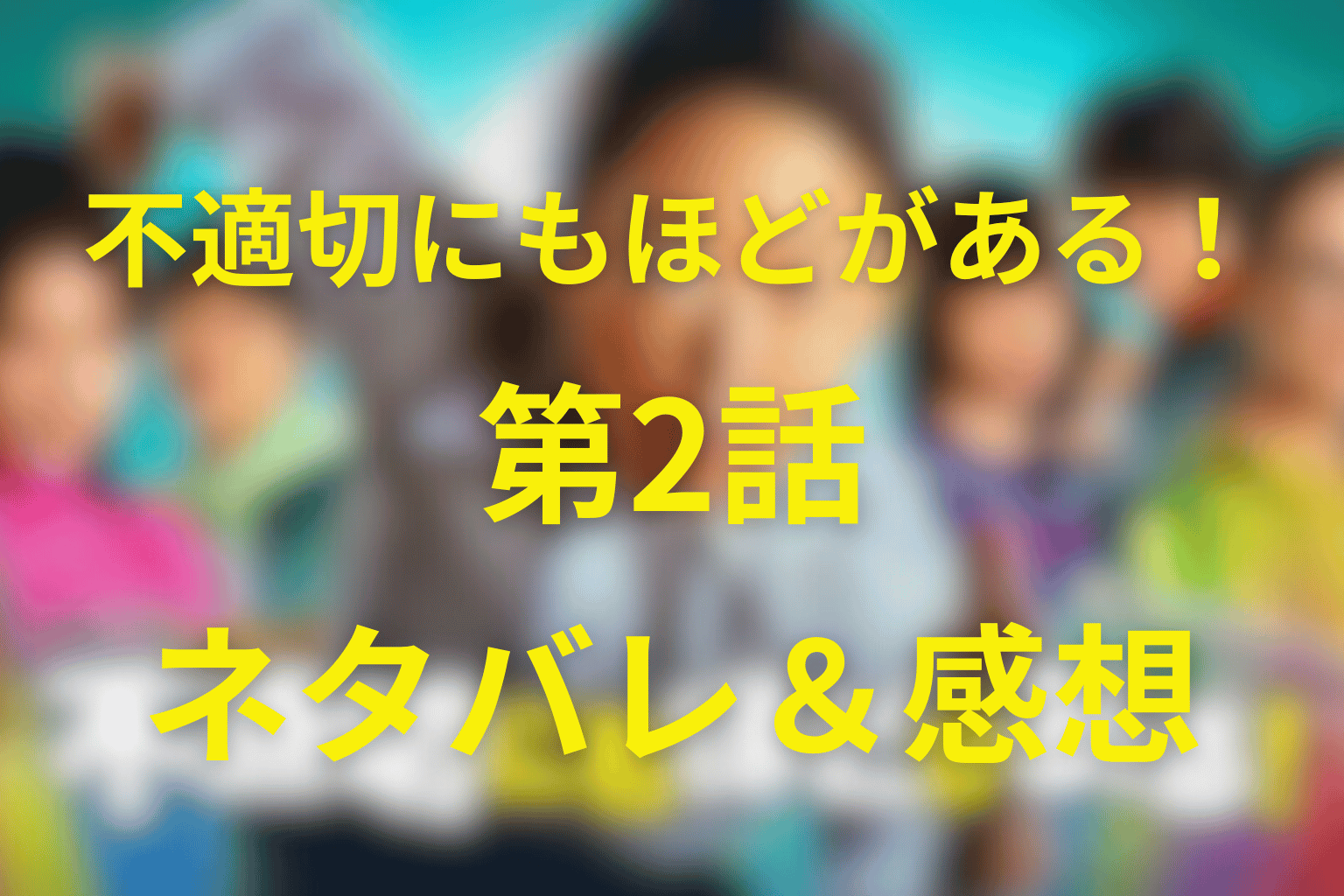
コメント