前回第2話では、競馬事業部の再建を賭けてイザーニャとファイトがデビューし、初勝利を掴んだ矢先にアクシデントが発生――希望と不安が交錯する展開で幕を閉じた。
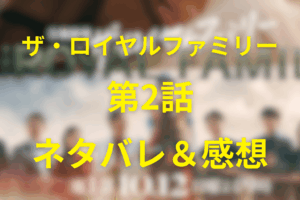
「勝てる馬を“買う”のか、それとも“育てる”のか」。
第3話は、競馬を支える“人と人の信頼関係”に焦点を当てたエピソードだ。イザーニャとファイトの離脱で追い詰められた山王家とロイヤルヒューマンの面々が、北海道・日高で新たな希望…と出会う。
そこに描かれるのは、データや資金では測れない“人の誇り”と“信じる力”の物語。
伝統の「庭先取引」を通して、競走馬を“商品ではなく夢”として扱う者たちの矜持が浮かび上がる。
「ザ・ロイヤルファミリー」3話のあらすじ&ネタバレ
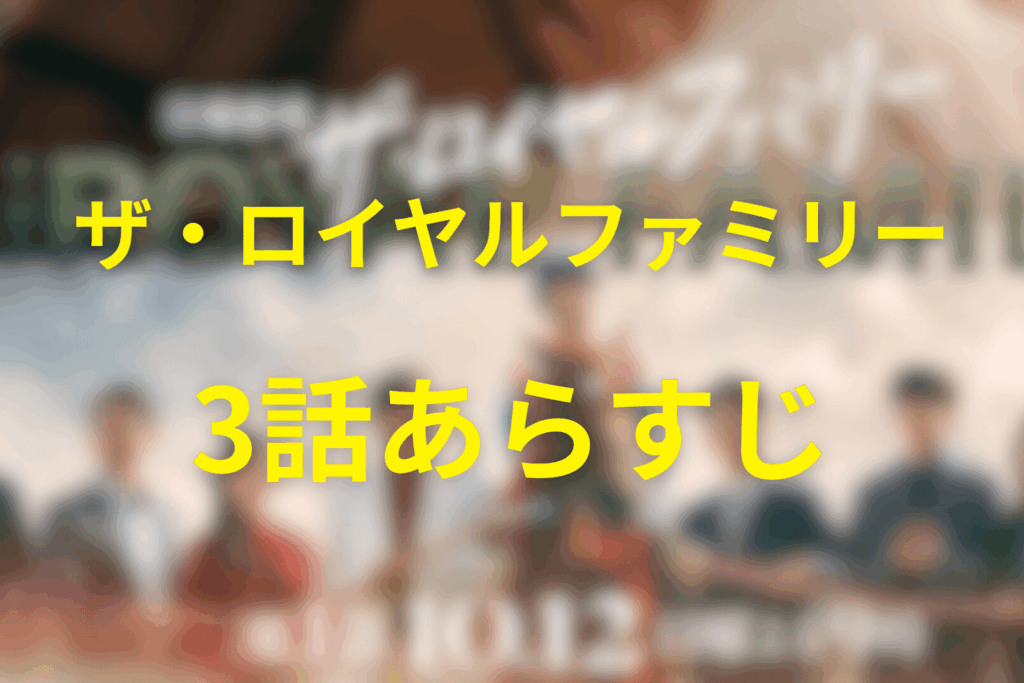
第3話の副題は「庭先取引」(10月26日放送)。
日高の生産牧場と大企業・山王家、そしてセリ市のリングで交差する“馬の値段”と“人の矜持”が静かに火花を散らす回となった。
物語の軸は大きく二本。
①生産者サイド(野崎家)で揺れる直接取引=庭先取引の是非。
②山王側(栗須・耕造)による新たな良血馬の探索と、宿敵・椎名善弘(沢村一樹)との競合。
この二つが、のちの“1億円落札”(第4話)につながる準備線として周到に描かれている。
序章:生産牧場の現実――「庭先で売る」という誇りと重荷
牧場経営者の野崎剛史(木場勝己)は、セリを介さず馬主と直接やり取りする“庭先取引”にこだわる人物。
しかし娘の加奈子(松本若菜)は、父の頑固なやり方がたびたび馬主を怒らせ、破談を招くことに頭を抱えている。
第3話は、生産地の台所事情。
理想(誇り)と現実(資金繰り)のギャップを真正面に置き、以降の“購買の物語”に切実なリアリティを与えた。
補足:庭先取引とは何か
競走馬の売買を公設のセリ市場を通さず、生産者と馬主が直接交渉して値段を決める手法。
近年は透明性や価格形成の公正さからセリ主流が進む一方、血統や信頼関係を重視して“庭先”を守る生産者も多い。
第3話の焦点はまさにこの価値観の衝突であり、誇りと生存のバランスをどう取るかが描かれている。
山王家のテーブル――百合子の誕生日会が映す“家と馬”
一方、栗須栄治(妻夫木聡)は、山王耕造(佐藤浩市)の娘・百合子(関水渚)の誕生日会に出席。
その場で山王家の競馬事業を語る京子(黒木瞳)は、「家と馬は似ている。どちらも血と誇りで成り立つもの」と口にする。
だがその席で、息子の優太郎(小泉孝太郎)が「結局イザーニャの一勝しかできなかった」と辛辣に言い放ち、空気が凍る。 耕造の妻・京子(黒木瞳)は、夫が競馬事業にのめり込む姿を見て複雑な想いを抱いていた。
実は彼女の実父も競馬に熱中するあまり家庭を顧みず、母に苦労をかけた過去があった。
夫がその父と同じ道を歩み始めていることに京子は不安を隠せず、「父のようになってほしくない」と涙混じりに呟く。
競馬を巡る家族の溝――この家庭の緊張は、後の物語にも繋がっていく。
かつてイザーニャの勝利で息を吹き返した山王だが、その後イザーニャもファイトも相次いで故障。
「有馬記念を勝つ」という悲願を果たすには、新たなエースが必要だと語る耕造。栗須と耕造は次の一頭を求め、名門・北陵ファームのセリへ向かう。
イザーニャ&ファイトの故障――“いま”を失う痛み
ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を支えてきたイザーニャとファイトに、相次いで故障が発生。
現有戦力で有馬記念を戦うことは不可能だと突きつけられ、耕造と栗須は新たな主役探しを決断する。ここで“馬の世代交代”が明確に打ち出され、物語の核である「継承」のテーマ――親から子へ、過去から未来へ――が競走馬にも重ねられる。
セリ前夜――リングで出会う“敵”と“条件”
北陵ファームのセリに挑む山王陣営の前に現れるのは、国内屈指の馬主・椎名善弘(沢村一樹)。
狙うのは同じ一頭。
合理的な投資を重ねる椎名の“セリの流儀”は、誇りで値段を決めがちな“庭先取引”との鮮烈な対比として機能する。
第3話では落札の結果まで描かず、「誰が、どの条件で、どんな哲学で買うか」という構えの差を丁寧に積み上げ、次話への緊張を極限まで高める。
購買とは価格の勝負であると同時に、信念の勝負であることを観客に突きつける構成だ。
北海道・北陵ファームのセリへ――ライバル椎名の影
新たなスター候補を求めて、耕造と栗須は北陵ファームのセリへ向かう。
しかしそこには、資金力と情報力を兼ね備えたライバル・椎名(沢村一樹)も同じ馬を狙っていた。入札をめぐる駆け引きが火花を散らし、栗須の理想と耕造の野心、そして椎名の策略がぶつかり合う構図が生まれる。
椎名の資金力に負けて、耕造と栗須は馬を落札できなかった。
野崎ファーム訪問と剛史の信念
耕造と栗須は日高へ飛び、野崎ファームで加奈子と父・剛史に出会う。早速商談を持ちかける耕造に、剛史は厳しい眼差しを向けて言い放つ。
「あんたに勝つ気はあるのか?」
理由を問う耕造に、剛史は静かに答える。
「商売じゃない、勝負なんです。勝つために選んだ命懸けの勝負なんです。」
それは、競走馬を“商品”ではなく“誇り”として扱う生産者の信念。耕造は真摯に耳を傾けつつも、同じ経営者としてのプライドが刺激され、二人の言葉はぶつかり合い、交渉は決裂する。
しかし栗須と加奈子は、父たちの間に芽生えた“共通の熱”を感じていた。
日高の現実と耕造の理解
居酒屋で牧場主たちと語らう中、耕造は日高の過酷な現状を知る。
後継者不足、高齢化、資金難――夢を持っても生き残るのは一握り。
それでも剛史は「自分の牧場の馬でG1を勝ちたい」という信念を捨てていなかった。
彼の頑なさの裏に、日高の生産者としての誇りと孤独があったことを、耕造は初めて理解し始める。
再交渉への道――ロイヤルハピネスと資金繰りの提案
初日の交渉が失敗に終わった後、栗須は諦めず策を練る。
そんな時、ロイヤルヒューマン社の所有馬ロイヤルハピネスを預けていた牧場が廃業するという報せが入る。栗須は機転を利かせ、「その馬を野崎ファームで預かってもらう」提案を思いつく。
預託料が野崎の運転資金になり、経営の助けになるはずだ。耕造も賛同し、二人は再び野崎ファームを訪れる。
剛史もこの提案に「……うちで預かっていいんですか?」と驚きつつ受け入れた。
こうして、互いの信頼が少しずつ芽生えていく。
奇跡の仔馬との出会いと“1億円”の決断
剛史は頑なに隠していた“とっておき”の仔馬を、ついに耕造に見せる。
生まれて間もない青鹿毛の牡馬――それがのちにロイヤルホープと名づけられる仔馬だった。剛史はこの仔に、自身の夢と日高の未来をすべて託していた。
父は世界的名馬ファイナルダンサーの系譜、母は牧場自家生産の良血。だが価値はまだ低く、他の馬主たちは皆この仔を恐れて近寄らなかった。
しかし、初対面の耕造がそっと手を伸ばすと、仔馬は驚くほど穏やかに受け入れた。
誰にも懐かなかった馬が、自ら耕造に歩み寄る。剛史と加奈子は息を呑み、耕造も言葉を失う。その瞬間、馬主と生産者の心が通じた。
剛史は語る。
「俺たちは皆、この仔に夢を託しているんです。」
その言葉に胸を打たれた耕造は、「その夢、私にも見させてください」と応じる。
そして剛史は提示する。「1億円です。」
高額にも関わらず、耕造は即答する。「買わせていただきます。」
こうして、野崎ファームの命運を懸けた馬の売買契約が成立した。
新たな夢の船出――馬名「ロイヤルホープ」の誕生
契約成立後、耕造・栗須・剛史・加奈子の四人は杯を交わし、新しい夢を祝う。
「これからは皆で同じ夢を追おう」と耕造。
名付けの場面では、栗須が稲妻模様の白斑から「ロイヤルサンダー」を提案するが、採用はされず。
後日、耕造が自らの口で告げた。
「ロイヤルホープ――希望を託す馬だ。」
“Hope”という言葉に、生産者と馬主それぞれの願いが重なり、「ロイヤルホープ」は日高の希望と山王家の夢を乗せて産声を上げる。
ラストで耕造は栗須に語る。
「これでまた、一緒に夢を追えるな。」
静かな笑みと共に、ロイヤルファミリーの新たな挑戦が始まる。
ラストの着地――“信じる力”の再定義
「勝てる馬を買う」のではなく、「勝てると信じる生産者と手を組む」。栗須のこの言葉が“庭先”の緊張を解き、売買の向こう側にある“共同作業としての競馬”を照らし出す。
第3話は、ロイヤルホープへの出会いをクライマックスに据えつつ、競馬事業を支える“信頼の物語”として幕を閉じる。次回、第4話では1億円での獲得後、育成の過程で再び訪れる試練が描かれることが予告されている。
「ザ・ロイヤルファミリー」3話の感想&考察
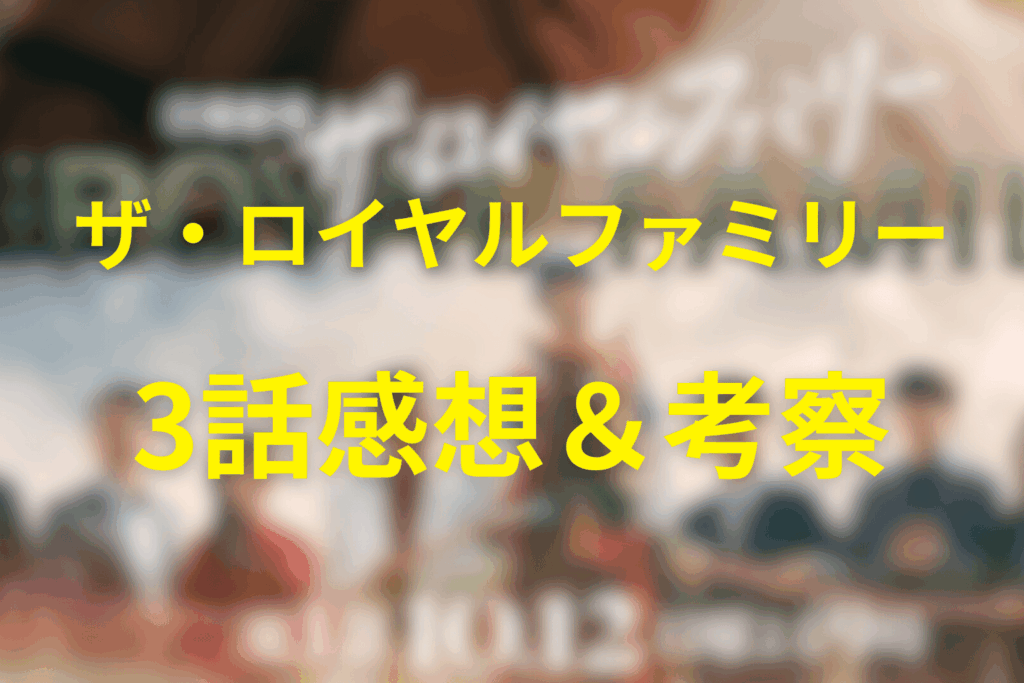
第3話は、競馬ビジネスの“現実”と“信じる力”という物語的テーマを、極めて精密に噛み合わせた回だった。
競走馬は投資であり資産であると同時に、“生き物”であり、人が注ぐ想いの結晶でもある。その二面性を「庭先取引」という伝統的な取引様式の中で描き出し、言葉や態度、矜持といった“目に見えない価値”をドラマ化した構成は見事だった。
「勝てる馬」vs「売れる馬」――数値化できない価値のせめぎ合い
スピード指数、血統表、歩様動画など、データで勝ち負けを測れる時代にあっても、最後に問われるのは人間の胆力と信頼関係だ。剛史の頑固さは単なる偏屈ではない。生産者にとって馬は「売る」ものではなく「託す」もの。そこに職人としての哲学がある。
一方の耕造と栗須は、投資家として冷徹な計算を持ちながらも、“勝利を共有できる相手”を探している。
だからこそ栗須は、「日高だからダメ」「北陵だから良い」といった土地やブランドの記号を拒み、「信じられる人」を基準に動く。3話の熱量は、まさにこの“人間を信じる経済”の中にある。
“家族の記憶”が夢にリアリティを足す
百合子のバースデーを起点に、山王家の記憶を紐解く構成が巧みだった。
京子が語る一族と馬の来歴によって、耕造の夢は裸の野心から“家族の祈り”へと転化する。血の時間が夢の根拠を支えた瞬間、視聴者は「勝ったら泣ける」理由を受け取る。
日曜劇場の王道文法ともいえる“家族の温度”がここで強く息を吹き返した。
剛史の誇りと耕造の柔軟さが生んだ奇跡
剛史を演じる木場勝己さんの演技は、まさに圧巻。老いた小規模牧場主が、都会の大企業社長に真正面から啖呵を切る姿に胸が震えました。
「庭先取引にこだわる職人」としての誇りと、頑なすぎる不器用さが絶妙に同居しており、その人間くささが物語を支える柱になっています。
そして耕造もまた、資金力だけで勝負する経営者ではなく、「馬を愛する人の想いにこそ未来がある」と気づく柔軟さを見せました。
互いのプライドをぶつけ合った二人が、最後には同じ夢を見て杯を交わす。その和解の瞬間に“本当の勝負の意味”が宿っていました。
剛史は信念を曲げたのではなく、耕造という新たな理解者を得て信念を貫くための方法を更新したのです。
この二人の和解劇は、多くの視聴者の涙腺を刺激したことでしょう。
「馬を見る目」ではなく「人に賭ける」耕造の流儀
第3話で改めて感じたのは、耕造という人物の器の大きさです。
彼は自ら「俺には馬を見る目はない」と言い切りながら、その分「人間を見る目には自信がある」と行動で証明してみせました。
耕造が野崎ファームの仔馬に心を決めたのは、血統や価格ではなく、牧場の芝生の手入れや働く人々の真摯な姿を見たから。細部に宿る誠実さを見抜く力――それが彼の強さです。
また、栗須(妻夫木聡)の提案を受け入れてロイヤルハピネスを預託する決断も印象的でした。
経営者としての合理性に加え、“人情を汲み取る判断”ができる耕造の人間味が際立っています。
ワンマンに見えて実は繊細で温かい。
佐藤浩市さん演じる耕造は、まさに「豪胆と優しさ」を併せ持つ理想のリーダー像でした。
栗須と加奈子――旧友の距離感が生む“柔らかな情”
栗須と加奈子(松本若菜)の関係も、3話の隠れた見どころです。
元恋人という設定がありながら、今は互いを尊重し合う大人の距離感が絶妙。久々の再会で少しぎこちない空気が流れる中、競馬の話になると自然に息が合い、当時の信頼関係が蘇るのが微笑ましい。
そしてラスト近く、耕造が「お前の昔の女だろ?」と栗須を茶化すシーン。気まずさの中に優しいユーモアが漂い、重厚な物語に温度を加えていました。
また、加奈子の息子・翔平が作文で「将来の夢はジョッキー」と書く場面も胸を打ちます。
日高の小さな牧場の息子が、自ら騎手を目指す――まさに夢を次世代へ繋ぐ象徴的な描写でした。この親子の夢が、ロイヤルホープの物語とどこかで交差する未来を期待したいです。
ロイヤルホープという“旗”が掲げられた意味
第3話の最大の見せ場は、新馬・ロイヤルホープの登場だ。〈ロイヤル〉は山王家の“家印”、〈ホープ〉は未来への継承。
イザーニャとファイトの離脱によって空いた席を、希望という言葉が埋める。これは単なる補強ではなく、物語の旗そのものを掛け替える行為だ。
ロイヤルホープは、耕造と栗須が「勝つために信じる」対象であり、同時に次世代へ繋ぐ象徴となった。次回は“1億円で購入したロイヤルホープが育成段階で壁にぶつかる”ことが予告されており、「勝負は買った後から始まる」という現実主義的視点が貫かれている。
経済合理性と“作り手の面子”をつなぐ、栗須の交渉術
庭先取引の場面で空気を変えたのは、栗須の言葉だった。理屈で押し切らず、感情にも媚びず、目的(勝利)と敬意(作り手への尊重)を両立させる交渉術が光る。
投資家が“人を買う”姿勢を見せたことで、生産者は“馬を託す”覚悟を固めた。条件闘争を価値共有に変える――栗須の交渉は、ビジネスドラマとしても完成度が高い。
ライバル・椎名の存在意義――物語を“競走化”する装置
椎名(沢村一樹)は、このドラマを“競馬”として成立させる存在だ。資金力・情報力・人脈、すべてにおいて優位な彼が同じ馬を狙うだけで、価格は上がり、決断の時間が削られる。
3話は“交渉の物語”であると同時に、“時間とのレース”でもある。
椎名という外圧が、耕造・栗須、そして加奈子に腹の底からの決断を迫る構図が緊張感を生んでいた。
なぜ「庭先取引」がドラマになるのか
庭先取引とは、セリ市と違い透明な市場原理が存在しない、まさに“人間関係の交渉”だ。血統や測尺だけでなく、どの厩舎に預け、どの騎手が乗るのか、どのように育てるのか――未来まで含めて語り合う場所である。
剛史の不器用さは誇りの裏返しであり、同時に商機を逃すリスクでもある。
そのバランスを次の世代――加奈子がどう引き継ぎ、更新していくかが物語の鍵になる。
総括:3話は“関係の物語”としての転換点
イザーニャとファイトの故障は、物語上の都合ではなく、現実の競馬が抱える「戦力の劣化」を描いたリアリティだ。
ここからドラマは、“関係で勝つ”物語へと舵を切る。ロイヤルホープという旗の下、山王家(耕造・京子・百合子)、ロイヤルヒューマンの社員、ノザキ父娘、そして栗須が同じ方向を向けるのか。
3話はその初動を丁寧に描き、次への期待を大きく膨らませた。第4話では、1億円の投資を現実の勝利に変えるために、育成段階での試練――気性・馴致・騎手問題――が立ちはだかるだろう。
「子は親を超えられるのか」という原作の命題が、家族から馬、そしてチームへと拡張していくターニングポイントである。
ザ・ロイヤルファミリーの関連記事
ザ・ロイヤルファミリーの全話ネタバレはこちら↓
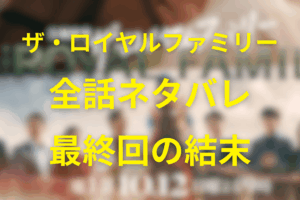
ザ・ロイヤル・ファミリーの原作についてはこちら↓
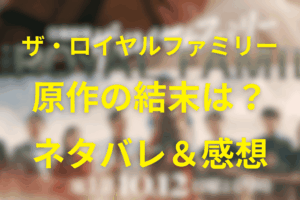
ザ・ロイヤル・ファミリーの4話についてはこちら↓
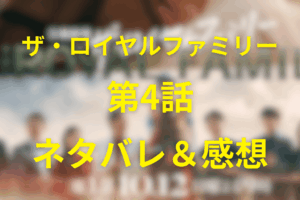
ザ・ロイヤル・ファミリー1話についてはこちら↓
ザ・ロイヤル・ファミリーの目黒蓮についてはこちら↓
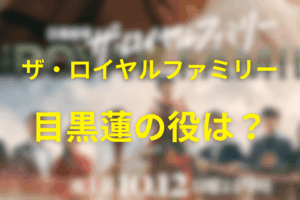
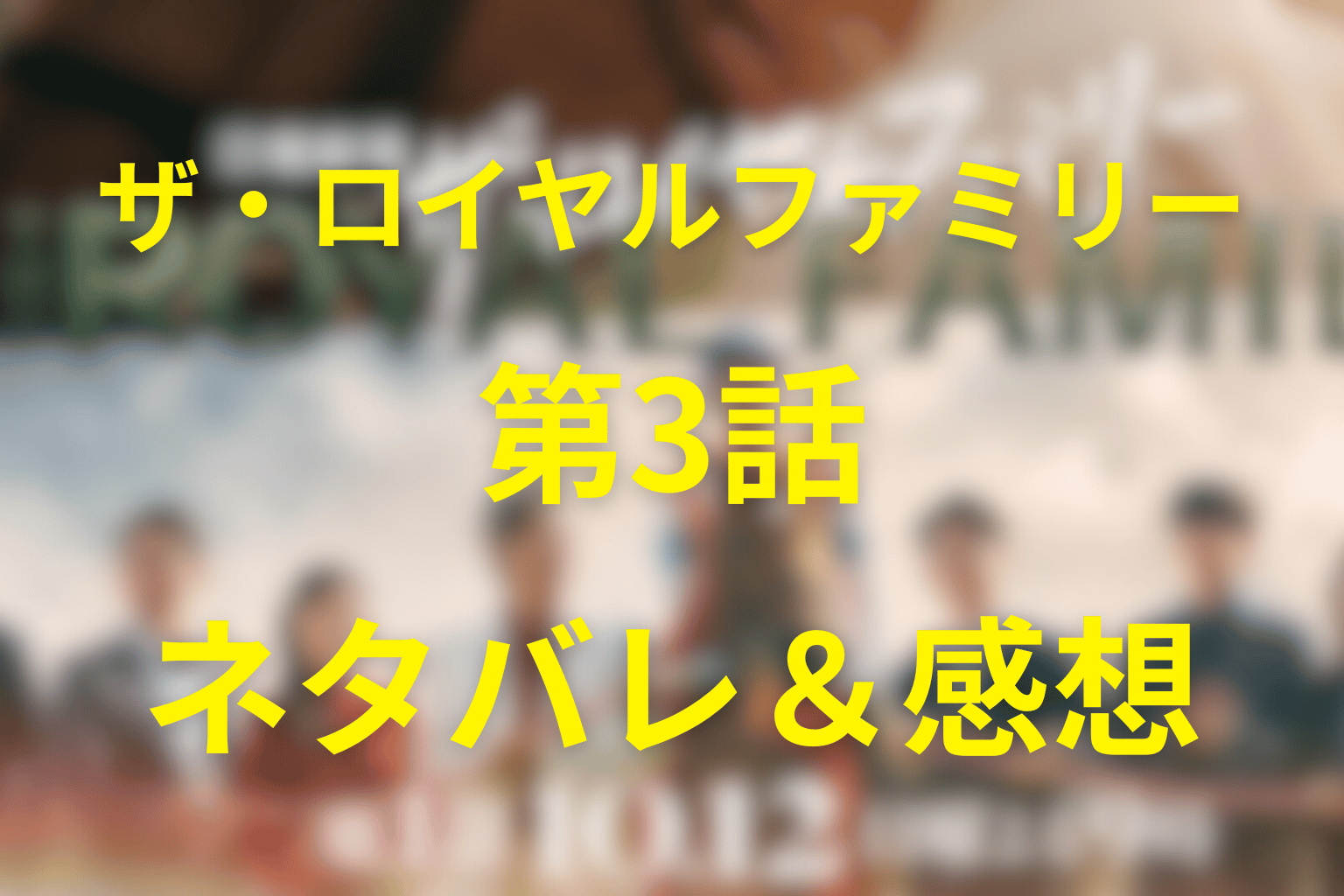
コメント