ついに迎えた『今際の国のアリス』シーズン3の最終回、第6話。
これまで数々の極限ゲームを乗り越えてきたアリスとウサギの物語は、最後に「生と死の選択」という究極のテーマに直面します。
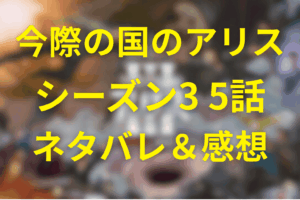
舞台は「ミライすごろく」の決着から始まり、仲間を救うために誰が残り、誰が未来へ進むのか――その決断が物語の核心を突き動かしていきます。
さらに、謎多き“バンダ”との対峙、そして新たに姿を現す“番人”による衝撃の真実の開示。シリーズを貫いてきた「選択」「犠牲」「未来」というモチーフが一気に収束する最終回は、観る者に強烈な余韻と考察の余地を残しました。ここからは、そんな第6話を振り返りながら感想と考察を深めていきます。
※ここからはネタバレに注意です。
今際の国のアリス(シーズン3)6話(最終回)のあらすじ&ネタバレ
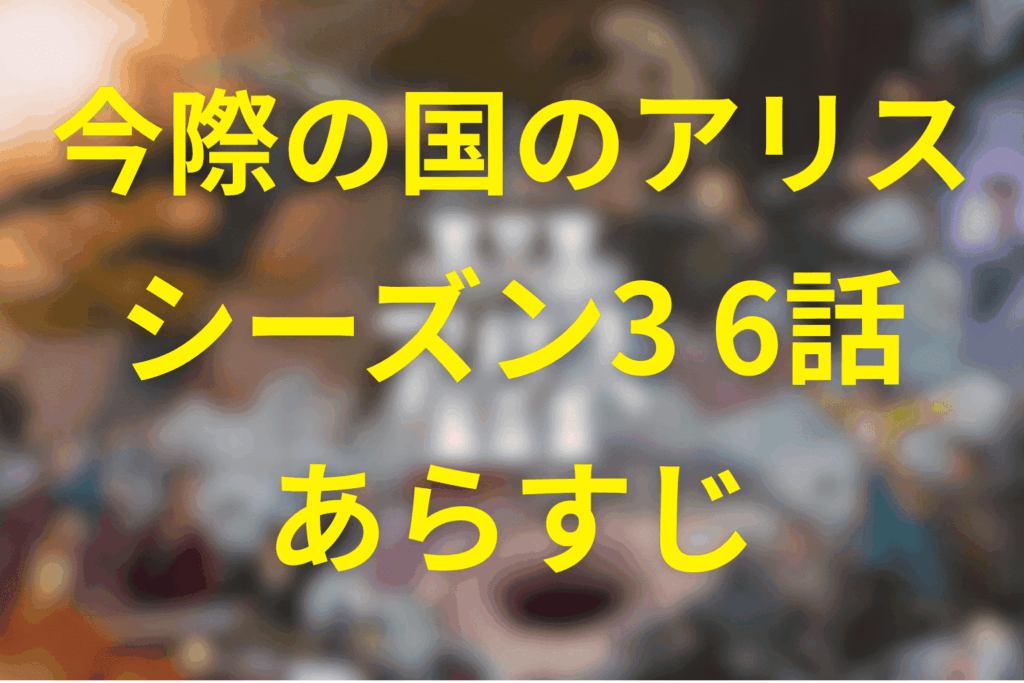
最終回は“選択”の物語でした。誰かを救うために何を捨てるのか。
生と死の狭間に引き寄せられた人間は、たとえ「正解のないゲーム」でも、最後は自分の手で道を引く――6話は、その姿を徹底的に描き切ります。以下、完全ネタバレでお届けします。
シーズン3は全6話構成で9月25日(木)にNetflixで一挙配信開始。今作の導入=アリスとウサギは結婚し、ウサギ失踪を機に“今際の国”へ再突入する――という大枠も公式情報として明示されています。
ミライすごろくの続き…
5話の続き、舞台はミライすごろく。
5話でテツとソウタが命を落とし、その結果、残るはアリス、ウサギ(赤ちゃん)、サチコ、リュウジ、レイ、ノブ、ユウナの8人となりました。
ノブはビジョンの未来から逃げるように独走していましたが、正気を取り戻し、アリス達とも最終的に合流する決断をします。
アリスは残る8人全員の生存を念頭に、戦略的にも前進していきます。
ウサギの胎児用リストバンドが物語の鍵になる
サチコがロック状態となり、プレイヤー同士で挟む形の部屋に入らねば、サチコを救う術が今のところまったくない。
ただ、プレイヤー達の点数は既にボロボロの状態。
サチコを救えば8人全員は守れず、誰かが欠ける、と覚悟させられる展開にも。
そこでアリスは、レイが隣室にいながら身体の一部を外へ出しても爆発しなかった点に強く着目する。
どうやらリストバンドが部屋内にあれば、その部屋に“在る”と認識され、バンドさえ外へ出なければ安全だというロジックが明確に判明。
ウサギはサチコ救出のため、リストバンドのみを部屋へ置く作戦を敢行。その結果、部屋側はプレイヤーとして認識し、無事にサチコの強制ロックを見事に解除。胎児用のリストバンドは最後まで得点が残っていたため無事だった。
ミライすごろく、いよいよ決着へ
各部屋のビジョンに映る映像は、これから起こる未来を示すものだと言える。
ウサギは…赤ちゃんのリストバンドをなんとか救い出し、隣室へ向かう途中で、アリスが部屋内でひとりとなり、死に至るその未来を目撃する…。
アリス達と合流する他ないが、この先へ進むとアリスが死んでしまう…という未来に足がすくむ思い。
そんなウサギを見たアリスは、自ら部屋に入り、彼女の救出へすぐ向かう。
リュウジら仲間の助力も重なり、全員が出口部屋のある「A5」へ到達する。
“7”の出目と身代わり――アリスは残り、ウサギたちは扉の向こうへ
ついに出口の間際。
アリスがサイコロを振ると“7”――8人いるため通過可能な人数が足りない。ここでアリスは自ら残ることを選ぶ。ウサギは必死に拒むが、アリスは彼女を出口へ押し出し、仲間に託す。
「誰かが残らなければ誰も帰れない」というシリーズの根底にある命題に、正面から挑んだ瞬間でした。
アリスはリュウジにウサギを任せ、ウサギを除いた全員は出口を通過する。
出口の先は渋谷の外で、アリス以外の全員が無事に脱出できた。
自己犠牲を選んだアリスに向け、スクリーンは「クリア」を告げる――。
アリスは部屋の中から外の光景を目にし、胎児を含めた7人の姿を確認する…。その時、リュウジはバンダの命令に従い、ウサギを銃で撃とうとしていた…。
その光景を見て、必死に止めようとするアリス。しかし声は届かない…。
だが土壇場でリュウジは引き金を引かず、ウサギは命を救われた…。
しかし安堵も束の間、渋谷は轟音と共に崩壊し、都市を濁流が呑み込む。向こう側のウサギ達は濁流に飲まれてしまうのだった。
バンダの登場と…アリスとの会話
外の混乱を気にかけるアリスの中で、部屋は突如真っ白に染まる…。
最後の部屋に残されたのはアリスひとり。スクリーンには今回のゲームの主催者であるバンダの姿が浮かび上がる…。
バンダは、アリスをこの国の市民にするため、ウサギを利用して呼び寄せたのだと語る…。
アリスは壁を叩き壊し、自ら道を切り拓いて再び彼女を追い飛び込む。ここからが最終回の“核心”へと続いていく。
現実世界でのバンダとの攻防
濁流に飲まれた後、舞台は現実世界へと移る。
アリスは臨死状態にあり、眼前には杏の姿があった。
バンダはアリスをこちらの世界に引きずり込もうと、現実のアリスの顔を覆い――命を奪おうとする…。もしここで殺されれば、アリスは永遠に今際の国に留まるしかなくなる。
だが現実世界の杏が必死にそれを阻止し、バンダはアリスを殺すことに失敗するのだった。
バンダと最後の交渉…
再び今際の国へ戻ると――。
濁流の中でウサギを追うアリスの前に、銃を構えたバンダが立ちはだかる。
彼は最後の忠告を突きつける――「国民になる気になったかね?」。アリスは即座に拒絶する。「何度聞かれても、俺は国民になるきはない」。
拒絶を受けたバンダは銃を引き絞り、アリスを撃とうとする…。
その刹那、天から放たれたレーザーがバンダを貫いた。
「どうやら彼には、この役目は早すぎたようだな」
――謎の男性の声が響く。
バンダは“市民”としての資格を剥奪され、ボーダーランドを支配してきた制度が崩れ始めたことを示す決定的な光景だった。
〈時間停止〉と“番人”――ジョーカーは“誰か”ではなく“概念”
世界がスッと静止する。アリスの目の前に、黒い帽子をかぶった老紳士が現れる。
演じるのは渡辺謙、“番人”の登場である。
彼は自らをジョーカーではないと告げ、二枚のカードを差し出しラストゲームを提示する。「ジョーカーを引けば君の負けだ」。だがアリスはすぐに悟る――どちらもジョーカーであることに。
今回のカードはジョーカーを含めて365枚。そしてもう一枚のジョーカーを加えれば366枚。つまり人間界の時間、平年と閏年に対応しているのだ。
ここで“番人”は核心を明かす。
ジョーカーとは人ではなく、数字に属さない“隙間”を埋める札。
時間の継ぎ目であり、生と死をつなぐ道化。つまり境界の機能そのものだ――と。彼自身はただの“見守る者”にすぎず、アリスに差し出すのは「生へ戻るか、死へ進むか」という究極の選択だけだった。
選ぶのは“生”――ウサギの救出、そしてリュウジの決断
アリスは“生”を選択する。
すると時は再び動き出し、濁流の中でウサギへと手を伸ばす。リュウジはウサギを“死”へと引き込もうとするが、最後の瞬間にその手を放す。
彼は自ら“死”を選び、罪と執着に彩られた物語に自ら幕を下ろすのだった。
ウサギは亡き父と再会し、言葉を交わすことで、長く心に残っていた傷がひとつ癒えていく。こうしてアリスとウサギは再び現実へと帰還し、そこでふたりは生まれてくる子どもの名を語り合う――“名は運命に触れる”というシリーズを貫く比喩が、静かに優しく回収される場面である。
再会のモンタージュ――チームの「その後」と最終カット
現実に戻った後、クイナ、平屋、アグニ、ニラギ、チシヤら、おなじみの仲間たちの“今”が短いシーンで映し出され、「生は続く」というメッセージが静かに刻まれる(互いに直接の関わりはなく、それぞれの日常として描かれる)。物語はひとまずハッピーエンド寸前で幕を閉じる。
しかし直後、世界規模で地震が多発しているというニュースが流れ、舞台はロサンゼルスのバーへ。そこで映し出されるのは、顔の見えないウェイトレスの胸につけられた名札――そこには“ALICE”の文字が…。そして物語は幕を下ろす。
今際の国のアリス(シーズン3)6話(最終回)の感想&考察
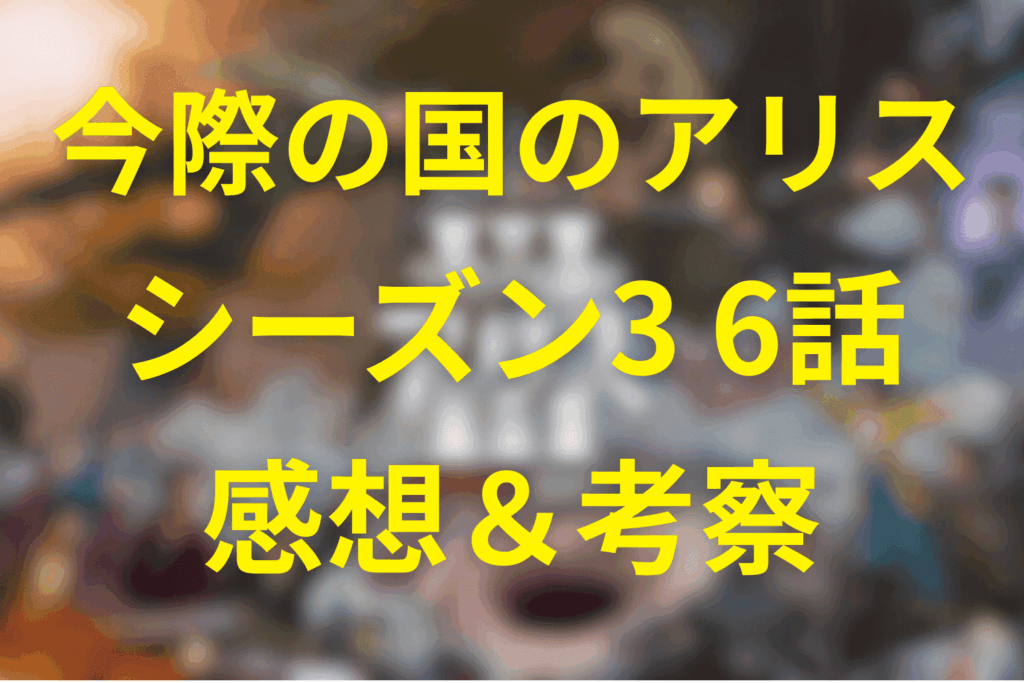
最終回を見終えた直後にまず浮かんだのは、「これは“勝敗”の物語ではなく“選択”の物語だった」という感触です。
プレイヤーが生き延びるための最適解を計算することと、“他者と未来を共有するための解”を引き受けることは、似て非なる行為。
6話はその差分を、ゲーム設計・演出・人物の決断を重ねて論理的に可視化しました。以下、あらすじ&ネタバレ(ご提供テキスト)を踏まえたうえでじっくり掘り下げていきます。
「残る」とは何か──“自己犠牲”ではなく“責任の引き受け”という解釈
“7”の出目でアリスが残る。ここは一見、定石どおりのヒーロー的自己犠牲に見えますが、6話が用意した論理はもう一段階深い。
なぜならこの局面は、「8人全員が最短距離で帰る手は存在しない」という構造の行き止まりが先行しているからです。
つまり彼が取ったのは「誰かが不在になることを前提に、他者の“生活”を先に成立させる」選択。犠牲というより、“コストの引き受け先を自分に固定する”という意思決定でした。ウサギを押し出す所作は、“残る者”が“行く者”に未来を与える交換行動であり、シリーズが繰り返し描いてきた「誰かと生きることの難しさ」を最もミニマムな形で結晶化しています。
ミライすごろくのルール設計が語るテーマ性:点数=“生の余白”、サイコロ=“運”、バンド=“存在の定義”
今回のゲームは、点数(リソース)・サイコロ(運)・通過可能人数(他者の余地)・リストバンド(存在認識)という4要素で構成されます。
特に面白いのは胎児用バンドの導入で、ここにより「個体数」と「存在の重み」が切り離されず、実用上は“二人分の制約”として立ち上がります。
結果、最適解の更新は常に“誰と行くか”に依存する。これは「正解は盤面上の一点にある」のではなく、“関係の配置”が正解を生成することを示すデザインです。さらに「バンドが部屋内にある=在ると認識される」という仕様は、存在が“肉体”ではなく“関係の位置”で定義されるという、このシリーズらしい哲学を露わにしました。
未来ビジョンは“誘惑”であり“抑止”でもある──先取り幸福が生む資源の誤配分
各部屋のビジョン=未来の断片は、単なるデバフではなく、人間の合理を壊す“甘いノイズ”として機能します。
「今ここで点を投じれば、先に幸福が手に入る」という短期志向にプレイヤーを誘導し、現在の資本(点数)の適正配分を狂わせる。結果的に、“生存合理”と“幸福追求合理”の衝突がゲーム内で可視化されるのです。
ここでアリスの役割は、“幸福の先取り”を遅延させるナビゲーションに変わる。進むよりも“いったん踏みとどまる”という非直感的な判断を、関係のために選ばせるのが彼の強みであり、6話の彼はその最適化を見事に遂行します。
“7”の出目が孕む象徴:余剰と不足、そして“残余の倫理”
8人に対して“7”という数字が突き付けるのは、“1の不足”という残酷な算数です。
最短経路の“完全性”は崩れ、“残余”が必ず発生する。ここで試されるのは、残余を偶然の犠牲に委ねるのか、責任ある選択として引き受けるのか。
アリスは後者を選んだ。だからこの場面は、悲劇ではなく倫理の成立として記憶されるべきです。彼が“残り”を選ぶ瞬間、ゲームはゼロサムから非ゼロサムに転化する。扉の向こうに渡るのは勝者ではなく、「生活を始める権利を得た者たち」であり、その地平をつくるのが残った者の役目だ、と。
リュウジの“手放す”決断:救済は奪うことではなく、離すことでも起こる
ウサギを“死”へ引こうとした手を、リュウジは最後に離す。
ここにあるのは、支配と救済の境界です。彼は“自分が救う”という自己目的化した執着から脱し、“救いは自分の手の中にはない”ことを認めた。
これはキャラアークとして非常に腑に落ちる結末で、贖罪とは能動的な善行の積み上げではなく、“力の返上”という消極的選択でも成立し得るという提示になっています。結果として彼の死は、加害の連鎖を断ち切る止血になり、6話は彼に“美化されない終わり方”を与えました。
バンダ=制度の擬人化、その崩落を示す“一条のレーザー”
バンダが銃口を向け、上位からのレーザーで消される。ここは痛快さと同時に、ボーダーランドの統治論を映すキーフレームです。
すなわち市民の資格を付与している上位規約が、制度逸脱を検知した瞬間に“資格”を剥奪する。悪の退場劇というより、制度の自己防衛ロジックが働いたショット。
これにより、バンダ個人の物語は“悪の最期”に矮小化されず、「制度は人を救わない」というシリーズの冷徹なメッセージが際立ちました。アリスが拒絶したのは支配者バンダではなく、“市民”という形式の束縛そのものだったと読めます。
後にバンダが番人であったのなら、人の選択の自由を拒否してはいけないというルールに抵触したということが考えられる。
〈時間停止〉と“番人”:ジョーカーは“人物”ではなく“機能”である
“番人”の提示する二枚のカード。どちらもジョーカーであることにアリスが気づくくだりは、「この世界は“余白”で継ぎ足されている」というメタな宣言です。
365(平年)と366(閏年)の比喩は、世界が数理的完結ではなく調整で回っていることの象徴。つまりジョーカーは“誰か”の正体探しではなく、欠けたものをつなぐ“役割”としての実体を持つ。
ここで“番人”がジョーカー本人ではないと名乗るのも合理的で、管理と変動は別プロセスという分離が世界観の安定を確保しています。「生か死か」を選ばせるだけの“見守る者”という姿勢も、自由の最小単位=選択の保全を任務とするなら理にかなっています。
“生を選ぶ”をドラマとして成立させる演出:静寂→奔流→再静寂の呼吸
アリスが“生”を選ぶ刹那、演出は音と運動の落差で身体的な説得力を生みました。
いったん凍った時間が再起動し、濁流のノイズが一気に押し寄せる。その直後、リュウジが手を放す“無音に近い瞬間”を挟み、ウサギの救出へ。加速(濁流)と間(静寂)を交互に撃つことで、「選んだ結果が外界の物理に波及する」体感が獲得されます。
さらに、現実での杏との対峙を差し込む編集によって、“選択の影響範囲が複数レイヤーにまたがる”ことを直感させてくる。ここは純粋に映像の呼吸が上手いと感じました。
“再会のモンタージュ”が示すもの:関係の証明は“私的な日常”に残る
クイナ、平屋、アグニ、ニラギ、チシヤ――それぞれの“今”が短く映るモンタージュは、劇的な再会や大団円の集合写真を意図的に避けます。むしろ、各人が“別々の場所で”生活に回帰しているという提示。
これは「絆=いつも一緒にいること」ではなく、“同じ痛みの言語を共有していること”としての定義に寄り添っています。だからこそ、“世界規模の地震”のニュースと“LAのALICE”という含みが、彼らの現在を軽々と上書きしない。
最終カットがもたらすのは続編の煽りというより、境界が世界の別相へ広がるかもしれないという、静かな波紋です。
「制度」と「物語」の距離:支配の正統性はどこから来るのか
“市民”の制度は、参加者の死生に正当性を与えるフレームでした。
しかし、最終回はその正統性が循環参照(制度が制度を正当化)でしかないことを露呈します。バンダの剥奪は、支配原理が“上位規約”の気まぐれに依存することを示してしまった。
だからこそ、アリスの拒絶は政治闘争ではなく、制度信仰からの離脱に近い。6話は「支配の正義」より先に、“誰が誰の未来に責任を取るか”という倫理を置いた。ここにシリーズの矜持を感じます。
〈現実レイヤー〉の挿入効果:杏の行為が補完する“生の側”のリアリティ
現実世界で杏がバンダの引き込みを阻止するくだりは、今際の国の選択が“どこに響いているのか”を説明する要のシーンです。ここを挿むことで、視聴者は選択の外部性(第三者の介入)を認識できる。
つまり、アリスが“生を選ぶ”とき、それは“個の決断”に見えて、周囲の関係の網に支えられた行為だということ。この補助線があるから、最終盤の“生活への軟着陸”が空虚にならないのだと思います。
物語の“出口”は二重に設計されている:私的エンディングと公的不穏
1つ目の出口は、“二人の生活”に収束する私的な終わり(名を選ぶ)。
2つ目の出口は、地震と“LAのALICE”が示す世界的な不穏。
この二重構造により、視聴後に「終わった満足」と「終わっていないざわめき」が同居します。シリーズとしての持続可能性を保ちつつ、今季単体の満足点を越えない絶妙な塩梅。個人的には、ここで物語を“開きっぱなし”にしない抑制(名を語る私的な終止符)を置いたのが、たいへん好みでした。
シリーズ全体から見た6話の位置づけ:サバイバルから“生活設計”へ
シーズン1は「生き延びるための合理」、シーズン2は「支配/反支配の政治性」、そしてシーズン3は「生活を選ぶための倫理」へ。
最終回はこの移行を、ゲームで殴り、概念で包むという二段構えで完遂しました。結果、シリーズが蓄えてきた“血と汗のリアリティ”が、生活の手触りへと無理なく接続される。終わり方として、とても強いです。
SNSでの賛否をどう読み解くか:尺・ラブライン・続編示唆
「もっとゲームを見たかった」「ラブラインのウェイトが重い」といった声は当然出ると思います。ただ、6話は“ゲームの量”で押す話数構成ではなく、“意味の密度”で押す最終話だった。ウサギの胎児バンドという設定は、ラブラインの情緒を超えてルール設計の中核になっており、ここをラブの過剰と解するのは、少しもったいない。
続編示唆に関しては、商業的な布石以上に世界観の論理から出てくる含みとして、今回はきれいに機能していたと感じます。
“穴”はなかったか?あえて粗を探すなら
強いて言えば、バンダの思想の厚みはもう一段欲しかった。
彼の論理(なぜ市民にしたいのか、そこにどの程度の“救い”の自己正当化があるのか)を、もう一押し掘る余白があれば、レーザーでの退場が“物語上の必然”から“思想の破綻”へと重みを増した可能性はある。
とはいえ、最終回の時間配分の中で、番人とジョーカーの開示に尺を振った判断は妥当。全体のバランスとしてはほぼ最適だと僕は考えます。
総評:評価軸を“勝つ”から“帰る”に切り替えたことの価値
最後にまとめます。6話は、ゲームの勝利より“帰還後に生活が続くかどうか”に評価軸を切り替えた最終回でした。アリスがやったのは、他者の未来のために自分を“残余”に置くこと。ウサギがやったのは、残された未来を“名前”で世界へ接続すること。番人が提供したのは、選ぶ自由の最後の保証。そして制度は崩れ、支配の正統性というフィクションが剥がれ落ちた。
結論として、僕はこの最終回を高く評価します。ルールは意味を運び、演出は倫理を映し、キャラクターは“押す/覆う/放す”という身体動作で核心を語る。“勝つより、帰るのが難しい”。その当たり前の真理を、ここまでドラマティックに、かつ論理的に描き切った快作でした。
今際の国のアリス(シーズン3)の関連記事
全話まとめた記事はこちら↓
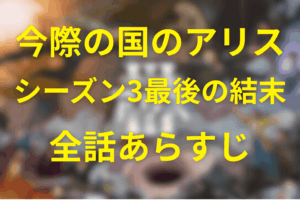
1のネタバレはこちら↓
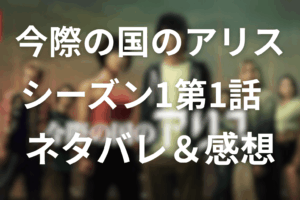
シーズン2のネタバレはこちら↓
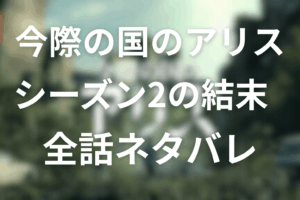
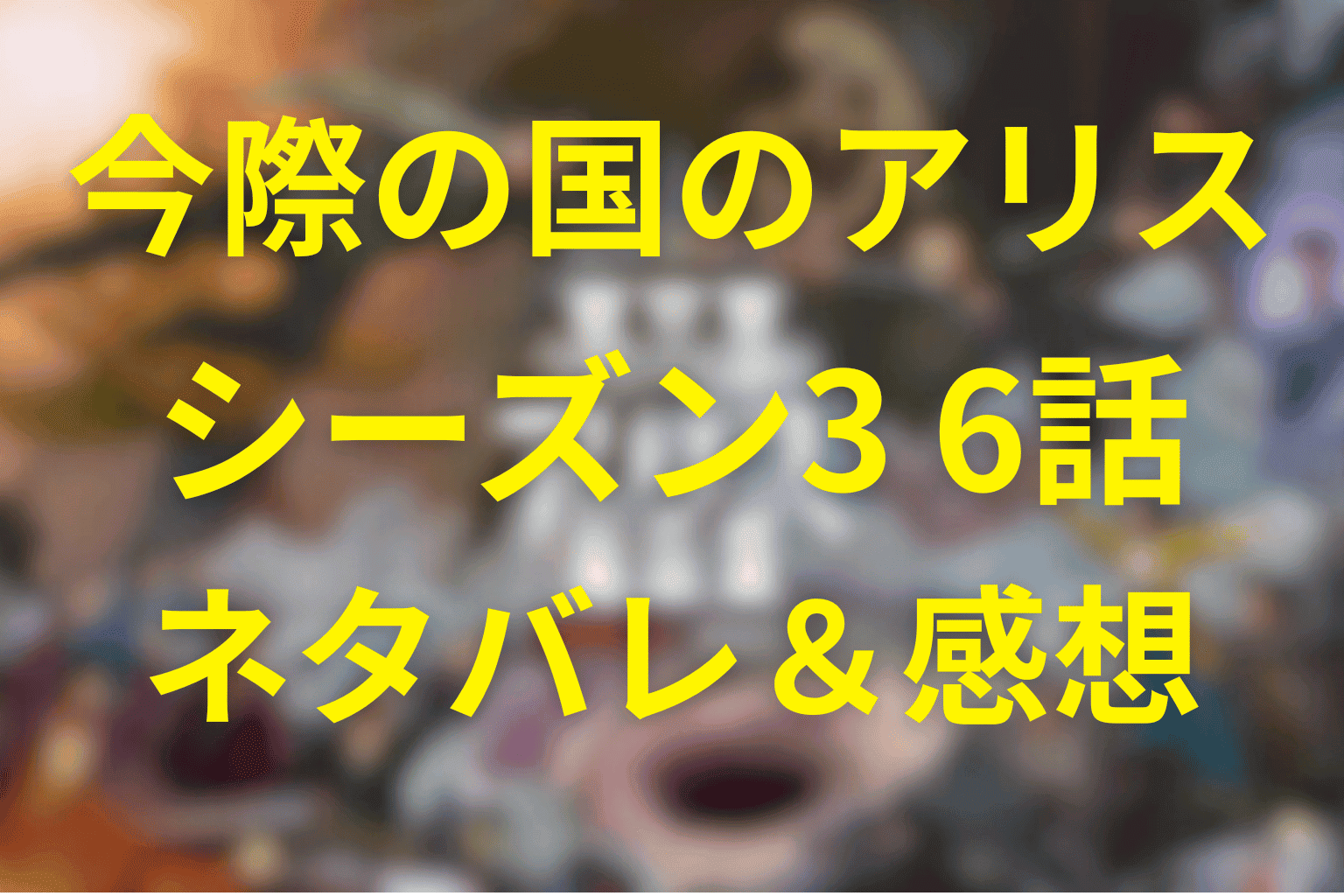
コメント