第6話は、失踪した“マチルダ”の捜索が『ランボー』という謎の男にフォーカスして一気に加速する回です。肇の妄想が作る「不審者像」から始まり、鶴見の記録、1988年の名簿、そして妹の証言が積み上がるほど、ランボーの見え方が反転していきます。
名簿で浮かぶ“同じアパート”の一致、病院での雄太の父による口止め、元夫から逃げていた可能性――。
失踪は「誰かに消された」だけでは説明できない形へ広がり、守りと隠蔽の境界が曖昧になっていく。ラストは真実の入口に触れながら、決定的な背中を見失う不穏さで締まります。
※この記事は、ドラマ「ラムネモンキー」第6話のネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
ドラマ「ラムネモンキー」6話のあらすじ&ネタバレ

第6話は、失踪した“マチルダ”をめぐる捜索が『ランボー』という謎の男にフォーカスして加速する回だ。
怪しさ全開の存在だったはずが、調べるほどに見え方が変わっていく。
名簿と証言がそろったことで、マチルダの失踪は『単なる被害』ではなく、誰かの保護や口止めが絡む事件として立ち上がってきた。
そしてラスト、4人は“真実の入口”に触れながらも、決定的な背中を見失う。
肇の“妄想”から始まる第6話:ランボーは犯人なのか?
第6話の幕開けは、肇の妄想が暴走して『ランボー=不審者』に決め打ちするところから始まる。
この作品らしく、現実よりも先に“疑いの結論”を見せて、視聴者を一度ミスリードに連れていく。
妄想パートでは、かつての映画研究部が忍び込んだ化学工場の記憶がフラッシュバックし、映像の隅に映る“見知らぬ男”の存在感が増幅される。
「怪しい」「怖い」「何かを隠している」――その空気だけが先行し、ランボーがマチルダ失踪と直結するように見える。
ただ、今回も妄想はあくまで入口で、後半に向かって『疑う理由』が『守る理由』へ塗り替わっていく。
“思い込み→検証→反転”の流れがあるからこそ、回ごとの情報がちゃんと積み上がっていく。
そして今話のキーマンは、雄太(ユン)・肇(チェン)・紀介(キンポー)の3人だけじゃない。
白馬と鶴見が「観測者」と「公式情報」の役割を担い始めて、素人の追跡が“事件の形”を帯びてくるのが第6話だ。
生活のために引き受けた“自伝映画”の仕事:肇の現実パート
肇には、小野寺さつきから“自伝映画”という小さな仕事が舞い込む。
建設会社の会長・石渡秀信がポケットマネーで制作する作品で、規模は小さくても「仕事として成立させろ」という圧は重い。
かつて映画に夢中だった肇が、今は「生活のために撮る」。
この対比が、今作のテーマである“青春の回収”を一番シビアに映す。好きだったものが、そのまま自分を救うとは限らない。むしろ現実は、好きだったものから自分を引き剥がそうとしてくる。
肇は脚本を書き、現場を回し、最低限のクオリティにまとめるつもりで引き受ける。
ところが、石渡は肇の台本に容赦なく口を出してくる。仕事としての“理屈”があるダメ出しというより、「俺の人生はこうだ」という感情の圧が強い。
ところが石渡は、肇の脚本に容赦なくダメ出しし、『別の脚本でいく』と言い出して肇を振り回す。
肇は反論できる立場じゃないし、反論しても状況は好転しない――そういう“負ける交渉”を飲み込む場面が、妙にリアルだ。
ここで肇は、青春の謎を追うことが「遊び」ではなく、今の自分にとっては「逃げ場」でもあると気づいていく。仕事で心が削られるほど、過去の映像にすがりたくなる。その感情が、のちの“ランボー調査”の執念に繋がっていく。
古いビデオに映る“怪しげな男”――ランボーの記憶が蘇る
中学時代の映像を見返す中で、肇はビデオの片隅に映る“怪しげな男”を思い出す。
彼らが当時「ランボー」と呼んでいた人物で、画面の端にいるだけなのに、なぜか目が離せない。
白馬が働く「ガンダーラ珈琲」で、雄太・肇・紀介はその記憶を持ち寄る。
3人の語りが面白いのは、“同じ出来事”でも解釈がズレているところだ。雄太は直感で危険を嗅ぎ、肇は映像の痕跡で確かめ、紀介は違和感を言語化する。役割分担が自然にできている。
そして話の中で浮上するのが、「ランボーは町のトラブルに現れる」という奇妙な噂。
誰かが呼んだわけでもないのに、争いが起きるとそこにいる。しかも、説教もしない、笑いもしない、ただ“鎮める”。
ランボーは、町でトラブルが起きると現れては、ほとんど無言で場を鎮める得体の知れない存在として語られる。
それが“正義”なのか“脅し”なのか判断がつかないからこそ、マチルダ失踪と結びつけたくなるのも無理はない。
「怪しい男がいた」だけなら、記憶のノイズで終わる。
でも、町のあちこちで“介入していた”となると、話は変わる。ランボーは目撃される位置に、意図的に立っていた可能性が出てくる。
中学時代の化学工場潜入:ランボーとの遭遇と“脱臼の処置”
回想では、映画研究部の3人がロケ地探しで化学工場に忍び込み、そこでランボーと鉢合わせる。
子どもらしい無鉄砲さと、見つかった瞬間の「詰んだ感」が、画面から伝わってくる。
工場という場所がまた良い。
広い敷地、死角、機械の音、薄暗さ。大人が本気で追ってきたら子どもが逃げ切れるはずがない空間で、ランボーは“突然”現れる。
3人は逃げる。肇は焦る。足がもつれる。転ぶ。
そして肩を痛め、動けなくなる。ここから先は、恐怖の描写が一気に生々しくなる。痛みは嘘をつかないからだ。
ランボーは追い詰めるだけでなく、脱臼した肇の肩を手際よく処置し、『先生を連れて来い』と一喝する。
この行動が、ランボーを単純な悪役にできなくする。怖いのに、助けている。乱暴なのに、医療的に正しい。
“助けた”という一点だけを取れば善人に見える。
でも、“助け方”が乱暴で、支配的で、相手に選択肢を与えない。ここに、後の「守っていたのか?」という論点が自然に繋がってくる。
当時の3人にとって、ランボーは「理解できない大人」だった。
だからこそ今、50を越えた彼らがランボーを追うのは、“事件の解決”と同時に“理解できなかった過去”を回収する作業にもなっている。
鶴見巡査が動く:ランボー調査の糸口をもたらす
これまで面倒くさがっていた鶴見巡査が、第6話では少しずつ4人に協力的になる。
「また来たよ…」という顔はしながらも、突き放し切れない距離に入ってきたのが大きい。
鶴見がもたらす情報は、噂や記憶ではない。
“記録”に基づく事実だ。だから、3人がいくら妄想で走っても、最後に現実へ着地できる。
ランボーについて調べる中で出てくるのが、傷害事件の過去。
しかも相手は、町に竿竹を売りに車で来ていた人物――鳥飼久雄だと判明する。
ランボーが傷害事件を起こした相手が、町に竿竹を売りに来ていた鳥飼久雄だと判明し、過去の回想で何度も映っていた“竿竹屋”が一気に意味を持つ。
背景にしか見えなかった存在が、事件の中心へ引っ張り上げられる感覚がある。
竿竹屋という“外から来る商売”は、町に違和感を持ち込む装置でもある。
地元の人間は見慣れているからスルーする。でも外から来る人間は、目撃されやすいし、噂も立つ。ここが後の「誰が何を見たのか」を揺さぶるポイントになりそうだ。
鶴見が協力することで、捜索チームは“やってることが捜査っぽく”なる。
ただし、彼らは警察じゃない。踏み込める範囲は限られる。だからこそ、次のパートで「名簿」というログが効いてくる。
1988年の工場関係者と名簿:ランボーの実在と“思わぬ一致”
3人は1988年にランボーと一緒に工場で働いていた人物に辿り着き、当時の名簿を見せてもらう。
ここが第6話の“地味だけど決定的”な場面で、情報が一段現実になる。
昔の事件って、記憶に頼るとブレる。
でも名簿はブレない。少なくとも「その時、その場所に、その人がいた」という一点は固められる。ドラマの考察に必要なのは、この“固め”だ。
名簿を手にした紀介が気づくのは、ランボーだけじゃない。
住所欄に、マチルダ(宮下未散)の名前と接点が浮かび上がる。
その名簿から見えてきたのは、ランボーとマチルダの間に“思わぬ共通点”があったこと—同じアパートの住人だったという事実である。
これが偶然なら怖すぎるし、必然ならもっと怖い。
同じアパートというのは、単なる距離の近さじゃない。
生活圏が重なる、目が届く、監視もできる、助けにも入れる。守るにも追うにも、成立しやすいポジションだ。
ここで3人の中に、ランボー像の揺れが生まれる。
「犯人だから近いのか」
「守りたいから近いのか」
同じ事実が、真逆の結論に繋がる地点に来た。
ランボーの妹が語る過去:血まみれの帰宅、病院、口止め
さらに調査を進めた一行はランボーの妹を見つけ出し、ついに家族側の証言に辿り着く。
名簿が“客観”、妹の証言が“感情”。この2つが揃うと、事件は単なる謎解きじゃなく、人生の傷として見えてくる。
妹が語るのは、子ども時代の衝撃だ。
ランボーが血まみれで帰ってきた。家族は驚き、トラックで病院へ運んだ。家の中が一瞬で“非常事態”に変わる。そういう夜は、子どもの記憶に一生残る。
さらにその病院で、思いもよらない人物が現れる。
雄太の父と、マチルダがそこにいたのだ。家族の事情とは別の事情が、すでにあの夜に絡んでいたことになる。
そして父は言う。黙っていてくれ、と。
口止めは“守り”にも“隠蔽”にもなるから、この一言が重い。
病院に現れた雄太の父が『このことは黙っていてくれ』と口止めしたことで、マチルダの失踪事件が“雄太の家”とも地続きである可能性が浮上する。
青春の謎が、家庭の謎に繋がった瞬間だ。
ここから先は、父が何者なのかで見え方が変わる。
善意の口止めなら「守るための嘘」。
利害の口止めなら「隠すための嘘」。
どちらに転ぶかで、雄太が抱えてきた“人生の迷子感”にも意味が乗ってくる。
ランボーはマチルダを守っていた?元夫から逃げた女の“その後”
妹の話から、ランボーとマチルダの父親が戦友だったことが明かされ、ランボー像が一気に反転する。
最初に植え付けられた「不審者」の印象が、今度は「見守り役」へ置き換わっていく。
戦友の娘を守る。
それは、責任や義理としては筋が通る。でも現代の法や倫理に照らすと、暴力や監視に踏み込みやすい危険な正義でもある。ランボーは、そのギリギリの場所に立っている。
さらに、マチルダの過去もここで更新される。
一度結婚し、離婚し、その後に美術教師になった。ここだけでも人生の大きな転換だが、問題はその“離婚の後”にある。
どうやら、元夫から逃げていたらしい。
つまりマチルダは、静かに暮らしたいのに、静かにさせてもらえない状態だった可能性が高い。
マチルダは一度結婚し離婚してから美術教師になっており、どうやら元夫から逃げていたらしいという情報が、失踪の動機を“外側”に広げた。
失踪は事件だけで起きるわけじゃない。逃げるという選択でも起きる。
ここで、失踪の見取り図が変わる。
「誰かに消された」だけじゃなく、「誰かから逃げた」「誰かに守られた」「誰かに口止めされた」――複数の矢印が同時に走り始める。
ランボーが守っていたなら、守り切れなかった理由があるはずだ。
守り切れなかったのか、守った結果として“消える選択”をさせたのか。第6話はそこまで答えないが、問いは確実に強くなった。
真実の入口で見えた“怪しい人影”――追跡と見失い
鶴見から鳥飼久雄の線を聞き、4人が情報を整理している最中、町で怪しい人影を見つけて追跡に出る。
名簿と証言で頭が回り始めた直後に、“体を動かす局面”が来るのがうまい。
追いかける側は、雄太・肇・紀介・白馬。
全員がプロじゃない。だから走り方も、判断も、どこか危なっかしい。けれどこの危なっかしさが、「事件の怖さ」を逆に増幅させる。
人影は逃げる。
追う。
曲がる。
見失う。
この一連の流れが、“町のどこかに確実に誰かがいる”という感覚を残す。
結局その影は見失われ、手がかりだけを残して逃げたことで、4人は『真実の入り口に辿り着いた』という手応えと同時に新しい不安を抱える。
追跡の失敗は、情報の不足じゃなく、相手が一枚上だった証拠でもある。
第6話は、ランボーの正体を追う回であり、同時に“別の誰か”の輪郭が出る回でもあった。
守り手がいて、追跡者がいて、口止めする大人がいて、逃げた女がいる。いよいよ事件は、青春の思い出だけでは語れない場所まで来ている。
ドラマ「ラムネモンキー」6話の伏線

第6話の最大の収穫は、『ランボー=加害者』という見立てが崩れ、事件の矢印が“別の追跡者”へ向き始めたことだ。
ここでは、作中で提示された情報を伏線として整理していく。
特に重要なのは①雄太の父の口止め、②マチルダの元夫、③竿竹屋(鳥飼久雄)ライン、④怪しい人影の4本線である。
どれも単体では弱いが、繋がると“失踪の構図”が見えてくる。
“ランボー=犯人”のミスリードと反転(守る側の存在)
第6話は、序盤でランボーを犯人候補に見せながら、後半で“守る側”にひっくり返した。
この反転は、今後も「疑い→検証→逆転」が起きる作劇の宣言でもある。
重要なのは、ランボーが“善人”になったわけじゃない点だ。
守るために暴力を使う人間は、味方になった瞬間に安心できるタイプではない。むしろ、情報を握るほど危険になる。
ランボーが『無言でトラブルを鎮める』描写は、町の裏事情を知る“調停役”である伏線にも見える。
調停役は、争いの原因にも結果にも接続していることが多い。
ランボーが何を知っているのか。
そして、何を知らないふりをしているのか。守り手の沈黙は、次の爆弾になりやすい。
雄太の父が口止めした理由:病院シーンが示す隠蔽ライン
血まみれのランボーを病院に運んだ夜に、雄太の父が口止めした事実は、事件の中心に“身内の秘密”がある可能性を上げた。
父が善意で動いていたとしても、「黙れ」は状況を歪める。
なぜ父は病院にいたのか。
なぜマチルダもいたのか。
この2点だけで、父とマチルダが“偶然の知り合い”ではない可能性が濃くなる。
もし父が当時から町の治安側にいたなら、口止めは“正義のための隠蔽”にも“個人的な保護”にも転ぶ。
どちらにせよ、父の口止めは「誰かを守る行為」であり、「誰かを追い詰める行為」でもある。
この作品は“守る”が美談になりきらない。
だから父の口止めは、後で必ず代償として戻ってくるはずだ。
マチルダの元夫=追ってくる存在の伏線(失踪は自発か強制か)
マチルダが離婚後に教師になり、元夫から逃げていたらしいという情報は、失踪が“被害”ではなく“逃亡”の線を強める。
逃亡が成立するなら、マチルダは能動的に動いていたことになる。
逃げる人は、情報を切る。
連絡先、住所、勤務先、交友関係。切れるものから切っていく。だからこそ、名簿の“同アパート”という一致は、逃亡前の生活圏を特定するヒントとして効いてくる。
元夫が本当に追っていたなら、失踪の前後で『住居』『職場』『交友関係』が切り替わっているはずで、名簿の一致(同アパート)がその切替点になり得る。
逃亡は、過去の生活を“畳む作業”でもある。
元夫が誰で、どれだけ暴力的なのか。
ここが見えた瞬間、失踪の重さが一段変わる。
竿竹屋・鳥飼久雄ライン:町の暴力装置が本線へ入ってきた
鶴見が持ち込んだ『ランボーの傷害相手=竿竹屋(鳥飼久雄)』は、町の事件が“外部から来る暴力”と繋がっていたサインだ。
回想で何度も出ていた“竿竹屋”が、背景から容疑へスライドした。
竿竹屋は移動する。
移動する人間は、目撃される。
目撃は証拠になる一方で、噂にもなる。噂は改ざんされやすい。つまり、竿竹屋は“情報の拡散装置”になり得る。
“竿竹を売るトラック”は、人の出入りと目撃情報を作りやすい装置で、失踪当日のアリバイ工作に使える伏線でもある。
町の人の記憶が、誰かの都合で組み立てられていたら厄介だ。
鳥飼が「何を見たか」ではなく、「何を見たことにされたか」。
この視点が必要になってきそうだ。
怪しい人影と“真実の入口”:監視者は誰か、なぜ姿を見せたのか
ラストで4人が見た怪しい人影は、『こちらを見ていた誰かがいる』という監視線の提示だ。
追う側が、追われる側にもなる瞬間は、物語の温度が一段上がる。
ここがポイントで、監視者が“完全に隠れる気”なら、そもそも姿を見せない。
見せた上で逃げたのは、「警告」か「誘導」か「様子見」――いずれにせよ、相手が主導権を握ろうとしている動きに見える。
姿を見せて逃げたということは、犯人が“完全に隠れたい”のではなく、4人を特定の方向へ誘導したい可能性もある。
追うほどに、相手の描いた線の上を走らされる危険が出てくる。
第6話の伏線は、“点が揃った”というより“線が引ける材料が揃った”回だった。
次の一手は、誰がどの線を握っているか――そこになる。
ドラマ「ラムネモンキー」6話の感想&考察

第6話を見終えて一番印象に残るのは、事件の中心が“殺した/殺してない”から“守った/守れなかった”へ移ったことだ。
笑える会話の裏で、守りの暴力と逃亡の現実がじわじわ浮いてくる回だった。
そして、名簿・証言・追跡という“証拠の出どころ”が揃ったことで、考察は妄想ではなく検証フェーズに入ったと僕は感じた。
ここからは確定情報と推測を分けつつ、第6話時点の見立てを置いておく。
第6話は“犯人探し”より“守りの物語”に舵を切った
ランボーがマチルダを守っていた可能性が出た瞬間、物語はサスペンスから“恩と責任”の話に変わった。
守る話は美談にもなるけど、同時に「守るための嘘」「守るための暴力」を正当化しやすい。
ランボーの行動は、確かに危ない。
でも彼が完全な悪に見えないのは、やっていることが“排除”じゃなく“抑止”に寄っているからだと思う。無言で鎮める、というのは相手に理屈を渡さない行為で、怖いけれど、目的が「黙らせる」以上に「被害を止める」に見える。
もしランボーが守り手なら、彼は“真犯人を知っている”というより、“真犯人が何者かを知り得る立場”にいるだけで十分怖い。
守る側は、情報を抱えた瞬間に狙われるし、守り切れなかった時に“共犯”扱いされる危険もある。
つまりランボーは、犯人よりも「真実へ近い証人」側の爆弾。
この立ち位置が見えたのが、第6話の一番の収穫だと思う。
情報戦の主導権が動いた:鶴見巡査と白馬のポジション
第6話で鶴見が協力的になったことで、3人の捜索は『根拠のある線』を引けるようになった。
素人の執念は怖いけど、根拠が伴うと一気に強い。逆に言うと、根拠を渡した鶴見ももう無関係ではいられない。
白馬も同じだ。
カフェ店員という距離感のはずが、今や彼女は“情報が集まる場所”そのものになっている。3人が集まる場を提供し、会話を受け止め、時には追跡にも付き合う。彼女がいることで、3人の暴走がギリギリ社会に接続される。
一方で白馬は“追う側”でありながら“追われる側”にもなっていて、彼女の身の危険がそのまま事件のリアルさを底上げしている。
中年3人の軽口が成立するのは、白馬が“現実の怖さ”を背負ってくれるからでもある。
鶴見が事実を渡し、白馬が場を作る。
この2人の存在が、事件を「過去の思い出」から「今の危険」へ引き上げている。
ランボーを「動機/機会/後処理」で見ると、むしろ“証人”側に近い
ランボーがもし“仕掛ける側”だと仮定しても、動機は個人的な怨恨より『守るため』に寄っている。
ここがポイントで、守る動機での犯罪は“正当化”とセットになりやすい。
機会はある。
町のトラブルに現れていたということは、町の時間軸に常に接続しているということだ。マチルダの生活圏にも近い。名簿で同じアパートが出たなら、尚更だ。
ただ、後処理が弱い。
本気で隠す犯人なら、そもそも“町のトラブルを鎮める”なんて目立つことをやらないはず。目立つというのは、疑われるリスクを背負う行為だから。
動機/機会/後処理のうち、ランボーは“機会”だけは揃っているが、“後処理”を徹底するタイプには見えないのがポイントだ。
だから僕は、ランボーを「犯人」より「守り手(=事情を知る側)」として見た方が筋が通ると思っている。
守り手は守り手で、真実を言えない。
言った瞬間、守っていた相手も、自分も、終わるから。第6話のランボーは、そういう“言えない立場”の匂いが強かった。
マチルダは「逃げた」のか「消された」のか:元夫・町・組織の三角形
元夫から逃げていた線が本当なら、マチルダの失踪は“能動的な消失”として成立する。
逃げるなら、偽名・引っ越し・仕事の変更はセットで起きる。マチルダの人生の転換(結婚→離婚→教師)がそこに接続してくる。
ただ、物語には白骨がある。
これが“本人”だとしたら、逃亡は成立しない。逆に、本人ではないなら、誰かが“マチルダの死”を演出したことになる。ここが一気に危険だ。
一方で白骨が見つかっている以上、『誰かが別の遺体をマチルダに見せかけた』可能性も残り、逃亡と他殺は同時に走る。
逃げたマチルダと、死んだマチルダ――二つの物語が並走し得るのが、この作品の恐さだと思う。
元夫が追い、町の暴力が絡み、そして“ジュピターの家”のような大人のネットワークが臭う。
これが三角形で噛み合った瞬間、青春ミステリーは一気に社会派になる。
次回に向けて残る問い:竿竹屋、雄太の父、そして“見ていたはず”の人物
次回以降で一番効いてくるのは、竿竹屋・鳥飼久雄が“何を見て、誰を運んだのか”という目撃の線だ。
トラックで来る人間は、移動の自由度が高い。だから事件の当日に“運ぶ”ことも“目撃を作る”こともやりやすい。
もう一つが、雄太の父の口止めの意味。
口止めが「家族を守る嘘」なら、雄太が抱える裁判や人生の迷子感とリンクしていく。
口止めが「町の秩序を守る嘘」なら、町ぐるみの構図が見えてくる。
そして、雄太の父の口止めが“家族を守る嘘”だったのか“町の秩序を守る嘘”だったのかで、物語の着地点がまるごと変わる。
第6話は、その分岐点がはっきり見えた回だったと思う。
ランボーは守り手になり得る。
マチルダは逃げた可能性がある。
竿竹屋は目撃の中心にいる。
そして誰かが、今も4人を見ている。――第7話は、線が線として繋がる回になりそうだ。
ドラマ「ラムネモンキー」の関連記事
全話ネタバレについてはこちら↓
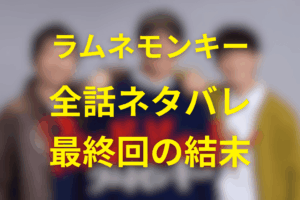
ラムネモンキーの過去の話についてはこちら↓
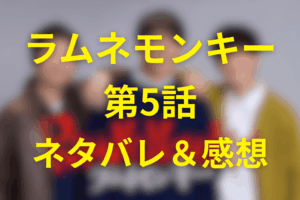
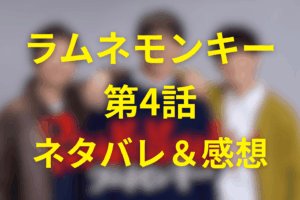
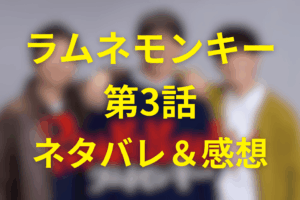
マチルダについてはこちら↓
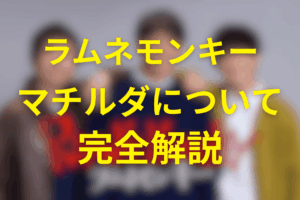
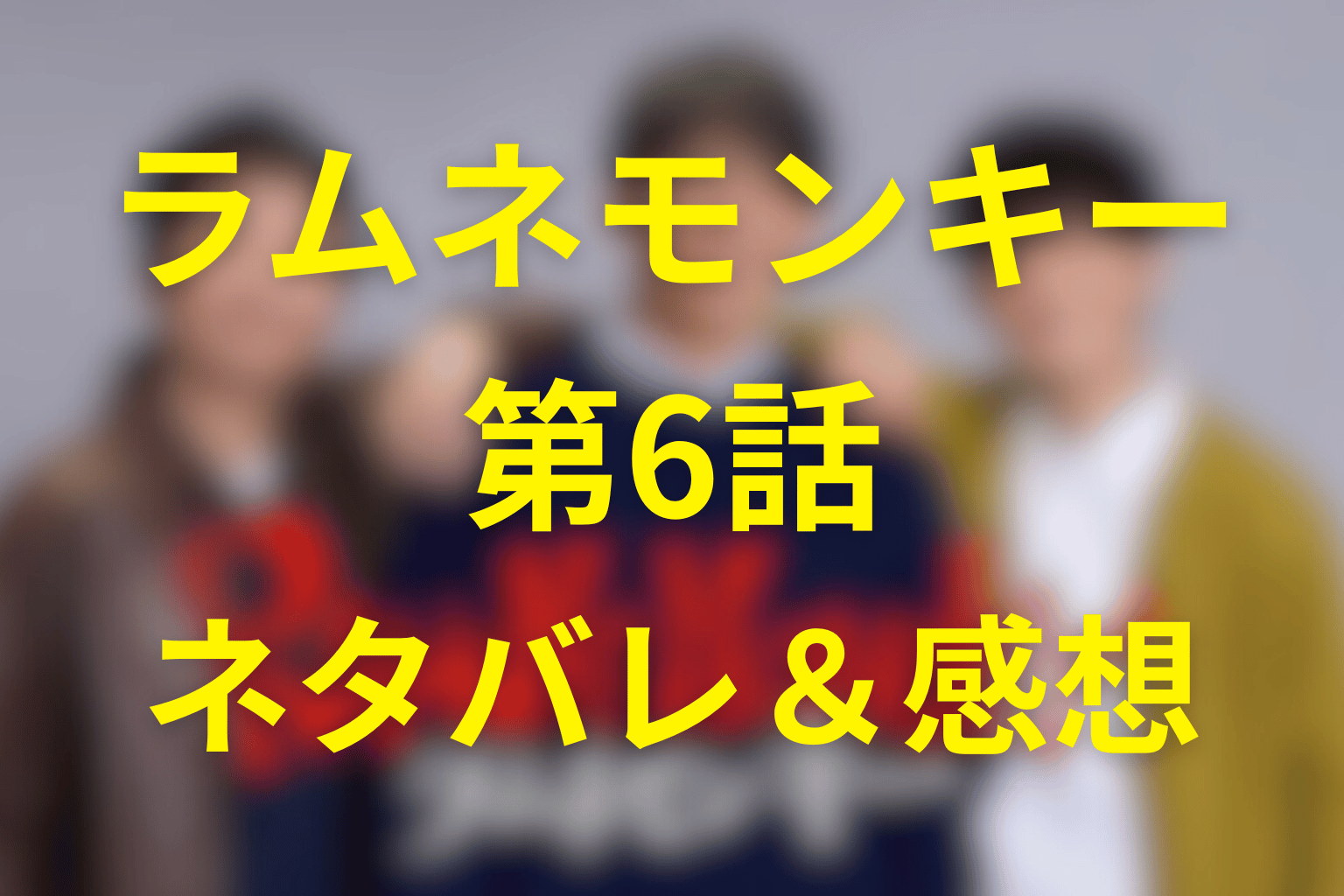
コメント