前話で小さなほころびが見え始めた「たそがれステイツ」。
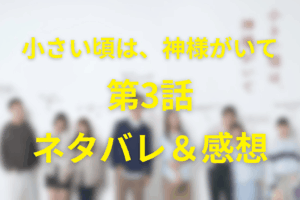
第4話では、その“支え”だった永島夫妻がいない朝から始まる。
渉は慎一の代わりに玄関を掃き、あんはさとこの代わりに屋上で水をまく。
いつもと同じ光景のはずが、どこか空気が違う——支える人がいないだけで、日常の意味が変わっていくのだ。穏やかな朝に見つけた小さな虹は、誰も予想しなかった“喪失”への前触れ。
「育てる」と「別れる」、二つの決断が重なり合うこの回は、シリーズ全体の“深呼吸の瞬間”といえる。
小さい頃は、神様がいて4話のあらすじ&ネタバレ
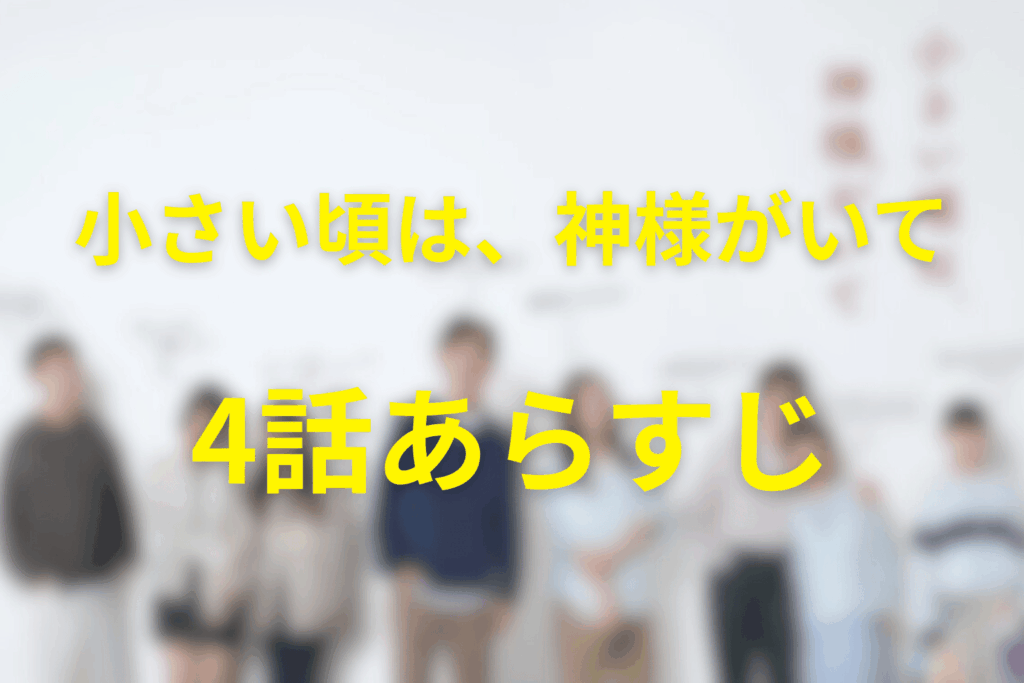
フジの木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、東京郊外のレトロマンション「たそがれステイツ」を舞台に、三家族の“日常の揺れ”をつづるホームコメディ。
小倉渉(北村有起哉)と妻・あん(仲間由紀恵)、娘のゆず(近藤華)、独立した消防士の息子・順(小瀧望)、そして1階には永島慎一(草刈正雄)とさとこ(阿川佐和子)。
2階には樋口奈央(小野花梨)と高村志保(石井杏奈)が暮らすという配置だ。放送は毎週木曜22時。主題歌は松任谷由実の書き下ろし「天までとどけ」。作品の“やわらかい強さ”を支える音楽的な背骨になっている。
永島夫妻の“不在”から始まる静かな朝
第4話は、永島夫妻の“不在”から始まる。慎一とさとこが「緊急事態」で家を留守にし、渉は慎一のルーティンである早朝のラジオ体操の当番を引き受け、あんはさとこから頼まれて屋上の植物に水やりをする。
渉は玄関掃除まで慎一に倣ってこなし、あんは屋上でホースを空へ向け、ふと掛かった小さな虹を見つけて奈央・志保を呼び寄せる——女三人がしばし虹を眺める朝。穏やかで、しかしどこか落ち着かない時間が流れる。
夫婦の距離と“別れ”の予感
家に戻れば、夫婦の“別れ”がにじむ。渉は、わざとらしくも見える“わかってます”の空気をまとい、あんに対して「離婚のことは分かってますよ」とでも言いたげな距離を取る。
あんはその態度にイラつきを募らせる。彼らは娘のゆずに離婚を悟られないよう振る舞うが、ゆずはすでに知っていて、胸の奥にもやが溜まっている。ここまでが、第4話の導入として描かれる家族の空気だ。
言葉がすれ違う車内の会話
やがて、渉とあんは「ゆずに聞かれないように」といつものように車内で話す。
だが、言葉は噛み合わない。渉の“良かれと思って”が、あんにはずっとズレて届いてきたのだ。
ついに渉が「もう離婚するんだから、よくないか?」と零した瞬間、あんの苛立ちは飽和する。にもかかわらず、ふたりの会話は“決壊”に至らず、どこか宙ぶらりんに止まってしまう。そのとき、さとこから一本の電話が入る——。
ゆずと順、子どものまなざし
同じ頃、ゆずは兄・順に「もう知っていることを、親に伝えてもいいか」と相談する。
順は“家族の空気”を読みすぎる性格ゆえに躊躇しつつ、妹の心配を受け止める。子ども側の“成熟し過ぎたまなざし”がにじむ短い場面だ。
永島夫妻の“不在”の理由——明かされる悲報
そして、さとこの電話で“外に出ていた理由”が示される。
第4話は、慎一とさとこの娘夫婦が事故で急逝していた事実を明かす回となった。
二人が「たそがれステイツ」を離れていたのは葬儀などのためであり、孫を永島家で引き取って育てる決断に至ったことも語られる。物語のトーンに“深い影”が落ちる転回点であり、視聴者にも衝撃を与える展開となった。
日常に落ちる影と“支える不在”
物語は“日常の音”を止めない。玄関を掃き、屋上に水をやり、小さな虹を眺めた朝は、夕方には重い知らせを抱える。
永島夫婦の不在が、彼らの“支え”の大きさを逆照射し、渉とあんの夫婦のズレを濃く浮かび上がらせる。
支える人がいないだけで、マンション全体の空気がわずかに傾く——そんな静かな異変が丁寧に描かれている。
離婚までの“残日”と次章への橋渡し
第4話のラストは、言葉にしにくい静けさを残す。親の“離婚カウントダウン”は進む一方で、永島家には“育てる”というまったく別種の重さが降ってきた。
作中で刻まれる離婚までの残日が52日→36日に縮まったことも示され、時間が確実に進んでいることを思い出させる。
新たな章へ——“育てる”と“別れる”の交錯
次回予告では、永島家が迎え入れる孫の名が“凛(和智柚葉)”と“真(山本弓月)”であることが公表されている。
第4話の余韻のまま、物語は“70代の孫育て”という新章へ踏み出していく。渉とあんの離婚問題と、永島家の子育て——“育てる”と“別れる”が一本の線で結ばれる、その最初の音が第4話で鳴ったといえる
小さい頃は、神様がいて4話の感想&考察。
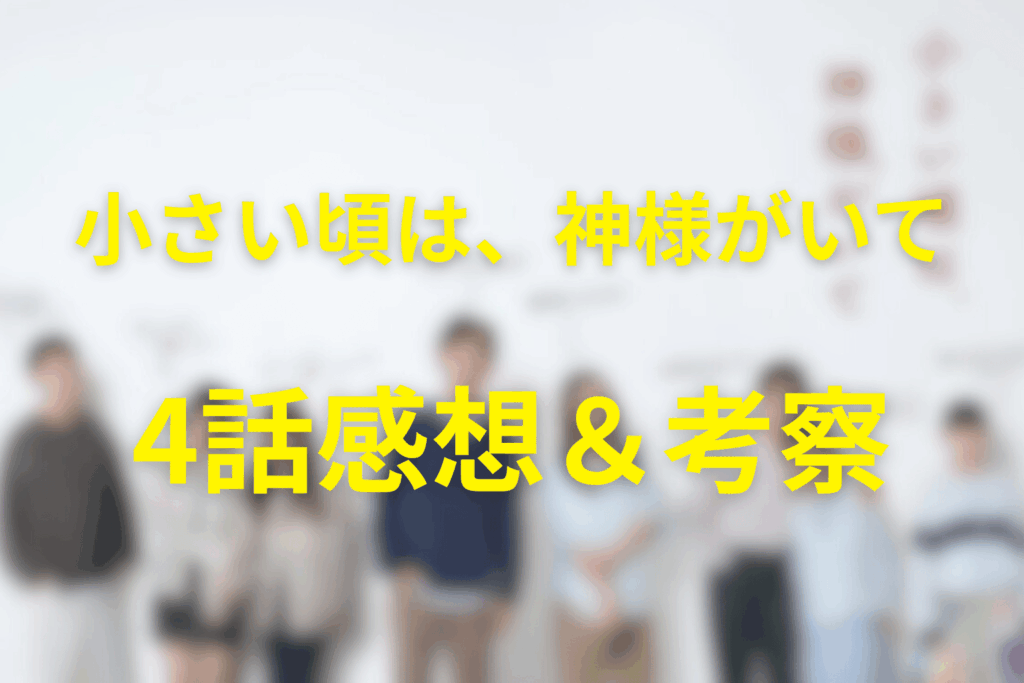
第4話は、シリーズの“呼吸”が一段深くなった回だ。
筆者の要点は三つ。(1)不在が可視化する支え、(2)ズレの連鎖が生む笑いと痛み、(3)“育てる”と“別れる”の同時進行である。以下、順にほどく。
「支える側の不在」で、日常の地盤沈下が見える
慎一とさとこがいない朝——これで初めて、彼らがこの集合住宅の“基礎”だったと分かる。
渉が玄関を掃き、あんが屋上に水をやる。行為は同じでも、空気は違う。支えが抜けると、同じ習慣が“代行”に見えるのだ。
第4話は「やっていることは変わらないのに、意味が変わる」という日常のレイヤーを見せた。
音の少ないショット割りが“空洞”を際立たせ、穏やかな朝にわずかな不安の影を落とす。静けさそのものが、支えの不在を語っていた。
虹のショット——“希望”の演出ではなく“距離”の演出
屋上でホースの水が作る小さな虹。奈央と志保、あんの三人は同じ虹を見上げるのに、心はそれぞれ違う。
同じものを見ているのに、同じ気持ちではない——岡田惠和脚本の真骨頂は、まさにこうした“非同期の共有”にある。
虹を“希望”の象徴にせず、“距離”の可視化として描くさじ加減が巧みだ。あえて感傷に寄せず、淡々と描写することで、作品全体の“品のよさ”を保っている。
会話劇の“ズレ”が笑いと痛みを同時に立ち上げる
渉の「離婚するんだから、よくないか?」は、論理のショートカットだ。
こう(結論)が決まっているのだから、だから(過程)は省略してよい——という発想。しかし、あんが求めているのは“過程そのもの”だ。“わかっている”という態度が、どれだけ相手を置き去りにするか。
このすれ違いは、観ていても笑えるのに痛い。岡田作品が得意とする、ユーモアと哀しみの混在がここでも生きている。感情を爆発させず、静かに互いを傷つけ合う会話劇の完成度が光る。
子ども側の成熟——「守られる」はずの視線が、家族を守る
ゆずが兄・順に「知っていることを伝えていいか」と相談する場面は、子どもが親の感情のクッションになってしまうという、現代的なねじれの描写だった。
親は子を守るつもりで隠しているが、実際には子が親の心を守っている。この逆転を“重く語らない”のが本作の美点だ。ゆずの成熟と、順の距離の取り方に、彼らがどれほど長く“家族の空気”を吸ってきたかが滲む。静かな会話の裏にある思いやりが、切なくも温かい余韻を残した。
“育てる”と“別れる”を同時に抱えるという難題
第4話最大の衝撃は、永島夫妻の娘夫婦の急逝と、70代の孫育てという決断だ。タイトルがユーミンの歌詞「小さい頃は神様がいて」から着想されたと解説されている通り、“生きることは大変だけど、その大変さを軽やかに言葉にする”のがこのドラマの構え。
あまりに重い事実を、涙に沈ませきらず、笑いの粒(渉のしゃっくりなど)で呼吸を確保する。視聴者が“重すぎる”と感じながらも目を離せなかったのは、悲しみを抱えながらも前へ進む“人間の呼吸”を感じ取ったからだろう。
岡田惠和の“やわらかい強さ”——言葉を置きすぎない美学
説明しない。断言しない。けれど、確かに届く。第3話の評で繰り返し語られていた“岡田節”——当事者が自分の気持ちを言い切らない余白が、4話では“別離”と“託児”という二つのテーマを両立させた。
登場人物は誰も“善い人”にも“悪い人”にも固定されない。誤配の多さがそのまま愛しさに変わり、シリーズの推進力になっている。
タイトルと主題歌——“やさしさに包まれたなら”への応答
タイトルの出自と、ユーミンの新曲「天までとどけ」はセットで効いている。“世界は優しく見える瞬間がある”と“でも現実は重たい”の二層。
4話は虹のショットで前者を、電話一本で後者を並置した。ここに、「軽やかさで重さを抱える」という本作の主題がくっきり現れる。
次回予告に映る“凛と真”という名前は、希望の具体であり、未来を照らす灯となる。
次回への予測——“関係の設計”が物語の鍵
“孫を迎える”永島家に、マンションの住人たちはどう関わるのか。渉とあんは、自分たちの別離を進めながらも、他者の子育てを支えることを迫られるだろう。
ゆずは奈央・志保のカップルを撮ることで、“家族のかたち”を別の角度から見直すかもしれない。
他者との関係設計が、自分の家族設計を変える——第4話の余韻から導かれる自然な推測だ。孫の登場が、このマンションの空気をどう変えるか。そこに次話への焦点がある。
「小さい頃は、神様がいて」の関連記事
「小さい頃は、神様がいて」の全話ネタバレはこちら↓
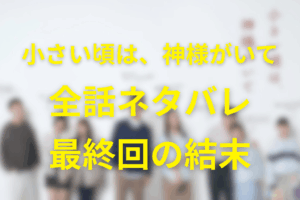
「小さい頃は、神様がいて」の次回以降の話はこちら↓
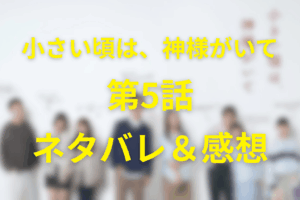

「小さい頃は、神様がいて」の過去の話↓
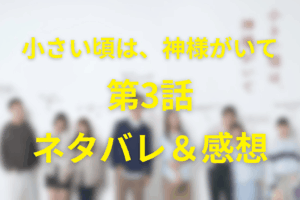
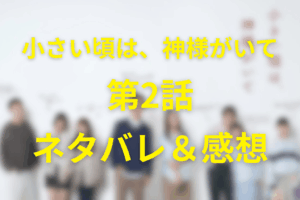
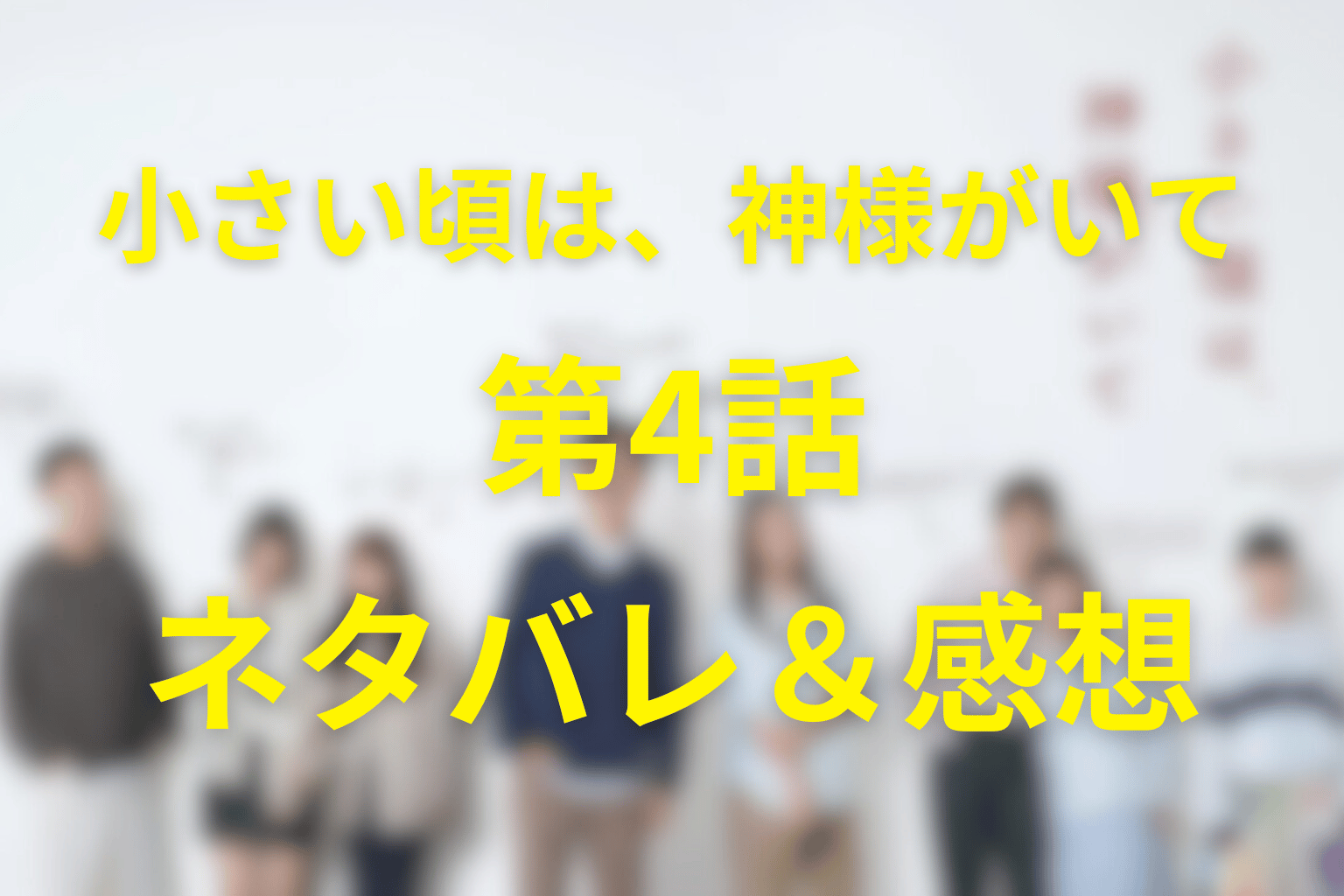
コメント