前回の6話では、『夏の夜の夢』の終幕を経て、WS劇場の“生き残り”が現実味を帯び始めた。
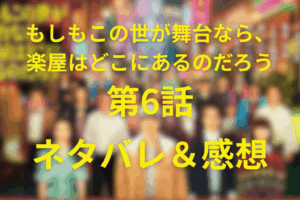
そして第7話は、冬の到来を前にした“再挑戦”の物語。
久部三成(菅田将暉)は新作『冬物語』に挑む覚悟を決め、舞台界の大御所・是尾礼三郎(浅野和之)を迎える。
しかし、支配人・大門(野添義弘)は経営難にあえぎ、「逃げるが勝ち」と囁く妻・フレ(長野里美)の現実的な声に心が揺れる。
芸術の理想と生活の帳尻、情熱と撤退――。
すべての選択が“舞台に立ち続ける”とは何かを問う第7話。
ここから、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)』7話のあらすじ・ネタバレ・感想・考察を詳しく紹介します。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)7話のあらすじ&ネタバレ
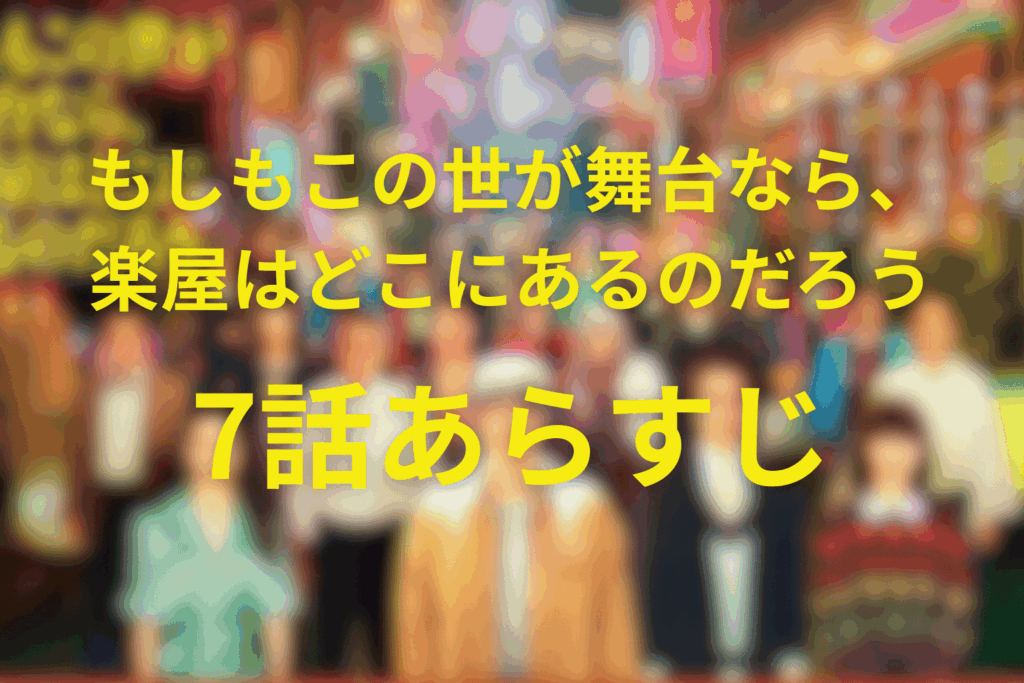
7話は「第二幕・冬物語」開幕編。是尾礼三郎の加入で舞台は熱を増しつつ、WS劇場は経営破綻寸前。
お笑いコンビ「コントオブキングス」の王子はるおに舞い込んだテレビのレギュラーオファーと、前金150万円を巡って、久部の“クズさ”と演劇への狂気がむき出しになります。
さらにリカの元カレ・トロが本格的に動き出し、恋愛パートも不穏な空気に包まれていく回でした。
「冬物語」始動と是尾礼三郎の条件
『夏の夜の夢』初日から1週間。うる爺を失ったWS劇場では、久部三成が伝説の俳優・是尾礼三郎を新たな切り札として迎え入れます。劇団クベシアターは、昼は次回作『冬物語』の稽古、夜は『夏の夜の夢』本番という“地獄の二毛作”スケジュールに突入します。
是尾が舞台に立つ条件はただひとつ、「やるならシェイクスピア後期の名作『冬物語』」。かつてシェイクスピア俳優として名を馳せた男のこだわりに、久部は即座に応じ、徹夜で上演台本を書き上げます。
開場時間を迎えたWS劇場。隣のスナック「ペログリーズ」を“楽屋代わり”にしている是尾は台本を読み込んでいました。久部が様子を見に行くと、是尾は「リオンティーズという役にはシェイクスピアのすべてが詰まっている」と語り、覚悟をにじませます。
一方、久部は「いつか西武劇場で僕たちの『冬物語』をやりたい」と目を輝かせながら夢を語りますが、その横で是尾の手は震えている。
アルコール依存の噂が現実味を帯び、蓬莱は不安を隠せません。久部がケントちゃんに“見張り”を命じるも、是尾は言いくるめて明かり取りの小窓から脱走してしまいます。
ノルマ120万円と“赤鎧”を売る支配人
芸術的には夢いっぱいの「是尾礼三郎復活公演」。しかし興行の現実は冷酷です。オーナーのジェシー才賀は週120万円のノルマを課し、『夏の夜の夢』の売上は半分ほどの51万6千円。
支配人・浅野大門の妻フレは「売上金を持って田舎へ逃げよう」と夜逃げを提案するほど追い詰められています。だが久部は「是尾礼三郎の復活は演劇界にとって大ニュースだ」と熱弁し、大門を説得。
最終的に大門は、父の代から受け継いだ家宝“赤糸威本大札大鎧”を売却。その代金でノルマをギリギリ工面します。震える背中には“親父の覚悟”が宿っていました。
しかしジェシーは小細工を見透かし、「次にヘマをしたら即アウト」と言わんばかりの圧を久部にかけます。
酔っぱらい是尾の名演と「次にやったらクビ」
『冬物語』初日。毛利里奈のダンスで開演時間を引き伸ばしながら、是尾の行方を探す久部たち。ようやく見つけた是尾は道端で酔いつぶれていました。
しかし舞台に立つと、アルコールの気配を吹き飛ばす集中力でリオンティーズを熱演。久部は袖からうっとりと見惚れ、客席も息を呑みます。
終演後、是尾はケントちゃんにマッサージされながら、カットされていた長ゼリフを戻すよう要求。しかしすぐに「さっきの話は忘れてくれ」と頭を下げ、「次に同じことをしたらクビで構わない」と久部と約束します。老いとプライドと酒癖を全部抱えながら舞台にしがみつく姿が凝縮された場面でした。
蓬莱が飲酒を危惧し「このままではいけない」と忠告する一方、久部は「いまの俺たちに是尾を切る余裕なんかないだろ」と一喝。蓬莱は黙り込み、その顔には納得しきれない影が残ります。
テンペストの夜、リカと樹里、そしてトロ
劇場ロビーでは、コンビ「コントオブキングス」の彗星フォルモンが、テレビの仕事の前祝いに仲間を焼肉へ誘います。パトラやモネは喜びますが、リカは「客と約束がある」とテンペストへ。
一方そのテンペストでは、王子はるおがテレビ局のプロデューサーからレギュラー出演の話を受けていました。条件は“コンビ解散”。
同じ店では樹里が『冬物語』のカット案を考えていました。そこへリカが座り、久部も店に入ってくると、リカを気にしつつ樹里との台本相談を優先。樹里が作り込んだ人物相関ノートを見て提案した「キャラクターごとカット」はリカに「役そのものを消すのは違う」と一蹴され、樹里は固まります。
そのタイミングで現れたのが、リカの元恋人トロ。風呂須とも旧知の男で、リカを迎えに来て親しげに店を出ていきます。久部は動揺しつつも、礼儀正しく去っていく樹里の“飲み込んだ感情”には気づけないまま。
その後、八分神社でリカとトロが賽銭箱前で激しくキス。
偶然いた樹里は物陰に隠れ、宮司の父に見せまいと必死に引き留めます。このシーンは、リカのプライベートと舞台の世界が衝突し始める予兆として描かれています。
はるおのテレビオファーと150万円の前金
テンペストの片隅で、はるおはレギュラー出演の詳細を聞きます。芸人としての飛躍か、相方フォルモンとの関係かで葛藤。
久部は「自分の幸せを掴んでいい」と背中を押しますが、はるおが『冬物語』を降板すると知るや「自分だけ幸せになればいいのか」と態度を急変。店員の仮歯もあきれます。
しかし、はるおが前金150万円を受け取ったと知ると、久部は再び「絶対受けるべきだ」と豹変。はるおが「これは皆へのお礼に使いたい」と伝えると、久部は「僕が預かって渡す」と半ば強引に金を託されます。
久部はその150万円を“来週の売上が足りない時の保険”としておばばに預けます。
フォルモンの怒りと「5万円」にすり替えられた友情
大瀬六郎がはるおのテレビ出演と前金の話を周囲に広め、知らされていなかったフォルモンは激怒。
久部はフォルモンを屋上へ連れ出し、「はるおからの感謝の金」として提示したのは、実際の150万円ではなく5万円。フォルモンは侮辱と感じ、「バカにするな」と怒鳴ります。
久部の取り繕いも届かず、友情には深い亀裂が刻まれました。
はるおの旅立ちと、残されたフォルモン
グローヴ荘で私物を片付けるはるおのもとへ蓬莱が訪れます。蓬莱は励ましつつ、久部が本当に150万円を正しく扱うのか疑念を抱えています。はるおも「確認してほしい」と蓬莱に頼むほど不安を感じていました。
WS劇場に戻ると、劇団員に拍手で送り出されるはるお。そこへフォルモンが通りかかり、さらに伝説のコメディアンである父が高級車で迎えに現れます。
フォルモンは「いつか俺もテレビに呼んでくれよ」と照れながら言いますが、はるおは「どいてください」と冷たく返す。しかし車に乗り込んだ直後に涙をこらえきれず崩れ落ちます。フォルモンの前で冷たく振る舞ったのは、きれいな決別のための“優しい残酷さ”でした。
路上に取り残されたフォルモンは座り込み、劇団員たちは「明日からの『冬物語』どうするの」と不安を漏らします。大瀬が代役を申し出るも、フォルモンは「はるお以上の相棒はいない」とつぶやきます。
久部の“横領”と蓬莱の不信、そしてトニー覚醒
はるおを見送ったあと、久部は前金150万円を劇場支配人・大門とフレに「来週の売上が足りなくなった時のための保険」として手渡し、「法に触れていません」と言い聞かせるように語ります。
しかし蓬莱は、その金がはるおの前金であることを察し、「このまま先の見えない劇団を続けるつもりか」と問い詰めます。久部は怒りで黙らせますが、蓬莱の不信は消えません。
蓬莱が去った後、久部は廊下に座り込み頭を抱えます。そこへ聞こえてくるのは、用心棒トニー安藤の稽古の声。
トニーは劇場の一角で台詞を繰り返し、必死に芝居を掴もうとしていました。久部が演技指導を始めると、トニーの芝居は劇的に変わっていきます。久部は涙を流し、自分の言葉で舞台が変わる瞬間に胸を震わせます。
こうして7話は、「役者を覚醒させる演出家」と「仲間の前金150万円を劇団資金に回す演出家」という相反する久部像を提示したまま、重たい余韻を残して幕を閉じます。
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)7話の感想&考察
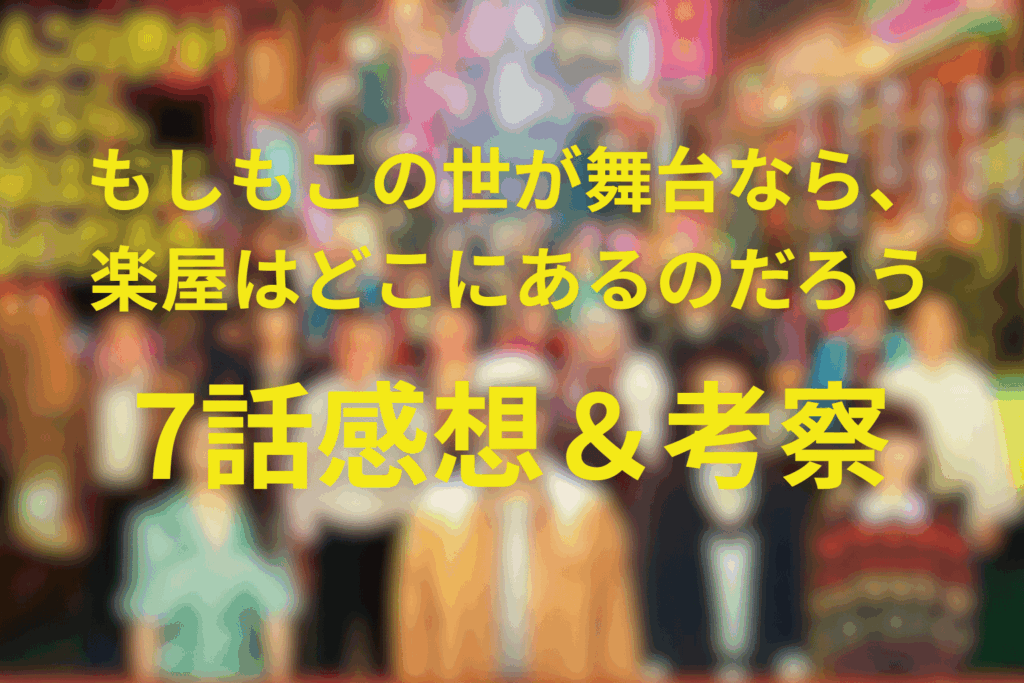
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(もしがく)7話の見終わった後の感想&考察
7話は「逃げるか、賭けるか」「守るか、削るか」「相方か、自分の未来か」という三つ巴のテーマが、演劇論と生活のリアルにガッチリ噛み合った回でした。
個人的には、シリーズの中でもかなり胸に刺さる一本。ここからは、演劇オタク寄りの視点で整理していきます。
「冬物語」とヘンリー四世、久部の変身
毎回サブタイトルに引用されるシェイクスピア作品。7話では「私をかつての私だと思ってはいけない」という『ヘンリー四世』の一節が掲げられています。
これ、見終わったあとに振り返ると、まんま久部の状態なんですよね。
かつては“売れない劇団の若き演出家”だった久部が今や「伝説の俳優の復活」と「劇場の存続」を一人で背負い仲間の前金にまで手を伸ばしてしまう。
つまり、芸術のためなら多少の“黒”も飲み込む存在へと変わってしまった。
「昔の俺だと思うなよ」という宣言をしているように見える一方で、本人はそれを自覚しきれていない。その危うさが、7話の久部の魅力でもあり、怖さでもあります。
同時に、『冬物語』は嫉妬と赦し、失われた時間の回復を描く後期シェイクスピア。酒に翻弄される是尾、元カレ・トロに翻弄されるリカ、金に追い詰められる久部たち。
誰もが「取り返しのつかない一歩」を踏み出しかけている冬の入り口として、よく出来た題材だなと感じました。
はるおとフォルモン、別れの場面がエグい
この回でもっとも心を持っていかれたのは、コントオブキングスの別れ。
はるおは「芸人としての大チャンスであるレギュラーオファーが来たものの、その条件がコンビ解散で、しかも自分は伝説のコメディアンを父に持つ“血筋付きのエリート”にも見える」という、相当しんどい状況に立たされています。
一方フォルモン側から見ると、「ずっと自分が引っ張ってきたつもりの相方が、自分を置いて個人仕事で飛躍していくうえに、その重大な決断を直接伝えてもくれなかった」という
握手を求めるフォルモンに「どいてもらっていいですか」と突き放すのは最低なのに、車に乗った瞬間に顔をくしゃくしゃにして号泣する姿を見せられると
、「これは彼なりの優しさでもあったのか」と捉え直してしまう。フォルモンが格好良すぎる場面としても語られるのは、この二重構造が丁寧に芝居で描かれているからこそでした。
久部はどこまで「クズ」なのか
SNSを見ると「久部クズすぎ」「でも嫌いになれない」と揺れる感想が多いですが、同感です。
行動だけ並べると、
・大門の家宝を売らせる
・はるおの前金150万円を強引に預かる
・そのうち5万円だけをフォルモンに“お礼”として提示
・残りは劇場存続のために勝手に使用
完全にアウト。でも、根底には、
・WS劇場を守りたい
・是尾の復活を成功させたい
・仲間の才能が活躍できる場所を守りたい
という“白い動機”がある。
これはまさに「正しい間違い」。だからこそ、視聴者は“倫理的にはムカつくのに、嫌いになれない”という矛盾に陥る。三谷作品らしい人間の厚みです。
蓬莱は“観客の良心”ポジション
久部の「正しい間違い」をもっとも近くで見ているのは蓬莱です。是尾の酒問題を真っ先に指摘し、前金の扱いに違和感を抱き、「こんなこといつまで続けるんですか」と爆発しかける。
彼は視聴者の「それ大丈夫か?」という良心を代弁する存在で、現場のリアルそのもの。小劇場では誰かにしわ寄せがいく瞬間を見てきた人間だからこその視点で、胸が痛む描写でした。
樹里・リカ・トロの三角線
7話で樹里の存在が一気に重要になります。
『冬物語』の進行を握る裏方でもあり、リカに“もっと勉強しなさい”と刺され続ける後輩でもあり、久部に片思いしつつ父はリカ推しという複雑な立場でもある。
そこにトロという“外から侵入してくるノイズ”が登場する。
神社の強引なキスを目撃した樹里は、リカを案じる友としても、公演を守りたいスタッフとしても、父に見せられない娘としても焦りが走り、その全部が「父をなんとか追い払う」という行動に収束する。人間の感情レイヤーを丁寧に描いた名シーンでした。
トニー覚醒シーンに込められた演劇論
ラストのトニー安藤の自主稽古シーンは、完全に演劇ファンへのご褒美。
大声を出しているだけの芝居が、久部の指導で「誰に向けて、どの距離で、どんなリズムで声を出すか」という技術を獲得し、視聴者にも“芝居が良くなった”と体感できるレベルにまで変化していく。
この瞬間に誰よりも泣いてしまうのが久部本人というのが象徴的。金の扱いでは最悪なのに、演出家としては誰よりも本物。このアンビバレンスこそ、三谷ドラマの人間描写です。
8話への伏線と、「未解決のまま進む」美学
7話は問題をほとんど解決しません。
是尾の酒、ジェシーのノルマ、久部の前金、トロの侵入。
それでも「今夜も幕は上がる」。この“未解決のまま前へ進む”感覚が、演劇そのもの。舞台の理想・生活・人間関係がぶつかり合う第二幕の入口として、7話は見事な回でした。
もしがくの関連記事
全話のネタバレについてはこちら↓
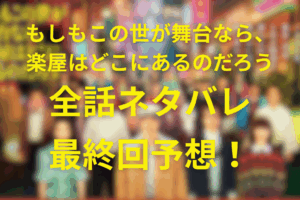
次回以降についてはこちら↓
過去についてはこちら↓
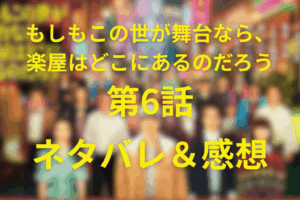
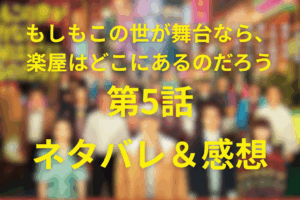
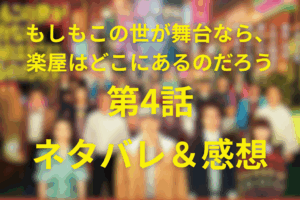
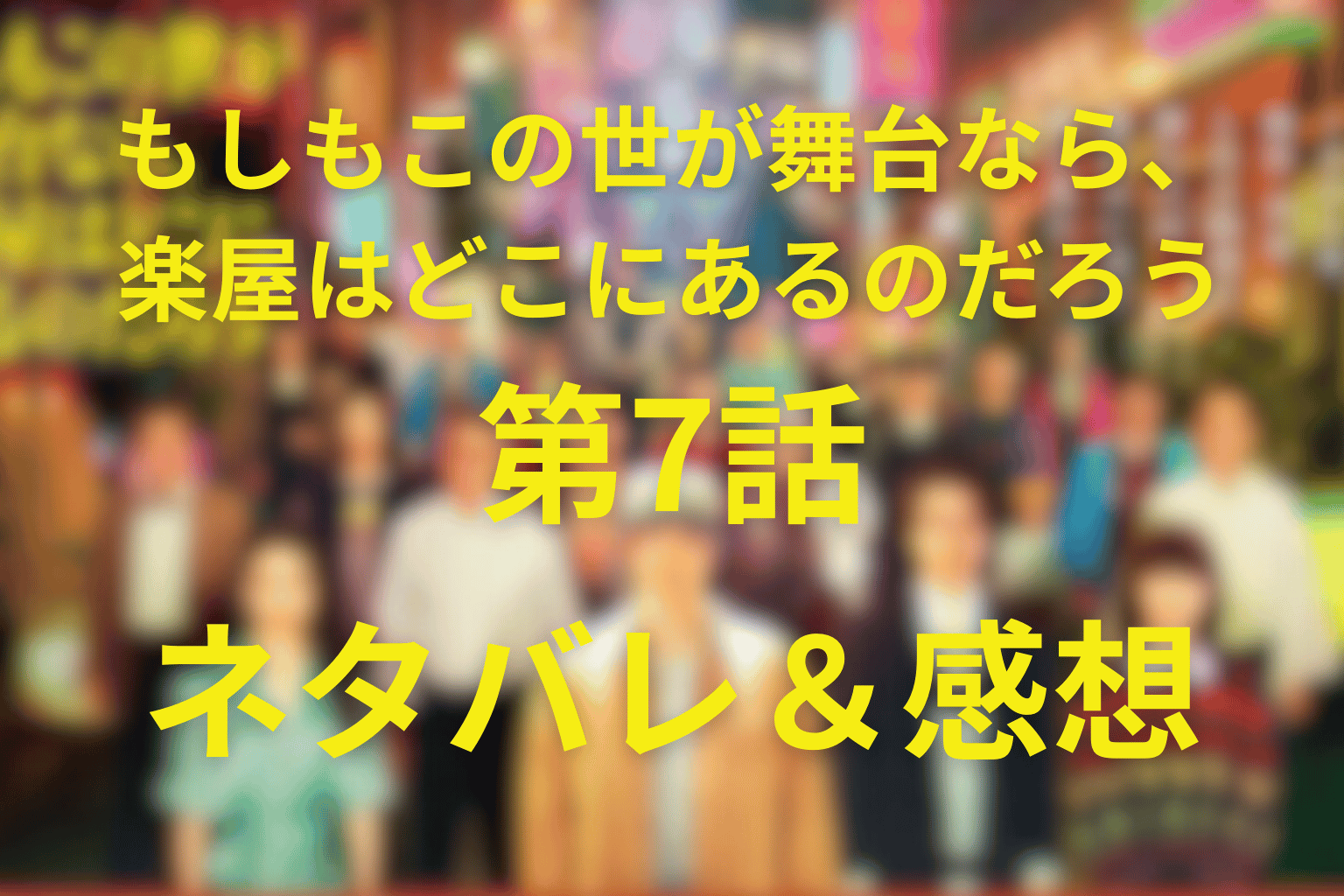
コメント