第5話は、「帰ってくること」と「言えなかったこと」をそっとほどく回だった。
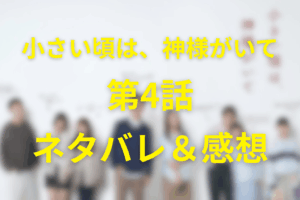
永島夫妻の帰還を中心に、たそがれステイツの住人たちは再び食卓を囲む。
夜更け、順が語る“消防士になった理由”に滲む優しさと、翌朝のラジオ体操で見える共同体の息づかい。
一方で、あんと渉の夫婦の間に漂う小さなズレが、夜のドライブで静かに浮かび上がる。そして最後に描かれる、凛の失踪。
それは“家族の再生”という大きなドラマではなく、誰かが“痛みを抱えたまま動き出す”ための、ほんの小さな一歩。
ここからドラマ『小さい頃は、神様がいて』第5話のあらすじと感想・考察を紹介します。
小さい頃は、神様がいて5話のあらすじ&ネタバレ
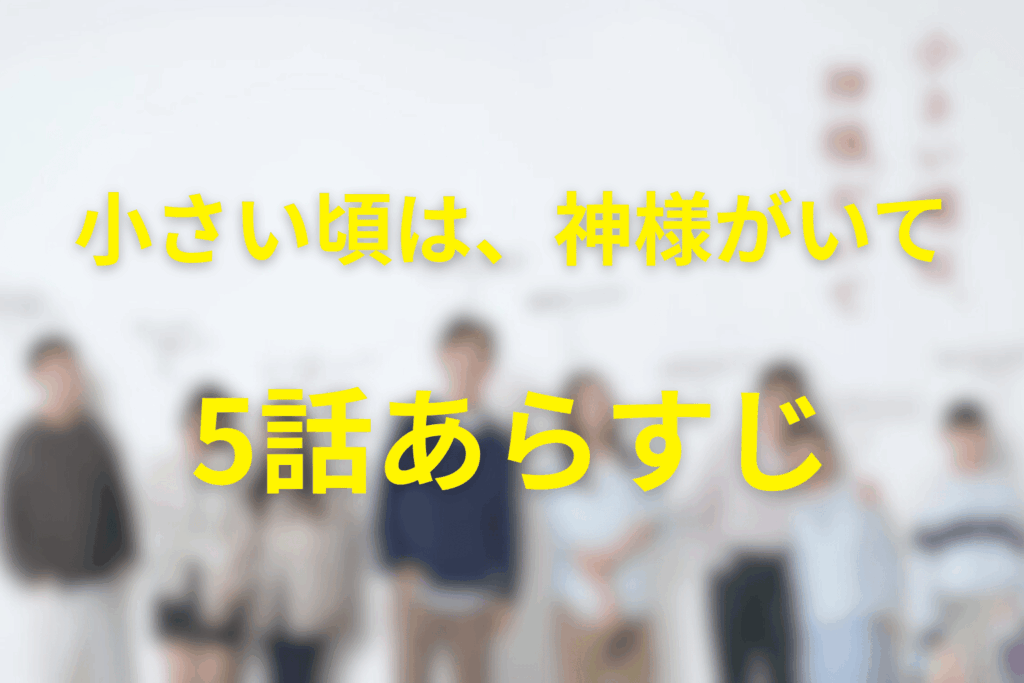
第5話は、「帰ってくること」と「言えないままに抱えてきたこと」を、ゆっくりと日常へ戻していく回だった。
永島慎一・さとこ夫妻が「たそがれステイツ」へ帰還し、孫の凛と真との新生活が始まる。
住人たちは温かなパーティーで迎え、夜更け、順が“消防士になった理由”を語る。翌朝は慎一のふさぎ込み、賑やかなラジオ体操、ゆずの“奈央×志保”密着撮影、そして──同窓会へ向かうあん。
最後に静かな衝撃として、凛の失踪が描かれる。公式の粗筋が示す出来事を、生活の呼吸として描いた一編である。
「お帰り&ようこそ」──帰還と語られなかった本心
慎一(草刈正雄)とさとこ(阿川佐和子)の帰還は、「喪失を抱えながらも生活を再起動する」合図として置かれる。
住人総出の「お帰り&ようこそパーティー」は、笑顔の下に痛みを隠しつつ、それでも同じテーブルを囲む選択の場だ。
子どもたちが眠った後、渉(北村有起哉)とあん(仲間由紀恵)の息子・順(小瀧望)が消防士になった理由を静かに打ち明ける。
「迷わず動ける人になりたかった」「両親を心配させたくなかった」――そんな言葉の余白に、あんは小さな違和感を覚える。ここで初めて“順はずっと何かを飲み込んできたのでは”という予感が立ち上がる。
翌朝の沈黙──慎一のふさぎ込みと、共同体の呼吸
翌朝、慎一は気持ちが沈み、ラジオ体操へ向かう足取りも重い。
さとこが軽く背を押し、住人たちが賑やかに集まることで、空気が少しずつほどけていく。大仰な演出はないが、“体操”という規則的な動きが痛みを抱えた人々を揃えていく。
慎一の表情に戻る笑みは、「元に戻る」ではなく「痛みを抱えたまま動き出す」ための小さな合図。日常のリズムが人を支える、そのささやかな力を丁寧に映している。
ゆずのカメラ──奈央と志保に“一日密着”する意味
同時進行で、ゆず(近藤華)は二階の奈央(小野花梨)と志保(石井杏奈)を追いかけ、彼女たちを一日かけて記録する。
三階・小倉家の“映画監督志望の娘”という設定がここで生き、カメラという他者の視線が、二人の関係に新しい輪郭を与える。
シリーズ全体の舞台である「三階建てのレトロマンションで暮らす三家族」という構造が、“記録される日常”という層を得て、関係の距離感を微妙に変える。ゆずの撮影はこの先も続きそうで、次回への伏線としても機能している。
同窓会の夜──夫婦のズレを測定する会話
その夜、あんは同窓会の誘いを思い出す。
軽く「行けばいいじゃん」と言う渉に、あんは短く冷たい視線を向ける。
渉は職場で“同窓会前後の女性の心理”を同僚に相談し、会長の「帰宅後は機嫌が悪くなることもある」という助言まで引き寄せて、正解を探そうとする。
帰宅後、あんを車に乗せ、夜のドライブへ。二人はこれまでのような衝突ではなく、言葉を選びながら慎重に会話を試みる。第5話は、夫婦のすれ違いを荒々しく描かず、“会話の温度”で関係を測る。だからこそ、翌朝の出来事が深く響く。
消えた凛──静かなクライマックス
翌朝、さとこが目覚めると凛の姿がない。
住人総出の捜索の末、順が高台の階段で凛を見つける。ここで第5話は、「子どもが背中で語る痛み」を描き出す。前夜の会話や大人の気配をどこまで理解していようと、子どもは“いない場所”を確かめるために世界から一度消える。
順が凛を見つけ、抱き上げ、声をかける。その一連の動作が、彼自身の過去――幼い頃から家族のために“良い子”を演じてきた時間――と重なる。
あんはその姿を見つめ、胸の奥で確信する。
物語は静けさの中に痛みを沈め、次の章への気配を残して幕を閉じた。
小さい頃は、神様がいて5話の感想&考察
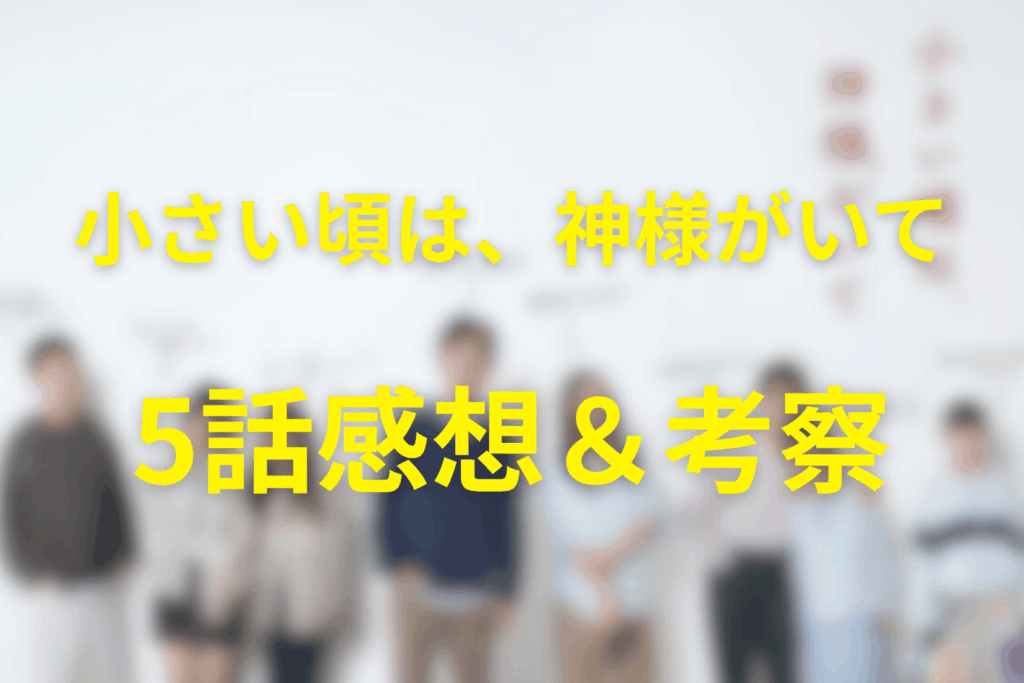
第5話を見終えて最初に残るのは、「日常に戻る」とは“痛みが消えること”ではないという実感だ。
むしろ痛みを抱えたまま、体操をして、ご飯を食べて、誰かの話を聞く。そこへ「言えなかったこと」が少しずつ言葉になる──この回は、その“言葉になる瞬間”をひたすら待ち、支える演出が多い。
シリーズの核である「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束(小倉夫妻の出発点)は、話数が進むほど“関係の再設計”の物差しとして機能している。
順が語った“消防士”の理由──我慢の奥にある優しさ
順の告白は、職業選択の動機という表層よりも、「迷いを飲み込む癖」を自分で受け止め直す行為に見える。
子どもの頃、空気を読みすぎた記憶。両親を心配させないように、勤務地さえ遠く選んだ配慮。彼の“優しさ”は衝動の抑制ではなく、“他者を先に置く”習慣の積み重ねだった。
だからこそ、凛の失踪に順がすぐ反応し、高台で見つけて寄り添えたのだろう。
行動は語る。順が誰かを助けるとき、彼は過去の自分をも救っている。第5話は、“我慢の奥にある優しさ”をほどく回だった。
“同窓会”という地雷──ズレを「会話」で設計し直す
同窓会のエピソードは、夫婦のズレを可視化する社会的な装置だ。
渉の「行けばいいじゃん」は、相手の記憶と虚栄と不安が交差する場への浅い理解を露呈する。
彼は職場で知識を仕入れ、あんは車内で「あなたは優しいし、子どもたちも良い子」と言われる“外からの評価”にもやもやを感じる。重要なのは、二人が“勝ち負け”ではなく、「どこが痛いのか」を共有できたこと。
ズレは消えないが、輪郭は共有できる。
物語はそれを“夜のドライブ”という定点の会話で描く。これが本作の呼吸だ。
ラジオ体操の演出──共同体が痛みを抱えたまま動き出す
ラジオ体操は、悲しみの後にコミュニティが再起動する“儀式”として描かれる。
揃った動き、交わる挨拶、混じる笑い声。
慎一の表情の回復は、さとこの言葉だけでなく、“体を動かすこと”がもたらす変化でもある。ドラマは「派手な解決」ではなく「繰り返しの救い」に賭けている。
関係は一気に直らない。けれど毎朝の動きの中で、人は少しずつ“痛みを扱える自分”に戻っていく。その確かさが画面に満ちていた。
ゆずのカメラ──“記録”が関係を設計し直す
ゆず(近藤華)が奈央(小野花梨)と志保(石井杏奈)を一日撮る。これは単なるサブエピソードではない。被写体になる側は“見られる自分”を獲得し、撮る側は“見たい自分”を自覚する。
記録は関係を外へ開き、共同体の中での位置を再定義する。
シリーズの舞台が「三階建ての三家族」という構造でできているため、フロアを越えて視線が交差する。
二人の来歴と“笑顔という防具”の解体が進むことで、ゆずのカメラは“変化の証拠”となる。次回に向けても、物語を動かす装置としての意味を帯びていた。
凛の失踪──「消える」ことで示す子どもの主体
凛がいなくなるのは、危機の演出であると同時に、子どもの主体の表明でもある。
彼女は「いない場所」を自分の目で確かめようとする。
誰もいない家、遠くにある“元いた生活”。
順が見つけて声をかける動線は、“優しさは我慢ではない”という今回の主題と響き合う。
あんが涙をこぼし、順の“天使”という比喩の真意に触れるくだりで、この失踪が“一家の感情史”に通路を開いたことが示される。消えることは、誰かに見つけてもらうことの別名でもある。そこに家族の定義が宿る。
伏線と反復──「提示→変奏→回収」のどこまで来たか
- 離婚カウントダウン: 「あと○日」という表示が時限装置のように機能し、“別れ”を前提とした行動を促す。今回は「33日→32日」。
- 夜のドライブ: これまでの衝突の場が“対話の場”へと変化し、夫婦の関係が説明から共感へと移行。
- ラジオ体操: 共同体の再起動装置。慎一の表情を細やかに追い、再生の可能性を描く。
- ゆずの撮影: 二階カップルの物語に「観測者」を導入し、次話への橋渡しを担う。
作品全体のテーマとの接点──“関係の再設計”の進み方
このシリーズは、19年前に交わされた“二十歳で離婚”という約束から始まり、夫婦・親子・隣人がそれぞれの〈正しさ〉を擦り合わせていく物語だ。
第5話は、合意や解決を急がず、まず「話せる関係」を描く。
順の語り、渉の学び直し、あんの涙、慎一の笑み、ゆずのカメラ──それぞれが“関係の設計図”の線を引き直す。
主題歌『天までとどけ』の開放感とともに、日常へ戻る勇気は“誰かの隣に並ぶこと”からしか始まらないというメッセージが一貫していた。
次回への布石──“関係の行方”に焦点が移る
強い事件の予告よりも、関係の奥行きが深まっていきそうだ。
ゆずが記録した奈央と志保の“笑顔の防具”と“他者恐怖”が掘り下がり、順は“良い子”の殻を破り、自分の言葉で生き始めるのではないか。
小倉夫妻は“別れ”を前提にしながら、“どう別れるか”を設計する段階へ。
第5話で描かれた「やわらかな対話」の回路を保てるかどうか――そこが次の焦点になる。
「小さい頃は、神様がいて」の関連記事
「小さい頃は、神様がいて」の全話ネタバレはこちら↓
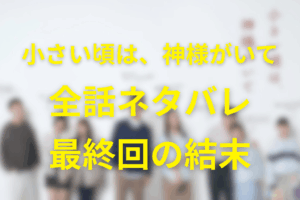
「小さい頃は、神様がいて」の次回以降の話はこちら↓
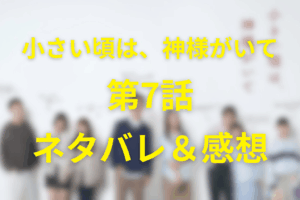

「小さい頃は、神様がいて」の過去の話↓
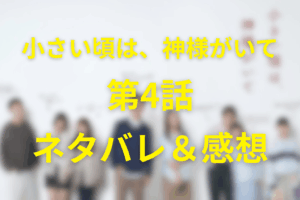
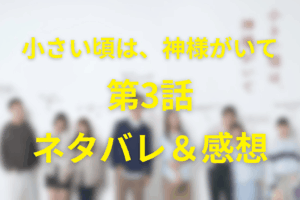
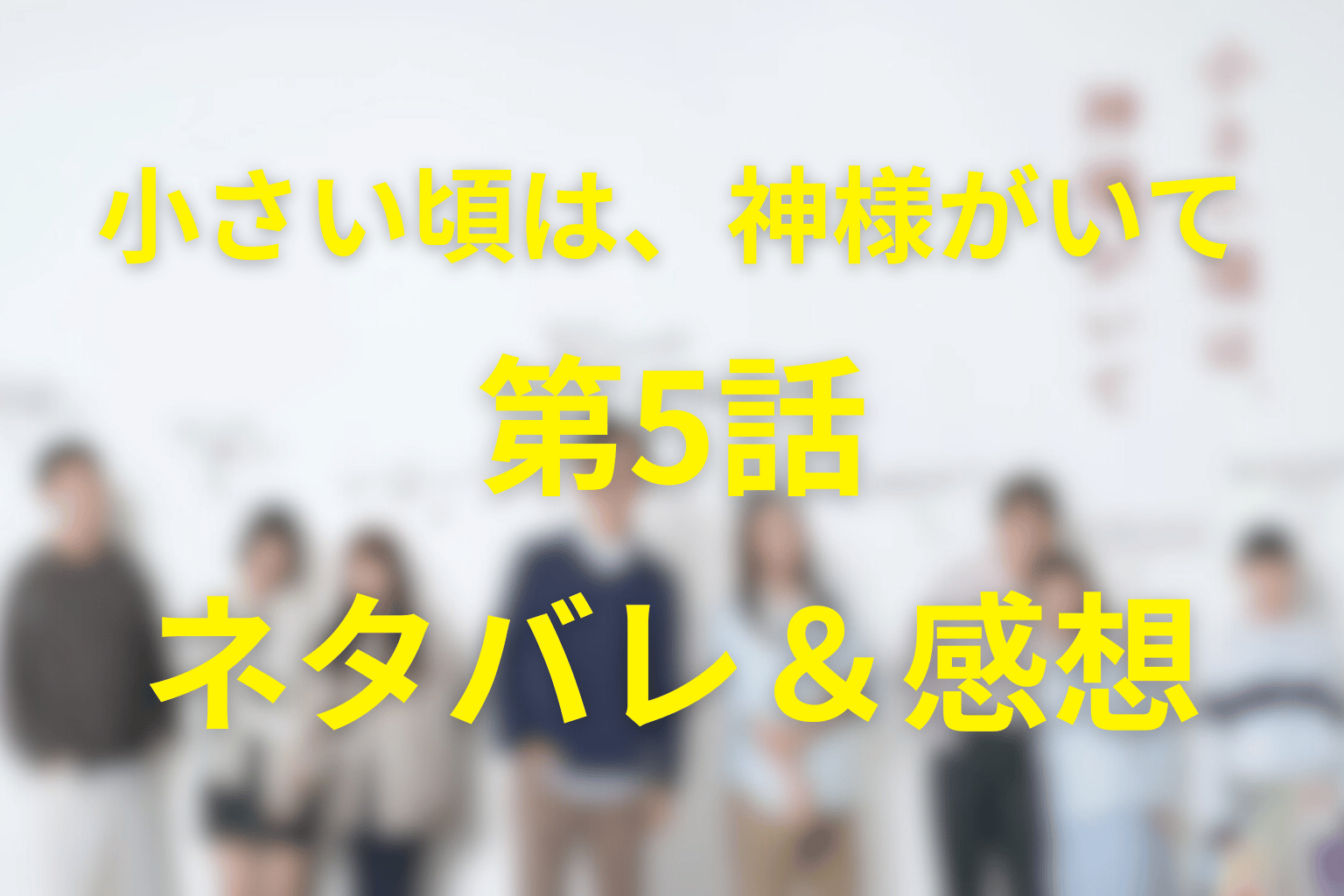
コメント